第1節 エネルギーを巡る情勢の変化
1.脱炭素化の潮流の加速
パリ協定は、2015年12月に開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして採択されました。各国は、温室効果ガス削減に向けたNDCを定め(パリ協定第3条)、またNDCとは別に、長期的な温室効果ガス低排出型の発展すべきための戦略(以下「長期戦略」という。)を作成し、通報するよう努力すべきとされています(パリ協定第4条19)。各国は国家レベルの約束であるNDCや長期戦略に基づき、温室効果ガスの削減に向けた様々な取組を実施していますが、民間でも金融業やIT産業を筆頭に脱炭素化に向けた取組が加速しています。
(1)金融の脱炭素化
金融機関や投資家が投融資を行う際には、収益性や回収可能性など様々な観点を考慮・評価して判断を行っていますが、その評価軸の一つとして、気候変動・脱炭素化への対応が重視され始めてきています3。具体的な動きとして、①ESG投資4等を通じた環境分野への資金供給量の増大と、②投資戦略多角化を通じた投融資先への関与の積極化が挙げられます。
①ESG投資の増加
環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素を投資判断に組み込む「ESG投資」の規模が近年大きく拡大しています。例えば、世界全体のESG資産保有残高は2016年から2018年の間で1.3倍に増加しました(第121-1-1)。
このようにESG投資の規模が拡大してきた背景には、ESG要素の「E」に分類される気候変動リスクへの注目が高まったことが挙げられます5。国連防災機関(UNDRR)は、この20年(1998年~ 2017年)の自然災害経済損失額は2兆9,080億ドルにのぼりますが、そのうち気候変動による経済損失額は全体の77%に当たる2兆2,245億ドルと推計しています。これはその前の20年間(1978年~ 1997年)の気候変動関連経済損失額の1.5倍になっているとの報告をしています6。災害の激甚化など、気候変動リスクが顕在化する中、金融機関や投資家は、企業による気候変動リスクへの対応状況や関連情報の開示状況を投資判断の一部として重視しています(第121-1-2)。
【第121-1-1】地域別のESG資産保有残高
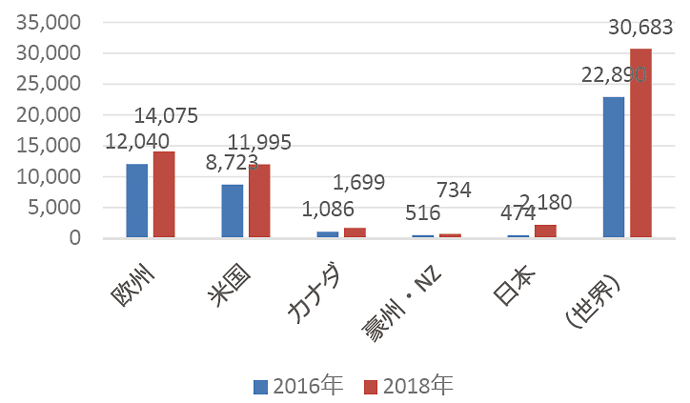
【第121-1-1】地域別のESG資産保有残高(ppt/pptx形式:54KB)
- 出典:
- GSIA, Global Sustainable Investment Review 2018より経済産業省作成
【第121-1-2】機関投資家がエンゲージメント活動において重視するテーマ
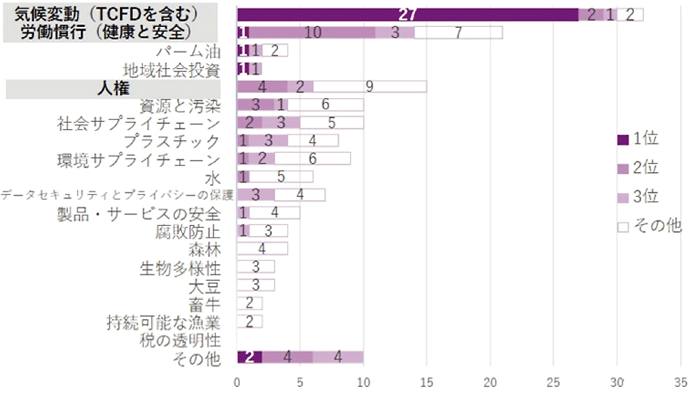
【第121-1-2】機関投資家がエンゲージメント活動において重視するテーマ(ppt/pptx形式:265KB)
- 出典:
- QUICK ESG研究所「ESG投資実態調査2020」経済産業省作成
②投資戦略の多角化
ESG投資の投資戦略としては、伝統的に欧州では、投資家が設定した基準を満たさない企業を一律に投資対象から外す「ネガティブ・スクリーニング」の割合が高く、環境関連では、温室効果ガスを多く排出する投資を対象から排除する手法が用いられてきました(第121-1-3)。
日本でも、大手金融機関や損害保険会社が、新設の石炭火力発電所に対する投融資を原則として行わないとした上で、環境配慮技術が導入された案件については別途考慮する等の投融資方針の表明が行われています。また、石炭火力発電の輸出支援に関しては、2020年12月に経協インフラ戦略会議で決定された「インフラシステム海外展開戦略20257」において、世界の実効的な脱炭素化に責任を持って取り組む観点から、それまでの要件の明確化を行い、石炭火力輸出支援を厳格化しました。世界では、石炭に止まらず、化石燃料全般の投資から撤退する動きも出てきています8。
しかしながら、ネガティブ・スクリーニングだけでは、結果的に温室効果ガスの削減につながらないとの指摘があります。投資対象から外した企業に対し、別の金融機関から資金が供給されることがあるためです。そこで米国を中心に拡大をしてきたのが「エンゲージメント」や「インテグレーション」の手法です。「エンゲージメント」は、投資家が投資先企業と温室効果ガス削減を事業の中でどのように実現するか等について建設的に対話を行い、投資先企業に行動を促す手法です。例えば、米大手資産運用会社のブラックロックは、2020年1月にESGを軸とした運用を強化し、投資先企業がサステナビリティに関する情報開示において十分な進展がなければ、議決権を行使し反対票を投じることをより積極的に検討することなどを表明しています。また、「インテグレーション」は、投資判断に当たって、財務情報に加えて、環境や社会問題への対応等に関する取組を非財務情報として組み入れ、総合的に企業を評価するものです。インテグレーションにおいて、非財務情報の活用方法は様々ですが、比較的取り組みやすい手法として、米国や日本で拡大してきています。
パリ協定の実現には、世界で最大8,000兆円必要との試算9もあります。脱炭素化のための取組に対して資金を供給する観点から、世界で3,000兆円ともされるESG投資を呼び込むことは今後も重要です。ただし、ESG投資を行う機関投資家が受託者責任10を果たす上で重要な論点であるESG投資と経済的リターンの関係については、必ずしも定量的な相関関係が見出されていないとされています11。ESG投資が一時的なブームとならず、脱炭素化に向けた資金が将来にわたって安定的に供給されるためにも、ESG投資による経済的、社会的リターンの定量法化手法のさらなる改善が期待されています。
【第121-1-3】投資戦略別のESG投資額
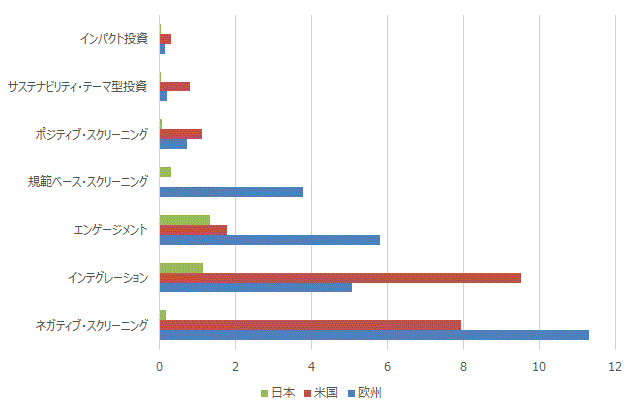
【第121-1-3】投資戦略別のESG投資額(ppt/pptx形式:53KB)
- 出典:
- GSIA, Global Sustainable Investment Review 2018より経済産業省作成
【第121-1-4】石炭火力輸出支援の厳格化
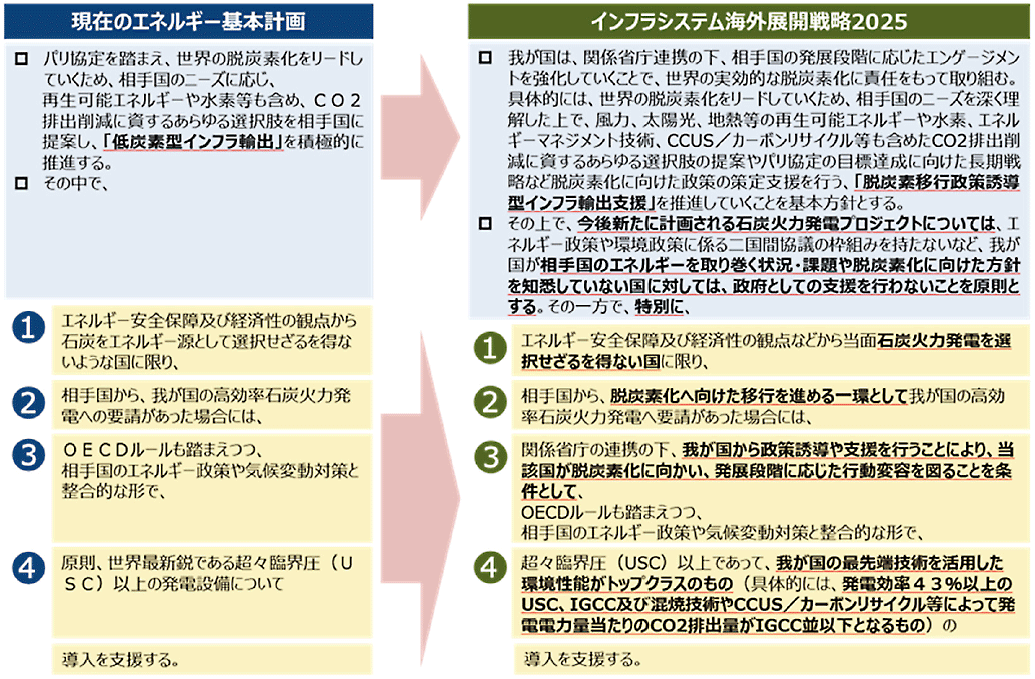
【第121-1-4】石炭火力輸出支援の厳格化(ppt/pptx形式:469KB)
- 出典:
- 経済産業省作成
COLUMN
トランジション・ファイナンス ~脱炭素社会への「移行」の重要性~
金融業界での脱炭素化に向けた動きをより強化するものとして、欧州では、「持続可能な金融推進のためのアクションプラン」の一環として、「グリーンな経済活動に関するEUタクソノミー(以下「EUタクソノミー」という。)」を策定し、「グリーンな活動」を定義する動きが出てきています。EUタクソノミーは、EUのサステナビリティ方針に資する経済活動を分類するに当たっての基準を示すもので、提供する金融商品や投資対象となる事業活動がサステナブルであるか(基準に適合しているか)の開示が金融機関と企業に求められます。EUタクソノミーでは、対象となる活動(発電方法など)ごとに、パリ協定の1.5度シナリオへの適格性の基準を示し、その基準に達しないものは「グリーンな活動」としては認められません。EUタクソノミーは、欧州委員会により制定される規則として、2021年4月時点では立法段階にありますが、規則の適用が開始されると、金融機関や企業はEUタクソノミーへの適合についての開示を義務付けられることになります。
EUはサステイナブル・ファイナンスを提唱し、グリーンな経済活動を限定的に定義する形で取組を進めていますが、再生可能エネルギー等へのグリーン投資の一層の推進に加え、パリ協定の実現に向けて、世界全体で排出量を着実に削減していく観点からは、排出削減困難なセクター(hard-to-abate)(現段階において、脱炭素化が困難な産業部門・エネルギー転換部門)における低炭素化の取組など、脱炭素へのトランジション(移行)を図っていくことも重要となります。
パリ協定の目標に整合する「移行」のための投融資(クライメート・トランジション・ファイナンス)を実施するための国際的に統一した考え方を共有するため、国際資本市場協会(International Capital Market Association: 以下「ICMA」という。)において、2020年12月に「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」が作成されています。
新興国のCO2削減なくして、世界のカーボンニュートラルは実現できません。トランジション・ファイナンスを通じて、これらの国に低炭素技術の導入が進み、CO2排出削減につながることが期待されています。
経済産業省では、世界全体のカーボンニュートラル、さらには過去のストックベースでのCO2削減(「ビヨンド・ゼロ」)を可能とする革新的技術の確立と社会実装を目指す「革新的環境イノベーション」の実現に向け、個別の挑戦課題とこれらを社会実現する道筋・手法について提示するため、2020年10月に関連の6つの国際会議12を連続的に開催しました(東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク)。とりわけ、世界で約3200人が参加したTCFDサミット2020では、新たなTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Forceon Climate-related Financial Disclosures)13)活用の在り方として、トランジションへの取組開示による資金供給促進の重要性が共有されました。
【第121-1-5】EUタクソノミーとICMAクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック
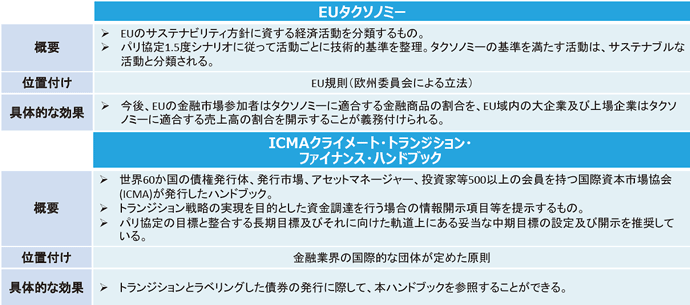
- 出典:
- 経済産業省作成
(2)民間事業の脱炭素化
金融機関や投資家が脱炭素化に向けた取組を進め、エンゲージメントを通じて、企業に対して、気候変動リスクへの対応等を求める中、IT企業が先導し、製造業なども追随する形で企業の脱炭素化の取組が近年加速しています。
なかでも日本企業は脱炭素化に積極的に取り組んでおり、気候変動関連の情報開示を行う枠組みであるTCFDの賛同機関数は日本が世界で第1位、脱炭素化に向けた中長期の目標設定を行うSBT(ScienceBased Target)の認定企業数は米国に次ぐ第2位(アジアでは首位)、事業活動に必要な電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指すRE100(Renewable Energy 100)も米国に次ぐ第2位(アジアでは首位)となっています(第121-1-6)。
【第121-1-6】TCFD、SBT、RE100の賛同機関数(国別)
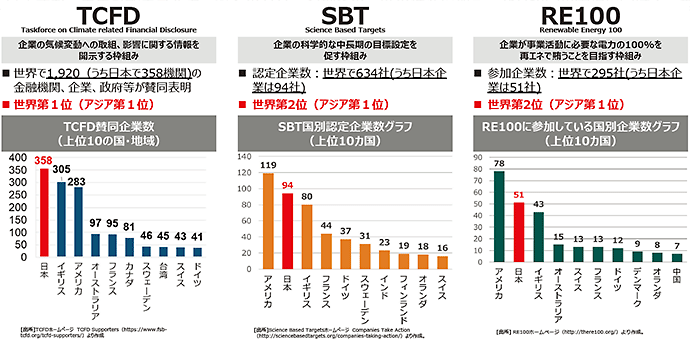
- 出典:
- 環境省・経済産業省「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」より抜粋(2021年3月29日時点)
さらに、自社が排出する温室効果ガスの削減(スコープ114)や自社で使用するエネルギーに係る温室効果ガスの削減(スコープ215)のみならず、サプライチェーン全体(スコープ316)での脱炭素化を図る企業も増加しています(第121-1-7)。例えば、Appleは、2030年までにサプライチェーン全体でカーボンニュートラルを実現することを目標に掲げ、サプライヤーに対して省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用を求めています。このように、サプライチェーンの脱炭素化を目指す企業との取引関係を継続するために、我が国の企業も脱炭素化を図らなければならないといった状況が今後増えていくことが想定されます。こうした観点から、脱炭素エネルギーへのアクセスのしやすさが、国際的な、そして地域間の産業の立地競争力に将来的に影響を及ぼすとの指摘もあります17。
【第121-1-7】脱炭素化をサプライヤーに求めている企業の例
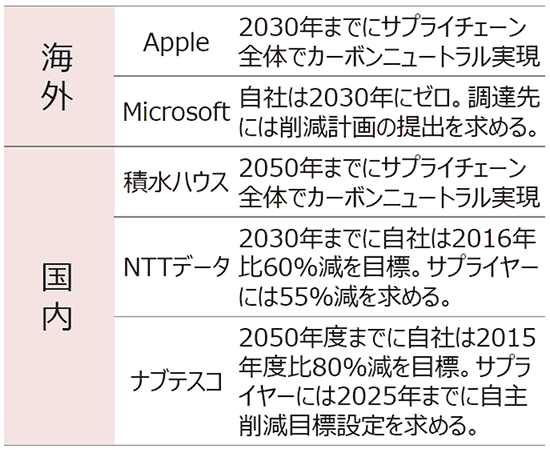
- 出典:
- 各社プレスリリース等から経済産業省作成
2. 新型コロナウイルス感染拡大が与えたエネルギーへの影響
2019年12月に新型コロナウイルス(COVID-19)の最初の症例が中国で確認されて以降、世界経済は急速に悪化しました。新型コロナウイルスが世界的に感染拡大した2020年のGDPと石油需要の前年同期比を比較すると、2020年第1四半期(1月~ 3月)及び第2四半期(4月~ 6月)にかけてGDP・石油需要ともに大幅に減少していますが、石油需要の方が大きな落ち込みを見せています。また、2020年第3四半期(7月~ 9月)以降は、GDPの回復と軌を一にして、石油需要も回復基調にありますが、GDP成長率が2020年第3半期の時点で前年同期と同水準まで回復した一方で、石油需要は2020年第4四半期(10月~12月)でも前年同期比5%以上のマイナスが続いています(第121-2-1)。
GDPよりも石油需要の方が大きく落ち込み、そして回復の幅も小さくなっていますが、これは経済の需要と供給の両面による影響が理由と考えられます。まず、供給面では、感染拡大防止のため、人同士のコミュニケーションや人の移動が制限された結果として、生産活動や物流が停滞しました。また、ロックダウン(都市封鎖)やレストラン・エンターテイメント等の営業が停止するなど、通常の経済の停滞では発生しないような人や物の移動を減少させる事象が生じました。こうした事象が、GDPと比較して石油需要が大きな落ち込みをした要因として考えられます。
【第121-2-1】世界の石油需要とGDPの推移
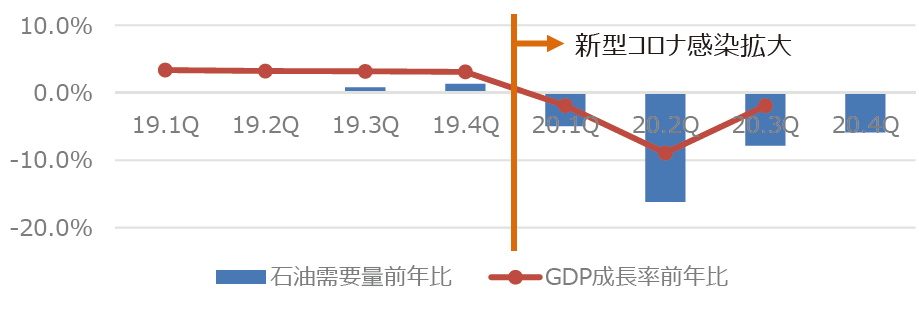
【第121-2-1】世界の石油需要とGDPの推移(ppt/pptx形式:763KB)
- 出典:
- IEA, Oil Market Report, IMF, World Economic Outlookより経済産業省作成
次に、需要面では、ガソリンは、需要の落ち込みは2021年後半にかけて回復すると見込まれていますが、ジェット燃料は需要の低迷が続くと見られています(第121-2-2)。これは、各国の移動制限措置が解除されるまでに時間がかかることが予想されていることに加え、会議のオンライン化等に伴う移動需要の構造的減少が影響しているとの指摘がされています18。こうした事象が重なって、GDPと比較して石油需要の回復が小さいと考えられます。
【第121-2-2】石油製品別の需要の比較
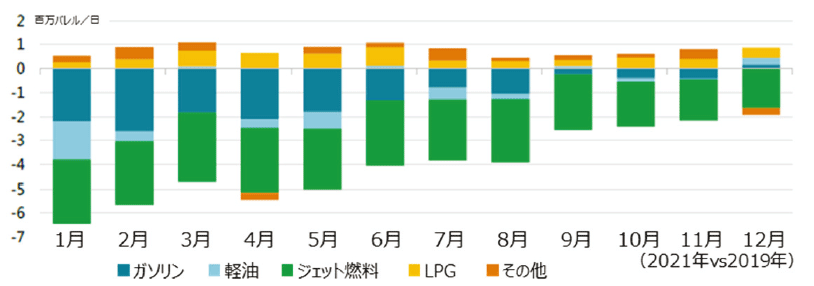
【第121-2-2】石油製品別の需要の比較(ppt/pptx形式:55KB)
- 出典:
- IEA, Oil Market Report
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、短期的な需要・供給の減少のみならず、デジタル化や電子商取引等の増加等の接触回避、リモートワークや在宅勤務等の職住不接近、生産現場等の無人化やAI化の進展等の省人化・合理化など、永続的なものとなる可能性があり、エネルギー需要にも影響を及ぼしていくものと考えられます。
- 3
- 2006年に100機関で始まった国連責任投資原則(PRI:Principles for Responsible Investment)への署名機関数は2021年1月には3,500機関以上へと増加。
- 4
- 2006年に国連の提唱で「責任投資原則(PRI: Principle for responsible Investment)」が策定され、環境・社会・ガバナンス要素を投資判断に組み込む「ESG投資」の考え方が打ち出された。
- 5
- 「S」や「G」の要素と比較して、「E」の要素は二酸化炭素排出量など定量的に評価しやすいという側面もあると指摘されている。
- 6
- UNISDR (2018)「EconomicLosses,Poverty&Disasters 1998-2017」。なお同レポートが執筆された2018年時点では、設立時の名称である「UNISDR:United Nations International Strategy for Disaster Reduction」(国連防災戦略事務局)であったが、2019年5月に「United Nations Office for Disaster Risk Reduction」(国連防災機関)に名称変更された。
- 7
- 「インフラシステム海外展開戦略2025」第49回経協インフラ戦略会議(令和2年12月10日)決定。
- 8
- 世界主要都市の気候変動対応ネットワークC40(世界大都市気候先導グループ)は、2020年9月に12市長の共同宣言として、自市の運用資産からの化石燃料関係の除外、年金基金や政府にも化石燃料の除外を呼びかけるなどしている。
- 9
- IEA(2020), World Energy Outlook 2020
- 10
- 機関投資家は、資産保有者から資産運用を受託していることから、受託者として資産を運用する責任を負っている。経済的リターン以外の要素を考慮しうるESG投資は、受託者責任を果たしていると言えるのかという論点が存在し、米国では、「1974 年従業員退職所得保障法」(通称ERISA 法)に規定される受託者責任の解釈通達が2008年や2015年に発出されている。
- 11
- 日本銀行「ESG投資を巡るわが国の機関投資家の動向について」(2020年7月)
- 12
- 「ICEF2020」「RD20」「TCFDサミット2020」「第9回LNG産消会議」「カーボンリサイクル産学官国際会議2020」「水素閣僚会議2020」が開催された。
- 13
- 企業の気候変動への取組、影響に関する情報を開示する枠組み。
- 14
- 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
- 15
- 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
- 16
- Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)
- 17
- 横浜市と12の市町村が2019年に結んだ「脱炭素社会の実現を目的とした再生可能エネルギーに関する連携協定」等において言及がある
- 18
- EA「Oil Market Report」(2021年3月17日)