第1節 日本を取り巻く近年の環境変化
1.ロシアによるウクライナ侵略等による経済安全保障上の要請の高まり
2022年2月のロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化など、ここ数年、エネルギーの安定供給やエネルギー価格に影響を与えるリスクが顕在化し、経済安全保障上の要請が高まっています(第121-1-1)。
【第121-1-1】世界のエネルギーを取り巻く動向
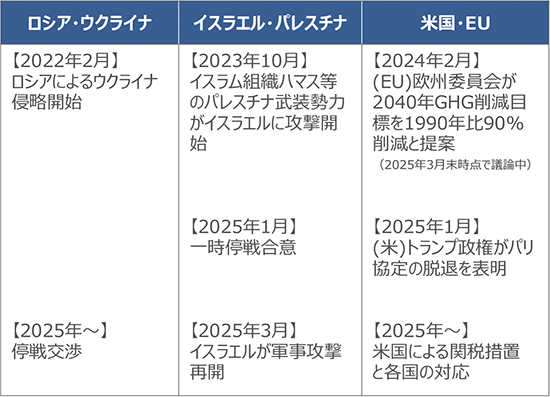
【第121-1-1】世界のエネルギーを取り巻く動向(pptx形式:49KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
日本は、エネルギー自給率は2023年度時点で15.3%であり、G7各国で一番低い水準になっています。こうした中、ロシアによるウクライナ侵略以降、LNGの需給ひっ迫や世界的な化石燃料の価格高騰などエネルギー危機が危惧される事態となりました。このような事態は、日本のエネルギー供給体制が脆弱であり、エネルギー安定供給上の脆弱性を抱えていることを改めて浮き彫りにするとともに、日本の貿易収支にも大きな影響を与えています。
また、一次エネルギー供給で見ると、海外からの輸入に頼る化石エネルギーが8割以上を占めており、この水準はG7各国と比較しても高い水準にあります(第121-1-2)。
【第121-1-2】各国のエネルギー自給率及び一次エネルギー供給・電源構成に占める化石エネルギー比率(2022年)
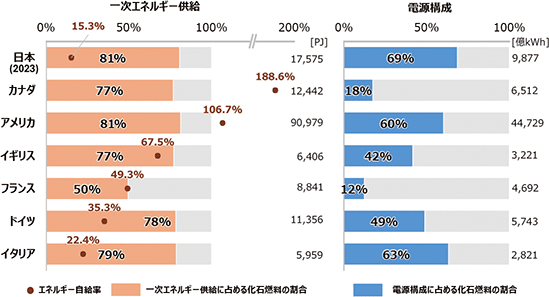
【第121-1-2】各国のエネルギー自給率及び一次エネルギー供給・電源構成に占める化石エネルギー比率(2022年)(pptx形式:652KB)
- 資料:
- IEA「World Energy Balances 2024」、「総合エネルギー統計」を基に経済産業省作成
2.DX・GXなどの進展に伴う電力需要増加の可能性
世界では、DXやGXなどの進展に伴う電力需要の増加が見込まれています。国際エネルギー機関(IEA)の「World Energy Outlook 2024」では、電力需要の主な変動要因として、データセンター需要、平均気温の上昇、電気機器の省エネルギー(以下「省エネ」という。)、EV需要拡大などが挙げられています。
日本においては、これまで人口減少や節電・省エネなどにより電力需要は減少傾向にありましたが、電力広域的運営推進機関が2025年1月に公表した「全国及び供給区域ごとの需要想定」(2025年度)では、今後は、節電・省エネなどの影響は継続しつつも、経済成長及びデータセンター・半導体工場の新増設に伴う需要増加により、電力需要が増加に転じると見込まれています。こうした場合においても必要となる脱炭素電源の供給が確保されるように万全の備えを行うことが重要となっています(第121-2-1)。
【第121-2-1】今後10年の電力需要の想定(左)、データセンター・半導体工場の新増設に伴う最大需要電力(右)
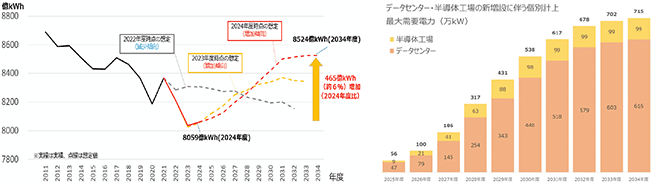
【第121-2-1】今後10年の電力需要の想定(左)、データセンター・半導体工場の新増設に伴う最大需要電力(右)(pptx形式:197KB)
- 資料:
- 電力広域的運営推進機関「全国及び供給区域ごとの需要想定」(2025年度)等を基に経済産業省作成
3.気候変動の野心維持と現実的かつ多様な対応
2023年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量は約10億1,700万トン(CO2換算)であり、前年度(2022年度)から4.2%減少し、基準年である2013年度と比べると27.1%減少しました。2023年度の排出量は排出量を算定している1990年度以降で過去最低値を記録し、これまでのところ2050年目標に向けた減少傾向を継続しています。しかし、日本の最終エネルギー消費の増減の動向を見ると、今の状況はエネルギー多消費産業の生産減退も大きな減少要因となっており、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素の同時実現に向け、予断を許さない状況となっています。
こうした中、日本は、2025年2月18日に、世界全体での1.5℃目標と整合的で、2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、新たな「日本のNDC1(国が決定する貢献)」を、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。新たなNDCでは、基準年度である2013年度からのフォアキャストと、長期的に目指している2050年ネット・ゼロからのバックキャストの両面から、直線的な経路での削減計画が示され、2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを目指すとの目標が掲げられました(第121-3-1)。
【第121-3-1】日本の新たな削減目標(NDC)
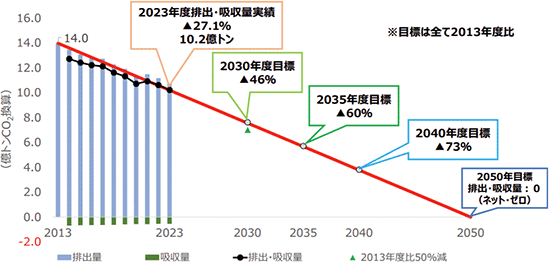
【第121-3-1】日本の新たな削減目標(NDC)(pptx形式:161KB)
- 資料:
- 日本のNDC「国が貢献する決定」
世界に目を転じると、国際エネルギー情勢の変化を受け、主要国は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた野心的な脱炭素目標を維持しながらも、各国の置かれた固有の状況を踏まえ、経済性やエネルギー安定供給との間でバランスを取る現実路線への転換を進めており、野心的な脱炭素目標と現実の乖離が拡大する傾向も見られています。
4.エネルギー政策と産業政策の一体化
欧米各国を中心に、世界各国では、気候変動対策と産業政策を連動させ、2050年カーボンニュートラル実現に向けた国内外のエネルギー転換を自国の産業競争力強化につなげるための政策を強化しています。
例えば、EUは2023年に採択した「グリーンディール産業計画」等により、域内におけるグリーン産業支援を強化しており、2025年2月には、気候変動対策と競争力強化を同時に実現させるための「クリーン産業ディール」を公表しています。ドイツなど各国でも新たな投資促進政策により、積極的なグリーン産業への支援が進められています。米国でも同様に、2022年8月に成立した「インフレ削減法」による支援を行ってきました2。
また、欧州中央銀行(ECB)元総裁・イタリア元首相のマリオ・ドラギ氏が2024年9月に公表した「The future of European competitiveness」(通称「ドラギ・レポート」)では、各国が脱炭素に向けて野心的な目標を掲げている中、その野心的な目標が産業界に短期的な追加コストとなり、大きな負担となっている点も踏まえ、産業政策の必要性を強調しています3。
日本においても、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換するGXの取組を通じて、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素の同時実現を目指しています。2023年2月の「GX実現に向けた基本方針」の策定(閣議決定)以降、10年間で150兆円規模の官民投資を呼び込むため、20兆円規模の先行投資支援策や成長志向型カーボンプライシング構想を順次実施しているほか、2025年2月には、将来の見通しに対する不確実性が高まる中、GXに向けた投資の予見可能性を高めるため、GXの取組の中長期的な方向性を官民で共有すべく、「GX2040ビジョン」が閣議決定されました。
- 1
- NDCとは「国が決定する貢献」を意味する、「Nationally Determined Contribution」の略称であり、パリ協定に基づいて、各国が自ら設定する、温室効果ガス排出削減のための目標等です。パリ協定においては定期的なNDCの見直しが求められており、日本は最新のNDCを2025年2月に提出しました。
- 2
- 2025年1月、第2期トランプ政権がパリ協定からの脱退を表明し、これまでのエネルギー・産業政策から大きく方針を転換しています。
- 3
- 2024年9月9日、欧州委員会は「The future of European competitiveness」と題する報告書(通称「ドラギ・レポート」)を公表しました。欧州の野心的な脱炭素目標が、産業界に短期的な追加コストをもたらし、欧州産業界にとって大きな負担となっている点を踏まえ、脱炭素に向けた取組は堅持しつつも、成長を加速させるためのEU域内投資の加速や、そのための公的資金の必要性等、産業政策の必要性が強調されています。