第2節 再生可能エネルギーの長期電源化に向けた取組
再エネの技術自給率を向上させ、より強靱なエネルギー供給構造を実現していくためには、次世代太陽電池である「ペロブスカイト太陽電池」や浮体式洋上風力等における技術の開発・実装を進め、再エネ導入に向けたイノベーションを加速させていく必要があります。
また、再エネの主力電源化を進めるためには、再エネを電力市場へ統合していくことも重要です。2022年度からは、FIT制度に加えて、市場連動型のFIP制度が導入されています。FIP制度では、発電事業者自身が卸電力取引市場や相対取引で売電を行うため、必要な環境整備、特にアグリゲーターの活性化が重要です。こうした状況を踏まえ、電力市場への統合を通じた再エネの導入拡大と新たなビジネスの創出を図るべく、FIP制度の詳細設計とアグリゲータービジネスの活性化に向けた検討を一体的に行いました。
さらに、分散型エネルギーリソースも柔軟に活用する電力システムへの変化が進む中、家庭や企業、公的機関、地域といった需要の範囲ごとに、自家消費や地域内系統の活用を含む需給一体型の再エネ活用モデルをより一層普及させるため、分散型エネルギーリソースのさらなる導入促進や分散型エネルギーリソースを活用する事業の構築支援、関係するプレイヤーの共創の機会創出等の事業環境整備も進めています。
加えて、欧州を中心に世界中で導入が拡大している洋上風力発電については、大量導入・コスト低減・経済波及効果が期待される再エネであり、再エネ海域利用法の着実な施行により案件形成を進めるとともに、洋上風力関連産業の産業競争力の創出に向けた取組を進めています。
1.認定案件の適正な導入と国民負担の抑制
(1)新規認定案件のコストダウンの加速化
日本における再エネの発電コストは、国際水準よりも依然高い水準にあり、FIT制度に伴う国民負担の増大をもたらしています。日本における再エネの発電コストが高い原因として、例えば、太陽光発電については、「市場における競争が不足しており、太陽光パネルや機器等のコスト高を招いていること」や、「土地の造成を必要とする場所が多く、台風や地震の対策も行う必要がある等、日本特有の地理的要因が工事費の増加をもたらしていること」等が挙げられます。
再エネの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、FIT制度では、入札を通じて調達価格を決定することが国民負担の軽減につながると認められる電源については、入札対象として指定することができるとしています。事業用太陽光発電については、2017年度の入札制度の導入以降、入札対象範囲を順次拡大しており、2020年度からは「250kW以上」に拡大しました。2021年度からは、予見可能性の向上のために上限価格を公表するとともに、参加機会の拡大のために入札実施回数を年2回から年4回としました。また、陸上風力発電については、2021年度から「250kW以上」を入札対象とし、2022年度からは入札対象を「50kW以上」に拡大しました。加えて、一般木材等バイオマスによるバイオマス発電(10,000kW以上)及びバイオマス液体燃料によるバイオマス発電等についても、入札を行ってきました。
今後、2050年カーボンニュートラルの実現を目指す上では、再エネのさらなる導入拡大が不可欠であり、コスト低減に向けた継続的な取組とともに、案件組成が促されるような制度設計・環境整備が必要です。そうした中、2023年度までの調達価格等算定委員会での議論を踏まえ、2024年度における事業用太陽光発電の入札対象範囲については「250kW以上」とするとともに、設置の形態等に応じてメリハリをつけてさらなる導入促進を図るべく、屋根設置の太陽光発電については引き続き入札制の適用を免除することとしました。また、陸上風力発電(50kW以上)、一般木材等バイオマスによるバイオマス発電(10,000kW以上)及びバイオマス液体燃料によるバイオマス発電については、2024年度も引き続き入札対象とすることとしました。なお、陸上風力発電については、入札実施回数が年に1回であることから、最大限の導入と国民負担の抑制を図るため、応札容量が募集容量を大きく上回った場合には、同年度内に追加の入札を行うこととしています。また、着床式洋上風力発電(再エネ海域利用法適用外)についても、再エネ海域利用法に基づく公募における事業者の参加状況や評価結果を踏まえ、国内の着床式洋上風力発電において、一定程度の競争効果が見込まれることから、入札制を適用することとしました。
(2)住宅用太陽光発電設備の意義とFIT買取期間終了の位置づけ
太陽光発電は、温室効果ガスを排出せず、日本のエネルギー安全保障に寄与するとともに、火力発電等とは異なり燃料費が不要であり、また、自家消費を行い、非常用電源としても利用可能な分散型電源となりうる等の特徴があります。一般家庭が太陽光発電設備を設置する理由は様々ですが、光熱費の節約や売電収入を得るといった経済的な理由だけでなく、自ら発電事業者として再エネの推進に貢献することを目指している方もおられます。一般的に、太陽光パネルは20年以上にわたって発電し続けることが可能であり、特に住宅に設置された太陽光パネルは、住宅が改築・解体されるまで稼働し続けることが期待されます。
2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた住宅用太陽光発電設備については、2019年11月以降、固定価格での調達期間が順次満了を迎えています。その規模は、2023年までの累積で約135万件、約819万kWとなっており、今後も2025年までの累積で約200万件、約860万kWに達する見込みとなっています。しかし、これはFIT制度という支援制度に基づく10年間の買取が終了しただけに過ぎず、その後も10年以上にわたって、自立的な電源として発電していくという役割が期待されています。
10年間にわたる調達期間終了後の円滑な移行に向けて、現行の買取事業者からは、買取期間の終了が間近に迫った世帯に対して、調達期間終了日等が個別に通知されています。また、資源エネルギー庁のホームページ上にも情報提供ページを開設しており、調達期間終了後の選択肢の提示や、電気の買取を希望する事業者情報の提供等を行っています。
2.FIP制度へのさらなる移行促進に向けて
再エネの主力電源化には、再エネを電力市場へ統合していくことが重要です。2020年2月に主力電源化小委員会でまとめられた「中間取りまとめ」の内容を踏まえ、同年6月に成立した再エネ特措法の改正を含むエネルギー供給強靱化法に基づき、2022年度より、FIT制度に加えて、市場連動型の「FIP制度」が導入されています。
FIP制度とは、再エネ発電事業者が、発電した電気を他の電源と同様に卸電力取引市場や相対取引で自ら自由に売電し、その際に得られる市場売電収入を踏まえ、「発電コスト等により算出されるプレミアム算定の基準となる価格(基準価格)と市場価格に基づく価格(参照価格)の差額(プレミアム単価)×売電量」を基礎とした金額を交付することで、再エネ発電事業者が市場での売電収入に加えてプレミアムによる収入を得ることにより、投資インセンティブを確保する仕組みです。
基準価格は、FIT制度における調達価格に対応するものであり、各区分等のFIT制度における調達価格と同水準となっています。また、参照価格は、卸電力取引市場の前年度1年間の平均価格を基に、月ごとの価格補正や電源の発電特性等も踏まえて算定されます。この2つの価格の差額を踏まえたプレミアムが再エネ発電事業者に交付されることで、再エネ事業の投資インセンティブが確保されるだけでなく、電力市場への統合に向けて、再エネ発電事業者に電力市場を意識した電気供給を促していくことができます。その際に発現される効果は、基準価格が固定であるため、参照価格の変更頻度によって変わりますが、事業者に対し、燃料調達やメンテナンス時期の工夫等により、電力需給を踏まえた季節をまたぐ行動変容を促すため、前述の算定方法を採用しました。また、これに加えて、出力制御が発生するような時間帯にはプレミアムを交付しないという算定方法を設定することにより、再エネ発電事業者に対し、蓄電池の併設や太陽光パネルの設置方法の工夫等、電力需給を踏まえた電気供給をするインセンティブとなるよう、設計されています(第332-2-1)。
【第332-2-1】FIP制度の概要
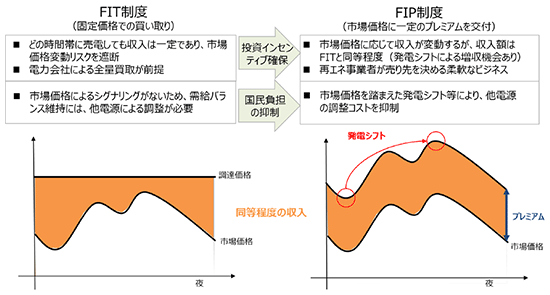
【第332-2-1】FIP制度の概要(ppt/pptx形式:144KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
さらに、FIP電源の持つ環境価値については、市場とFIP制度の双方からの環境価値の二重取りにならないようにする前提で、再エネ発電事業者が自ら販売する仕組みとしています。
FIP制度の対象については、調達価格等算定委員会において、それぞれの再エネ電源の発電特性、動向、事業環境、業界団体からのヒアリング等を踏まえながら審議が行われており、一定規模以上の新規認定については、FIP制度のみ認めています。加えて、50kW以上の認定事業者については、FIT制度の対象事業者であっても、FIP制度の利用を認めることとしています。2023年度からは、一定の要件を満たした場合、10kW以上50kW未満の太陽光発電事業者についても同様に、FIP制度を利用することが可能となっています。
また、FIT制度における市場取引を免除された特例的な仕組みを見直し、FIP制度への移行を通じて、他の電源と同様に市場取引を行う仕組みへと改めていくためには、様々な環境整備が重要です。
まず、再エネの市場統合を進めていくためには、再エネ発電事業者自らが、発電した再エネ電気の市場取引等を行う必要があります。その具体的な方法としては、自ら卸電力取引市場で取引を行う方法、小売電気事業者との相対(直接)取引を行う方法、アグリゲーターを介して卸電力取引市場で取引を行う方法の3つの方法が主に想定され、こうした取引を通じて、再エネ関連ビジネスの高度化や電力市場の活性化が進むと期待されます。一方で、電気を引き受ける側の小売電気事業者やアグリゲーターにとっては、発電予測や出力調整が従来電源に比べて容易ではない再エネ電気を相対取引するインセンティブが低い可能性もあるため、発電予測支援ビジネスやアグリゲーション・ビジネスの活性化のための環境整備を進めていくことも重要です。FIT制度からFIP制度へと移行してもなお、引き続き再エネの導入を拡大させていくために、アグリゲーターには、小規模再エネ由来の電気も含めたより多くの再エネ電気を、効率的・効果的に市場取引することが期待されます。
こうした市場環境整備を進めるための仕組みを、FIP制度の詳細設計においても検討しました。例えば、再エネ発電事業者やアグリゲーターが持つ調整電源を上手く活用するため、FIP電源については、FIP電源以外の一般電源や他のリソースと一緒の発電バランシンググループを組成することを認めることにしました。また、アグリゲーションが可能な電源をFIP制度の開始当初から増やしていくため、FIT認定事業者が希望する場合には、FIP制度へ移行することを認めることにしました。
加えて、FIT制度において免除されてきた再エネ発電事業者のインバランス負担についても、FIP制度においては、再エネの市場統合を図っていくため、他電源と同様に再エネ発電事業者にその負担が課されることになります。その際、再エネ発電事業者にインバランスを抑制させるインセンティブを持たせ、当該コストを下げるように努力することを促す制度とするため、FIP認定事業者には、バランシングコストとして、再エネ電気の供給量に応じてkWh当たり一律の額を交付することとしました。バランシングコストについては、発電量の予測や予測誤差への対応が、発電事業者がFIT制度からFIP制度に移行するに当たってのボトルネックになっていることを踏まえ、大量導入小委員会及び調達価格等算定委員会において議論を行い、変動電源の発電事業者がFIP制度として運転を開始してから3年間のバランシングコストを時限的に見直す措置を、2024年度より開始しました。
また、FIT制度からFIP制度への移行をさらに促進させるために、国民負担の増大を抑制しつつ、蓄電池の活用を促す観点から、FIT制度からFIP制度への移行案件に対して、事後的に蓄電池を設置した場合の基準価格変更ルールの見直しについて、大量導入小委員会及び調達価格等算定委員会において議論がなされ、2023年度より運用を開始しました。具体的には、発電設備の出力(PCS出力と過積載部分の太陽電池出力)と基準価格(蓄電池設置前の基準価格と蓄電池設置年度における該当区分の基準価格)の加重平均値に変更することで、従来の「最新価格への変更」に比べ、移行案件に対する蓄電池設置のインセンティブが高まることが期待されます。さらに、2024年度からは、蓄電池の稼働率の向上を図るため、FIP認定設備に併設する蓄電池に系統から充電する場合の価格算定ルールを開始しています。
3.需要家主導による再生可能エネルギーの導入
世界及び日本において、太陽光発電コストの急激な低下、デジタル技術の発展、電力システム改革の進展、再エネを求める需要家とこれに応える動き、多発する自然災害を踏まえた電力供給システムの強靱化(レジリエンス向上)への要請、再エネを活用した地域経済の活性化等への注目等、様々な変化が生じています。加えて、2019年11月以降は、FIT制度による調達期間を終え、投資回収を終えた安価な電源として活用できる住宅用太陽光発電(FIT卒業電源)が出現しています。
こうした構造変化により、「大手電力会社が大規模電源と需要地を系統でつなぐ従来の電力システム」から、「分散型エネルギーリソースも柔軟に活用する新たな電力システム」への大きな変化が生じつつあり、こうした変化を踏まえ、自家消費や地域内系統の活用を含む、需給一体型の再エネ活用モデルをより一層促進することが求められています。こうしたモデルの普及のために、DRを活用した民間の様々なサービスや、EVをはじめとした新たな分散型エネルギーリソースも含めた新たなビジネス創出の動きを加速化するための事業環境整備が必要となっています。
こうした中、官民が連携して課題分析を的確に行うとともに、分散型エネルギーに関係するプレイヤーが共創していく環境を醸成することを目的として、「分散型エネルギープラットフォーム」を開催しました。これは、2019年度から経済産業省と環境省が共同で開催しており、取組事例の共有や課題についての議論等を行う場を設けることで、幅広いプレイヤーが互いに共創する機会を提供するものです。2023年度は、物流・運輸部門の脱炭素化、木質バイオマスの利活用、製造業における太陽光発電導入のビジネスモデル、大規模・中小規模の需要家によるソーラーカーポートや水上太陽光等を含めた自家消費型太陽光の導入拡大といったテーマに関して、関係する事業者等が参加し、課題の整理等について議論しました。
太陽光発電については、「RE100」等の潮流により需要家サイドの再エネに対するニーズが高まる中、需要家の再エネの調達ニーズを満たすビジネスモデルは普及途上にあります。FIT・FIP制度は再エネの導入を急速に進めましたが、国民負担の抑制や地域との共生に課題があり、今後は需要家による再エネ電気のニーズを背景に、需要家と発電事業者等が連携して、非FIT・非FIPの太陽光発電の導入を促進していく必要があります。また、太陽光発電等の出力の安定しない電源の導入量が増加し、出力制御が喫緊の課題となっている中において、発電設備に蓄電池を併設して、ピークシフトを行うことは、再エネの導入拡大及び電力の安定供給の観点から有効な手段です。
住宅用太陽光発電の価格低下による自家消費のメリットの拡大や、FIT制度を卒業した太陽光発電の出現により、今後は、自家消費や余剰電力活用の多様化が進んでいくことが期待されます。一方、住宅を購入する多くの消費者にとっては、太陽光発電への設備投資に伴う追加的な経済的負担は大きく、住宅のZEH化に向けた課題となっています。このような中で、再エネの導入をより一層拡大しつつ、ZEHを普及させていくためには、太陽光発電等の設備を第三者が保有するビジネスモデルを活用した新たなZEHのあり方について検討していくことも重要となってきています。また、家庭や大口需要家に設置された再エネによる自家消費を促進するためには、エコキュートや蓄電システム、電気自動車等の分散型エネルギーリソースの導入促進も重要です。そのため、特に家庭用蓄電システム等については、普及拡大に向けた課題及びその対応策を整理するとともに、目標価格や導入見通し等を策定しています。目標価格については、経済産業省等の補助事業において、採択要件として活用しています。
再エネ電源を自律的に活用する地域における需給一体的なエネルギーシステムは、エネルギー供給の強靱化(レジリエンス)や、地域内のエネルギー循環・経済循環等の点で有効です。そのため、地域の再エネをコージェネレーション等の他の分散型エネルギーリソースと組み合わせて利用するといった、地域レベルで再エネを需給一体的に活用する取組について、こうした取組をより行いやすくするための仕組みのあり方や、他分野の政策との連携強化等について、検討をさらに深めていくことが重要です。
また、自営線を活用してエネルギーを面的に利用する分散型エネルギーシステムの構築については、導入コスト等のコスト面や工事の大規模化が大きな課題となっています。こうしたコスト面の課題解決に向けて、災害等による大規模停電時に、既存の系統配電線と地域にある再エネや分散型電源を活用することで、自立した電力供給が可能となる「地域マイクログリッド」の構築が進められています。一方、災害時だけでなく、平時における活用も見据えて、制度的・技術的課題の整理を行い、事業環境の整備を進めていく必要もあります。そこで、地域マイクログリッド事業に申請する事業者向けに、一般送配電事業者や地元自治体等のステークホルダーとの調整や事業を進めていく上での具体的な手順を示した手引書を作成しました。また、2022年度は、千葉県いすみ市や北海道釧路市等において、地域マイクログリッドが構築されました。
加えて、自家消費や地域と一体となった事業を優先的に評価するため、一定の要件(地域活用要件)を満たす再エネ事業については、当面、FIP制度のみならず、現行のFIT制度の基本的な枠組みを維持して支援しています。その具体的な地域活用要件については、下記のとおりです。
まず、小規模事業用太陽光発電は、立地制約が小さく、需要地近接での設置が容易な電源です。このため、需要地において需給一体的な構造として系統負荷の小さい形で事業運営がなされ、災害時にも活用されることで、全体としてレジリエンスの強化に資することを要件とする、「自家消費型」の地域活用要件を設定することが必要です。
そうした中、特に低圧事業(10kW以上50kW未満)については、地域でのトラブルや、大規模設備を意図的に小さく分割することによる安全規制の適用逃れ、系統運用における優遇の悪用等が発生し、地域での信頼が揺らぎつつあります。地域において信頼を獲得し、長期安定的に事業運営を進めていくためには、全量売電を前提とした野立て型設備ではなく、自家消費を前提とした屋根置き設備等への支援を重点化し、地域に密着した形での事業実施を求めていくことが重要です。このため、低圧事業については、2020年度から、自家消費型の地域活用要件をFIT制度の認定基準として求めています。
自家消費型の具体的な要件として、まず、自家消費を行う設備構造を有しており、加えて、需要地内において自家消費を行う計画であることを求めています。その際、ごくわずかしか自家消費を行わない設備が設置され、全量売電となることを防ぐため、自家消費の確認を厳格に行います。さらに、災害時に活用するための最低限の設備を求めるものとして、給電用コンセントを有し、災害時には利活用が可能であることを求めることとしました。ただし、営農型太陽光発電設備については、営農と発電の両立を通じて、エネルギー分野と農林水産分野での連携の効果が期待されるものもある中で、一部の農地においては近隣に電力需要が存在しない可能性もあることに鑑み、農林水産行政の分野における厳格な要件確認を条件として、自家消費を行わない案件であっても、災害時における活用が可能であれば、自家消費型の地域活用要件を満たすものとして認めることとしています。
また、2022年度以降の新規認定においては、共同住宅の屋根に設置する10kW以上20kW未満の太陽光発電設備について、自家消費を行う設備構造を有していれば、自家消費量の基準も満たしているものとして取扱うこととしています。さらに、近接した10kW未満の複数設備(地上設置)において認定を取得し、設備を意図的に10kW未満に分割する等、10kW以上50kW未満の地域活用要件逃れの疑いのある案件が生じていることから、10kW未満で地上設置を選択した案件についても、建物登記等の提出を求めて自家消費を行う建物等の確認を行うこととし、地域と共生した形での太陽光発電の導入加速を図っています。
なお、高圧以上事業(50kW以上)については、調達価格等算定委員会での議論を踏まえ、地域活用要件を設定してFIT制度による支援を当面継続していくのではなく、各電源や事業環境の状況を踏まえながら、FIP制度の対象を順次拡大していき、早期の自立を促す方針です。
地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電については、太陽光発電と比べて立地制約が大きく、太陽光発電や風力発電と比べると、FIT制度の開始以降も導入スピードは緩やかであり、現時点では発電コストの低減に向けた道筋が明確化していません。他方で、電源特性の観点から、地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電は、発電予測又は出力調整がしやすく、FIP制度への適性が比較的高いことも明らかになってきました。
こうした中、再エネの自立化を促すため、調達価格等算定委員会での議論を踏まえ、地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電でFIT制度の新規認定を認める対象については、FIP制度が施行された2022年度から地域活用要件を求めることとし、その規模について、地熱発電・水力発電は1,000kW未満、バイオマス発電は2,000kW未満としました。また、陸上風力発電については、50kW未満(リプレース案件は1,000kW未満)のものを対象に、2023年度から地域活用要件を求めています。
また、これらの電源に適用される地域活用要件については、調達価格等算定委員会での議論を踏まえ、FIP制度の適用対象の拡大を念頭に置いた制度設計であるという発想の下、いたずらにコストの増加をもたらさず、相対的に緩やかなものが設計されています。具体的には、自家消費型・地域消費型の地域活用要件又は地域一体型の地域活用要件のいずれかを満たすことが求められています。
自家消費型・地域消費型の地域活用要件としては、低圧太陽光発電事業の地域活用要件と同程度に電気を自家消費することが求められます。又は、再生可能エネルギー電気特定卸供給により供給し、かつ、その供給先の小売電気事業者等が、小売供給する電気の一定割合を当該発電設備が所在する都道府県内へ供給することが求められます。あるいは、発電設備から産出された熱を原則として常時利用しつつ、一定の電気についても自家消費することが求められます。
地域一体型の地域活用要件としては、当該発電設備が所在する地方公共団体の名義の取決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む電気又は熱の当該地方公共団体内への供給が位置づけられていることが求められます。又は、地方公共団体が当該発電事業を自ら実施又は直接出資することが求められます。あるいは、再生可能エネルギー電気特定卸供給により供給し、かつ、その供給先の小売電気事業者等が、地方公共団体が自ら事業を実施又は直接出資するものであることが求められます。なお、こうした地方公共団体が自ら事業を実施又は直接出資するものについては、地方公共団体の主体的な関与を求めていきます。
4.立地制約克服に向けた取組
(1)洋上風力を巡る世界の動き
洋上風力発電には、陸上風力発電と比較して様々な特徴があります。まず、洋上は陸上よりも風況が比較的優れているため、設備利用率をより高めることが可能(世界平均では陸上が約30%、洋上が約40%)です。また、輸送制約等が小さく、大型風車の設置が可能であり、建設コスト等を抑えることができるため、コスト競争力のある再エネ電源といえます。さらに、事業規模が数千億円に至る場合もあり、部品数も数万点と多いため、部品調達・建設・保守点検等を通じて、地元産業を含めた関連産業への波及効果が期待できます。
このような特徴を持つ洋上風力発電は、近年世界で飛躍的に導入が拡大している再エネ電源の1つであり、世界風力エネルギー協会(GWEC)によると、世界の洋上風力発電の導入量は、2013年以降毎年増加しており、2022年には約8.8GWが導入されました。2022年末の累積導入量は約64.3GWとなっており、全風力発電導入量の約6%を占めています。
欧州では、1990年に、スウェーデンで世界初の洋上風力発電所の実証試験が開始されたのを皮切りに、デンマークやオランダ等で次々に実証試験が行われました。2000年頃からは、デンマークを中心に、事業化を目指した洋上風力発電所の建設が始まり、2000年代半ば頃からは、英国やベルギー、ドイツ等の参入が進みました。2022年末時点では、世界の洋上風力発電導入量の約4割を欧州が占めています。
欧州において洋上風力発電の導入が進んだ背景には、いくつかの要因があります。まず、北海等の欧州の海は風況が良く、加えて、海岸から100kmにわたって水深20m〜40mの遠浅の軟弱地盤の地形が続く等、自然的条件に恵まれている点が挙げられます。また、2000年代後半以降、欧州では洋上風力発電についてのルール整備が進められ、設置のための調査や、事業を実施する区域の選定、電力系統の確保等について政府の役割が増しており、これによって、事業者の開発リスクが低減してきたことも大きな要因です。また、入札制度も導入されており、事業者間の競争が促されたことで、コストが急速に低下している点も重要です。例えば、2015年以降の入札では、落札額が10円/kWhを下回る事例や市場価格となる事例(補助金ゼロ)も生まれています(第332-4-1)。
【第332-4-1】欧州における洋上風力発電の入札の動向
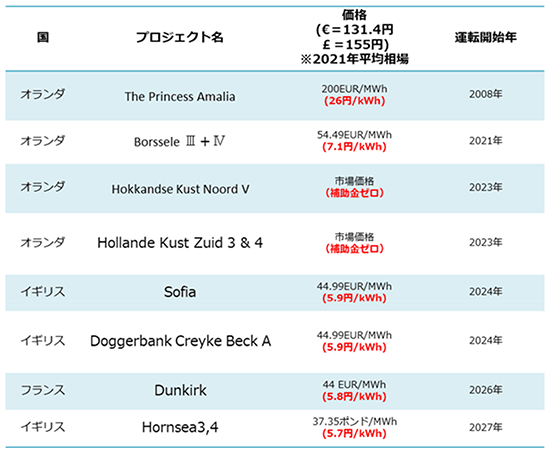
【第332-4-1】欧州における洋上風力発電の入札の動向(ppt/pptx形式:114KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
(2)日本の状況と再エネ海域利用法の運用
周囲を海に囲まれた日本にとって、洋上風力発電の導入は重要です。「第6次エネルギー基本計画」の中でも「特に、洋上風力は、大量導入やコスト低減が可能であるとともに、経済波及効果が大きいことから、再生可能エネルギー主力電源化の切り札として推進していくことが必要である」と明記されています。また、洋上風力発電は、海外において急激にコストの低下が進んでおり、大規模な開発も可能であることから、再エネの最大限導入と国民負担の抑制を両立しうる重要な電源です。しかし、主に2つの課題により、日本においては導入が進んでいない状況にありました。
1つ目の課題は、「海域の占用に関する統一的なルールがない」ことです。従来、海域の大半を占める一般海域には、占用に関する統一ルールがなく、都道府県が条例に基づき通常3年〜5年の占用許可を出すといった運用がなされていました。FIT制度の調達期間である20年と比較して、短期間の占用許可しか得ることができないため、中長期的な事業予見性が低くなり、資金の調達が困難になっていました。2つ目の課題は、「先行利用者との調整の枠組みが不明確」ということです。海域を新たに利用するに当たっては、漁業や海運業等の地域の先行利用者との調整が不可欠ですが、調整のための枠組みが存在せず、事業者にとっては大きな負担となっていました。
これらの課題の解決に向けて、2019年4月に再エネ海域利用法が施行されました。再エネ海域利用法の手続の流れに基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が、自然的条件が適当であること、漁業や海運業等の先行利用者に支障を及ぼさないこと、系統接続が適切に確保されること等の要件に適合した区域を「促進区域」として指定し、公募による事業者選定を行います。選定された事業者は、促進区域内で最大30年間の占用許可を受けるとともに、再エネ特措法に基づく認定を得ることができます。公募による事業者選定では、長期的・安定的・効率的な事業実施の観点から、最も優れた事業者を選定することにより、コスト効率的かつ長期安定的な洋上風力発電の導入を促進する仕組みとなっています(第332-4-2)。
【第332-4-2】再エネ海域利用法の手続の流れ
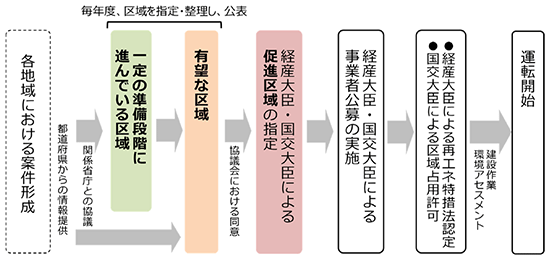
【第332-4-2】再エネ海域利用法の手続の流れ(ppt/pptx形式:236KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
制度運用を進めるため、2019年5月には、再エネ海域利用法に基づく「海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を策定するとともに、同年6月には、関係審議会での議論を踏まえて、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」と「一般海域における占用公募制度の運用指針」の2つのガイドラインを定めました。このうち、一般海域における占用公募制度の運用指針については、2022年10月に改訂を行っています。
前述の法令及びガイドラインに基づき、毎年着実な案件形成を進めており、2023年10月には、今後の促進区域の指定に向けて、既に一定の準備段階に進んでいる区域として8区域、有望な区域として9区域を整理しました。
「長崎県五島市沖」については、2019年12月に促進区域として指定し、公募占用計画の審査を経て、2021年6月に事業者選定を行いました。秋田県・千葉県の計3海域(「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」、「千葉県銚子市沖」)については、2020年7月に促進区域として指定し、公募占用計画の審査を経て、2021年12月に事業者選定を行いました。秋田県・新潟県・長崎県の計4海域(「秋田県八峰町及び能代市沖」、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」)については、「秋田県八峰町及び能代市沖」を2021年9月に、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」を2022年9月に促進区域として指定し、公募占用計画の審査を経て、2023年12月に「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」の事業者選定を行い、2024年3月に「秋田県八峰町及び能代市沖」の事業者選定を行いました。
さらに、「青森県沖日本海(南側)」、「山形県遊佐町沖」については、2023年10月に新たに促進区域として指定しており、2024年1月より、洋上風力発電事業を行うべき者を選定するための公募を開始しました。
これらにより、2024年3月末時点で、事業者が選定されている8区域を含む10の促進区域を指定しており、合計で約4.6GWの案件を形成しています(第332-4-3)。
【第332-4-3】再エネ海域利用法の施行状況(2024年3月時点)
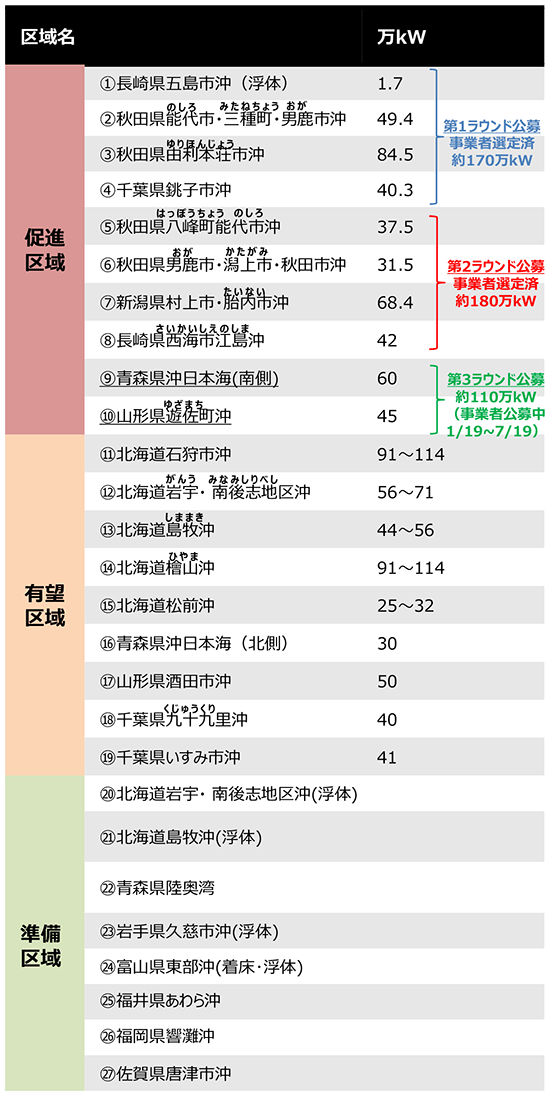
【第332-4-3】再エネ海域利用法の施行状況(2024年3月時点)(ppt/pptx形式:49KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
また、洋上風力発電の導入に当たっては、海洋環境を含む環境への適正な配慮と、地域との対話プロセスが重要になります。洋上風力発電の環境配慮に関しては、2022年6月の「規制改革実施計画」において、「環境アセスメント制度について、立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適な在り方を、関係府省、地方公共団体、事業者等の連携の下検討する」とされたことを受け、2022年度にとりまとめた新たな環境影響評価制度の方向性に基づき、関係省庁で「洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方に関する検討会」を開催し、2023年8月には、洋上風力発電に係る新たな環境影響評価制度についてのとりまとめを行いました。また、このとりまとめを踏まえ、2024年3月には、中央環境審議会において、「環境影響評価法(平成9年法律第81号)」と再エネ海域利用法が適切に接続され、海洋環境への適切な配慮を確保しつつ洋上風力発電の導入を図るための新たな環境影響評価のあり方に関する「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)」が提言されました。当該中央環境審議会第一次答申を踏まえ、同年3月12日に政府から第213回国会に提出した再エネ海域利用法の改正法案において、促進区域の指定の際に環境大臣が環境に係る調査を行い、当該調査結果を踏まえた環境配慮を図るとともに、当該手続を踏まえた事業者の環境影響評価手続に係る環境影響評価法の特例措置の規定を導入することとしています。
このほか、質の高い環境影響評価を効率的に進めるために、環境省及び経済産業省共同で「洋上風力発電に係る環境評価手法の技術ガイド」を公表しました。また、環境省は、環境影響評価に活用できる地域の環境基礎情報を収録した「環境アセスメントデータベース”EADAS(イーダス)”」において、情報の拡充や更新を行いました。
(3)洋上風力関連産業の産業競争力強化に向けた取組
再エネ海域利用法に基づき、洋上風力発電の案件形成は着実に進んでいます。洋上風力発電のさらなる導入拡大には、洋上風力関連産業の産業競争力を強化し、コスト低減をしっかりと進めていくことが重要です。このため、再エネ海域利用法を通じた洋上風力発電の導入拡大と、これに必要となる関連産業の産業競争力強化や国内産業集積、インフラ環境整備等を、官民が一体となる形で進めて相互の「好循環」を実現していくため、「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」を2020年7月から開催しました。同年12月には、「洋上風力産業ビジョン(第1次)」(以下「産業ビジョン」という。)を策定し、中長期的な政府及び産業界の目標、目指すべき姿と実現方策等について、一定の方向性を示しました。
この産業ビジョンでは、「魅力的な国内市場の創出」、「投資促進・サプライチェーン形成」、「アジア展開も見据えた次世代技術開発と国際連携」といった基本方針に基づき、方策等についての一定の方向性をとりまとめました。政府による導入目標としては、年間100万kW程度の区域指定を10年継続し、2030年までに1,000万kW、2040年までに浮体式も含む3,000万kW〜4,500万kWの案件を形成することを掲げています(第332-4-4)。
【第332-4-4】「洋上風力産業ビジョン(第1次)」の概要
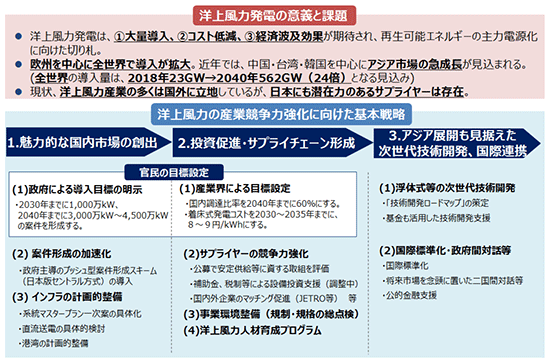
【第332-4-4】「洋上風力産業ビジョン(第1次)」の概要(ppt/pptx形式:170KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
この政府目標の達成に向けた案件形成を加速するためには、まず、「セントラル方式」による事前調査等のプッシュ型の案件形成や、ポテンシャルのある適地と需要地を結ぶ系統整備等の国内インフラ整備を進めていく必要があります。これまで、洋上風力発電の実施に当たっては、同一区域における初期段階の調査等を、複数の事業者が重複して実施することの非効率性が指摘されてきました。この課題を解消するために、案件形成の初期段階から政府が主導的に関与し、より迅速かつ効率的に調査等を実施する「セントラル方式」の一環として、JOGMECが担い手となり、風況や海底地盤といった洋上風力発電事業の検討に必要な調査を実施していくことにしています。2023年度からは、①北海道岩宇・南後志地区沖、②北海道島牧沖、③北海道檜山沖を対象に調査を実施しており、さらに、2024年度からは、①及び②の沖合海域、山形県酒田市沖を追加して、調査を実施する予定です。
また、電力の安定供給や経済波及効果といった観点からは、産業競争力があり、強靱なサプライチェーンを形成することが重要です。足元では、東芝の京浜事業所におけるGE製風車のナセル組立計画や、JFEエンジニアリングのモノパイル製造工場の建設、石狩湾新港洋上風力発電所における日鉄エンジニアリングのジャケット及び清水建設のSEP船(自己昇降式作業台船)の活用等、「着床式」の洋上風力を中心としたサプライチェーンの構築が進んでいます。このように、着床式の洋上風力の導入を着実に進めていくことも重要ですが、遠浅な海が広がる欧州と比べ、急深な地形・複雑な地層を有する日本では、深い海域でも利用可能な「浮体式」の洋上風力の導入拡大が不可欠です。浮体式洋上風力の商用化を早期に実現するため、グリーンイノベーション基金の「洋上風力発電の低コスト化プロジェクト」に対して1,195億円を割り当て、風車・浮体・電気システム・メンテナンスの4項目において、2021年にプロジェクトの採択を行い、フェーズ1として要素技術開発を進めています。2024年2月には、フェーズ2として、フェーズ1の技術を活かしながら実海域での大規模実証を行うため、実施事業者の公募を開始しました。
さらに、大量生産に向けてコストの低減を図っていく上では、各構成要素を1つのシステムとして統合し、全体最適を図っていくことが必要です。2023年に追加した40億円の予算も活用して、産業界が横断的に協調して共通基盤となる研究開発を進めつつ、さらには、先行する欧米とも連携することで、浮体式洋上風力における国際標準化等を活用し、グローバル展開を目指していきます。その先駆けとして、2023年10月にはデンマークとの間で、浮体式洋上風力に関する産学官の協力枠組みを立ち上げることを目的に、浮体式洋上風力の協力に関する基本合意書を締結しました。今後は、デンマークと同様に、他国との協調も進めていきます。
加えて、産業界においては、浮体式洋上風力の大量導入や発電コストの低減を目的として、発電事業者を中心に「浮体式洋上風力技術研究組合」を立ち上げ、2024年2月に経済産業大臣が設立を認可しました。今後、浮体式洋上風力の普及拡大に向けて、諸外国との連携等の取組がますます加速していくことが見込まれます。
さらに、風車については、グローバルなコスト競争と開発競争が激化しており、風車の大規模化が加速しています。日本としても、浮体式洋上風力の導入目標を掲げ、その実現に向けて、引き続き技術開発・大規模実証を実施するとともに、風車や関連部品、浮体基礎等の洋上風力関連産業における大規模かつ強靱なサプライチェーン形成や、人材育成の取組等を進めています。
特に、人材育成については、長期的、安定的に洋上風力発電を導入・普及させていく上で、風車製造関係のエンジニア、洋上工事や調査開発に係る技術者、メンテナンスを担う作業者等、幅広い分野における人材が必要です。2021年には、産業界と連携して必要なスキルの棚卸しを行っており、2022年度からは、大学・高専等や企業が洋上風力人材育成のために提供するカリキュラム作成や、風車設備のメンテナンスや洋上作業に係る訓練を行うための訓練設備整備費の補助を開始しました。今後も、引き続き、産業界とも連携をしながら支援を行っていく予定です。
(4)洋上風力発電の導入促進に向けた港湾法に基づく基地港湾の指定
洋上風力発電設備の設置及び維持管理に利用される基地港湾においては、重厚長大な資機材を扱うことが可能な耐荷重や広さを備えた埠頭が必要であり、参入時期の異なる複数の発電事業者間の利用調整も必要となります。このため、2019年12月に「港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第68号)」が公布され、国が基地港湾を指定し、当該基地港湾の特定の埠頭を構成する行政財産について、国から再エネ海域利用法等に基づく許可事業者に対し、長期的かつ安定的に貸し付ける制度を創設しました。これらの措置を講じることにより、事業の見込みが立ちやすくなり、洋上風力発電事業のより一層の円滑な導入に資することになります。
当該制度に基づき、2020年9月に能代港、秋田港、鹿島港、北九州港、2023年4月に新潟港を基地港湾として指定するとともに、2024年4月には新たに青森港及び酒田港を指定しました。秋田港については、既に地耐力強化のための工事が完了しており、2021年4月に発電事業者への貸付を開始しました。2020年9月に基地港湾として指定された他の3港については、2023年度も引き続き地耐力強化等の必要な整備を実施しています。