第2節 燃料アンモニアの導入拡大に向けた取組
アンモニアは天然ガスや再エネ等から製造することが可能であり、燃焼してもCO2を排出しないため、温暖化対策の有効な燃料の1つとされています。さらにアンモニアは、水素キャリアとしても活用でき、水素と比べ、既存インフラを活用することで、安価に製造・利用できることが特徴となっています(第382-1-1)。
【第382-1-1】燃料アンモニアの製造、輸送から利用
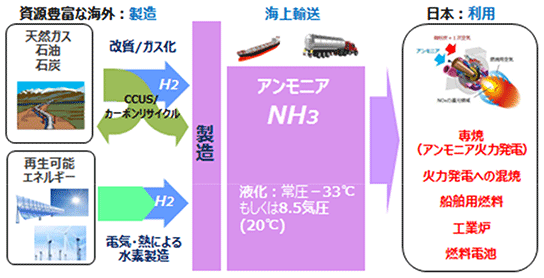
【第382-1-1】燃料アンモニアの製造、輸送から利用(ppt/pptx形式:289KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
1.2050年カーボンニュートラル達成に向けた燃料アンモニア政策の位置づけ
2020年10月の2050年カーボンニュートラル宣言を受けて、2020年12月に公表され、2021年6月にさらなる具体化がされた「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、燃料アンモニアは水素とともに、同戦略の14の重要分野の1つに位置づけられました。ここで、燃料アンモニアの活用については、2030年までに石炭火力への20%アンモニア混焼の導入・普及を目標に、実機を活用した混焼・専焼の実証を推進することで、2030年には国内需要として年間300万トン(水素換算で約50万トン)を想定し、そのためにN㎥-H2当たり10円台後半での供給を目指すこととしています。また、2050年には国内需要として年間3,000万トン(水素換算で約500万トン)を想定しており、アンモニアの利用拡大に対応したさらなる製造の大規模化、高効率化を追求した日本企業主導のサプライチェーンを構築することを目指しています。
こうした動きを踏まえ、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」においては、2030年度の電源構成においてアンモニアが水素とともに明記され、水素・アンモニアで1%程度を賄うこととされました。
さらに、クリーンエネルギー戦略の検討の中においても、燃料アンモニアの導入・拡大に向けた具体策について議論されており、2022年5月に公表された同戦略の中間整理において、水素と並んでアンモニアへの今後の投資額と支援検討の必要性が明記されました。また、GX実行会議においては、規制・支援一体型の投資促進策の例として水素・アンモニア等が明記されるとともに、GX実現に向けた基本方針の中でも水素・アンモニアの導入促進が記載されています。
このように、アンモニアの利用推進に向けた議論が進められており、燃料アンモニアに対して官民でのGX投資を進め、2050年カーボンニュートラル達成に貢献していく必要があります。日本は水素・アンモニア発電や海上輸送技術等の分野で世界をリードしています。これらの蓄積した技術を最大限活用して、今後も世界の成長市場を獲得するために、引き続き国としても燃料アンモニアへの支援を行っていく方針です。
2.燃料アンモニアの利用促進に向けた政策的な取組
(1)アンモニアの発電分野での利用
アンモニアは肥料等の用途で既に世界中で広く使われていることから、既存の製造・輸送・貯蔵技術を活用したインフラ整備が可能で、安全対策も確立されています。火力発電においてアンモニアを混焼する場合にも、バーナー等を変えるだけで対応できるため、既存の設備を利用することができ、新たな設備や初期投資を最小限に抑えながらCO2排出を削減することができます。特に、アンモニアと石炭は混焼が容易であることから、まずは石炭火力発電への利用が見込まれています。
アンモニアの混焼技術については、2014〜2018年における内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)での研究開発において、燃料時における窒素酸化物(NOx)の排出抑制が可能となりました。これを受けて、経済産業省(NEDO)の支援の下、2021年度から、JERAが愛知県に保有する碧南火力発電所でのアンモニア混焼の実証事業を実施しています。本事業はアンモニア混焼バーナーの開発を目的とし、従来のバーナーにアンモニア供給ノズルを追加した上で、2022年3月まで混焼バーナーとしての試験運転を実施し、アンモニア供給ノズルの材料選定を行いました。また、JERAは2022年5月に、100万kW級石炭火力実機での燃料アンモニア20%混焼実証の開始時期を、当初予定から約1年前倒しして、2023年度から実施することを発表しており、現在その開始に向けて取組を進めているところです(第382-2-1)。
【第382-2-1】石炭火力実機における20%アンモニア混焼の実証事業
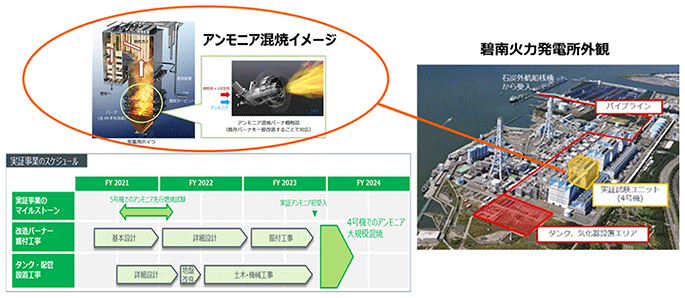
【第382-2-1】石炭火力実機における20%アンモニア混焼の実証事業(ppt/pptx形式:646KB)
- 資料:
- JERAプレスリリース
他方で、アンモニアが発電燃料として使われるようになると、石炭火力1基(100万kW)の20%混焼で年間50万トンのアンモニアが必要となるため、アンモニアの供給不足ひいては価格の高騰を招く恐れがあります。そのため、低廉かつ安定的な燃料アンモニアのサプライチェーンを構築することが課題となっています。
(2)燃料アンモニアに係る技術開発
燃料アンモニアの大規模な需要の創出と、安定的で安価な供給の実現に向けては、長期にわたる技術開発が不可欠となっています。そこで2021年9月に、グリーンイノベーション基金事業の1つとして実施する、「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクトの研究開発・社会実装計画を策定しました。
本計画では、①低温・低圧でより高効率にブルーアンモニアを製造する技術や、再エネから水素を経由することなくグリーンアンモニアを製造する技術といった、アンモニアの供給コスト低減に必要な技術の開発、②石炭ボイラやガスタービンでのアンモニア高混焼・専焼技術の開発、を主な内容としています。
本計画を基に、NEDOが「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクトの公募を行い、2022年1月に実施予定者を公表しました。本プロジェクトを通じて、アンモニア製造の高効率化・低コスト化から利用拡大までの技術的な課題を解決し、需要と供給が一体となった燃料アンモニアサプライチェーンの構築を目指します(第382-2-2)。
【第382-2-2】グリーンイノベーション基金:「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクト(概要)
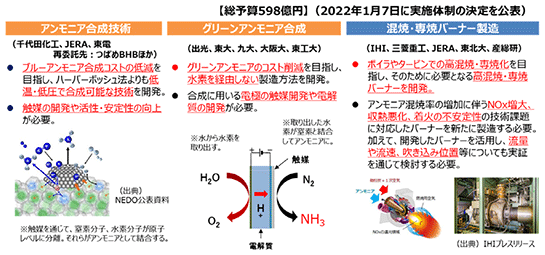
【第382-2-2】グリーンイノベーション基金:「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクト(概要)(ppt/pptx形式:422KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
- グリーンイノベーション基金事業「燃料アンモニアのサプライチェーン構築」の事業内容
実施期間:2021年度〜2030年度(予定)
国費負担上限:598億円
●【研究開発項目1】アンモニア供給コストの低減
- 研究開発内容(1) アンモニア製造新触媒の開発・実証
燃料アンモニアサプライチェーン構築に係るアンモニア製造新触媒の開発・技術実証
燃料アンモニアの利用拡大に向けて、製造コストの低減を実現できるアンモニア製造新触媒をコアとする国産技術を開発します。 - 研究開発内容(2) グリーンアンモニア電解合成
常温、常圧下グリーンアンモニア製造技術の開発
水と窒素を原料とした電解反応を活用し、常温常圧でアンモニアを製造する方法を開発します。
●【研究開発項目2】アンモニアの発電利用における高混焼化・専焼化
- 研究開発内容(1) 石炭ボイラにおけるアンモニア高混焼技術(専焼技術含む)の開発・実証
事業用火力発電所におけるアンモニア高混焼化技術確立のための実機実証研究
アンモニアと微粉炭を同時に燃焼するアンモニア高混焼微粉炭バーナーを新規開発し、事業用火力発電所においてアンモニア利用の社会実装に向けた技術実証を行います。
アンモニア専焼バーナーを活用した火力発電所における高混焼実機実証
アンモニア専焼バーナーを開発し、事業用火力発電所において従来の微粉炭バーナーと組み合わせ、アンモニア混焼率50%以上での実証運転を行います。 - 研究開発内容(2) ガスタービンにおけるアンモニア専焼技術の開発・実証
アンモニア専焼ガスタービンの研究開発
ガスタービンコジェネレーションシステムからの温室効果ガスを削減するため、2MWガスタービンに向けた液体アンモニア専焼(100%)技術を開発します。
(3)新たなサプライチェーン構築に向けた取組
前述の通り、燃料アンモニアの導入拡大に向けては、その新たなサプライチェーン構築が不可欠です。そこで、燃料アンモニアの需要・供給両面での国際連携を進めるために、①燃料アンモニアの国際的認知度の向上のため、国際エネルギー機関(IEA)から分析レポート発行で連携、②燃料アンモニアの新たな供給確保のために、産ガス国や再エネ適地国(北米・中東・豪州等)とサプライチェーン構築に向けた連携、③燃料アンモニアの海外での需要拡大のために、石炭火力利用国とアンモニア発電の可能性調査で連携、④燃料アンモニア国際会議を主催することで、日本主導で国際連携のプラットフォームを設立し、燃料アンモニアサプライチェーンの構築を主導、といった具体的な取組を進めています。
さらに、2022年5月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合の閣僚声明においては、アンモニアが火力発電の脱炭素化の有効な手段として初めて位置づけられたほか、現在、インドやインドネシア、マレーシア等、アジアを中心に各国でアンモニア混焼に向けた事業性調査が実施されており、多くの国や企業おいて燃料アンモニアの活用に向けた検討が活発化しています。
また、2030年以降を見据え、大規模なアンモニアの利活用を図る上では、需要側での大規模調達や供給側での大規模商用投資を促すことが、アンモニアの重要な課題となっています。そのため、こうした課題解決に向けた検討に当たり、2022年3月に総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会の下にアンモニア等脱炭素燃料小委員会を設置し、アンモニアの本格導入に向けた強靱な大規模サプライチェーンの早期構築と、社会実装の加速化に資する支援制度に関して、議論を開始しました。2022年12月までに計7回にわたる議論を重ね、2023年1月、これまでの議論内容を踏まえた中間整理を公表しました。本中間整理では、アンモニアと既存燃料との価格差に着目した支援制度や、大規模な需要を創出する供給インフラの整備に対する支援制度について、制度の骨格や方向性を示しています。今後、制度の具体化を進め、早期に国際競争力のあるサプライチェーン構築に向けた支援を行っていきます。
〈具体的な主要施策〉
①化石燃料のゼロ・エミッション化に向けた持続可能な航空燃料(SAF)・燃料アンモニア生産・利用技術開発事業
(再掲 第5章第2節 参照)
②燃料アンモニアサプライチェーンの構築【グリーンイノベーション基金:国費負担上限598億】
燃料アンモニア市場の構築に向けては、利用面・供給面一体での大規模サプライチェーンの構築が必要です。既に日本では、世界に先駆けてアンモニア混焼に向けた技術開発を開始しており、国内のみならず、早期にアジアを中心とする海外市場にも展開する観点からも、製造面では大規模化やコスト削減、CO2排出量低減に資する製造方法の開発・実証を進め、利用面では、高混焼・専焼化に向けた技術開発を進めています。