第4節 国際的なエネルギーコストの比較
1.原油輸入価格の国際比較
国際石油市場は、北米、欧州、アジアの三大市場に大きく分類され、各市場において、基準価格となる指標原油が確立されています。北米市場における代表的な指標原油は、ニューヨーク商業取引所(NewYork Mercantile Exchange)等で取引されるWTI(West Texas Intermediate、及びそれとほぼ等質の軽質低硫黄原油)であり、欧州市場での指標原油はインターコンチネンタル取引所(ICE Futures Europe)等で取引されるブレント原油となっています。また、アジア市場においては、ドバイ原油が指標原油となっています。世界では数百種類の原油が生産されていますが、各国が産油国から原油を購入する際の価格は、例えばサウジアラビア等においては、指標原油価格に一定の値を加減する方式(市場連動方式)で決まるのが通例となっており、加減値については、指標原油との性状格差で決定されます。各国における輸入原油価格は、輸入する原油の種類や、運賃、保険料等で異なります(第224-1-1)。
【第224-1-1】原油輸入価格の国際比較(2019年)
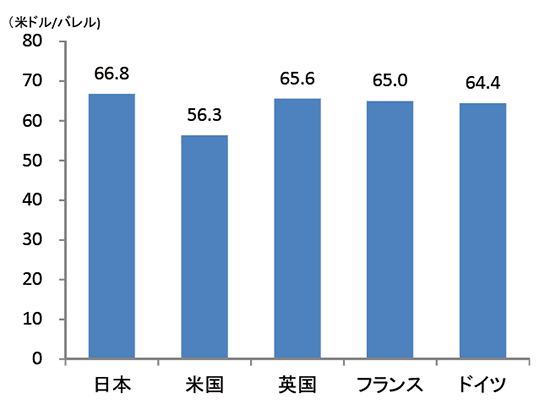
【第224-1-1】原油輸入価格の国際比較(2019年)(xlsxlsx形式251KB)
- 出典:
- IEA「Energy Prices and Taxes 2020」を基に作成
2.石油製品価格の国際比較
日本、米国、英国、フランス、ドイツでのガソリンと自動車用軽油の製品小売価格(税込み、ドル建て価格、2021年2月時点)を比較すると、ガソリン価格の高い順にフランス、ドイツ、英国、日本、米国となっており、軽油価格は高い順に英国、フランス、ドイツ、日本、米国となっています。ガソリンの小売価格(税込み)は、最高値のフランス(1.74ドル/l)と最安値の米国(0.66ドル/l)で1.08ドル/lの差がありますが、本体価格(税抜き)に大きな違いはなく、各国の税制が小売価格差の原因です。また、自動車用軽油についても、小売価格(税込み)では最高値の英国(1.73ドル/l)と最安値の米国(0.75ドル/l)に0.98ドル/lの差がありますが、本体価格(税抜き)ではガソリンと同様に大差がなく、各国の税制が小売価格差を生じさせています。灯油については、小売価格、本体価格(税抜き)ともに各国で大差はありません(第224-2-1)。
【第224-2-1】石油製品価格の国際比較(固有単位)(2021年2月時点)
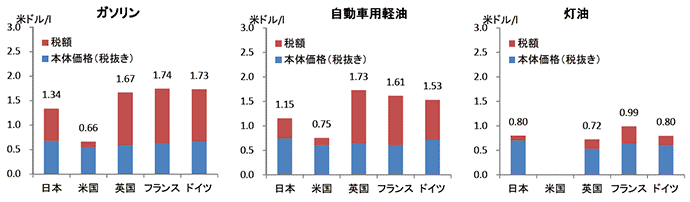
(注)米国の灯油価格はデータなし。
【第224-2-1】石油製品価格の国際比較(固有単位)(2021年2月時点)(xlsxlsx形式175KB)
- 出典:
- IEA「Oil Market Report(2021年3月号)」を基に作成
3.石炭価格の国際比較
石炭の価格は市場における需給状況を反映するものですが、石炭の性質の違いより価格に差が生じます。通常、一般炭であれば発熱量が高いほど、原料炭であれば粘結性が高いほど価格が高くなります。また、賦存量の少ない原料炭の方が一般炭より高値で取引されます。
石炭の輸入価格(CIF価格)は、石炭の輸出国におけるFOB価格と輸出国から輸入国までの輸送費(保険を含む)で構成され、FOB価格が同じであれば、輸送距離の短い方がCIF価格は安価なものとなります。
日本、韓国、中国といったアジアの石炭輸入国は、豪州やインドネシアからの輸入が主であり、これらの国々で産出される石炭の国際価格を反映し、輸入価格は同様の推移を示していますが、日本が輸入する一般炭は発熱量が高い等、主に石炭の品質の違いが輸入価格の違いに反映されていると考えられます(第224-3-1)。
【第224-3-1】石炭輸入価格の国際比較
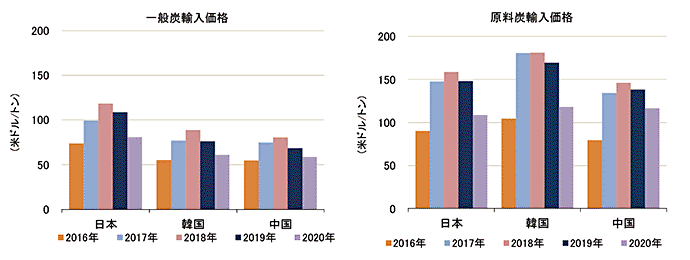
(注)各国の平均石炭輸入価格(CIF価格)。
【第224-3-1】石炭輸入価格の国際比較(xlsxlsx形式28KB)
- 出典:
- 貿易統計及び「TEX Report」掲載データを基に作成
4.LNG価格の国際比較
天然ガスの主要市場は石油と同じく北米、欧州、アジアですが、天然ガス・LNGの価格決定方式は地域ごとに異なっており、石油のように指標となるガス価格がこれら市場全てについて存在しているわけではありません。アジアにおけるLNG輸入価格は、一般的にJCC(Japan Crude Cocktail)と呼称される日本向け原油の平均CIF価格にリンクしています。大陸欧州でのパイプラインガスやLNG輸入価格は主として石油製品やブレント原油価格にリンクしていましたが、近年では各国の天然ガス需給によって決定されることも多くなっています。ガス市場の自由化が進んでいる米国や英国では、Henry HubやNBP(NationalBalancing Point)といった国内の天然ガス取引地点での需給によって価格が決定されています。そのため、各国におけるLNG輸入価格は、原油や石油製品価格の動向、それぞれの市場でのガスの需給ひっ迫状況等によって異なったものとなります(第224-4-1)。国際原油価格が2014年後半から大きく下落したことを受け、原油価格に連動する価格フォーミュラを採用しているアジア諸国のLNG輸入価格も下がり、LNG価格の地域間価格差(アジアプレミアム)は縮小しました。2019年以降は、北米に加えて欧州でも、天然ガス市場価格が急速に下落したことで、原油価格リンクのLNG価格との乖離が鮮明になっていましたが、2020年3月以降の原油価格急落の影響により、再び原油価格リンクのLNG価格との乖離は縮小しました。
【第224-4-1】LNG輸入平均価格の国際比較(2019年平均)
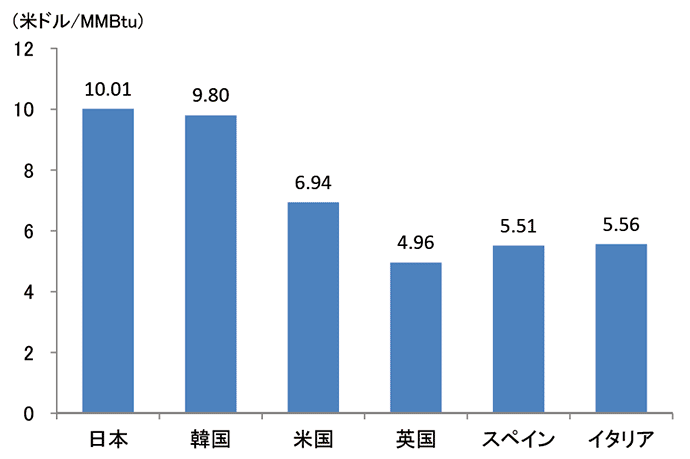
【第224-4-1】LNG輸入平均価格の国際比較(2019年平均)(xlsxlsx形式413KB)
- 出典:
- 日本貿易統計、日本税関、Korea Customs Service、EIA Natural gas imports bycountry、Eurostat、IMFを基に作成
5.ガス料金の国際比較
我が国のガス事業については、事業の効率化によるガス料金の低減を目的の一つとした規制改革が推進されてきました。1995年、1999年、2004年、2007年にそれぞれ段階的な小売自由化範囲を拡大し、2017年に全面自由化しました。また、ネットワーク部門の公平性や透明性向上等の制度整備も同時に図られてきました。2000年代初頭までは、LNG価格が安定していたこともあり、これらガス事業の制度改革と事業者の努力とがあいまって、これまで都市ガス料金は下降する傾向にありました。2000年半ば以降にLNG価格が上昇し、都市ガス価格も値上げされましたが、2014年後半以降の国際原油価格下落を受け、2017年まで下降傾向にありました。しかし、2018年には家庭用・産業用ガス料金共に上昇し、2019年においても同水準にあります。今後は、全面自由化におけるガス小売事業者間の競争により、ガス料金のさらなる低減・安定化が期待されます。また、米国においては、非在来型天然ガスの生産拡大等によって天然ガス価格が低下しています。
ガス料金の原価は様々な要素で構成されており、またその比較には多様な方法があるため単純な対比は困難ですが、日本のガス料金は他国と比べて高位にあります(第224-5-1)。
【第224-5-1】ガス料金の国際比較(2019年)
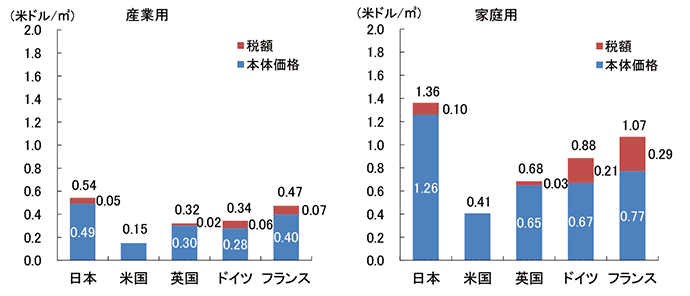
(注) 米国は本体価格と税額の内訳不明。
【第224-5-1】ガス料金の国際比較(2019年)(xlsxlsx形式498KB)
- 出典:
- IEA「Energy prices and taxes for OECD countries 2020」を基に作成
6.電気料金の国際比較
様々な方法があるため単純な比較は困難ですが、OECD/IEAの資料を基に各国の産業用と家庭用の電気料金を比較した結果は、次の図のとおりです(第224-6-1)。日本の電気料金は、家庭用、産業用ともに高い水準となっていましたが、各国での課税・再生可能エネルギー導入促進政策の負担増で格差は縮小してきています。
内外価格差は燃料・原料の調達方法や、消費量の多寡、国内の輸送インフラの普及状況、人口密度、あるいは為替レート等といった様々な要因によって生じるため、内外価格差のみを取り上げて論じるのは現実的ではありません。電気事業の効率的な運営と、電気料金の低下に向けた努力を怠ってはなりませんが、その際には我が国固有の事情、すなわち、燃料・原料の大部分を輸入に依存しておりその安定供給が不可欠なこと等、供給面での課題に配慮しておく必要があります。
【第224-6-1】電気料金の国際比較(2019年)
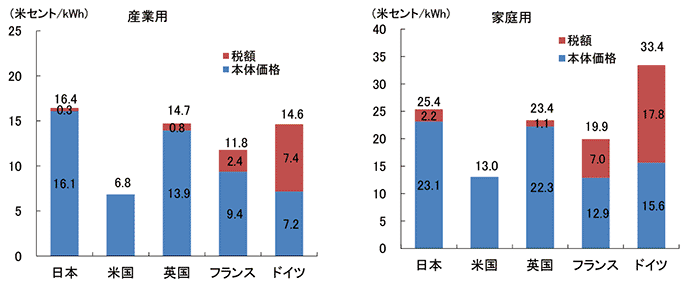
(注)米国は本体価格と税額の内訳不明。
(注)産業用の税額には、付加価値税は含んでいない。
【第224-6-1】電気料金の国際比較(2019年)(xlsxlsx形式532KB)
- 出典:
- IEA「Energy Prices and Taxes for OECD Countries 2020」を基に作成