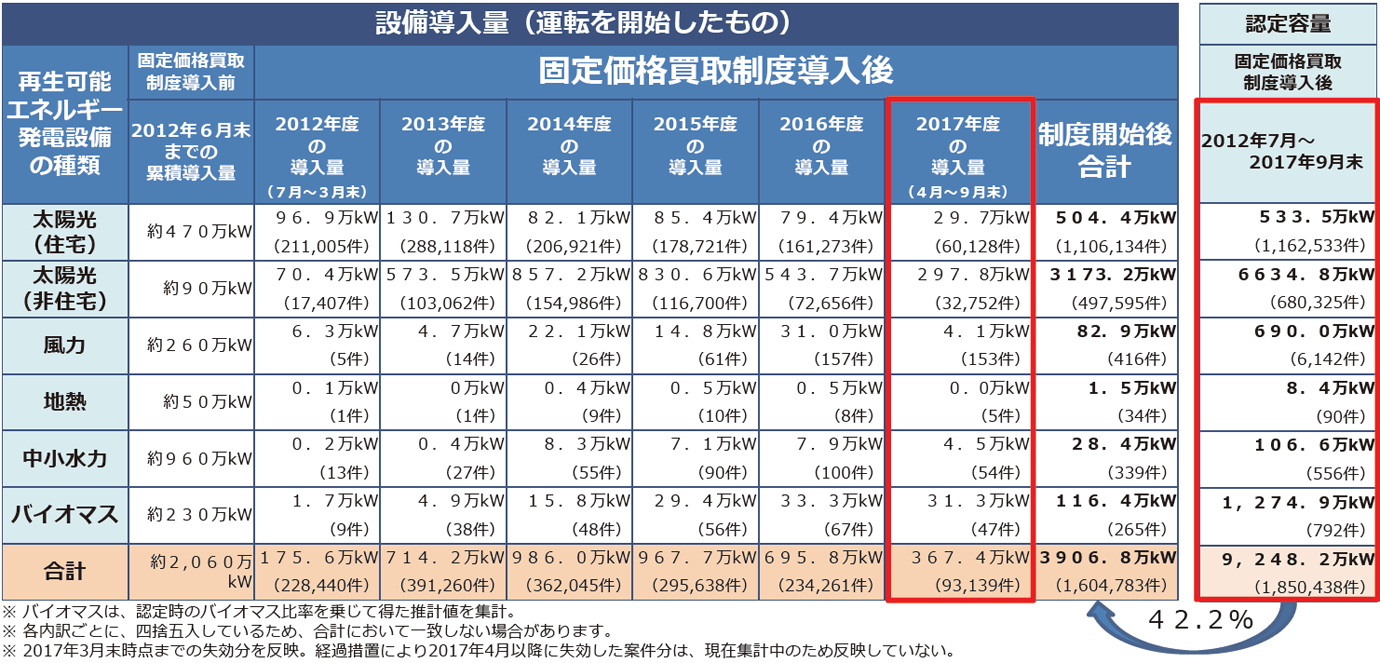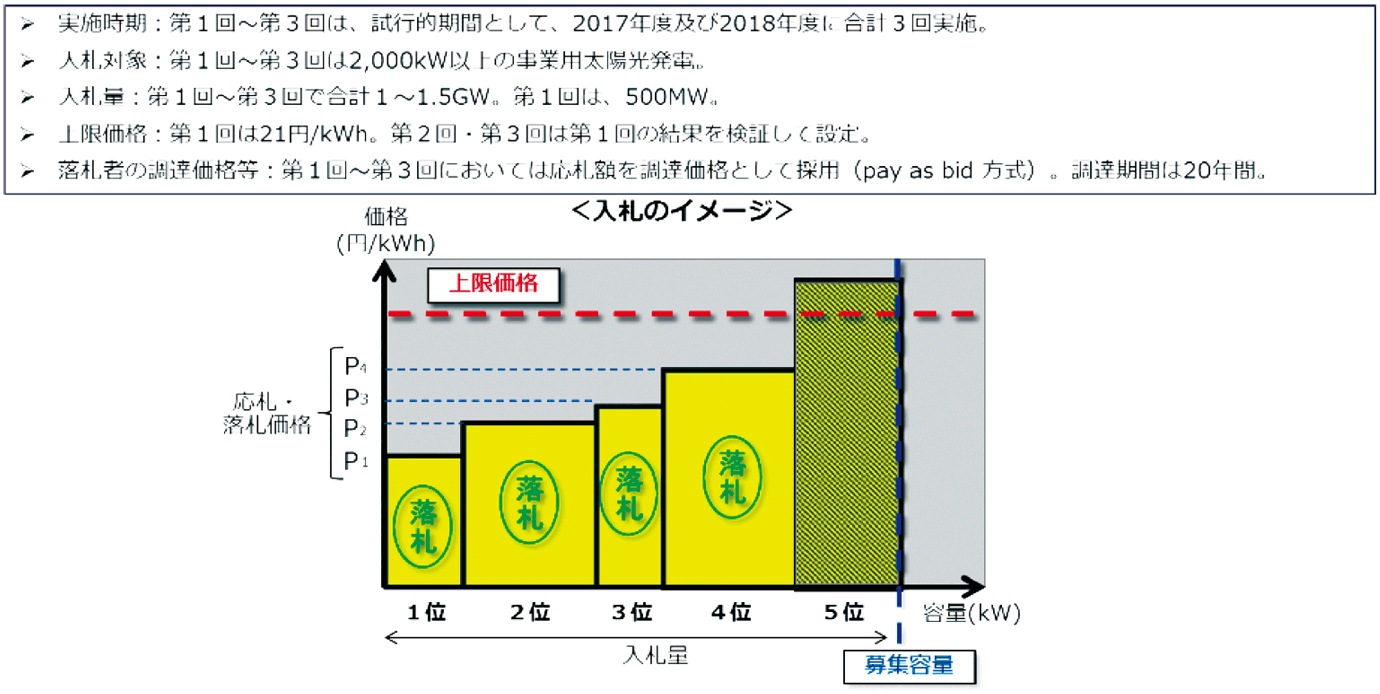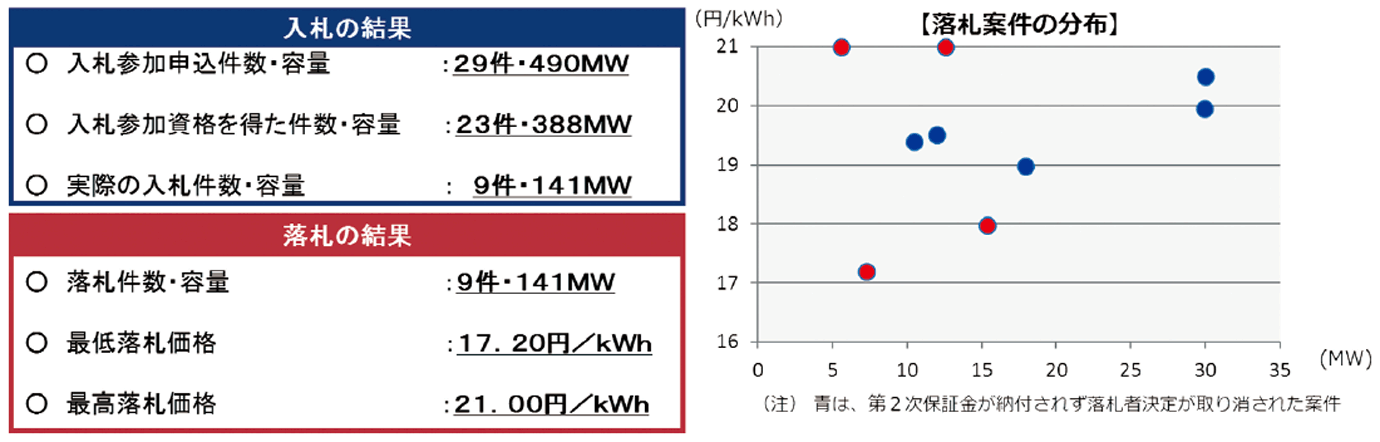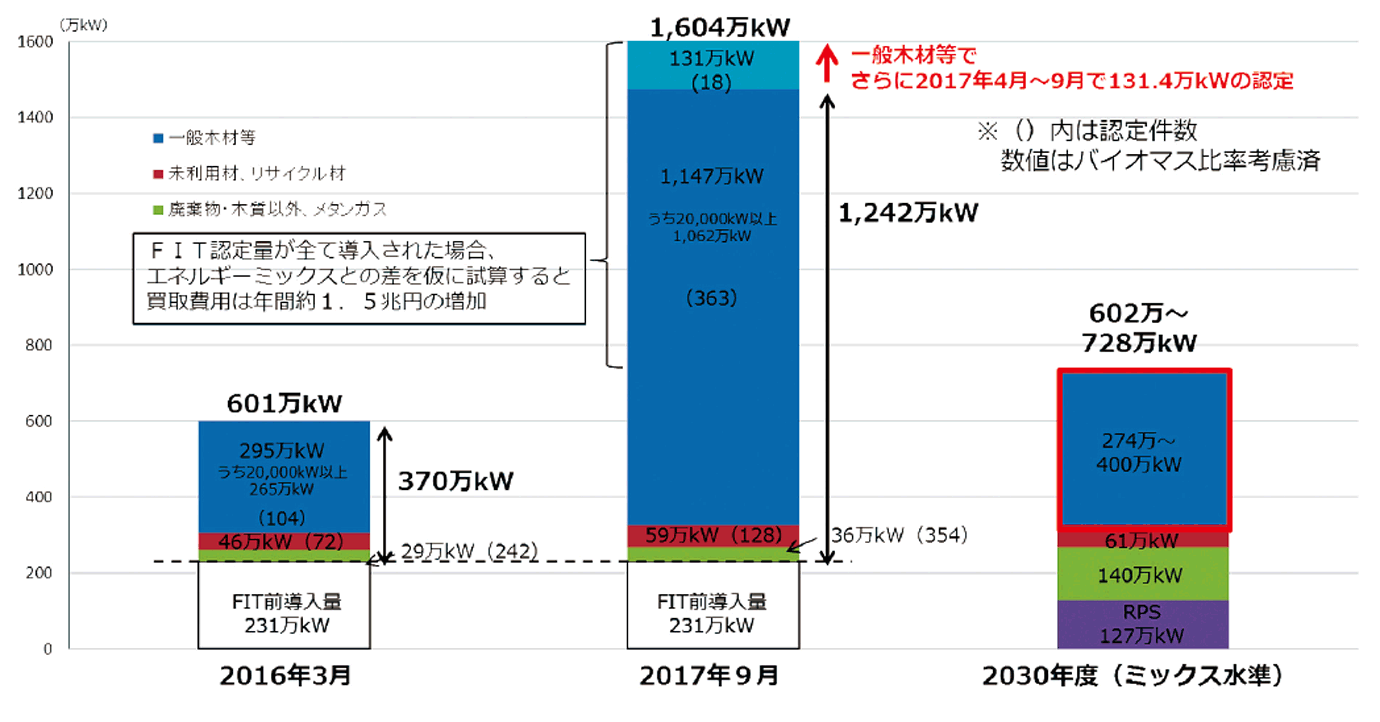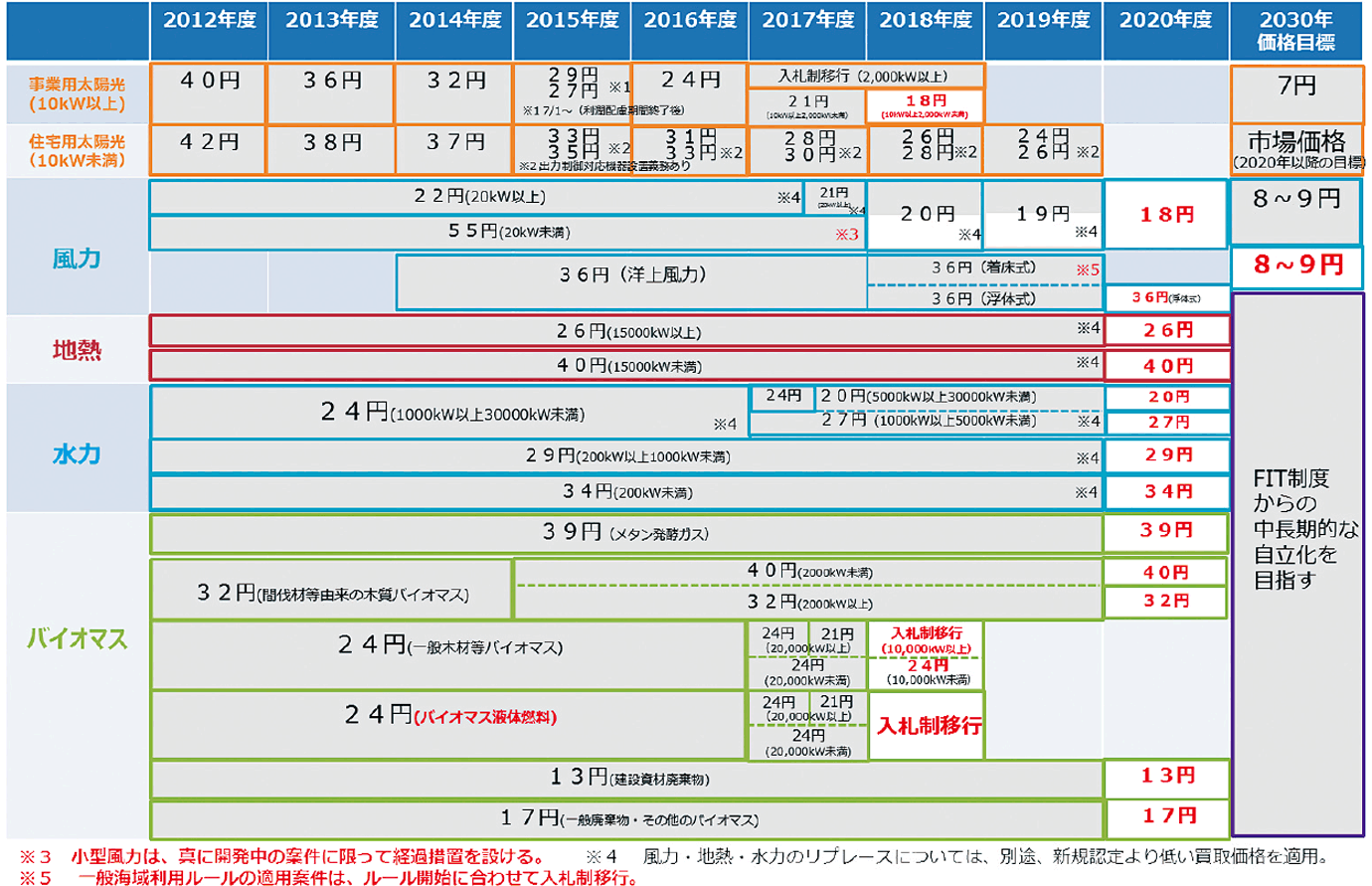第1節 固定価格買取制度(FIT)の適切な運用
2012年7月に開始したFITは、制度開始以来約5年で対象となる再エネの導入量が概ね2.9倍となるといった成果を挙げるなど、再エネの導入の原動力となっています。他方で、再エネの導入拡大に伴い、国民負担の増大や事業用太陽光に偏った導入の拡大など、様々な課題が生じています。こうした課題に対応するため、2017年4月に改正FIT法を施行しました。改正FIT法では、FIT法に基づく認定(以下「FIT認定」という。)を得たまま稼働しない案件を排除するため、認定制度を「設備認定」から「事業計画認定」に変更し、電力会社との接続契約を前置することとしました。2017年3月末までに電力会社と接続契約を締結していない事業者については、FIT認定が原則失効することとし、2018年1月時点で、少なくとも16GWの未稼働案件の失効が確認されています。また、改正FIT法では、中長期的な価格目標の設定や入札制の導入により、コスト効率的な再エネの導入を促す仕組みを措置し、リードタイムが長く導入が進んでいない電源については、複数年度の買取価格を予め設定することとしました。さらに、電力システム改革の成果も活かし、広域融通などを通じた再エネの更なる導入拡大を進めるべく、買取義務者を送配電事業者とすることとしました。
改正FIT法の施行後は、2MW以上の大規模太陽光発電の入札を試行的に実施するなど、入札制の活用に取り組むとともに、法改正だけでは十分に対応できなかった課題についても運用レベルの制度見直しを行い、FITの適切な運用に取り組みました。
(1)大規模太陽光発電の入札の試行的実施
再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、FIT法第4条第1項においては、入札により国民負担の軽減につながると認められる電源については、入札対象として指定することができるとされています。これを踏まえて、2017年度及び2018年度を入札の試行的期間として位置付けた上で、2017年度については、2MW以上の大規模太陽光発電に対して入札制を導入することとしました。具体的には、2017年度に第1回、2018年度に第2回・第3回(2年間で合計3回)の入札を実施することとしました。入札量については、第1回~第3回で合計1~1.5GWを募集することとし、第1回における入札量は500MWとしました。
入札の結果、上限価格21円に対し、最低落札価格は17.20円となり、コスト効率的な再エネの導入に一定の効果があったと考えられます。しかし、第1回の落札価格は、国際水準と比べると依然として高い水準であり、第2回以降に向けた入札制の改善点について、調達価格等算定委員会で議論がなされました。
(2)入札制の更なる活用
① 2017年度の入札結果を踏まえた見直し
より多くの事業者の入札参加を促し、事業者間の競争による価格の低減を図っていくため、入札制導入2年目となる2018年度の入札については、引き続き試行的期間として、2017年度の入札結果や調達価格等算定委員会における事業者団体へのヒアリング結果も踏まえ、運用について見直しがなされました。具体的には、太陽光第1回入札では、上限価格で落札された案件があったことなどを踏まえ、上限価格は非公表として実施することとしました。
また、事業の確実な実施の担保として求める第2次保証金の没収条件が入札参加に対するリスク要因となっていたことから、認定取得期限までに認定取得できなかった場合に、第2次保証金を即時没収せず、当該認定取得期限の経過後、最初に実施する入札の保証金として充当することを可能にするほか、大規模災害等の発生により事業を中止せざるを得ない場合等の不可抗力事由を第2次保証金没収の例外として位置付けることとしました。
こうした見直しの下、2018年度は2MW以上の大規模太陽光の第2回・第3回及び大規模バイオマスの第1回の入札を実施します。太陽光については、第2回の入札量は250MWとした上で、第3回の入札量は原則250MWとしつつ、第2回の応札容量が250MWを下回った場合には、第2回の応札容量と同じ量とすることとしました。(大規模バイオマスについては後掲)
② 大規模バイオマス等・洋上風力の入札制への移行
(i)大規模バイオマス
2016年3月時点で370万kWであったバイオマス発電設備のFIT認定量は、2017年9月時点では1,300万kWを超えました。エネルギーミックスにおいて、2030年度のバイオマス発電設備の容量を602万~728万kWと見通しているところ、既にこの水準に迫る勢いとなっています。とりわけ、一般木材等バイオマス発電のFIT認定量が急増しており、既にエネルギーミックスで想定した2030年度の導入水準の3倍程度となっています。
FIT認定量の急増した一般木材等バイオマスについては、既に2019年度までの複数年度の調達価格等が設定されていたところですが、こうしたFIT認定量の急増に鑑みると、調達価格等を定める際に勘案した再エネ電気の供給の量の状況からの著しい乖離を生むおそれがある急激な状況変化が生じており、国民負担への影響が大きい(マクロインパクトが大きい)ことから、既に決めた2018年度と2019年度の調達価格等を改めて設定することとしました。その上で、一般木材等バイオマスについては、FIT認定量や導入量、コスト低下のポテンシャルといった要素から競争状況を勘案し、2018年度より、10,000kW(バイオマス比率考慮前)以上の一般木材等バイオマス(バイオマス液体燃料以外)全規模のバイオマス液体燃料についてを入札制に移行することとしました。その上で、2018年度の入札量については、FIT認定量や導入量を踏まえ、一般木材等バイオマス(バイオマス液体燃料以外)は180MW、バイオマス液体燃料は20MWとしました。
このほか、一般木材等バイオマスについては、FIT認定量の急増を踏まえ、既認定案件も含めて燃料の安定調達に関する認定基準を充足しているか確認する方法を見直すこととするとともに、国民負担の抑制の観点から未稼働案件を防止するため、既認定案件には設備発注期限を、新規認定案件には運転開始期限を設けることとします。
(ii)洋上風力発電
洋上風力発電については、東北地方を中心に直近で具体的な事業計画が顕在化しており、また、欧州では、海域利用ルールの整備とともに入札制を導入するなどといった取組により、コスト効率的な導入が短期間で進んでいます。こうした中で、ポテンシャルのより大きな一般海域の海域利用ルールが整備されれば、顕在化している具体的な事業計画が実現しやすくなり、また日本でも欧州の経験を活用したコスト低減が見込まれることから、一般海域の海域利用ルールの適用される案件については、当該ルールの開始にあわせて、入札制へ移行することとしました。
なお、2018年度以降のFITにおける調達価格等については、2018年2月に調達価格等算定委員会で取りまとめられた「平成30年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、パブリックコメントも踏まえつつ、2018年3月に経済産業大臣が決定しました。中長期的な価格目標の実現に向け、事業用太陽光や陸上風力の調達価格を引き下げることとしています。
(3)FIT発電事業の適正化
① 太陽光パネルの事後的な過積載への対応
太陽光発電設備の認定においては、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナー(以下「パワコン」という)の定格出力のどちらか低い方を「発電出力」として登録することとなっており、認定取得後にパワコンの定格出力よりも出力の大きい太陽光パネルを増設すること(いわゆる事後的な過積載)が可能となっています。認定取得後にパネルを増設して過積載をする場合、事前変更届出のみで調達価格の変更なく事業計画が変更可能だったため、過去の高い調達価格を維持したまま、安価にパネルの出力を増加させることができ、国民負担の増大につながっていました。そのため、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図る観点から、「太陽電池の合計出力」を変更する場合の手続を、調達価格が変更されない「事前変更届出」から、「変更認定申請」に変更する措置を講じて太陽光パネルの合計出力を3%又は3kW以上増加させる場合に調達価格を変更する制度改正を行いました。
② 運転開始期限の設定
諸外国の固定価格買取制度では、運転開始時に調達価格が決定する制度になっているケースが多い一方が、日本においては、ファイナンスの実態や事業者の予見可能性を重視し、認定時に調達価格を決定する仕組みとなっています。このため、早期に認定を取得して調達価格を確定させた上で、コストの低下を待って意図的に運転開始を遅らせ、未稼働の案件を発生させるなど、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両面からの課題が発生していました。こうした課題に対応するため、2017年4月より、太陽光発電については先行的に、認定日から3年という運転開始期限を導入し、未稼働案件の防止を図ることとなっています。
さらに、今後コスト低下局面を迎える全ての電源について、運転開始の遅延による利益を発生させないよう、2018年度以降に認定する案件に運転開始期限を設定することとしました。運転開始期限は、各電源の開発の特性に応じて、風力は4年(※1)、中小水力は7年(※2)、地熱は4年(※1)、バイオマスは4年としています。なお、運転開始期限を超過した場合の取扱いについては、太陽光と同様に、ファイナンスの実態や事業者の予見可能性に配慮し、超過期間分だけ調達期間を月単位で短縮することとしました。また、運転開始期限については、環境影響評価法に基づく手続に要する期間等を考慮し、適宜見直しを行うこととしています。
③ 出力増加時の価格変更
太陽光については、認定から時間が経過した認定案件(未稼働案件を含む)が、設備コストが低下した時点で発電出力を増加させることによる過剰な国民負担を抑制するため、認定後に発電出力を増加する場合には、運転開始前後を問わず、適用される調達価格がその変更時点の価格に変更になる、というルールとしていました。(ただし、10kW未満の設備であって、変更後の出力も10kW未満である場合は、価格変更はありません)。
他方で、風力、中小水力、地熱、バイオマスについては、運転開始前は発電出力の増加が10kW未満かつ20%未満であれば、運転開始後は制限なく発電出力を増加させても調達価格は維持されるルールとなっていました。今後は、太陽光以外の電源についても、価格低下局面を迎えることが予想されることから、過剰な国民負担を抑制するため、2018年4月から太陽光と同様に既認定案件も含め、発電出力を増加する場合には、運転開始前後を問わず、調達価格をその変更時点の価格に変更することとしました。
このほか、土地の確保に関する要件も全ての電源について厳格な確認を行うこととするなど、FIT発電事業の適正化に向けて不断の見直し・運用改善を行っていきます。