第4節 1970・80年頃~
1. さらなる都市ガスの利用拡大と省エネ・低炭素化技術の展開へ
(1)天然ガス利用の始まり
日本の都市ガスの原料は、石炭に始まり、その後、石油が主流となりました。天然ガスはメタンを主成分とし、石炭や石油に比べ、CO2や、大気汚染、酸性雨の原因となる硫黄酸化物と窒素酸化物の燃焼時における発生量が少なく、高カロリーなエネルギーです。また、天然ガスは世界中に分布しており、政情が不安定な中東に集中している石油に比べ、エネルギーセキュリティーが高く、石油系エネルギーに代わる都市ガス原料として早くから注目されていました。国内では、1959年に、帝国石油が新潟の頸城(くびき)地方一帯で大規模な天然ガス田を発見し、東京までのパイプラインを建設、これにより天然ガスは1962年10月から都市ガスの原料として導入されました。
1969年、日本は天然ガスをLNGとして導入を開始しました。1969年11月、LNGタンカーが日本で初めて東京ガス根岸工場に着岸しました。このLNGは、東京ガスのガス原料、東京電力の発電用燃料として導入されました。その後、全国各地にLNG受入れ基地が建設され、日本におけるLNG導入が進展しました。日本のLNGの輸入量は、1975年度は501万tでしたが、1980年度には1697万t、1985年度には2783万t、1990年度には3608万t、1995年度には4369万tと年々増加していきました。
(2)都市ガスの利用拡大
都市化の進展、高齢化、ライフスタイルや価値観の変化などから、特に家庭用ガス機器において、より一層コンパクトで、利便性、安全性、制御性のよい機器が求められるようになりました。給湯・暖房分野では、快適で便利なフローリング温水式床暖房が1988年に、また、よりコンパクトで空気清浄機能が付いたガスファンヒーターが1995年に開発されました。厨房分野では、1987年に超コンパクト湯沸器やマイコン式タイマー電子ジャー付ガス炊飯器が開発されました。
また、都市ガスによるコージェネレーションの導入も始まりました。都市ガスによるコージェネレーションは、ガスエンジンやガスタービンを稼働させ、発電機を動かして電気を作るとともに、その排熱を回収して工場などの熱利用や業務用ビルなどの給湯や冷暖房を利用するシステムであり、熱力学的にみても合理性の高いシステムです。このため、熱需要と電需要が適切に組み合わされれば、総合エネルギー効率を70~80%にまで高めることが可能です。
この都市ガスを用いたコージェネレーションは、当初は民生用から普及し、その後、産業用にも導入されるようになりました。都市ガスによるコージェネレーションは、1989年頃から急速に導入が図られ、1989年3月末に170件・約15万kwであった導入実績が、1997年3月末では、820件・約142万kwの稼働となり、大幅に増加しました。
2.核燃料サイクル政策の開始
我が国の核燃料サイクル政策については、原子力基本法制定(1955年)の翌年の1956年に原子力委員会により策定された「原子力開発利用長期基本計画」(長計)から位置づけられています。1956年の長計においては、「燃料要素の再処理については、極力国内技術によることとし、原子燃料公社をして集中的に実施せしめる。」「主として原子燃料資源の有効利用の面から見て、増殖型動力炉がわが国の国情に最も適合すると考えられるので、その国産に目標を置くものとする。」との方針の下、「将来わが国の実情に応じた燃料サイクルを確立するため、増殖炉、燃料要素再処理等の技術の向上を図る」との考え方が示されました。
また、1961年に改定された長計では「使用済燃料の再処理および劣化ウラン(回収ウラン)の再使用に関する技術の開発を並行してすすめることにより、燃料サイクルを国内で自立することができるように努力する。」「プルトニウム燃料の開発は、燃料サイクルの基礎ともなるべき事項であるので、(計画期間1961年~1980年の)後期10年の前半において熱中性子炉への実用化(いわゆるプルサーマル)を、後期10年の後半において高速中性子増殖炉への実用化を目標とし、原子燃料公社および日本原子力研究所の共同研究プロジェクトとして、強力に推進する。」とされました。
高速増殖炉の開発については、高速増殖実験炉常陽の建設を1971年に開始し、1977年、初臨界に成功しました。また、常陽の次の段階としての高速増殖原型炉もんじゅは1985年に建設が始まり、1994年に初臨界を達成しました。(ただし、翌年のナトリウム漏れ事故を発端に長期間運転を停止。その後、試験を再開するもトラブルが続き、最終的に2016年に廃炉を決定。)
核燃料サイクル技術の確立に関しては、1971年に動力炉・核燃料開発事業団(元:原子燃料公社、現在の日本原子力研究開発機構)が我が国初の再処理工場である、東海再処理工場の建設に着工。1977年より実際の使用済燃料を使用した再処理試験を行い、1980年に本格運転を開始しました。また、商業用の再処理工場については、1980年、再処理を行う事業主体として、電力業界が中心となり民間関連会社の協力を得て、日本原燃サービス株式会社を設立しました。同様に1985年には、ウラン濃縮及び低レベル放射性廃棄物埋設を行う事業主体として、日本原燃産業株式会社が設立されました。同年、青森県、六ケ所村、日本原燃サービス、日本原燃産業、電気事業連合会の5者間で「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書」の署名が行われました。1987年に日本原燃産業は六ヶ所ウラン濃縮工場の事業許可申請を行い、1988年に事業許可、濃縮工場の建設を開始しました。1989年に日本原燃サービスは六ヶ所再処理工場の事業指定申請を行い、1992年に事業指定、1993年に再処理工場の建設を開始しました。
1968年締結の日米原子力協定では米国の個別の同意なしには再処理を行えない規定となっていましたが、1988年に、協定発効後30年間(2018年まで、加えてその後も日米いずれかが終了通告を行わない限り存続)、米国の個別の事前同意なしに包括的に日本の再処理を可能とする現行日米原子力協定が成立しました。
【第114-2-1】核燃料サイクルの歴史
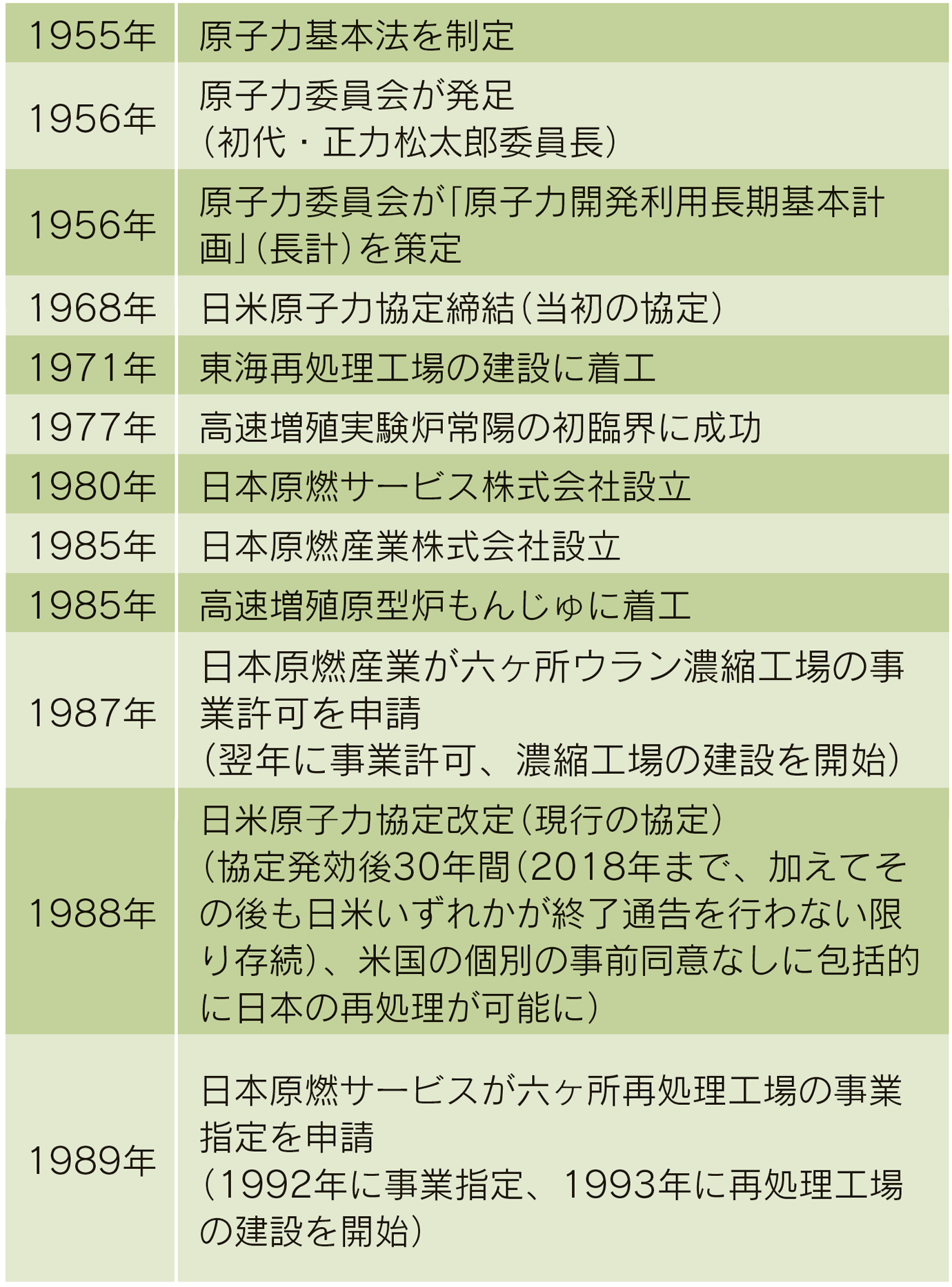
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
3.オイルショックによる価格高騰と供給ひっ迫~石油備蓄の開始と供給確保~
(1)民間備蓄の開始
ヨーロッパ諸国では、1956年のスエズ動乱、1967年の第三次中東戦争時の対ヨーロッパ石油禁輸などの経験から、石油備蓄の必要性について早くから認識されていました。例えば、1962年7月には、OECD(経済協力開発機構)がヨーロッパ加盟国に対して最低備蓄水準として60日分を確保するよう勧告し、また、1971年7月には、OECDがヨーロッパ加盟国に対して90日分の備蓄を確保するよう勧告をしました。さらに、1971年10月には、EC(欧州共同体)も、加盟各国に対して、90日分の石油備蓄の確保を勧告しています。
一方、我が国においても、1967年2月の総合エネルギー調査会の答申において、石油備蓄の必要性がうたわれました。その後、1971年12月には、総合エネルギー調査会石油部会の中間報告において、1974年度までに60日間の石油備蓄を達成すること、このために必要な財政面等の措置を講ずること等が勧告されました。これを受け、政府は、1972年より、毎年度5日分の備蓄増強を進め、1974年度中に60日分備蓄を実現する「60日備蓄増強計画」をスタートさせました。同時に、このための支援措置として、1972年5月に石油開発公団法の改正を行い、石油開発公団の臨時業務として、民間備蓄増強のための原油購入資金の低利融資を開始しました。
(2)90日備蓄増強計画と国家石油備蓄の開始
その後、我が国で民間備蓄が開始された翌年の1973年、第四次中東戦争を契機とし、世界各国に大きな衝撃を与えた第一次石油危機が発生しました。第一次石油危機の経験は、石油備蓄の重要性に関する認識を一挙に高めることとなりました。第一次石油危機の発生から1年を経た1974年11月に設立されたIEA(国際エネルギー機関)は、加盟国に対して、純輸入量の60日分の石油備蓄を保有すること、さらに1980年までに90日分の備蓄を達成することを義務付けました。
我が国でも、1974年7月に発表された総合エネルギー調査会総合部会の中間とりまとめにおいて、「政府は、90日分まで備蓄水準を計画的に増強するよう備蓄増強体制の確立に努めなければならない」と指摘しました。この提言やIEAによる90日分石油備蓄義務付けを受けて、政府は、1975年に石油備蓄法を制定し、1979年度末までに90日分の備蓄を達成する「90日備蓄増強計画」をスタートしました。
「90日備蓄増強計画」は、イラン革命の影響によって、当初の計画から1年遅れとなる1980年度に達成されましたが、欧米諸国の水準に対し、我が国の備蓄量が低水準であったこと等の理由から、民間備蓄90日だけでは不十分であり、さらなる備蓄増強の必要性が認識されていました。一方、90日備蓄の実施は、原油価格上昇による金利負担の増大等によって、石油企業への大きな負担となっており、さらなる備蓄増強については、政府が主導で実施すべきとの声が、相次いで経済界からあげられました。こうした中、1977年の総合エネルギー調査会石油部会の中間とりまとめを受けて、石油開発公団から石油公団へと名称変更するとともに、石油公団の実施業務に石油の備蓄を行うことを追加し、1978年から国家石油備蓄が開始されることとなりました。18
【第114-3-1】民間備蓄と国家備蓄の推移
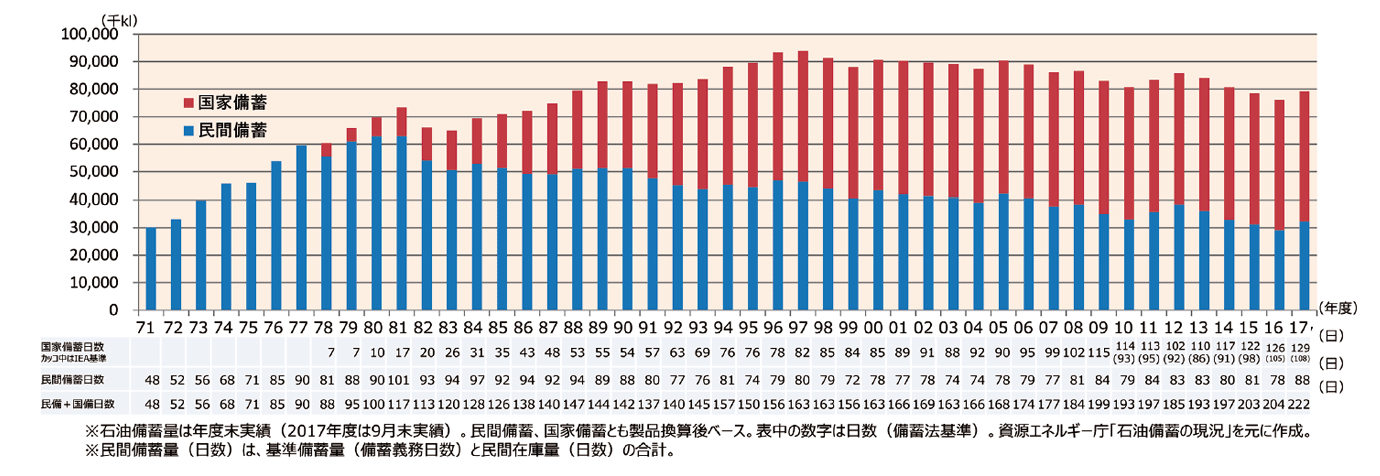
- 出典:
- 資源エネルギー庁「石油備蓄の現状」を元に作成
(3)オイルショックの発生と石油二法の制定
また、第一次石油危機の発生によって、石油不足によるモノ不足からトイレットペーパー等の買い占めが発生しました。こうした危機的な状況に対処するとともに、危機の拡大を防止することを目的として、いわゆる石油二法と呼ばれる、「石油需給適正化法」及び「国民生活安定緊急措置法」を制定し、石油供給目標の策定や石油使用の制限、一部物資の標準価格の設定などの対策を実施し、石油需給の適正化を図りました。
【第114-3-2】共同石油の省エネルギーキャンペーン

- 出典:
- ビジュアル社史1995-2005 新日鉱グループの百年
4.省エネ法の制定~石油危機によるエネルギー効率化の重要性の高まり~
いわゆる第四次中東戦争を契機に1973年に発生した第一次石油危機(原油価格の高騰と供給減少)は、当時石油依存度が7割を超えていた我が国にとって、国民生活及び経済に対し大きな衝撃を与えるものでした。そこで、第一次石油危機後、脆弱なエネルギー供給構造を改善するため、資源の効率的な利用に向けた省エネルギーの重要性が認識され、エネルギー消費効率の向上のための、法規制の整備と技術開発等の支援の両輪で、省エネルギー政策が推進されることとなりました。
(1)<法規制>省エネ法の制定(1979年)
燃料資源の有効な利用を進めるため、第二次石油危機が生じた1979年に「エネルギーの使用の合理化に関する法制」(省エネ法)を制定・施行しました。工場、建築物及び機械器具に関する省エネルギーを総合的に進めるために、各分野において事業者が取り組むべき内容等を定めています。例えば、工場分野においては、事業者が省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準を示すとともに、一定規模以上の工場にはエネルギーの使用状況を記録させ、取組が不十分な場合は勧告等を措置しました。
(2)<技術開発支援>「ムーンライト計画」(1978年~1992年)
石油に依存しないエネルギー構造の確立を目的に、省エネルギーによる資源の有効活用を目指すため、1978年に通商産業省工業技術院が「ムーンライト計画」を策定し、省エネルギー技術開発プロジェクトをスタートさせました。
「ムーンライト計画」では、エネルギー転換効率の向上、未利用エネルギーの回収、エネルギー供給システムの安定化によるエネルギー利用効率の向上とエネルギーの有効利用を図る技術の研究開発が行われ、具体的には、1978年から1992年まで、高効率ガスタービンの運転研究や、廃熱利用技術システム、高性能圧縮式ヒートポンプなどの研究開発が進められました(予算総額:1,400億円)。成果としては、例えば1976年度から6年間で約40億円を投じた廃熱利用技術システムは、吸収式ヒートポンプシステムの開発等を達成し、国内外で実用に供されました。
なお、「ムーンライト計画」は1992年に終了し、先行していた「サンシャイン計画」(2000年を目途として、数十年後における我が国のエネルギー需要の相当部分をまかなう新しいクリーンエネルギーを供給する技術開発を目指すもの)と一体化した「ニューサンシャイン計画」に統合されました。
これらの対策の成果もあり、我が国の省エネ取組は大幅に進展し、我が国のエネルギー消費効率(=エネルギー消費量/対実質GDP)は世界最高水準となりました。
【第114-4-1】エネルギー消費効率の各国比較(2015年)
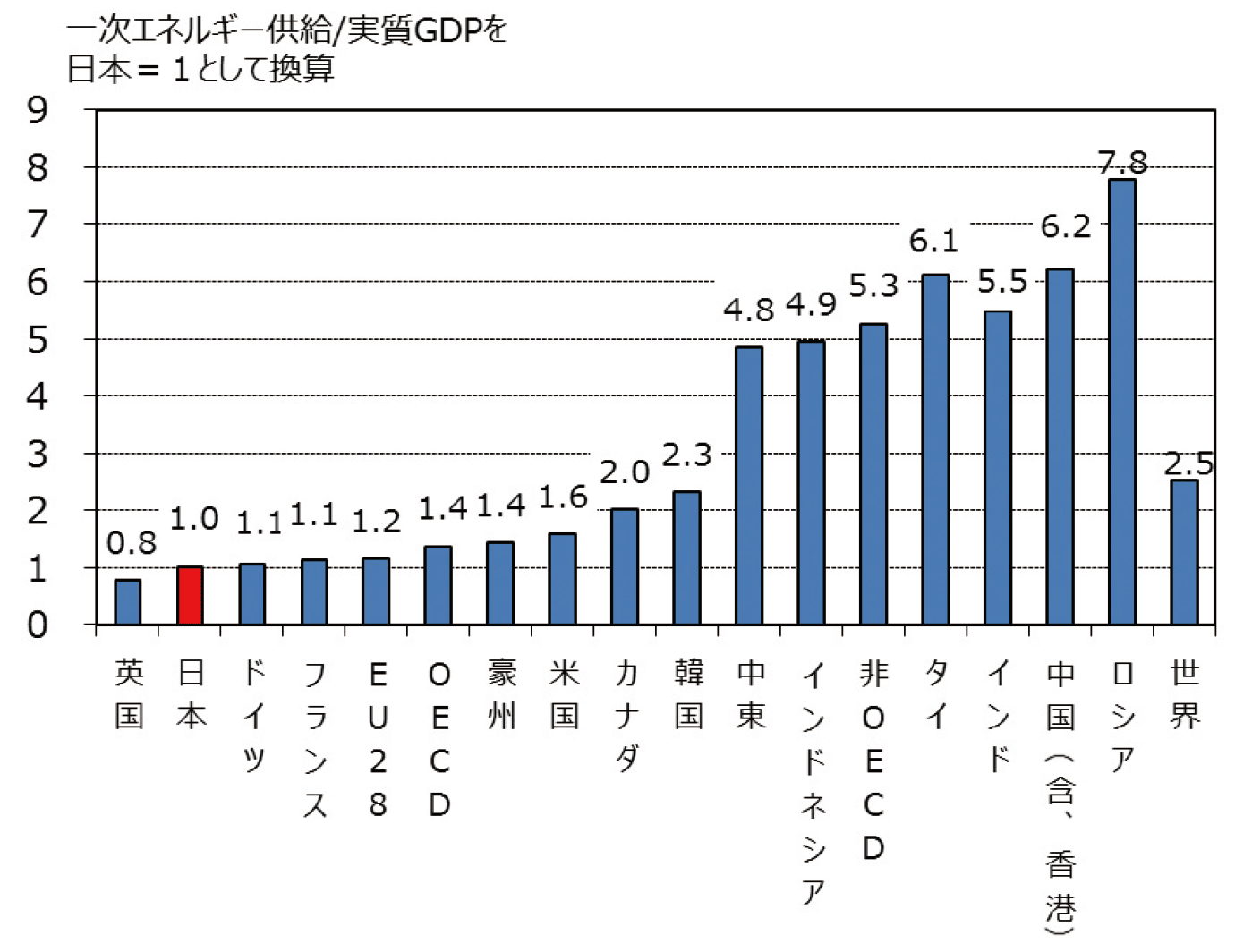
- (注)
- 一次エネルギー消費量(石油換算トン)÷実質GDP(米ドル、2010年基準)を日本=1として換算
- 出典:
- IEA「World Energy Balances 2017 Edition」、World Bank「World Development Indicators 2017」を基に作成
5.再生可能エネルギーの開発・導入の開始~石油危機による脱化石燃料の重要性の高まり~
1970年代の二度の石油危機を契機として、エネルギーの安定的な供給確保の観点から、石油に代わるエネルギー源(石油代替エネルギー)の確保の重要性が高まりました。太陽光・風力・地熱をはじめとする再生可能エネルギーも石油代替エネルギーとして認識され、技術開発や法制度整備が国の施策として本格的に開始されます。
(1)<技術開発支援>「サンシャイン計画」(1974~1992年)の開始
技術開発については、1974年に通商産業省工業技術院(現在の独立行政法人産業技術総合研究所)において「サンシャイン計画」が開始されました。1980年以降は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)主導の下進められた本計画は、名前の通り、太陽光など枯渇しないクリーンエネルギーの活用技術を開発するという目標を掲げ、特に太陽光・地熱・石炭・水素の4つの石油代替エネルギー技術について重点的に研究開発を進めるものでした。また、風力発電やバイオマスエネルギーの研究なども、「総合研究」として進められました。(予算総額:4,400億円)
【第114-5-1】サンシャイン計画のプロジェクト

六甲新エネルギー実験センター(兵庫県神戸市)

100kW級風力発電実験機(東京都三宅島)
- 出典:
- 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 「focus NEDO 特別号」
【第114-5-2】1990年度の石油代替エネルギーの供給目標(1980年度閣議決定)
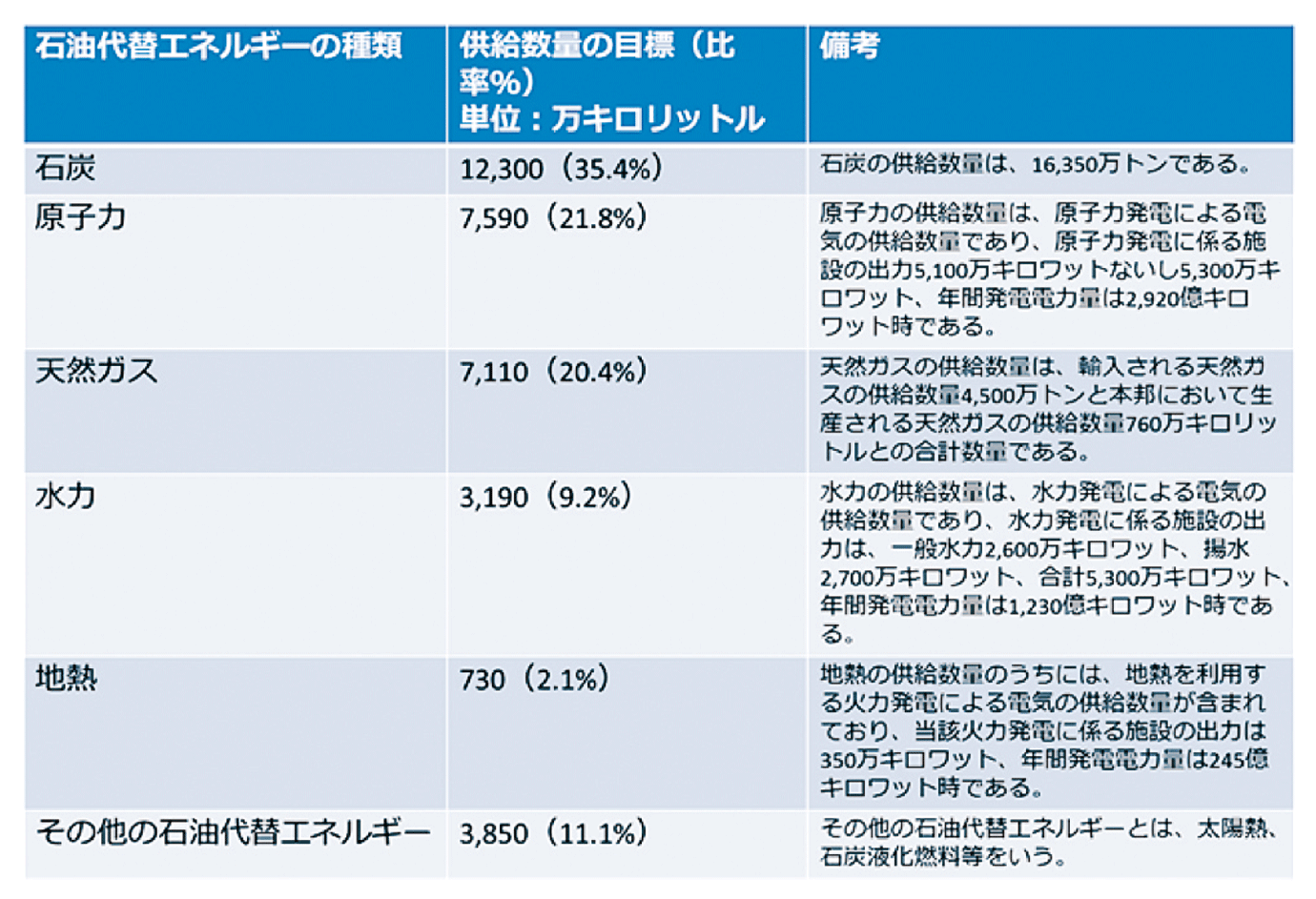
- 出典:
- 通商産業省年報 昭和55年度版
(2)<法制度>「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(代エネ法)」の制定
国際石油情勢の不安定化をうけて、1980年のベニス・サミットでは経済成長と石油消費を切り離す必要性が明示され、90年のサミット参加国全体での石油代替エネルギー供給量目標がとりまとめられました。こうした国際情勢も踏まえ、従来、個別エネルギーごとにまたは多数の関係者によって分散的に実施されてきた国内の石油代替エネルギーの開発、導入を総合的かつ効率的に推進するため、80年に「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(代エネ法)」が制定されました。
代エネ法では、(1)石油代替エネルギー供給目標の閣議決定(2)事業者に対する石油代替エネルギーの導入指針(3)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の設置などが定められました。同年に閣議決定された供給目標によって、再生可能エネルギーの政府目標が初めて掲げられ、また新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の設置や特別会計制度の整備によって再生可能エネルギー開発の法律面・財政面での基本体制が次第に確立されていきました
- 18
- 「石油公団、『石油の開発と備蓄 1992-12』、石油公団、1992年」を参考に記載。