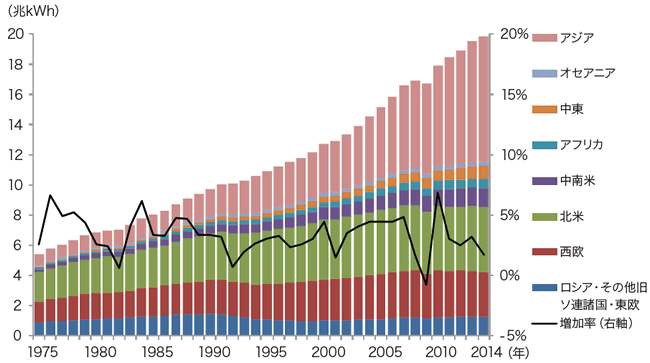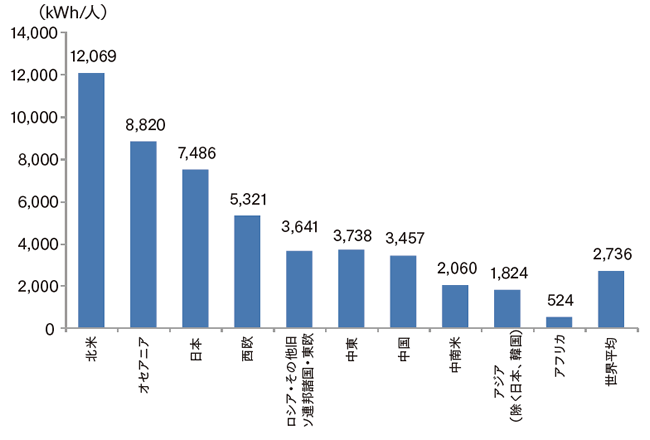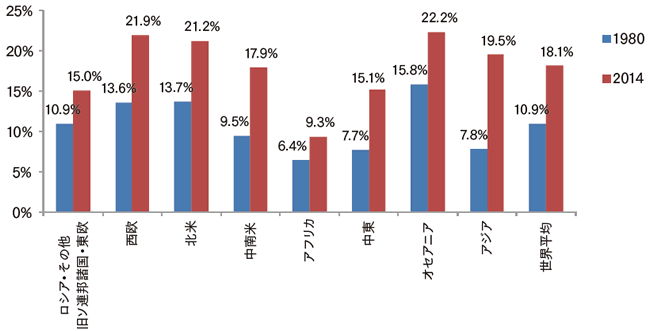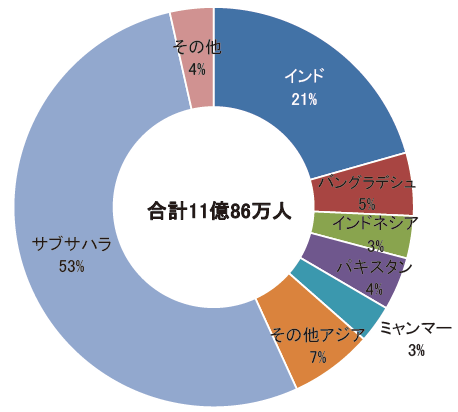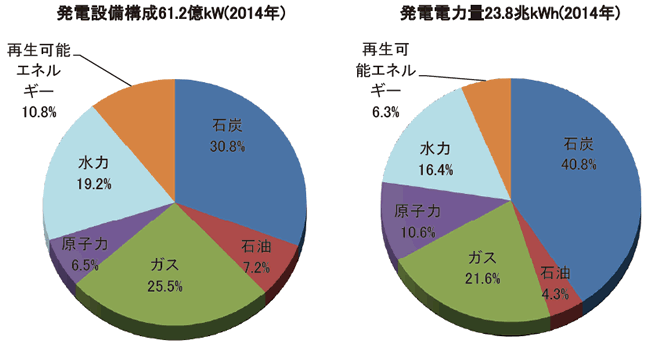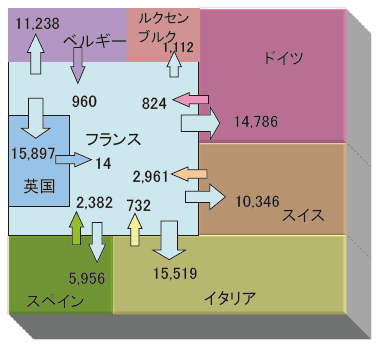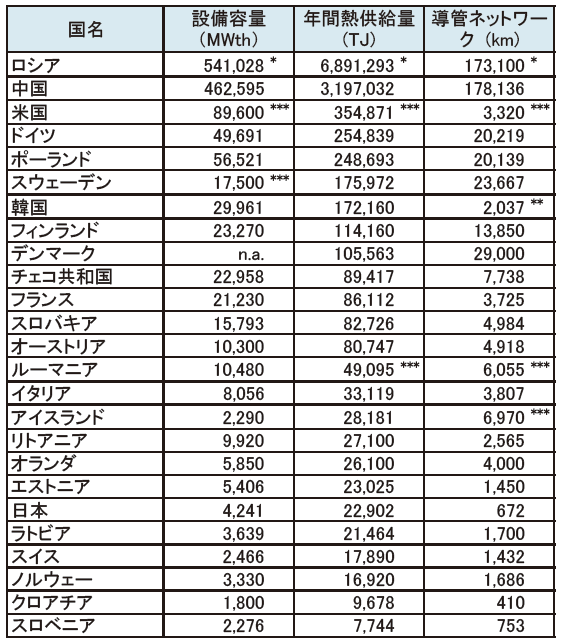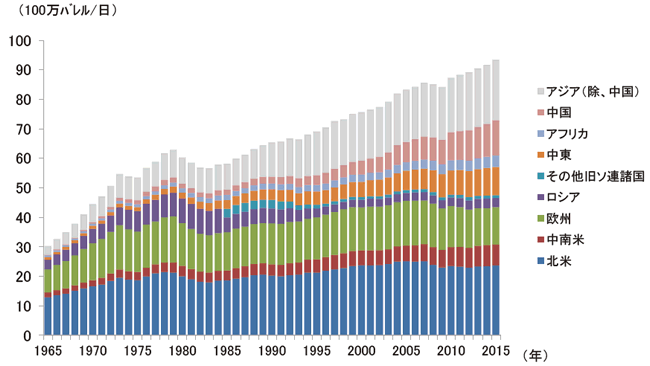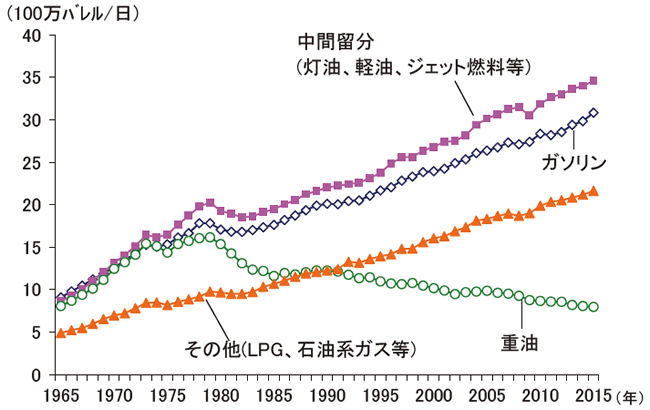第3節 二次エネルギーの動向
1.電力
(1) 消費の動向
世界の電力消費量はほぼ一貫して増加してきました。これを年代別に見ると、1970年代は石油ショック後に一時的な消費の低迷がありましたが、年平均5.3%と高い伸びを維持しました。その後、1980年代は3.6%、1990年代は2.5%と、徐々に伸び率が低下しましたが、2000年代は年平均3.1%と堅調な伸びを維持しました。
これを地域別に見ると、先進国の多い北米・西欧地域は世界全体の伸びを下回りました。また、ロシア及びその他旧ソ連邦諸国・東欧地域は、ソ連崩壊後の経済の低迷も影響し、1990年代は年平均マイナス4.3%と消費量が低下し、2000年代も年平均1.3%と低い伸びに止まりました。一方、1975年から2014年までの世界の電力消費量を増加させる大きな原因となったのは、開発途上国を多く抱えているアジア、中東、中南米等の地域でした。特にアジア地域は、1994年以降、電力消費量で西欧地域を上回るようになり、2004年以降、北米を上回るようになりました(第223-1-1)。
- 出典:
- IEA「World Energy Balances 2016 Edition」を基に作成
その一方で、アジア(除く日本、韓国)、アフリカ、中東、中南米は、北米や西欧に比べ、1人当たりの電力消費量は、依然として低い水準でした。例えば、2014年時点でアジア(除く日本、韓国)の1人当たり電力消費量は、OECD北米地域の15.1%程度に過ぎませんでした(第223-1-2)。
また、電力化率(最終エネルギー消費量全体に占める電力消費量の比率)は、世界全体で見ると1980年の10.9%から2014年の18.1%と約7.2ポイント上昇しました(第223-1-3)。これは、世界全体で電化製品等の普及が目覚ましかったことも大きな理由です。
その一方で、2014年時点で、日本の人口の10倍にもなる12億もの人々が電力供給を受けていません。その多くは、南アジアやサブサハラアフリカに存在しています(第223-1-4)。途上国にとって、未電化率の改善は大きな政策課題の一つとなっています。その実現のためには、電力供給インフラ(発電、送配電、再エネによる分散型電源)に対する大規模な投資が必要とされています。
- (注)
- 地域の定義はIEAによる。
- 出典:
- IEA「World Energy Balances 2016 Edition」及びWorld Bank 「World Development Indicators」を基に作成
- (注)
- 電力化率とは最終エネルギー消費に占める電力消費量の割合を指す。
- 出典:
- IEA「World Energy Balances 2016 Edition」を基に作成
- 出典:
- IEA「World Energy Outlook 2016, Energy Access Database」を基に作成
(2) 供給の動向
世界の電源設備容量は一貫して増加しており、2014年時点で61.1億kWとなりました(第223-1-5)。年代別に見ると、電源設備全体で1980年代は年平均3.5%、1990年代は年平均2.1%、2000年代は年平均3.8%の拡大となりました。将来に目を向けると、特に中国の拡大見通しが著しく、2013年1月に国務院が公表しました「エネルギー発展第12次5か年計画」の中で、発電設備容量を9.7億kWから14.9億kWまで増加させる(平均伸び率9%相当)目標を掲げています。
2014年の世界の電源設備容量を電源別に見ると、火力発電の比率が63.5%を占めており、主電源の役割を果たしたことが分かります。一方、1970年代の石油ショックを契機として、石油代替エネルギーとして原子力発電の開発が促進され、1980年代には原子力発電は年平均9.6%と高い伸び率を示していました。しかし、先進国での原子力開発が鈍化した結果、1990年代は伸び率が年平均0.5%、2000年代は伸び率が年平均0.8%に止まりました。また、水力発電は新規の立地が難しくなってきており、伸び率は低い水準にあり、したがって、1990年代の電源設備容量の伸びは火力発電が中心となる構造でした。国別に見ても、全般的には世界の傾向と類似していました。ただし、フランスのように、第一次石油ショックを契機に原子力発電の開発を加速し、全電源設備に占める原子力発電の構成比が1974年の6%から2014年の49%に増えているような例もありました。
世界の発電電力量もほぼ一貫して増加し、2014年時点で23.8兆kWhでした(第223-1-5)。これを世界の電源設備容量と比較すると、電源設備容量が1980年代は年平均3.5%、1990年代は年平均2.1%の伸びになっているのに対して、発電電力量が1980年代は年平均3.8%、1990年代は年平均2.5%と電源設備容量を上回る伸びとなっており、電源設備の稼働率が向上している状況が分かります。2000年代は、2008年秋に発生したリーマン・ショック等による世界的な景気後退の影響を受け、発電電力量が年平均3.0%の伸びとなり電源設備容量の年平均3.8%の伸びを下回りました。
火力発電電力量を電源別に見ると、石炭火力の伸び率は、1980年代から電源全体の伸び率を上回るようになり、全発電電力量に占める石炭火力の割合は1975年の36.5%から2014年の40.8%と増加しました。石油火力は、1970年代には年平均5.7%と堅調な伸びを示していましたが、石油ショックを契機に代替エネルギーへの転換が図られた結果、1980年代は年平均マイナス2.3%、1990年代は年平均マイナス0.7%、
2000年代は年平均マイナス2.6%と減少傾向が続いています。一方、天然ガス火力発電は、1970年代は伸び率の年平均は4.1%でしたが、1980年代年平均5.4%、1990年代年平均4.4%、2000年代は年平均5.4%と電源全体の伸び率を上回るようになり、石油火力の代替エネルギーの一つとして重要な役割を果たしてきました。2010年代に入り、政策的な支援を受けた再生可能エネルギーの導入拡大が進んでいます。また、燃料価格の高騰により、ガス火力の伸びが年平均1.7%に鈍化する一方で、安価な石炭火力の伸びは年平均2.9%で相対的に堅調に推移しています。
2014年の各国の電源別発電電力量を見ると、米国はシェールガス生産の増加により2010年以降石炭の割合が減少したのに対して、ガスが27%を占めるまで増加しました。英国はもともと国内に石炭が豊富であり、石炭火力が主力電源の役割を担っていましたが、北海ガス田の開発や電力自由化に伴って、天然ガス発電の比率が増加した後、CO2価格の低迷もあり石炭火力の割合が30%にまで戻りました。フランスでは原子力の比率が78%と非常に高くなっていました。再生可能エネルギーの導入が進んでいる国でも、ドイツでは原子力のシェアの低下に伴って石炭の比率が46%と一定の水準にあるものの、イタリアではガスの比率が34%まで低減しました。中国は経済発展とともに発電電力量も非常に高い伸びを示していますが、石炭の割合が73%と高く、環境問題が課題となっていました。また韓国は、石炭の比率が42%、原子力の比率が29%と高くなっていました(第223-1-6)。
なお、欧州や北米では国境を越えて送電線網が整備されており、電力の輸出入が活発に行われました(第223-1-7)。
- 出典:
- IEA「World Energy Outlook 2016」を基に作成
【第223-1-6】主要国の発電電力量と発電電力量に占める各電源の割合(2014 年)
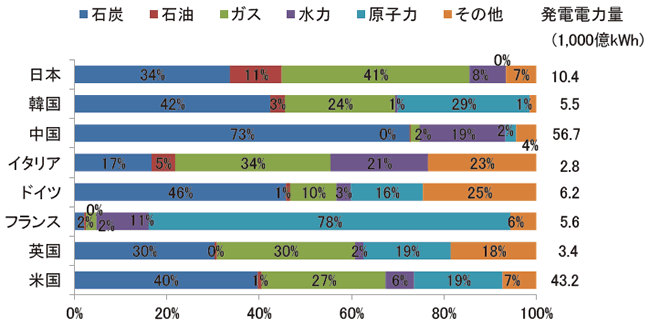
【第223-1-6】主要国の発電電力量と発電電力量に占める各電源の割合(2014 年)(xls/xlsx形式:126KB)
- 出典:
- IEA「World Energy Balances 2016 Edition」を基に作成
- 出典:
- IEA 「Electricity Information 2016」を基に作成
2.ガス事業
先進国のガス事業状況を見ると、従来欧州では、国営企業が上流のガス生産・輸入から、国内ガス輸送・配給、販売まで一元的に行うケースが主流でしたが、1980年代から英国等で国営ガス事業者の民営化やガス市場自由化が進められました。その後、1998年の第一次EUガス指令、2003年の第二次EUガス指令、2009年7月には第三次エネルギーパッケージによって、EU全体でガス市場自由化が進められ、現在では、小売市場の全面自由化や輸送部門の所有権分離若しくは機能分離が実施されています。
米国では、特に1985年以降、連邦規制により州際(州をまたぐ)パイプラインの第三者利用、ガスの輸送機能/販売機能の分離が進められました。同時に、各州でも家庭用まで含めた自由化の拡大及びガス配給会社(LDC)による託送サービスの提供を制度化する州が出現しました。しかし、自由化の程度は州によって異なり、小売市場の全面自由化は8州で実施されているに過ぎません。
都市ガスの消費量を先進国で比較すると、2014年では米国における消費量が多く、26,283PJ(ペタジュール)の消費量となりました。EU諸国は、英国の2,783PJ、ドイツの2,969PJ、フランスの1,517PJで、日本は1,557PJでした。
パイプラインについては、2014年の米国の輸送パイプライン総延長は486千km、配給用パイプラインの総延長は2,035千kmとなりました。欧州諸国では、輸送パイプラインと配給パイプラインの総延長合計が、英国は286千km、ドイツは505千km、フランスは232千kmとなりました。
一方、我が国は、2014年では、電気事業者や国産天然ガス事業者等によって整備されている輸送パイプラインの総延長が約3千km、一般ガス事業者の配給パイプライン総延長は約255千kmとなりました。
3.熱供給
熱供給(一般的には地域冷暖房)の始まりは19世紀に遡りますが、石油ショック後、特に欧州において飛躍的に発展しました。熱源として化石燃料だけでなく、再生可能エネルギー、廃棄物、工場排熱等が利用できるほか、熱電併給16も適用できることから、石油依存度の低減、エネルギー自給率向上、環境保護といった観点からの有効性が注目されてきました。
熱供給の主たる燃料は様々であり、例えば米国やオランダでは天然ガスが主に用いられています(熱供給に占める天然ガスの割合は、米国が約74%、オランダが約70%)。一方、北欧諸国では、再生可能エネルギーや廃棄物の利用比率が他国と比べ高いという特徴があり、例えばノルウェーでは熱供給に占めるこれらの熱源の利用割合は約65%17となっています。
地域単位で空調用の熱をまとめて製造・供給する地域熱供給設備は、ロシアや中国で大規模に普及しています。これらの国々は特に広大な寒冷地を抱えており、暖房需要が大きいため、長期的かつ計画的に熱の供給網が整備されてきました。また、地域熱供給設備は欧米諸国(北欧、中東欧を含む)においても導入されてきたほか、韓国においても欧州諸国と同水準の熱供給が行われてきました。熱を伝えるための導管ネットワークの長さで比較すると、これらの国々はいずれも日本の672kmに対してはるかに大きな数値となっており、大規模な供給網整備が行われてきたことが分かります(第223-3-1)。
- (注)
- *は2007年の値、**は2009年の値、***は2011年の値。
- 出典:
- Euroheat & Power「 District Heating and Cooling: Country by Country」2013年版及び2015年版を基に作成
4.石油製品
世界の石油消費量は2015年に9,501万バレル/日となり、北米が25%、欧州が13%、中国を含むアジアが34%となりました。1960年代に比べ、世界の石油消費量は約3倍に拡大し、近年では中国や中東地域の消費が拡大したのが特徴です(第223-4-1)。
世界の石油消費量の推移を製品別に見ると、ガソリンや灯油、軽油等の軽質油製品の消費が堅調に増加してきたことに対して、重油の消費量が低下しており、製品消費の軽質化が見られます(第223-4-2)。
- (注)
- 1984年までのロシアには、その他旧ソ連邦諸国を含む。 出典:BP「Statistical Review of World Energy 2016」を基に作成
- 出典:
- BP「Statistical Review of World Energy 2016」を基に作成