第2節 主要10か国・地域のGHG排出削減とカーボンニュートラル実現に向けた動向
世界各国は、2050年~2070年代のカーボンニュートラル実現に向けた取組を進めていますが、その状況や取組の内容には違いがあります。主要10か国・地域(日本・米国・EU・英国・韓国・カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・中国)のGHG排出削減率の目標と進捗、その背景にある最終エネルギー消費量削減率と非化石電源比率(発電に占める再エネと原子力の比率の合計)は次のとおりです(第132-1-1)。
【第132-1-1】主要10か国・地域におけるGHG排出削減率・最終エネルギー消費量削減率・非化石電源比率
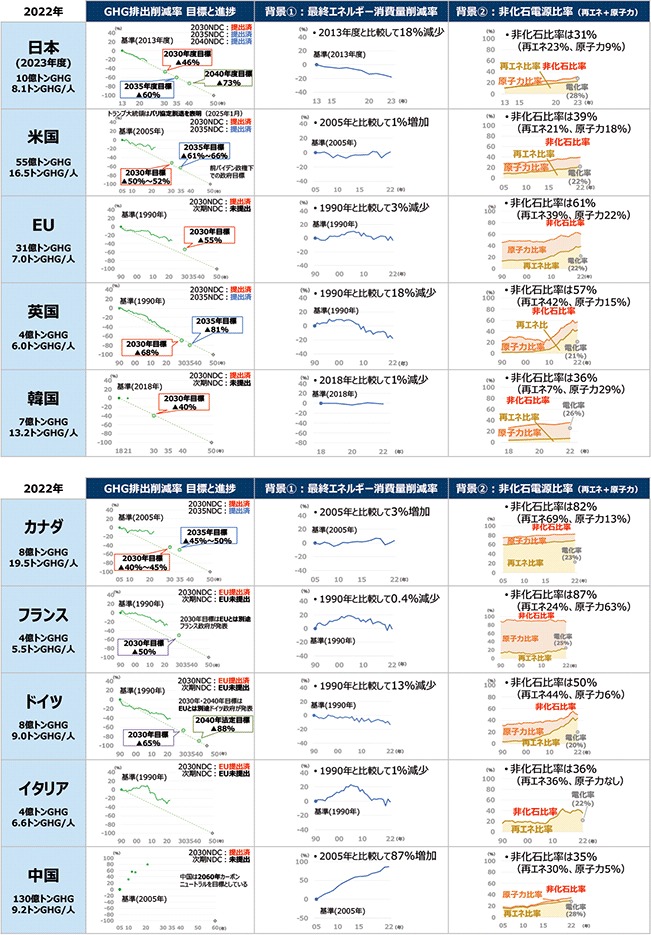
(注1)各国のGHG排出目標・実績は、土地利用、土地利用変化及び林業(LULUCF)分野における排出・吸収量を考慮して算出している。
(注2)最終エネルギー消費量削減率の基準年及び基準年度は、各国のNDC基準年及び基準年度と合わせている。
(注3)電化率はIEAと総合エネルギー統計でエネルギー換算基準等の前提条件が異なる。
- 資料:
- 以下の出典資料を基に経済産業省作成
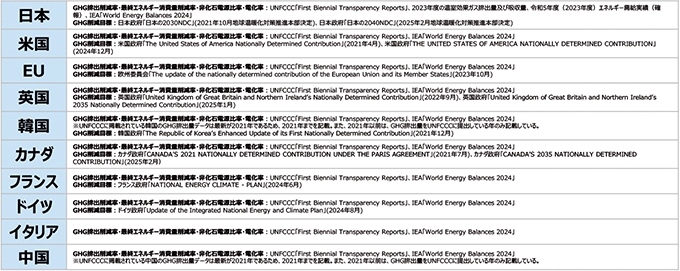
【第132-1-1】主要10か国・地域におけるGHG排出削減率・最終エネルギー消費量削減率・非化石電源比率(pptx形式:203KB)
本節では、主要10か国・地域のこれまでのGHGの排出削減に向けた取組を、GHG排出量・最終エネルギー消費・非化石電源比率等の観点から確認するとともに、今後のGHGの排出削減目標やカーボンニュートラル実現に向けた取組を確認することで、GHGの排出削減に向けた各国の動向を概観1していきます。
1.日本
(1)これまでの進捗
日本のGHG排出量は、2010年代半ば以降、減少傾向にあります。2023年度のGHG排出量の削減実績は2013年度比で約24%2となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、エネルギー転換部門の排出量が最も多く、製造・建設部門がこれに続き、この2部門の合計で、GHG排出量の約6割を占めています。エネルギー転換部門の排出量は、2011年の東日本大震災後に火力発電の割合が高まったことを受けて一時的に増加しましたが、現在は減少傾向に転じています。製造・建設部門についても、エネルギー消費効率の改善に加えて生産量の減少等により、排出量は減少傾向にあります。
最終エネルギー消費量は、徹底した省エネの取組もあり、2000年代半ばから減少しています。2013年度の最終エネルギー消費量は原油換算で約3.6億kLでしたが、2023年度には約3.0億kLに減少しました。一方、DXやGXの進展により電力需要の増加が見込まれるため(第1部第2章第1節参照)、更なる省エネの推進が必要な状況です。
日本の最終エネルギー消費のうち約3割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2011年の東日本大震災後に下落しましたが、近年は上昇傾向にあります。再エネについては、2012年にFIT制度(再生可能エネルギー固定価格買取制度)が開始されたことで、増加しています。原子力については、2011年の東日本大震災後に稼働を停止していましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた新規制基準に基づき安全性が確認された14基(2025年3月末時点)の原子炉が再稼働しています。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
日本は2020年10月に2050年カーボンニュートラル(ネット・ゼロ)3を宣言し、2021年4月に、2030年度においてGHG排出量の46%削減(2013年度比)を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。その後、2025年2月に、世界全体での1.5℃目標と整合的で、2050年カーボンニュートラル実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、2035年度、2040年度に、GHGを2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを目指すことを地球温暖化対策推進本部で決定し、新たな削減目標(NDC)として、国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。また、これらの削減目標及びその目標実現に向けた対策・施策を含む新たな「地球温暖化対策計画」が2025年2月に閣議決定されました。日本は、「地球温暖化対策計画」に加え、同計画と一体的に検討が進められ、2025年2月に閣議決定された「GX2040ビジョン」「第7次エネルギー基本計画」に基づき、エネルギー安定供給、経済成長と脱炭素の同時実現を目指し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組を着実に進めていきます。
主に2040年に向けたエネルギー政策の方向性を示す「第7次エネルギー基本計画」では、「すぐに使える資源に乏しく、国土を山と深い海に囲まれるなどの日本の固有事情を踏まえれば、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく。」「エネルギー危機にも耐え得る強靱なエネルギー需給構造への転換を実現するべく、徹底した省エネ、製造業の燃料転換等を進めるとともに、再エネ、原子力等エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用する。」などの方針が掲げられています。今後、「第7次エネルギー基本計画」に基づき、省エネ・非化石転換や、脱炭素電源の拡大と系統整備を進めていくほか、次世代エネルギーの確保に向けて、幅広い分野での活用が期待される水素等(アンモニア、合成燃料、合成メタンを含む。)の社会実装を進めるとともに、電化や水素等を活用した非化石転換では脱炭素化が困難な分野においても脱炭素を進めるため、CCS4等を進めていきます。
2.米国
(1)これまでの進捗
米国のGHG排出量は、2000年代後半をピークに減少傾向にあります。2022年時点のGHG排出量の削減実績は2005年比で約17%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、運輸部門、エネルギー転換部門の順に排出量が多くなっており、この2部門の合計で、GHG排出量の約6割を占めています。エネルギー転換部門のGHG排出量は2000年代後半から減少しており、2020年頃には、この間GHG排出量が横ばいの運輸部門を下回りました。2000年代後半に進展した「シェール革命」により石炭から天然ガスへの燃料移行が進み、エネルギー転換部門のGHG排出量の削減が進んだことが要因として挙げられます。
最終エネルギー消費量は2000年頃から横ばいで推移しており、2022年時点では原油換算で約17億kLとなっています。
米国の最終エネルギー消費のうち約2割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2010年頃から増加し、2022年時点で39%となっています。再エネは2010年頃まで10%程度で横ばいに推移していましたが、税額控除(投資税額控除・生産税額控除)等の再エネの導入支援が講じられたことで2010年頃から増加し、2022年には21%となっています。原子力は、1979年のスリーマイル島原子力発電所の事故以降、1996年のワッツバー原子力発電所1号機、2016年ワッツバー2号機が新しく稼働しましたが、新しく稼働した原子力発電所がこれら2基だけであったことや、老朽化した原子力発電所が閉鎖されたことを背景に、比率は横ばいで推移しており、2022年には18%となっています。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
米国は前バイデン政権時の2021年の大統領令により2050年カーボンニュートラルを宣言しており、NDCでは、2030年に2005年比で50~52%削減(2021年発表)、2035年に61~66%削減(2024年発表)というGHG排出量の削減目標を掲げています。2024年12月、2035年の新たな削減目標(NDC)を国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。
また、最終エネルギー消費の今後の見通しについては、米国エネルギー情報局(EIA)が前述のGHG排出量の削減目標とは別途、2025年に独自にシナリオ分析を行っており、この分析において、2050年に2024年比で約6%減少するとの見通しが示されています。
GHG排出量削減目標の実現に向けて、前バイデン政権は、省エネの促進、再エネや原子力の更なる導入拡大、電化やネガティブエミッション等の取組に向けた各種政策を発表し、順次実施してきました。取組の一例として、2022年8月に気候変動対策等を盛り込んだ「インフレ削減法」5が成立し、省エネや、再エネや原子力といったクリーン電力への移行を促進するための支援策が示され、設備投資に対する税額控除や生産税額控除等が講じられてきました。原子力については、2050年カーボンニュートラル実現とエネルギー安全保障の強化に向けて、2050年に300GW程度まで原子力の設備容量を増強する目標を掲げており、既存炉の活用と新たな原子力発電所の継続的な建設の両方に支援が行われてきました。こうした中、約30年ぶりに新設の原子炉として建設されていたボーグル原子力発電所3・4号機が、それぞれ2023年7月、2024年4月に稼働しました。また、次世代エネルギーについても、米国政府は2023年、2050年までに年間5,000万トンのクリーン水素6の製造を目指すこと等を掲げた「国家クリーン水素戦略」を発表するとともに、「インフレ削減法」によりクリーン水素の製造に対する税額控除が講じられてきました。CCUS7についても、「インフレ削減法」によりCO2の貯留に対して税額控除が講じられてきました。
しかし、2025年1月に就任したトランプ大統領は、こうしたクリーンエネルギー政策の大幅な転換を進めています。トランプ大統領は同月、パリ協定からの脱退を盛り込んだ大統領令に署名するとともに8、前バイデン政権下で発令された気候変動・環境保護・再エネ・EVの導入などに関する大統領令を正式に撤回9し、「インフレ削減法」に基づく関連支出の一時停止を決定10するとともに、省エネについては、機器が満たすべき省エネ基準の規制を緩和し、又は撤回しました。さらに、国内に低コストのエネルギーを提供するため、領海外の大陸棚において洋上風力発電を実施するための新規リースを凍結し、新たな風力発電プロジェクトを停止しました。一方で、資源開発については、国産エネルギー資源の開発を促進することを示す大統領令を発令しています。同大統領令におけるエネルギーの定義には、ウラン・地熱が含まれており、原子力と地熱発電は導入を促進する方針であることがうかがえます。また、アラスカでの資源開発の加速11にも意欲を示しています。
3.EU
(1)これまでの進捗
EUのGHG排出量は2000年代半ばから減少傾向にあります。2022年時点のGHG排出量の削減実績は1990年比で約33%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、運輸部門、エネルギー転換部門の順に排出量が多くなっており、この2部門の合計で、GHG排出量の約5割を占めています。エネルギー転換部門の排出量は、石炭火力発電の廃止等によって脱炭素化が進行したことにより2000年代後半から減少し、2022年時点では運輸部門と同程度になっています。
最終エネルギー消費量は2000年半ばから減少しており、2022年時点では原油換算で約11億kLとなっています。
EUの最終エネルギー消費のうち約2割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2010年頃に増加し、2022年時点で61%となっています。再エネについては、欧州委員会において2009年に採択された「再生可能エネルギー指令」(RED)の下で各国が導入支援を行ったことにより2000年代後半から増加傾向にあり、2022年には39%となっています。一方で原子力は、脱原子力を進めている加盟国もあるため、2010年頃から減少傾向にあり、2022年には22%となっています。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
EUは欧州気候法により2050年カーボンニュートラルを定めており、NDCでは、2030年に1990年比で少なくとも55%削減というGHG排出量の削減目標を掲げています。欧州委員会は2024年2月、欧州科学的助言機関(ESABCC)の提案を参考に、2040年の削減目標の水準のオプションを3通り提示した上で、2040年までに1990年比で90%のGHG排出量削減を目標水準とすることを提案しており、今後、欧州理事会及び欧州議会で議論され、法制化される予定です。次期NDCについては、2025年3月現在、国連気候変動枠組条約事務局に提出されていません。
最終エネルギー消費量については、2030年NDC目標の更新版において、2030年NDC目標(1990年比で少なくともGHG排出を55%削減)に向けた「欧州脱炭素化政策パッケージ(Fit for 55)」(2021年7月採択)のうち、「エネルギー効率化指令」を改正し、従前のEUリファレンスシナリオ2020からさらに11.7%削減することを目標としました。これは2030年に1990年比で約2割、最終エネルギー消費量を削減することに相当します。また、2030年NDC目標の更新版において、最終エネルギー消費における再エネの割合を2030年までに少なくとも42.5%とする目標も掲げています。
GHG排出量削減目標の実現に向けて、EUは、ロシアによるウクライナ侵略以降、エネルギーの脱ロシア依存を加速化しつつ、米国や中国などに対抗するため、欧州域内におけるグリーン産業支援を強化し、省エネや再エネの導入拡大等、カーボンニュートラル実現に向けた様々な取組を行っています。欧州議会等において、前述の「欧州脱炭素化政策パッケージ(Fit for 55)」(2021年7月採択)に加え、グリーン水素を中心に水素経済を発展させる取組を示した「EUクリーン水素戦略」(2020年7月採択)、ロシアからの化石燃料の脱却や再エネや水素などの拡大を目的とした「REPowerEU計画」(2022年5月採択)、欧州のカーボンニュートラル産業の競争力を強化するための「グリーンディール産業計画」(2023年2月採択)、気候変動対策と競争力強化を同時に実現させるための「クリーン産業ディール」(2025年2月公表)等が採択又は公表され、取組が具体化されています。例えば、2030年までの年間100GWの再エネ導入、2030年までの年間2,000万トンのグリーン水素の域内供給、2030年までの年間5,000万トンのCO2貯留容量開発に向けた石油ガス業界等に対するCO2貯留プロジェクトの建設・運営等の貢献の義務付け、等の取組を進めているほか、CO2の排出量取引については、対象部門の拡大(海運セクター等)や排出枠の無償割当の削減(航空機等)といった排出量取引制度(EU-ETS)の強化に加え、2026年1月には、炭素国境調整措置(CBAM)12の本格適用が予定されています。EU-ETSは2005年から取引が開始され、当初の価格は約7euros/tCO2でしたが、2024年12月時点の取引価格は約63euros/tCO2(約65ドル)となっています。
原子力については、欧州委員会が環境的にサステナブルな経済活動を分類・定義したEUタクソノミーにおいて、放射性廃棄物の管理等の資金を確保すること等、一定の条件を満たした場合に原子力への投資はサステナブルな経済活動であると認定されています。また、2024年2月に政治合意に達した「ネットゼロ産業法」において、廃棄物を最小化し得る先進原子炉技術や小型モジュール炉(SMR)が戦略的ネット・ゼロ技術の一つとして位置づけられています。原子力についてはEU加盟国間で様々な意見があり、その利用の可否を含めて、各政府に委ねられていますが、例えば、イタリアやスペイン、ベルギーといった過去に原子力の閉鎖等を政府決定したEU加盟国における原子力利用への回帰の動きも見られます。
4.英国
(1)これまでの進捗
英国のGHG排出量は、1990年以降減少傾向にあります。2022年時点のGHG排出量の削減実績は1990年比で約50%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、運輸部門、家庭・業務部門、エネルギー転換部門の順に排出量が多くなっており、これら部門の合計で、GHG排出量の約7割を占めています。2015年に「今後10年以内に石炭火力発電の使用を終了する」旨が宣言されて以降、発電全体の約2割以上を占めていた石炭火力発電の発電量が減少したことなどを背景に、2010年代半ばからエネルギー転換部門のGHG排出量が減少しています。その他の部門も運輸部門を除いて減少傾向にあります。また、産業部門については、製造業の生産量が下落傾向にある中、GHG排出量全体に占める割合は主要国と比較して小さく、排出量自体も減少しています。
最終エネルギー消費量は、2000年代前半に気候変動税(CCL)や排出量取引制度といった経済的手法が相次いで導入されたことにより、2000年代後半から減少傾向にあり、2022年時点では原油換算で約1.2億kLとなっています。
英国の最終エネルギー消費のうち約2割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2010年頃から増加し、2022年時点で57%となっています。これは主に、再エネの電源比率が2010年代から増加したことに起因しています。英国では、FITやCfD制度13等の再エネの導入支援策が2010年代前半に導入されたことで再エネの導入が進み、再エネの電源比率は2022年に42%まで上昇しました。原子力については、英国は2000年代以降一貫して再エネとともに推進していますが、新設が進まない一方で古い原子力発電所の廃炉も進んだことで、原子力の発電比率は2010年頃にかけて減少し、2022年時点では15%となっています。なお、英国は2024年9月、国内で唯一稼働していた石炭火力発電所を運転停止し、石炭火力発電所を全廃しました。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
英国は2050年カーボンニュートラルを宣言しており、NDCでは2030年に1990年比で少なくとも68%削減、2035年に少なくとも81%削減というGHG排出量の削減目標を掲げています。2025年1月、2035年の新たな削減目標(NDC)を国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。
また、最終エネルギー消費量については、2030年のNDC目標と整合的な目標として、2030年に2021年比で15%削減するという目標を掲げており、省エネ技術開発の促進、住宅・建築物における低炭素暖房システムの導入、EVの導入等の省エネを進めていくとしています。
GHG排出量削減目標の実現に向けて、英国は引き続き、再エネと原子力の活用による電源の非化石化を進めていくとしており、2022年4月に発表した、エネルギー安全保障を強化するための総合的な戦略である「エネルギー安全保障戦略」において、再エネの拡大に加え、新設を含めて原子力を活用する方針を明確にしています。同戦略において、太陽光は2035年までに現在の5倍となる70GWに増強する、洋上風力は2030年までに最大50GW導入する(うち、浮体式洋上風力発電で最大5GWを確保することを目指す)、原子力は導入を大幅に加速して2030年までに最大8基の原子炉を新設し、2050年までに発電容量を最大24GW(英国電力需要の25%相当)に拡大する等の目標を掲げており、このために必要な制度整備や支援策を進めるとしています。原子力については、ヒンクリーポイント原子力発電所やサイズウェル原子力発電所において新規の原子力発電所の建設を進めているほか、こうした従来型の大型原子力発電所に加え、小型モジュール炉(SMR)の開発や導入も進めるとしています。また、天然ガス火力については、再エネの変動性をカバーするため、既存のガス火力発電所を維持するとともに、将来的に水素燃焼やCCUSに対応可能なガス火力を支援する方針を示しています。
次世代エネルギーについては、英国は2023年12月に発表した「水素製造輸送ロードマップ」において、2030年までの低炭素水素の生産能力の目標を10GW(そのうち6GWはグリーン水素、残り4GWはブルー水素)と掲げており、水素の製造プロジェクトへの支援等を引き続き行うとしています。
CCUSについては、2050年までにGHG排出量を実質ゼロにするための包括的な脱炭素ロードマップとして2021年10月に策定された「ネットゼロ戦略」において、2030年までに4つのCCUSクラスターを立ち上げ、年間2,000万トン~3,000万トンの回収を実現することを掲げています。
英国は、2050年カーボンニューラル実現に向けて、気候保護法に基づき、独立諮問機関であるClimate Change Committee(CCC)が5年間のGHG排出量に上限を設ける「カーボンバジェット」(Carbon Budget)を設定しています。現在は「第6次カーボンバジェット14」として、2033年から2037年までの5年間のGHG排出量の上限値を設定(2035年に1990年比で78%削減する量に相当)しており、この実現に向けて引き続き、気候変動税(CCL)、発電事業者を対象にした炭素税、国内排出量取引制度(UK-ETS)といった経済的手法も講じるとしています。UK-ETSは、2021年1月から取引が開始され、最初の排出枠オークションが実施された2021年5月時点の価格は約44pounds/tCO2でしたが、2024年11月時点の取引価格は約37pounds/tCO2(約47ドル)となっています。
なお、英国は2024年7月に14年ぶりに保守党から労働党に政権交代し、スターマー政権が誕生しました。スターマー政権は、前政権での再エネ拡大や原子力の推進等のエネルギー政策を継承しつつ、クリーンエネルギーの導入拡大等を図っていくとしています。具体的には、2024年12月に発表した「2030年クリーン電力行動計画」において、前述の「エネルギー安全保障戦略」において2030年までに電力部門の95%をクリーンエネルギー化するとしていた目標について95%以上とする等の目標を掲げており、2030年に向けて、再エネ等の拡大に向けた産業支援や投資促進、水素技術の開発やCCUS等を進めていくとしています。
5.韓国
(1)これまでの進捗
韓国のGHG排出量は、1990年以降から増加傾向にありましたが、2018年をピークに減少傾向にあります。2021年時点のGHG排出量削減実績は2018年比で約0.4%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、エネルギー転換部門の排出量が最も多く、全体の約4割を占めています。1990年から2010年代にかけて、経済発展による電力需要の増加等によりエネルギー転換部門のGHG排出量は増加しましたが、石炭火力発電の発電量減少や高効率なガス火力発電の導入等により、2018年以降は減少傾向にあります。
最終エネルギー消費量は一貫して増加傾向にありましたが、省エネ等により2010年代後半から横ばいとなり、2022年時点では原油換算で約2.0億kLとなっています。
韓国の最終エネルギー消費のうち約3割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は1990年以降減少していましたが、2010年代半ばから増加し、2022年時点で36%となっています。2010年頃まで非化石電源のほぼ全てを原子力が占めていましたが、再エネ供給義務化制度(RPS)の導入等により再エネも2010年代半ばから増加しており、2022年時点で7%となっています。原子力については、2017年に脱原子力の方針が宣言されましたが、60年以上で漸進的に進める政策であったため、その後も原子力が一定割合を占めており、2022年に脱原子力政策を撤回する方向性が発表された後は、ハヌル原子力発電所1号機・2号機の新設により原子力の比率は増加傾向にあり、2022年には29%となっています。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
韓国は2050年カーボンニュートラルを宣言しており、NDCでは2030年に2018年比で40%削減するというGHG排出量の削減目標を掲げています。次期NDCについては、2025年3月現在、国連気候変動枠組条約事務局に提出されていません。
韓国は、気候危機対応とカーボンニュートラル実現のための法的基盤として、GHG排出量を2030年までに2018年比で40%削減すること等を盛り込んだ「カーボンニュートラル・グリーン成長基本法」を施行しています。これに基づき、2023年に2030年の再エネの導入目標等を盛り込んだ「炭素中立グリーン成長国家戦略及び第1次国家基本計画」等が策定され、取組が進められています。
また、最終エネルギー消費量については、2019年に公表した「第3次エネルギー基本計画」において、2040年までに追加の省エネ対策を実施しなかった場合と比較して最終エネルギー消費量を18.6%削減するという目標を掲げており、産業分野における高効率機器の導入支援、住宅・建築物の省エネ基準の引き上げや公共建築物の改修、EVの導入等の省エネを進める方針を示しています。
エネルギーについては、2025年2月に採択された「第11次電力需給基本計画」(2024年から2038年までの15年間を対象)において、カーボンニュートラルの実現に向けて、再エネと原子力をバランスよく拡大させる方針を示しています。再エネについては、洋上風力を拡大させることで2038年に電源に占める割合を29%程度と現在の4倍以上に拡大させる方針を示しており、再エネ投資への融資支援等を行うRE100ファンドの構築等を進めています。原子力については、同計画において、2038年までに大型原子炉2基と小型モジュール炉(SMR)1基を建設する計画を示しています。
次世代エネルギーについては、韓国では2020年に世界で初めて水素法が制定され、水素政策の推進と関連企業への支援を行っており、2021年に制定された「水素先導国家ビジョン」においては、2030年に100万トン、2050年に500万トンのクリーン水素を生産する目標を掲げています。
CCUSについては、2030年までに12億ドルのCCUS支援を行うことを発表しており、既存の油田やガス田施設を再利用できる洋上CCS施設についても支援対象としています。
GHG排出の規制手段として、2015年から排出量取引制度(K-ETS)を導入しており、CO2排出量の7割程度がカバーされています。取引開始時の2015年の価格は約8,000KRW/tCO2でしたが、2024年12月時点の取引価格は約10,000KRW/tCO2(約7ドル)となっています。
6.カナダ
(1)これまでの進捗
カナダのGHG排出量は、1990年以降増加した後、2000年代以降は横ばいで推移しています。2022年時点のGHG排出量削減実績は2005年比で約8%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、エネルギー転換部門、運輸部門の順に排出量が多くなっており、これら部門の合計で、GHG排出量の約4割を占めています。エネルギー転換部門の排出量は石油・天然ガス等の上流開発、とりわけオイルサンド(石油成分を含む砂岩)の開発等の理由により、1990年代に増加した後、石炭火力発電の発電量減少等に伴い、徐々に減少しています。
最終エネルギー消費量は2000年代前半にかけて増加した後は横ばいで推移しており、2022年時点では原油換算で約2.2億kLとなっています。
カナダの最終エネルギー消費のうち約2割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2000年前後に一時的に低下したものの、1990年以降一貫して8割程度と高い水準であり、2022年は82%となっています。再エネについては、カナダは水力発電が発電に占める割合が大きいことから、再エネ比率が1990年以降一貫して高い水準で推移しており、2022年時点では69%となっています。原子力については、2000年頃から横ばいで推移しており、2022年時点では13%となっています。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
カナダは2050年カーボンニュートラルを宣言しており、NDCでは2030年に2005年比で40~45%削減(2021年提出)、2035年に45~50%削減(2024年発表)というGHG排出量の削減目標を掲げています。2025年2月、2035年の新たな削減目標(NDC)を国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。
GHG排出量削減目標の実現に向けて、カナダは産業用設備が満たすべきエネルギー効率規制の強化や高効率設備の導入支援、住宅や建築物の省エネ基準の段階的な引き上げ、EVの導入等の省エネを進めていくとしています。また、2024年12月に発表した「クリーン電力戦略」において、引き続き再エネや原子力を推進するとともに、電力部門のGHG排出を削減するため、化石燃料を使用する発電設備にCO2排出量の上限を設定するクリーン電力規制を2035年に導入する方針を示しています。加えて、電力の供給側だけでなく需要側の管理にも重点を置き、エネルギー消費を最適化していく等の取組により、クリーンで信頼性が高く、安価な電力システムを構築していくとしています。
次世代エネルギーについては、2020年に公表された「カナダ水素戦略」において、水素の製造や利活用推進の方針を示しており、2050年までに年間2,000万トン以上の水素製造を目指すとしています。
CCUSについては、2023年9月に発表した「炭素管理戦略」において、CCSの可能量を拡大し、2030年までに年間1,500万トンのCO2を回収・貯留することや、CCUS事業への直接補助等の支援を行うことを掲げています。なお、CCSを行わない石炭火力発電所は2030年までに段階的に廃止していく旨を2016年に発表しています。
GHGの排出規制として、カナダ政府は2019年から、化石燃料の販売事業者を課税対象とする炭素税を導入していましたが、国民負担を低減させるため、2025年3月に炭素税の税率をゼロに引き下げる決定がなされ、炭素税は事実上廃止されることとなりました。他方、炭素税とあわせて2019年に導入された、大規模排出者が一定の排出量を超えた場合にオフセットクレジットを購入すること等を求める「排出量基準制度」については、今後も維持するとしています。
7.フランス
(1)これまでの進捗
フランスのGHG排出量は、1990年頃をピークに減少傾向にあり、2022年時点のGHG排出量削減実績は1990年比で約28%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、運輸部門、家庭・業務部門の順に排出量が多くなっており、これら部門の合計で、GHG排出量の約5割を占めています。フランスは非化石電源の比率が高いため、エネルギー転換部門の排出量は小さくなっています。
最終エネルギー消費量は2000年代半ばから減少傾向にあり、2022年時点では原油換算で約1.5億kLとなっています。
フランスの最終エネルギー消費のうち約3割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は1990年以降90%程度と高い水準で推移しており、2022年時点で87%となっています。再エネについては、FIT制度や競争入札制度等の導入支援により、2010年代前半から増加し、2022年には24%となっています。原子力については、設備の老朽化に伴う改修により稼働率が低下していた等の要因により減少傾向にありますが、従前から原子力比率が高く、2022年においても63%と、他国と比較して高い水準にあります。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
フランスは2050年カーボンニュートラルを宣言しており、2023年に公表した「国家エネルギー・気候計画」において、2030年に1990年比で50%削減というGHG排出量の削減目標を掲げています。
GHG排出量削減目標の実現に向けて、マクロン大統領は2022年2月、再エネの更なる加速と原子力の推進(既存原子力の運転延長、原子炉の新設)を表明しています。2023年11月には、2050年カーボンニュートラル実現に向けて省エネを促進しつつ、化石燃料依存からの脱却と低炭素電力・地域暖房網の拡大などを図る「エネルギー気候戦略」を公表し、取組を強化しています。具体的には、2030年のNDC目標と整合的な目標として、2030年の最終エネルギー消費削減目標(2012年比で30%減)を設定し、建築物の省エネ改築や化石燃料を利用した暖房システムからの脱却等に取り組むとともに、エネルギー供給の低炭素化に向けて、既存原子力の運転期間の延長や原子力の容量の増強(現行の279TWhから2030年に360~400TWhに増強)等、原子力を推進するとしており、2050年までに6基の原子力発電所の建設を計画しています。直近ではフランマルビル原子力発電所3号機が2024年12月に送電を開始しました。再エネについては、「国家エネルギー・気候計画」において、2035年の設備容量の目標を設定(例えば、太陽光発電の目標は現行の3~4倍となる75~100GW)し、税制優遇等の導入支援を行うとしています。なお、石炭火力発電については、2027年に廃止するとしています。
また、次世代エネルギーについては、「エネルギー気候戦略」において、再エネや原子力から製造される脱炭素水素の製造能力の拡大を図るとしており、同戦略において、2030年に6.5GW、2035年に10GWの水電解装置を導入する目標を掲げています。
CCUSについては、2024年7月に発表したCCUS戦略の更新版において、2025年から2030年までに年間400~850万トン、2030年から2040年までに年間1,200~2,000万トン、2040年から2050年までに年間3,000~5,000万トンのCO2を回収する目標を掲げており、この目標に向けて、国内におけるCO2貯留地の開発や、CO2貯留地と産業地域等を結ぶ欧州大のCO2輸送インフラの創設、大気中からのCO2回収等を進めるとしています。
GHG排出の規制手段として、排出量取引制度(EU-ETS)に加え、燃料に対する炭素税を2014年から運用しています。
8.ドイツ
(1)これまでの進捗
ドイツのGHG排出量は、1990年以降減少傾向にあり、2022年時点のGHG排出量削減実績は1990年比で約41%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、エネルギー転換部門、運輸部門の順に排出量が多くなっており、これら部門の合計で、GHG排出量の約5割を占めています。エネルギー転換部門の排出量は1990年以降横ばいに推移してきましたが、石炭火力発電のフェーズアウト等により、2010年半ば以降、減少傾向に転じています。
最終エネルギー消費量は2000年半ばから減少傾向にあり、2022年時点では原油換算で約2.3億kLとなっています。
ドイツの最終エネルギー消費のうち約2割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2000年代後半から増加し、2022年時点で50%となっています。再エネについては、2000年に制定された「再生可能エネルギー法」において、再エネがエネルギー政策の中心として位置づけられたことなどを背景に、2000年代以降増加しており、2022年には44%となっています。原子力については、2002年に脱原子力を法制化して以降、段階的に原子力発電所を閉鎖しており、2022年には6%となっていますが、2023年4月には全ての原子力発電所の運転が停止して脱原子力発電を完了しました。また、電力の安定供給を確保するため、中東・北米・欧州諸国からのLNG輸入強化の動きやガス火力発電を活用する動きも足下で見られます。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
EUが2050年カーボンニュートラルを目指す中、ドイツは2045年カーボンニュートラルというより高い目標を宣言しており、1990年比で2030年に少なくとも65%削減、2040年に少なくとも88%削減というGHG排出量の削減目標を掲げています(いずれも2021年発表)15。
最終エネルギー消費量については、2030年のNDC目標と整合的な目標として、「エネルギー効率化法」において、2030年までに2008年比で27%削減する目標を掲げ、産業分野における高効率機器の導入支援、公共部門における省エネの義務化、EVの導入等の省エネを推進しています。
2023年4月に原子力を全廃したドイツは、GHG排出量削減目標の実現に向けて、「再生可能エネルギー法」において2030年に再エネ比率を80%まで引き上げる旨の目標を掲げるとともに、2035年までに国全体の電力を脱炭素化する方針を掲げています。火力発電については、早ければ2030年まで、遅くとも2038年までに石炭火力発電を廃止する方針を掲げるとともに、水素混焼・専焼が可能なガス火力を新設(10GW)し、2035年から2040年までには水素専焼に切り替える方針を示しています。
次世代エネルギーについては、2023年に改定した「国家水素戦略」に基づく取組を進めています。2030年における国内の水素生産能力を10GWに倍増させる目標を掲げる等、国内での水素生産能力の強化を図るとともに、国外からの輸入水素については、水素の供給側と需要側のダブルオークションにより水素輸入の支援を行うH2Globalに加え、2024年に策定した「水素輸入戦略」に基づき、水素の海外からのパイプライン輸送を含めたインフラ整備等を進めるとしています。
CCUSについては、2024年5月に閣議決定された「炭素管理戦略」とCO2貯留法改正法案に基づき、今後、CCUSの活用や、CO2の海上輸送・海底貯留を進めていくとしています。
GHG排出の規制手段として、排出量取引制度(EU-ETS)に加え、運輸部門等を対象にした独自の排出量取引制度を2021年から運用しています。
9.イタリア
(1)これまでの進捗
イタリアのGHG排出量は、2000年代後半から減少傾向にあり、2022年時点のGHG排出量削減実績は1990年比で約24%となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、運輸部門、エネルギー転換部門の順に排出量が多くなっており、これら部門の合計で、GHG排出量の約5割を占めています。エネルギー転換部門は1990年から2010年代半ばまでの間、最大の排出源でしたが、石炭火力から天然ガス火力への移行に伴う排出量の削減や再エネの増加等により、エネルギー転換部門の排出量は、運輸部門の排出量を下回っています。
最終エネルギー消費量は省エネの推進や再エネの導入等により、2000年代半ばから減少傾向に転じた後、2010年代半ばから横ばいで推移しており、2022年時点では原油換算で約1.2億kLとなっています。
イタリアの最終エネルギー消費のうち約2割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2000年代後半から増加し、2022年時点で36%となっています。再エネはFIT制度の導入等を背景として、2000年代後半から2010年代半ばまで増加し、以降は横ばいで推移しています。原子力は1987年の国民投票により原子力発電所の廃炉が決定され、1990年から発電量はゼロになっています。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
イタリアは2050年カーボンニュートラルを宣言しており、GHG排出量削減目標の実現に向けて、省エネについては、中小企業を含めた産業分野における高効率設備の導入支援、公共部門のエネルギー効率の向上、EVの導入等を進めるとしています。また、「国家エネルギー・気候計画」において、太陽光発電と風力発電の電源比率を2030年に2022年比でそれぞれ2倍以上とすることや、最終エネルギー消費における再エネの割合を2030年までに39.4%に引き上げること、などを目標として掲げています。
原子力については、前述のとおり、1990年から発電量がゼロになっていましたが、GHG排出量の削減やエネルギーコスト抑制の観点から、2024年以降、原子力再開への動きが活発化しており、2027年中に原子力再開に向けた法令等を整備することを明らかにしています。石炭火力発電については、原則として2025年までに撤廃するとの方針を掲げており、2025年以降も稼働を続けるサルディーニャ石炭火力発電所についても、2028年までに撤廃するとしています。
次世代エネルギーについては、2020年に「水素国家戦略予備ガイドライン」を策定し、水素を脱炭素化に向けて短期的にも長期的にも重要な役割を果たすものと位置づけた上で、2030年までに水素利用によって最大800万トン相当のCO2を削減することや、2030年までに最終エネルギー需要の2%を水素で賄うこと、などを目標として掲げています。
CCUSについては、「国家エネルギー・気候計画」において、カーボンニュートラル実現に向けて重要な技術と位置づけており、まずはラヴェンナにおいてプロジェクトが進められています。同プロジェクトは、天然ガス供給設備の燃焼排ガスから最大96%のCO2を回収するもので、2030年までに本プラントで回収されたCO2をパイプラインで輸送し、枯渇ガス田に圧入・貯留することで、年間400万トンの貯留を目指すとしています。
GHG排出の規制手段として、排出量取引制度(EU-ETS)に参加しています。
10.中国
(1)これまでの進捗
中国のGHG排出量は増加傾向にあり、2021年時点のGHG排出量実績は2005年比で約79%増加となっています。
GHG排出量を産業別に見ると、エネルギー転換部門、製造・建設部門の順に排出量が多くなっており、これら部門の合計で、GHG排出量の約7割を占めています。いずれの部門も排出量は増加していますが、例えばエネルギー転換部門については、増加する電力需要を賄うために、再エネ・原子力に加え、石炭火力発電の利用を拡大していること等が要因として挙げられます。
最終エネルギー消費量は2000年代以降増加傾向にあり、2022年時点では原油換算で約25億kLとなっています。
中国の最終エネルギー消費のうち約3割を電力が占めています。電力部門における非化石電源比率は2010年頃から増加しており、2022年時点で35%となっています。2007年に発表された「再生可能エネルギー中長期発展計画」(同年9月)と「原子力発電中長期発展計画」(同年11月)に基づき再エネと原子力の開発が推進されたことを背景に2010年頃から増加しており、2022年には、再エネは30%、原子力は5%となっています。また、再エネと原子力の設備容量の合計は火力発電の設備容量を上回っています。
(2)今後の目標とカーボンニュートラル実現に向けた取組
中国は2021年に発表した「第14次5か年計画」において、2060年までにカーボンニュートラルを実現する目標を掲げており、2021年に国連気候変動枠組条約事務局に提出した2030年度のNDC目標では、2030年までに単位GDP当たりのCO2排出量を2005年比で65%削減するとの削減目標を掲げるとともに、2030年までにCO2排出量がピークを迎えられるように努めるとしています。次期NDCについては、2025年3月現在、国連気候変動枠組条約事務局に提出されていません。
当該目標の実現に向けて、中国は「第14次5か年計画」において、2025年の単位GDP当たりのエネルギー消費量とCO2排出量をそれぞれ2020年比で13.5%、18.0%引き下げるという目標を掲げ、産業分野における鉄鋼等の重点業種の設備改良支援、新築建築物の省エネ基準の強化、EVの導入等の省エネを進めていくとしています。あわせて、非化石電源比率を2025年までに39%とすることや、風力と太陽光発電の合計の設備容量を2030年までに1200GW以上に拡大する等の目標を掲げており、この目標達成に向けて、化石燃料使用量の削減、再エネ・原子力の利用促進等を進めるとしています。原子力も拡大する方針を示しており、「第14次5か年計画」においては、原子力の規模を2025年までに70GWに引き上げるとしており、2024年8月時点で約58GWの規模の原子力が稼働中としています。直近では、漳州原子力発電所1号機が2024年11月に新たに稼働しています。石炭については、「第14次5か年計画」において、石炭の生産を資源が豊富な地域に集約化して効率化することや、石炭火力発電の新設を適正に管理すること、石炭を直接利用するのではなく電化に利用すること等の方針を示しており、こうした取組により、石炭の消費量を2025年以降に減少させるとしています。
近年は、中国は再エネ・蓄電池・EVを中核とする産業政策を展開し、世界シェアの拡大を図っているほか、水素・CCUSの取組も進めています。水素については、2023年時点の生産量は年間約3,600万トンと、世界の総需要の約3割を占める世界最大の水素生産国であり、2022年3月に発表した「水素エネルギー産業発展中長期計画」において、2025年までにFCVの保有を5万台、グリーン水素製造を年間10~20万トンにする等の目標を示しています。
CCUSについては、2021年に発表した「2030年までの炭素排出ピークアウトに関する行動計画」において、CCUS技術の大規模実証プロジェクトの実施等が盛り込まれており、その一環として、江蘇省泰州市の国内最大の石炭火力発電所におけるCCUSプロジェクトが2023年6月に稼働しています。
中国では、2021年に排出量取引制度が導入されています。2024年末時点の累計取引量は約6億3,000万トンであり、世界最大規模となっています。現在は発電事業だけが排出量取引制度の対象になっていますが、今後は対象業種の拡大も予定されています。なお、取引価格は、取引を開始した2021年の価格は約60元/tCO2でしたが、2024年12月時点で約100元/tCO2(約14ドル)となっています。
- 1
- 原則として、2025年3月末時点までの各国の動向について概観しています。
- 2
- 2013年度のLULUCF分野のGHG排出及び吸収も含んだ日本のGHG排出量と、2023年度のLULUCF分野を含んだ日本のGHG排出量とを比較し算出した削減率です。
- 3
- 2050年カーボンニュートラル宣言以降、閣議決定文書において「カーボンニュートラル」との用語を用いる例が多数であることから、本白書においても、原則は「カーボンニュートラル」との用語を用いています。なお、国際的な文脈では、「ネット・ゼロ」と表現することが一般的ですが、両者の基本的な意味は同じという認識の下、「カーボンニュートラル」との用語を用いています。
- 4
- CCSとは、Carbon dioxide Capture and Storageの略で、CO2の回収・貯留のことです。
- 5
- 「Inflation Reduction Act(IRA)」のことで、インフレ抑制法とも呼ばれています。
- 6
- クリーン水素とは、再エネやCCS等を使って、製造工程においてもCO2を排出しない、又は排出量を低減してつくられた水素を指します。
- 7
- CCUSとは、Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略で、CO2の回収・利用・貯留のことです。
- 8
- パリ協定の規定上、脱退は通告の1年後に効力を生じるとされることから、米国のパリ協定からの正式な脱退は2026年1月になる見込みです。他方で、同大統領令では、米国のパリ協定からの脱退は国連気候変動枠組条約事務局への通告をもって直ちに効力を生じるものと見なすとしています。
- 9
- トランプ大統領は、2025年1月20日に5つの大統領令を発令しています。そのうちの一つ、「米国のエネルギーを解き放つ」という大統領令において、気候変動・環境保護・再エネ・EVの導入などに関連する前バイデン政権下で発令された12本の大統領令を正式に撤回し、それにより設置された政府機関やプログラムも全て廃止するとしています。
- 10
- 大統領令を通じて、IRAにより支出される予定だったクリーンエネルギーや気候変動対策関連の補助金等が停止されました。しかし、この支出停止は、政府の補助金等を対象としており、EVの税額控除等は既に法的拘束力を持つ形で議会において承認されていたことから、議会の承認なしには撤廃できず、一部の支援措置が継続されている場合もあります。
- 11
- 「アラスカの並外れた資源の潜在能力を解き放つ」という大統領令において、2023年9月に前バイデン政権が北極圏の環境保護を理由に導入した開発規制を撤廃し、同州での石油・ガス開発を全面的に再開するとしています。
- 12
- 炭素国境調整措置(CBAM)とは、排出量取引制度(EU-ETS)に基づいてEU域内で生産される対象製品に課される炭素価格に対応した価格を、域外から輸入される対象製品に課す制度です。
- 13
- CfD(Contract for Difference)とは、政府が電力の落札価格と市場価格の差額を補塡する仕組みです。
- 14
- 2025年2月に「第7次カーボンバジェット」についてCCCより英国政府に提言されていますが、2025年3月末時点では議会での承認待ちとなっています。
- 15
- ドイツでは、2025年2月に行われた連邦会議選挙にて、キリスト教民主・社会同盟が第一党となっており、2025年3月末時点で、連立交渉が行われています。同党はエネルギーについて、引き続き2045年カーボンニュートラル実現を目指すものの、目標を達成するための方法については、多様なオプションの活用を維持する等の選挙公約を掲げていました。このため、今後、カーボンニュートラル実現に向けた取組に変更が生じうる点に留意が必要です。