第2節 原子力被災者支援
帰還困難区域のうち、「特定復興再生拠点区域」については、2023年11月までに6町村(葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、飯舘村)の特定復興再生拠点区域の全てにおいて、避難指示を解除しました。また、特定復興再生拠点区域外についても、2023年6月の「福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)」(以下「福島特措法」という。)の改正により、「特定帰還居住区域」を制度として創設し、その後、2024年4月までに大熊町、双葉町、浪江町、富岡町の4町における「特定帰還居住区域復興再生計画」が認定される等、段階的な避難指示の解除に向けた取組が進展しています。このように、地域によって復興の段階は様々であり、特定復興再生拠点区域等、本格的な復興が始まったばかりの地域もあります。帰還困難区域については、「たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組む」との決意の下、可能なところから着実かつ段階的に、帰還困難区域の1日も早い復興を目指して取り組んでいきます。
避難指示を解除した地域においては、事業・なりわいの再建、そして、新たな産業の創出が課題となります。こうした地域の自立的・持続的な産業発展の実現を目指し、福島イノベ構想の推進、事業者・農林漁業者の再建、風評の払拭に向けた取組等を引き続き進めるとともに、帰還促進とあわせて、新たな住民の移住・定住の促進、交流人口・関係人口の拡大等を進めていきます。さらに、2023年4月に設立された「福島国際研究教育機構」(以下「F-REI」という。)が行う研究開発を通じて、福島の復興と産業化を加速していきます。
1.避難指示区域への対応
(1)避難指示解除の状況
2013年8月までに、避難指示区域の見直しが被災11市町村の全てで完了し、避難指示区域について、「避難指示解除準備区域」(立入可・事業活動可・宿泊原則禁止)、「居住制限区域」(立入可・一部事業活動可・宿泊原則禁止)、「帰還困難区域」(原則立入禁止・宿泊禁止)が設定されました。2013年8月時点で、避難指示区域からの避難対象者数は約8.1万人でした(第112-1-1)。
【第112-1-1】避難指示区域(区域見直し完了後:2013年8月時点)
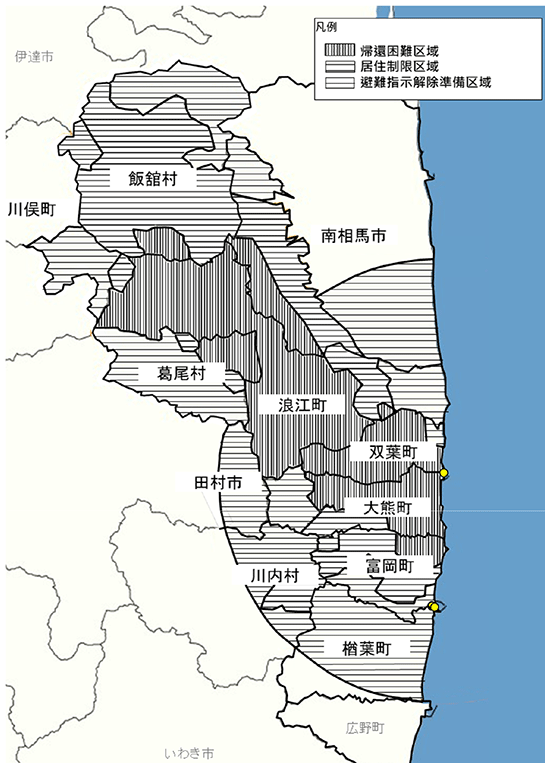
【第112-1-1】避難指示区域(区域見直し完了後:2013年8月時点)(ppt/pptx形式:417KB)
- 資料:
- 原子力被災者生活支援チーム作成
その後、2020年3月までに、帰還困難区域を除く、全ての避難指示解除準備区域と居住制限区域において、避難指示の解除を行ってきました。帰還困難区域に関しても、2023年11月までに、葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、飯舘村の6町村の全ての特定復興再生拠点区域において、避難指示を解除しました。これにより、2023年11月末時点で、避難指示区域からの避難対象者数は約8千人となっています(第112-1-2)。
【第112-1-2】避難指示区域(特定復興再生拠点区域全域の解除後:2023年11月末時点)
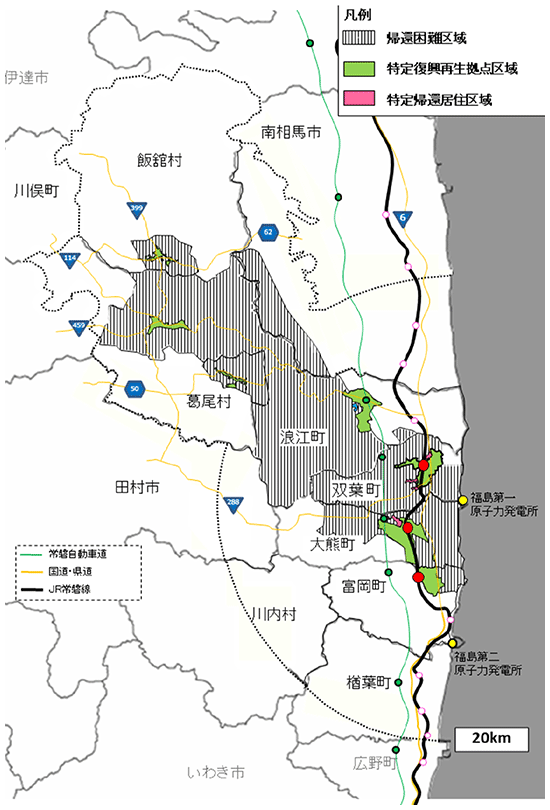
【第112-1-2】避難指示区域(特定復興再生拠点区域全域の解除後:2023年11月末時点)(ppt/pptx形式:239KB)
- 資料:
- 原子力被災者生活支援チーム作成
避難指示の解除後の本格的な復興のステージにおいても、政府一丸となって、市町村ごとの課題にきめ細かく対応するとともに、国・県・市町村が連携しながら、産業の再生や雇用の創出、インフラ・生活環境の整備、避難者の生活再建支援10等、当該区域の復興及び再生をさらに進めていきます。
(2)帰還に向けた安全・安心対策
政府では、2016年12月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」において、以下のような総合的・重層的な防護措置を講じることとしています。
- 住民の方々の放射線不安に対するきめ細かな対応
- 避難生活の長期化等や放射線による健康不安への適切な対応
- 関係省庁におけるリスクコミュニケーションの取組の強化
- 生活支援相談員について、帰還後も支援を継続できるよう支援対象の明確化や関係省庁との連携促進
こうした取組を通じ、住民の方々が帰還し、生活する中で、個人が受ける追加被ばく線量を、長期目標として、年間1ミリシーベルト以下にすることを引き続き目指していくこととしています。また、線量水準に関する国際的・科学的な考え方を踏まえた日本の対応について、国内外で継続的に実施されている放射線影響に関する最新の研究の状況も踏まえつつ、住民の方々に丁寧に説明を行い、正確な理解の浸透に努めています。
2.帰還困難区域への対応
避難指示区域のうち「帰還困難区域」については、2011年12月に、警戒区域と計画的避難区域の見直しを行った際、「将来にわたって居住を制限することを原則とした区域」として設定されました。一方、事故から5年が経過した2016年8月、一部では放射線量が低下していることや地元の強い要望を踏まえ、原子力災害対策本部・復興推進会議において、「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」を決定し、帰還困難区域のうち、5年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「特定復興再生拠点」の整備等について、基本的な考え方を示しました。
こうした中、2017年9月以降、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村における「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を、内閣総理大臣が認定しました。また、2018年11月までに全ての特定復興再生拠点の整備が開始され、国と自治体が連携して、これらの計画に基づく事業を進めてきました。2020年3月には、JR常磐線の全線開通にあわせて、双葉町、大熊町、富岡町の帰還困難区域に設定されている特定復興再生拠点区域の一部(JR常磐線の3駅周辺)について、初めて避難指示を解除しました。その後、2022年6月12日には、葛尾村の特定復興再生拠点区域の避難指示を解除し、帰還困難区域において初めて住民の帰還が可能となりました。同月30日には大熊町、同年8月には双葉町、2023年3月には浪江町、同年4月には富岡町、同年5月には飯舘村の特定復興再生拠点区域の避難指示もそれぞれ解除しました。加えて、同年11月30日には、富岡町の特定復興再生拠点区域のうち、残っていた区域の避難指示も解除し、これにより、6町村の特定復興再生拠点区域の全てにおいて、避難指示の解除を完了しました。引き続き、福島県や市町村の意向を踏まえながら、関係省庁と緊密に連携して、特定復興再生拠点区域の帰還環境の整備に全力で取り組んでいきます。
また、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域外については、2021年8月に原子力災害対策本部・復興推進会議で決定した「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」に基づき、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還に関する意向を個別に丁寧に把握した上で、帰還に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取組を進めていくこととしています。この方針を実現するため、特定復興再生拠点区域外に帰還する住民の生活の再建を目指すための「特定帰還居住区域」を創設する規定を含む、「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第49号)」が、2023年6月に公布・施行されました。第1回目の帰還意向の確認を踏まえ、2024年4月までに、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町の4町における「特定帰還居住区域復興再生計画」を、内閣総理大臣が認定しました。今後、これらの計画に基づき、除染・インフラ整備等をはじめとした避難指示解除に向けた取組を進めていくとともに、「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」に基づき、引き続き、帰還意向の確認を実施していきます。残された土地・家屋等の扱いについては、地元自治体と協議を重ねつつ、引き続き検討を進めていきます。また、2020年12月の原子力災害対策本部では、特定復興再生拠点区域外の居住を前提としない土地活用による避難指示解除に関する仕組みを決定しました。これに基づき、2023年5月には、飯舘村の特定復興再生拠点区域外の一部について、公園用地として避難指示が解除され、本仕組みを活用した初めての避難指示解除となりました。引き続き、国は、この仕組みについて、各自治体の意向を十分に尊重し、運用していきます。
また、同年8月に原子力災害対策本部で決定した「特定帰還居住区域における放射線防護対策」も踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な放射線防護対策や、科学的根拠に基づくリスクコミュニケーションに取り組むとともに、空間線量率等、それぞれの土地の状況や地元自治体の意向も踏まえ、帰還困難区域においてバリケード等の物理的な防護措置を実施しない立入規制の緩和を行うことを含め、住民等の今後の活動のあり方について検討を行っていきます。
3.環境汚染への対処
東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが、喫緊の課題となりました。こうした状況を踏まえ、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)」が可決・成立し、2011年8月に公布されました。
この法律は、除染の対象として「除染特別地域」と「汚染状況重点調査地域」を定めています。除染特別地域とは、警戒区域又は計画的避難区域の指定を受けたことがある地域のことで、国が除染実施計画を策定し、除染事業を進めてきました。他方、汚染状況重点調査地域は、地域の空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域がある市町村について、あらかじめ関係地方公共団体の長の意見を聴いた上で国が指定した地域のことで、各市町村等が除染を行ってきました。その後、帰還困難区域を除く除染特別地域については2017年3月に、汚染状況重点調査地域については2018年3月に、除染実施計画に基づく面的除染がそれぞれ完了しました。
福島特措法に基づき、立入が厳しく制限されてきた帰還困難区域については、2017年5月に福島特措法が改正され、帰還困難区域内に「特定復興再生拠点区域」を設定し、除染や避難指示解除を進められる制度が整えられました。その後、特定復興再生拠点区域における除染は概ね完了し、2023年11月までに、6町村(葛尾村、大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、飯舘村)全ての特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。
さらに、2023年6月に福島特措法が改正され、特定復興再生拠点区域外において、住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度が創設されました。同年9月には、大熊町及び双葉町が先行的に一部の区域を特定帰還居住区域に設定し、これを受け、同年12月より除染を開始しました。さらに、2024年2月までに、浪江町及び富岡町が特定帰還居住区域を設定するとともに、同年2月に大熊町、同年4月に双葉町が特定帰還居住区域を変更しており、これらの区域における早期の除染開始に向けた準備を進めています。
また、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む除去土壌等や、福島県内に保管されている1kg当たり10万ベクレルを超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全かつ集中的に管理・保管する施設として、中間貯蔵施設を整備しています。中間貯蔵施設事業の実施に当たっては、2021年3月に閣議決定された「『第2期復興・創生期間11』以降における東日本大震災からの復興の基本方針12」及び2024年3月に公表した「令和6年度の中間貯蔵施設事業の方針」に沿って、特定帰還居住区域等で発生した除去土壌等の搬入や、中間貯蔵施設内の各施設の維持管理等、安全を第一に、地域の理解を得ながら事業を実施していきます。なお、中間貯蔵施設の整備に必要な用地全体の面積は約1,600haを予定しており、2024年3月末までの契約済面積は約1,301ha(全体の約81.3%。そのうち民有地は、全体面積約1,270haに対し、約95.0%に当たる約1,207haについて契約済)となっており、計1,883人(全体2,360人に対し約79.8%)の方と契約に至っています。
中間貯蔵施設については、2016年11月から受入・分別施設と土壌貯蔵施設等を整備しました。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌を受け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された土壌を、放射能濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。
中間貯蔵施設への除去土壌等(帰還困難区域を含む)の輸送については、2024年3月末までに、累計で約1,376万㎥の輸送を実施しました。また、より安全で円滑な輸送のため、運転者研修等の交通安全対策や必要な道路補修等に加えて、輸送出発時間の調整等、特定の時期・時間帯への車両の集中防止・平準化を実施しました。
除去土壌等の最終処分については、「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)」において、中間貯蔵に関する国の責務として、福島県内除去土壌の中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることが規定されています。県外最終処分の実現に向けては、2016年4月にとりまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って取組を進めています。
これらに沿って、飯舘村長泥地区における実証事業について、順次栽培試験等を実施し、2020年度、2021年度に栽培した作物の放射能濃度は一般食品の基準値を大きく下回りました。農地造成については、2021年4月に着手した除去土壌を用いた盛土が、2022年度末までに概ね完了しました。2023年度は、水田試験等を実施し、水田等に求められる機能を概ね満たすことを確認しました。これまでに実証事業で得られたモニタリング結果からは、施工前後の空間線量率に変化がないこと、農地造成エリアからの浸透水の放射性セシウム濃度は概ね検出下限値(1Bq/L)未満であること等の知見が得られています。また、道路整備での再生利用について検討するため、2022年10月に着工した中間貯蔵施設内における道路盛土の実証事業については、2023年10月に工事を完了しました。モニタリング結果からは、施工前後の空間線量率に変化がないこと、作業者の追加被ばく線量が1ミリシーベルト/年以下であること等の知見が得られています。こうした知見から、再生利用を安全に実施できることを確認しています。
減容等技術の開発に関しては、2023年度も、大熊町の中間貯蔵施設内に整備している技術実証フィールドにおいて、中間貯蔵施設内の除去土壌等も活用した技術実証を行いました。また、2023年度は、双葉町の中間貯蔵施設内において、2022年度に引き続き、仮設灰処理施設で生じる飛灰の洗浄技術・安定化に係る基盤技術の実証試験を実施しています。
また、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向け、減容・再生利用の必要性・安全性等に関する全国での理解醸成活動の取組の1つとして、2021年度から全国各地で開催してきた対話フォーラムについて、第9回を東京都内で2023年8月に開催しました。さらに、2023年度も引き続き、一般の方向けに飯舘村長泥地区の実証事業や中間貯蔵施設の現地見学会を開催しています。このほか、大学生等への環境再生事業に関する講義、現地見学会等を実施する等、次世代に対する理解醸成活動も実施しました。
また、中間貯蔵施設に搬入して分別した土壌の表面を土で覆い、観葉植物を植えた鉢植えについて、2020年3月以降、総理官邸、環境大臣室、新宿御苑等の環境省関連施設や関係省庁等に設置しています。鉢植えを設置した前後の空間線量率はいずれも変化はなく、設置以降1週間〜1か月に1回実施している放射線のモニタリングでも、鉢植えの設置前後の空間線量率に変化は見られていません。
4.原子力災害の被災事業者等のための自立支援策、風評被害対策
住民の方々が帰還して故郷での生活を再開するためには、また、外部から新たな住民を呼び込むためには、働く場所、買い物をする場所、医療・介護施設、行政サービス機能といった、まちとして備えるべき機能が整備されている必要があります。避難指示が解除された多くの市町村内において、学校の再開や第二次救急医療機関の開院、消防署の再開等、生活環境の整備は進展していますが、まちの様々な機能を担っていた事業者の多くは、住民の避難に伴う顧客の減少、長期にわたる事業休止に伴う取引先や従業員の喪失、風評被害による売上減少といった苦難に直面しており、こうした状況を克服するためには、生活、産業、行政の三位一体となった政策を進めていく必要があります。
こうした状況を踏まえ、2015年8月に、国、福島県、民間(福島相双復興推進機構)からなる福島相双復興官民合同チーム(以下「官民合同チーム」という。)が創設されました。その主な活動内容は、避難指示等の対象となった12市町村の被災事業者を個別に訪問し、事業再開等に関する要望や意向を把握するとともに、その結果を踏まえ、事業再建計画の策定支援、支援策の紹介、生活再建への支援等を実施していくことです。国、県、民間が一体となって腰を据えた支援を行うため、2017年5月に福島特措法を改正し、福島相双復興推進機構へ国の職員の派遣を可能とする等の措置を盛り込み、同年7月から、経済産業省及び農林水産省の職員を派遣する等、体制強化を図りました。
官民合同チームは総勢261名の体制(2024年4月1日時点)で、福島県内(福島市、いわき市、南相馬市等)と東京都内の計6か所を拠点に、個別訪問等を実施しています(第112-4-1)。商工業分野においては、チーム発足翌日から事業者訪問を開始しました。2024年3月末時点で、これまでに約5,800者に訪問し、そのうち約1,600の事業者に対して専門家によるコンサルティングを実施する等、被災事業者の自立に向けた支援に取り組んでいます。農業分野についても、2016年7月から国と県による認定農業者約500者への個別訪問を実施した後、2017年4月からは、官民合同チームによる認定農業者以外の農業者への個別訪問を開始しており、2024年3月末時点で、これまでに約2,700者への訪問を実施しています。また、速やかな営農再開に向けて、官民合同チームが被災市町村等を訪問し、集落座談会において営農再開支援策の説明等を行うとともに、地域農業の将来像の策定やその実現に向けた農業者の取組を支援しています。今後も、官民合同チームによる個別訪問等を通じて課題を把握し、支援の充実を図っていきます。
【第112-4-1】福島相双復興推進機構(官民合同チーム)の概要
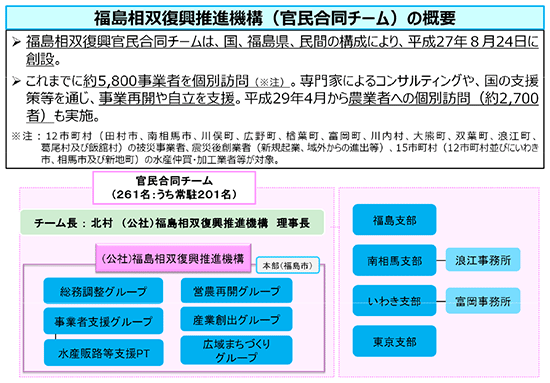
【第112-4-1】福島相双復興推進機構(官民合同チーム)の概要(ppt/pptx形式:124KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
2017年9月以降は、分野横断・広域的な観点から、商業施設やまちづくり会社の創設・運営、企業誘致に係る戦略策定等、12市町村のまちづくり専門家支援も進めているほか、交流人口の拡大に向けた情報発信支援や、外部からの人材の呼び込み・創業支援の取組を進めています。さらに、2021年6月からは、新たに浜通り地域等の15市町村の水産関係の仲買・加工業者等への個別訪問を開始しています。2024年3月末時点で、これまでに101者に訪問し、そのうち61の事業者に対し、販路開拓や人材確保等の支援を実施しています。
事業・なりわいの再建は徐々に進みつつありますが、地域によって復興の状況は異なります。今後も官民合同チームは、被災事業者の帰還、事業・なりわいの再建を進め、まちの復興を後押しすべく、個々の実情を踏まえたきめ細かな対応を粘り強く続けていきます。
このように、事業者の方々による取組やまちの復興をサポートする体制が整いつつある一方で、事故発生後いまだに継続している風評被害の存在は、農林水産業をはじめ、福島の産業・なりわいの復興の大きな妨げとなっています。放射線に関する正しい知識や福島の復興の現状、農林水産物等の県産品の安全性や質の高さ等を国内外に正しく発信し、風評を払拭していくことが大きな課題です。各種の国際会議等を含めて、あらゆる機会を活用し、風評対策を強力に推進していきます。特に農林水産物については、生産段階における第三者認証取得や安全性検査への支援、流通・販売段階における販路開拓への支援等、あらゆる段階で風評払拭に必要な支援を行うことにより、安全性についての消費者の正しい理解を促進し、県産品のブランド力の回復を後押ししていきます。
こうした取組をより実効的なものとしていくために、福島特措法に基づき、2017年度から毎年度、流通段階における販売不振の実態や要因の調査を行い、その結果に基づき、復興庁・農林水産省・経済産業省の連名で、小売業者等への指導や生産者への助言等に関する通知を発出する等の対応を行っています。また、国、福島県、農業関係団体等が参画する「福島県産農林水産物の風評払拭対策協議会」により、風評被害の実態や施策の効果を継続的に検証する体制を構築しています。
さらに、テレビやインターネット、SNS、ラジオ等、あらゆる媒体を活用した正確でわかりやすい効果的な情報発信や、在京大使館への働きかけ及び海外メディアによる被災地の訪問取材等を進めており、日本産食品への輸入規制措置を講じた55か国・地域のうち、48か国・地域が輸入規制措置を撤廃しています(2024年3月末時点)。関係府省庁からなる「原子力災害による風評被害を含む影響への対策タスクフォース」の開催や「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」(2017年12月策定)により、風評払拭に向けて関係府省庁が連携し、政府一丸となって情報発信等に取り組んでいます。
5.福島イノベーション・コースト構想
福島イノベ構想は、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会13の開催時に、世界中の人々が、浜通りの力強い再生の姿に瞠目する地域再生を目指して検討が始まり、特に、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業・雇用を回復するため、当該地域の新たな産業基盤の構築を目指して、2014年6月に、福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会において、とりまとめられました。
福島イノベ構想の実現に向けて、多岐にわたる課題を政府全体で解決していくため、2017年5月には福島特措法を改正し、同法に福島イノベ構想を位置づけました。2018年4月には、この改正法に基づき福島県が策定した「重点推進計画」について、内閣総理大臣の認定を行うとともに、同日に開催した第2回福島イノベーション・コースト構想関係閣僚会議において、「福島イノベーション・コースト構想の今後の方向性」を一部改正しました。また、復興・創生期間後も見据えた浜通り地域等の自立的・持続的な産業発展の姿と具体的な取組を示すため、2019年12月に、「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」を復興庁・経済産業省・福島県の3者で策定し、2020年5月には、この青写真を踏まえた重点推進計画の改定について、内閣総理大臣の認定を行いました。また、重点推進計画が統合された「福島復興再生計画」については、2021年4月に内閣総理大臣の認定を行いました。
加えて、2017年7月には、福島県が、福島イノベ構想を推進する中核的な組織として、一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構を設立しました。同機構は、2018年4月より体制を順次強化し、2019年1月には公益財団法人に移行しました。また、2020年6月に公布・一部施行された「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)」には、国職員をその身分を保有したまま、同機構に派遣することができる措置を盛り込み、2020年度から順次、国職員を同機構に派遣し、さらなる体制強化を図っています。
2023年11月には、約4年ぶりとなる第4回福島イノベーション・コースト構想推進分科会を開催し、これまでの福島イノベ構想の成果や進捗、今後の課題等を、国(経済産業省・復興庁)、福島県、15市町村で共有するとともに、福島イノベ構想のさらなる発展に向けた見直しの検討を開始することに合意しました。
また、廃炉やロボット等の分野における技術開発・拠点整備等のプロジェクトについては、現在着々と具体化が進められています。例えば、2020年3月に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」は、物流、インフラ点検、災害対応で活躍するロボット・ドローンの研究開発、実証試験、性能評価が1つの場所で実施可能な、世界に類を見ない研究開発拠点です。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や内閣府の研究開発プロジェクトにおいて活用されているだけでなく、民間企業の利用も進んでおり、「空飛ぶクルマ」の試験飛行の場所としても活用されています。また、2020年9月の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の見直しにより、福島ロボットテストフィールドにおける研究開発目的のドローンの飛行のための手続が容易となった事例のように、関係省庁等とも連携して、福島ロボットテストフィールドの有する設備や環境を活かし、拠点としての優位性をさらに高めていきます。なお、2021年10月には、世界中のロボット関係者が一堂に集まり、ロボットの社会実装と研究開発を加速させることを目的とした競演会「World Robot Summit 2020」の一部の競技を福島ロボットテストフィールドで開催し、地元企業連合チームが災害対応の部門で準優勝を飾る等、その技術力の高さを証明しました。さらに、福島県は、「福島浜通りロボット実証区域」として、各市町村や関係機関等と事業者等の仲介を行い、ロボットやドローンの実証試験や操縦訓練の場を提供しており、2023年8月にはドローン等の広域飛行試験ルートの整備に向けた約50kmの長距離飛行を実施する等、2024年3月末時点で1,337件の実証試験が実施されています。
廃炉関連分野では、2016年4月から、楢葉町において、遠隔操作機器・装置の開発・実証施設である「楢葉遠隔技術開発センター」の本格的な運用が開始されています。また、2017年4月には、富岡町で、廃炉に向けて国内外の英知を結集する拠点である「廃炉国際共同研究センター(現:廃炉環境国際共同研究センター)国際共同研究棟」の運用が開始されました。さらに、2018年3月には、大熊町において、放射性物質分析・研究施設である「大熊分析・研究センター」の施設管理棟の運用が開始され、2022年6月からは中・低線量の廃棄物試料を分析する第1棟の運用も開始されました。人材育成については、2018年10月に、廃炉事業に必要な技術者を養成する目的で、放射線防護教育等の基礎・基盤的な技能を身につけるための研修施設として、東京電力福島第一原子力発電所内に、「福島廃炉技術者研修センター」が設置されました。
原子力災害を中心とした複合災害の記録と記憶を後世に継承し、世界と共有する「東日本大震災・原子力災害伝承館」については、2020年9月に、双葉町において開館しましたが、その後、2023年3月末までに、来館人数が計18万人を超えました。通常展示に加え、「地図と写真でみる東日本大震災」 企画展等を開催し、また、東京において所蔵資料を出張展示する特別展も開催しました。
さらに、災害及び復興に向けた取組の実態や、福島が抱える課題(風評・風化・リスクコミュニケーション等)に関する調査研究事業が本格的に開始されています。環境・リサイクル分野では、2015年以降、福島県が環境・リサイクル産業の集積を図るために立ち上げた「ふくしまエネルギー・環境・リサイクル関連産業研究会14」の会員によって、太陽光パネル、バイオマス系廃棄物、二次電池、風力発電設備のリサイクル等のテーマについて、事業化に向けた検討が進められています。エネルギー分野では、福島イノベ構想の取組を加速し、その成果も活用しつつ、福島県全体を未来の新エネ社会を先取りするモデル創出拠点とする「福島新エネ社会構想」を推進しています(福島新エネ社会構想については次節参照)。
福島イノベ構想の推進に向けた道筋は、拠点の整備や主要プロジェクトの具体化に留まりません。これらの拠点やプロジェクト等も活用しながら、地元企業と浜通り地域の外から進出してくる企業とが一体となって、重点分野における実用化技術開発を進めていくことが必要であり、民間企業が主体となって行う実用化開発等を支援しています。2021年度からは、浜通り地域等の自治体と連携して実施する実用化開発等を重点的に支援する制度を開始しました。また、2023年度からは、スタートアップ企業への優遇措置(スタートアップ企業への加点措置及び大企業の補助率引き下げ)を新設し、浜通り地域ならではの地形を活かした実証フィールドの整備を実施しています。さらに、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金においては、2021年度から、福島イノベ構想の重点分野の補助率を引き上げる制度改正も行いました。加えて、福島イノベーション・コースト構想推進機構が福島相双復興推進機構とも連携しながら、地元企業と進出企業の連携による新たなビジネス機会の創出に向けたビジネスマッチングの取組等を実施しています。2020年度からは、浜通り地域等で起業・創業を目指す企業や個人等に対して、専門家による伴走支援等を行う「Fukushima Tech Create」事業も実施しています。さらには、拠点の強みを活かした交流人口の拡大や、生活環境の整備、高等教育機関等における研究活動の促進、初等中等教育機関と大学、企業等とが連携した福島イノベ構想を支える人材の育成等を推進しています。
また、2022年5月には、「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第54号)」が成立しました。この福島特措法の改正に基づき、福島イノベ構想をさらに発展させ、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとするとともに、その活動を通じて、日本の科学技術力の強化を牽引し、イノベーションの創出によって産業構造を変革させることを通じて、日本の産業競争力を世界最高の水準に引き上げ、経済成長や国民生活の向上に貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指すF-REIを、2023年4月に設立しました。F-REIでは、福島の優位性を発揮できる①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、④放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用、⑤原子力災害に関するデータや知見の集積・発信の5分野を基本とした研究開発(例えば、エネルギー分野では、カーボンニュートラル15社会の実現に向けたネガティブエミッションのコア技術やバイオ統合型グリーンケミカル技術の実証、水素エネルギーネットワークの構築等)を推進するとともに、その研究開発成果の産業化や、これを担う人材の育成・確保にも取り組んでいます。また、研究開発の特性に応じて、実証フィールド等の活用や県内外の様々な主体との連携を適切に行い、F-REI設置の効果が広域的に波及するよう取組を進めています。
- 10
- 2018年7月、避難指示区域等における被災者の生活再建に向けた関係府省庁会議(第3回)において、「避難指示区域等における被災者の生活再建に向けた対応強化策」をとりまとめました。
- 11
- 2011年7月に、政府は「東日本大震災からの復興の基本方針」を策定(2011年7月29日 東日本大震災復興対策本部決定)し、復興期間を2020年度までの10年間と定めました。2015年6月には「平成28年度以降の復旧・復興事業について」を策定(2015年6月24日 復興推進会議決定)し、復興期間の後期5か年である2016年度から2020年度までを「復興・創生期間」と位置づけました。さらにその後、2020年7月には「令和3年度以降の復興の取組について」を策定(2020年7月17日 復興推進会議決定)し、2021年度から2025年度までの5年間を、新たな復興期間として「第2期復興・創生期間」と位置づけました。
- 12
- 「『第2期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の基本方針」は、2024年3月に改定されています。
- 13
- 2020年3月30日に、東京オリンピック競技大会は2021年7月23日から同年8月8日に、東京パラリンピック競技大会は同年8月24日から同年9月5日に開催されることが決定され、それぞれ同日程で開催されました。
- 14
- 2015年8月の立ち上げ当時の名称は「ふくしま環境・リサイクル関連産業研究会」でしたが、2022年11月に「ふくしまエネルギー・環境・リサイクル関連産業研究会」に改称されました。
- 15
- 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする(排出量から吸収量を差し引いた合計を実質的にゼロにする)ことを指します。