第6節 バックエンドプロセス加速化に向けた取組
1.核燃料サイクルの推進に向けた取組
「第7次エネルギー基本計画」でも示されているとおり、日本では、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としています。
<具体的な主要施策>
(1)六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場の竣工に向けた取組
2024年8月に、六ヶ所再処理工場は2026年度中、MOX燃料工場は2027年度中に、それぞれ竣工目標が見直されました。これらの工場の竣工に向け、審査対応の進捗管理や必要な人材確保などを行うべく、使用済燃料対策推進協議会の幹事会で議論するなど、官民一体で取り組んでいます。
(2)プルトニウムバランスの確保に向けた取組
2018年7月に、原子力委員会は「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」を公表し、「利用目的のないプルトニウムは持たない」という原則を堅持することや、プルトニウム保有量を減少させることといった方針を示しています。
その上で、電気事業連合会は、2020年12月に「新たなプルサーマル計画について」を公表し、地元理解を前提に、稼働する全ての原子炉を対象にプルサーマルの導入に向けた検討を進め、2030年度までに少なくとも12基の原子炉でプルサーマルの実施を目指す方針を示しています。また、電気事業連合会は、2025年2月に新たな「プルトニウム利用計画」を策定し、引き続き、プルサーマルの推進に取り組む方針です。
国は、再処理等拠出金法の枠組みに基づき、使用済燃料の再処理等の実施主体であるNuROが策定する使用済燃料再処理等実施中期計画について、経済産業大臣が原子力委員会の意見を聴取した上で同計画を認可することで、プルトニウムの利用と回収のバランスの確保を図っています。また、国は、プルサーマルを推進する自治体向けの支援策として、2023年6月に「プルサーマル交付金」を創設しており、プルサーマル推進に取り組んでいます。
(3)使用済燃料対策
安定的かつ継続的に原子力発電を利用する上で、使用済燃料の貯蔵能力の拡大は重要な政策課題です。2015年10月の最終処分関係閣僚会議で策定された「使用済燃料対策に関するアクションプラン」に基づき、原子力事業者は「使用済燃料対策推進計画」を策定(2015年11月策定、2025年2月改訂)し、2020年代半ばには計4,000トン程度、2030年頃には計6,000トン程度の使用済燃料の貯蔵容量の確保を目指しています。
①使用済燃料の貯蔵能力拡大に向けた取組
2024年11月にリサイクル燃料貯蔵株式会社のむつ中間貯蔵施設が事業を開始しました。また、同年12月には、玄海原子力発電所3号機で、使用済燃料プールの貯蔵能力変更工事が完了し、運用を開始するなど、使用済燃料の貯蔵能力拡大に向けた取組が進展しています。
②使用済MOX燃料の再処理に向けた取組
「第7次エネルギー基本計画」では、使用済MOX燃料の再処理について、「国際連携による実証研究を含め、2030年代後半を目途に技術を確立するべく研究開発を進めるとともに、その成果を六ヶ所再処理工場に適用する場合を想定し、許認可の取得や実運用の検討に必要なデータの充実化を進める」とされており、事業者も2023年以降、フランスで、使用済MOX燃料に関する再処理実証研究の実施に向けた取組を進めています。
③放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究委託事業
【2024年度当初:12億円】
MOX燃料を含む様々な種類の使用済燃料の再処理により発生する放射性廃液を安定的かつ効率的にガラス固化する技術を確立することを目指し、ガラス原料の基礎特性の評価やガラス溶融炉のモニタリング技術の開発等を実施しました。さらに、使用済MOX燃料を安全かつ安定的に処理するため、施設の安全性や処理性能の向上を図るための基盤技術の開発にも取り組んでいます。
(4)立地地域との共生に向けた取組
2024年10月に「青森県・立地地域等と原子力施設共生の将来像に関する共創会議」を開催し、立地地域等の将来像とその実現に向けた取組等について「工程表」を取りまとめました。また、六ヶ所再処理工場の竣工目標の見直しを受け、2024年12月に「核燃料サイクル協議会」を開催し、同工場の竣工に官民一体で取り組むこと等、核燃料サイクルの推進について確認しました。
(5)核燃料サイクル政策の理解促進に向けた取組
「第7次エネルギー基本計画」で示されているとおり、日本の原子力利用は、原子力立地地域の関係者の理解と協力に支えられており、立地地域との共生に向けた取組が必要不可欠です。そのため、核燃料サイクル政策の理解促進を図るべく、原子力を含むエネルギー政策、核燃料サイクルの意義や仕組み、核燃料サイクル関連施設の現状や安全対策等、科学的根拠や客観的事実に基づく情報提供を行いました。
(6)高速炉サイクル技術の研究開発
【2024年度当初:261億円】
高速炉サイクル技術の研究開発として、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減に資するため、マイナーアクチノイドの分離技術やマイナーアクチノイド含有燃料製造技術等の基盤的な研究開発に取り組みました。また、これまでの高速増殖原型炉もんじゅの研究開発から得られた知見をいかし、多国間協力や二国間協力による国際協力を進め、シビアアクシデント発生時の高速炉の安全性向上に向けた研究開発等に取り組みました。
2.廃炉の円滑化に向けた取組
日本では、2025年3月時点で、計24基の商業用原子炉が廃止措置中となっており、廃炉の安全かつ円滑な実施が重要な課題となっています。
2023年5月に成立したGX脱炭素電源法により、再処理等拠出金法が改正され、NuROが、全国の廃炉のマネジメント等の廃炉推進業務を行うこととなりました。加えて、同改正により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため、実用発電用原子炉設置者等に対し、廃炉拠出金をNuROに納付することを義務づけることとしました。NuROは、政府の指導・監督のもと、廃炉の円滑化や効率化に向けて、今後取組の充実化を進めることとなります。
また、廃炉等に伴って生じる廃棄物の処分については、低レベル放射性廃棄物の処分場確保を含めた処理・処分を、発生者責任の原則の下、原子力事業者等が着実に進めることを基本としつつ、国として、その円滑な実現に向けた戦略を検討し、必要なサポートや指導を行います。特に、クリアランス物については、廃止措置の円滑化及び資源の有効活用の観点から、フリーリリースに向けたロードマップを策定するとともに、電炉メーカー等の協力も得ながら、より需要規模の大きい建材加工に取り組み、更なる再利用先の拡大を進め、早期のフリーリリースを実現します。加えて、クリアランス物の検認の効率化に向けて、集中処理事業等の取組の支援を行い、関係者と連携して進めていきます。
<具体的な主要施策>
(1)低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発委託費
【2024年度当初:1.8億円】
原子力発電所の解体に伴って発生する低レベル放射性廃棄物のうち、放射能レベルが比較的高い廃棄物を対象とする中深度処分(地下70m以上の深さで実施)に関して、大規模な坑道や地下空洞型処分施設等を建設する上で必要な、岩盤にかかる圧力(地圧)の三次元的な分布を把握するための技術開発を継続しました。
(2)クリアランス金属資源循環促進事業
【2024年度補正:5.1億円】
原子力発電所の廃止措置等に伴い発生する金属のうち、通常のスクラップ金属と同様に取り扱うことができるクリアランス金属が今後、年間1万トン程度発生する見込みです。また、スクラップ金属は有効に活用することで鉄鋼業の脱炭素化に貢献することができ、クリアランス金属の有効活用は重要な課題です。こうした状況に鑑み、クリアランス金属を適切な管理の下で集中的に処理することにより、国内資源としての再利用を効率的に実現し、資源の有効活用及び関連産業の創出等につなげることを目的に、クリアランス金属を効率的に処理するための集中処理事業に関する施設・設備の詳細設計等の費用に対して補助を行いました。
3.最終処分の実現に向けた取組
過去半世紀以上にわたって原子力を利用し、使用済燃料が既に存在している以上、高レベル放射性廃棄物等の最終処分は、必ず解決しなければならない国家的課題です。
日本では、原子力発電で使い終えた燃料を再処理してウランやプルトニウムを取り出し、再び燃料として使うこととしています。そして、この過程で残った廃液をガラス固化したもの(ガラス固化体)及び再処理の過程で発生するTRU廃棄物の一部については、人間の生活環境から長期間にわたって隔離するために、地下深くの安定した岩盤中に処分する「地層処分」をすることにしています(第246-3-1)。
【第246-3-1】高レベル放射性廃棄物の地層処分
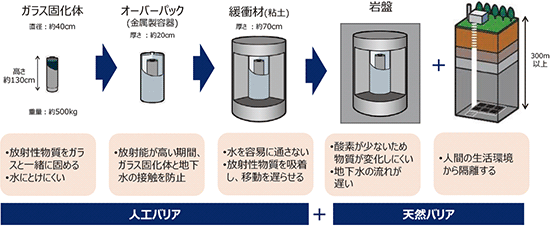
【第246-3-1】高レベル放射性廃棄物の地層処分(pptx形式:188KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
2020年11月に、北海道の寿都町及び神恵内村において文献調査を開始し、2024年11月に文献調査報告書を取りまとめ、報告書の公告、縦覧、説明会などの法定の理解プロセスを開始しました。法定の理解プロセスに合わせて、最終処分事業の必要性や北海道の状況について、全国的な対話活動やメディア広報を強化しました。また、2024年6月には、佐賀県玄海町において、文献調査を開始しました。引き続き、1つでも多くの地域に最終処分事業に関心を持っていただけるよう、政府一丸となって、かつ、政府の責任で取り組んでいきます。
具体的な主要施策>
(1)北海道寿都町及び神恵内村における文献調査プロセスの丁寧かつ着実な実施
北海道寿都町及び神恵内村での文献調査について、2024年11月に文献調査報告書を取りまとめ、報告書の公告、縦覧、説明会などの法定の理解プロセスを開始しました。また、法定の理解プロセスに合わせて、最終処分事業の必要性や北海道の状況について、全国的な対話活動やメディア広報を強化しました。引き続き、地域の皆様、全国の皆様にご理解いただけるよう、丁寧に取り組んでいきます。
(2)最終処分事業の理解促進に向けた取組等
多くの方々に最終処分事業への理解を深めていただくため、全国各地での対話型全国説明会の開催、自治体向けの説明会の開催等の対話活動に取り組んでいます。
また、国・NUMO・事業者による合同チームを地域ブロックごとに新設し、2023年7月から全国の自治体を個別訪問する全国行脚を開始しました。その後、2025年3月末時点で計203市町村を訪問しました。
加えて、地層処分事業が長期にわたる事業であることを踏まえ、次世代層の関心喚起のための広報活動を実施しました。具体的には、大学生が主体となって同世代への理解促進を図る「ミライブプロジェクト」、次世代層を対象にしたシンポジウム「大切なエネルギーと紡ぐ私たちの未来~どこかの誰かだけの問題じゃない地層処分~」を実施しました。
(3)研究開発及び調査に関する取組
1999年に核燃料サイクル開発機構(現在の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA))が公表した「地層処分研究開発第2次取りまとめ」では、日本の地質環境における地層処分の技術的な成立性及び信頼性が示されました。その後も、地層処分事業の技術的信頼性の更なる向上を図るための技術開発を行っています。NUMOでは、地層処分研究開発調整会議が2023年3月に策定した「地層処分研究開発に関する全体計画(令和5年度~令和9年度)」で示された研究開発項目を踏まえ、文献調査の着実な実施、地層処分技術の継続的な信頼性向上等を目的とした技術開発を進めています。
また、資源エネルギー庁では、「地層処分研究開発に関する全体計画(令和5年度~令和9年度)」に基づき、地下数十kmのマグマの分布を把握するための技術開発や、処分場閉鎖後に坑道が水みちにならないように埋め戻すための技術開発、廃棄体の回収可能性を確保するための技術開発、廃棄体-人工バリア-岩盤-生活圏土壌における核種移行の現象理解に関する技術開発等を2024年度に実施しました。
①高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託費
【2024年度当初:37億円】
高レベル放射性廃棄物等の地層処分技術の信頼性のより一層の向上を目指すため、火山や断層、地震等の自然事象の影響を評価する技術、沿岸部の地質環境調査や設計手法に関する技術、処分施設の施工・操業に関する技術、人工バリアの長期的な挙動や放射性核種の移行を評価する技術、直接処分等の代替処分オプション技術に関する研究開発を実施しました。
②放射性廃棄物共通技術調査等委託費
【2024年度当初:2.3億円】
放射性廃棄物の処分については、諸外国においても、処分地の選定や処分方法の検討等、日本と共通する課題を抱えていることから、それぞれの国で行われている調査・分析・研究開発等の内容や動向を調査しました。また、放射性廃棄物の処分に関する研究者・技術者の人材確保・育成の一環として、公募型の研究開発や、効果的な人材育成プログラムの構築を実施しました。さらに、クリアランス制度の社会定着に向けた再利用先の拡大のため、これまでの実績を元にした展開等を行いました。
③深地層の研究施設を使用した試験研究成果に基づく当該施設の理解促進事業費補助金
【2024年度当初:1.6億円】
深地層の研究施設を活用した成果を通じて地域に貢献し、深地層研究に対する地域の理解を促進するため、深地層の研究施設を有効に活用した学術的研究として、堆積岩中の微生物に関する研究、微生物の働きによりCO2をCH4(メタン)に変換する技術の開発等を実施しました。
(4)国際連携に関する取組
最終処分の実現は、原子力を利用する全ての国にとって共通の課題であり、長い年月をかけて地層処分に取り組んでいる各国政府との間で、国際協力を強化することが重要です。2019年6月のG20軽井沢大臣会合を契機とし、同年10月と2020年2月には、「最終処分に関する政府間国際ラウンドテーブル」が開催されました。加えて、JAEAは、経済協力開発機構(OECD)/原子力機関(NEA)の協力を得て、幌延深地層研究センターを活用した国際共同プロジェクトを2023年2月に立ち上げました。このプロジェクトは、地層処分技術に関し国際的に関心の高い項目について、研究開発成果の共有や次世代を担う国内外の技術者の育成を目指しており、2024年度は、2025年度以降の成果の体系化に向け、個別課題の成果の取りまとめと国内外の会議での成果の積極的な発信を実施しました。