第4節 次世代電力ネットワークの形成
電力ネットワークの次世代化を進めることは、電力の安定供給を確保しつつ脱炭素化を進めるために不可欠であり、「日本版コネクト&マネージ」等による系統運用の高度化や、「広域連系系統のマスタープラン」の早期具体化等が重要となります。
また、再エネの導入拡大に伴い、出力制御が実施されるエリアが全国に拡大しています。再エネの出力変動を調整し得る「調整力」を効率的かつ効果的に確保することが、国際的に見ても、大量の再エネを電力系統に受け入れるための課題となっています。
1.系統制約の克服(ネットワーク改革等による系統増強への対応)
これまで、既存系統を効率的に活用するため、ノンファーム型接続の推進等により、活用可能な送電容量の拡大を進めてきました。こうした取組を引き続き推進しつつ、再エネの更なる導入拡大と電力の安定供給を実現するため、系統の増強を進めています。
電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)においては、主要送電線の整備計画を定める「広域系統整備計画」を順次策定しており、また全国大の広域連系系統の将来的な絵姿を示すマスタープランを2023年3月に策定しています。再エネの導入を加速化する政策的な観点から、東地域(北海道~東北~東京間)、中西地域(関門連系線、中地域)については、マスタープランの策定に先行して、2022年7月から、計画策定プロセスを開始しました。中地域については2024年6月に広域系統整備計画を策定しており、東地域及び関門連系線については、2024年4月に基本要件を決定した後、広域系統整備計画の策定に向けた対応を進めています。
再エネの導入等に資する地内基幹系統等についても、これまで以上に効率的な整備が必要となります。このため、各エリアの一般送配電事業者等が、より効率的・計画的に整備を進めるための仕組み等を検討していきます。
2.調整力の確保・調整手法の高度化
(1)出力制御
再エネ電源(太陽光・風力)は、気象条件等によって発電量が変動する特性があるため、地域内における発電量が需要量を上回る場合には、電力の安定供給を維持するため、発電量の制御が必要となります(第234-2-1)。
【第234-2-1】再エネ発電量と出力制御の関係
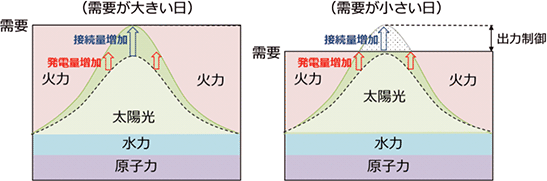
【第234-2-1】再エネ発電量と出力制御の関係(pptx形式:130KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
こうした場合、法令等で定められた優先給電ルールに基づき、火力発電の抑制、揚水発電の汲み上げ運転による需要創出、蓄電池の充電、地域間連系線を活用した他エリアへの送電を行います。それでもなお、発電量が需要量を上回る場合には、再エネの出力制御を実施することとしており、2023年6月までに、東京エリアを除く全国のエリアで出力制御が行われました。出力制御は、電力の安定供給を維持しつつ再エネの最大限の導入を進める上で必要なものです。こうした中、再エネ導入拡大に向けて、出力制御を抑制するため、2023年12月に「再エネ出力制御対策パッケージ」を取りまとめました。また、2024年12月1日には、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」を改定し、出力制御時における新設火力発電の最低出力を30%以下まで引き下げる方針を定めました。
(2)グリッドコードの整備
発電量が変動する再エネの導入拡大に伴い、今後、制御機能や柔軟性を有する火力発電・バイオマス発電の「調整力」としての重要性が一層高まっていくことが予想されます。日本においては、実効性や手続の適正性が担保されている「系統連系技術要件」をグリッドコードの中心に位置づけ、発電機の個別技術要件については、原則として「系統連系技術要件」に規定していくこととしました。2020年9月以降、広域機関に設置した「グリッドコード検討会」において系統連系等に関する課題と解決策について検討を行っており、2024年度からは、導入拡大が進んでいる系統用蓄電池に関する周波数や電圧変動に対する要件の検討を開始しました。