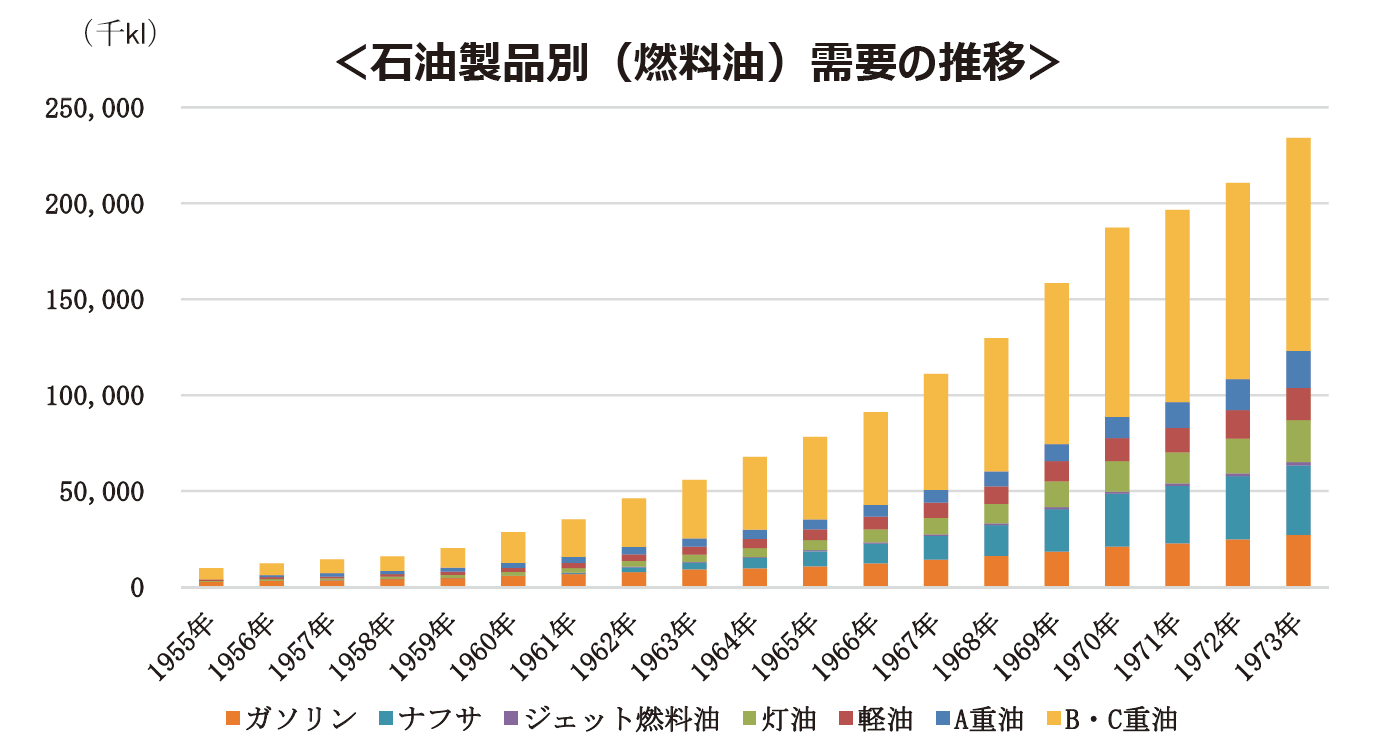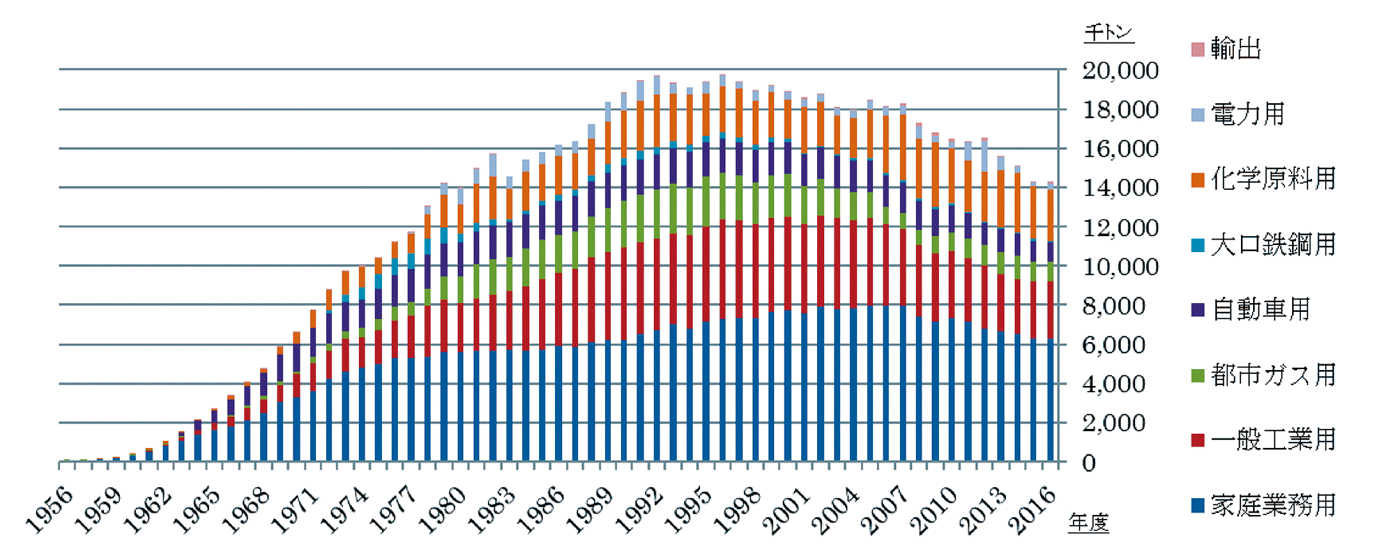第3節 1940年頃~
1.電気事業再編成による9電力体制の成立
戦後、電気事業再編成の機運が高まる中、1947年12月の過度経済力集中排除法の制定によって戦中の日本発送電と9配電会社は持ち株会社整理委員会から集中排除の指定を受けました。電気事業再編成審議会での再編成の検討や総司令部の再編成要求を経て最終的に戦中の電力国家管理が廃止に至ったのは、1950年11月にポツダム政令として公布された電気事業再編成令と公益事業令でありました。両政令の施行に伴い、1950年12月には、電力国家管理の法的基盤となっていた電力管理法が廃止され、電気事業の新しい行政機関として公益事業委員会が発足しました。そして1951年5月には日本発送電が解散すると同時に、発送配電一貫経営の北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州の9電力会社が誕生し、民営9電力体制が成立しました。これにより戦中から戦後の13年間にわたる電力国家管理は幕を閉じ、以後20世紀後半の電力業界の体制となる、発送電一貫形成、民営による独占的な地域別9電力体制が構築されることになりました。
なお、公益事業委員会は1952年8月に廃止されたため、通商産業省が電力行政の所管官庁となりました。加えて大規模な電源開発を行うべく、同年7月には電源開発促進法が成立されました。電源開発促進法に基づいて9月には電源開発株式会社が特殊法人として設立されましたが、これは地域別9電力体制を補完する意味も持っており、電力拡充政策、特に大規模水力開発を飛躍的に推進する契機となりました。
その後、オイルショックまでの高度経済成長時は急速な経済発展と共に電力使用量も急増し、電力業界は日露戦争後から1920年代にかけての期間に続く、日本電気市場の第2の急成長期を迎えました。
2.火力への再シフトと揚水水力の興隆
第二次世界大戦後、産業が加速度的に復興したことで、電源開発の要請は高まる一方となりました。全国的に、水力発電の開発地点が次第に奥地化していき、開発に有利な地点が少なくなってきていたということや、ダム開発に伴う水没保障問題の厳しさが増したなか関西電力は世界銀行借款の成功もあり、「世紀の大工事」とまでいわれた黒部ダムの建設工事を進めました。しかし、水力発電では急激な電力需要の高まりに対応することが難しくなってきていました。
そこで、開発期間が短い火力発電の開発が進んでいき、再度電源構成が水力から火力中心(火主水従)に移行することとなりました。戦後間もない時期には火力発電用燃料の大半は石炭で占められていましたが、1960年度以降石炭価格よりも重油価格が割安となったため、重油の使用量が著しく増加し、1960年代後半には、原油の使用量も急増しました。こうした中、ベースロードを高効率・大容量火力発電所が担い、ピーク調整は貯水池式の大規模一般水力発電所が行うようになりました。
しかし、1960年代後半に入り、昼間と夜間の需要の差(デイリーピーク)の拡大という需要サイドの変化が進行すると、貯水池式発電所による調整能力では不十分になりました。そういった日中の需要に対応するため、揚水式水力発電が開発されていくことになります。
1965年に日本で最初のデイリーピーク対応を主目的とした揚水式水力発電として東京電力・矢木沢発電所(24万kW)が運転を開始しました。矢木沢発電所は、上池を作る矢木沢ダムの事業主体が東京電力から建設省に、さらに水資源開発公団に移り、洪水調節、灌漑、発電に携わる多目的ダムと位置づけられ、当時としては画期的な大容量揚水式水力発電所として運転開始しました。
3.原子力のエネルギー利用の開始
(1)日本での原子力利用のはじまり
1950年代から1960年代は、世界各国で「原子力の平和利用」が始められた期間といえます。1951年に米国が世界初の原子力による発電を成功させて以来、世界ではエネルギー源としての原子力に注目が集まり、平和利用が進められてきました。1953年12月に、国連総会でアイゼンハワー米国大統領による『Atoms for Peace』と呼ばれる歴史的演説が行われ、我が国の原子力開発も、1954年の保守3党による原子力予算の計上で幕を開けました。
当時、我が国の原子力の開発状況は先進国に比べ著しく立ち遅れていました。そこで、できる限り速やかに原子力開発利用を推進する必要が指摘され、1955年、自主・民主・公開の三原則に従いその利用を平和目的に限ることを謳った「原子力基本法」が制定されました。
原子力開発の行政機構としては、1956年に「原子力基本法」に基づき、国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため原子力委員会が発足するとともに、総理府に原子力局が設置され、推進体制が整備されました。また、原子力委員会により、安全の確保、平和利用の堅持等の原子力に係る基本的考え方、我が国の原子力研究開発利用の基本方針や推進方策等を示した「原子力開発利用長期基本計画」が策定(以降約5年毎に改定)されました。
(2)日本で初めての商業用原発の誕生
原子力開発の推進体制は整備されたが、当時の日本には、まだ原子力発電所を建設するノウハウがありませんでした。そこで、米国や英国などに協力を仰ぎ、原子力発電所の開発が進められました。また、当時の先端技術であった原子力発電所を、民間企業のみで開設することは難しかったことから、国も協力して「日本原子力発電株式会社(日本原電)」という会社が設立されました。
そして我が国最初の商業用原子力発電所(日本原子力発電(株)東海発電所)が茨城県那珂郡東海村に建設され、1965年5月に臨界を記録、翌1966年に営業運転を開始しました。これは英国から導入された「黒鉛減速ガス冷却炉」と呼ばれる方式で、核分裂によって放出される中性子の速度を、黒鉛によって下げる仕組みでした。東海発電所の運転開始により、原発に関する日本への技術移転が始まり、徐々に国産の原発が開発されていくこととなります。
(3)現在につづく軽水炉の登場
その後、世界では、現在の原発の主流である「軽水炉」の建設が盛んになります。「軽水炉」とは、中性子を私たちが普段目にする普通の水(専門用語で「軽水」と呼ばれる)によって減速する方式です。日本では1970年に、日本原電の「敦賀発電所1号機」と関西電力の「美浜発電所1号機」の2基が運転を開始しました。福井県にある日本原電の「敦賀発電所1号機」は、日本で初めての「沸騰水型軽水炉(BWR)」として運転を開始しました。また、同じく福井県にある関西電力の美浜発電所では、「美浜発電所1号機」が日本で初めての「加圧水型軽水炉(PWR)」として運転を開始しました。
1970年は、大阪で日本万国博覧会が開催された年でもあり、高度成長期の真っ只中にあった日本では、未来を担う様々な先端技術への期待が高まっていました。こうした流れの中で、「原子力は発電に利用することのできるエネルギーである」という認識が、日本にも広まっていきました。
4.高度経済成長による石油需要の増大と石油業法の制定~重化学工業への転換と石油需要の増大~
(1)コンビナートの設立と石油需要の増大
第二次世界大戦後の我が国は、1955年から1973年までの18年間にわたって、実質経済成長率が年平均10%以上を記録する高度経済成長期を迎えました。1950年に勃発した朝鮮戦争による特需を皮切りに、神武景気、岩戸景気といった好景気を迎え、1960年には、当時の池田内閣による所得倍増計画が発表されるなど、我が国はかつてない好況の時代に突入しました。
こうした状況の中、活発な民間投資などを背景に、軽工業から重化学工業への転換が図られ、1958年には、我が国最初のコンビナートが岩国大竹、新居浜で稼働を開始しました。その後も、太平洋沿岸を中心とする各地で石油・石油化学・鉄などの様々な業種が集積するコンビナートが設立され、戦後の我が国経済をけん引する存在となっていきました。また、重化学工業への転換によって、産業用燃料としての重油需要が増大し、さらに、石油化学工業のめざましい発展に伴うナフサ需要の増加や、1964年の東京オリンピックの開催による高速道路を含む道路整備の加速化を背景とするモータリゼーションの進展に伴うガソリン、軽油需要の増加も相まって、1973年における石油需要は、一次エネルギーの8割近くになるなど、石油は、日本のエネルギーの大宗を占める地位を不動のものとしました。13
【第113-4-1】岩国大竹コンビナート

- 出典:
- 三井化学
- 出典:
- 資源・エネルギー統計
(2)石油業法の制定
前述のとおり、石油は、高度経済成長期の我が国を支えてきましたが、戦後間もない我が国では、石油輸入が認められていませんでした。第2節で触れましたが、1951年から民間企業による石油輸入が再開されたものの、当初は石油輸入は「外貨割当制度」に基づいて行われていました。しかし、その後経済復興が急速に進行した結果、我が国経済は、貿易・資本の自由化を実施して、開放体制へ移行することになりました。1960年に決定された「貿易・為替自由化計画大綱」に基づいて、1962年には石油輸入の大部分を占めていた原油の輸入自由化が実行に移されました。
貿易・資本の自由化は、我が国の石油業界のあり方にも、大きな変化をもたらしました。自由化の枠組みの下では、占領期以来の外貨割当という方策を継続することができなくなったため、政府は、日本経済における石油の重要性に鑑み、石油産業に対する新しい規制策を導入する方針をとることとし、原油の輸入化が行われた同年に「石油業法」が制定されました。
石油業法は、石油精製業等の事業活動の調整により、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを目的とし、①通商産業大臣による石油供給計画の作成、②石油精製業の許可制、③特定の精製設備の新・増設の許可制、④石油製品生産計画・石油製品輸入計画の届出制、⑤必要な場合における通商産業大臣の石油製品販売価格の標準額の告示などを定めたものでした。14
5.石油自主開発の推進~本格的な海外油田開発の開始へ~
(1)戦後の産業復興に向けた「石油資源総合開発5カ年計画」策定
太平洋戦争の影響としては、戦争末期の米軍による本土爆撃により中流部門の精製工場は大きな被害がありましたが、上流開発地域は爆撃の対象外だったため、無傷で残りました。
一方、敗戦の結果、①北樺太油田の採掘権放棄、②台湾油田の喪失、③生産設備の南方移転、④石油開発従事者の中から2,000名に上る犠牲者を出したこと、⑤約1万2,000名にのぼる石油開発関係従事者を国内のわずかな油田で養わなければならなくなったこと等により、石油上流開発企業は軒並み厳しい経営環境に直面しました。
こうした背景から、1946年には官民合同の臨時石油鉱業調査会(商工省鉱山局長の諮問機関)が設置され、産学官が協力して油田の回復に努めました。同年11月には総司令部天然資源局の勧奨に基づき、臨時石油鉱業調査会の一部会として石油資源開発促進委員会が設けられ、同会では総司令部指導の下、産学官からの委員により、第一次石油資源開発5カ年計画を作成しました。また、米国より地震探鉱、重力探鉱など最新の探鉱技術等が導入され、国内の探鉱地域は著しく拡大しました。これにより、秋田県八森油田や同県八橋油田の深層部開発等が進展しました。
1952年5月に「石油及び可燃性天然ガス資源開発法(法律第162号)」が交付されたことに伴い「石油資源開発法」が廃止され、同法に基づいて設立された石油及び可燃性天然ガス開発審議会は1953年9月「石油資源総合開発5カ年計画案」を通商産業大臣へ答申しました。
同答申では主に
- (i)5カ年後の原油生産量の目標は年間100万klとし、探鉱部門に傾注することで約900万kl(5年間)の可採埋蔵量を発見する。
- (ii)地質調査を徹底的かつ計画的に行う。
- (iii)156地域について、468坑を掘削し、その掘削総計深度を約64万mとする。これにより、10油田(約900万kl)を発見する。
- (iv)新油田、既存油田に対し、深掘井、採掘井を掘削し、老朽油田に対して二次採油法を実施して残存埋蔵油の採取を図る。
が決定されました。
同じく、1955年には石油資源開発株式会社法(昭和30年法律第152号)が成立し、石油資源開発が設立されました。同社は帝国石油から一部の財産・人員を承継し、国内の石油資源の新規探鉱・開発活動を行うこととなり、一方の帝国石油は既存油田及び天然ガス資源の開発を行うという分業体制が成立しました。
(2)海外における石油開発の再開・本格化
一方、海外での上流開発は1952年まで連合国軍の占領下におかれたため、全く手を付けられない状況でした。こうした中、1957年にサウジアラビア政府より土田サウジアラビア大使に、未開発地域の開発にアジアの先進国の日本に進出を求めたい旨の意向が伝えられました。この情報を得た日本輸出石油社長の山下太郎氏らは1957年サウジアラビアとの間でクウェートとサウジアラビアの中立地帯沖合鉱区の石油利権協定に調印しました。翌1958年には電力、鉄鋼、商社等約40社からなるアラビア石油が設立され、日本輸出石油から利権を継承し、続いてクウェートとの間で同鉱区の利権協定に調印しました。
アラビア石油は1958年8月から地震探査を開始し、翌年に試掘1号井の採掘を開始しました。1960年には1,000kl/日(約6,000バレル/日)の試油テストに成功し、同油田はカフジ油田と名付けられました。本油田は戦後日本最初の本格的な海外油田の開発でした。
同時期、1960年にインドネシアの石油公社であるプルミナ(現プルタミナ)から財界の小林中氏らを中心とする小林グループに対し、円クレジット供与による援助方式で北スマトラの諸油田の復旧開発を行い、その見返りに原油の無償供給を行うという申し出があり、同年4月に協定が調印されました。1960年6月に北スマトラ石油開発協力(NOSODECO)が石油資源開発を中心とした52社の出資により設立されました。
また、インドネシアでは1966年に、石油資源開発の出資により、後に現在の国際石油開発帝石となる北スマトラ海洋石油資源開発が設立され、プルタミナとスマトラ沖海上鉱区の開発に関する生産物分与契約が締結されました。翌年には、石油資源開発より1966年締結の東カリマンタン、ブニュー沖・マハカム沖両鉱区に関する生産物分与契約の権利義務一切を譲り受け、北スマトラ石油開発協力とともに、インドネシアにおける我が国石油開発事業の礎となりました。
【第113-5-1】サウード国王に謁見する山下太郎氏

- 出典:
- 富士石油(旧日本輸出石油)ホームページ
6.LPガスの普及~家庭用燃料として需要拡大~
(1)家庭用燃料としての普及
戦後、原油の輸入と製油所の再建・再開が許可されると近代的な製油所が整備されました。近代的な製油所が稼働すると、副生品としてLPガスも生産されました。また、同時期には日本海側の油田やガス田からもLPガスが分離・回収され、1953年頃にはLPガスが市場に出回ることとなりました。15
当時家庭用燃料としては、薪や炭などの固形燃料が主流でしたが、取り扱いが比較的容易で熱量の高いLPガスは急速に普及し、国内生産だけでは需要を賄いきれなくなり、1961年には海外からの輸入も開始されるほどで、1962年頃には国内需要は100万トンを超えるまでに至りました。また、国内需要が200万トンを超えた1964年の東京オリンピックでは、国立競技場の聖火台の燃料として採用され、鮮やかな炎が花を添えました。
(2)LPガス自動車の普及
戦前には不足していたガソリンに代わる自動車用燃料としてLPガスを用いた自動車が既に存在していましたが、本格的な普及には至りませんでした。その後、家庭用燃料としてLPガスが急速に普及し始めた頃、ガソリンに対し割安な燃料費や高オクタン価が着目され、1962年にはタクシー事業者がLPガス自動車の本格的な導入を開始しました。16その後LPガス自動車は急速に増加し、1967年には登録台数が10万台を超え、自動車用需要量も同年には現在と同程度の100万トンを超えるまでに至りました。
(3)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の成立
LPガスの普及拡大に伴い、事故も全国で急増することとなりました。そのため、LPガスの保安体制の確立や取引の適正化に向けて、LPガス販売事業の許可制(1996年から届出制に変更)、一般消費者等の保安の確保、製造事業者や器具製造事業者に対する技術基準の遵守及びLPガス規格表示の義務化などの規制を課す「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」が1967年に成立しました。17以後法整備やLPガス業界の自主的取組が進んだこともあり、2017年には死亡者数0を達成しました。
- 出典:
- 資源エネルギー庁液化石油ガス需要想定委員会「LPガス需要見通し」を基に資源エネルギー庁にて作成
(4)災害時にも活躍するLPガス
国内で増加し続けるLPガスの需要を賄うため、1961年の輸入開始以後、国内供給に占める輸入割合は8割を超えるに至り、その多くが中東産でした。1977年にはサウジアラビアでプラント事故が発生し、輸入量が激減するなどしたため、石油の備蓄の確保等に関する法律が改正され、民間LPガス輸入事業者に備蓄義務を課すこととしました。その後1991年には湾岸戦争による輸入の一時中断などが生じ、1992年に国家備蓄目標を策定し、現在では民間備蓄及び国家備蓄あわせて国内輸入量の90日分が備蓄され、万が一の際に備えた体制を整備しています。
LPガスは都市ガスや電気といった系統供給とは異なる分散型供給という特徴があります。その特徴を活かし、現在では国内世帯の約4割で活用されるエネルギーとなりました。分散型供給の最大の特徴は、災害時の復旧が迅速であるという点であり、実際に2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震では都市ガスや電気にさきがけて復旧しました。
東日本大震災時には、被災地だけでなく全国的なガソリン不足が生じる一方、LPガススタンドの多くは燃料不足を免れました。そのため、被災直後からLPガス自動車は「国境なき医師団」の医師や看護師の人員輸送や支援物資の輸送を担いました。また、被災地域だけでなく、東京では福島県からの避難者の透析のための通院送迎を行うなど活躍しました。
他方で、東日本大震災を踏まえ、今後の大規模災害に備えたLPガス供給体制のさらなる強化の必要性が生じました。具体的には、輸入基地の停電等に備えた移動式電源車の配備及び受電設備の設置を行うとともに、災害時に地域のLPガス供給を広域で対応するために非常用発電設備、緊急用通信設備やLPガス自動車等を配備した「中核充填所」を全国で約340か所整備しました。また、石油の備蓄の確保等に関する法律を改正し、全国9地域で「災害時石油ガス供給連携計画」を策定し、LPガスの輸入事業者やLPガス販売事業者が、大規模災害発生時に互いに協力してLPガスの供給を行えるようにしました。