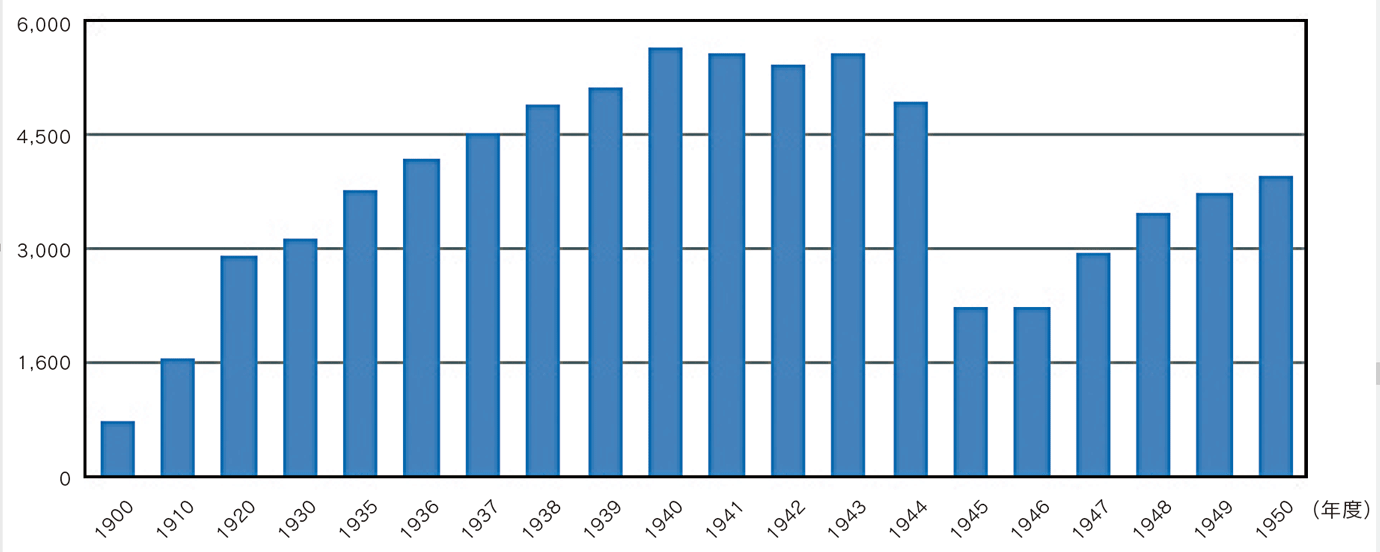第2節 1900年頃~
1.ガス利用の照明から熱への転換
(1)ガスの熱利用
まず照明から利用が開始されたガスですが、1900年代に入ると、熱利用が徐々に進んでいきました。常用七輪と呼ばれたコンロ、かまど、レンジに相当する焼物器、ストーブ等、現在のガス機器の原型ともいうべきものがイギリスから輸入され、次々と国産化されていきました。1910年代に入ると、一般家庭に、ガス七輪、ガスかまど、ガスストーブ、ガス湯沸器等が本格普及してきました。
(2)工業用ガスエンジンの登場
ガスの工業利用としては、1889年ごろに初めてガスエンジンが輸入され国民生活に貢献しました。1900年代、動力としての電力はかなり高価かつ頻繁に停電していたため、普及が滞っていました。このため、動力としては、もっぱら蒸気機関が利用されていましたが、据え付けに場所をとり、貯炭場や煙突が必要であったため、中小企業はなかなか設置できませんでした。これに対し、ガスエンジンは取り扱いが簡単なため動力源として急速に普及し、1914年には2700台に達しました。しかし、電気モーターの出現で徐々に減少していき、1925年には497台となりました。
(3)ガスの普及拡大
1910年代~1920年代は、ガス事業の礎が築かれた時期でした。1900年代に全国で10社程度だったガス事業者は1915年には90社を超え、現在も活躍するガス事業者が誕生しています。また、大正時代は、それまでの生活様式が様変わりした時代でもあります。洋服の普及や職業婦人の登場と並び、電灯、ガス、水道の普及が本格化していきました。ガス会社は、こうした時代背景の中で、大都市圏を中心に、ガスストーブ、ガスコンロ、ガスかまど、ガス風呂等の普及に力を注ぎました。1925年には、最初の瓦斯事業法が施行され、都市ガスは国民の暮らしを支える基幹インフラへと成長を遂げていきました。
2.電力は火力から水力へシフト
当時、送配電網が整備されていなかったため、小規模な火力発電が需要地に近い場所で建設されることが一般的で、水力発電は、中部山岳地帯のような、大都市からの離れた場所に建設され周辺地域に供給するのみでした。そのため、当時は火主水従の時代でした。
電気の利用が盛んになるのは日露戦争や第一次世界大戦が契機となります。この時代の、経済の拡大ならびに官民一体となった工業化によって電気の利用は盛んになり、電灯需要とともに電力需要も増加しました。その結果、1907年から1925年までの18年間で電気事業者数は約6倍に拡大しました。
日露戦争後、電気の需要が拡大する中、さらなる電源の開発が急務でしたが、火力発電の燃料となる石炭の価格が高騰していました。このような状況変化を受けて、アメリカの超長距離送電技術を取り入れ、東京電燈は山梨県桂川水系に駒橋発電所(1万5,000kW)を建設し、5万5,000Vの電圧で東京へ向けて76㎞の距離の送電を実現しました。その後、全国で中長距離の高圧送電を利用した水力開発が活発化し、1910年代前半には、水力発電所の出力が火力発電所の出力を超え、水主火従の時代へと突入しました。各地に大容量水力発電の開発が進んだことによって、電気料金を低下させることが可能となり、電気の利用の拡大にいっそう拍車がかかっていきました。
3.戦前~戦中の電気事業者の変遷
電気事業者にとって日露戦争後から太平洋戦争期に至る時期は、電気市場の急拡大と電気事業者の乱立から5大電力と国家統制への収斂に特徴づけられます。本項では、これら1920年代~1930年代の電気事業の特徴をそれぞれ見ていきます。
後発であるにも関わらず、欧米先進諸国とほぼ同時期に成立した日本の電力業ですが、電力市場は日露戦争後期から第一次世界大戦を経て1920年代に至る時期に爆発的に拡大しました。電力市場の急拡大をもたらしたのは、遠距離高圧送電技術の導入や大規模水力発電の開始といった供給側の要因に加えて、前述した電灯の普及や工場電化の進展といった需要拡大でありました。
当初は中小の電気事業者が乱立していましたが、遠距離高圧発電と大規模水力発電の振興によって規模の経済性が働いたことで収斂し、東京電燈、東邦電力、大同電力、宇治川電気、日本電力の5大電力が登場しました。
一方で1920年代の日本の電力業界では、従来認められていた電灯や小口電力の重複供給が許可されなくなったために、「電力戦」と呼ばれた需要家争奪戦が激化しました。「電力戦」はサービス改善と電力料金の低下をもたらしましたが、供給設備の二重投資や電気料金の過当競争による電気事業者の収益悪化という業界の混乱をもたらすことにもつながり、社会問題化しました。
この局面の打開のために志向されたのが、「電力統制」と呼ばれる電力の再編成です。当時電力業界を所管していた逓信省は1927年3月に臨時事業調査部を設置し、統制措置をまとめ、この措置をさらに具体化するために1929年1月には臨時電気調査会を発足させました。加えて、電力業界の内部からも自主統制の機運が高まったことを背景に、電気事業者が一堂に会する電力統制会議も開催されました。
電力統制会議での議論を経て5大電力が結成したのが、電力連盟です。また、電力連盟とともに「電力戦」の終焉に寄与したのが電事法改正です。供給区域の独占と公的監視機関である電気委員会の設置を定めた改正電気事業法は1931年4月に公布され、1932年12月に施行されました。電力連盟が既存の重複供給権を凍結し、電気委員会が新規の重複供給を厳しく制限するという呼応をしたことで供給区域の独占が確立されるようになりました。
「電力統制」は低廉かつ安定的な電力供給についてもある程度実現させましたが、30年代半ばからは電力を国家統制下に置くことを志向する動きが強まり、激烈な電力国家管理論争が展開されました。当初は5大電力を中心に電気事業者の間で国家統制に反対する動きがありましたが、結局1938年には電力国家管理関連4法案が成立し、電力連盟は解散しました。そして1939年4月には既存の電力事業者から強制的に設備出資をさせて日本発送電が誕生し、電力は日本発送電と9配電会社による国家管理の時代を迎えました。
4.石油の需要構造の変化~灯油から動力エネルギーへ~
(1)需要構造の変化
石油ランプに使用されていた灯油の需要は、1910年頃から電灯の普及により著しく減少し、これに代わって軽油、ガソリンの需要が著しく増加しました。これは、石油内燃機関の発達、特に発動機付き漁船(軽油)と、自動車(ガソリン)の需要増加が大きく影響しています。1907年には我が国初の国産ガソリン車タクリー号が東京自動車製作所により制作され、大正末年にかけて自動車は急速に普及しました。自動車の普及に伴い、ガソリン販売政策の一環として1912年2月、東京市神田区鎌倉河岸(現・千代田区外神田)に初のビジブル式ガソリンスタンド(地下タンク式で、手動ポンプでガソリンを汲み上げると計量機上部の透明部分にたまるのが見える)が完成しました。スタンドを建設した当時、鎌倉河岸には中央魚市場があり、そこで同市場に出入りする自動車を供給対象としてスタンドが建設されました。9
また、第一次世界大戦中に、日本海軍の軍艦の燃料が石炭から重油に切り替えられたことにより、大正後期にかけて重油需要も大きく増加していくことになります。海軍により1918年に起案された「軍事上の必要に基づく石油政策」においては、①石油事業の国営化及び②国内石油会社の合同一体化が提言されており、我が国最初の具体的な石油政策の提言と言われています。
こうして、石油は「灯火用エネルギー」から「動力エネルギー」へと転換され、重要な国家戦略物資となり、国内における開発競争の激化と石油産業の海外進出を促すことになります。
【第112-4-1】国内石油製品需要の推移
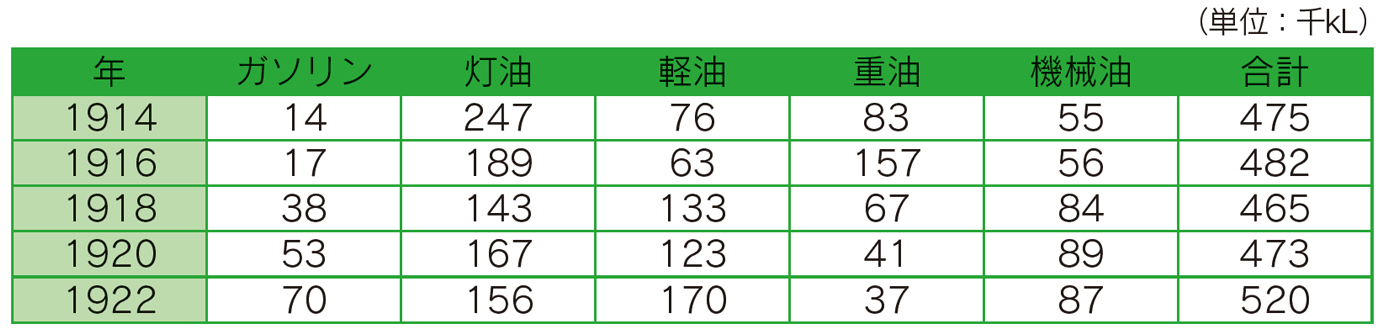
- 出典:
- JXTGエネルギー「石油便覧」より作成
【第112-4-2】我が国初の国産ガソリン車タクリー号
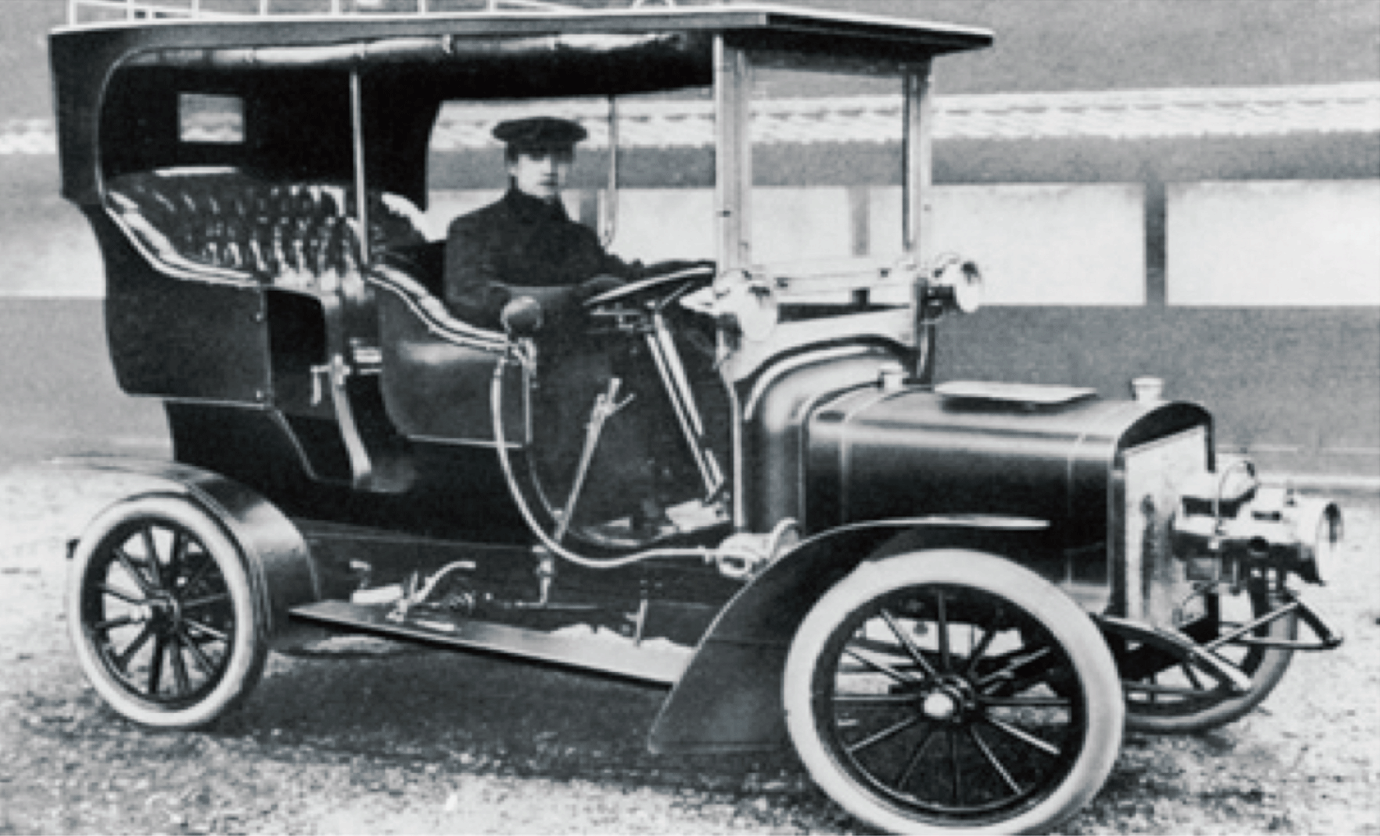
- 出典:
- 日本石油株式会社「日本石油百年史」
(2)第一次世界大戦による石油需要の高まりと生産減少
国内での石油生産は、1909年を一時ピークとして減退傾向に入っていたものの、米国での油田開発で活用されていたロータリー式掘削10の導入により国内の石油開発は最盛期を迎えました。生産量は再び上昇に転じ、1915年に約48万klという第二次世界大戦以前における最高値を記録しています。特に、秋田の黒川油田は、1914年に掘削したロータリー式5号井で大噴油が起こり、一時日量約1,800klを記録し、我が国最大の油田として成功しました。
1914年に勃発した第一次世界大戦は、物資の輸送が途絶したことから、国内の油田開発の重要性が一層強く認識されました。大戦による産業振興、石油製品の需要増に伴い、国内石油市況が活発化し、油価は高騰を続け、日本石油、宝田石油など産油量の多い企業は好成績を収めた一方、開発設備の輸入途絶により新油田の開発作業に支障を来すこととなり、多くの新興石油会社が淘汰され、需要と反比例するように石油生産量は減少を続けました。
(3)海外油田への進出と海外原油の輸入増加
国内原油の限界が見え始めると、我が国石油鉱業資本の目は海外に向けられました。我が国と地理的に近接するロシア・北樺太での油田開発は、1918年頃より日露共同での石油採掘が企図されていたものの、ロシア革命等の影響で本格的な開発は進んでいませんでした。1925年、北樺太の石油利権に係る契約が締結され、翌年北樺太石油株式会社が設立、同年末には日量170トンを計上するに至りました。
1920年代にはインドネシア、フィリピン、ミャンマー、メキシコ、ペルー、カナダなどの石油鉱区への進出を試みる動きも見られました。これらはいずれも実現には至らなかったものの、徐々に石油産業の海外進出が見られるようになりました。
また、減退を続ける国内生産とは逆に増加を続ける国内需要に対応するため、海外原油の輸入及びその国内での精製が本格化することとなりました。1921年に福岡県・西戸崎(さいとざき)製油所で海外原油の精製事業が開始されたことを契機に、我が国への石油供給は輸入原油が優勢となり、また石油産業の中心は、日本海側からより輸入に便利な太平洋側に移動することとなりました。
さらに、長らく我が国の石油産業を担ってきた日本石油、宝田石油の二大企業は、国内での採掘及び販路確保における競争が外国企業に市場への参入を許し、国内石油産業の競争力を害するとの結論から、1921年に両社合併して新しい「日本石油」が誕生しました。
【第112-4-3】原油生産量及び輸入量の推移
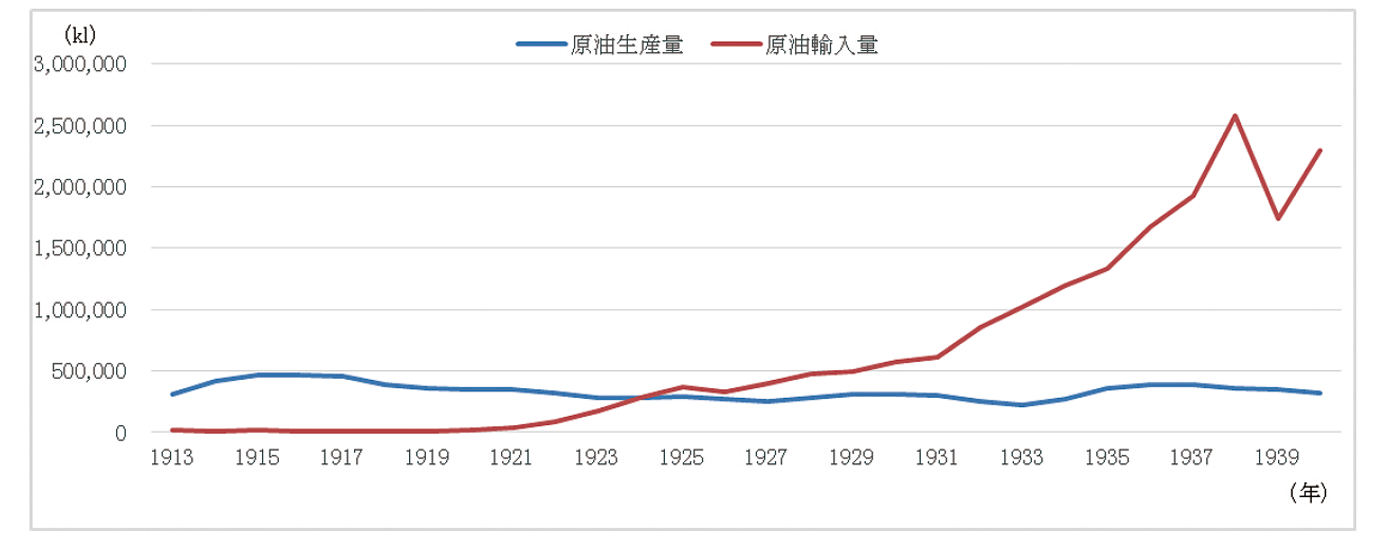
- 出典:
- 日本石油(現・JXTGエネルギー) 「本邦鉱業ノ趨勢」、「石油便覧」
(4)戦争を契機とした政府による石油政策樹立
第一次世界大戦によって石油の重要性が世界的に認知され、国際的な石油開発競争が進んだ結果、世界的な供給過剰が発生し、1930年代はむしろ石油販売市場の競争が激化することとなりました。日本も例外ではなく、販路獲得のための欧米企業がダンピングを強行した結果、国内の需要は増加していたにもかかわらず、激しい価格競争が行われました。1933年にソ連産のガソリンの輸入が開始され、価格競争がさらに熾烈になったことから、国内石油産業は大打撃を受けることとなり、政府に対する基本的な石油政策樹立の要請が高まりました。
こうした背景から、1934年、石油貯蔵の義務化と石油精製業・輸入業の許可制等を内容とする石油業法が制定され、増加する需要に対する十分かつ安定的な供給を確保し、また戦時に向けた原油貯蔵のための方策が講じられました。なお1934年当時、我が国は原油の80%を輸入に頼っていましたが、同法による統制等を背景にガソリンに替わる燃料の研究が盛んに行われるようになり、例えば、電気自動車用電池やディーゼルエンジンの研究、木炭車の開発・改良等が進みました。11
また、石油需要増加に対応するため、国内での石油開発も政府により積極的に奨励され、我が国最大級の油田である秋田県・八橋(やばせ)油田の開発や、台湾における錦水(ちんすい)ガス田の開発などが進められました。一方で、太平洋戦争開戦直前、我が国は石油の9割以上を海外からの輸入に依存していました。1941年、米国、英国、オランダにより石油の全面禁輸が実施されたことを契機として、我が国は太平洋戦争に踏み切ることになります。開戦早々、我が国は不足する石油資源の獲得を求め、パレンバンを有するスマトラ島をはじめ、ボルネオ島、ジャワ、ビルマなど米・英・蘭が植民地化していた広範囲な産油地で石油等の採取を行いました。一時は相当量の石油が算出され、日本国内に輸送されていたものの、米軍の攻撃等による施設や輸送船の破壊等により徐々にその機能は低下し、終戦直前はほとんど麻痺状態であったと言われています。
石油業法の制定と、戦争による時局の変転に伴う統制強化により、石油精製業者の整理統合が進むこととなりました。1941年には、精製業者は日本石油、昭和石油、丸善石油、大協石油、東亜燃料工業、三菱石油、興亜石油、日本鉱業の八会社に整理されました。開発事業に関しては、1938年に石油資源開発法が成立し、民間企業による石油開発に係る政府の計画管理と試掘への助成の制度化がなされました。さらに、内外石油資源の積極的開発は産業上・国防上急務であったことから、1941年には帝国石油株式会社法が成立し、政府が半額を出資する国策会社として「帝国石油」が設立され、国内企業のほぼ全ての石油鉱業部門を吸収した大企業が誕生することとなりました。
このように、第一次世界大戦及びその後の国内市場の混乱を受け、太平洋戦争開戦前後には、我が国石油政策の骨格が構築されることとなりました。精製事業の確立に向けては海外原油の十分な輸入による事業の活性化を図り、開発事業はこれとは別に法律によって保護・育成がなされるという方針が進められた結果、現在にまで及ぶ、石油産業の開発事業と精製事業との分離が図られることになります。
5.エネルギー産業の構造変化~石炭から石油へ~
(1)出炭量がピーク
石炭鉱業は、景気変動の波を受けながらも産業発展の先導役として年々増産を重ね、日露戦争の勃発した1904年には1,072万トン、昭和に入ってからは採炭や運搬現場において機械化が進み、出炭能率も著しく向上したことから出炭量は3,000万トン~4,000万トンに拡大、1940年には5,631万トンの出炭実績を上げています。この記録は我が国の石炭史上における出炭最高記録となっています。
翌1941年の太平洋戦争開戦時には5,560万トンの出炭を確保したものの、戦争の激化に伴い、熟練労働者の不足や資材不足により能率は徐々に低下していきました。
戦前の石炭鉱業は、産業振興、のちには戦争遂行の重要物資であることの使命を担っての増産奨励により、産炭地においては中小・零細を含め繁忙を極めました。
太平洋戦争は1945年8月に日本の敗戦をもって終戦を迎えましたが、この間の激しい空襲により、石炭鉱業の地上施設は甚大な被害を受け、坑内の状況は戦時中の乱採掘によって著しく荒廃、加えて労働者の離散と資材不足が石炭の生産能力を半減させることとなりました。
この結果、鉄道輸送、産業復興に必要な石炭不足が深刻な問題となり、このため、政府は戦後経済再建の突破口を、石炭を始めとする鉄鋼、肥料の集中生産に求め(傾斜生産方式)、1947年度における3大基礎産業の生産目標を、石炭3,000万トン、鉄鋼80万トン、硫安(りゅうあん)110万トンと定め、特に石炭は鉄鋼、硫安の生産に必要な原料であったため、最重要産業として緊急の増産対策を講じました。
- 出典:
- エネルギー生産・需給統計年報、及び石炭エネルギーセンター調べ及び北海道管内石炭生産実績表
(2)石炭の統制撤廃
第二次世界大戦後、石炭産業は国を復興させる重要な産業として位置づけられ、傾斜生産方式の導入、臨時石炭鉱業管理法及び配炭公団法が公布され、石炭鉱業は需要、供給とも国の完全な統制下に入り、生産は急速に回復しましたが、需要産業の復興が遅れたため需給にアンバランスが生じ、生産過剰の状態となりました。
その後、経済の安定とともに、政府は石炭統制の全面撤廃に向けた諸般の準備を進め、段階的な石炭統制の撤廃課程(配炭公団の廃止等)を経て、1950年に石炭企業は自由競争市場へ復帰することになりました。
(3)石油の輸入自由化
太平洋戦争の終了後、1951年から民間企業による石油輸入が再開されたものの、我が国の外貨資金は極めて限られていたため、原油及び石油製品の輸入も他の物資の輸入と同様に「外貨割当制度」の下に行われていました。
その後、日本経済の急速な発展に伴い、自由貿易を基調とする国際経済社会において応分の責任を果たすことが求められ、我が国においても世界の大勢である貿易自由化の体制を早急に確立することが緊急の課題になりました。日本政府は、1960年6月に「貿易・為替自由化計画大綱」を決定し、これに伴い1962年10月には石油輸入の大部分を占める原油の輸入自由化を行いました。12
(4)国内石炭炭鉱閉山に向けて
石炭各社は懸命の合理化努力に傾注して、炭価の引き下げを実施していましたが、1960年度以降における石油価格の値下がり及び国内諸物価の値上がりによる石炭採掘コストの上昇等を背景として、石炭鉱業の経営は悪化を続けていたほか、労使間紛争に伴う大規模なストライキが頻発し、生産能力の低下と生産コストの上昇が顕在化してきました。
石炭情勢の悪化と、石炭労使間紛争の混乱を危惧した政府は、1962年4月に「石炭鉱業調査団」の編成を行い、本調査団の検討によって新しい石炭鉱業再構築についての答申を求め、新石炭政策を展開することについての閣議決定を行いました。
調査団は直ちに九州、宇部、常磐、北海道の現地視察を実施して、石炭労使、産炭地自治体、石炭関連業界から意見聴取を行い、1962年10月に「石炭が重油に対抗できないということは、今や決定的である。」との「答申大綱」を政府に提出しましたが、答申は続けて「石炭鉱業の崩壊がもたらす関係者への影響、地域社会に与える深刻な打撃、国民経済の被る損失を防止することは、国民的な課題である。」との指摘があり、本答申以後における石炭鉱業合理化政策の目標は、これまでの「競合エネルギーと、価格面で競争することを目標とした閉山合理化政策」から「石炭が重油に対抗できないことを認めつつ、石炭鉱業の崩壊がもたらす社会的摩擦の回避等に注目した幅広い政策」へと転換が行われました。
この政策転換により、2002年3月末までに、北海道の一部の露天掘り炭鉱を除き全ての炭鉱が閉山しました。
なお、最後の閉山となった北海道の釧路炭鉱(太平洋炭礦(たいへいようたんこう))は、地元関係者の運動により釧路コールマインとして再出発し、国内唯一の坑内掘り炭鉱として採炭を行うとともに、これまで日本が培ってきた坑内掘りに関する産炭、保安技術を海外産炭国に技術移転するため、国の支援を受け、釧路炭鉱の前に閉山した長崎県の池島炭鉱(三井松島リソーシス)とともに、技術移転研修事業を実施しています(池島炭鉱での国内受入研修事業は2009年度まで)。
【第112-5-2】釧路コールマイン

- 出典:
- 釧路コールマイン株式会社