第3節 エネルギーコストへの対応
1.成長戦略に対する障害のおそれ
「日本再興戦略(2013年6月14日閣議決定)」においては、企業が活動しやすい国とするために、日本の立地競争力を強化するべく、エネルギー分野における改革を進め、電力・エネルギー制約の克服とコスト低減が同時に実現されるエネルギー需給構造の構築を推進していくことが強く求められています。また、エネルギー需給構造の改革は、エネルギー分野に新たな事業者の参入を様々な形で促すこととなり、この結果、より総合的で効率的なエネルギー供給を行う事業者の出現や、エネルギー以外の市場と融合した新市場を創出する可能性があります。2014年6月24日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2014 ~デフレから好循環拡大へ~」(骨太方針2014)では、「経常収支の黒字の急減には、我が国経済の構造変化、新興国の需要減速等に加え、エネルギー価格の上昇や為替変動による輸入物価上昇の影響が大きい」とし、「当面はエネルギーコスト高への対策を講じ、資源・エネルギーを安価かつ安定的に確保するとともに、省エネ・省資源や海外の資源権益確保等により価格交渉力の強化に努めることが必要」とされました。エネルギーのコスト上昇や供給不安が、新たな投資や雇用の拡大を阻害し、経済の制約となることへの懸念から、エネルギーコスト高への対策を早急に講じ、資源・エネルギーを安価かつ安定的に確保すること、そのため、省エネ投資を始めとする徹底した省エネの推進のほか、老朽火力発電所の更新時等における高効率火力発電(石炭・LNG)の活用、電力・ガスシステム改革の推進、資源外交等による供給源の多角化、石油・LPガスサプライチェーン等の維持・強化の促進等に取り組むこととされました。 さらに、2014年12月27日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」においても、緊急経済対策の具体的施策の一つとしてエネルギーコスト対策が挙げられ、「エネルギー価格の影響への耐性を強化するため、省エネルギー・再生可能エネルギーの推進やエネルギー価格の影響を受けやすい分野の対策に取り組むとともに、資源・エネルギーの安定供給のために必要な施策を講じる」とされました。 政府は、東日本大震災以降の電力料金の上昇や為替変動等によるエネルギーコストの上昇が我が国経済に与える影響について、自営業・小規模事業者等も含め、各府省庁が所管する業界を網羅した地域別のきめ細かい状況把握を行うとともに、必要な検討を政府一体となり関係行政機関が連携して行うため、「エネルギーコスト上昇に関する関係副大臣等会議」(議長:内閣官房副長官)を、2014年11月から開催しています。2014年度は3回開催し、エネルギー価格動向、エネルギーコスト上昇の影響とその対応などがテーマとして取り上げられました。
2.緊急的なエネルギーコスト対策
2014年夏以降、原油価格の下落に伴い燃料価格は下落基調になりましたが、中長期的には、高騰と下落を繰り返しながら上昇してきたところであり、引き続き、価格動向については注視が必要な状況です。また、電力料金は震災前に比べて、産業用で約40%、家庭用で約25%上昇しており、依然として高い水準にあります。このように燃料価格が高水準であり、企業や家計に与える影響も大きかったことから、政府も様々な分野で緊急的にエネルギーコスト高への対応を行っています。
(1)省エネルギー対策の強化
エネルギーコスト高を乗り越える企業体力を強化するとともに省エネルギー投資の促進により経済活動の活性化に繋げる観点から、機器・設備単位での簡易な省エネルギー投資の促進や工場・オフィス・店舗等の省エネルギーや電力ピーク対策、エネルギーマネジメントに役立つ設備等の改修・更新の支援を行いました(2014年度補正予算額929.5億円)(後掲 3.(1)(ア) 参照)。
(2)中小企業・小規模事業者支援
エネルギーコスト高や原材料の高騰が、中小企業・小規模事業者の収益を圧迫していることから、経済産業省は2014年10月3日に原材料・エネルギーコスト増加分の転嫁対策パッケージを発表し、以下の①から⑥の措置を講じました。
①資金繰り支援の要請
日本政策金融公庫、商工中金及び全国信用保証協会連合会に対し、中小企業・小規模事業者の返済条件緩和等について、配慮することを要請する文書を発出しました。これらの公的金融機関においては、中小企業・小規模事業者に対して、2015年4月末までの7か月間に、合計約35万9,000件・5兆2,000億円の返済条件の変更を実施しています。
②業界団体及び親事業者への要請文書の発出
各省関連の業界団体(計745団体)に対し、原材料・エネルギーコスト増加分の価格転嫁に関する経済産業大臣名の要請文書(他省庁関連は両大臣連名)を発出しました。下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)(以下「下請代金法」という。)上の親事業者(約20万社)に対して取引適正化を要請する文書を発出しました。
③下請代金法の厳格な運用
下請代金法に基づく立入検査時に原材料・エネルギーコスト増加分の価格転嫁を拒否していないか検査を強化しました。原材料・エネルギーコスト増の影響が大きい業種のうち、代表的な大企業約200社を選定し、2014年内に集中的な立入検査を実施しました。
④転嫁Gメンとの有機的な連携
消費税の転嫁状況の監視・取締りを行う転嫁対策調査官(転嫁Gメン)が立入検査を行う際、原材料・エネルギーコスト増加分の転嫁状況についても厳正に確認しました(2014年10月以降、2014年度末までに590社)。
⑤原材料・エネルギーコスト増に関する相談員の配置
中小企業・小規模事業者の相談を受ける「下請かけこみ寺に、原材料・エネルギーコスト増に関する相談員を配置しました。商工会、商工会議所など全国2,328か所でも相談を受付けました(2014年10月以降、2014年度末までに原材料・エネルギーコスト増に関する相談14件)。
⑥影響調査の実施
商工会、商工会議所などを通じ、原材料・エネルギーコスト増に係る調査を実施しました。 これら2014年10月に打ち出した①から⑥の対策に引き続き、経済産業省は2015年1月23日に更なる対策として、以下の⑦から⑪の措置を講じました。
⑦産業界に対する適正な取引の要請
2014年12月の政労使会議における取りまとめ(注)も踏まえ、様々な機会を活用して、約270団体に対して取引の適正化等について要請しました。
- (注)
- 2014年12月16日「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について」(抄)「政府の環境整備の取組の下、経済界は、賃金の引上げに向けた最大限の努力を図るとともに、取引企業の仕入れ価格の上昇等を踏まえた価格転嫁や支援・協力について総合的に取り組むものとする。」
⑧価格転嫁等に係るフォローアップ
(ア)価格転嫁等に関するアンケートを、下請構造を有する業界については業界団体(127団体)を通じて約1万9,000社に対して、また広く下請け企業の状況も把握するため、民間データ会社を通じて約1万社に対して、それぞれ実施しました。 (イ)適正な取引の好事例等を記載した、業種ごとの「下請取引ガイドライン」(経産省所管13業種)を2014年度内に改訂(14業種)し、ガイドラインに沿った取引適正化に取り組むよう業種ごとに要請しました。
⑨下請代金法による取締りの強化
(ア)2014年10月に選定した200社に加え、2014年度末までに合計約500社の大企業に対し集中的な立入検査を実施しました。 (イ)消費税の転嫁状況の監視・取締りを行う転嫁対策調査官(転嫁Gメン)が立入検査を行う際、原材料・エネルギーコスト増加分の転嫁状況についても厳正に確認しました(2014年10月以降、2014年度末までに590社)【再掲】。
⑩資金繰り支援の強化
日本政策金融公庫及び商工中金において、中小企業・小規模事業者向けの貸付制度として、新たに「原材料・エネルギーコスト高対策パッケージ融資」を創設しました。原材料・エネルギーコスト高などの影響を受け、資金繰りに困難を来たす事業者や省エネ投資を促進する事業者に対して、経営支援を含む手厚い資金繰り支援を行っています。この制度によって、両機関では、2015年5月末までの3か月半の間に、合計約4万6,000件・1兆円の貸付を実施しています(2014年度補正予算額721億円)。
3.2014年度補正予算における対応
2014年度補正予算では、大規模なエネルギーコスト高対策として、計3,601億円を計上しました。その内訳は、省エネルギー・再生可能エネルギーの推進として2,197億円、エネルギー価格の影響への対策として460億円、資源・エネルギーの安定供給として943億円となっています。
(1)省エネルギー・再生可能エネルギーの推進
(ア)地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金【929.5億円】
エネルギーコストの高止まりに苦しむ地域の工場・事務所・店舗等において、最新モデルの省エネ設備・機器の導入や既存設備の更新・改修による省エネの促進を支援します。また、地域できめ細かく省エネの相談に対応するプラットフォームを構築します。
(イ)住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業【150.0億円】
エネルギー消費量が増大している住宅・ビルの省エネを推進するため、ZEHの導入及びZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物の導入を支援します。また、既築住宅・建築物の断熱性能向上を図るため、高性能な断熱材や窓等の導入を支援します。
(ウ)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業【130.0億円】
家庭等に設置される定置用リチウムイオン蓄電池の導入時の費用を補助することで、蓄電池の普及拡大を目指します。
(エ)水素供給設備整備事業費補助金【95.9億円】
2014年12月の燃料電池自動車の市場投入を踏まえ、四大都市圏を中心に民間事業者等の水素ステーション整備費用の補助を行います。また、水素ステーションの適切な整備・運営方法の確立に向けて、水素供給整備を活用して行う、燃料電池自動車の新たな需要創出等に必要な活動費用の補助を行います。
(オ)次世代自動車充電インフラ整備促進事業【300.0億円】
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に必要な充電インフラの整備を加速することにより、次世代自動車の更なる普及を促進し、運輸部門における二酸化炭素の排出抑制や石油依存度の低減を図ります。
(カ)クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金【100.0億円】
燃料電池自動車を含むクリーンエネルギー自動車を対象に、これら車両と同格のガソリン車の価格差の一部を補助し、初期需要を創出します。
(キ)民生用燃料電池(エネファーム)導入支援補助金【222.0億円】
省エネルギー及び二酸化炭素削減効果が高い家庭用燃料電池(エネファーム)の更なる普及の促進を図るため、設置者に対し導入費用の補助を行います。特に新築住宅のみならず、普及が遅れている既築住宅において、既設給湯器からの買換えを重点的に促進します。
(ク)地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金【78.0億円】
地域内での再生可能エネルギー等の最大活用やエネルギー需要の最適化を図り、エネルギーコストを最小化するため、再生可能エネルギー等の分散型エネルギーを面的に利用する先導的な地産地消型システムを構築する取組を支援するとともに、そのノウハウの蓄積、他地域への普及を図ります。
(ケ)独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金【35.0億円】
地域における分散型エネルギーシステムの構築を推進する観点から固定価格買取制度の対象とならない自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム(太陽光発電、風力発電等)やその発電量変動を吸収するための蓄電池の設置補助を行います。
(コ)再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費 補助金【60.0億円】
地域における再生可能エネルギーの熱利用の拡大 を図るため、自治体や民間事業者等による地中熱や 太陽熱など再生可能エネルギー由来の熱利用設備の 導入支援を大幅に強化します。
(サ)次世代エネルギー技術実証事業費補助金【30.0億円】
電力のピーク需要を効果的に削減するため、複数 の工場、業務用ビル等のネガワット(節電量)を管理 し、取引する「ネガワット取引」の制度構築に向けた 実証を行い、地域における安定的かつ効率的なエネ ルギーネットワーク構築に向けた環境を整備します。
(シ)再生可能エネルギーの接続保留への緊急対応 【744.0億円】
再生可能エネルギーの受入可能量の拡大方策を緊 急的に講ずる必要があるため、遠隔で出力制御を可 能とする技術の確立、蓄電池の活用、原子力災害や 津波の被災地における再生可能エネルギー導入支援 等を行います。
(ス)再生可能エネルギー余剰電力対策技術高度化 事業【65.0億円】
再生可能エネルギーの導入拡大による余剰電力対 策用蓄電池として、2020年に揚水発電と同等の設 置コスト(2.3万円/kWh)まで大幅に低減することを 目標とした蓄電池技術の高度化を行います。
(セ) 地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進【2.0億円】
(国土交通省所管) 地域や事業者による電気自動車(バス、タクシー及びトラック)の集中的導入等について、他の地域や事業者による導入を誘発・促進するような先駆的取組を重点的に支援します。
(2)エネルギー価格の影響への対策
(ア)石油製品供給安定化促進支援事業【74.8億円】
サービスステーションの経営安定化につながる高効率計量機や省エネ型洗車機等の整備の導入等を支 援します。
(イ)石油コンビナート事業再編・強靱化等推進事業 【95.0億円】
石油精製コストの低減や石油コンビナートの国際競争力強化につながる生産性向上のため、複数の製油所・石油化学工場等の事業再編・統合運営に対する 支援をします。また、製油所等が首都直下型地震等による被害を受け、石油の安定供給が損なわれることのないよう、①設備の耐震・液状化対策等や、②設備の安全停止対策、③他地域の製油所とのバックアップ供給に必要な入出荷設備の増強対策等を支援します。
(ウ)灯油配送合理化促進支援事業【30.0億円】
老朽化した小型灯油ローリーの大型化や配送用ローリーの共同所有、共同配送システムの導入等による灯油配送の合理化を促進する取組を支援します。
(エ)省燃油活動推進事業【80.0億円】 (農林水産省所管)
燃油コスト削減を図るため、漁業者グループが行う省燃油活動を支援します。
(オ)省エネ機器等導入推進事業【40.0億円】 (農林水産省所管)
漁業者グループが行うLED集魚灯等の省エネ型漁業用機器設備の導入に対して支援します。
(カ)漁業経営セーフティネット構築事業 【100.0億円】(農林水産省所管)
漁業者と国の拠出により、燃油価格や養殖用配合飼料価格が高騰したときに補塡金を交付します。
(キ)中小トラック事業者の燃料費対策事業 【35.0億円】(国土交通省所管)
中小企業が多く投資余力が小さいトラック事業者を対象に燃料費削減に資する設備の導入を支援します。
(ク) 地域公共交通確保維持改善事業【2.3億円】 (国土交通省所管)
国庫補助対象離島航路の存続とサービスレベルの確保を図るため、燃料油価格の高騰によって生じた運営費の増加に対応します。
(ケ)独立行政法人航海訓練所等の燃料費対策 【2.7億円】(国土交通省所管)
船員、航空機操縦士の安定的な供給源である航海訓練所及び航空大学校において、確実に訓練が実施できるよう必要な燃料費を確保します。
(3)資源・エネルギーの安定供給
(ア)メタンハイドレート開発促進事業【20.0億円】
表層型メタンハイドレートの資源量把握のための地質調査や地質サンプル取得等を加速します。
(イ)海底熱水鉱床採鉱技術開発等調査事業【8.0億円】
海底熱水鉱床の生産技術の開発を加速化します。
(ウ)延伸大陸棚等資源開発促進事業費補助金【10.0億円】
我が国が新たに主権的権利を有することとなった延伸大陸棚等の海域において実海域における資源調査等を実施し、海洋鉱物資源の探査・開発の促進を目指します。
(エ)探鉱・資産買収等出資事業出資金【98.0億円】
燃料調達費の低減等に向け、リスクマネー供給の強化により石油探鉱事業を強力に推進します。
(オ)リサイクル優先レアメタル回収技術開発・実証【1.0億円】
レアメタル資源の安定供給確保とともに、持続的な循環型社会の形成を図るため、パソコンや携帯電話等から回収・濃集するための技術開発や、次世代自動車の使用済リチウムイオン電池回収システムの構築及び再生技術の効率化等を支援します。
(カ)低品位炭利用促進技術開発等事業【7.0億円】
輸送時の発火リスク等から現在はほとんど利用されていないものの、より低廉で資源ポテンシャルのある低品位炭を有効活用するための実証事業を加速化して行い、早期の実用化を行うことで、エネルギーコストの低減を図ります。
(キ)代替フロン等排出削減先導技術実証支援事業 【1.0億円】
代替フロン等4ガスのうち、排出量に占める割合の高い冷凍空調分野を中心に、ノンフロン等製品の 開発・普及を大きく加速させるため、指定製品制度における目標値を大きく超えた転換を可能とする製品等に関して、国の補助により機器の設置環境等が異なる場所における技術実証に係る支援を行い、より早期の転換を促進します。
(ク)安定的なエネルギーの確保に向けた海洋資源開 発・海上輸送技術の向上【3.2億円】(国土交通省所管)
シェールガスの安全かつ効率的な海上輸送体制の整備及び浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備の海洋資源開発市場への参入等、エネルギーの安定的な確保を促進します。
(ケ)海洋資源確保に向けた調査研究の加速 【40.0億円】(文部科学省所管)
経済の成長力底上げや持続的な経済成長の実現に必要不可欠な海洋資源の確保に向け、海洋資源ポテンシャル把握に向けた取組を加速します。
(コ) 革新的エネルギー技術の研究開発加速 【4.0億円】(文部科学省所管)
エネルギー貯蔵・利用技術や省エネルギー技術等の有望なシーズの研究開発を加速します。
(サ)核融合研究開発の推進(高性能核融合実験装置(JT-60SA)計画の加速))【7.0億円】(文部科学省所管)
我が国のエネルギー問題等を解決し、将来の基幹的エネルギー源として期待される核融合エネルギーの実現に向け、高性能核融合実験装置JT-60SAにおける研究開発を進めます。
4.中長期的観点からの エネルギーコスト低減に向けた対応
こうした緊急的な対応とともに、中長期的な観点から、エネルギーコスト低減に繋がる取組も進めています。 エネルギー分野の一体改革については、低廉で安定的な電力供給を実現すべく、3段階の電力システム改革の総仕上げを行うとともに、ガスや熱供給の 分野の改革も一体的に進めることで、これまで縦割りであったエネルギー市場の垣根を取り払い、総合的なエネルギー市場を創り上げます。
また、北米からのシェールガス・LNG輸入の実現等を通じた供給源の多角化などにも取り組んでいきます。
(1)電力システム改革
電力の安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を目的とした電力システム改革を実行しているところであり、電気の小売業への参入の全面自由化等を盛り込んだ電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が2014年6月に成立し、2016年を目途に実施されることとなりました。
これにより、一般家庭でも電力会社や多様な料金メニューを選べるようになります。消費者の選択の中で、各電力会社の経営努力や他業種からの新規参入が進むことにより、電気料金の最大限の抑制など消費者にとってのメリットやダイナミックなイノベーションが生み出されることが期待されます。
電力市場における活発な競争を実現する上では、送配電ネットワーク部門を中立化し、適正な対価(託送料金)を支払った上で、誰でも自由かつ公平・平等に送配電ネットワークを利用できるようにすることが必要となります。このため、電力システムに関する改革方針(2013年4月閣議決定)や、電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)の附則で定めた「改革プログラム」に基づき、電力システム改革の第3段階である「法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保や電気の小売料金の全面自由化」や、(2)で後述するガス・熱のシステム改革等を内容とする電気事業法等の一部を改正する等の法律案を、2015年3月に国会に提出しました(後掲 第3部第6章第1節3. 参照)。
(2)ガスシステム改革及び熱供給システム改革
電力システム改革と併せ、縦割りのエネルギー市場の垣根を取り払い、エネルギー供給構造の一体改革を進める観点から、都市ガス及び熱供給の 改革も遅らせることのできない重要な課題です。そこで、電力システム改革と相まって、ガスが低廉・安全かつ安定的に供給され、消費者に新たなサービスなど、多様な選択肢が示されるガスシステム改革や、熱供給に係る需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大するとともに、需要家利益を保護するための熱供給システム改革について、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会において検討を進め、2015年1月に報告書をとりまとめました。
本報告書を受け、ガス小売参入の全面自由化(2017年実施予定)やガス導管網の整備促進、大手3社を対象とした導管部門の法的分離(2022年4月実施予定)、 熱供給事業の料金規制や供給義務の撤廃(2016年実施予定)等の内容を盛り込んだ前述の法律案を2015年3月に国会に提出しました(後掲 第3部第6章第2節2. 参照)。
(3)燃料調達費の低減等
我が国の燃料調達費を低減させるために、シェールガスの生産拡大で価格が低下している米国からのシェールガス・LNG輸入の早期実現や日本企業の上流権益の確保等(オーストラリア、カナダ等)を通じた供給源の多角化、LNG産消会議の開催を始めとする消費国間の連携強化等による買主側のバーゲニングパワーの強化等にも取り組んでいます。
【第133-4-1】電力システム改革の全体像
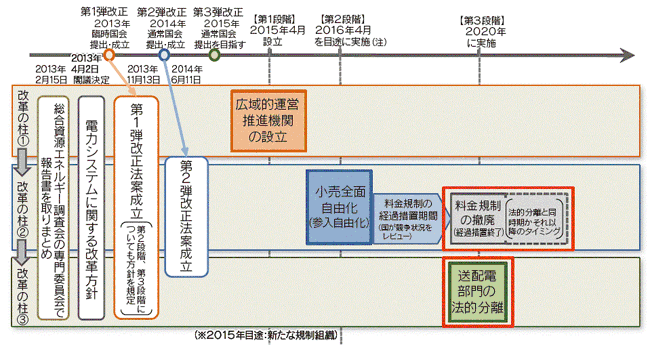
- (注)
- 改革の第2段階の施行は公布日(6月18日)から2年6月を超えない範囲で政令で定める日とされており、2016 年4月の施行を念頭に詳細制度設計を進めている。
- (出典)
- 資源エネルギー庁作成
COLUMN
長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)について
2015年1月より、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会長期エネルギー需給見通し小委員会に おいて、2014年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画を踏まえた将来のエネルギー需給構造の見 通しについて検討が開始され、計8回の議論を経て、長期エネルギー需給見通しの骨子がとりまとめら れました。当該骨子を踏まえ、長期エネルギー需給見通しの決定に向けたプロセスが進められています。
長期エネルギー需給見通し 骨子
1.長期エネルギー需給見通しの位置づけ
長期エネルギー需給見通しは、エネルギー基本計画を踏まえ、エネルギー政策の基本的視点である、 安全性、安定供給、経済効率性、環境適合(以下、「3E+S」)について達成すべき政策目標を想定した上で、 (政策の基本的な方向性に基づいて)施策を講じたときに実現されるであろう将来のエネルギー需給構造 の見通しであり、あるべき姿を示すもの。
マクロの経済指標や産業動向等を踏まえた需要想定を前提にした見通しであるとともに、対 策や技術等裏付けとなる施策の積み上げに基づいた実行可能なものであることが求められる。 なお、今般の長期エネルギー需給見通しは、エネルギー基本計画を踏まえ、中長期的な視点から、 2030年のエネルギー需給構造の見通しを策定する。
2.長期エネルギー需給見通し策定の基本方針
- 3E+Sに関する具体的な政策目標は、安全性を大前提としつつ、以下のとおりとする。
- (1)自給率は震災前を更に上回る水準(概ね25%程度)まで改善すること
- (2)電力コストは現状よりも引き下げること
- (3)欧米に遜色ない温室効果ガス削減目標を掲げ世界をリードすること
- これらの政策目標を同時達成する中で、徹底した省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や 火力発電の効率化などを進め、原発依存度は可能な限り低減させるものとする。
3.2030年のエネルギー需給構造の見通し
上記の基本方針を踏まえた2030年のエネルギーの需給構造の見通しは以下のとおりである。
(1)エネルギー需要及び一次エネルギー供給構造
経済成長等によるエネルギー需要の増加を見込む中、徹底した省エネルギーの推進により、石油危機 後並みの大幅なエネルギー効率の改善を見込む。
このエネルギー需要を前提とした一次エネルギー供給構造は以下のとおり。
震災後大きく低下した我が国のエネルギー自給率は24.3%程度に改善。また、エネルギー起源CO2 排出量は、2013年比▲21.9%減となる(注1,2)。
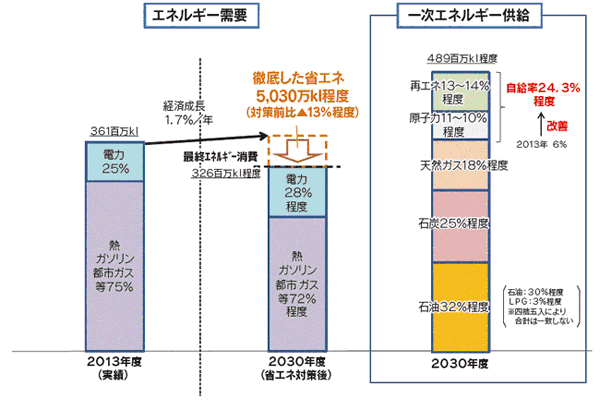
(2)電源構成
このうち、電力需給構造については、徹底した省エネルギー(節電)の推進、再生可能エネルギーの 最大限の導入、火力発電の効率化等を進めつつ、原発依存度を低減した結果、以下のとおり。
経済成長等による電力需要の増加を見込む中、徹底した省エネルギー(節電)の推進及び再生可能エ ネルギーの最大限の導入により約4割を賄うことにより、原発依存度の低減に大きく貢献する。ベース ロード電源比率は56%程度となる。
これにより、現状より電力コストが低減される。
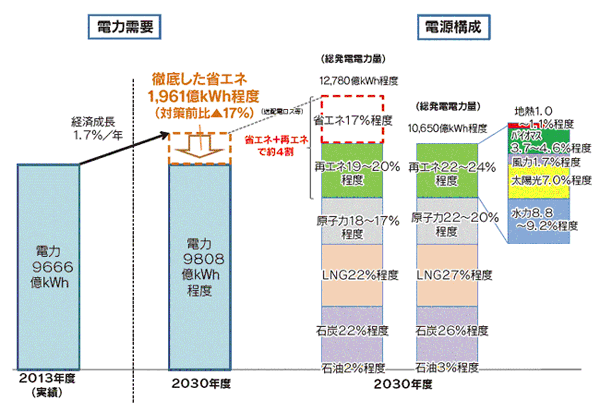
4.各分野の主な取組
(1)省エネルギー
産業、業務、家庭、運輸各部門における省エネルギーの強化を図るとともに、ディマンドリスポンス によるエネルギー消費行動の変革、エネルギーマネジメントの推進等を通じたエネルギーの最適利用に より、スマートな省エネルギーを実現する。さらに、エネファームや燃料電池自動車といった水素関連 技術の活用も推進する。
これらにより、5,030万kl程度の省エネルギーを図り、エネルギー効率を35%程度改善する(2012 ~ 2030年)。
(2)再生可能エネルギー
各電源の個性に応じた最大限の導入拡大と国民負担の抑制を両立する。 このため、自然条件によらず安定的な運用が可能な地熱、水力、バイオマスを積極的に拡大し、それ により、ベースロード電源を確保しつつ、原発依存度の低減を図る。
また、自然条件によって出力が大きく変動する太陽光や風力についてはコスト低減を図りつつ、国民 負担の抑制の観点も踏まえ、大規模風力の活用等により最大限の導入拡大を図る。
(3)火力
非効率な石炭火力発電の抑制に向けた取組等火力発電の高効率化を図り、環境負荷の低減と両立しな がら、その有効活用を推進する。石油火力については必要な最小限の量とする。
また、化石燃料の低廉かつ安定的な供給に向けた資源確保の取組を強化する。
(4)原子力
安全性の確保を全てに優先し、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合する と認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。また、規制基準を満たすこ とにとどまらない不断の自主的安全性の向上、高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定に向けた取組 等を推進する。さらに、原子力依存度の低減や電力システム改革後などを見据えた原子力発電の事業環 境整備を図る。
- (注)
- 原子力発電比率は、2030年時点における電源構成上の見通しを示したものであり、個別の原子力発電所の安全性に関する原子 力規制委員会の審査に影響を与えるものではない。
(5)多様なエネルギー源の活用と供給体制の確保
エネファームを含むコージェネレーション(1,190億kWh程度)等分散型エネルギーの推進による エネルギーの効率的利用の推進、各部門における燃料の多様化等を推進するとともに、これらを支える 供給体制の確保を図る。
(6)2030年以降を見据えた取組
3E+Sに関する政策目標の確実な実現と多層・多様化した柔軟なエネルギー需給構造の構築に向け、 水素をはじめとする新たな技術の活用を推進する。
5.長期エネルギー需給見通しの定期的な見直し
長期エネルギー需給見通しは、省エネルギーの進展、再生可能エネルギーの導入、各電源の発電コス トの状況や原発を巡る動向等を踏まえつつ、少なくとも三年ごとに行われるエネルギー基本計画の検討 に合わせて、必要に応じて見直す。
COLUMN
地方創生と再生可能エネルギー
「地方創生」の重要性が増す中で、地域の資源を活用した再生可能エネルギーの利用推進は、地域に新 しい事業を起こし、地域活性化につながるものであるとともに、緊急時に大規模電源等からの供給に困 難が生じた場合でも、地域において一定のエネルギー供給を確保することに貢献するものとして、全国 各地で取組が進められています。その例として、木質バイオマス、小電力、地熱に関する取組について 紹介します。
地元の木材を有効活用する地域循環型エネルギー
木質バイオマスについては、地域に豊富に存在する資源である木材を有効活用して地域で自立した循 環型システムを構築することが可能ですが、そのためには、安定的にエネルギー源として木材を供給で きる仕組みを確保することが鍵となります。
山形県最上町では、山(森)林が町域の84%を占めており、山(森)林の整備のために間伐が不可欠で すが、費用面等を理由に間伐が進まない状況となっていました。これを解消するため、従来は価値が低 かった間伐材等を有効活用する仕組みを検討、構築しました。
具体的には、GISデータを活用して計画的かつ効率的に間伐を行い、発生した間伐材を福祉センター、 病院、園芸ハウス等の地域施設の冷暖房システムのエネルギー源として供給しています。
間伐材を燃料として安定的に利用することで、間伐費用の手当が可能となり、継続的に間伐が行われ ることで山(森)林の整備、安定的な原料供給、エネルギー需給のバランスの確保といった地域循環型シ ステムの構築が図られています。


- (出典)
- 最上町「森のある暮らし」(
 http://mogami.tv/info/01town-info/09morinoarukurashi.php)
http://mogami.tv/info/01town-info/09morinoarukurashi.php)
地域社会と共生する小水力発電所
鹿児島県内では、県内の豊富な水力資源に着目し、小水力発電が新設されており、県内有力企業と地 元自治体等が連携して事業化が次々と進められています。
そのうち、県内1号機(肝付町)(995kW)については、町内に高齢者が多く病院通いが大変であるこ とから、肝付町が運行している地域循環バスの運用費用の一部を事業者が発電収益から寄付として負担 する等を行っています。
また、県内2号機(霧島市)(980kW)の施工にあたっては、取水口付近が土砂災害の起こりやすい地点 であったことから、事業者が発電所工事の際に河川管理者が行う河川改修と協力しながら実施したこと により、地域の防災機能の向上にも寄与することになっています。
このように、地域との連携を図りながら小水力発電事業の開発が進んでおり、現在、5号機までの計 画が固まり、順次建設されていく予定となっています。
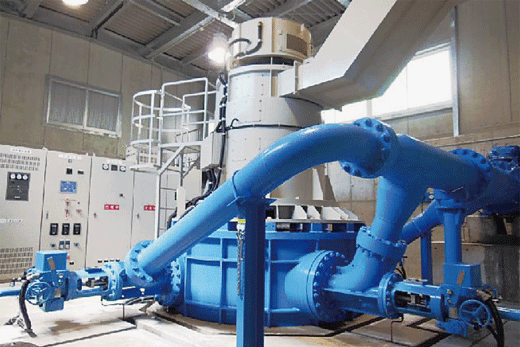
1号機(肝付町)
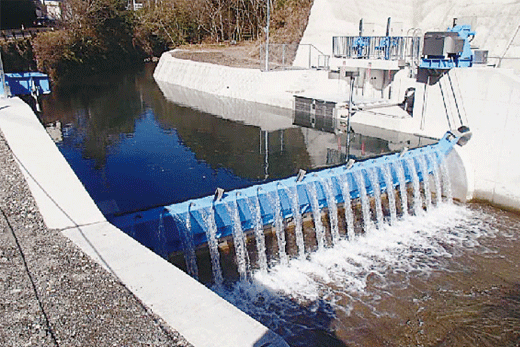
2号機(霧島市)
マグマによって熱せられ、地中深くに閉じ込められている蒸気を、約2kmの井戸を掘って取り出し、 発電するのが地熱発電です。その地熱発電は、発電コストが安く、天候に左右されずに発電できること から、設備利用率が高い電源(約80%)として、ベースロード電源に位置付けられています。また、火 山大国である日本は、アメリカ、インドネシアに次ぐ世界第3位(約2,300万kW)の地熱資源量を有し ており、今後、積極的に導入していくべき電源です。温泉資源などを活用した小型のバイナリー発電に ついても、分散型の再生可能エネルギーとして、地域に新しい産業を起こし地域活性化につながるもの であるとともに、緊急時の非常用電源としても活用可能なものです。
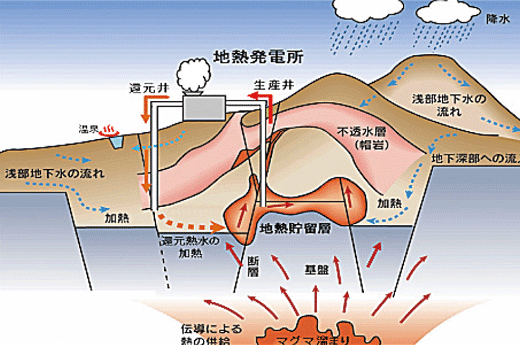
地熱発電の仕組み

北海道森地熱発電所
そんな地熱発電は、電源として重要な役割を担うだけではなく、発電後の熱水を地域に供給すること で、ハウス栽培事業や魚の養殖事業、道路の融雪事業など、農産物や観光資源として各地で活発に行わ れています。
例えば、北海道洞爺湖(とうやこ)町では、洞爺湖温泉利用共同組合が、新たに掘削した泉源を活用し た地熱発電を実施しています。町では、その電力を温泉街の街路灯や電気自動車の充電源などに利用す るとともに、発電後の熱水を使った「温泉たまご(ジオたまご)」を製造し、ホテルや飲食店に提供するな どし、新たな観光商品を開発し、地域活性化に繋げています。

地熱資源掘削調査現場

ジオたまごの製造
他にも、山川発電所(九州電力、鹿児島県指宿市)では、発電に利用できない余剰熱を供給する設備を 設置し、近隣農家(約30棟)への熱供給を実施しており、低コストで高品質な胡蝶蘭(こちょうらん)な どの農産物の育成を行うなどの取組を実施しております。

発電後の熱水を供給する周辺のハウス栽培施設

ハウス栽培で育てられた胡蝶蘭(山川地熱発電所PR館にて)
このように地熱発電は、電力を供給するだけではなく、農産物や観光資源などの地域の活性化にも寄 与することができる電源として、期待されています。
COLUMN
水素社会の実現
周期表で最初に出てくる元素である水素。これまでは、石油化学や半導体加工など、主に工業用途で 活用されてきました。この水素をエネルギーとして活用しようとする取組に注目が集まっています。 水素は、利用段階では二酸化炭素を排出せず、多様なエネルギー源から製造可能です。このため、環 境負荷の低減やエネルギーセキュリティの向上に資する将来の有力な二次エネルギーの一つとして期待 されています。
これまでは、水素をエネルギーとして活用する代表例は宇宙ロケットなどに限られていまし た。我が国の主力大型ロケットであるH-ⅡAロケットは、液化水素を燃料として活用しています。 近年、同じく水素をエネルギーとして活用するものとして、燃料電池を用いた家庭用燃料電池(エネ ファーム)や燃料電池自動車が登場し、エネルギーとしての水素の活用がより身近な用途にも広がりつ つあります。
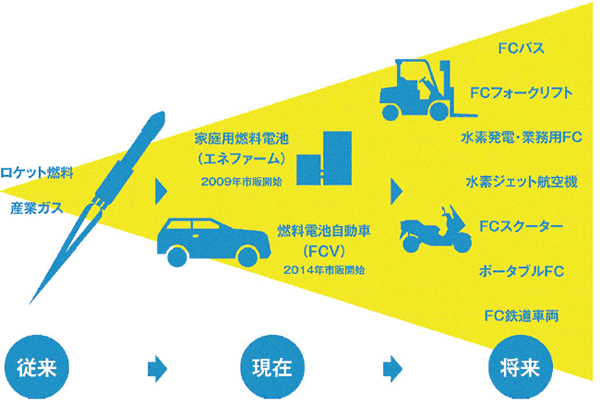
- (注)
- FC=燃料電池
- 水素エネルギー利活用の推進
家庭用燃料電池(エネファーム)等の普及
身近な水素の活用の先駆けは、家庭用燃料電池です。
「エネファーム」という統一名称で販売されている家庭用燃料電池は、燃料電池技術を活用し、都 市ガスやLPガスから取り出した水素と空気中の酸素を反応させることで発電を行います。燃料電池 とは、水素と酸素を化学反応させることで発電を行う発電機です。エネルギーを化学反応により直 接電気に変換するため、エネルギー損失が少なく、NOx等の有害物質をほとんど排出しない上、騒 音もありません。加えて、家庭用燃料電池は発電の際に生じる熱を給湯などに有効活用します。こ れにより、90%を超える高いエネルギー効率を実現し、省エネや省CO2、さらには家庭におけるレ ジリエンスに貢献する機器として、普及してきています(2014年度末時点で、11万台以上が普及)。
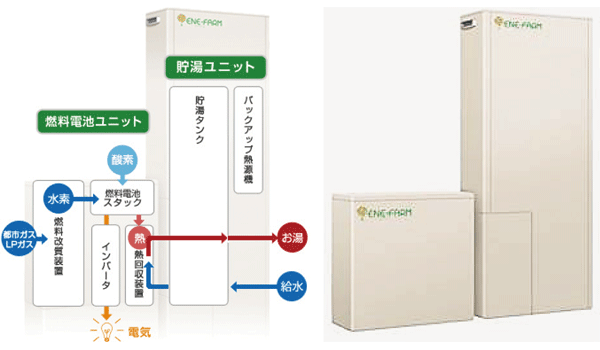
家庭用燃料電池(エネファーム)
- (出典)
- 燃料電池普及促進協会
さらに、家庭用のみならず、業務・産業向けのより大型の燃料電池についても、海外製の業務用燃料 電池が日本に参入するなど注目が集まっています。
我が国企業でも、発電効率の高い固体酸化物形燃料電池を用いた業務・産業用燃料電池の実用化に向 けた実証が進められており、2017年の市場投入を目標として掲げています。
燃料電池自動車の登場
燃料電池自動車(Fuel Cell Vehicle :FCV)は、燃料となる水素と空気中の酸素の化学反応によって 発電した電気エネルギーを用いてモーターを回して走る自動車です。
2014年12月に、トヨタ自動車より燃料電池自動車“MIRAI”が世界に先駆けて発売され、いよいよ 水素を燃料とする燃料電池自動車の普及が始まりました。記念すべき1台目の燃料電池自動車は、総理 官邸に納車され、安倍総理大臣が試乗を行いました。

燃料電池自動車
- (出典)
- トヨタ自動車、本田技研工業

納車式の様子(2015年1月)
燃料電池自動車は、燃料の充填時間が3分程度と短く、航続距離も500km以上と長いなどの特性が あり、既存のガソリン車と同程度の性能を持ちます。また、長年にわたる技術開発で蓄積してきた高度 な燃料電池技術や、燃料となる水素を貯蔵する圧縮水素タンクに用いられる炭素繊維など、燃料電池自 動車に用いられる技術は我が国企業が強みを持つ分野も多く、今後成長が期待される市場でも我が国企 業が競争力を持っていくと考えられます。
水素ステーションの整備加速化
燃料電池自動車の普及に向けては、燃料となる水素を供給するための水素ステーションが不可欠のインフラとなります。
2013年度から、燃料電池自動車の市場投入に向けて、4大都市圏を中心に商用水素ステーションの 先行整備が進められ、2014年7月には、日本初となる商用の水素ステーションが兵庫県尼崎市に開所 しました。2015年6月時点で、国内で81か所(再 生可能エネルギー由来の小型水素ステーションを 含めると85か所)の整備が進められ、うち23か 所が開所済みです。

尼崎水素ステーション
- (出典)
- 岩谷産業
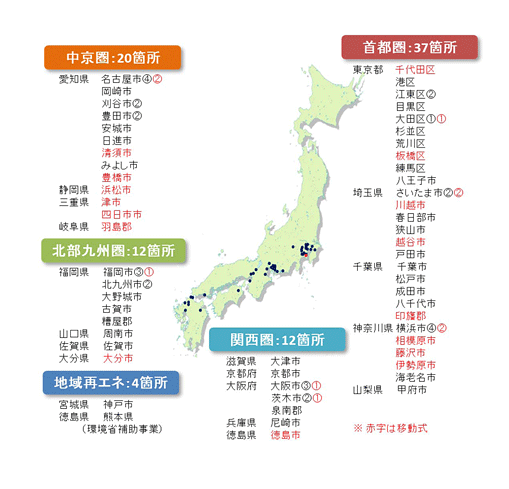
水素ステーション整備状況(2015年6月11日時点)
政府としても、水素ステーション整備に対して補助を行うとともに、水素ステーションに係る規制の 見直しや、部素材の低コスト化に向けた技術開発を行うなど、水素ステーションの整備を後押しする取 組を行っており、引き続き官民の適切な役割分担の下、水素ステーションの整備を拡大していくことで、 燃料電池自動車が日常生活でも利用できる環境を実現していきます。
水素社会の実現に向けて
水素のエネルギーとしての利用は、家庭用燃料電池(エネファーム)や燃料電池自動車だけでなく、バス やフォークリフトなど乗用車以外の車両等についても検討されており、2016年度の市場投入に向けて 様々な技術開発・実証が進められています。また、発電向け燃料として水素を活用する水素発電の取組 も検討されています。

燃料電池フォークリフト
- (出典)
- 豊田自動織機

燃料電池バス
- (出典)
- トヨタ自動車

水素混焼ガスタービン
- (出典)
- 川崎重工業
水素社会の実現には、水素の利用側の取組に加えて、安価かつ環境負荷の低い水素の供給も必要です。
このため、将来、大規模な水素の需要が生じることを想定して、褐炭や副生水素等の海外の未利用エ ネルギーから水素を製造し、国内に輸送するため、有機ハイドライド(水素をトルエン等の有機物と反 応させることで液化して貯蔵・輸送を行う方法)や液化水素(水素を極低温で液化させることで貯蔵・輸 送を行う方法)に関する技術開発が進められています。
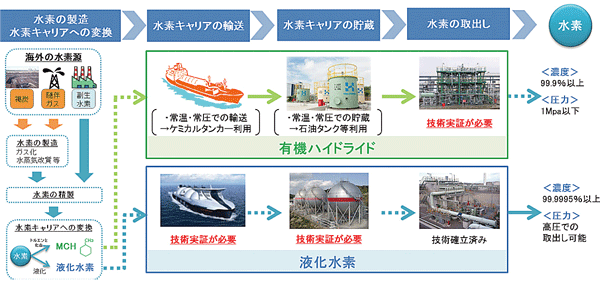
未利用エネルギーを活用した水素供給チェーンの概要
また、再生可能エネルギーからの水素製造も検討されており、自然変動電源である太陽光発電や風力 発電の発電状況に応じて、安価かつ大規模に水素を製造することのできる水素製造装置の開発などが進 められています。加えて、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、余剰となった再生可能エネルギー を水素に変換・貯蔵し、平常時はピークシフト向けに活用しつつ、非常時に備えて貯蔵しておく取組も 進められています。
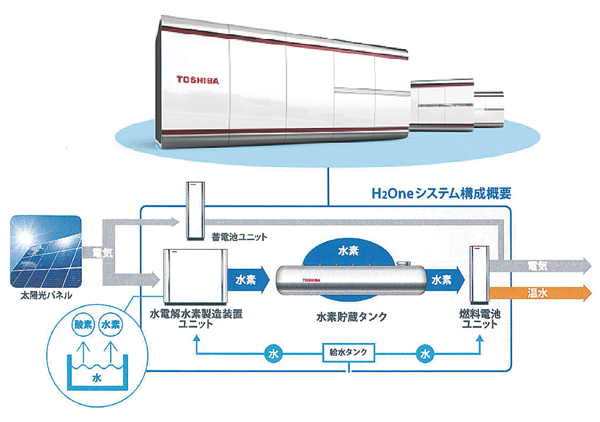
自立型水素エネルギー供給システム
- (出典)
- 東芝
特に、2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会に照準を合わせ、水素エネルギーの活用の 成果を内外に対して発信するための取組も進められています。