第2節 エネルギーコストの影響
ガソリン価格や電気料金などを始めとしたエネルギー関連コストの上昇は、物価の上昇、支出の増加という形で、家庭に影響を与えています。賃金や所得の大幅な改善が見られない中でのエネルギーコスト高は、家庭への負担を増すこととなります。
(1)消費者物価指数から見る影響
全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を表す消費者物価指数において、エネルギー関連の項目を見てみます。
「消費者物価指数年報」(総務省)で、基準年(2010年平均)を100とした場合の物価指数を見ると、全体(総合指数)の変動はごくわずかであるものの、「光熱・水道」は2011年平均103.3、2012年平均107.3、2013年平均112.3、2014年平均119.3と、年々上昇しています。
エネルギー関連の個別項目の2014年平均の消費者物価指数を見ると、「電気代」126.0(前年比8.1%増)、「灯油」138.0(同5.9%増)、「ガソリン」123.2(同4.9%増)と、顕著な上昇が見られます。
(2)家計支出から見る影響
次に「家計調査結果」(総務省)から、家庭(二人以上世帯)における支出の変化を見てみます。
1世帯当たり1か月間の支出のうち、電気代の推移を見ると、震災前の2010年平均では月9,850円(消費支出に占める割合:3.4%)でしたが、2014年平均では月11,203円(同3.8%)と、月1万円を超える支出となっています。
また、ガソリン代などを含む「自動車等維持」の項目についても、2010年平均では月15,538円だったものが、2014年平均では16,480円と増加しています。
家計に占める電気代の上昇率(13.7%)や自動車等維持費の上昇率(6.1%)は、この期間の消費支出全体の上昇率(290,244円から291,194円へ0.3%上昇)、食料費の上昇率(67,563円から69,926円へ3.5%上昇)を大きく上回るなど家計に与える影響は大きなものとなっています。
他方、この期間に減少した費用としては、「教育費」6.9%減、「教養娯楽費」9.2%減、「その他の消費支出」5.2%減の3項目です。このうち、「その他」の詳細を見ると、「こづかい代(使途不明)」(20.0%減)、「仕送り金」(9.5%減)、「交際費」(5.9%減)などの減少が顕著となりました。
エネルギー関連に係る出費がかさむ一方で、こづかい代、教養娯楽費などの出費が抑制されている状況となっています。
【第132-1-1】主な費目における近年の消費者物価指数の推移
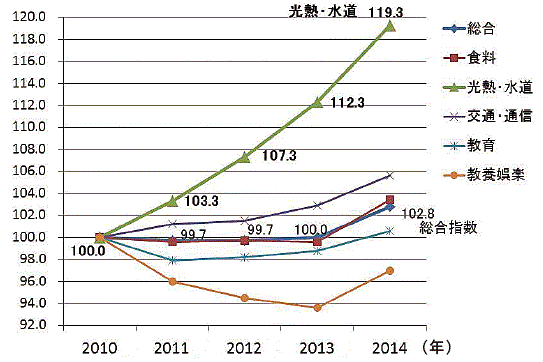
- (出典)
- 総務省「消費者物価指数年報 平成26年」を基に作成
【第132-1-2】エネルギー関連項目における近年の消費者物価指数の推移
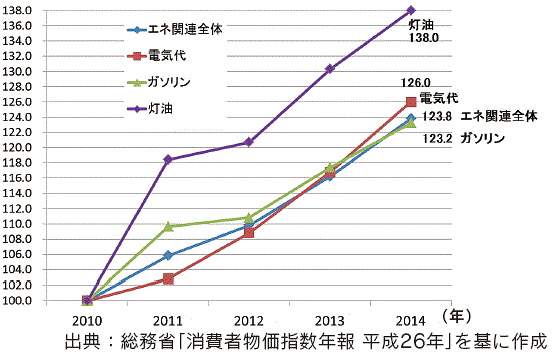
- (出典)
- 総務省「消費者物価指数年報 平成26年」を基に作成
【第132-1-3】石油製品における近年の消費者物価指数の推移
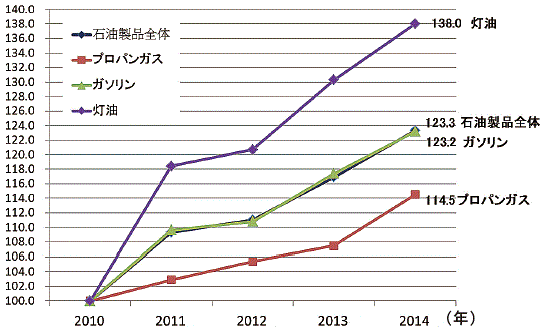
- (出典)
- 総務省「消費者物価指数年報 平成26年」を基に作成
【第132-1-4】電気代等に係る支出額及び増減率(1世帯当たり1か月間の支出(二人以上世帯)
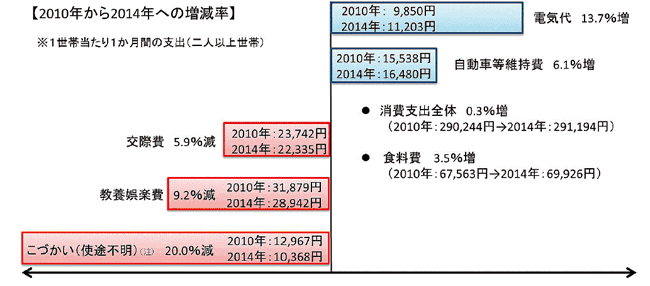
- (注)
- こづかい(使途不明):こづかいのうち使途が不明なもの。
- (出典)
- 総務省「家計調査結果(2014年)」を基に作成
また、2010年から2014年の消費支出全体の上昇に影響を及ぼしている項目を見ると、「光熱・水道」は、「交通・通信」「食料」に次いで、3番目に高い項目となっており、電気代の上昇等が家計に与える影響が大きいことがわかります。
次に、エネルギー関連に係る出費について家計支出に占める割合を地域別に見ると、地方では乗用車の保有率が高いこともあり(注)ガソリン代が、それに加えて寒冷地では灯油代が比較的大きな割合となっており、エネルギー関連費目の高騰は二重三重となって家計に影響を与えています。
- (注)
- 都道府県別の自家用乗用車の世帯当たり普及台数(2014年3月末)を見ると、1世帯当たり普及台数が1台を下回っているのは、兵庫県、京都府、神奈川県、大阪府及び東京都の5都府県のみ((一財)自動車検査登録情報協会HP「自家用乗用車の世帯当たり普及台数(都道府県別)(2014年3月末現在)」参照)。
【第132-1-5】家計支出に占めるガソリン代・灯油代の割合(年間ベース)
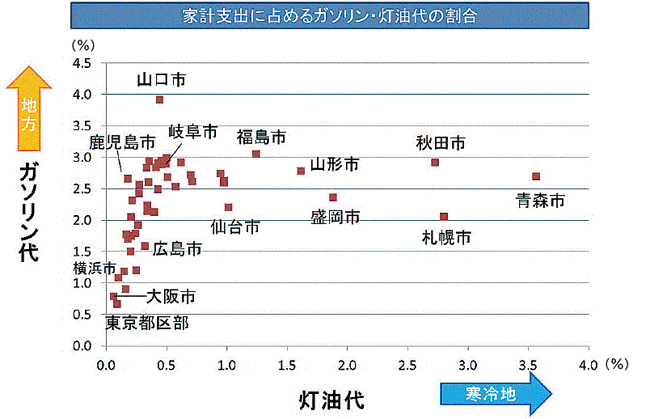
- ※
- 都道府県庁所在地別1世帯当たり年間の支出金額(二人以上の世帯)
- (出典)
- 総務省「家計調査結果(2014年)」を基に作成
さらに、消費支出に占める電気代の割合を年間収入階級別や世帯主の年齢階級別に見ると、年間収入が低い階層や年齢階級が高い層において、その割合は大きくなっており、これらの層にとって電気代高騰の影響は大きなものとなっています。
【第132-1-6】消費支出(年額)と消費支出に占める電気代の割合[年間収入別](二人以上世帯)
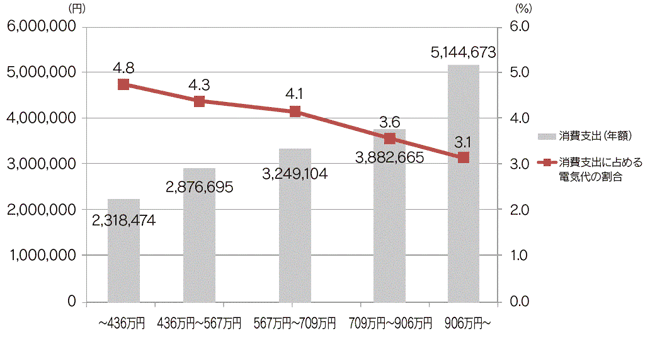
- (出典)
- 総務省「家計調査結果(2014年)」を基に作成
【第132-1-7】消費支出(年額)と消費支出に占める電気代の割合[年齢階級別](二人以上世帯)
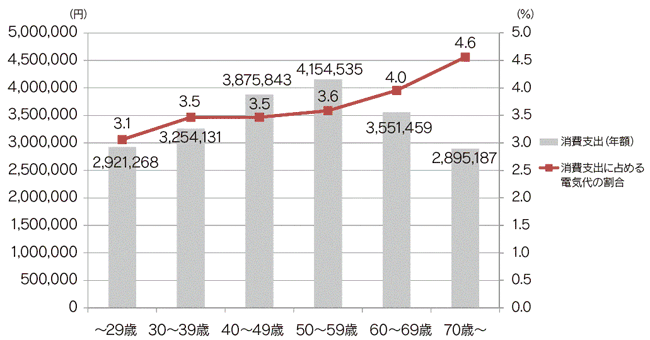
- (出典)
- 総務省「家計調査報告(2014年)」を基に作成
こうした電気料金の上昇を背景に、家庭における節電意識は高まっています。節電に取り組んだ理由について見ると、「節電することが習慣化した」、「環境意識が高まった」との理由を挙げる家庭よりも、「節電をすれば電気代の節約になる」ことを理由に挙げる家庭の方が多数となっています。
実際、家計調査において家庭における電気使用量を見ると、東日本大震災前の2010年(年平均:5,566.3kWh)から直近データの2014年(年平均:5,137.9kWh)にかけて7.7%減少しています。しかしながら、既に見たとおり、この期間の電気代に係る支出は13.7%増加している状況です。
【第132-1-8】2014年度夏季の節電に関するヒアリング・アンケート調査(家庭)概要
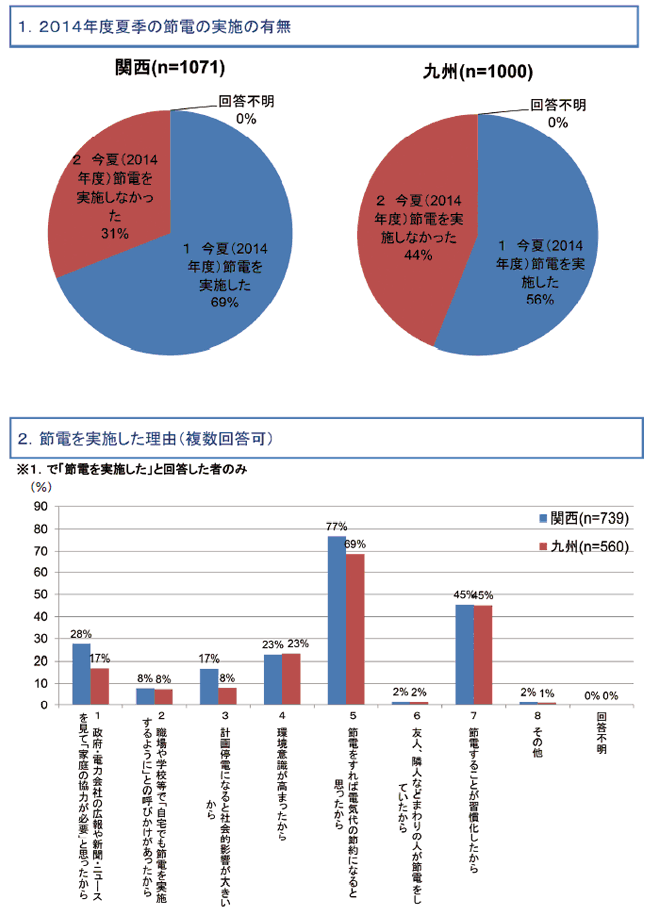
- (出典)
- 2014年10月1日総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力需給検証小委員会(第7回)事務局提出資料
【第132-1-9】 電気代支出額と電力使用量の推移
(支出については、1世帯当たり1か月間の支出(二人以上世帯))
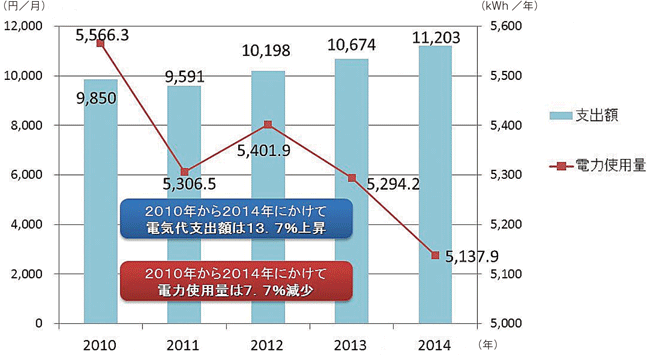
- (出典)
- 総務省「家計調査結果(2014年)」を基に作成
2.産業界への影響
産業界、特に中小企業においては、電気料金の上昇や燃料価格の高騰などのエネルギーコスト高を価格に転嫁できず、経営が非常に厳しいという声が高まりました。
経済産業省が2014年10月に実施した中小企業に対するアンケート調査(注)によると、1年前と比べて原材料・エネルギーコストが増加したとする企業は約8割、そのうち約4割の企業が原材料・エネルギーコストの増加により経常利益が「10%以上圧迫」と回答しています。さらに、半数を超える企業において原材料・エネルギーコスト増を価格へ転嫁することが困難な状況であること、資金不足のため省エネルギーなどの具体的な対策に着手できていないことなどが浮き彫りとなりました。
- (注)
- 経済産業省中小企業庁
「ここ1年の中小・小規模企業の経営状況の変化について」
調査期間:2014年10月2日から10日
回答社数:1,414社
【第132-2-1】企業における燃料費等の販売価格への転嫁状況調
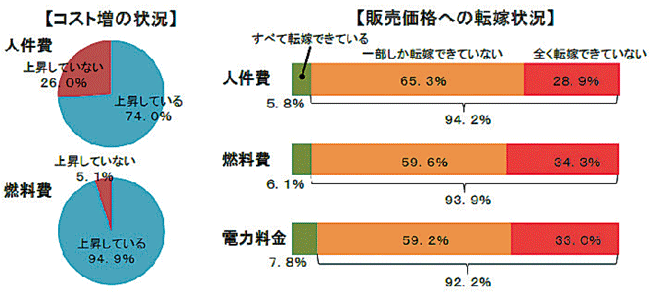
- 調査対象企業数:3,150企業 調査期間:2014年8月15日から21日
- (出典)
- 日本商工会議所「商工会議所LOBO(早期景気観測)2014年8月調査結果」を基に作成
また、企業における燃料費等の販売価格への転嫁状況について見ると(注)、約9割の企業が、燃料費、電力料金を販売価格に「全く転嫁できてない」又は「一部しか転嫁できていない」状況です。
- (注)
- 日本商工会議所
「商工会議所LOBO(早期景気観測)2014年8月調査結果」
調査期間:2014年8月15日から21日
回答企業数:3,150社
東日本大震災直後の1年間(2011年4月から2012年3月)と、2013年9月から2014年8月の1年間の企業における電力コストを見ると、約3割(28.7%)上昇しました。産業界が行った調査(注)において、今後、電力コストが更に上昇した場合、どこまで負担が可能なのか(以下「負担限界」という。)確認したところ、67.2%の企業が「1円/kWhまで」としています。この負担限界を超えた場合の影響としては、従業員の一部を解雇する、設備投資を諦めざるを得ない、経営を続けていくこと自体が難しい状況になるなど、雇用の維持、事業の存続への影響を懸念する声が示されています。
- (注)
- 日本商工会議所「電力コスト上昇の負担限界に関する全国調査」
調査期間:2014年11月25日から12月10日
回答企業数:335社
このように、エネルギー関連コストの上昇は産業界に大きな影響を及ぼしています。例えば鋳造業では、電気料金の上昇により業界全体で年間83億円の負担増と推計されています。これに対応するため、夜間電力を活用した生産体制へのシフトや使用最大電力削減に向けた省エネルギー努力を行っていますが、こうした対応のみで急速なエネルギー関連コストの上昇に対応することは難しく、また、従業員数30人未満の中小企業が8割以上を占める経営基盤の弱い製造業において、エネルギー関連コストの上昇分を取引価格に反映することは困難な状況にあります。このため、とりわけエネルギー多消費産業においては、エネルギー関連コストの上昇が企業の業績、雇用の維持などに直接大きな影響を及ぼしています。
【第132-2-2】電力コスト上昇の負担限界について
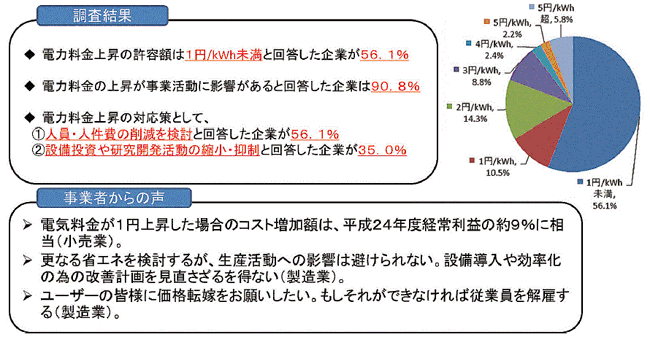
- (出典)
- 日本商工会議所「電力コスト上昇の負担限界に関する緊急調査(2014年11月から12月)結果」を基に作成
【第132-2-3】エネルギー多消費産業の動向
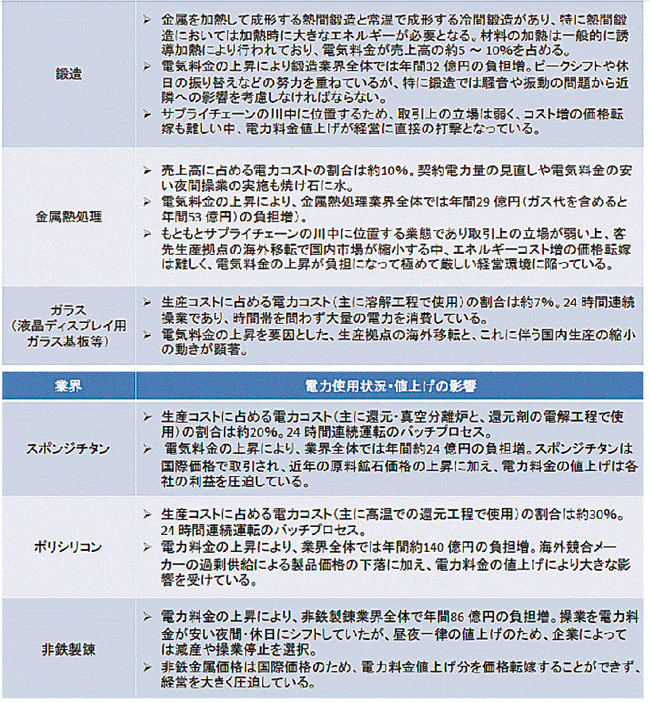
- (出典)
- 経済産業省、厚生労働省、文部科学省「2014年版ものづくり白書」を基に作成
【第132-2-4】エネルギーコスト上昇に対する各業界への影響
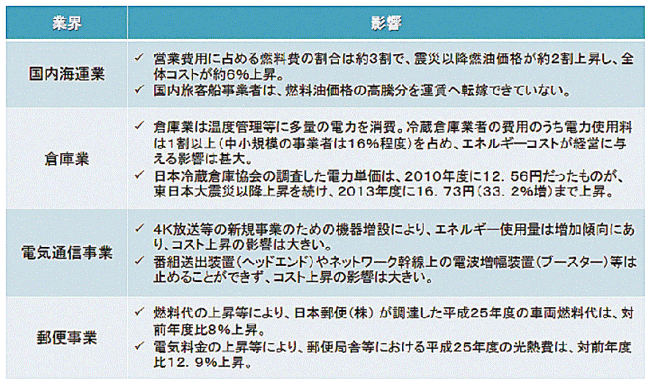
- (出典)
- 「エネルギーコスト上昇に関する関係副大臣会議第1回及び第2回配布資料」を基に作成
3.産業界からの提言、要望等
これまで、エネルギー関連コストの上昇が家庭に加えて、産業界においても大きな負担をもたらすことを見てきましたが、こうした状況を受け、各経済団体からはエネルギーコスト高の是正を求める累次の要望・提言がなされました。
これら要望等では、総じて、東日本大震災後、電気料金や燃料価格などのエネルギーコストの高騰や供給不安が、企業規模を問わず、新たな投資や雇用の拡大を阻害していることが指摘されました。この背景には、電気料金の値上げにより、経営のベースコストを大幅に押し上げるだけでなく、価格転嫁が容易ではない中小企業の収益を大きく悪化させていること、電力の適正価格と安定供給の確保がなければ、大部分の中小企業はさらに疲弊し廃業の増加が大いに懸念されることなどがあり、エネルギーの安価で安定的な供給の実現を求め、エネルギーコスト低減に向けた取組支援策を拡充することが必要であるとされました。
【第132-3-1】2014年に提出された主な要望・提言
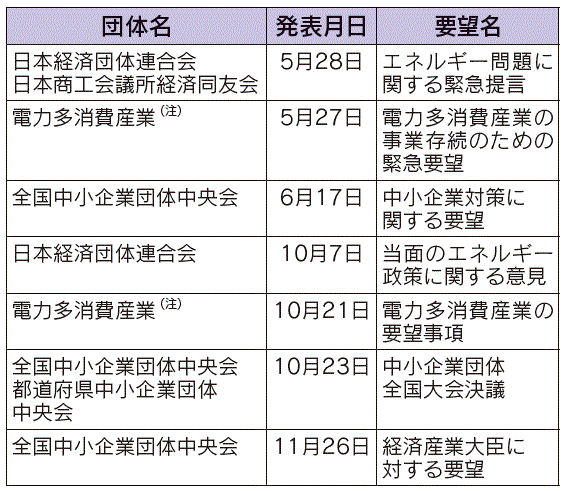
- (注)
- 日本鉄鋼連盟特殊鋼会、新金属協会、日本金属熱処理工業会、日本鉱業協会、日本産業・医療ガス協会、日本ソーダ工業会、日本チタン協会、日本鋳造協会、日本鋳鍛鋼会、普通鋼電炉工業会及び日本鉄鋼連盟