第4節 原子力損害賠償
1. 原子力損害賠償紛争審査会における原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針等
政府は2011年3月11日の東京電力福島第一、第二原子力発電所事故に関して、原子力損害賠償を円滑に進められるよう、原子力損害の範囲など当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定等の業務を行うため、「原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)」に基づき、同年4月11日、「原子力損害賠償紛争審査会」(以下「審査会」という。)を開催しました。
審査会においては、被害者の迅速な救済を図るため、原子力損害に該当する蓋然性の高いものから順次、指針として提示することとしており、2011年8月5日、原子力損害の範囲の全体像を示す「東京電力福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)を策定しました。
その後、審査会では、2011年12月6日に自主的避難等に係る損害に関する中間指針第一次追補、2012年3月16日に政府による避難区域等の見直し等に係る損害についての中間指針第二次追補、2013年1月30日に農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害についての中間指針第三次追補、同年12月26日に避難指示の長期化等に係る損害についての中間指針第四次追補を策定しました。
これらは、賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその範囲等を示したものです。また、これらの指針に明記されていない損害についても、事故との相当な因果関係がある損害と認められるものは賠償の対象となり、東京電力には、個別具体的な事情に応じた柔軟な対応を求めています。
2.賠償の実績
東京電力は、中間指針等を踏まえて、政府による避難等の指示等によって避難を余儀なくされたことによる精神的損害に対する賠償、財物価値の毀損に対する賠償、営業損害に対する賠償等を実施してきました。2021年3月31日時点で、総額約10兆46億円の支払が行われています。2021年3月で東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年が経過しましたが、今後とも、被害を受けた方々の個別の状況を踏まえて適切かつ迅速な賠償を行っていくよう、国としても東京電力を指導していきます。
【第114-2-1】東京電力による原子力損害賠償の仮払い・本賠償の支払額の推移(2021年3月末時点)
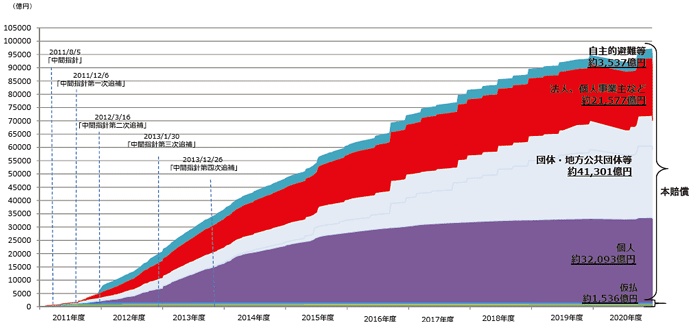
【第114-2-1】東京電力による原子力損害賠償の仮払い・本賠償の支払額の推移(2021年3月末時点)(ppt/pptx形式:116KB)
- 出典:
- 東京電力ホールディングス資料より経済産業省作成
3. 原子力損害賠償紛争審査会における指針等を踏まえた賠償基準の策定
審査会が策定した中間指針及びその追補では、政府による避難等の指示等により避難の対象となった十数万人規模の住民の方々や、事業活動の断念を余儀なくされた多くの事業者等に対して、賠償を行うべき損害項目やその範囲等が示されています。さらに、中間指針等に従って、これまでに順次、損害の種類に応じた賠償の具体的な基準が策定されてきました。
4.原子力損害賠償紛争解決センターの取組状況
原子力損害賠償紛争解決センターは、2011年3月の東京電力福島第一、第二原子力発電所事故により被害を受けた方々の原子力事業者(東京電力)に対する損害賠償請求に対して、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを目的とし、東京都港区と福島県郡山市、福島市、会津若松市、いわき市、南相馬市において業務を行っています。同センターにおいては、事故の被害を受けた方からの申立てにより、仲介委員が当事者双方から事情を聴き取って損害の調査・検討を行い、双方の意見を調整しながら和解案を提示する、和解の仲介業務を実施しています。 同センターでは、2020年末までに26,407件の申立てを受理し、25,692件の手続を終えています。終了した案件のうち、約80%に当たる20,562件が和解成立により終了しています。
また、今後の賠償を円滑に進めていく上での参考とするため、同センターで実施されている和解仲介手続を広く周知し、和解事例を紹介するなど、広報活動を実施しています。具体的には、パンフレットや代表的な和解事例を盛り込んだ小冊子等について、被害者の方々に活用していただくため、被災自治体や関係団体等に配布しました。
さらに、2020年末時点で和解仲介を行う仲介委員を270名配置しており、審理の迅速化を図っています。2020年に和解が成立した事案については、仲介委員の指名から概ね10か月程度で和解案提示が行われ、和解成立に至っています。
5. 原子力損害賠償補償契約に関する法律に基づく措置
政府は、「原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第147号)」に基づき、原子力損害賠償補償契約を原子力事業者と締結しており、地震、噴火等により原子力損害が発生した場合には、この契約に基づく補償金を支払うこととなっています。
東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、政府は、2011年11月、原子力損害賠償補償契約に基づき、同発電所分の1,200億円を東京電力へ支払いました。また、東京電力福島第二原子力発電所において発生した原子力事故についても、原子力損害賠償補償契約に基づき、2015年3月に同発電所分の約689億円を東京電力へ支払いました。
6.原子力損害賠償・廃炉等支援機構
(1)設立・改組の経緯
2011年3月11日の東日本大震災により、東京電力福島原子力発電所事故による大規模な原子力損害が発生したことを受け、同年6月14日に「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」が閣議決定されました。具体的には、政府として、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、
① 被害者への迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置
② 東京電力福島原子力発電所の状態の安定化・事故処理に関係する事業者等への悪影響の回避
③電力の安定供給
の3つを確保するため、「国民負担の極小化」を図ることを基本として、損害賠償に関する支援を行うための万全の措置を講ずることが確認されました。
こうした中、2011年8月10日に「原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)」及び関連する政省令が公布・施行され、原子力事業に係る巨額の損害賠償が生じる可能性を踏まえ、原子力事業者による相互扶助の考えに基づき、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる支援組織を中心とした仕組みを構築するため、同年9月12日に原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)が設立されました。
また、東京電力福島第一原子力発電所について、溶融燃料の取り出しや汚染水の処理など廃炉に向けた取組は、完了までに長い期間を要する極めて困難な事業であり、その推進に当たっては、国内外の英知を結集し、予防的かつ重層的な取組を進める必要があります。そのため、廃炉を適正かつ着実に進められるよう、国が前面に出て、技術的観点からの企画・支援と必要な監視機能を強化する新たな体制の構築に取り組むべく、機構の業務に、「廃炉関係業務」を追加すること等を定めた「原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第40号)」が2014年5月に成立しました。また、同年8月18日に機構が原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組されました。
2016年12月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針について」において、廃炉・汚染水・処理水対策については、東京電力グループ全体で総力を挙げて責任を果たしていくことが必要であり、国はそれに必要な制度整備等を行うこととされたこと等を踏まえ、事故炉廃炉の確実な実施を確保するため、事故炉の廃炉を行う原子力事業者(事故事業者)に対して、廃炉に必要な資金を機構に積み立てさせるべく、機構の業務に「廃炉等積立金管理業務」を追加すること等を定めた「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案」が2017年2月に閣議決定されました。同法案は閣議決定日と同日に国会に提出され、2017年5月に成立し、同年10月に施行されました。
2018年12月には、被害者への賠償を早期に実施するために、国が原子力事業者に仮払いのための資金を貸し付ける仮払い資金の貸付制度の創設や、当該貸付制度に関する業務を国から原子力損害賠償・廃炉等支援機構に委任することができること等を定めた「原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第90号)」が成立し、2020年1月に施行されました。
(2) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構による賠償・廃炉支援の枠組み
①原子力事業者からの負担金の収納
機構は、機構の業務に要する費用に充てるため、原子力事業者から負担金の収納を行います。機構は、毎事業年度、損益計算において利益が生じたときは、原子力損害が発生した場合の損害賠償の支払等に対応するため、損害賠償に備えるための積立てを行います。
②機構による通常の資金援助
機構に、電気事業、経済、金融、法律、会計に関して専門的な知識と経験を有する者からなる「運営委員会」を設置し、原子力事業者への資金援助に係る議決等、機構の業務運営に関する議決を行います。原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を経て、資金援助(資金の交付、株式の引受け、融資、社債の購入等)を行います。
機構は、資金援助に必要な資金を調達するため、政府保証債の発行、金融機関からの借入れをすることができます。
③機構による特別資金援助
(ア)特別事業計画の認定
機構は、原子力事業者に資金援助を行う際に政府の特別な支援が必要な場合、原子力事業者とともに「特別事業計画」を作成し、主務大臣の認定を受けることが必要です。
特別事業計画には、原子力損害賠償額の見通し、賠償の迅速かつ適切な実施のための方策、資金援助の内容及び額、経営の合理化の方策、賠償履行に要する資金を確保するための関係者に対する協力の要請、経営責任の明確化のための方策等について記載し、機構は、計画作成に当たり、原子力事業者の資産の厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底した見直しを行うとともに、原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認します。その上で、主務大臣は、関係行政機関の長への協議を経て、特別事業計画を認定することとなります。
2017年4月には、原発事故に伴う費用が増大する中、福島復興と事故収束への責任を果たすため、東京電力の経営改革に向けた方向性や取組等について議論を行った「東京電力改革・1F問題委員会」において取りまとめられた東電改革提言を反映した「新々・総合特別事業計画(第三次計画)」を認定いたしました。
また、2017年7月、2018年4月、2019年4月及び同年10月には、賠償の迅速かつ適切な実施を確保する観点から、それまでの賠償等の実績や見通しを踏まえた資金援助額とするため、新々・総合特別事業計画の変更について認定いたしました。
(イ)特別事業計画に基づく事業者への資金援助
特別事業計画の認定後、政府は、機構による特別事業計画に基づく資金援助(特別援助)を実施するため、機構に国債を交付し、必要に応じて、機構は政府に対し国債の償還を求め(現金化)原子力事業者に対し必要な資金を交付します。
政府は、国債が交付されてもなお損害賠償に充てるための資金が不足するおそれがあると認めるときに限り、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金の交付を行うことができます。
2021年3月31日時点で、11兆1,644億円の資金援助を決定し、9兆8,181億円の資金を交付しています。
(ウ)機構による国庫納付
原子力事業者は、機構の事業年度ごとに、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対し、一般負担金を納付します。特別事業計画の認定を受けた原子力事業者は、一般負担金に加えて、特別負担金を納付します。
機構は、負担金等を原資として国債の償還額に達するまで国庫納付を行います。
ただし、政府は、負担金によって電気の安定供給等に支障を来し、または利用者に著しい負担を及ぼす過大な負担金を定めることとなり、国民生活・国民経済に重大な支障を生ずるおそれがある場合、予算で定める額の範囲において、機構に対し、必要な資金の交付を行うことができます。
2020年度は、2,572億円を国庫納付しました。
(エ)損害賠償の円滑化業務
機構は、損害賠償の円滑な実施を支援するため、(i)被害者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うとともに、(ii)原子力事業者が保有する資産の買取り、及び(iii)賠償支払の代行(原子力事業者からの委託を受けて賠償の支払、国または都道府県知事の委託を受けて仮払金の支払)を行うことができます。
④ 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の企画・推進
機構は、廃炉等技術委員会の議決及び主務大臣の認可を経て、「廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する業務を実施するための方針」を定めました。この方針に基づき、廃炉を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の企画、調整及び管理に関する業務を実施しています。
その一環として、政府が主導する研究開発事業について、これまでに実施された事業の評価を行うとともに、今後実施する事業の企画に参画しています。
⑤廃炉等積立金の管理業務
事故炉の廃炉を行う原子力事業者(事故事業者)は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、事故炉の廃炉に充てるために必要な資金として機構から毎年度通知される金額を機構に積み立てなければならないとされています。
機構は、当該事業者が積み立てるべき資金の金額について、主務大臣の認可を受けて毎年度額を定めるほか、積み立てられた資金に利息を付すべく廃炉等積立金の運用を行い、廃炉等積立金を取り戻すに当たって必要な取戻し計画を当該事業者と共同で作成する等の業務を行います。また、必要に応じて、当該事業者の本社や現場等への立入検査を行います。
2020年度は廃炉等積立金として約2,600億円を2021年3月に認可しました。また、同年4月には、2021年度から2023年度に必要な金額に係る取戻し計画を承認しました。
⑥ 廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告
機構は、法定業務である「廃炉等の適切かつ着実な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告」及び「廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発」の一環として、「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン」を策定します。今後の廃炉を安全かつ着実に実施するため、中長期的観点から専門的な検討を行い、特に、溶け落ちた核燃料の取り出しや廃棄物の対策について、重点的に検討し戦略を策定します。この戦略については、実効性を高めていくために、現場の状況や研究開発の成果を踏まえて絶えず見直します。また、使用済み燃料の取り出しや汚染水の対策についても、事故収束に向けた技術的な観点から、助言、指導、勧告を行います。