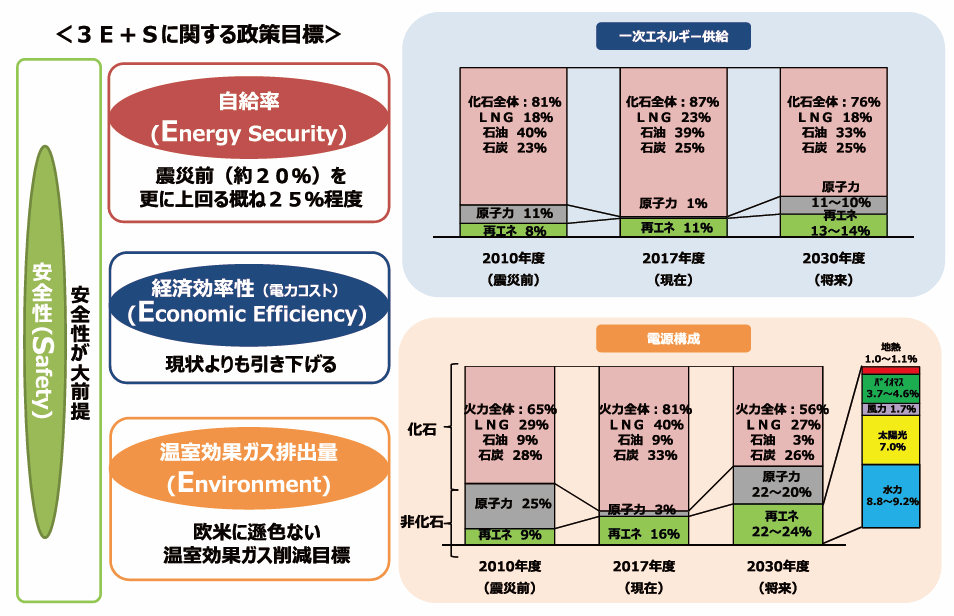第1節 地球温暖化対策を巡る動向(パリ協定の発効等)
1.パリ協定を踏まえた日本の対応
(1)GHG削減に向けた政府の方針(地球温暖化対策計画)
日本のGHG排出の約9割はエネルギー起源のCO2が占めています。日本のINDCは、先立って2015年7月に決定された「長期エネルギー需給見通し」(以下、「エネルギーミックス」という。)と整合的なものとなるよう策定(平成27年7月17日地球温暖化対策推進本部決定)されました。この中において、日本のGHG排出は、エネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能な削減目標として、国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度に2013年度比▲26.0%(2005年度比▲25.4%)の水準(約10億4,200万t-CO2)とすることとされました。
こうしたGHG削減に向けた中期目標は、2016年5月に閣議決定された地球温暖化対策計画の中でも明記されました。また、同計画では、長期的な目標を見据えた戦略的取組として、全ての主要国が参加す公平かつ実効性ある国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80%のGHG排出削減を目指すこととされました。このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難であり、抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに、国内投資を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期的、戦略的な取組の中で大幅な排出削減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献していくこととしています。
- 出典:
- 資源エネルギー庁
(2)エネルギー分野における対応(エネルギー基本計画)
日本のGHG排出量の約9割をエネルギー由来のCO2が占めているため、エネルギー分野でのCO2削減に向けた対応は、温暖化対策を進める上での要となります。こうした問題意識の下、2018年7月に閣議決定された第五次エネルギー基本計画では、2030年のエネルギーミックスの確実な実現へ向けた取組の更なる強化を行うとともに、2050年のエネルギー転換・脱炭素化への挑戦をすることとしています。
① 基本的視点(3E+S)
エネルギー政策の推進に当たっては、生産・調達から流通、消費までのエネルギーのサプライチェーン全体を俯瞰し、基本的な視点を明確にして中長期的に取り組んでいくことが重要です。
エネルギー政策の要諦は、安全性(Safety)を前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図るため、最大限の取組を行うことです。
この3E+Sの原則の下、エネルギー政策とそれに基づく対応を着実に進め、2030年のエネルギーミックスの確実な実現を目指しています。
② 2030年に向けた対応(エネルギーミックスの実現)
我が国が、安定したエネルギー需給構造を確立するためには、エネルギー源ごとにサプライチェーン上の特徴を把握し、状況に応じて、各エネルギー源の強みが発揮され、弱みが補完されるよう、各エネルギー源の需給構造における位置付けを明確化し、政策的対応の方向を示すことが重要となります。
特に、電力供給においては、安定供給、低コスト、環境適合等をバランスよく実現できる供給構造を実現すべく、各エネルギー源の電源としての特性を踏まえて活用することが重要です。
主なエネルギー源ごとの政策の方向性としては、
- -再生可能エネルギーは、2017年度の電源構成では16%となっています。エネルギーミックスの水準で示した22~24%の実現とともに、確実な主力電源化への布石としての取組を早期に進めていきます。そのために、系統強化、規制の合理化、低コスト化等の研究開発などを着実に進めます。
- -原子力は、エネルギーミックスの水準で示した20~22%に対し、2017年度の実績では3%となっています。いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力の再稼働を進めることとしています。
- -石炭火力は、エネルギーミックスで示した26%の水準に対し、2017年度の実績では32%となっています。利用可能な最新技術の導入による新陳代謝を促進することに加え、発電効率を大きく向上し、発電量当たりのGHG排出量を抜本的に下げるための技術等(IGCC、CCUSなど)の開発を更に進めていきます。
こうした施策を通じてエネルギー起源CO2排出を2030年度に2013年度比で25%削減し、NDCの確実な達成を目指しています。
③ 2050年に向けた対応(脱炭素化に向けた、あらゆる選択肢の追求)
エネルギー転換・脱炭素化への挑戦は、我が国の電力・熱・輸送システムの脱炭素化への挑戦と、海外での脱炭素化貢献による大幅な排出量削減、この両面での取組に他なりません。他方、現状、脱炭素化エネルギーシステムの選択肢は複数存在しますが、変動するエネルギー需要に単独で対応が可能な実用段階の選択肢はなく、あらゆる選択肢にはそれぞれの特徴、光と影があります。野心的な目標を着実に実現していくためには、最新の情勢と技術の動向を見極め、その時点で最適な形で、複数の脱炭素化エネルギーシステムを組み合わせ、国内と海外での脱炭素化へ向けた取組を着実に進めていく必要があります。
(3)パリ協定に向けた中期目標と長期戦略
① 中期目標(NDC)
パリ協定においては、第4条の2に「各締約国は、自国が達成する意図を有する累次の国が決定する貢献を作成し、通報し、及び維持する。」と定められており、これがいわゆる中期目標となります。
この中期目標を定めることとなった経緯としては、2013年のCOP19におけるワルシャワ決定により、全ての国に対して,2020年以降の削減目標について、INDCを2015年12月のCOP21に十分先立ち作成することが招請されました。
その後、各国が作成した自国が決定する貢献案は、それぞれの国のパリ協定締結後、NDCとなりました。
2018年のCOP24では、この各国が掲げたNDCの進捗・達成状況等を確認する方法が決定されました。
なお、日本においては、2015年7月に決定した長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)と整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能な削減目標として、国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度に2013年度比▲26.0%(2005年度比▲25.4%)の水準(約10億4,200万t-CO2)にするという「約束草案」を 2015年7月に地球温暖化対策推進本部において決定し、現在UNFCCCに提出しているNDCとなっています。
② 長期戦略(長期低排出発展戦略)
パリ協定においては、第4条の19に「全ての締約国は、各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力を考慮しつつ、第2条の規定に留意して、GHGについて低排出型の発展のための長期的な戦略を立案し、及び通報するよう努力すべきである。」と定められており、長期戦略の策定と提出が努力義務として課されました。
また、2016年11月にパリ協定が発効されるまでは、2016年5月27日のG7伊勢志摩首脳宣言において、2020年の期限に十分先立って今世紀半ばのGHG低排出型発展のための長期戦略を策定し、通報することにコミットすることに合意しました。
そして、現在我が国は、2019年のG20議長国として、環境と成長の好循環を実現し、世界のエネルギー転換・脱炭素化を牽引する決意の下、成長戦略として、パリ協定に基づく、GHGの低排出型の経済・社会の発展のための長期戦略の策定に向けて、その基本的考え方について議論を行うべく、パリ協定長期成長戦略懇談会を開催し、2019年4月2日に提言をとりまとめました。