第3節 次世代電力ネットワークの形成
日本の電力系統(送配電網)は、これまで主として大規模電源と需要地を結ぶ形で形成されてきており、再エネ電源の立地ポテンシャルのある地域とは必ずしも一致しておらず、再エネの導入拡大に伴い、系統制約が顕在化しつつあります。このため、今後、再エネの主力電源化を進める上で、この系統制約を解消していくことが重要です。
さらに、今後の電力ネットワーク形成を検討するに当たっては、2030年以降を見据え、人口減・需要減といった構造的課題や2018年9月の北海道胆振東部地震や2019年の台風15号、19号等による大規模停電を始めとした自然災害に対するレジリエンスの強化を含む系統の在り方等、多様な視点・目的が存在します。これらを踏まえ、日本の電力系統を再エネの大量導入等の環境変化に適応する「大規模電源と需要地をネットワークでつなぐ従来の電力システム」から「分散型電源も柔軟に活用する新たな電力システム」へと長期的に転換していくための環境整備を進めていかなければなりません。
また、2018年10月には、九州エリアにおいて本土初となる再エネの出力制御が行われました。出力が天候等によって変化する変動再エネ(太陽光・風力)の導入が拡大することで、その出力変動を調整し得る「調整力」を効率的かつ効果的に確保することが、国際的にみても、大量の再エネを電力系統に受け入れるための課題になります。
日本の電力系統を再エネの大量導入等の環境変化に適応した次世代型のネットワークへと転換していくため、それぞれの課題を整理しながら道筋を描いていく必要があります。
1.系統制約の克服
(1)既存系統の最大限の活用
日本のこれまでの制度では、新規に電源を系統に接続する際、系統の空き容量の範囲内で先着順に受入れを行い、空き容量がなくなった場合には系統を増強した上で追加的な受入れを行うこととなっています。一方、欧州においては、既存系統の容量を最大限活用し、一定の条件付での接続を認める制度を導入している国もあります。系統の増強には多額の費用と時間が伴うものであることから、まずは、既存系統を最大限活用していくことが重要です。このため、以下のとおり、系統の空き容量を柔軟に活用する「日本版コネクト&マネージ」を具体化し、早期に実現するための取組を進めています。
【第333-1-1】日本版コネクト&マネージの進捗
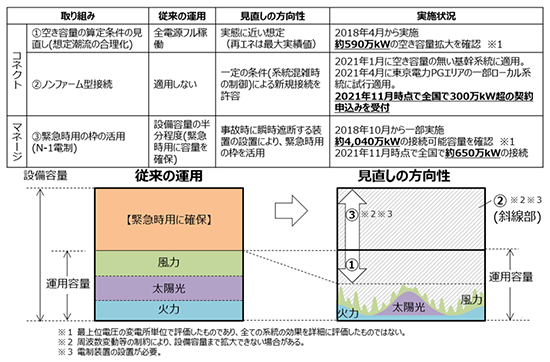
- 資料:
- 経済産業省作成
①想定潮流の合理化
過去の実績をもとに実際の利用率に近い想定を行い、より精緻な最大潮流を想定して送電線の空き容量を算出する「想定潮流の合理化」については、2018年4月から全国的に導入されています。電力広域的運営推進機関(以下、「広域機関」という。)において、想定潮流の合理化の適用による効果として、全国で約590万kWの空き容量の拡大することが確認されています。
②ノンファーム型接続
再エネ導入拡大の鍵となる送電網の増強には一定の時間を要することから、早期の再エネ導入を進める方策の一つとして、2021年1月より全国の空き容量の無い基幹系統において、送電線混雑時の出力制御を条件に新規接続を許容する「ノンファーム型接続」の受付を開始しました。今後、再エネ主力電源化に向けて、基幹系統より下位のローカル系統等についても、ノンファーム型接続の適用の仕方について検討を進めています。また、配電系統への適用については、2020年度から行っている、分散型エネルギーリソース(DER)を活用したNEDOプロジェクトにおいて、必要となる要素技術等の開発・検証を進めています。
③N-1電制
落雷等による事故時には電源を瞬時に遮断する装置(以下、「電制装置」という。)を設置することを条件に、緊急時用に確保している送電線の容量の一部を平常時に活用する「N-1電制」については、2018年10月からその先行適用1が実施され、本格適用2に向けては、2022年度中の開始を目指し、具体的な仕組みの検討を進めています。広域機関において「N-1電制」の適用による効果として、全国で約4,040万kWの接続可能容量が確認されています。
④基幹系統の利用ルール見直し
現行は、送電線の容量制約により、接続されている全ての電源の発電量を流せない場合、後から接続した電源を先に出力制御することとなっています(先着優先ルール)。一方、ノンファーム型接続の電源の増加が予想される中で、新規参入したノンファーム型接続の電源は、系統の空き容量が無い時間帯においては、従来から接続している石炭火力等より先に出力制御を受けることになります。今後は、再生可能エネルギーが石炭火力等より優先的に基幹系統を利用できるように、メリットオーダーを追求した市場を活用する新たな仕組み(市場主導型:ゾーン制やノーダル制)への見直しと早急な実現を目指すこととし、必要な制度面やシステム面の検討を進めながら、当面は、S+3Eの観点から、CO2対策費用、起動費、系統安定化費用といったコストや、運用の容易さを踏まえ、送配電事業者の指令により電源の出力を制御する再給電方式の導入に向けた系統利用ルールの見直しを進めています。また、上位系統の容量制約の対策に向けて、ディマンドリスポンス等、同地域内の分散型エネルギーリソースの有効活用を進めていきます。
(2)出力制御の予見可能性を高めるための情報公開・開示
系統制約が顕在化する中で、発電事業の収益性を適切に評価し、投資判断と円滑なファイナンスを可能とするため、事業期間中の出力制御の予見可能性を高めることが、既存系統を最大限活用しながら再エネの大量導入を実現するために極めて重要です。一方で、発電事業者の事業判断の根拠となる出力制御の見通しを送配電事業者が示そうとすると、安定供給重視の万全の条件とする、見通しよりも高い出力制御が現実に発生する事態を確実に避ける、といった観点から見積り自体が過大となるおそれがあります。
このため、一般送配電事業者が基礎となる情報を公開・開示し、それを利用して発電事業者等が出力制御の見通しについて自らシミュレーションを行い、事業判断・ファイナンスに活用できるよう、①需給バランス制約による出力制御のシミュレーションに必要な情報と、②送電容量制約による出力制御のシミュレーションに必要な情報(「需要・送配電に関する情報」及び「電源に関する情報」)について、新たな情報公開・開示の運用を開始しています。
(3)ネットワーク改革等による系統増強への対応
再エネ電源の大量導入を促しつつ、国民負担を抑制していくためには、電源からの要請に都度対応する「プル型」ではなく、再エネをはじめとする電源のポテンシャルを考慮し、一般送配電事業者や広域機関等が主体的かつ計画的に系統形成を行っていく「プッシュ型」で、再エネ主力時代に応じた次世代の系統形成を進めていく必要があります。
このプッシュ型の考え方に基づき、広域機関において、中長期的な系統形成についての基本的な方向性となる広域系統長期方針や、B/C分析(費用対効果分析)のシミュレーションに基づいて主要送電線の整備計画を定める広域系統整備計画を定めることとしました。この広域系統長期方針と広域系統整備計画を併せていわゆる「マスタープラン」とし、これに基づき、送配電事業者が実際の整備を行います。全国の再エネ導入見込みへの対応、電力融通の円滑化によるレジリエンス向上に向けて、全国大での広域連系系統の形成を計画的に進めるため、広域機関によって送電網整備のマスタープランの中間整理が2021年5月に取りまとめられました。今後、2022年度中を目途に完成を目指していきます。
また、プッシュ型の系統形成に当たって、特に地域間連系線等を増強することは、広域メリットオーダーや再エネの導入による環境への負荷軽減効果や燃料費用の削減といった効果があり、こうした効果は全国大で需要家が裨益するものと考えられます。しかし、従来の費用負担の考え方では、地域間連系線等の増強費用は増強する連系線の両側の地域が負担することが原則であり、今後再エネの地域偏在性によって地域間で系統増強にかかる負担格差が生じるとの懸念がありました。このため、連系線等の増強に伴う便益のうち、広域メリットオーダーによりもたらされる便益分は受益者負担の観点から原則全国負担とし、特に再エネへの導入促進効果が認められる範囲で、全国一律の賦課金方式を活用することや、連系線の送電容量が不足していることで市場分断が生じ発生する卸電力取引市場の値差収益を活用することを促すための制度整備を行いました。今後、こうしたプッシュ型系統形成の実際の導入に向け、関係機関と協力しながら、さらに取組を進めていきます。
【第333-1-2】電力系統の増強
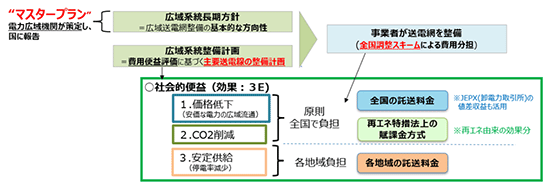
- 資料:
- 経済産業省作成
2.調整力の確保・調整手法の高度化
(1)出力制御
太陽光発電・風力発電といった再エネ電源は天候や日照条件等の自然環境によって発電量が変動する特性があるため、地域内の発電量が需要量を上回る場合には、電気の安定供給を維持するため、発電量の制御が必要となります。こうした場合、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則や広域機関の送配電等業務指針で定められた優先給電ルールに基づき、火力発電の抑制、揚水発電のくみ上げ運転による需要創出、地域間連系線を活用した他エリアへの送電を行います。それでもなお発電量が需要量を上回る場合には、再エネの出力制御を実施することとされており、太陽光発電の導入が急速に進む九州エリアでは2018年10月に本土初となる再エネの出力制御が行われました。加えて、2022年4月には、四国・東北・中国エリアで、同年5月には、北海道エリアでも初めて再エネの出力制御が行われました。こうした出力制御は送電線に再エネをより多く送電線につなぐために必要な取組であり、スペインやアイルランドといった再エネ先進国でも変動する再エネを無制限に発電しているわけではなく、むしろ適切な制御を前提とすることで送電線への接続量を増やすための取組として採用されています。
再エネの出力制御を低減させるための取組として、①地域間連系線の更なる活用による他エリアへの送電、②実需要に近いタイミングでの柔軟な調整を可能にするオンライン制御の拡大、③火力等発電設備の最低出力の引下げ、④発電事業者間の公平性及び効率的な出力制御を確保するための出力制御の経済的調整等が挙げられます。このうち①については、連系線の運用改善や、転送遮断システムまた特高再エネ出力制御システムの活用による電源制限量の確保等によって、再エネの送電可能量を段階的に拡大してきました。また、②について、まずは2022年度に出力制御が発生する蓋然性が高いエリアにおいて、オフライン事業者におけるオンライン化への切替率を、例えば2から3年内に1割増やすことを目指すこととしています。当該目標を達成するため、オンライン化のメリットを引き続き周知していくことに加え、メリットを特段感じない事業者に対し、どのようにオンライン化を促していくか、引き続き検討を進めていきます。③については、エネルギー政策の基本方針であるS+3Eを大前提に、火力等発電設備の最低出力の引下げにより、結果的に安定供給が損なわれることがないよう、既存設備への影響を念頭に、全国の火力等発電設備の実態や今後の対応可能性について、引き続き丁寧に確認を続けつつ、取組を進めていきます。④については、2022年早期のオンライン代理制御(オフライン事業者が本来行うべき出力制御をオンライン事業者が代わりに実施し、オフライン事業者が出力制御を行ったとみなして、オンライン事業者が発電を行ったものとして、通常の買取価格で対価を受ける仕組み)の導入を目指し、技術的課題の検討等を進めています。
【第333-3-1】再エネ発電量と出力制御の関係
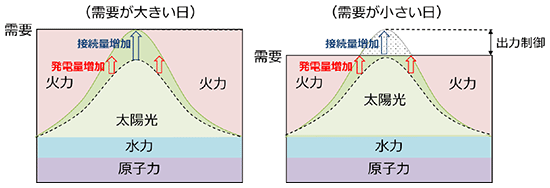
- 資料:
- 経済産業省作成
(2)グリッドコードの整備
変動再エネの導入拡大に伴い、急激な出力変動や小刻みな出力変動等に対応するための調整力の必要性が高まり、電力システムで求められる対応が高度化することから、今後、変動再エネが有する制御機能や柔軟性を有する火力発電・バイオマス発電の調整力としての重要性が一層高まっていくことが予想されます。そこで日本においては、実効性や手続きの適正性が担保されている「系統連系技術要件」をグリッドコードの中心に位置づけ、発電機の個別技術要件は原則として「系統連系技術要件」に規定していくこととしました。また、本個別技術要件の具体化は、機能性・適切性・透明性の確保をしつつ、包括的かつ実効的な審議が可能な枠組みの中で実施すべく、広域機関を中心に検討を進めていくこととなりました。これを踏まえ、2020年9月には広域機関によりグリッドコード検討会が開始され、必要な技術要件を2023年には「系統連系技術要件」に規定すべく、日本での再エネ導入拡大に伴う課題と解決策の検討、「系統連系技術要件」に規定する個別技術要件等の選定、具体的要件内容の検討、議論が進められています。