第4節 燃料アンモニアの導入拡大に向けた取組
1.燃料アンモニアの背景・概要
(1)燃料アンモニア利用に向けた経緯
燃料として利用するアンモニア(以下、「燃料アンモニア」という。)は、燃焼してもCO2を排出しないゼロエミッション燃料であり、地球温暖化対策において有効な手段の1つとなっています。「新国際資源戦略」(2020年3月策定)においては、そのカーボンフリーの特性とグローバルサプライチェーンが確立済みという利点から、「今後は、火力発電や工業炉、船舶等からのCO2削減に向け、水素と同様に、諸外国で生産された再生可能エネルギーを石油や天然ガスと同様にエネルギー資源として捉えて輸入するというコンセプトを強く意識しながら、現在FSが進められている燃料アンモニアの混焼を含めて、着実に技術開発等を進めることが必要である」と、その利用拡大を明記しています。
燃料アンモニアの利用に向けて、技術面においては、2014 ~ 2018年における内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)での研究開発において、燃料時における窒素酸化物(NOx)の排出抑制が可能となり、それを受けて新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)でのフィージビリティスタディ事業を実施しているところです。他方で、今後、燃料アンモニアの実際の利用とその拡大に対応するためには、技術面のみならず、サプライチェーン面も検討する必要があり、需要者・供給者等の民間企業と政府の連携が不可欠となっています。
(2)アンモニアの概要
アンモニアは、現在、その大半が天然ガス等の化石燃料から製造されています。また、技術的には、再生可能エネルギーによる製造も可能です。前者の場合は改質反応、後者の場合は電気分解によって水素を製造し、いずれもハーバー・ボッシュ法によってアンモニアを製造する流れとなります。これらアンモニア製造により発生するCO2は、CCU/カーボンリサイクルやCCS(EORを含む)によって抑制することが可能です(第384-1-1)。
【第384-1-1】燃料アンモニア製造方法
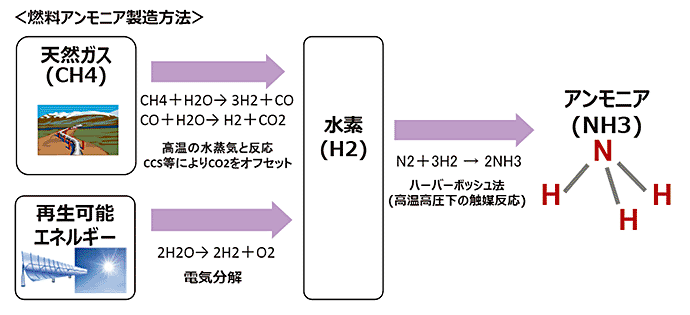
- 出典:
- 経済産業省作成
これまでアンモニアは「水素基本戦略」(2017年12月26日関係閣僚会議決定)において、水素キャリア(液化水素、MCH等)の一つとして位置づけられ、液化水素やMCHと比べて、運搬が容易である点に優位性が見出されています。他方で、前述の技術開発によって、燃焼してもCO2を排出しないゼロエミッション燃料、すなわち「燃料アンモニア」として火力発電や工業炉、船舶(燃料電池を含む)等への直接利用が可能となっています。
特に火力発電への直接利用においては、アンモニア専焼(アンモニア火力発電)によって発電設備からのCO2排出量削減に大きな効果を期待できます。そのためには、まずは専焼に向けた過程である混焼技術の早期実現が求められるところ、アンモニアと石炭は混焼が容易であることから、先ずは石炭火力発電への利用が見込まれています。また、船舶業界においても、2018年に国際海事機関(IMO)がGHG削減戦略・目標を打ち出して船舶部門の脱炭素化を推進しており、アンモニアの船舶用燃料としての利用が期待されています(第384-1-2)。
【第384-1-2】燃料アンモニア利用の概略
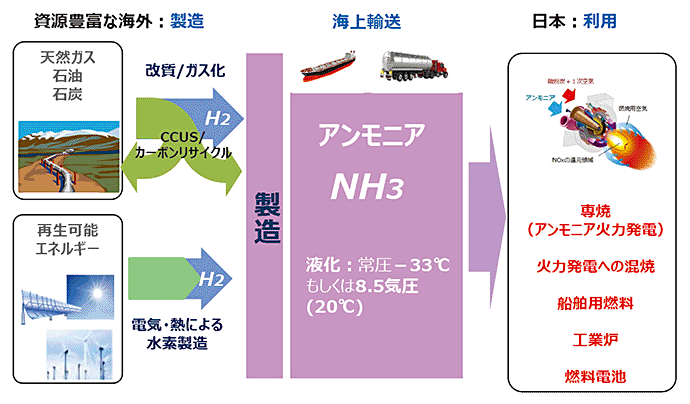
- 出典:
- 経済産業省作成
2. アンモニアの現状と燃料アンモニアの導入・拡大における課題
(1)アンモニアの「ゼロエミッション」
先に述べたとおり、アンモニアは燃焼してもCO2を排出しないゼロエミッション燃料です。近い将来に実現が期待される石炭火力発電での20%混焼(エネルギーベースでの20%。以下同じ。)によっても、CO2排出量は20%削減となります。これは超々臨界圧発電(USC)への20%混焼で、1,700℃級(石炭ガス化複合発電(IGCC)以上のCO2排出係数となることを意味します。
また、アンモニアの利用により我が国におけるCO2排出が抑制されることに加えて、ライフサイクルで見た場合、その外国での炭化水素からのアンモニア製造においてCO2が排出されることに留意し、その排出されるCO2を適切に処理していくことも重要です。
(2)アンモニアの価格動向
現在行われているアンモニア取引は化学原料用のものですが、その市場価格としては、輸出港を念頭に置いた「カリブ海産(トリニダード・トバゴ)」、「黒海産(ロシア)」、「中東産」、「東南アジア産(インドネシア、マレーシア)」と、需要地を念頭に置いた「CFR欧州」、「CFR米州」、「CFRインド」、「CFR極東(中国、韓国、台湾、日本)」が存在しています。我が国の輸入価格は「CFR極東(中国、韓国、台湾、日本)」を中心に、「中東産」、「東南アジア産(インドネシア、マレーシア)」を参照して決定されています。
こうした市場価格は原油価格に相関性を有しており、最近の原油価格低迷を受けて、2020年10月時点のアンモニア価格は300米ドル/トン程度となっています。
アンモニアの製造・輸送にかかる費用の概算は以下のとおりですが、製造(ハーバーボッシュ法)・輸送・貯蔵というサプライチェーンの各段階で既存の技術を活用することが可能なことから、アンモニア同様にゼロエミッションである水素と比較して専焼や混焼時の発電価格を抑えることが可能となっています。仮に石炭火力発電に20%のアンモニア混焼を行った場合の発電価格は12.9円/kWhと試算され、石炭火力の発電価格(2015年コスト検証WGの試算では10.4円/kWh)の1.2倍程度となっています。また、今後の技術開発が必要ではあるものの仮に専焼(アンモニア発電)を行った場合には、23.5円/kWhと試算することができます。(なお、(第384-2-2)での「アンモニア専焼設備」では、既存の石炭火力発電所建設費に加えて、港湾の受入・貯蔵・払出設備追加費、専焼バーナー及びボイラー改修費を含めて試算しています。)
【第384-2-1】燃料アンモニアの価格動向
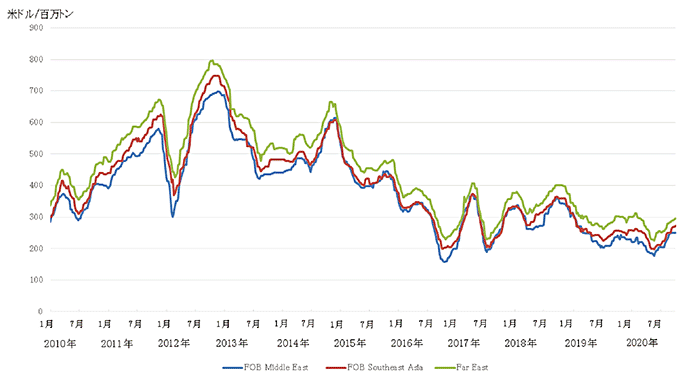
- 出典:
- 燃料アンモニア導入官民協議会中間とりまとめ資料より抜粋
【第384-2-2】水素・アンモニア発電のコスト比較
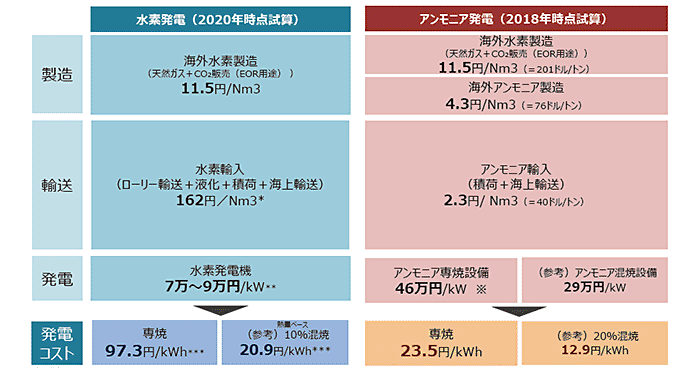
- 出典:
- * 事業者ヒアリングに基づき試算
** 富⼠経済「2020年版⽔素利⽤市場の将来展望」⽔素ガスタービン発電
***発電コスト検証WGより試算
・アンモニア製造・輸⼊コスト:⽇本エネルギー経済研究所SIP「CCS・EOR技術を軸としたCO2フリーアンモニアの事業性評価」をもとに資源エネルギー庁試算
・アンモニア混焼設備、発電コスト価格:電源開発SIP「⽕⼒発電燃料としてのCO2フリーアンモニアサプライチェーンの技術検討」
・アンモニア専焼設備、発電コスト:事業者へのヒアリング等をもとに資源エネルギー庁試算 - ※
- 「アンモニア専焼設備」では、既存の⽯炭⽕⼒発電所建設費に加えて、港湾の受⼊・貯蔵・払出設備追加費、専焼バーナー及びボイラー改修費を含めて試算
このように、現在の我が国の発電価格と比較してもアンモニアによる混焼・専焼のコストは一定程度の競争力を持つものと考えられますが、当然ながら、そのコスト負担を下げる取組は更に求められます。
また、地域による製造コストの差異はあるものの、現時点では、再生可能エネルギーから製造されたアンモニア(グリーンアンモニア)に比べ、天然ガスや石炭を原料としたアンモニア(グレーアンモニア)の価格競争力は極めて高い状況です。また、天然ガスや石炭を原料として開発・製造段階で生じるCO2をCCU/カーボンリサイクルやCCSによって回収したアンモニア(ブルーアンモニア)についても、グリーンアンモニアと比較して1/2 ~ 1/3程度の価格となっており、依然として価格競争力が高くなっています。
【第384-2-3】製造方法毎のコスト比較
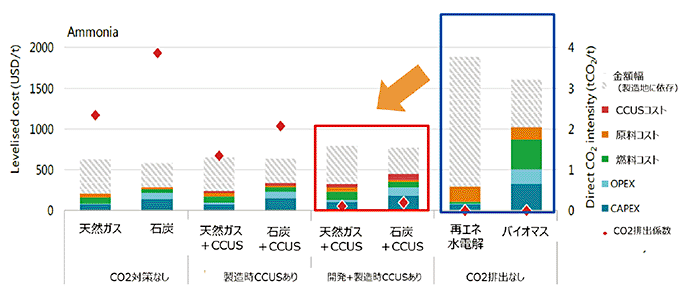
- 出典:
- IEA, The Future of Hydrogen
(3)アンモニアの市場規模
アンモニアの市場は、既に肥料用途や工業用途といった原料用で確立しています。世界の原料用アンモニア生産は2019年で年間約2億トン程度であり、そのうち貿易量は1割(約2,000万トン)で、ほとんどが地産地消されています。日本国内で見ると、原料用アンモニア消費量は約108万トン(2019年)であり、国内生産は約8割、輸入は約2割(輸入元はインドネシア及びマレーシア)と、世界的に見ても小規模な市場となっています。
既にこうした原料用市場が存在している一方、その規模が限られる中で、今後新たに燃料用途での活用を進めていくに当たっては、市場価格の高騰を防ぎつつ、安定的に必要量を確保していくことが必要となります。
今後、石炭火力発電にアンモニアの20%混焼を実施すると、1基(100万kW)につき年間約50万トンのアンモニアが必要となります。例えば、国内の大手電力会社の全ての石炭火力発電で20%の混焼を実施した場合、年間約2,000万トンのアンモニアが必要となり、現在の世界全体の貿易量に匹敵します。そのため、これまでの原料用アンモニアとは異なる燃料アンモニア市場の形成とサプライチェーンの構築が課題となります。
3. 燃料アンモニアの導入・拡大に向けた方策
(1)「燃料アンモニア導入官民協議会」の設立
2020年10月に我が国は2050年にカーボンニュートラルを目指すことを宣言したことで、その実現に向けた方策の具体化が政府全体で進められる中、そして同時に次期エネルギー基本計画に向けた検討が総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の場で進められる中、燃料アンモニアの利用拡大に向けた検討も加速化するべく、同月に「燃料アンモニア導入官民協議会」が設立されました。
同協議会は、燃料アンモニアの利用拡大に向けた課題を整理し、解決に向けたタイムラインを官民で共有し、一体となって取組を進めることを目的としています。同協議会での議論を通じて整理された課題や方向性については、2020年12月25日に経済産業省が、関係省庁と連携して策定した「グリーン成長戦略」の14の重要分野の1つ(「②燃料アンモニア産業」)として盛り込むとともに、第3回(2021年2月)に中間取りまとめを行いました。この成果については、グリーン成長戦略の改定に向けた深堀や次期エネルギー基本計画に向けた議論に反映されていくことになっています。
【第384-2-4】アンモニアの市場規模
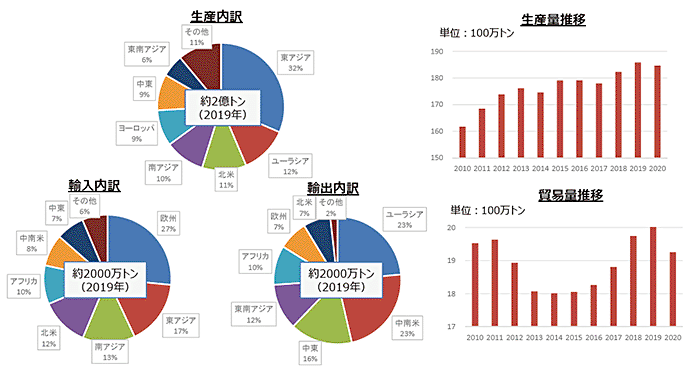
- 出典:
- 三菱商事の資料をベースに一部加工
(2)燃料アンモニアの導入・拡大に向けた4つの視点
上記協議会の中間取りまとめにおいては、我が国における2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、官民が以下の視点を理解して取組を実施していくことで、燃料アンモニアの導入・拡大を着実に進めていくこととしています。
①安定確保
電力燃料の安定確保は、言うまでもなく、極めて重要です。2020年12月以降の電力需給のひっ迫の一因はLNGの安定調達に支障が生じたことでした。将来的に燃料アンモニアが電源構成に実質的な割合を占める段階では、レジリエンスの観点から燃料アンモニアを安定的に調達することが必要不可欠です。
燃料アンモニア供給の安定化を図るため、調達先国の政治的安定性・地理的特性に留意した上で、単に外国事業者からアンモニア調達するのではなく、天然ガスの上流権益や安定的な再生可能電源を確保するなどして、我が国企業が中長期的に安定してアンモニアをコントロールできる形での調達に努めます。また、中長期的には、供給途絶の影響を最小限にとどめるため、調達先等をできるだけ分散していくことが重要です。
②コスト低減
将来的なアンモニア専焼を目指し、今後混焼を導入・拡大した場合には、アンモニアの燃料コストが電力料金等に占める割合は増大していきます。2020年代に火力発電への混焼の実用化に進むためにも、競争力のある燃料アンモニアを確保し、サプライチェーンを確立することが不可欠です。燃料アンモニアの調達、生産、輸送/貯蔵、利用、ファイナンス等においてコスト低減を図ります。
③環境配慮
2050年カーボンニュートラルに向けてアンモニア専焼(アンモニア火力発電)の実現を目指していきますが、それに向けては、ステップ・バイ・ステップでの移行が現実的です。第一段階は火力発電へのアンモニア混焼の実現ですが、製造国との関係(製造国の法制度等)にも留意しつつ、当面は製造プロセスでのCO2の処理がなくとも、燃料アンモニアの導入・普及を図っていくべきです。その上で、一定の導入・普及後には、生産時に排出されるCO2についてはCCS、カーボンリサイクル、植林、ボランタリークレジットによるオフセット等から適切な手段を通じて、合理的な形でCO2排出の処理を行います。
また、非化石価値の顕在化等を通じて、アンモニア由来の電気が評価される環境整備を図ります。
④海外展開
将来においても電源構成の相当程度を火力発電が占めるであろうアジア諸国をはじめ世界の脱炭素移行に貢献するため、同時に我が国のグリーン産業の成長を促すため、国内での専焼・混焼技術の確立及びその普及と並行して、海外への燃料アンモニアに係る技術やノウハウの展開を図ります。また、そのために、燃料としてのアンモニアの国際的な普及を後押しする規格・標準化等の環境整備を図ります。
(3)燃料アンモニアの導入・拡大に向けたロードマップ
また、同協議会の中間取りまとめにおいては、以下のような燃料アンモニア導入・拡大に向けたロードマップも策定しています。今後、このロードマップに基づいて、官民で連携していくこととしています(第384-3-1)。
【第384-3-1】燃料アンモニア導入・拡大に向けたロードマップ
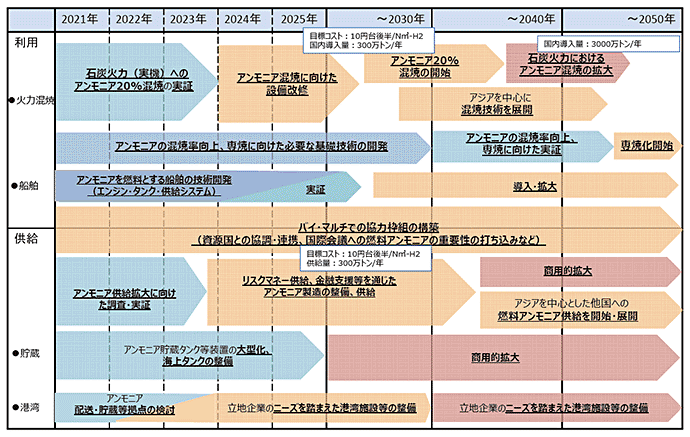
- 出典:
- 経済産業省作成
<具体的な主要施策>
1.次世代火力発電等技術開発
(再掲 第5章第1節 参照)