第1節 電源の特性に応じた制度の構築
現行のFIT制度においては、再エネ発電事業者が発電した再エネ電気を電気事業者が買い取ることが法律によって義務付けられています。再エネ発電事業者自身は市場取引を免除されていることにより、再エネ発電事業者の発電収入が予見可能なものとなり、再エネ発電事業の投資インセンティブが強固に担保されています。その一方で、再エネ発電事業者にとっては、電力市場の需給状況や市場価格の変動によらず、どの時間帯に発電を行っても固定価格での買取りが保証されているため、需給がひっ迫し、市場価格が高い時に売電を行うといった電力市場の需給状況に応じた発電行動をとるインセンティブが生じず、それを受け入れる系統側のコストが増大する等、電力システムへの悪影響が生じています。
こうした状況も踏まえ、再エネの主力電源化を実現していくためには、再エネ発電事業者が「市場取引を免除する措置」から脱却し、「市場への統合」を進め、電力市場において他の電源と同様な売電行動を促していくことが必要です。我が国に先行してFIT制度を導入してきた諸外国においても、再エネの電力市場への統合に向け、既にFIT制度から別の制度への移行が進んでおり、我が国においてもこうした事業環境の整備を進めていくことが求められています。その一方で、発電コストの低減状況や、その導入状況、地域貢献の程度などについては、電源によって様々であり、電源ごとの特性に応じた制度的アプローチを具体的に検討していく必要があります。
主力電源化小委員会においては、こうした電源の特性に応じた制度の在り方について議論が進められ、概ね以下のような方向性が取りまとめられました。
1.主力電源化に向けた2つの電源モデルと政策の方向性
競争電源に係る制度の在り方
大規模事業用太陽光発電や風力発電といった、技術革新等を通じて発電コストが確実に低減している電源、または低廉な電源として活用し得る電源については、今後、さらにコスト競争力を高めてFIT制度からの自立化が見込める電源として、現行制度の下での入札を通じてコストダウンの加速化を図るとともに、再エネが電力市場の中で競争力のある電源となることを促す制度を整備していくことが必要です。
その際、FIT制度で確保されている投資インセンティブについては、再エネのコスト競争力が他の電源と比較してまだ十分でないことに鑑みれば、引き続きその確保が必要と考えられる一方、FIT制度に基づく市場取引の免除については、電力システムへの悪影響を生じさせている状況を踏まえ、その見直しが必要です。こうしたことから、FIT制度に代わり電力市場への統合を図る新制度の在り方として、ドイツやフランスといった欧州等を中心に導入が進んでいる「FIP(Feed in Premium)制度」を念頭に検討していくことが適当であると考えられます。
①FIP制度について
FIP制度は、再エネ発電事業者が、発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で自ら自由に売電し、そこで得られる市場売電収入に、「あらかじめ定める売電収入の基準となる価格(以下、「FIP価格」という。)と市場価格に基づく価格(以下、「参照価格」という。)の差額(=プレミアム)×売電量」の金額を上乗せして交付することで、再エネ発電事業者が市場での売電収入に加えてプレミアムによる収入を得ることにより、投資インセンティブを確保する仕組みです。
FIP価格は、FIT制度における調達価格に対応するものであり、その水準の決定が実質的にプレミアムの額の水準を規定します。また、参照価格は、卸電力取引市場の電力価格の実績の平均を基礎に算定されることが想定されます。この両者の差額がプレミアムとして発電事業者に付与されることで、発電事業者は他の電源と同様に市場取引等による売電を行いつつ、そこで得られる売電収入に加えて一定のプレミアムの上乗せを受けることができるため、再エネ事業の投資インセンティブを確保しつつ、電力市場への統合に向け、市場を意識した発電行動を促していくことができます。
その際、FIP制度により発現する効果は、FIP価格が固定であるため、参照価格の変更頻度によって変わってきます。市場で電力取引を行う再エネ発電事業者の売電収入は、時間帯・季節による市場変動に加え、長期の気候変動や長期的な市場価格の下落などにより投資回収の予見性を著しく損なうリスクにさらされており、参照価格の期間や算定方法の設定に当たっては、こうしたリスクを最小化し、かつ日中・季節変動の中で市場価格に応じた発電・売電行動(市場価格が低い時期に定期メンテナンスをする、蓄電池を活用する等)に誘導できるような設定を行うことが必要です。
【第331-1-1】FIP制度の概要について
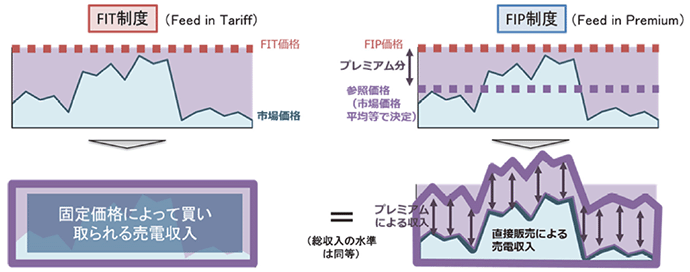
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
②再エネの市場取引を進めていくための環境整備について
FIT制度における市場取引を免除された特例的な仕組みを見直し、FIP制度への移行を通じて他の電源と同様に市場取引を行う仕組みへと改めていくためには、様々な環境整備が必要です。
まず再エネの市場統合を進めていくためには、再エネ発電事業者自らが、発電した再エネ電気の市場取引等を行う必要があります。その具体的な方法としては、①自ら卸電力市場取引を行う方法、②小売電気事業者との相対(直接)取引を行う方法、③アグリゲーターを介して卸電力取引市場における取引を行う方法、の3つが想定され、こうした取引を通じて再エネ発電ビジネスの高度化や電力市場の活性化が期待されます。一方で、電気を買い取る側の小売電気事業者にとっては、発電予測や出力調整が難しいFIP電気(再エネ電気)を相対取引するインセンティブが低い可能性もあるため、発電予測支援ビジネスやアグリゲーション・ビジネスの活性化のための環境整備を進めていくことも重要です。FIT制度からFIP制度へと移行してもなお引き続き再エネの導入を拡大させていくためには、アグリゲーターが小規模再エネ由来のものも含めたより多くの再エネ電気を効率的・効果的に市場取引することが、期待されます。
また、通常、発電事業者は、常に需要の増減に合わせて自らが発電する電気の量をバランスさせることが求められており、事前の計画値と実際の実績値に差分が発生した場合には、その調整に係る費用のの負担(インバランス負担)分を支払わなければなりません。しかし、FIT電源については、再エネ発電事業者の代わりに一般送配電事業者または小売電気事業者が、発電計画を作成し、計画と実績のずれであるインバランスリスクを負う「FITインバランス特例制度」が設けられています。FIT制度において免除されてきたインバランス負担についても、今後再エネの市場統合を図っていくためには、他電源と同様に再エネ発電事業者にその負担が課されることが適切であると考えられます。発電予測技術や小売電気事業者・アグリゲーターとの契約ノウハウを持たない再エネ発電事業者が新たに市場に出てくることを踏まえた負担軽減のための経過措置も検討しつつ、発電事業者にインバランスの発生を抑制するインセンティブを持たせていくことが必要です。
(2)地域活用電源に係る制度の在り方
需要地に近接して柔軟に設置できる電源(住宅用太陽光発電、小規模事業用太陽光発電等)や地域に賦存するエネルギー資源を活用できる電源(小規模地熱発電、小水力発電、バイオマス発電等)については、災害時のレジリエンス強化等にも資するよう、需給一体型モデルの中で活用していくことが期待されています。したがって、自家消費や地域と一体となった事業を優先的に評価するため、一定の要件(地域活用要件)を設定した上で、当面は現行のFIT制度の基本的な枠組みを維持していく方向で検討を行っています。
①自家消費型の地域活用要件
小規模事業用太陽光発電は、立地制約が小さく需要地近接での設置が容易である電源です。このため、需要地において需給一体的な構造として系統負荷の小さい形で事業運営がなされ、災害時に活用されることで、全体としてレジリエンスの強化に資することを要件とする「自家消費型」の地域活用要件を設定することが必要です。
特に、低圧設備(10 ~ 50kW)については、地域でのトラブル、大規模設備を意図的に小さく分割することによる安全規制の適用逃れ、系統運用における優遇の悪用などが発生し、地域での信頼が揺らぎつつあります。地域において信頼を獲得し、長期安定的に事業運営を進めるためには、全量売電を前提とした野立て型設備ではなく、自家消費を前提とした屋根置き設備等の支援に重点化し、地域に密着した形での事業実施を求めることが重要です。このため、主力電源化小委員会や調達価格等算定委員会での議論も踏まえ、低圧設備については、2020年度から、自家消費型の地域活用要件をFIT制度の認定基準として求めることとなりました。一方で、高圧以上設備(50kW以上)については、地域での活用実態やニーズを見極めつつ、引き続き検討を深めていきます。
自家消費型の具体的な要件については、主力電源化小委員会や調達価格等算定委員会での議論を踏まえ、まず、自家消費を行う設備構造を有し、かつ需要地内において自家消費を行う計画であることを求めることとします。その際、ごく僅かしか自家消費を行わない設備が設置され、全量売電となることを防ぐため、厳格な自家消費の確認を行っていきます。加えて、災害時に活用するための最低限の設備を求めるものとして、災害時のブラックスタート(停電時に外部電源なしで発電を再開すること)が可能であること(自立運転機能)を前提とした上で、給電用コンセントを有し、その災害時の利活用が可能であることを求めることとしました。
営農型太陽光発電設備については、営農と発電の両立を通じて、エネルギー分野と農林水産分野での連携の効果も期待されるものもある中で、一部の農地には近隣に電力需要が存在しない可能性もあることに鑑み、農林水産行政の分野における厳格な要件確認を条件に、自家消費を行わない案件であっても、災害時の活用が可能であれば、自家消費型の地域活用要件を満たすものとして認めることとしています。
②地域一体型の地域活用要件
小規模地熱発電・小水力発電・バイオマス発電については、FIT制度開始以降も、導入スピードは緩やかであり、発電コストの低減が進んでいません。FIT制度は、再エネ導入初期において、国民負担を通じた導入拡大によるコストダウンを図り、将来的に自立的な導入が進むことを目指した時限的措置であることを踏まえると、これらの電源については、地域に賦存する資源エネルギーを活用できるという特性を活かし、その地域への便益を内在化させながら、将来的な自立化を目指すことが求められます。これらの電源も自家消費型での活用を拡げる可能性が期待されるものですが、立地制約が大きいことから、自家消費型だけでなく、「地域一体型」の地域活用要件を設定する方向で議論が進められました。
地域一体型の具体的な要件については、調達価格等算定委員会での議論を踏まえ、①災害時(停電時)の電気の活用が地方自治体の防災計画等に位置付けられていること、②災害時(停電時)の熱の活用が地方自治体の防災計画等に位置付けられていること、③地域が再エネ発電事業に自ら取り組むものとして、地方自治体が再エネ発電事業に自ら取り組むものであること、または地方自治体が再エネ発電事業に直接出資するものであること、のいずれかを求めることとしました。また、地域マイクログリッド(平時は系統配電線を活用し、緊急時にはオフグリッド化して地域内に電力供給を行う方法)についても、将来的に方法が確立した時点で要件とすることとしています。
その上で、小規模地熱発電・小水力発電・バイオマス発電は、系統接続・地元調整等に要するリードタイムが長いことを踏まえ、調達価格等算定委員会の意見を踏まえ、2020年度及び2021年度のFIT認定案件については、推奨事項として地域活用を求めるものと位置付けつつ、FIT制度の認定要件としての施行時期は2022年4月とすることとしました。また、事業者の予見可能性を確保するため、2022年度に地域活用電源となり得る(地域活用要件が支援の要件となり得る)可能性がある規模について、小規模地熱発電は2,000kW未満、小水力発電は1,000kW未満、バイオマス発電は10,000kW未満とされています。
2.需給一体型の再エネ活用モデルの促進
世界及び日本において、①太陽光発電コストの急激な低下、②デジタル技術の発展、③電力システム改革の進展、④再エネを求める需要家とこれに応える動き、⑤多発する自然災害を踏まえた電力供給システムの強靱化(レジリエンス向上)の要請、⑥再エネを活用した地域経済への取組、といった大きな変化が生じています。加えて、2019年11月以降順次、FIT調達期間を終え、投資回収が済んだ安価な電源として活用できる住宅用太陽光発電(FIT卒業電源)が出現しています。
こうした構造変化により、「大手電力会社が大規模電源と需要地を系統でつなぐ従来の電力システム」から「分散型エネルギーリソースも柔軟に活用する新たな電力システム」へと大きな変化が生まれつつあり、こうした変化を踏まえ、自家消費や地域内系統の活用を含む需給一体型の再エネ活用モデルをより一層促進することが求められています。こうしたモデルの普及のために、民間の様々なサービスやEVを始めとした新たな分散型エネルギーリソースもあわせ、新たなビジネス創出の動きを加速化するための事業環境整備が必要です。
そのため、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(以下、「再エネ大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」という。)において、特に発電と自家消費の需給の範囲ごとに(1)家庭・大口需要家、(2)地域の単位で、それぞれの論点と方向性について検討を行いました。
(1)家庭・大口需要家
住宅用太陽光発電の価格低下による自家消費のメリットの拡大やFIT卒業太陽光の出現により、今後は、自家消費や余剰電力活用の多様化が進んでいくことが期待されます。自家消費率向上にはZEHが有効な施策の一つですが、これまでのZEHは、余剰売電を前提として普及していたことが課題となっており、今後、自家消費のメリットが大きくなる中で、再エネ導入を一層拡大しつつZEHを普及させるためには、自家消費率向上に有効な機器の導入を支援し、余剰電力を売電ではなく他の住宅やEVなど他の電力需要へ融通することも可能とするなど、新たなZEHの在り方を検討すべきです。また、大手電力会社・新電力ともに余剰電力を狙った買取りメニューを発表しており、余剰電力を活用する市場が活性化することが期待されます。
事業用太陽光発電についてもコスト低下が著しく、RE100加盟やESG投資等もあいまって、大口需要家においてもオンサイト発電の第三者所有サービスやオフサイトの非FIT再エネ電源の活用などFIT制度を前提としない再エネ自家消費モデルが出始めてきています。
このような需要家側の需給一体型の再エネ活用モデルが出始めてきているところ、一層これらを推進すべく、今後対応すべき課題として、主に①再エネ価値の見える化(再エネ活用に対するインセンティブを高める取組)、②中核技術の普及(PV&EVモデルの促進/蓄電池の普及拡大/VPP等のエネルギー統合技術)、③既存電力システム・制度との調和、④プラットフォームの形成について検討を行いました。
(2)地域
再エネ電源を自律的に活用する地域での需給一体的なエネルギーシステムは、エネルギー供給の強靱化(レジリエンス)、地域内エネルギー循環、地域内の経済循環などの点で有効です。そのため、地域の再エネをコージェネレーションなどの他の分散型エネルギーリソースと組み合わせて利用するなど、地域レベルで再エネを需給一体的に活用する取組について、より取組を行いやすくするための仕組みの在り方や、他分野の政策と連携強化等について、さらに検討を深めていくことが重要です。
また、自営線を活用してエネルギーを面的に利用する分散型エネルギーシステムの構築については、導入コスト等の採算面や工事の大規模化が大きな課題となっています。こうした課題には、地域の再エネと既存の系統配電線を活用し、災害等の大規模停電時には自立して電力を供給できる地域マイクログリッドの構築が有効であり、その制度的・技術的課題の整理を行い、事業環境の整備につなげていく必要があります。
また、こうした検討を踏まえ、官民が連携して課題分析を的確に行うとともに、分散型エネルギーに関係するプレイヤーが共創していく環境を醸成することを目的として、「分散型エネルギープラットフォーム」を開催しました。当該プラットフォームは、経済産業省と環境省が共同で、多様なプレイヤーが一堂に会し、取組事例の共有や課題についての議論等を行う場を設けることで、こうした幅広いプレイヤーが互いに共創する機会を提供するものです。
第1回(2019年11月1日開催)では、分散型エネルギーシステムについての事例紹介を交えたプレゼンテーションを通して、議論の論点を整理しました。また、第2回(2020年1月29日開催)及び第3回(2020年2月17日開催)では、「家庭」、「大口需要家」、「地域」という需要地ごとに、分散型エネルギーモデルを普及させるに当たっての課題について、グループ別にディスカッションを実施するとともに、第4回(2020年3月19日Web配信にて開催)では、ディスカッションされた分散型エネルギーモデル普及に向けた課題等について報告を行いました。とりまとめにおいては、本プラットフォームにおいて提案された分散型エネルギーモデル普及に向けた施策について、必要に応じて適切な場において検討を続けるとともに、プレイヤーが共創する環境を醸成するための次なるステップについても検討を進めることとしています。
3.認定案件の適正な導入と国民負担の抑制
(1)新規認定案件のコストダウンの加速化
現在、我が国の再エネの発電コストは国際水準と比較して依然高い水準にあり、FIT制度に伴う国民負担の増大をもたらしています。我が国の再エネの発電コストが高い原因として、例えば、太陽光発電については、①市場における競争が不足し、太陽光パネルや機器等のコスト高を招いていることや、②土地の造成を必要とする場所が多く、台風や地震の対策をする必要があるなど、日本特有の地理的要因が工事費の増大をもたらしている、といった点が挙げられます。
FIT制度では、発電事業者・メーカー等の努力やイノベーションによる再エネの発電コストの低減を促すため、中長期の価格目標を定めています。2019年4月から、事業用太陽光発電の「2030年発電コスト7円/kWh」という目標を5年前倒すとともに、住宅用太陽光発電についても、事業用のコスト低減スピードと合わせて、「売電価格が卸電力市場価格並み」という価格目標を達成する年限を「2025年」と設定しました。また、風力発電(陸上・洋上(着床式))については、引き続き、「2030年発電コスト8?9円/kWh」という価格目標の実現に向けて、コスト低減の取組を深掘りしていきます。さらに、その他の電源については、「FIT制度からの中長期的な自立化を目指す」という目標が掲げられており、この目標に向けて、コスト低減を進めていく必要があります。
また、再エネの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、FIT制度では、入札により調達価格を決定することが国民負担の軽減につながると認められる電源については、入札対象として指定することができることとされています。事業用太陽光発電は、2017年度の入札制度導入以降、入札対象範囲を「2,000kW以上」としていましたが、競争性を確保するため、2019年度から対象範囲を「500kW以上」に拡大しました。2019年度には、2回(上期(第4回)・下期(第5回))の入札を実施しています。一般木材等バイオマスによるバイオマス発電(10,000kW以上)及びバイオマス液体燃料によるバイオマス発電についても、2018年度より入札対象としており、2019年度は1回(下期(第2回))の入札を実施しました。
2019年度の調達価格等算定委員会においては、これまで拡大してきた事業用太陽光発電の入札対象範囲を引き続き段階的に拡大させていくこととし、将来のさらなる拡大を見据えながら、2020年度の入札対象範囲を「250kW以上」とする意見が取りまとめられました。また、着床式洋上風力発電(再エネ海域利用法適用外案件)についても、2020年度から入札制に移行する旨の意見が取りまとめられました。この意見を尊重し、経済産業大臣として、2020年度の事業用太陽光発電の入札対象範囲を「250kW以上」に拡大するとともに、着床式洋上風力発電(再エネ海域利用法適用外案件)も2020年度から入札制に移行することを決定しています。
(2)既認定の未稼働案件がもたらす問題と対応
2012年7月のFIT制度開始以降、事業用太陽光発電は急速に認定・導入量が拡大しており、資本費の低下などを踏まえて調達価格は半額以下にまで下落しました(2012年度40円/kWh→2020年度12 ? 13円/kWh)。この価格低減率は他の電源に比べて非常に大きく、認定時に調達価格が決定する仕組みの中で、大量の未稼働案件による歪みが顕著に現れてきています。具体的には、高い調達価格の権利を保持したまま運転を開始しない案件が大量に滞留することにより、①将来的な国民負担増大の懸念、②新規開発・コストダウンの停滞、③系統容量が押さえられてしまうといった課題が生じています。
こうした未稼働案件に対しては、これまでも類似の対策が講じられてきました。2017年4月に改正された再エネ特措法においては、接続契約の締結に必要となる工事費負担金の支払いをした事業者であれば、着実に事業化を行うことが見込まれるとの前提の下、原則として2017年3月末までに接続契約を締結できていない未稼働案件の認定を失効させる措置を講じ、事業用太陽光発電は、これまでに約2,070万kWが失効となりました。加えて、2016年8月1日以降に接続契約を締結した事業用太陽光発電については「認定日から3年」の運転開始期限を設定し、それを経過した場合は、その分だけ20年間の調達期間が短縮されることとしました。
しかしながら、接続契約を締結した上でなお多くの案件が未稼働となっているのが現状であり、このうち2016年7月31日以前に接続契約を締結したものは、早期の運転開始が見込まれることから上記の運転開始期限は設定されませんでしたが、現在では逆に早期に稼働させる規律が働かない結果となっています。
再エネ特措法において調達価格は、その算定時点において事業が「効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用」を基礎とし、「適正な利潤」を勘案して定めるものとされています。太陽光パネル等のコストが年々低下し、2020年度の調達価格が12~13円/kWhとなっている中で、運転開始期限による規律が働かず運転開始が遅れている事業に対して、認定当時のコストを前提にした調達価格が適用されることは、再エネ特措法の趣旨に照らして適切ではありません。
こうした状況に鑑み、国民負担の抑制を図りつつ、再エネの導入量をさらに伸ばしていくため、再エネ大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での審議を経て、運転開始までの目安となる3年を大きく超過した2012 ~ 2016年度にFIT認定を取得した事業用太陽光発電で、運転開始期限が設定されていない未稼働案件について、①原則として一定の期限までに運転開始準備段階に入っていないものには、認定当時のコストを前提にした高い調達価格ではなく、適時の調達価格を適用する、②早期の運転開始を担保するために原則として1年の運転開始期限を設定する等の措置を講じることとしています。
さらに、一連の未稼働対策を講じてもなお長期間事業を開始せず系統容量を空押さえする案件の存在が懸念されることから、主力電源化小委員会において、認定を受けてから一定期間にわたり事業が実施されない場合には、認定を失効させる等の措置を導入するという方向性が取りまとめられ、今後、措置の具体化に向けた検討が行われることになります。
【第331-3-1】年度別FIT認定の稼働状況
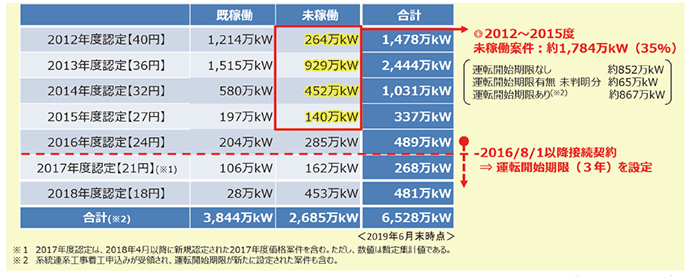
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(3)住宅用太陽光発電設備の意義とFIT買取期間終了の位置付け
太陽光発電は、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることでエネルギー安全保障にも寄与することに加え、火力発電などと異なり燃料費が不要であり、自家消費を行い、非常用電源としても利用可能な分散型電源となり得る特徴があります。一般家庭が太陽光発電設備を設置する理由は様々ですが、光熱費の節約や売電収入を得るといった経済的な理由だけでなく、自ら発電事業者として再エネの推進に貢献していくことを目指している方もいらっしゃいます。一般に、太陽光パネルは20年以上発電し続けることが可能であり、特に住宅に設置されたパネルは改築・解体等をするまで設備が維持されて稼働し続けることが期待されます。
このような状況の中、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた住宅用太陽光発電設備について、2019年11月以降、固定価格での調達期間が順次満了を迎えています。その規模は、2019年11月と12月だけで約53万件、200万kWが対象となり、累積では2023年までに約165万件、670万kWに達する見込みですが、これはFITという支援制度に基づく10年間の買取りが終了するに過ぎず、その後も10年以上にわたって自立的な電源として発電していくという役割が期待されます。
調達期間終了後の円滑な移行に向けて、現行の調達事業者からは、買取期間が終了が間近に迫った世帯に対して、調達期間終了日などが個別通知されています。また、資源エネルギー庁Webサイトに情報提供ページを開設し、調達期間終了後の選択肢の提示や、電気の買取りを希望する事業者情報の提供などを行っています。