第3節 次世代電力ネットワークの形成
我が国の電力系統(送配電網)は、これまで主として大規模電源と需要地を結ぶ形で形成されてきており、再エネ電源の立地ポテンシャルのある地域とは必ずしも一致しておらず、再エネの導入拡大に伴い、系統制約が顕在化しつつあります。このため、今後、再エネの主力電源化を進める上で、この系統制約を解消していくことが重要です。
さらに、今後の電力ネットワーク形成を検討するにあたっては、2030年以降を見据え、人口減・需要減といった構造的課題や2018年9月の北海道胆振東部地震による大規模停電を始めとした自然災害に対するレジリエンスの強化を含む系統の在り方など、多様な視点・目的が存在します。これらを踏まえ、我が国の電力系統を再エネの大量導入等の環境変化に適応する「大規模電源と需要地をネットワークでつなぐ従来の電力システム」から「分散型電源も柔軟に活用する新たな電力システム」へと長期的に転換していくための環境整備を進めていかなければなりません。
また、2018年10月には、九州エリアにおいて本土初となる再エネの出力制御が行われました。出力が天候等によって変化する自然変動再エネ(太陽光・風力)の導入が拡大することで、その出力変動を調整し得る「調整力」を効率的かつ効果的に確保することが、国際的にみても、大量の再エネを電力系統に受け入れるための課題になります。
我が国の電力系統を再エネの大量導入等の環境変化に適応した次世代型のネットワークへと転換していくため、それぞれの課題を整理しながら道筋を描いていく必要があります。
1.系統制約の克服
(1)既存系統の最大限の活用
我が国のこれまでの制度では、新規に電源を系統に接続する際、系統の空き容量の範囲内で先着順に受入れを行い、空き容量がなくなった場合には系統を増強した上で追加的な受入れを行うこととなっています。一方、欧州においては、既存系統の容量を最大限活用し、一定の条件付での接続を認める制度を導入している国もあります。系統の増強には多額の費用と時間が伴うものであることから、まずは、既存系統を最大限活用していくことが重要です。このため、以下のとおり、系統の空き容量を柔軟に活用する「日本版コネクト&マネージ」を具体化し、早期に実現するための取組を進めています。
①想定潮流の合理化
過去の実績をもとに実際の利用率に近い想定を行い、より精緻な最大潮流を想定して送電線の空き容量を算出する「想定潮流の合理化」については、2018年4月から全国的に導入されています。電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)によると、想定潮流の合理化の適用による効果として、全国で約590万kWの空き容量の拡大が確認されました(2018年12月時点)。
②N-1電制
落雷等による事故時には電源を瞬時に遮断する装置(以下「電制装置」)を設置することを条件に、緊急時用に確保している送電線の容量の一部を平常時に活用する「N-1電制」については、2018年10月からその先行適用※1 が実施され、広域機関によると、全国で約4,040万kWの接続可能容量が確認されました(2018年12月時点)。「N-1電制」の本格適用※2 に向けては、2022年度の適用開始を目指し、具体的な仕組みの検討を進めています。
③ノンファーム型接続
系統の混雑時には出力制御することを前提として新規の接続を可能とする「ノンファーム型接続」について、広域機関によると、日本における再エネ電源の連系の中心となる小規模電源が多数接続される配電系統を含めた仕組みは海外にも例がなく、全くの新規の検討が必要であり相当程度時間を要するものとされています。今後は、まずは、海外でも例のあるファーム電源の暫定接続として平常時に混雑処理をする仕組みの検討を行いつつ、並行して、恒久的なノンファーム型接続の導入に向けて、フィージビリティスタディを行った上で、実系統での実証を実施していきます。
【第333-1-1】日本版コネクト&マネージの進捗
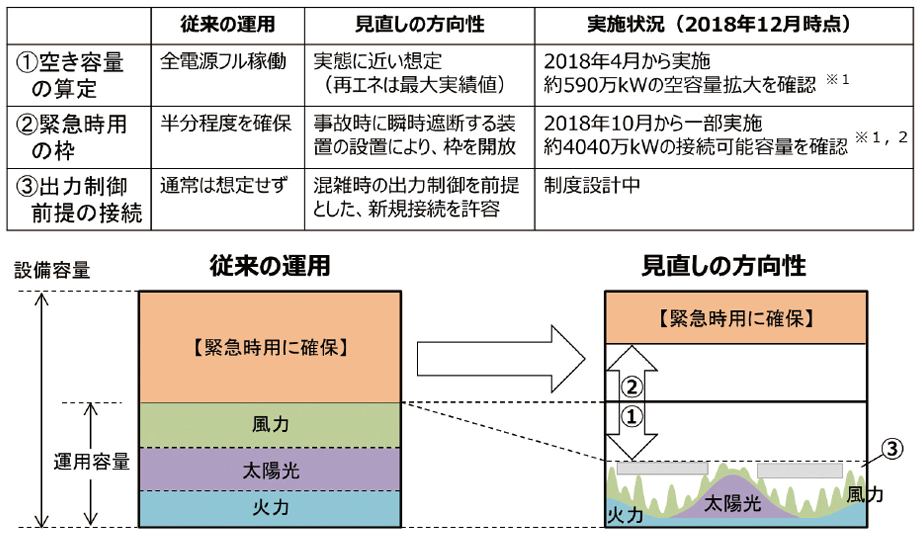
- ※1
- 最上位電圧の変電所単位で評価したものであり、全ての系統の効果を詳細に評価したものではない。
- ※2
- 速報値であり、数値が変わる場合がある。
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(2)出力制御の予見可能性を高めるための情報公開・開示
系統制約が顕在化する中で、発電事業の収益性を適切に評価し、投資判断と円滑なファイナンスを可能とするため、事業期間中の出力制御の予見可能性を高めることが、既存系統を最大限活用しながら再エネの大量導入を実現するために極めて重要です。一方で、発電事業者の事業判断の根拠となる出力制御の見通しを送配電事業者が示そうとすると、安定供給重視の万全の条件とする、見通しよりも高い出力制御が現実に発生する事態を確実に避ける、といった観点から見積り自体が過大となるおそれがあります。
このため、一般送配電事業者が基礎となる情報を公開・開示し、それを利用して発電事業者やコンサルタント等が出力制御の見通しについて自らシミュレーションを行い、事業判断・ファイナンスに活用できるよう、①需給バランス制約による出力制御のシミュレーションに必要な情報と、②送電容量制約による出力制御のシミュレーションに必要な情報(「需要・送配電に関する情報」及び「電源に関する情報」)について、それぞれ公開(「電源に関する情報」については開示)する具体的な内容や手続を取りまとめました。。今後、関係規程類を整備した上で、可能な限り早期に施行し、新たな情報公開・開示の運用を開始します。
(3)ネットワーク改革等による系統増強への対応
再エネの大量導入を始めとした環境変化を踏まえた次世代型の送配電ネットワークに転換するためには、国民負担を抑制しつつ、系統増強等の必要な投資が行われるための予見性確保等の環境整備が必要となります。ネットワークコスト改革にあたっては、再エネに係る発電コストを大幅に低減させるとともに、既存ネットワークコストの徹底削減を図ることで、次世代ネットワーク投資の原資を確保し、コストを全体として低減させることを基本方針としました。
国民負担抑制の観点から、再エネの導入拡大に伴い増大するネットワークコストを最大限抑制するため、既存ネットワーク等のコストを徹底して削減することが必要です。具体的には、仕様等の標準化や調達に関する国への情報開示の促進、コスト削減に向けた一般送配電事業者による自主的ロードマップの提出と取組状況の確認等によって、一般送配電事業者の調達改革を通じた徹底的なコスト削減を促進します。この際、これらの取組も前提としつつ、不断の効率化を促す託送料金制度についても検討を行います。また、次世代投資を促進するための費用負担の在り方について、投資にインセンティブが働くような託送料金制度や財政的な支援などの検討も含め、未来に向けた投資を促進する制度等環境整備も同時に進めていくこととしました。さらに、発電設備設置者もネットワークコストを意識した事業展開を行うためのインセンティブ・選択肢を確保するために、既に導入済みの系統増強における一部特定負担方式に加え、発電側基本料金のように、系統の効率的な活用を促すための仕組みを導入することとしています。あわせて、再エネ発電事業者の初期費用負担とのバランスを図る観点から、系統増強における一般負担上限額の見直し・適用を行いました。
【第333-1-2】電力NWコスト改革に係る3つの基本方針(概念図)
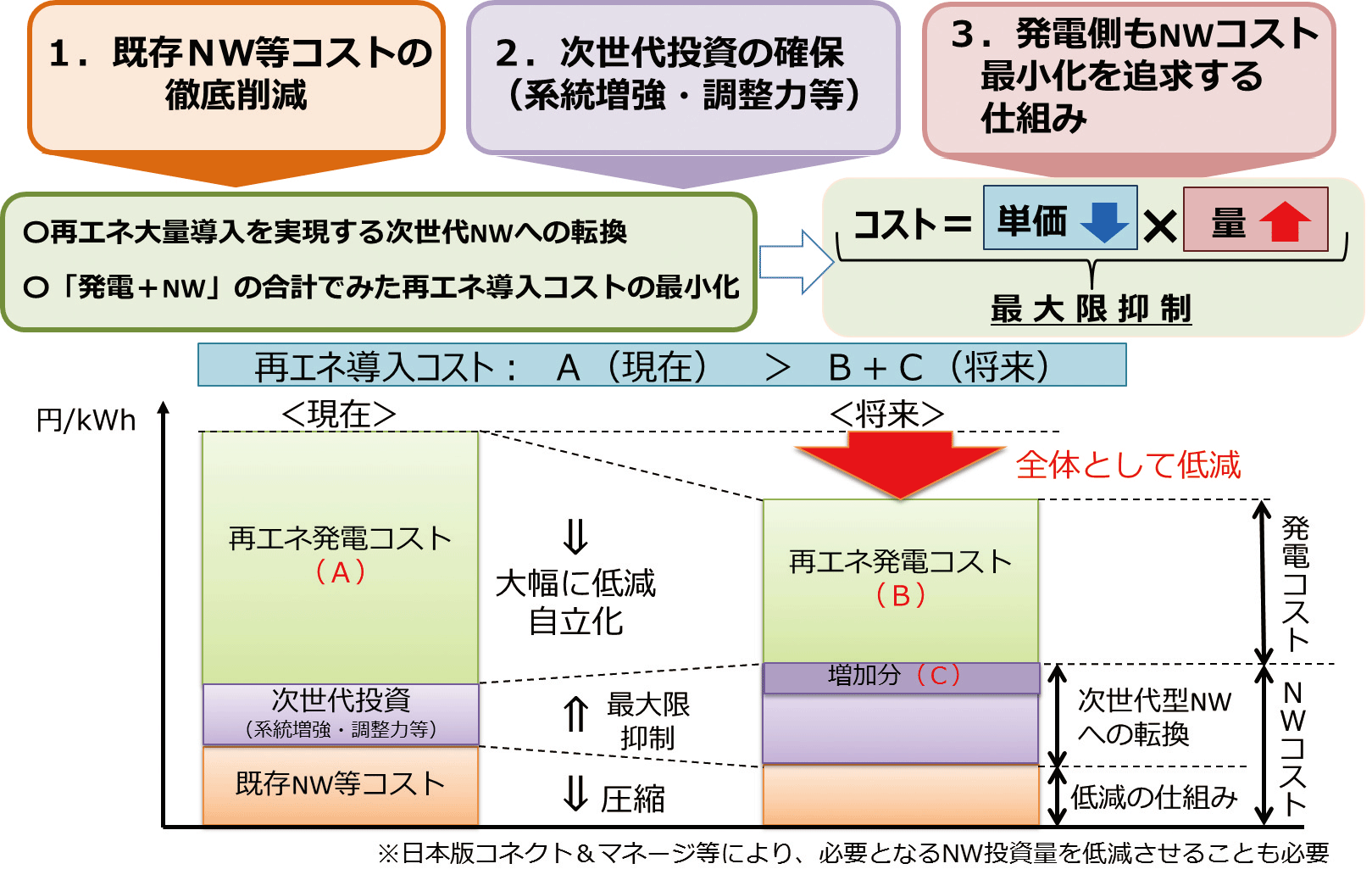
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
2.分散型エネルギーリソースの活用
2030年以降を見据えれば、人口減少等に伴う需要減少要因、高経年化対策等の構造的課題の顕在化や蓄電池や水素等の次世代型調整力等における技術革新やデジタル化の進展等ネットワークを取り巻く様々な環境変化が発生することが想定されます。将来についての正確な予測は困難ですが、都度都度の見直しを行う前提の下、次世代の電力ネットワークシステムの在り方を描き、そこからバックキャストして必要な投資は何かを考え、そのために必要となる制度・政策を講じていく必要があります。そこで、大きな方向性として「広域化(例えば、送電レベルでの全国大での最適運用)」「分散化(例えば、配電レベルでの多様なプレーヤーの参画)」が進展していく可能性が高いとの前提の下、大規模集中型から小規模分散型も含めた多様なプレーヤーのインフラへ転換させていく観点から、分散型エネルギーリソースと調和的な電力ネットワークはどうあるべきか、また、分散型エネルギーリソースを活用する新ビジネス・他産業連携のプラットフォームとしての萌芽について、具体的な事例を基に議論を深めてきました。
例えば、先んじて再エネのコスト低減が進んだ欧米諸国では、民間事業者の主体的・積極的な取組姿勢とも相まって、自家消費や電力販売契約(PPA)などにより、FIT制度を前提としない、需給一体的な形で分散型エネルギーの開発が加速しています。日本においても、太陽光発電を中心にコスト低減が進んでいるところ、既にこうしたFIT制度に頼らない電源開発の萌芽があり、今後の取引の加速が期待されています。また、デンマークにおいて、Enel社(イタリア)の逆潮機能付EV充電ポートを起点として世界初のV2Gの商業化が実現された事例では、EV充電ポートと制御システムによってネットワーク事業者とEV所有者をつなげることで、新たな取引機会が創出されました。今後は、分散型エネルギーの推進に加え、こうした配電分野を中心とした分散型エネルギーリソースを活用する新たなビジネスモデルとも整合的な形で次世代ネットワークについて検討を進めていくことが重要です。
【第333-2-1】Beyond 2030のNWシステム(「分散化」「広域化」)(イメージ)
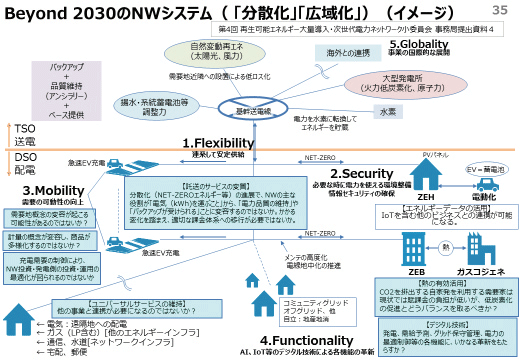
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
【第333-2-2】配電網とEVの連携による新ビジネス(イタリア:Enel)
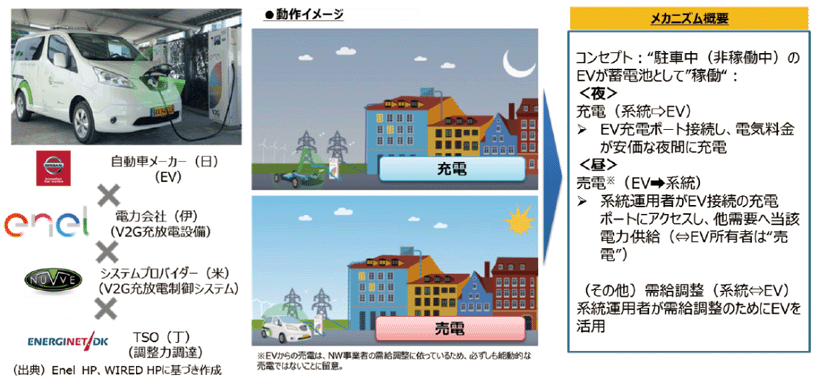
- 出典:
- 第1回次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会資料4より引用
3.調整力の確保・調整手法の高度化
(1)出力制御
太陽光発電・風力発電といった再エネ電源は天候や日照条件等の自然環境によって発電量が変動する特性があるため、地域内の発電量が需要量を上回る場合には、電気の安定供給を維持するため、発電量の制御が必要となります。こうした場合、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)や広域機関の送配電等業務指針で定められた優先給電ルールに基づき、火力発電の抑制、揚水運転、地域間連系線の活用などを行います。それでもなお発電量が過剰となる場合には再エネの出力制御を実施することとされており、太陽光発電の導入が急速に進む九州エリアでは2018年10月に本土初となる再エネの出力制御が行われました。こうした出力制御は送電線に再エネをより多く送電線につなぐために必要な取組であり、スペインやアイルランドといった再エネ先進国でも変動する再エネを無制限に発電しているわけではなく、むしろ適切な制御を前提とすることで送電線への接続量を増やすための取り組みとして採用されています。
再エネの出力制御を低減させるための取組として、①地域間連系線の更なる活用による他エリアへの送電、②実需要に近いタイミングでの柔軟な調整を可能にするオンライン制御の拡大、③火力発電等の最低出力の引下げ、④発電事業者間の公平性及び効率的な出力制御を確保するための出力制御の経済的調整、等が挙げられます。このうち①については、2017年以降、九州電力において、連系線の運用改善やOFリレー(電力需要と供給のバランスを表す周波数が一定値以上になった場合に、発電機などへの悪影響や大規模停電を防ぐために発電機を系統から切り離す機器)を活用した電源制限量の確保によって、再エネの送電可能量を段階的に拡大してきました。また、国の補正予算事業を活用して、転送遮断システムによる電源制限量の確保を進めており、この結果、2018年度末までに、関門連系線の再エネ送電可能量は当初の45万kWから135万kW程度(※一定の仮定の下で試算した数値であり、需要動向や電源制限機能付電源の稼働状況によって変動)に拡大する見込みです。
(2)グリッドコードの整備
自然変動再エネの導入拡大に伴い、急激な出力変動や小刻みな出力変動等に対応するための調整力の必要性が高まり、電力システムで求められる対応が高度化することから、今後、自然変動再エネが有する制御機能や柔軟性を有する火力発電・バイオマス発電の調整力としての重要性が一層高まっていくことが予想されます。こうした中、系統に接続される電源が持つべき機能や従うべきルールである「グリッドコード」の重要性が高まっています。まずは新規の風力発電が具備すべき調整機能(出力抑制、出力変化率制限等)を特定し、そのグリッドコードの具体化に向けた検討を進めているところです。これらの検討を踏まえつつ、太陽光発電など他の電源や既存の火力発電・バイオマス発電についても併せて検討を進めていきます。
また、2018年9月の北海道胆振東部地震を踏まえ、自然変動再エネの周波数変動への耐性を高めるための対応が必要とされており、レジリエンスの向上と再エネの大量導入を見据えてグリッドコードの整備を進めていきます。
【第333-3-1】再生可能エネルギー発電量と出力制御の関係
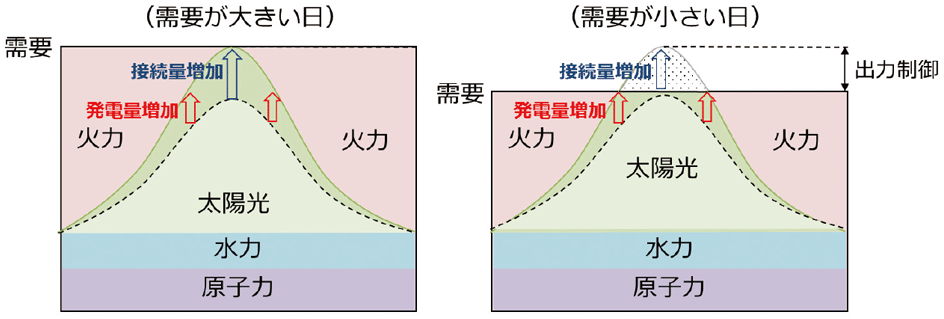
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(3)再エネ予測誤差への対応
再エネの大量導入を進めながらも、同時に社会コストの最小化も図っていかなければなりません。FIT電源については、FIT制度によって固定価格での売電収入が保証されるという特性と計画値同時同量制度の整合性を保つため、FIT発電事業者の代わりに一般送配電事業者又は小売電気事業者が発電計画を作成し、計画と実績のずれであるインバランスリスクを負う「FITインバランス特例制度」が設けられています。一方、自然変動電源は、天候予測の精度等によって、ほぼ必然的に予測誤差によるインバランスを発生させている状況であり、エリアインバランスの大半を太陽光発電の予測外れが占めています。今後、再エネ(特に太陽光発電)の導入拡大が進むにつれ、インバランスが一層増大する可能性がある中、一般送配電事業者・発電事業者・小売電気事業者の適切な役割分担の下で、市場メカニズムを活用しながら発電計画と発電実績とのギャップを縮減し、再エネに起因するインバランスを小さくするための対策(発電量の予測精度向上、発電計画の通知時期を可能な限り実需給断面に近づける等)の検討を進める必要があります。
具体的には、一般送配電事業者による出力予測の予測誤差自体を減らすなど、再エネに起因するインバランスを小さくし、国民負担の抑制を図るため、データの予測精度や運用実態、全体のインバランス設計も踏まえ、実現可能な方策について検討を進めることとしています。
加えて、一般送配電事業者による再エネ予測誤差の削減について広域機関が適正に監視・確認する仕組みとした上で、なお生じざるを得ない相応の予測誤差が残る場合には、予測誤差を削減し確保するべき調整力を減らすインセンティブが働くようにしつつ、その調整力の確保にかかる費用をFIT交付金により負担する仕組みについて検討を進めることとしています。
【第333-3-2】FITインバランス特例制度に起因する再エネ予測誤差
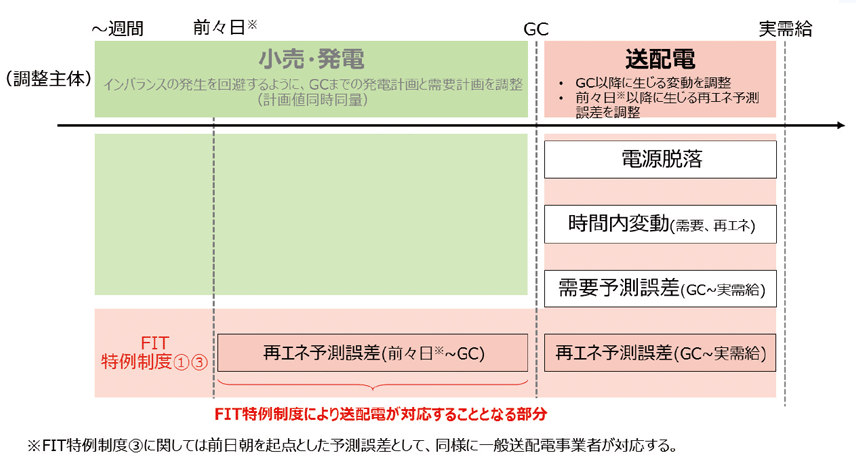
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成