第1節 コストダウンの加速化とFITからの自立化
欧州等に比べ発電コストが高い中でも再エネの導入が拡大しているのは、FIT制度が様々なリスクを極小化し投資回収を保障していることによるところが大きいと考えられますが、これはあくまで国民負担によって支えられた過渡的な措置であり、将来的にはFIT制度等による支援が無くとも、再エネが電力市場の中でコスト競争に打ち勝ち、自立的に導入が進むようにしなければなりません。
コストダウンに向けた取組として、中長期価格目標に向けたトップランナー方式での価格低減や入札制の活用に加え、国内外のコスト動向を踏まえつつ、新規案件のコストダウンの加速化に向けた取組の更なる具体化が必要です。また、FIT賦課金(国民負担)が2018年度で既に年間2.4兆円に達している中で、FIT認定を取得し過去の高い調達価格を確定させたまま長期間未稼働となっている案件が大量に滞留している状況が生じており、こうした既認定案件がもたらす国民負担に対する抜本的な打開策も必要不可欠です。
さらに、2019年11月以降の住宅用太陽光発電設備のFIT買取期間終了を1つの先駆けとして、FIT制度に頼らないビジネスモデルの検討が動き出しつつあり、それを早期に実現・確立していくため、FIT制度からの自立化に向けた方向性を具体化していく必要もあります。
1.新規認定案件のコストダウンの加速化
(1)中長期価格目標の見直し
発電事業者・メーカー等の努力やイノベーションによる再エネコストの低減を促すため、FIT制度では、中長期の価格目標を定めることとされています。エネルギー基本計画において「急速なコストダウンが見込まれる電源」とされた太陽光発電・風力発電については、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会や調達価格等算定委員会において、世界の急速なコストダウンの実績、日本の将来のコスト低減見通しや現在のトップランナーの事業実施状況等を踏まえ、目標の見直しが議論されました。
この議論を踏まえ、2019年1月9日、調達価格等算定委員会において、事業用太陽光発電の「2030年発電コスト7円/kWh」という目標を5年前倒すとともに、住宅用太陽光発電についても、事業用のコスト低減スピードと合わせて、「売電価格が卸電力市場価格並み」という価格目標を達成する年限を「2025年」と明確化するべきとする意見が取りまとめられました。また、風力発電(陸上・洋上(着床式))については、「2030年発電コスト8∼9円/kWh」という価格目標の実現に向けて、コスト低減の取組を深掘りしていくべきとする意見が取りまとめられました。2019年4月に、経済産業大臣として、調達価格等算定委員会の意見のとおり、太陽光発電の中長期価格目標の見直しを行いました。
その他の電源については、従前より「FIT制度からの中長期的な自立化を目指す」という目標が掲げられており、この目標に向けて、コスト低減を進めていく必要があります。
【第331-1-1】事業用太陽光の価格目標イメージ
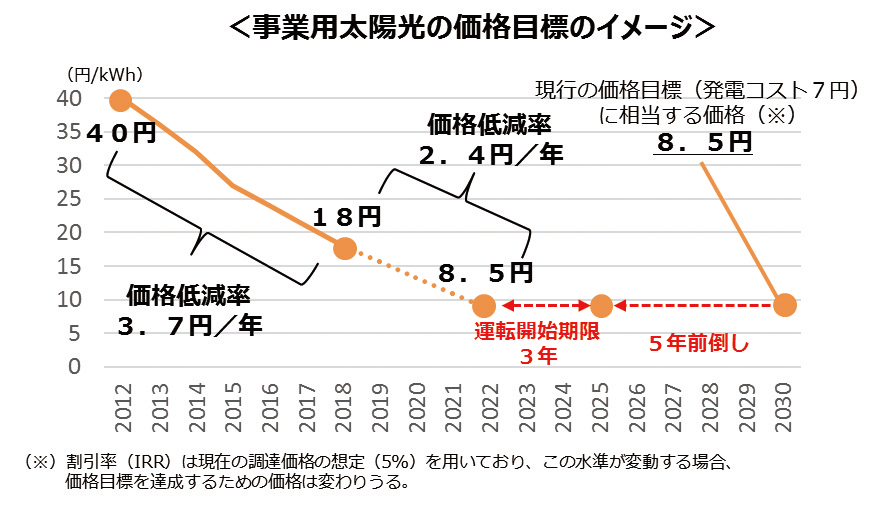
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(2)入札制の活用
再エネの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、FIT制度では、入札による競争によって認定を受けることができる者及びその調達価格を決定することが国民負担の軽減につながると認められる電源については、入札対象として指定することができることとされています。2,000kW以上の事業用太陽光発電は2017年度より入札対象としており、2018年度に計2回(上期(第2回)・下期(第3回))の入札を実施しました。また、一般木材等バイオマスによるバイオマス発電(10,000kW以上)及びバイオマス液体燃料によるバイオマス発電は2018年度より入札対象としており、2018年度にそれぞれ1回(下期(第1回))の入札を実施しました。
こうした中で、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、増大する国民負担の抑制を図り、FIT制度からの自立化に向けたコスト低減を促していくため、今後入札制をより一層活用していくべきとの方針が取りまとめられました。
調達価格等算定委員会においては、上記の議論も踏まえつつ、事業用太陽光発電について、国内外の状況、規模別のコスト動向やFIT認定量及び導入量等に鑑み、将来の入札対象範囲の更なる拡大を見据えつつ、まずは2019年度の入札対象範囲を500kW以上とする意見が取りまとめられました。この意見を尊重し、経済産業大臣として、2019年度の事業用太陽光発電の入札対象範囲を500kW以上とすることを決定しています。
【第331-1-2】各再エネ電源の入札制移行の考え方
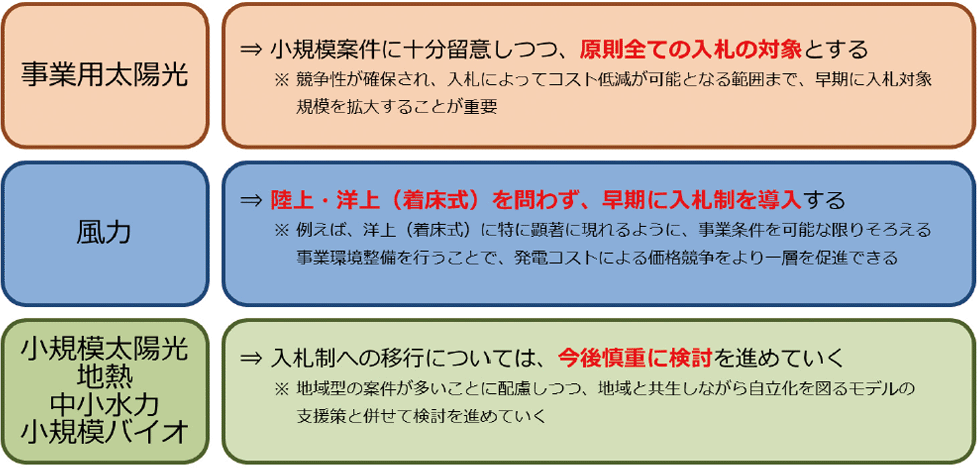
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
2.既認定案件による国民負担の抑制対策の推進(事業用太陽光発電の未稼働案件への対応)
(1)未稼働案件がもたらす問題
2012年7月のFIT制度開始以降、事業用太陽光発電は急速に認定・導入量が拡大しており、資本費の低下などを踏まえて調達価格は半額以下にまで下落しました(2012年度40円/kWh→2018年度18円/kWh)。この価格低減率は他の電源に比べて非常に大きく、認定時に調達価格が決定する仕組みの中で、大量の未稼働案件による歪みが顕著に現れてきています。具体的には、高い調達価格の権利を保持したまま運転を開始しない案件が大量に滞留することにより、1) 将来的な国民負担増大の懸念、2) 新規開発・コストダウンの停滞、3) 系統容量が押さえられてしまうといった課題が生じています。
(2)未稼働案件に対するこれまでの対応
こうした未稼働案件に対しては、これまでも累次の対策が講じられてきました。2017年4月に施行された改正FIT法においては、接続契約の締結に必要となる工事費負担金の支払いをした事業者であれば、着実に事業化を行うことが見込まれるとの前提の下、原則として2017年3月末までに接続契約を締結できていない未稼働案件の認定を失効させる措置を講じ、事業用太陽光発電は、これまでに約1,700万kWが失効となりました。加えて、2016年8月1日以降に接続契約を締結した事業用太陽光発電については「認定日から3年」の運転開始期限を設定し、それを経過した場合は、その分だけ20年間の調達期間が短縮されることとしました。
しかしながら、2012~2014年度の認定案件だけでも、接続契約を締結した上でなお約2,352万kWもの案件が未稼働となっているのが現状であり、このうち2016年7月31日以前に接続契約を締結したものは、早期の運転開始が見込まれることから上記の運転開始期限は設定されませんでしたが、現在では逆に早期に稼働させる規律が働かない結果となっています。
(3)未稼働案件に対する新たな対応
FIT法において調達価格は、その算定時点において事業が「効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用」を基礎とし、「適正な利潤」を勘案して定めるものとされています。太陽光パネル等のコストが年々低下し、2018年度の調達価格が18円/kWhとなっている中で、運転開始期限による規律が働かず運転開始が遅れている事業に対して、認定当時のコストを前提にした調達価格が適用されることは、FIT法の趣旨に照らして適切ではありません。
こうした状況に鑑み、国民負担の抑制を図りつつ、再生可能エネルギーの導入量を更に伸ばしていくため、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会での審議を経て、運転開始までの目安となる3年を大きく超過した2012~2014年度にFIT認定を取得した事業用太陽光発電で、運転開始期限が設定されていない未稼働案件について、1) 原則として2018年度中に運転開始準備段階に入っていないものには、認定当時のコストを前提にした高い調達価格ではなく、運転開始のタイミングに合わせた適時の調達価格を適用する、2) 早期の運転開始を担保するために原則として1年の運転開始期限を設定する等の措置を講じることとしました。
【第331-1-3】事業用太陽光発電の未稼働案件の状況
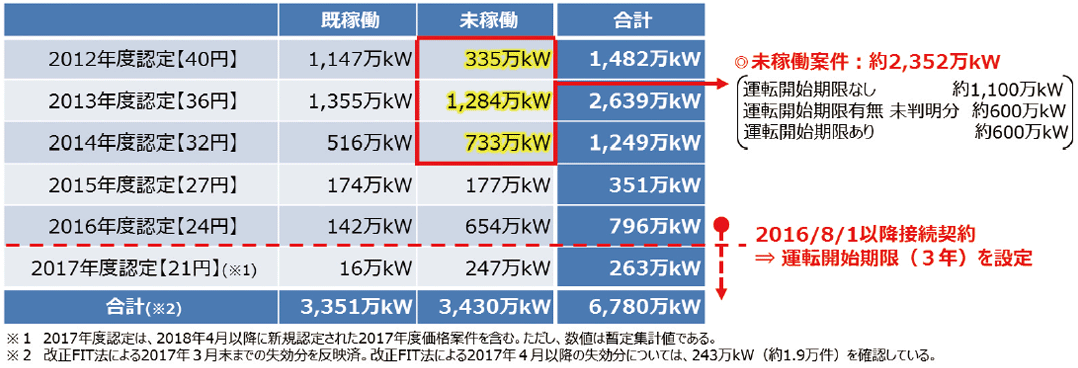
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
3.多様な自立モデルの検討
需給一体型の再エネ活用モデル
FIT制度からの自立化を進めていくため、FIT制度が無くとも再エネ事業への新規投資の採算が取れるような事業環境を整備していく観点から、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、自家消費と系統の活用を含む「需給一体型」のモデルについて、(i)家庭、(ii)大口需要家、(iii)地域、と需給の範囲を最小単位の家庭から地域単位へと徐々に拡大させながら、それぞれの論点と方向性について複数の事例を基に、事業環境整備の在り方について検討を行いました。
(1)家庭
住宅用太陽光発電が2019年11月以降順次、FIT買取期間を終え、投資回収が済んだ安価な電源として活用されることや、住宅用太陽光発電の調達価格が家庭用小売料金の水準(24円/kWh)と同額になり、自家消費の経済的メリットが大きくなります。こうした背景から、今後拡大し得ると考えられる家庭における再エネ活用モデルとして、「住宅用太陽光と蓄エネ技術を組み合わせた効率的な自家消費の推進」、「アグリゲーターによる、系統や蓄電池等を活用した家庭の余剰電力の有効活用」、「住宅用太陽光の自立運転機能の活用やエネファームなど他電源等と組み合わせた災害対策」等が想定されます。
(2)大口需要家
再エネのコスト低減の進展に加え、ESG投資の拡大やRE100など再エネを志向する企業の増加といった世界的なモメンタムの中で、我が国企業等の大口需要家においても、環境価値を持つ再生可能エネルギー電気へのニーズが高まっています。実際、欧米では電気販売契約(PPA)による再エネ電気の調達が盛んになっており、日本においても、非FITの再エネ発電事業から直接電力を購入するVirtual PPAの実現も視野に、ブロックチェーンを活用したP2Pの電力取引プラットフォームの開発に乗り出す事業者も登場しています。
他方で、現状、我が国において導入されている再エネの大半はFIT制度を利用したものであるため、大口需要家が再エネを活用する手段としては、非化石証書等と組み合わせた系統電気の購入がメインとなるのが現状です。そのほかには、1)敷地内(オンサイト)に再エネ電源を設置し、自家消費を行うモデルが考えられますが、立地上の制約次第では、2)敷地外又は需要地から一定の距離を置いた場所(オフサイト)に設置された再エネ電源から供給を受ける、という選択肢もあり得ます。また、3)大口需要家がこうした需給一体型のモデルを構築することで、レジリエンス対策にもつながることが期待されます。
(3)地域
電力・ガスシステム改革等が進展し、エネルギーシステムの構造が大きく変化する中、地域単位でも、エネルギー需給管理サービスを行う自治体や非営利法人等がエネルギー供給構造に参加する取組が生まれ始めています。こうした状況も踏まえ、地域におけるFIT制度から自立した再エネの需給一体型のモデルの構築について、以下の視点から検討を進めていくことが重要です。
- 地域に賦存する再エネを活用した地産地消や、地域に新たな産業を創出するなどの地域活性化をどのように進めるか。その際、FIT制度において地域との共生を図りながら緩やかに自立に向かうと位置付けた電源(小規模バイオマス発電等)を、どのように活用していくべきか。
- 「地域に根付いた電源を地域で使う」分散型エネルギーシステムが、効率的かつ経済的に成立するようになるためには、将来的な電力ネットワーク(託送サービス)はどうあるべきか。
- 緊急時に大規模電源などからの供給に困難が生じた場合も、地域において一定のエネルギー供給を可能にするなど、災害時における地域のエネルギー安定供給をどのように実現していくか。
4.住宅用太陽光発電設備の買取期間終了に向けた対応
(1)住宅用太陽光発電設備の意義とFIT買取期間終了の位置付け
太陽光発電は、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることでエネルギー安全保障にも寄与することに加え、火力発電などと異なり燃料費が不要であり、自家消費を行い、非常用電源としても利用可能な分散型電源となり得る特徴があります。一般家庭が太陽光発電設備を設置する理由は様々ですが、光熱費の節約や売電収入を得るといった経済的な理由だけでなく、自ら発電事業者として再エネの推進に貢献していくことを目指して導入が進められてきました。一般に、太陽光パネルは20~30年間、又はそれ以上発電し続けることが可能であり、特に住宅に設置されたパネルは改築・解体等をするまで設備が維持されて稼働し続けることが期待されます。
このような状況の中、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた住宅用太陽光発電設備を含め、2019年11月以降順次、買取期間が満了を迎えることになります。2019年11月・12月だけで約53万件・200万kWが対象となり、累積では2023年までに約165万件・670万kWに達する見込みですが、これはFITという支援制度に基づく10年間の買取りが終了するに過ぎず、その後も10年・20年にわたって自立的な電源として発電していくという役割が期待されます。
(2)2019年11月以降のFIT買取期間終了に向けた対応
住宅用太陽光発電設備の設置者は、発電・売電を行う供給者であると同時に、保有する情報量や交渉力に劣る消費者でもあるため、FIT制度による買取期間の終了を迎える対象者がその事実を認知し、その後の太陽光発電設備の使い方を積極的に選択するようになるための工夫が必要となります。
また、既に買取期間終了後も買取りを行うことを表明したり、具体的な買取メニューを発表して営業活動を展開したりする事業者や、蓄電池等の営業販売を行う事業者などが出始めていますが、小売全面自由化時とは異なり、どの世帯が、いつ買取期間終了を迎えるかについて第三者からは特定できないため、現在買取りを行っている事業者とそれ以外の事業者との間の競争上の公平性に関する懸念も生じています。
こうした観点から、政府としては、制度に関する情報提供やFIT卒業電源の活用メニューを提供する事業者のポータルとなる専用サイトの開設や新聞広告による周知等を行っています。また、事業者に対しては、全てのFIT卒業対象者に確実に認知してもらうため、買取期間が終了する旨の個別通知の実施を現在の全ての買取者に要請することに加えて、特に旧一般電気事業者(小売)に対しては、大宗の対象者の個人情報を保有しているという実態を踏まえ、競争上の公平性と予見性確保の観点から、買取メニュー公表時期の事前発表、個別通知における記載内容の中立性の確保、営業や契約における一定の制約を求めています。