第5節 東電改革
1. 東京電力改革・1F問題委員会の設立、委員会における議論
東京電力は、「新・総合特別事業計画」に基づき、ホールディングカンパニー制に移行し、中部電力の火力部門との機能別再編での新会社JERA設立により世界最大の火力会社に向けた事業統合に着手したほか、2022年度までの10年間で5兆円のコスト削減にも取り組んできています。他方、賠償や除染、廃炉など事故に伴う費用は増大しているほか、電力の小売り全面自由化の中で需要は構造的に減少しています。東京電力の構造的な競争力確保は未だ途上にあり、これを放置すれば福島復興や事故収束への歩みが滞りかねません。
原発事故に伴う費用が増大する中、福島復興と事故収束への責任を果たすため、東京電力はいかなる経営改革をすべきか。原子力の社会的信頼を取り戻すため、事故を起こした東京電力はいかなる経営改革をすべきか。自由化の下で需要の構造的縮小が続く中、世界レベルの生産性水準を達成し、福島復興と国民への還元につなげるため、東京電力はいかなる経営改革をすべきか。これらの課題への回答について、福島県の方々が安心し、国民が納得し、昼夜問わず第一線を支え続ける「現場」が気概を持って働ける解を見つけなければなりません。東電改革の姿は電力産業の将来を示し、この改革とパッケージで整備する国の制度改革は、被災者救済と事故炉廃炉促進のための制度となります。東電改革は、福島復興、原子力事業、原子力政策の根幹的課題です。
そこで、経済産業省は、「東京電力改革・1F問題委員会」(東電委員会)を開催し、東電改革の具体化についての提言の取りまとめを有識者に依頼しました。これを受けて、2016年10月から計11回の委員会が開催され、東京電力の非連続の経営改革に向けた方向性、東京電力の企業改革における取組、JERAの取組等について議論がなされ、2016年12月20日には東電改革提言がとりまとめられました。この提言内容は、2017年5月に政府が認定した東京電力の経営計画である「新々・総合特別事業計画(第三次計画)」に反映されており、東京電力は現在、当該計画を基に改革を実行しています。
2.「東電改革提言」
2016年12月20日にとりまとめられた東電改革提言の概要は以下のとおりとなります。
−「東電改革提言」の概要−
(1) 福島の長期展望と電力市場の構造変化を見据えた持続可能な仕組みの構築
① 福島事業を長い目で展望した上での必要な資金規模
東京電力福島第一原子力発電所廃炉:現状、東京電力は、廃炉に要する資金として見込んだ2兆円を事故収束対応に充当しているが、有識者ヒアリングにより得られた見解の一例に基づけば、燃料デブリの取出し工程を実行する過程で、追加で最大6兆円程度の資金が必要。合計最大8兆円程度の資金を要する。東電は、収益力を上げ、年間平均3,000億円程度の資金を準備。国は、事故炉廃炉事業を適正かつ着実に実施するための事故炉廃炉管理型積立金制度の創設等を行うとともに、送配電事業の合理化分を優先的に充当。
賠償:営業損害や風評被害が続く中で、約8兆円の支援枠が必要。東電は、収益力を上げ、賠償に要する資金として、年間平均2,000億円程度の資金を準備。国は、国民全体で福島を支える、需要家間の公平性を確保するといった観点から、福島原発事故の前には確保されていなかった賠償の備え不足についてのみ、託送制度を活用して広く新電力の需要家も含めて負担を求める。
除染・中間貯蔵:事業に要する費用の上振れなどにより、約6兆円の支援枠が必要。これまで通り、原賠機構が保有する東電株式の売却益の拡大や国の予算で対応。
② 新たな局面に対応するための東京電力と国の役割分担、東電改革の必要性
国の事故対応制度と事故事業者の抜本的改革で対処するとの原則を確立し、対処。
国の事故対応制度は、以下の3点から構成。
(ア)一時的支援と改革実現のモニタリング
(イ)福島復興加速化や賠償等の必要な事業の実施
(ウ)事故炉廃炉のための制度の整備
この事故対応制度の中で、事故事業者である東電が主たる対応を果たす原則は変わらず、総額約22兆円のうち、東電が捻出する資金は約16兆円と試算される。
東電は、賠償・廃炉については、その所要資金として年間5,000億円規模の資金を確保し、除染に関しては、より長い時間軸の中で、企業価値向上による株式売却益4兆円相当を実現する。
消費者の視点で見て、今回の措置により、総じて、電力料金は値上げとはならないようにする。
東電改革を契機として、電力産業全体に広がり、さらに大きな消費者利益が実現。東電改革の実現が福島の安定と国民利益の拡大を同時に達成する鍵となる。
(2)東電改革、2011年の緊急体制から本格的体制を築く
① 経済事業
JERAの事例に倣い、送配電事業・原子力事業についても、課題解決に向けた共同事業体を他の電力会社の信頼と協力を得て早期に設立し、再編・統合を目指す。各事業の性格に応じて時間軸を設定し、ステップ・バイ・ステップで進める。
経済事業の理念は、「世界市場で勝ち抜くことで、福島への責任を果たす」とする。
② 原子力事業
原発の再稼働は、確実に収益の拡大をもたらし、福島事業の安定にも貢献。
しかし、東電は原発事故を起こした事業者。過去の企業文化と決別し、安全性を絶えず問い続ける企業文化、責任感を確立することが必要。このため、他の電力会社の協力を躊躇なく要請し、海外の先進的事業者のチェックも受け入れ、安全性向上と効率化を実現。地元との対話を重ね、地元本位・安全最優先の事業運営体制を確立。
原発依存度低減の中で、安全防災を支える技術と人材を確保し、継続的な安全投資を行いつつ、海外市場や廃炉ビジネスへの展開を図るためには個社での努力では限界がある。こうした共通課題の解決に向けて、他の原子力事業者との共同事業体を設け、再編・統合を目指す。これにより、企業価値向上に貢献。
原子力事業の理念は、「地元本位、安全最優先」とする。
③ 福島事業
廃炉事業は、長期間、相当な規模の資金を投入して行う国家的事業。福島復興事業は、東電が国と共同で行うべき責任事業。
廃炉事業は、グローバルレベルのエンジニアリング能力を強化し、事業を貫徹。リスク・リソース・時間の3つの要素を最適化する事業体制を築き上げる。
福島事業の理念は、「福島事業が東電存続の原点、国と協力しながら世界最先端の技術を集積、福島への責任を果たす」とする。
④ 経済事業と福島事業とのブリッジ
福島事業を支えるためには、まずは廃炉と賠償のため当面の資金を確保することが重要。主として送配電事業や原子力事業が担う。
原賠機構が株式売却益により除染費用相当分を回収するための企業価値向上は、腰を据えてより長い時間軸の中で対応。再編・統合が先行する燃料・火力事業、異業種連携に着手した小売事業が貢献。加えて、送配電事業や原子力事業も、将来的な企業価値向上に貢献。
共同事業体を設立する過程で、経済事業による福島事業への貢献ルールを開発。
(3)実行体制を早期に確立、早期着手を
① 東京電力は、次世代への早期権限移譲を実現
原子力事業、経済事業は、過去と決別した新たな発想が必要。また、改革初期は相当なエネルギーを要し、改革が実現するまでには相当な時間を要する。このため、腰を据えてより長い時間軸の中で粘り強く取り組むことができる体制が必要であり、次代を担う世代を中心に権限移譲を実現し、過去の発想としがらみにとらわれず、大胆に実行できる体制を早急に構築し、改革を早期に着手することを求める。
東電は、JERAの先行例を参考に、再編・統合を目指した共同事業体の提案を受け付ける公正なプロセスを開始。このプロセスを通じて、東電が、他の電力会社から事業に対等に取り組みうるパートナーであるとの信頼を勝ち得るよう努力する。
これらの改革を進めるため、東電において、指名委員会等設置会社のガバナンスの下、取締役会と執行陣が密接に連携して改革初動を全うすることを期待。
② 国は、改革実行という視点で関与し、福島事業の安定と経済事業の早期自立を促す
東電改革の基本を実行できる東電の経営体制を国は求めるべき。国は、この視点に合致する限り、外部の人材が過半を占める指名委員会等設置会社の仕組みを最大限活用し、東電の意思決定を尊重。
国は、福島事業の安定と、経済事業の早期自立を求める。国は、2016年度末の経営評価も経て、2019年度に国の関与の基本的な考え方についてレビューを行い、判断。それまでに、改革の進捗を確認しながら、自立の可能性を見極める。
東電が、ベンチマークを達成目標として設定し、厳格に進捗管理を行い、その評価結果を責任とリンクさせることを要請。
③ 東電委員会の今後の対応
東電委員会は、本提言が、国が認定する東電の新・総合特別事業計画の改訂に反映され、東電の手で実行に移されるよう、国に要請。
また、2016年度末から半年は改革初動の時期であり、今後の改革の成否を左右する。福島事業、経済事業、原子力事業とも、次世代を中核とした新たな改革実行の体制が立ち上がり、他の電力会社などと真剣な協議も始まる極めて重要な時期。
そこで、東電委員会は、国から要請を受けて、新・総合特別事業計画の改訂内容と東電改革の実行体制が、この提言内容に沿ったものであるかどうかを確認。
3.原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の改正
2016年12月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針について」において、廃炉・汚染水対策については、東京電力グループ全体で総力を挙げて責任を果たしていくことが必要であり、国はそれに必要な制度整備等を行うこととされたこと等を踏まえ、事故炉廃炉の確実な実施を確保するため、事故炉の廃炉を行う原子力事業者(事故事業者)に対して、廃炉に必要な資金を機構に積み立てることを義務づける等の措置を講ずることを内容とする「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案」が2017年2月に閣議決定されました。同法案は閣議決定日と同日に国会に提出され、2017年5月17日成立しました。
本改正法は2017年10月1日に施行され、これに伴い、機構に廃炉等積立金管理業務が追加されました。
4.新々・総合特別事業計画(第三次計画)
(1)新々・総合特別事業計画(第三次計画)の経緯
政府は、東京電力による迅速かつ適切な賠償の実施を確保するため、2011年11月に機構及び東京電力により政府宛に申請された特別事業計画を初めて認定しました。その後、東京電力による迅速かつ適切な賠償の実施や経営合理化等を含む改革を着実に実施するため、2012年5月には、認定特別事業計画の変更の認定(「総合特別事業計画」の認定)を行いました。当該計画においては、その時点での要賠償額の見通し2兆5,462億7,100万円から、原子力損害の賠償に関する法律第7条第1項に規定する賠償措置額として既に東京電力が受領している1,200億円を控除した金額2兆4,262億7,100万円を、損害賠償の履行に充てるための資金として交付することとしていました。
2013年12月に原子力災害対策本部決定・閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」において、国と東京電力の役割分担が明確化されたこと等、政府は、2014年1月、認定特別事業計画の変更の認定(「新・総合特別事業計画」の認定)を行いました。当該計画において、東京電力は、「責任と競争」の両立を基本に、東京電力グループ全体として賠償、廃炉、福島復興等の責務を全うしていくとともに、電力の安定供給を貫徹しつつ、電力システム改革を先取りした新たなエネルギーサービスの提供と企業価値向上に取り組むこと等とされ、これらの取り組みについて、機構は、2016年度末に「責任と競争に関する経営評価」を行うこととしていました。当該計画では、機構は東京電力に対し、「新・総合特別事業計画」申請時点(2013年12月27日)の要賠償額の見通しから前述の1,200億円を控除した金額4兆4,788億4,400万円を、損害賠償の履行に充てるための資金として交付することとしていました。その後、新たな賠償基準の策定等により、要賠償額が増額する見通しとなったため、政府は2014年8月8日、2015年4月15日、2015年7月28日、2016年3月31日、2017年1月31日に新・総合特別事業計画の一部変更の認定を行いました。
2016年12月末の東電改革提言のとりまとめ等を受け、政府は2017年5月、さらなる認定特別事業計画の変更の認定(「新々・総合特別事業計画(第三次計画)」の認定)を行いました。本計画において、東京電力は、福島第一原子力発電所事故対応に係る必要資金を捻出するため、賠償と復興に引き続き全力を尽くし、廃炉を貫徹していくと同時に、グローバルなベンチマークを踏まえた生産性改革、「地元本位・安全最優先」を前提とした柏崎刈羽原子力発電所の再稼働、送配電や原子力発電の分野における共同事業体の設立を通じた再編・統合を始めとした各事業分野における再編・統合等に取り組むこととしています。また、本計画では、除染等費用の一部について一定の予見可能性が生じてきたことを踏まえて行われた同年7月の一部変更の認定を経て、要賠償額から1,889億2,666万円を控除した9兆5,157億7,733万円のうち、すでに機構が交付した約7兆5,020億円(2017年7月時点)を控除した金額を都度交付する予定となっています。
(2)新々・総合特別事業計画(第三次計画)のポイント
① 新々・総合特別事業計画(第三次計画)の全体像
東電は、賠償と復興に引き続き全力を尽くす。未踏領域に入る廃炉については、長期的な事業実施を着実に行えるよう、「先々を見据えたリスク低減」という基本思想の下で経済事業の状況に左右されない安定的な財源拠出や事業推進体制の確立を行う。
また、一層の収益改善努力やこれまでの事業の枠組みにとらわれない非連続の経営改革によって、公的資本・公的資金を早期に回収することを念頭に置くべき段階にある。このため、グローバルなベンチマークを視野におきながら生産性倍増にさらに取り組むとともに、中長期的には、共同事業体の設立を通じた再編・統合を目指し、さらなる収益力の改善と企業価値の向上を図るものとする。
機構は、福島事業に対しては、体制強化を図る一方で、その他の事業では、早期自立を促すため、体制の合理化を図るといったモニタリングの重点化を行うこととする。このモニタリングの結果に基づき、機構は、国と連携して、2019年度末を目途に同年度以降の関与の在り方を検討する。
② 福島事業
賠償については、引き続き、「最後の一人まで賠償貫徹」、「迅速かつきめ細かな賠償の徹底」及び「和解仲介案の尊重」という新・総合特別事業計画で掲げた「3つの誓い」に基づき、迅速かつ適切な賠償を実施していく。特に、農林業賠償については、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針(2016年12月20日閣議決定)」(以下、「2016年福島復興指針」という。)等を踏まえ、損害がある限り賠償するという方針の下、適切に対応していき、国による営農再開支援や風評払拭に向けた取組に対して最大限協力していく。公共賠償についても、適切な対応の在り方についての検討を加速する。
復興については、東電が国と共同で行うべき責任事業であるとの自覚の下、国等の取組に最大限協力し、復興のステージに応じた貢献を続けていく。
避難指示解除に伴い住民帰還が進展していく中で、福島相双復興官民合同チームへの貢献等を通じて、事業・生業や生活の再建・自立に向けた取組を拡充していき、帰還困難区域についても、除染を含む特定復興再生拠点の整備に係る取組について、最大限の人的協力を行う。
また、東電としても、浜通り地域に福島復興本社の社員をより多く配属し、これまで行ってきた清掃・除草・線量測定等の従来の取組の一層の拡充を図るとともに、復興推進の取組を一層充実させていく。加えて、浜通り地域の将来像の具体化に向けて、各拠点間の連携等により福島イノベーション・コースト構想のさらなる充実を図るとともに、産業基盤の整備や雇用機会の創出に向けて、廃炉等に関連した事業者誘致や地元調達等の真に地元に裨益する取組を推進する。
また、適正かつ着実な廃炉の実施は福島事業の大前提である。東電HDは、国民にとっての廃炉は「事故を起こした者がその責任を果たすため主体的に行うべき収束に向けた活動の一環」であることを深く認識し、自らの責任を果たし、廃炉を貫徹していく必要がある。東電HDは、引き続き汚染水対策と使用済燃料取り出し等に万全を期すとともに、燃料デブリ取り出しなど中長期的廃炉の取組を本格化させていく。
東電HDは、確かな技術基盤の重要性を踏まえつつ、「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ(2015年6月12日廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議決定)」(以下、「中長期ロードマップ」という。)で示された「リスク低減重視」の姿勢の下、優先順位を付けて、安全に作業を進めていくとともに、「東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン」(以下、「技術戦略プラン」という。)など機構による技術的検討を踏まえ、各リスク源に対する適切な低減策を講じていく。
これに加えて、東電HDは、今後、複雑かつ重層的な大規模プロジェクトを数十年にわたって安全かつ着実に遂行していく観点から、プロジェクトを常に見直していく組織運営力とともに、廃炉に係る幅広い技術力、地域・社会と向き合うコミュニケーション能力、安全意識を現場第一線まで徹底する現場ガバナンス等を包括的に具備するべく、「プロジェクト管理機能」を一層強化していく。また、日本原子力発電株式会社(以下、「原電」という。)との協力事業や産官学が一体となった研究開発、海外の知見の活用等により、「日本の総力を結集した廃炉推進体制」を確立していく。
さらに、廃炉等積立金制度が創設された際には、廃炉に係る資金を十分かつ確実に積み立て、機構による管理・監督の下で廃炉を実施していく。
③ 経済事業
東電委員会で示された福島第一原子力発電所事故関連の必要資金規模(約16兆円)に対応するため、廃炉等積立金の積み増し分(毎年2,000億円程度を積み増していく想定)を含む年平均約3,000億円を廃炉のために捻出するなど、賠償・廃炉に関して年間約5,000億円を確保する。加えて、除染費用相当の機構出資に伴う利益の実現に向け、より長い時間軸で、さらに年間4,500億円規模の利益創出も不可能ではない企業体力を確保する。
このため、賠償・廃炉に関して、年間5,000億円を確保するため、グローバルなベンチマークを踏まえた生産性改革により、10年以内に2,000億円超/年の収益改善を実現する。この5,000億円については、東電HDのみならず、最適な役割分担の下で、グループの総力を挙げて経営合理化等を進める中で確保する。
具体的には、送配電事業(東京電力パワーグリッド)において、合理化などにより年平均約1,200億円程度を捻出し、この資金を優先的かつ確実に廃炉に充てることとしている。また、柏崎刈羽原子力発電所については、「地元本位・安全最優先」という理念に沿って対応する。福島原子力事故を深く反省し、安全性を絶えず問い続ける企業文化、責任感を確立するとともに、地元との対話を重ね、立地地域を始めとする社会の信頼を得られる事業運営体制を構築する。これらの取組を通じ、再稼働を実現する。これにより、事業を継続的に実施でき、かつ、より安定的・持続的に賠償・廃炉に必要な資金を確保できる水準の収益力を目指す。
更に、年間4,500億円規模の利益水準に到達するため、今後10年以内に、送配電や原子力発電の分野における共同事業体の設立を通じた再編・統合を始め、各事業分野における再編・統合の歩みを進めつつ、少なくともJERAや子会社・関連会社の持分利益の増加(連結経常利益で3,000億円超/年)を実現し、10年後以降にはこの利益水準を達成することを目指す。
具体的には、燃料・火力事業(東京電力フュエル&パワー)については、2019年度上期に、中部電力との合弁会社であるJERAへの燃料・火力事業の完全統合を目指す。送配電事業については、他電力との対話を進め、2020年代初頭には共同事業体を設立し、新たな枠組みの形成を図る。原子力事業については、国のエネルギー政策を踏まえ、立地地域の理解を得つつ、協力を得られるパートナーを募り、2020年度頃を目途に協力の基本的枠組みを整えていく。
5.賠償の実績
東京電力は、中間指針等を踏まえて、政府による避難等の指示等によって避難を余儀なくされたことによる精神的損害に対する賠償、財物価値の毀損に対する賠償、営業損害に対する賠償等を実施してきました。2018年3月30日現在で、総額約8兆1,632億円の支払いが行われています。今後とも、被害を受けた方々の個別の状況を踏まえて適切かつ迅速な賠償を行っていくよう、国としても東京電力を指導していきます。
【第125-5-1】東京電力による原子力損害賠償の仮払い・本賠償の支払額の推移(2018年3月30日時点)
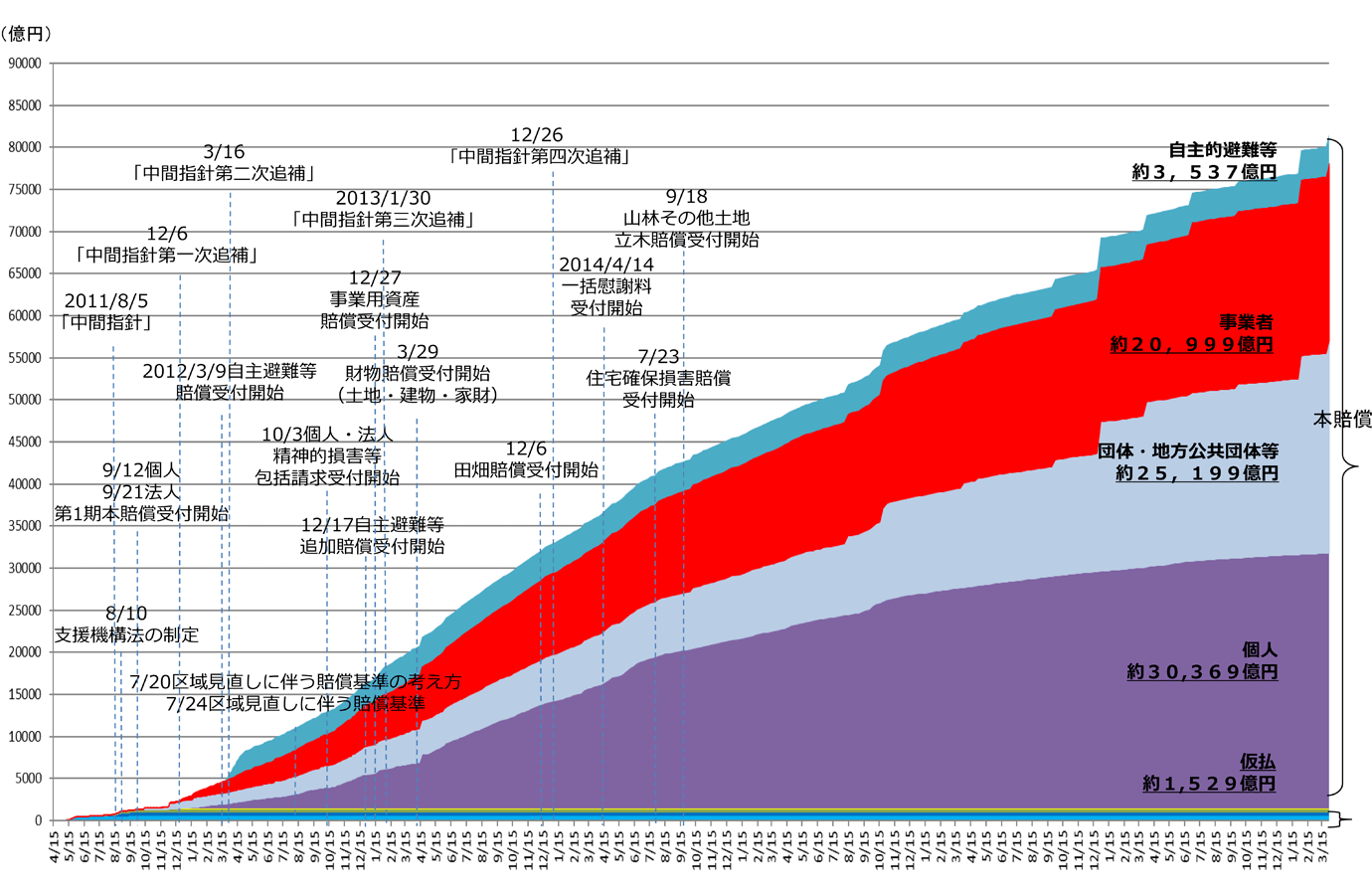
【第125-5-1】東京電力による原子力損害賠償の仮払い・本賠償の支払額の推移(2018年3月30日時点)(ppt/pptx形式:134KB)
- 出典:
- 東京電力ホールディングス資料より経済産業省作成