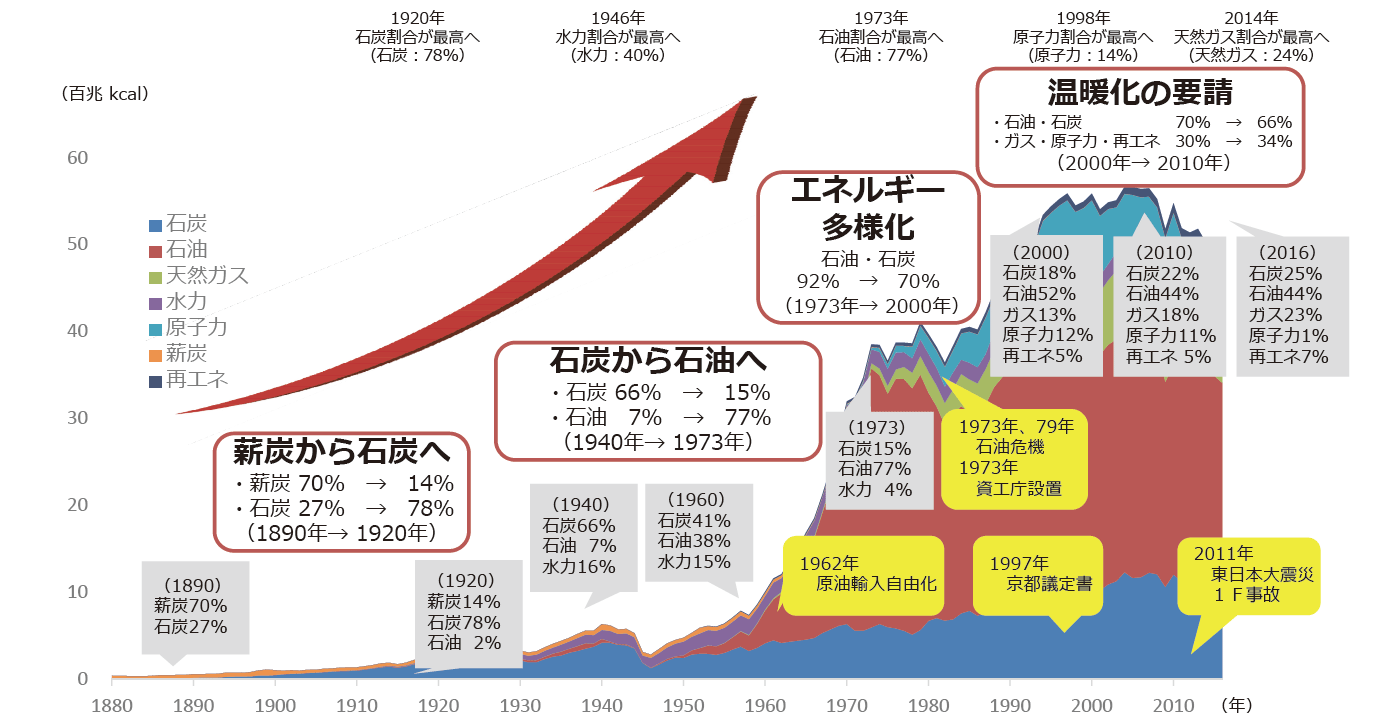はじめに
2018年(平成30年)は、1868年(明治元年)の明治維新から150年の節目の年となります。本章では、明治維新以降の近代化の歴史の中で、我が国のエネルギー開発や利用の歴史を振り返ります。
具体的には、(1)明治維新以降、それまでの薪炭から石炭の利用が本格化し、国内の石油開発が始まった1868年~1900年頃までの時代、(2)二度の世界大戦を経験し、大規模発電所や工場の電化等により電気市場が拡大した1900年頃から1950年頃までの時代、(3)戦後の復興により、高度経済成長を支える電気市場が成長し、石油需要が増大した1940年頃からの時代、(4)資源エネルギー庁設置の契機となった2度の石油危機を経験し、石油のみに依存した状態からの脱却を目指し、①省エネの促進、②石油備蓄拡大、③天然ガスや原子力の導入を推進した1970年・80年代、(5)電力、ガスの自由化が段階的にはじまるとともに、京都議定書により低炭素という環境価値や再エネ導入が注目され、自由化と温暖化の2つの課題に取り組んだ1990年以降の時代、(6)最大の供給危機に直面し、3E(エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合)に加え安全性の重要性を再認識した2011年の東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故までの時代について、それぞれの時代のエネルギーの歴史について紹介します。
- 出典:
- 日本エネルギー経済研究所資料より資源エネルギー庁作成