第1節 各部門における省エネルギーの取組
1.業務・家庭部門における省エネルギーの取組
業務・家庭部門は、産業部門に比べて、エネルギーコストの支出全体に占める割合が少なく、省エネへの取組による金銭的メリットが必ずしも多くないこと等から、需要家に省エネインセンティブが弱く省エネ対策が進みにくい部門です。そのため、トップランナー制度により製造事業者や輸入事業者に対して、エアコン・空調等のエネルギー消費機器や断熱材や複層ガラス、サッシといった建材の高効率化・高性能化を促すことで省エネを一層進めています。
また、家庭のエネルギー消費量の1/4程度を占める空調の効率性をより高めるため、住宅・建築物の外皮(壁・窓等)の高断熱化を進め、住宅・建築物の省エネ性能を向上させることが重要です。建材トップランナー制度では、住宅からの熱損失の81%をカバーしています。
さらに、住宅の高断熱化は省エネのみならず、高血圧症等の健康改善や、ヒートショックリスク低減といった効果も期待されており、こうした間接的便益の視点からも重要となっています。
【第321-1-1】住宅からの熱損失の割合
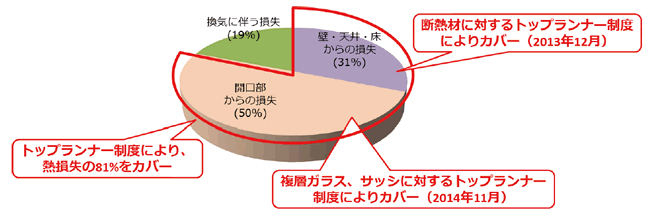
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
<具体的な主要施策>
(1)省エネ法に基づく産業トップランナー制度の流通・サービス業への拡大及びSABC評価制度の運用【制度】
省エネ法上の特定事業者(事業者単位で年度あたり原油換算1,500kl以上エネルギーを使用する事業者)に対しては、エネルギー消費原単位(エネルギー使用量とそれと密接な関係を持つ値の比率)の年平均1%以上低減を努力目標として定め、エネルギー消費原単位の低減率などを踏まえ、特定事業者の省エネへの取組を評価してきました。
他方、エネルギー消費原単位の算出方法は事業者により異なり、事業者間の省エネへの取組を相対的に比較することは難しいため、業界ごとの状況を考慮した新たな指標を設定し、事業者に業界における客観的な位置付けに基づいた取組を促す産業トップランナー制度を2008年に導入し、2016年度から対象業種を現状の製造業から流通・サービス業に広げています。具体的には、「日本再興戦略2016」(2016年6月閣議決定)に示された、3年以内に全産業のエネルギー消費の7割に対象を拡大するとの方針に沿って、まず、2016年4月にコンビニエンスストア業に導入しており、2017年度からはホテル・百貨店にも導入しました。引き続き、スーパー、貸事務所、ショッピングセンター等への導入を検討していきます。
また、2016年度から開始された事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)は、優良事業者と停滞事業者を中心に、事業者全体の省エネへの取組に対する意欲を向上させることを目的としています。2016年度は12,412事業者のうち、7,775事業者をSクラスと位置付け、経済産業省ホームページで公表しました。2016年度の実施結果のフォローアップを踏まえ、今後、事業者の自主的な省エネへの取組をさらに促進するためのSABC評価制度の活用を検討していきます。
(2)省エネ法に基づくトップランナー制度による機器の効率改善【制度】
省エネ法に基づくトップランナー制度を通じて、製造事業者及び輸入事業者に対して機器の効率改善を促した結果、多くの機器において、基準の策定当初の見込みを上回る効率改善が達成されています。
2016年には、照明のトップランナー基準の対象を白熱灯等へ拡大するため、電球類及び照明器具のトップランナー制度の対象機器への追加について、「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会照明器具等判断基準ワーキンググループ」において審議を行いました。加えて、2017年3月にはトップランナー制度の対象機器に新たにショーケースを追加し、基準等を策定しました。この結果、2017年4月時点で、32品目(うち3品目は建材)がトップランナー制度の対象機器に指定されています。
(3)省エネルギー機器に関する情報提供
家電製品やガス石油機器等について、省エネルギー機器のさらなる普及を促進すべく、小売事業者表示制度(省エネルギーラベル(注1)及び統一省エネルギーラベル(注2)を活用し、消費者に対して省エネ情報の提供を行いました。さらに、本制度をより市場の実態に即した形に見直すべく、本制度に対するニーズ調査等も行いました。
【第321-1-2】省エネルギーラベル(左)と統一省エネルギーラベル(右)

(4)業務・家庭部門における省エネルギーを促進するための情報提供事業情報提供事業
省エネへの理解や関心度を高めることによって省エネ行動を促し、業務・家庭部門における省エネを促進することを目的として、一般消費者及び事業者等に向けて省エネに関する客観的な情報や省エネ対策の先進事例等に関する情報提供を行いました。
具体的には、夏季・冬季における省エネの呼びかけ、省エネ関連のイベント・展示会・メディア等を活用した省エネ施策の紹介や省エネ機器・省エネ支援サービスの周知、住宅の省エネに関する認知度・理解度向上等、省エネに関する情報提供を行いました。
(5)ZEB・ZEHの実現・普及に向けたロードマップの実行
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)とは、室内外の環境品質を低下させることなく、大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)により、年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した建築物・住宅です。省エネ性と快適性を両立させるとともに、業務・家庭部門におけるエネルギー消費の抜本的改善に資する省エネ建築物・住宅です。
2014年に策定されたエネルギー基本計画において、「建築物については、2020年までに新築公共建築物等で、2030年までに新築建築物の平均でZEBを実現することを目指す。また、住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」とする政策目標が設定されました。これを受けて、2015年に取りまとめられたZEB・ZEHのロードマップを基に、2016年度はZEHの価格低減・普及加速化のため、ZEHの普及目標を掲げたハウスメーカー等(ZEHビルダー)の登録制度を開始し、2016年2月時点で約4,500社がZEHビルダーとして登録されました。また、ZEHのブランド化を図るため、「ZEHマーク」を作成しました。ZEHマークは、第三者による省エネ性能評価を受けた住宅、ZEHビルダーが製作する住宅カタログ、及びZEH実現に必要な高性能建材・高効率設備に表示することが可能です。
(6)住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金【2016年度当初:110.0億円】
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及加速事業【2016年度補正:100.0億円】
ZEBロードマップを基に、ZEBの実現・普及のためのZEB設計ガイドラインの作成を目的として、年間の一次エネルギー消費量を一定以上削減できる省エネ建築物に対し、その構成要素となる高性能設備機器や高性能建材等の導入に関する実証事業を行いました。住宅についても、ZEHロードマップを基に、ZEHビルダーが設計・建築・改築するZEHへ支援を行いました。また、ZEHビルダーの登録制度開始によるZEHの担い手の拡大を踏まえ、2016年度第2次補正予算においてZEH普及の加速を目的とした支援を行っており、引き続き、ZEHの市場拡大及び自立的普及に向けた取組を進めていきます。
(7)住宅省エネリノベーション促進事業
【2015年度補正:100.0億円】
住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するため、一定の省エネ性能を満たす断熱材や窓等を活用した断熱改修を支援するとともに、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(給湯設備等)の導入支援を行いました。
(8)住宅・建築物の省エネルギー基準の適合義務化
エネルギー基本計画においては、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020 年までに新築住宅・建築物の段階的な省エネ基準適合義務化を行うこととしています。2015年7月には、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布されました。その後、エネルギー消費性能基準等の整備について、「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ」(経済産業省と国土交通省との合同会議)にて審議しました。なお、エネルギー消費性能向上計画の認定制度等の誘導措置については2016年4月に施行されており、省エネ基準への適合義務等の規制措置についても、2017年4月に施行されました。
(9)省CO2型社会の構築に向けた社会ストック対策支援事業のうち省CO2型福祉施設等モデル支援事業
【2016年度当初:40.5億円の内数】
公共性が高い社会システムの省エネ・省CO2対策の一つとして、福祉関係施設等に対し、CO2削減ポテンシャル調査及び高効率の省CO2型給湯設備・空調設備やコジェネレーションシステム等の導入支援を行いました。
(10)環境・ストック活用推進事業
【2016年度当初:109.5億円、2016年度補正:1.5億円】
住宅・建築物の省エネ対策を促進するため、先導的な省CO2技術を導入する住宅・建築物リーディングプロジェクト、住宅・建築物ストックの省エネ改修及び診断・表示等に対して支援を行いました。
(11)住宅に係る省エネルギー改修税制【税制】
既存住宅において一定の省エネ改修(高断熱窓への取替等)を行った場合で、当該改修に要した費用が一定額以上のものについて、所得税の税額控除及び固定資産税の特例措置が講じられています。
(12)優良住宅整備促進事業
【2016年度当初:243.0億円の内数】
住宅金融支援機構が行う証券化支援事業の枠組みを活用し、省エネ性能に優れた住宅を取得する際の金利の引下げを行う「フラット35S」を実施しました。
(13)住宅性能表示制度等の効果的運用【制度】
住宅の性能について消費者等の選択を支援するため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、省エネ性能を含む住宅の性能を分かりやすく表示する「住宅性能表示制度」の普及に加え、建築物を室内等の環境品質・性能の向上と省エネ等の環境負荷の低減という両面から総合的に評価し、分かりやすく表示するシステムである建築環境総合性能評価システム(CASBEE)の開発及びその普及を推進しました。
また、建築物省エネ法における誘導措置(2016年4月施行)として、省エネ性能の優れた建築物の認定制度及び省エネ基準適合認定マーク、省エネ性能表示のガイドラインに従った「建築物省エネルギー性能表示制度(BELS:Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)」の普及促進を図っています。
(14)低炭素住宅・建築物の認定【制度】
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、省エネ基準より高い省エネ性能を有し、低炭素化に資する措置等が一定以上講じられている低炭素認定建築物の普及促進を図りました。
(15)低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業
【2016年度当初:2.7億円】
各家庭で省エネ・省CO2化を促進するためには、ライフスタイルに応じた具体的なアドバイスが効果的であることが分かりました。
そこで、さらなる低炭素ライフスタイルへの転換を促進し、家庭部門からのCO2削減を実現することを目的に、「家庭エコ診断制度」を実施し、民間企業や地方公共団体等のネットワークを活用して、家庭における着実な省エネを推進しました。
(16)超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
【2016年度当初:17.2億円】
今後情報処理量が急増すると予想されるサーバ等のIT機器の消費電力を大幅に削減するため、光信号と電気信号を変換する小型チップを開発し、光回路と電子回路を組み合わせて、IT機器の省電力、高速、小型化が可能となる光エレクトロニクス技術開発を行いました。
(17)クリーンデバイス多用途実装戦略事業
【2016年度当初:5.5億円】
大きな省エネポテンシャルを有する革新的デバイスを多様な用途に活用すべく、標準化・共通化、信頼性・安全性担保の方針策定等の基盤整備を推進しました。これにより民間活力を引き出し、革新的デバイスを実装した新たな製品・サービスを創出することで省エネを促進しています。
(18)HEMS等に係る標準化に関する取組【制度】
業務・家庭部門のエネルギーマネジメント等を普及拡大していくためには、発電所から家電機器までが一つのネットワークで繋がり、相互に通信可能な環境が整うことが必要です。そのため、産学官の検討の場である「スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会」において、EMS(Home Energy Manegment System)を中心とした家庭内機器の通信規格である「ECHONET Lite」の普及拡大に向けた取組等を推進しています。
2016年度は、HEMSと重点機器との相互接続性強化のため、ミドルウェア部分およびアプリケーション通信インターフェース(AIF)の第三者認証制度が開始、「ECHONET Lite」の普及拡大の基盤が構築されました。
さらに、太陽光発電の出力制御システムとHEMSとの連携のあり方について検討を進めるとともに、IoT技術を活用したより効率的なエネルギー活用の実現に向けて、アグリゲーターが需要家側のエネルギーリソース(太陽光発電施設、蓄電池、電気自動車、エネファーム、ネガワット等)を最適遠隔制御する「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」のユースケースとして、蓄電池、家庭用ヒートポンプ給湯器、業務用エアコン、業務用ショーケース、電気自動車用充放電器、エネファームといったエネルギーリソースの遠隔制御に対応した通信規格を策定しました。
(19)エネルギー小売事業者の省エネガイドラインの検討
2016年4月に始まった電力の小売全面自由化の中で、多様な製品・サービスが登場し、需要家のエネルギーの使い方が大きく変化すると考えられます。そこで、「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会」において、需要家と直接の接点を持ち、省エネ法で情報提供の努力義務が求められているエネルギー小売事業者による、需要家に対する省エネに資する情報提供等のあり方に関する検討を行いました。
(20)地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業【2016年度当初:50億円】
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定・改定や企画・実行・評価・改善のための体制整備に向けた調査・検討に係る費用を補助するとともに、この実行計画に基づく省エネ設備等の導入を支援しました。
2.運輸部門における多様な省エネルギー対策の推進
運輸部門は、2005年度の省エネ法改正により、一定量以上の輸送を行う貨物・旅客輸送事業者と輸送事業者に輸送を行わせる荷主が省エネ法の定期報告等の対象となりました。長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)において最も省エネ量を見込んでいる部門であり、運輸部門の省エネを推進することは重要です。今後、運輸部門における省エネを進めるためには、乗用車やトラック等輸送機器単体のエネルギー消費効率を進めるとともに、貨物輸送事業者と荷主の連携等による面的な省エネ努力を進める必要があります。
<具体的な主要施策>
(1)自動車の燃費基準【規制】
自動車燃費基準については、省エネ法に基づくトップランナー制度が導入された1999年に2010年度燃費基準を、2007年に2015年度燃費基準を策定する等、順次見直しを実施してきました。これらにより、ガソリン乗用車では2010年度に1995年度と比較して、約49%の改善が図られました。また、2006年には、世界初の重量車に対する燃費基準(2015年度基準)を策定しました。2013年には、さらなる省エネの推進等の観点から、乗用車の2020年度燃費基準を策定しました。加えて、2015年には、小型貨物自動車の2022年度燃費基準を策定しました。2016年には、乗用車等の燃費基準に国際調和燃費・排出ガス試験法(WLTP)を導入するため、関連法令の改正を行いました。
(2)自動車重量税・自動車取得税の軽減措置【税制】
2009年度に導入したエコカー減税について、燃費性能がより優れた自動車の普及促進等の観点も踏まえ、対象範囲を2020年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化するとともに、自動車市場にも配慮する観点から、2017年度においては2015年度燃費基準による従来の減税対象車の一部を引き続き減税対象とし、延長しました(自動車重量税:2017年5月から2019年4月まで、自動車取得税:2017年4月から2019年3月まで)。
(3)自動車税・軽自動車税の減免措置【税制】
排出ガス性能及び燃費性能が優れた環境負荷の小さい自動車・軽自動車(四輪)に対して、自動車税・軽自動車税の軽減措置(グリーン化特例)を燃費性能の向上に応じて対象を重点化した上で延長しました(2017年4月から2019年3月末まで)。
(4)クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金
【2016年度当初:137.0億円】
運輸分野における二酸化炭素の排出抑制や石油依存度の低減を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、燃料電池自動車等の導入に帯する補助を行いました。
(5)中小トラック運送業者向け環境対応型ディーゼル
トラック補助事業【2016年当初:29.7億円】投資余力の少ない中小トラック運送業者が燃費性能の低い長期経年車を使用し続けている状況に鑑み、中小トラック運送業者のCO2排出削減対策として、燃費性能の高い環境対応車両への代替を促進するため、環境対応型ディーゼルトラックの導入に対する補助を行いました。
(6)クリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関する研究開発【2016年度当初:4.0億円】
自動車の燃費向上及び排気ガス低減に向け、自動車産業のみならず、自動車産業以外の産業や大学等における研究成果を活用したクリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関する研究開発に対して、補助を行いました。
(7)交通需要マネジメントの推進
依然として厳しい道路交通渋滞を緩和し、道路交通の円滑化を図るため、バイパス・環状道路の整備や交差点の改良等の交通容量の拡大策等に加えて、既存ネットワークの最適利用を図るなど道路を賢く使う取組として、パークアンドライドの推進、情報提供の充実、相乗りの促進、時差通勤・通学、フレックスタイム制の導入等により、道路利用に工夫を求め、輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネジメント(TDM)を推進しました。
(8)自動走行の実現に向けた取組の推進
車両の効率的な走行を可能とする自動走行技術の社会実装が進むことで省エネルギー推進に貢献するため、高度な自動走行の普及に向けて重要となる基盤技術の研究開発を実施するとともに、民間の自動走行システムの実用化に向けた取組を促進しました。
(9)道路交通情報提供事業の推進
交通管制システム等で収集した道路交通情報を積極的に提供するほか、民間事業者が行う道路交通情報提供サービスの多様化・高度化を支援することにより、渋滞緩和及び環境負荷低減を図りました。
(10)違法駐車対策の推進【規制】【制度】
都市における円滑な交通流を阻害している違法駐車を防止し排除するため、駐車規制の見直し、地域の実態に応じた取締り活動ガイドラインによる取締りの推進、違法駐車抑止システムの運用等のハード・ソフト一体となった駐車対策を推進しました。
(11)路上工事の縮減
電気・通信・上下水道等のライフラインをまとめて収容し、道路の掘り返しを抜本的に縮減する共同溝整備を推進するとともに、複数の占用企業者等が工事実施時期を合わせて施工する共同施工の実施等、効率的な道路工事を推進しました。また、年末年始・年度末、観光シーズン及び地域の行事等の工事抑制を実施するなど、地方公共団体や占用企業者等とともに、地域の道路利用を踏まえたきめ細やかな路上工事対策を実施しました。
(12)交通安全施設等の整備
【2016年度当初:177.2億円】
交通管制システムの高度化及び信号機の改良等を推進し、交差点における発進・停止回数を減少させること等により道路交通の円滑化等を図るとともに、消費電力が電球式の約6分の1以下であるLED式信号機の整備を推進しました。
(13)道路施設の省エネルギー化
道路照明灯の新設及び既設の高圧ナトリウム灯等の更新に当たり、省エネルギー対策や環境負荷の低減に資するLED道路照明灯の整備を実施しました。
(14)モーダルシフト、物流の効率化等
鉄道・内航海運等のエネルギー消費効率が優れた輸送機関の活用を進めるため、関係事業者・国土交通省等により、幹線輸送の低炭素化に資するモーダルシフトに必要な設備導入経費の一部補助、貨物輸送における環境にやさしい鉄道・海運の利用促進を図ることを目的とした「エコレールマーク」・「エコシップマーク」の普及・促進等、鉄道や内航海運の利便性向上のための施策を推進することによりモーダルシフトを推進しました。併せて、「モーダルシフト等推進事業」において、荷主企業と物流事業者が協力して行う事業への支援を実施するとともに、「グリーン物流パートナーシップ会議」において、荷主企業、物流事業者等の関係者の連携による、物流分野における環境負荷の低減、物流の生産性向上等持続可能な物流体系の構築に資する優れた取組を行った事業者に対して国土交通大臣表彰、国土交通省物流審議官表彰、経済産業大臣表彰、経済産業省商務流通保安審議官表彰等を授与しました。
また、物流の効率化に資するよう、トラックの大型化・トレーラー化によるトラック輸送の効率化、国際物流に対応した道路ネットワークの整備、港湾における省エネルギー化の取組や港湾のターミナルの整備、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」による支援等を進めることを通じて、効率的な物流体系の構築を推進しました。
(15)低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金のうち、物流の低炭素化促進事業
【2015年度当初:73.0億円の内数】
地域の低炭素化に貢献する物流システムを構築するため、共同輸配送の実現に要する設備導入経費や、物流設備の省エネ化・物流業務の効率化の一体的実施に必要な設備導入経費、大型CNGトラック購入費やCNG充填施設の整備費、モーダルシフトに必要な設備導入経費の一部補助を行い、地域内輸送、幹線輸送、物流拠点の各段階におけるCO2抑制に資する効果的な対策を総合的に支援しました。
(16)次世代物流システム構築事業費補助金
【2016年度当初:1.4億円】
従前の施策だけでは十分に省エネ対策を図ることができない運輸分野について、荷主と連携して行う環境負荷低減及び物流効率化のための先行事業を行いました。
(17)鉄道分野の更なる環境性能向上に資する取組
鉄道分野における更なる省エネ・省電力化・低炭素化の取組を推進するため、節電、省エネ効果が期待される次世代ハイブリッド車両等の技術開発を推進するとともに、「エコレールラインプロジェクト」等により、エネルギー効率の良い車両の導入、鉄道駅や運転司令所等に対する再生可能エネルギーや省エネ設備の導入等、省電力化、低炭素化について計画的に取り組む鉄・軌道事業者を支援しました。
(18)鉄道技術開発費補助事業
【2016年度当初:4.8億円】
節電、省エネ効果が期待される次世代ハイブリッド車両の開発といった鉄道分野の安全対策、環境対策等に係る技術開発に要する費用の一部を補助しました。
(19)省CO2型社会の構築に向けた社会ストック対策支援事業のうちエコレールラインプロジェクト事業
【2016年度当初:40.5億円の内数】
駅舎及び運行に必要な施設(トンネル、検車場、車両基地、変電所)等の施設への省エネ機器導入、車両等の設備の省エネ化を推進する鉄・軌道事業者等に対し、補助を行いました。
(20)公共交通機関の利用促進
鉄道・バス等公共交通機関については、混雑緩和、輸送力増強、速達性の向上等を図ることが重要です。鉄道については、三大都市圏において混雑緩和や速達性向上のための都市鉄道新線や複々線化等の整備を推進しました。また、貨物線の旅客線化等の既存ストックの高度利用を推進するとともに、乗継円滑化等に対する支援措置を講じることによる利用者利便の向上施策を講じました。
一方、バスについては、公共車両優先システム(PTPS)の整備、バス専用・優先レーンの設定等により、定時運行の確保を図るとともに、バスロケーションシステムの整備等に対する支援措置による利用者利便の向上施策を講じました。また、事業所単位でのエコ通勤の取組支援として、エコ通勤優良事業所認証制度により655事業所を認証・登録(2017年3月末現在登録数)し、マイカーから公共交通等への利用転換の促進を図りました。
多様な交通モードが選択可能で利用しやすい環境を創出し、人とモノの流れや地域の活性化を促進するため、バスを中心とした交通モード間の接続(モーダルコネクト)の強化を推進しています。
また、2016年4月には、新宿駅南口に日本最大級のバスターミナルであるバスタ新宿が開業しました。バスタ新宿は道路事業(国道20号)で基盤整備を行い、民間バスターミナルが施設運営を行う官民連携事業により整備がなされ、鉄道と直結し、新宿駅西口周辺に19箇所点在していた高速バス停が集約されました。今後は、利用者の意見も踏まえながら、コンビニの本格営業やベンチの増設等の利便性のさらなる向上、国道20号の渋滞対策の強化を推進していきます。
(21)エコドライブの普及・推進
警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成する「エコドライブ普及連絡会」において、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる11月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジウムの開催や全国各地でのイベント等を連携して推進し、積極的な広報を行いました。併せて、当該連絡会が策定した「エコドライブ10のすすめ」の普及・推進に努めました。
(22)輸送機器の実使用時燃費改善事業費補助金
【2016年度当初:62.5億円】
実運行時の燃費改善を実証するため、トラック輸送事業者に対して、専門のコンサルタント会社からエコドライブ指導を受講するための経費や、エコドライブマネジメントシステム(EMS)用機器の導入に必要な経費等を支援しました。また、自動車の整備を高度化して実運行時の燃費向上を図るため、整備事業者に対して、次世代自動車に対応したスキャンツールの導入に必要な経費等を支援しました。さらに、船舶の実運航時の燃費改善を実証するため、内航海運事業者等に対して、革新的省エネ船舶の設計・建造等の経費等を支援しました。
(23)省エネ法に基づく運輸分野の省エネルギー措置【規制】
2005年に改正した省エネ法において、一定規模以上の輸送事業者及び荷主に対し省エネ計画の策定、エネルギー使用状況の報告を義務付ける等、運輸分野における対策を導入しました。2016年度においても、引き続き省エネ法に関する周知徹底等、事業者の省エネ取組の推進を行うとともに、省エネ法に基づく事業者からの定期報告書の内容から、省エネの取組が不十分であると判断された事業者に対して、エネルギー管理の徹底を図るべく、省エネ法に基づく指導を実施する等の措置を行いました。
また、省エネ法では、「判断基準」において、貨物輸送事業者との連携等による省エネ努力を求めています。Eコマース等の発展に伴い、小口輸送・再配達が増加し、運輸部門のエネルギー消費の構造に変化が見られる中、効率的な物流を構築するため、貨物輸送事業者に貨物輸送を発注する荷主と貨物輸送事業者の連携を強化することが必要です。支援措置や省エネ法に基づく規制制度の見直しについて、「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会」において議論し、2017年1月に中間とりまとめを公表しました。
(24)革新的新構造材料等技術開発
【2016年度当初:36.5億円】
部素材・製品メーカー、大学等が連携し、軽量化が求められている輸送機器への適用を軸に、強度、加工性等の複数の機能を向上した炭素繊維複合材料、革新鋼板、マグネシウム合金等非鉄軽金属材料等の高性能材料の開発に重点をおくとともに、異種材料の接着を含めた接合技術の開発等を行いました。
(25)革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発
【2016年度当初:28.8億円】
車載用蓄電池の大幅な性能向上、コスト低減に向け、2030年に500Wh/kgを達成する革新型蓄電池の実用化に向けた共通基盤技術の開発を行いました。
(26)リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発
【2016年度当初:14.5億円】
電気自動車等に搭載するリチウムイオン電池の性能を限界まで追求する技術開発を行うとともに、安全性・寿命等に関する試験方法の開発を行いました。
3.産業部門等における省エネルギーの加速
産業部門の最終エネルギー消費量は、1970年代の石油危機以降、省エネ設備の積極的導入によって、2割近く減少していますが、依然として全体の4割以上を占めていることから、今後もより一層の省エネを進めていく必要があります。
そこで、省エネ法に基づきエネルギー管理を徹底して行うとともに、製造プロセスの改善や省エネ改修等の省エネ設備投資に対する支援施策を講じ、規制と支援の両面から、事業者の省エネへの取組を促しています。
また、業種横断的に、大幅な省エネを実現する革新的な技術の開発を促進しています。加えて、スマートなエネルギー使用の取組を促すため、工場のエネルギー管理システム(FEMS)などのエネルギーマネジメントシステム設備の導入を促すとともに、エネルギーマネジメントの手順を定めたISO50001の認証取得を促進し、省エネ対策の情報提供等を実施しています。
<具体的な主要施策>
(1)省エネ法に基づくエネルギー管理の徹底【制度】
省エネ法に基づき指定された特定事業者等から提出された定期報告書並びに省エネ法に基づく第一種エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等及び特定事業者等の本社機能を有する事務所を対象とした現地調査により、工場等判断基準の遵守状況等を確認しました。確認の結果、省エネの取組が不十分であると判断された事業者に対して、エネルギー管理の徹底を図るべく、省エネ法に基づく指導を実施する等の措置を行いました。
これまで、現地調査は努力目標1%削減未達の事業者からランダムに抽出して実施していましたが、省エネへの取組が停滞している事業者を効果的に抽出するために、2016年度から、省エネ法の定期報告を提出する全ての事業者を定期報告の結果に基づき、S・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施する事業者クラス分け評価制度を導入しました。具体的には、優良事業者(S)を業種別に公表する一方で、停滞事業者以下(B,C)1,207社に対して注意喚起文書を送付するとともに現地調査を370事業者に対して実施することで、より重点的に省エネへの取組の改善を促しました。また、事業者の未利用熱購入を省エネへの取組として評価する未利用熱活用制度を創設し、定期報告のエネルギー消費原単位の算出にあたって、未利用熱の販売側に加えて、購入した側についても、未利用熱分のエネルギーをエネルギー使用量から差し引くこととしました。
(2)エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
【2016年度当初:515.0億円】
工場・事業場等において、省エネ効果や電力ピーク対策効果が高く、費用対効果が優れた先端的な設備等の導入を促進するため、これらを導入する事業者に対して費用の一部を補助する支援を行いました。また、同様に複数工場間で一体となって省エネを行う事業者に対しても支援を行いました。
(3)中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業
【2015年度補正:442.0億円】
中小企業等の省エネへの取組を支援するため、導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える補助制度を創設しました。高効率の省エネ設備への更新等を重点的に支援することで、中小企業等の事業の生産性や省エネ性能を向上させ、競争力の強化につなげます。
(4)低炭素社会実行計画の推進・強化【制度】
2016年5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」において、低炭素社会実行計画を産業界における対策の中心的役割と位置づけ、2030年度削減目標の達成に向けて産業界による自主的かつ主体的な削減貢献の取組を進めていくこととしています。政府としても、透明性・信頼性・目標達成の蓋然性の向上の観点から、低炭素社会実行計画の2015年度実績について、審議会による厳格な評価・検証を実施しました。具体的には、目標達成の蓋然性を確保するため、2015度に実施した取組を中心に各業種の進捗状況を点検し、2020年及び2030年の目標達成に向けて着実に対策が実施されていることを確認しました。また、足下の実績や取組だけでなく、業界や部門の枠組みを超えた主体間連携による削減貢献、優れた製品や技術、素材、サービスの普及等を通じた国際貢献、革新的技術の開発や普及による削減貢献といった各業種の取組についても深掘りし、こうした削減貢献を可能な限り定量化することにより、貢献の可視化とベストプラクティスの横展開等を促進しました。現在、115業種がこの自主的取組に参画していますが、産業界の取組は、国内事業活動における排出削減だけでなく、低炭素製品・サービスや優れた技術・ノウハウの普及により、地球規模での削減に貢献しています。より多くの業種の参加促進や、審議会における業種横断的な意見交換を通じたベストプラクティスの競い合いや主体間連携の促進、国内外に向けた各業種の取組内容の積極的な発信、審議会による厳格な評価・検証を通じて、引き続き産業界の削減貢献の取組を後押しします。
(5)戦略的省エネルギー技術革新プログラム
【2016年度当初:77.5億円】
開発リスクの高い革新的な省エネ技術について、シーズ発掘から事業化まで一貫して支援を行う提案公募型研究開発事業を実施しました。2016年度においては、「省エネルギー技術戦略2011」に掲げる重要技術を軸に、インキュベーション研究開発フェーズ3件、実用化開発フェーズ5件、実証開発フェーズ1件の計9件を新規採択しました。
また、省エネ技術の研究開発及び普及を効果的に推進するため、省エネに大きく貢献する重要分野を特定した「省エネルギー技術戦略2016」を2016年9月に策定しました。
【第321-3-1】戦略的省エネルギー技術革新プログラムのイメージ図
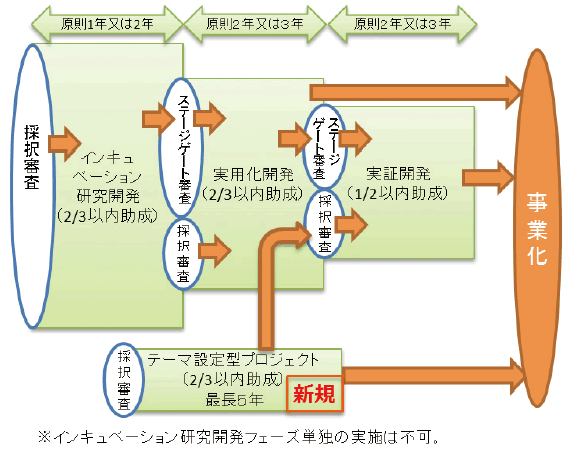
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(6)次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト
【2016年度当初:21.5億円】
電力を自在に操ることができるパワー半導体の新材料として期待される、耐電圧性及び耐熱性の高いSiC(炭化ケイ素)を応用した新型パワーエレクトロニクス装置等の開発を行いました。また、高い材料特性を有する我が国発のGaN(窒化ガリウム)をパワー半導体に適用するための応用基盤技術開発を行いました。
(7)グリーン購入・調達及び環境配慮契約の推進【制度】
国等における省エネ機器・設備を始めとした環境物品等の率先的な調達は、その初期需要創出や市場拡大に寄与するとともに、我が国全体での当該物品等の普及に資するものとして意義があり、国及び独立行政法人等は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(環境配慮契約法)を踏まえ、照明や空調設備等の物品等を調達する際には、率先して省エネルギー機器・設備を導入するとともに、電力の供給を受ける契約等において環境配慮契約の推進に取り組みました。
また、2016年度は、グリーン購入法においてディスプレイ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、庁舎管理等の特定調達品目に係る判断の基準等の見直しを行いました。また、環境配慮契約法において電気の供給を受ける契約に係る基本方針の見直しを行い、入札参加者に必要な資格として電源構成及び二酸化炭素排出係数の開示を位置づけました。
(8)グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業
【2016年度当初:4.4億円】
J-クレジット制度の運営及び同制度を活用する中小企業等に対し、申請書の作成支援等を実施するとともに、同制度におけるクレジット需要を開拓するため、各種制度との連携を図りつつ、クレジット活用推進事業を行いました。
(9)エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業費補助金【2016年度当初:27.0億円】
省エネ設備の導入や一部のトップランナー機器の設置を行う事業者が民間金融機関等から融資を受ける際の金利を引き下げるため、利子補給金を交付しました。
(10)省エネルギー対策導入促進事業費補助金
【2016年度当初:7.5億円】
中小・中堅事業者等に対し、省エネ・節電ポテンシャルの診断等を無料で実施するとともに、具体的な診断事例や省エネ技術などを広く情報発信し、横展開を図りました。また、中小企業等における省エネ投資等の支援を強化するため、「日本再興戦略2016」に示された、省エネルギー相談地域プラットフォーム(省エネ支援事業者が地域の商工会議所や自治体、コンサル及び金融機関等と協力して作る連携体)を拡大し、2017年度までに全国に省エネへの取組に係る支援窓口を構築するとの方針に沿って、2016年度は省エネルギー相談地域プラットフォームを19箇所に構築しました。
(11)環境調和型製鉄プロセス技術開発
【2016年度当初:21.4億円】
我が国の鉄鋼業は、排熱回収利用等の主要な省エネ設備を既に導入しており、製鉄プロセスにおけるエネルギー効率が世界最高水準であると同時にエネルギーの削減ポテンシャルが少ない状況です。他方で、高炉法による製鉄プロセスでは鉄鉱石を石炭コークスで還元するため、多量の二酸化炭素排出は避けられません。二酸化炭素排出量の約3割を削減することを目指して、①コークス製造時に発生する副生ガスに含まれる水素を増幅し、コークスの一部代替に当該水素を用いて鉄鉱石を還元する技術、②二酸化炭素濃度が高い高炉ガスから二酸化炭素を分離するため、製鉄所内の未利用低温排熱を利用した新たな二酸化炭素分離・回収技術の開発等を行いました。
【第321-3-2】環境調和型製鉄プロセス(CO2 Ultimate Reduction in Steelmaking process by Innovative technology for cool Earth 50)のイメージ図
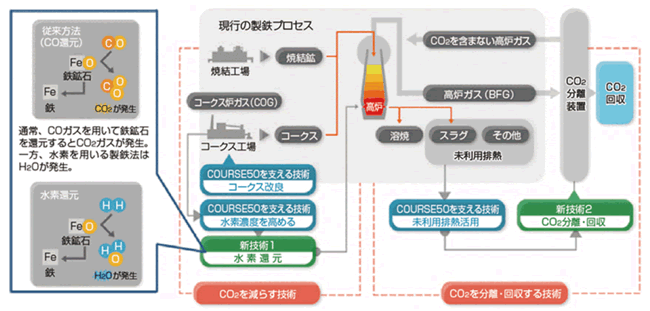
(12)超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト
【2016年度当初:17.8億円】
従来技術の延長線上に無い機能を有する超先端材料の創製とその開発スピードの劇的な短縮を目指し、計算科学、プロセス技術、計測技術から成る革新的な材料開発基盤技術の開発を行いました。
(13)高輝度・高効率次世代レーザー技術開発
【2016年度当初:20.0億円】
レーザー加工における省エネ化を進めるため、現在主流である炭酸ガスを用いたレーザー技術ではなく、従来にない高効率かつ高輝度(高出力・高ビーム品質)なレーザー技術の開発を行いました。
(14)高温超電導実用化促進技術開発
【2016年度当初:15.0億円】
大きな市場創出が期待される高磁場コイル分野や送配電分野において、超電導技術を世界に先駆けて社会実装することを目指し、高磁場を安定して発生させるコイルの設計・製造技術や長距離送配電区間を効率的に冷却する技術などの開発に取り組むとともに、送配電システムの実証を行いました。
4.部門横断的な省エネルギーの取組
各部門における徹底した省エネだけでなく、部門横断的に省エネを促していくことも重要です。そのため、事業者や消費者といった対象を特定せず、広く積極的な省エネを促す取組を行いました。
<具体的な主要施策>
(1)省エネルギー設備導入等促進広報事業
【2016年度当初:3.4億円】
国民の皆様から省エネに対する理解と協力を得るため、例えば夏季及び冬季を中心に積極的な省エネを実践していただくためのきめ細かなキャンペーンなどを実施するなど、省エネに関する客観的な情報提供を行いました。また、徹底した省エネと経済成長を両立するには、企業にビジネスの観点からも省エネに取り組むためのインセンティブを付与することが必要です。そこで、繊維・ファッション業界固有の省エネに資する取組を支援し、業界全体による自発的な省エネの取組を促すことを目的とした「SAVE THE ENERGY PROJECT」を2016年度に実施しました。
(2)低炭素型の地域づくりの推進
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)に基づき、都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとされ、特に都道府県、政令指定都市及び中核市(施行時特例市以上)は、区域における再生可能エネルギーの利用促進、省エネルギーの推進等を盛り込んだ地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定が義務付けられています。
2016年5月、地球温暖化対策計画が閣議決定されたことに伴い、政府においては、これにかかる説明会の開催や計画策定マニュアルの改定を行いました。また、2015年に引き続き、先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業(グリーンプラン・パートナーシップ事業)により、更なる計画策定の推進と計画に位置付けられた事業の実施支援による計画の内容充実を図ることとしました。
さらに、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与するため、都市機能の集約や、それと連携した公共交通の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じる「都市の低炭素化の促進に関する法律」が2012年12月に施行され、同法に基づく市町村による低炭素まちづくり計画の作成や各種の事業、取組に対して、財政措置等を通じ、低炭素まちづくりの実現に向けた総合的な支援を行いました。
(3)地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例(地球温暖化対策のための税)
我が国で排出される温室効果ガスの約9割は、エネルギー利用に由来する二酸化炭素(エネルギー起源CO2)となっており、今後温室効果ガスを抜本的に削減するためには、中長期的にエネルギー起源CO2の排出抑制対策を強化していくことが不可欠です。
このため、2012年10月から施行されている地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例の税収を活用して、省エネ対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起源CO2排出抑制の諸施策を着実に実施していきます。
- 注1
- トップランナー制度の対象機器のうち、家庭で使用される機器を中心とした19機器(エアコンディショナー、蛍光ランプを主光源とする照明器具等)について、トップランナー制度に基づく省エネ基準の達成率等を表示し、基準を達成している機器であることを消費者に分かりやすく表示するためのJISに基づくラベルです。2017年3月現在、特定エネルギー消費機器28機器のうちテレビジョン受信機、エアコンディショナー等を始めとする21機器が対象となっています。
- 注2
- トップランナー制度の対象機器のうち、家庭で使用される機器でエネルギー消費が大きい6機器(エアコンディショナー、蛍光灯器具、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座)について、省エネルギーラベルや、市場における製品の省エネ性能を5つ星から1つ星で表示した多段階評価、年間の目安電気料金等を表示したラベルです。1995年10月に通商産業省(当時)と米国環境保護庁との間で交わされた合意文書に基づき実施される、省エネ型OA機器(コンピュータ、プリンタ、ファクシミリ等)に関する表示制度です。