第1節 資源供給国との関係強化と上流進出の促進
1.石油・天然ガスの安定的かつ低廉な確保に向けた取組
従来から、石油・天然ガスのほぼ全量を海外からの輸入に頼っている我が国にとって、石油・天然ガスの安定的かつ低廉な確保は重要な課題です。さらに、東日本大震災以降、化石燃料である石油・天然ガスの需要は依然として高い水準で推移しており、引き続き重要な資源といえます。また、我が国は原油輸入の約9割、天然ガス輸入の約2割を中東に依存していることから、安定的な確保に向けて、チョークポイントであるホルムズ海峡を通らない輸入先の確保など、供給源の多角化を進めるとともに、中東産油国をはじめとする資源供給国との関係深化が極めて重要です。
<供給源の多角化に向けた取組>
供給源の多角化を進めるにあたって、ロシアは我が国と地理的にも近接し、豊富な石油・天然ガスの埋蔵量を有する、世界でも有数の産油・産ガス国であり、極めて重要な国です。我が国はすでにロシアから石油・天然ガスを輸入しているものの、日本の総輸入量に占める割合はそれぞれ約9%に留まっており、我が国にとって今後大きなポテンシャルを秘めた国であるといえます。2016年5月にロシア・ソチで行われた日露首脳会談において、安倍総理からプーチン大統領に提案した8項目の「協力プラン」の中には、「石油・ガス等のエネルギー開発協力、生産能力の拡充」が盛り込まれ、以降この具体化に向けた首脳・閣僚級の協議が続いていましたが、同年12月に山口及び東京で行われた日露首脳会談に合わせ、8項目の「協力プラン」のそれぞれの項目のもとで企業等が行うプロジェクトに関する文書に署名が行われました。全部で82ある成果文書のうち、政府・当局間のものも含め、石油・天然ガス開発に係る文書も計13件署名されており、今後これらのプロジェクトの実現が進むことで、ロシアからの安定的かつ低廉な石油・天然ガス供給の増加が期待されます。
また、近年シェールオイル・ガスの生産を拡大させている米国からは、2014年に我が国企業が関与する全ての液化天然ガス(LNG)プロジェクトについて米国政府から輸出承認を獲得するとともに、2015年には約40年ぶりに米国からの原油輸出が解禁になりました。これらを受けて、2016年5月にはシェールオイル由来の原油が初めて日本に輸入され、また、2017年1月にはシェールガス由来のLNGが初めて日本に輸入されました。今後米国からの石油・天然ガスの輸入が拡大することで、供給源の多角化によるエネルギーの安定供給に資するだけでなく、仕向地が自由な米国産LNGの調達により、柔軟かつ透明性の高い国際LNG市場の構築にも寄与することが期待されます。
<中東産油国等資源供給国における取組>
我が国の原油の輸入量の中東への依存度は依然として高いため、引き続き中東産油国との関係深化が必要不可欠です。また、アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ首長国にある海上油田は、世界有数の埋蔵量と生産量を誇る巨大油田群であり、我が国企業も石油権益を保有しています。同油田には、我が国の自主開発原油の約4割が集中していますが、その6割以上が2018年3月に権益期限を迎えるため、権益延長に向けた取組を早急に進める必要があります。
そのため、2016年5月、11月に、高木経済産業副大臣がUAEを訪問し、ハーミド・アブダビ皇太子府長官やジャーベルUAE国務大臣(新エネルギー・環境関連担当)兼アブダビ国営石油会社(ADNOC)CEOなどの王族・政府要人との会談において、我が国企業が保有する石油権益の延長について働きかけを行いました。
また、2017年1月、世耕経済産業大臣がワールド・フューチャー・エナジー・サミット(WFES)出席のためアブダビ首長国を訪問する機会を捉え、さらなる働きかけを行った結果、国際石油開発帝石(INPEX)が保有するサター油田及びウムアダルク油田(合計生産量:日量約3.5万バレル)の権益期限の延長について、ADNOCとの間での基本合意に成功しました。(権益比率40%、25年間)。この基本合意は、我が国の自主開発比率の向上に資するとともに、これまでの我が国とアブダビ首長国との良好な協力関係をさらに発展させるものであり、これまでの日アブダビ間の幅広い関係が評価されたものと言えます。また、さらに大きな生産量・埋蔵量を有し、2018年3月に権益期限を迎える他のアブダビ海上油田についても、引き続き、権益延長に向けた不断の取組を継続していきます。
また、我が国にとって第3位のLNG輸入相手国であるカタールとは、エネルギー分野を含む両国間の経済関係の強化を目的として、2006年に「日カタール合同経済委員会」を設置しており、2016年11月にその第10回会合が東京で開催されました。我が国からは世耕経済産業大臣、薗浦外務副大臣が出席し、アル・サダ・エネルギー工業大臣に対し、我が国企業が参画するカタールでの石油・天然ガス開発事業について、引き続き支援を依頼するとともに、柔軟かつ流動的なLNG市場の実現に向けた、仕向地条項の緩和や第三国での両国間での協力の重要性について議論を行いました。
さらに、我が国のLNG輸入量の2割以上を占め、最大の輸入相手国であるオーストラリアには、2016年8月、高木経済産業副大臣が出張し、イクシスLNGプロジェクトを視察しました。同プロジェクトは、日本企業(INPEX)が主導・操業する初の大型LNGプロジェクトであり、2017年度の生産開始に向けて開発が進められています。我が国としても、JOGMECをはじめ国際協力銀行(JBIC)や日本貿易保険(NEXI)による支援を行っています。生産が開始されれば、我が国の天然ガス需要の約7%に相当する年間約570万トンが日本向けに輸出される予定であり、我が国のエネルギーの低廉かつ安定的な供給に資するものとして、政府としても引き続き支援していきます。
2.石炭の安定供給確保に向けた取組
石炭は、石油や天然ガスと比べて供給安定性や経済性の面で優れるエネルギー資源ですが、2016年度の後半は、石炭市況で急激な上昇がありました。日本にとっては、安価で安定的な石炭供給は引き続き極めて重要な課題です。
鉄鋼用原料炭は、我が国石炭ユーザーはオーストラリアからの輸入を中心に安定的に調達していますが、オーストラリアへの依存度は7割近くあります。オーストラリアは、高品位炭の埋蔵量、輸送距離、インフラ整備の状況や政策の動向など、いずれの要素を見ても引き続き我が国にとって最も安定した供給国として位置付けられます。しかし、同国における環境問題への国民意識の高まりや高コスト炭鉱の操業停止が増加するなどの動きには注視が必要です。こうした点を踏まえ、オーストラリアからの安定的な供給確保を基本としつつも、供給源の多角化の観点からインドネシアやロシア、米国等からの供給確保を様々な面から支援していく必要があります。
我が国は、JOGMECによる地質構造調査や産炭国における人材育成等の支援措置を通じて我が国企業の探鉱活動の支援を実施しています。また、我が国の石炭ユーザーが必要とする多様な品種を中長期にわたり、安定的に確保していくためには、オーストラリアやインドネシアを始めとする産炭国との継続的な関係の構築が重要であり、資源外交や政策対話等の取組を積極的に実施しています。
<豪州以外の産炭国との関係維持・強化の取組事例>
2016年6月、総理官邸において、安倍総理大臣とモンゴル国エンフボルド国家大会議議長の立ち会いのもと、北村経済産業大臣政務官は、ジグジッド鉱業相と、「日本国経済産業省とモンゴル国鉱業省の間のクリーン・コール技術に関する協力覚書」の署名を行いました。これにより、経済産業省とモンゴル鉱業省は、クリーン・コール技術に関する交流の深化等の目標を達成するため努力していくことを確認しました。
ロシアについては、2016年12月、プーチン大統領訪日時に「エリガ石炭コンプレクス発展分野における協力に関する日本国経済産業省とロシア連邦エネルギー省との間の協力覚書」を世耕経済産業大臣とノバク・エネルギー大臣間で署名しました。ロシアエリガ炭田について、ロシアから日本へ同炭田の情報を提供し、日本側は同炭田から産出される石炭引取等に関して企業間の協力を促進します。
3.レアメタル等の鉱物資源の確保に向けた取組
鉱物資源については、その供給のほぼ全てを海外に頼っている一方、省エネルギー・再生可能エネルギー機器等に必要不可欠な原材料です。そのため、中長期的に我が国企業による投資を促進し、鉱物資源の供給源の多角化・安定供給確保につなげるため、我が国にとって重要かつ安定的な鉱物資源供給国や、鉱物資源のポテンシャルは大きいもののインフラや鉱業政策面など鉱業投資環境に課題を有する地域との継続的な関係構築に取り組んでいます。
我が国にとって重要かつ安定的な鉱山資源供給国の一つであるチリについては、2014年7月の安倍総理訪問時、プロジェクトにおけるトラブル発生時においても迅速に対応できる体制の構築等を目的として、両国政府は日チリ間の鉱業分野における関係強化のための覚書に署名しました。その後、同年10月には当該覚書のフォローアップ、更に2016年4月にはチリ鉱業省と共催で日智鉱業官民合同会議を実施し、協力強化に向けた具体的な取組内容について合意しました。
また、ペルーについては、2016年11月、APEC首脳会合・閣僚会合の開催に伴う安倍総理のペルー共和国訪問に合わせて、世耕経済産業大臣はエネルギー鉱山省タマヨ大臣と、鉱業分野に関する覚書を、両国首脳会談の場で締結しました。本覚書に基づく包括的な枠組みを通じて、日本企業の投資促進と現地での操業環境を改善し、加えてペルー共和国の経済発展に寄与することで、Win-Winな関係を構築することとしました。
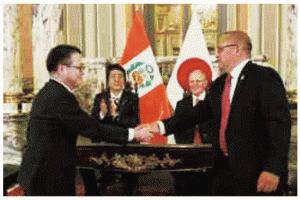
日ペルー首脳会談での署名式の様子(2016年11月)
- 出典:
- 内閣広報室
アフリカ地域との継続的な関係構築については、2013年5月に開催された「日アフリカ資源大臣会合」において、茂木経済産業大臣は「日アフリカ資源開発促進イニシアティブ」を公表し、参加国からの賛同を得て、同年6月に開催された第5回アフリカ開発会議(TICAD V)の成果である「横浜行動計画」に盛り込まれました。当該イニシアティブの中には、資源探鉱や開発プロジェクトに対するリスクマネー供給支援(今後5年間でJOGMECを通じて20 億ドル)や、資源分野での人材育成(今後5年間で1,000名)が盛り込まれました。また、2015年5月に開催された「第 2 回日アフリカ資源大臣会合」においては、当該イニシアティブの進捗状況が確認され、アフリカの資源開発促進に関する議論が行われました。また、宮沢経済産業大臣から、日本とアフリカとの関係をさらに発展させるため、TICADを活用した首脳レベルでの関係を軸に、二国間の関係強化を内容とする「日アフリカ資源大臣パートナーシップ」という新たな枠組みにステップアップすることを提案し、各国の同意を得、共同議長総括が採択されました。そして、2016年8月にケニアで開催されたTICAD Ⅵでは、前回からのフォローアップを踏まえ、エネルギー・資源開発を含むインフラ案件のリスクマネー供給の拡大や、次回までの3年間で更に1,000名の資源分野の人材育成を目標とした新たな取組の実施を表明しました。
また、南アフリカ共和国で毎年2月に開催される世界最大級の鉱業投資会議「マイニング・インダバ」について、2015年2月には山際経済産業副大臣が、2016年2月には北村経済産業大臣政務官が、そして、2017年2月には井原経済産業大臣政務官が参加し、アフリカ各国閣僚とのバイ会談を行い、協力関係の強化を図りました。
アフリカ諸国との二国間関係の取組について、南アフリカ共和国については、2016年10月に東京で開催された鉱業分野における「南アフリカ共和国投資促進セミナー」(経済産業省・JOGMEC共催)の機会を利用し、井原経済産業大臣政務官はズワネ鉱物資源大臣とバイ会談を行い、鉱物資源の安定供給、二国間関係の強化等について意見交換を行いました。そして、前述の2017年2月の「マイニング・インダバ」の開催に合わせて、再び井原政務官はズワネ大臣とのバイ会談を行い、その場で、鉱業分野における両国間の協力関係の強化を図るための覚書に署名しました。
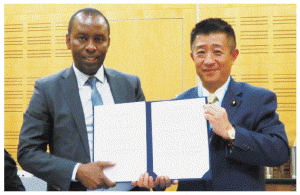
左:ズワネ鉱物資源大臣(南アフリカ共和国)との覚書交換式(2017年2月)
- 出典:
- 経済産業省
また、マダガスカルについては、2017年2月に井原経済産業大臣政務官が同国を訪問し、ラジャオナリマンピアニナ大統領及びラクトゥアリマナナ財政予算大臣と会談し、我が国へのニッケルの輸入や日本企業等が出資するプロジェクトに悪影響を与えないように働きかけ等を行いました。
以上のように、鉱物資源供給国と我が国との継続的な関係を構築することで、中長期的な鉱物資源の安定供給につながる機会の拡大を目指していきます。
4.資源権益獲得に向けたリスクマネー供給
我が国は、2010年のエネルギー基本計画において、原油・天然ガス及び石炭の自主開発比率(注1)をそれぞれ2030年に40%以上、60%以上、また、銅などの金属鉱物の自給率(注2)を2030年に80%以上に引き上げる目標を掲げ、取組を進めています。
2015年度の石油・天然ガス自主開発比率は約27.2%と統計開始から最も高い値となり、石炭自主開発比率は目標を維持しています。銅の自給率は、2010年度の54%から2015年度の56%へと向上しています。
一方で、資源権益の獲得に向けては、探鉱リスクやカントリーリスク等、事業リスクが非常に高く、また、巨額の資金を要しますが、我が国企業は、資源メジャーと呼ばれる海外企業等と比べると大幅に資金力が弱い状況にあります。特に近年の原油価格下落により資源開発企業の財務状況が悪化し、資源開発投資の抑制が進んでいます。このような動きは将来的なエネルギー需給のひっ迫につながるリスクがあります。一方で、近年の資源価格低迷は資源国からの優良な権益を獲得する良い機会にもなり得ると考えられます。このような状況の下、我が国企業による資源権益の獲得を推進するためには、資源外交の推進による相手国との関係強化とともに、資金面での支援がより一層必要となります。そのため、リスクマネー供給機能の強化の一環として、2016年にJOGMEC法を改正(同年11月施行)するとともに、JOGMECの出資及び債務保証支援対象事業の採択等に係る基本方針を策定しました。
<具体的な主要施策>
(1)石油・天然ガスに係る探鉱出資・資産買収等出資
【2016年度当初:560.0億円、補正:124.0億円、2016年度産投:360.0億円、産投補正:1,500.0億円】
JOGMECにおいては、我が国資源開発会社等による石油・天然ガスの探鉱・開発や油ガス田の買収等を資金面で支援するため出資を行っています。さらにJOGMEC法が改正され、企業買収などの支援メニューが拡充されたことを踏まえ、補正予算による措置を行いました。
(2)石炭及び金属鉱物に係る探鉱出資・債務保証等
【2016年度産投:135.0億円】
JOGMECにおいては、我が国法人の海外における鉱物資源の探鉱プロジェクト等を資金面で支援するため出資及び債務保証等を行っています。2016年度は我が国企業が参画する米国における亜鉛・銅探鉱プロジェクト等に対し出資等を行いました。
(3)政府系金融機関による資源金融
(国際協力銀行(JBIC))【金融】
我が国企業による長期取引契約に基づく資源輸入や、自ら権利を取得して資源開発を行う場合、さらには資源開発に携わる我が国企業の競争力が強化される場合または資源確保と不可分一体となったインフラ整備等、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進する場合に、国際協力銀行は輸入金融や投資金融による支援を行いました。
(4)貿易保険によるリスクテイク
(日本貿易保険(NEXI))【金融】
海外における重要な鉱物資源またはエネルギー資源の安定供給に資する案件に関し、海外エスクロー口座への資源引取り代金入金を条件に、NEXIは通常よりも低い保険料率で幅広いリスクをカバーする資源エネルギー総合保険等を通じて、我が国の事業者が行う権益取得・引取等のための投融資に対し支援を行いました。
また、2016年5月には、G7サミット伊勢志摩サミット「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」において、世界全体のインフラ・資源案件に対して「今後5年間の目標として、約2,000億ドルの資金等を供給」し、「関係機関について十分な財務基盤を確保」するとされたことを踏まえ、NEXIに650億円の出資を行うとともに、更なる制度拡充策として、投資保険及び輸出保険のカントリーリスクを100%カバーする等の措置を発表しました。これらの措置を通じ、引き続き日本企業が参画する海外での資源開発等のプロジェクトに対する資金調達を円滑化し、我が国企業の活動も支援していきます。
(5)海外投資等損失準備金制度【税制】
海外で行う資源(石油・天然ガス等)の探鉱・開発事業に対する投資等について、事業失敗による損失等に備えるために、投資等を行った内国法人に一定割合の準備金の積立を認め、これを損金に算入することを認める制度であり、平成28年度税制改正において、適用期限が2018年3月31日まで延長されました。
(6) 探鉱準備金・海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費・海外新鉱床探鉱費の特別控除制度(減耗控除制度、海外減耗控除)【税制】
鉱業を営んでいる者が、鉱業所得等を探鉱費に充てるための準備金として積み立てた時に損金算入できる制度、及びその準備金を取り崩して実際に新鉱床探鉱費に充てた場合等には特別控除できる制度であり、平成28年度税制改正において、鉱業の実態を踏まえ制度を見直した上、準備金積立ての適用期限が2019年3月31日まで延長されました。
(7)海外地質構造調査等事業
【2016年度当初:20.5億円】
世界においても探鉱実績が少なく、事業リスク等が高い海外のフロンティア地域等において、JOGMECが地質構造の調査を行うことにより、我が国企業の進出を促進しています。2016年度は、前年度に引き続きケニア、セーシェル及びウズベキスタンにおいて地質構造調査を実施しました。
(8)産油・産ガス国開発支援等事業
【2016年度当初:40.0億円】
資源国との戦略的かつ重層的な関係を構築するため、資源国のニーズに対応して、人材育成・交流、先端医療、環境対策技術など、幅広い分野での協力事業を日本企業等の強みを活かしつつ実施するとともに、資源国に対する日本からの投資促進等について支援を行いました。2016年度は、UAEのアブダビ首長国における我が国先端医療技術の導入支援、日アブダビ教育・交流センター運営等の留学促進事業等のプロジェクトを実施しました。
(9)海外炭開発支援事業
【2016年度当初:12.0億円】
我が国企業の権益獲得を支援し、自主開発比率の向上を図るため、海外の産炭国において、我が国企業が行う探鉱活動等への支援や炭鉱開発に不可欠なインフラ調査等を実施しました。
(10)産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業等
【 2016年度当初:14.1億円】
我が国の優れた炭鉱技術を、採掘条件の悪化が予想される海外産炭国へ移転するため、海外研修生の受入研修事業、我が国炭鉱技術者の海外炭鉱派遣研修事業等を実施しました。
(11) エネルギー使用合理化希少金属資源開発推進基盤整備委託費【2016年度当初:22.3億円】
最新の鉱床地質学の成果等を活用し、省エネ機器、再生可能エネルギー関連設備の製造に必要不可欠な銅、白金族等の鉱物資源の基礎的な資源探査等を実施しました。
(12)希少金属資源開発推進基盤整備事業
【 2016年度当初:4.0億円】
グリーン部素材(素材の高付加価値化)、次世代自動車の生産に必要不可欠なレアメタル等の鉱物資源の探査等を委託し、安定供給を図りました。
(13)大型船の受け入れ機能の確保・強化
国土交通省では、2016年度、資源・エネルギー等の海上輸送網の拠点となる埠頭の荷さばき施設等の整備を行うなど、資源・エネルギー等の安定的かつ効率的な海上輸送網の形成に向けた取組を推進しました。
(14)JICAの機能強化【制度】
2016年5月には、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」において、抜本的な制度拡充策として、円借款の更なる迅速化、民間企業の投融資奨励など円借款や海外投融資の制度改善を行うことを発表しました。具体的には、円借款については、コンサルタントが行う調査の迅速化を図り、事業実施可能性調査(F/S)開始から着工までの期間を最短1年半に短縮することを決定しました。また、JICA海外投融資の出資比率規制の柔軟な運用・見直しとして、JICA海外投融資の現地企業等への直接出資において、金額規模につき、個別案件の政策的重要性、リスク等を勘案しつつ、必要に応じて柔軟に対応することとしました。また、出資比率を25%から50%(最大株主にならない範囲)まで拡大する等出資比率上限規制の柔軟化、政策上特に重要な案件については、これを上回る出資比率を認める等の対応を検討することとしました。さらに、被援助国のニーズに応じてユーロ建て海外投融資を検討することとしました。