第1節 エネルギー関係技術ロードマップの策定
2014年4月に閣議決定された第4次エネルギー基本計画では、①我が国エネルギー需給構造の脆弱性の解決には、革命的なエネルギー関係技術の開発と社会全体における導入のため、長期的研究開発と制度変革を伴う取組が必要、②エネルギー需給に影響を及ぼす課題は、日々の省エネルギー化や安全性改善等、様々なレベルで存在しており、短期・中期それぞれの観点から、エネルギー需給を安定させ、安全性や効率性を改善していく不断の取組が重要であるとしています。この基本的方向性を踏まえ、短期・中期・長期それぞれの観点から技術課題を俯瞰するとともに、③どのような課題の克服が目標とされる取組なのか、④開発を実現する時間軸と社会実装化のための方策といった観点を踏まえて、2014年12月にエネルギー関係技術ロードマップ(以下「ロードマップ」という。)を策定しました。
当該ロードマップでは、これまで政府で策定されてきた「環境エネルギー技術革新計画(2013年9月総合科学技術会議決定)」等で整理された技術開発プロジェクトを中心に、以上の4つの観点から各技術を俯瞰的に整理することにより、高い安全性を誇るエネルギー供給体制の確立と、エネルギー需給構造の安定化・効率化・低環境負荷化の実現に、具体的に貢献するエネルギー関係の技術開発政策に関する指針を提示しました。
ロードマップ第1章では、我が国におけるエネルギー技術開発に関するこれまでの取組を歴史的な視点から整理することで、我が国の技術的蓄積(土台)とその発展可能性を明らかにしつつ、現在の技術開発政策を時間軸の中に位置付けています。
第2章では、海外のエネルギー関係技術開発戦略について、そうした戦略を必要とするそれぞれの国のエネルギー事情も踏まえて調査・分析することで、我が国との相違点や適用可能性も視野に入れつつ、我が国の技術開発政策を空間軸に位置付けています。
第3章では、技術開発プロジェクトの必要性と社会への実装化に向けた課題をあわせて整理した、各技術課題のロードマップを提示しています。36の主要技術課題(注)を取り上げ、ロードマップの作成に当たっては、それぞれの技術課題の開発の必要性を明確にすること、技術の社会実装化に向けた課題を明確にすること、どのような条件下で目標達成が可能となるのかといった現実的なロードマップとすること、個別の技術要素間の関連性を意識した細分化されたロードマップとすること、これらの諸点を明確に意識して整理を行うことで、より現実的かつ将来のエネルギー関連技術の社会への影響を理解しやすい形で示すように工夫しています。
今般のロードマップは、この3部構成により、我が国の現在の技術開発政策の位置付けを、時間軸、空間軸の両面から明らかにするとともに、単に技術を開発するのではなく、社会への実装化のための具体的な論点を提示しています。
【第391-1-1】エネルギー関係技術ロードマップ策定の考え方
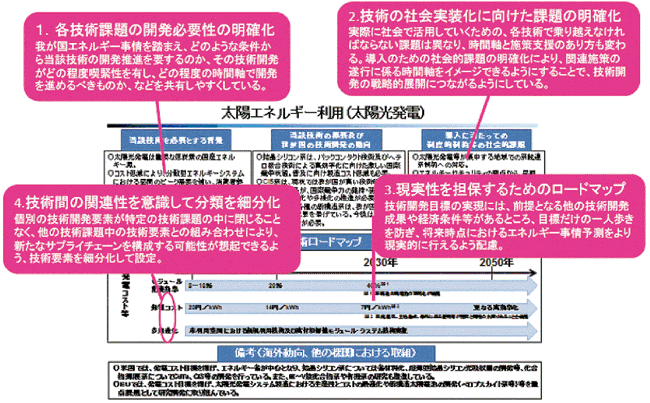
- (注)
- エネルギー関係技術ロードマップで取り上げた技術課題
1.太陽エネルギー利用(太陽光発電)、2.風力発電、3.地熱発電、4.バイオマス利活用、5.海洋エネルギー利用、6.人工光合成、7.宇宙太陽光発電システム、8.原子力発電、9.高効率石炭火力発電、10.高効率天然ガス火力発電、11.二酸化炭素回収・貯留、12.コージェネレーションシステム、13.再生可能エネルギー熱利用、14.制限開発技術、15.メタンハイドレート、16.海底熱水鉱床、17.超伝導送電、18.高性能電力貯蔵、19.蓄熱・断熱等技術、20.エネルギーマネジメントシステム、21.革新的デバイス、22.高効率エネルギー産業利用、23.環境調和型製鉄プロセス、24.革新的石油精製プロセス、25.革新的セメント製造プロセス、26.革新的デバイス(情報家電・ディスプレイ)、27.省エネ住宅・ビル、28.高効率ヒートポンプ、29.次世代自動車(HV,PHV,EV,クリーンディーゼル車等)、30.次世代自動車(燃料電機電池自動車)、31.低燃費航空機、32.高度道路交通システム、33.革新的構造材料、34.水素製造、35.水素輸送・貯蔵、36.水素利用