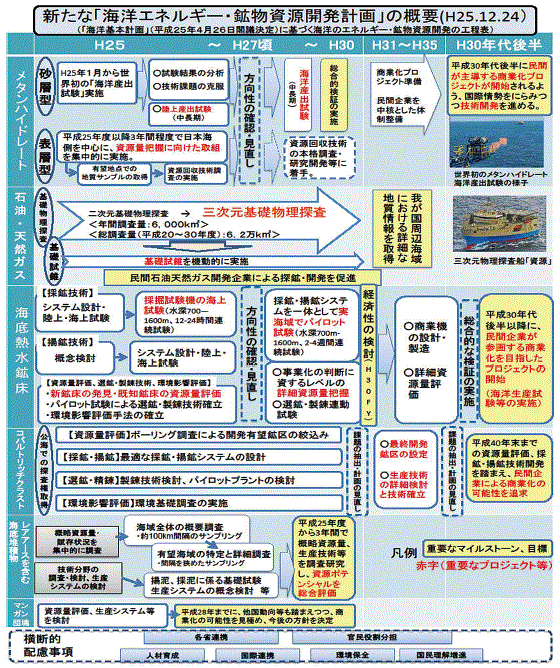第4節 メタンハイドレート等国産資源の開発の促進
我が国近海のエネルギー・鉱物資源は、国内資源に乏しい我が国にとって新たな供給源となり得る極めて重要な存在です。そのため、「海洋基本法」(2007年7月施行)及び「海洋基本計画」(2008年3月)に基づき策定した「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」(2009年3月)に従い、その開発を計画的に進めてきました。同開発計画は、2013年4月に策定された新たな「海洋基本計画」や、最近のエネルギー・鉱物資源を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、2013年12月には新たな「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」として策定されました。同計画において、鉱種毎に、新たな開発の目標と達成に至る筋道、必要となる技術開発を記すとともに、各省庁間の連携、国と民間の役割分担、さらには、横断的配慮事項として、人材育成、国際連携、海洋の環境保全、国民の理解促進に留意し、適切に進めることとしています。同開発計画における各資源に係る工程表については、進捗に応じて、方向性の確認・見直しを行う予定です。
メタンハイドレートに関して、主に太平洋側に確認されている砂層型メタンハイドレートについては、2013年3月に、海域において世界初となるガス生産実験を実施したところです。引き続き、長期間・安定的なガス生産に必要な技術開発や、生産コストの引下げなどが重要な課題であり、こうした課題に集中的に対応しつつ、2018年度を目途に商業化の実現に向けた技術の整備を行う予定です。また、2023年から2027年の間に、民間企業が主導する商業化プロジェクトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、技術開発を実施します。主に日本海側に確認されている表層型メタンハイドレートについては、まず資源量把握が課題であり、2013年度から本格的な資源量調査を実施しています。2014年度の調査では、隠岐周辺、上越沖、秋田・山形沖及び日高沖の調査海域において、表層型メタンハイドレートの存在の可能性がある構造(ガスチムニー構造)が、746か所存在することが新たに確認されました。また、上越沖、秋田・山形沖の調査海域において3か所を選び実施した地質サンプル取得調査では、表層型メタンハイドレートを含む地質サンプルを取得しました。その結果、いずれの箇所においても、海底面から50m程度の深さまではメタンハイドレートが厚さ数10cmから1m程度で、それより深いところでは厚さ1cm未満や直径1cm未満で存在していることがわかりました。2015年度においては、これまでの調査結果を踏まえ、より多くの地点において地質サンプル取得調査を実施するとともに、広域調査等も引き続き実施します。
石油・天然ガスについては、我が国周辺海域の資源ポテンシャルを把握するため、三次元物理探査船「資源」を活用した基礎物理探査を毎年6,000km2実施し、2018年度までに概ね62,000km2の三次元基礎物理探査を実施します。その結果を踏まえ、有望海域を選定の上、基礎試錐を機動的に実施していきます。これらにより得られた地質データ等の成果については民間企業に引き継ぎ、探鉱活動の促進を図ります。2014年度は、我が国周辺海域において引き続き三次元物理探査船「資源」による基礎物理探査を着実に実施するとともに、有望海域における基礎試錐(試掘調査)の実施に向けた準備作業を行いました。
海底熱水鉱床については、2014年12月、沖縄本島北西沖に、2015年1月には沖縄久米島西に新たな海底熱水鉱床を確認したことを発表しました。同鉱床は、これまで発見されているなかで最も規模の大きい熱水鉱床である伊是名海穴Hakureiサイトにマウンド分布域の広がり等で匹敵するものと期待され、今後の詳細調査により資源量が把握される予定です。今後とも、国際情勢をにらみつつ、平成30年代後半(2023年頃)以降に民間企業が参画する商業化を目指したプロジェクトが開始されるよう、既知鉱床の資源量評価、新鉱床の発見と概略資源量の把握、実海域実験を含めた採鉱・揚鉱に係る技術開発、環境影響評価手法の確立等を推進するとともに、その成果が着実に民間企業による商業化に資するよう、官民連携の下、推進します。
コバルトリッチクラストについては、2013年7月、JOGMECを通じて国際海底機構から南鳥島沖公海域におけるコバルトリッチクラストの探査鉱区の承認を得るとともに、2014年1月、JOGMECと国際海底機構(ISA)との間で探査契約が締結されました。
今後、国際海底機構との探査契約に基づき、2014年から南鳥島沖鉱区の資源量評価や生産技術の確立等に取り組み、2028年までに民間企業による商業化の可能性を追求します。
レアアースを含む海底堆積物については、2013年度から3年間程度で南鳥島周辺の排他的経済水域内において、分布状況の調査等を実施し、将来の資源としてのポテンシャルを総合的に評価します。マンガン団塊については、国際海底機構と契約しているハワイ沖の探査鉱区について、引き続き、資源量の評価等を行い、他国の動向等も踏まえながら、商業化の可能性を見極めます。
<具体的な主要施策>
1. 国内石油天然ガス基礎調査【2014年度当初:145.0億円】
2014年度は、約6,300km2の三次元物理探査データを取得しました。物理探査を実施するとともに、得られたデータを処理・解析し、順次その調査結果を我が国資源開発企業に提供することにより、企業による国内石油天然ガスの探鉱・開発活動を促進しました。また、2014年度は、有望海域における基礎試錐(試掘調査)の実施に向けた準備作業を行いました。
2. メタンハイドレート開発促進事業【2014年度当初:127.3億円、2014年度補正20.0億円】
日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートを将来のエネルギー資源として利用可能にすることを目的として、世界に先駆けて商業的産出のために必要な技術整備を行ってきました。2014年度は、砂層型メタンハイドレートについては、2013年3月に実施した世界初となる洋上でのガス生産実験の結果解析作業を引き続き実施するとともに、次回の海洋産出試験に向けた基本設計作業等を実施しました。表層型メタンハイドレートについては、資源量を把握するため、日本海側を中心とした海域において、音波探査、地質サンプル取得調査等による広域的な分布調査等を実施しました。
3. 深海底資源基礎調査事業【2014年度当初:45.0億円】
我が国周辺海域のコバルトリッチクラストやレアアース堆積物など深海底鉱物資源のポテンシャル評価のため、海洋資源調査船「白嶺(はくれい)」による調査を行うとともに、関連技術の基礎調査を実施しました。
4. 海底熱水鉱床採鉱技術開発等調査事業【2014年度当初:13.1億円、2014年度補正:8.0億円】
海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レアアース堆積物等の開発に必要な共通要素技術(採掘・揚鉱・選鉱・製錬)のうち、重要な要素技術である採鉱分野について、水中破砕機の設計・製造・試験を実施しました。
【第314-1-1】 新たな「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の概要