第1節 エネルギーコストの状況
1.燃料価格の状況
米国におけるシェール革命、中東地域における政治・社会構造の不安定化、中国・インドなど新興国におけるエネルギー需要の増加、ウクライナ問題をきっかけとした欧露関係や中露関係の変化など、世界のエネルギー需給構造を巡って、ダイナミックな変化が起きています。一方、我が国に目を転じると、東日本大震災以降、原子力発電所が停止し、海外からの化石燃料への依存が増大し、国際的な燃料価格の動向に大きな影響を受けやすい構造となっています。旺盛な世界需要や国際情勢の変化を背景に2014年夏にかけて化石燃料価格が高騰しました。その中で、石炭価格は相対的に安定していたものの、原油・LNG(液化天然ガス)の価格高騰が顕著となりました。
【第131-1-1】国際原油価格の動向
《中期の原油価格の動向》
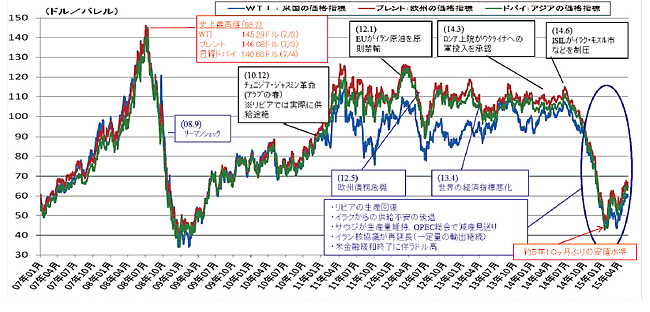
《2015年5月までの直近1年の原油価格の動向》
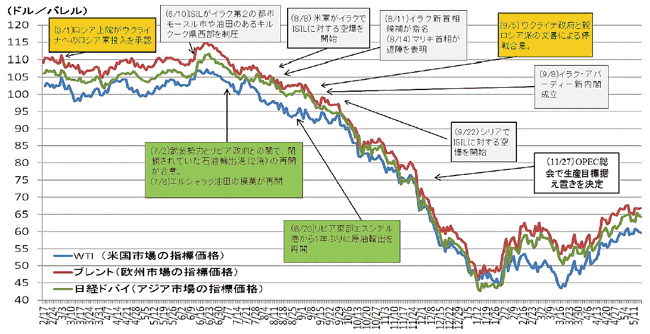
- (出典)
- 「ICE」(英ICE futures)、「CME」(シカゴ・マーカンタイル取引所)等のデータを基に作成
(1)石油
①国際原油価格の状況
国際原油価格は、新興国の需要急増などを背景に2008年7月に史上最高値(WTI:145.29ドル/バレル)を記録した後、同年9月の世界金融危機により急落しました。その後、世界経済の回復に伴い上昇し、いわゆる「アラブの春」(2010年12月)前まで70ドル/バレルから80ドル/バレルで推移してきました。
2011年から2014年6月にかけて、緊迫する中東情勢等を背景に、原油価格は高水準で推移してきましたが、同年7月以降は、中国やヨーロッパの景気の減速、供給面では北米のシェールオイルの堅調な生産、同年11月のOPEC総会での生産目標維持等により、2015年1月には原油価格は約5年10か月ぶりの安値水準まで下落しました。その後も、シェールオイル増産傾向を背景とした在庫積み上がりなどを受け、55ドルから60ドル前後で推移していましたが、直近では、EIAによる米国シェールオイル増産ペースの減速の見直し等を受け上昇傾向にあります。
②我が国の原油輸入の状況
日本に到着する原油価格(CIF価格)は、世界的な原油価格の急落と円高方向への為替の動きによって、2008年9月以降下落し、2009年1月に1リットル当たり20円台の水準にまで低下しました。しかし、その後は総じて上昇傾向にあり、2014年には1リットル当たり70円台の水準にまで上昇しました。2014年秋以降は、国際原油価格の急落を受け下落に転じ、足下2015年3月は40円台で推移しています。
【第131-1-2】 我が国の原油輸入価格(1リットル当たり)の推移
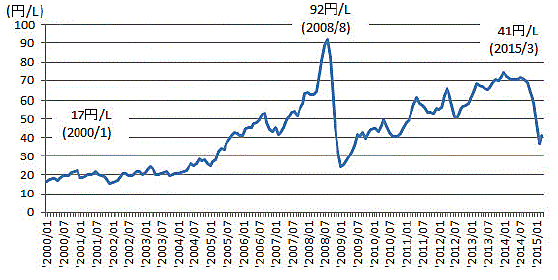
- (出典)
- 財務省「貿易統計」を基に作成
【第131-1-3】 我が国の原油輸入量の推移
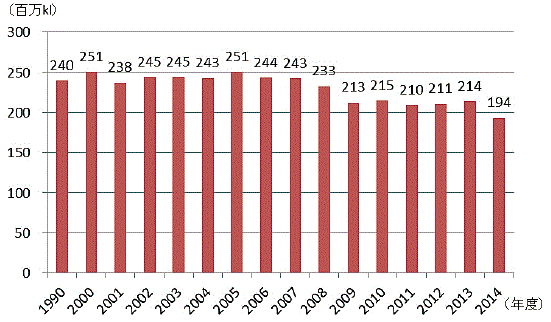
- (出典)
- 財務省「貿易統計」を基に作成
【第131-1-4】レギュラーガソリン価格、軽油価格、灯油価格の動向
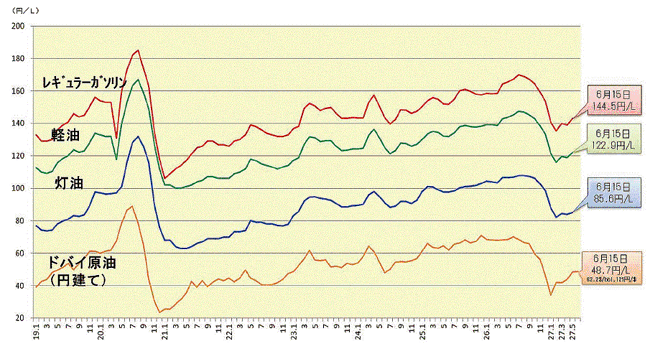
- (出典)
- レギュラーガソリン、軽油、灯油(店頭):「石油製品価格モニタリング調査」 ドバイ原油:日本経済新聞社調べ等
我が国の原油輸入量について、東日本大震災前と現在とを比較すると、2010年度の約2億1,500万klから2014年度には約2億klへと減少しましたが、この間の原油価格の高騰を背景に、輸入額は約9兆4,059億円から約13兆8,734億円へと上昇しました。
③国内の石油製品価格
2014年度の国内の石油製品価格は、7月中旬までは原油価格の上昇の影響等を受けて上昇し、レギュラーガソリンは7月に全国平均小売価格で一時169.9円/Lとなるなど、レギュラーガソリン、軽油、灯油の価格はいずれも7月にピークとなりました。このピーク時の全国平均価格を2012年7月と比較すると、この2年間でいずれの油種も約2割上昇しました。その後、原油価格の下落を背景に石油製品価格も2015年2月まで下落し、レギュラーガソリンの全国平均小売価格(1リットル当たり)は2010年12月以来の133円台となりました。2015年2月以降の石油製品価格は、小幅な上昇と下落を繰り返し、5月末のレギュラーガソリンの全国平均小売価格(1リットル当たり)は142円台となっています。
(2)天然ガス
①国際天然ガス価格の状況
天然ガス価格の決定方法は地域によって異なりますが、日本向けの天然ガス(LNG)価格は、JCC(Japan Crude Cocktail)と呼ばれる日本向け原油平均価格にリンクしています。米国、英国等の北米・欧州における天然ガスの売買価格は、それぞれの市場の需給状況等により決定されています。
天然ガス価格の推移について見ると、2014年平均の天然ガス価格(百万BTU当たり)は、米国では4.3ドル、欧州では8.4ドルとなっています。
②我が国のLNG輸入の状況
我が国では、東日本大震災以降の原子力発電の停止により、火力発電の稼働率が大幅に上昇した結果、LNGの需要は震災前の2010年度の約7,060万トンから2014年度には約8,900万トンと約27%上昇しました。加えて、我が国のLNG輸入価格も、2010年に10.8ドル/百万BTU(注)だったものが、2014年には16.2ドル/百万BTUへと大きく上昇しました。このような需要増・価格高騰を受け、我が国のLNG調達費は、2010年の3.5兆円から2014年の7.8兆円へと大幅に増大しました。
- (注)
- BTU(British Thermal Unit)とは、英国熱量単位のことであり、1BTU = 1.054kJ = 0.252kcal。
【第131-1-5】我が国のLNG輸入量の推移
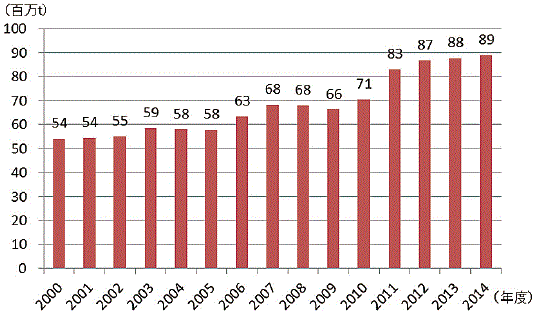
【第131-1-6】我が国のLNG輸入価格及び欧米の天然ガス価格の推移
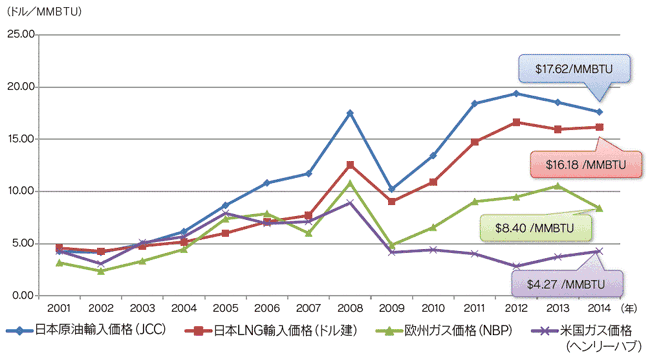
- (出典)
- 財務省「貿易統計」、「ICE」(英ICE futures)、「CME」(シカゴ・マーカンタイル取引所)等のデータを基に作成
【第131-1-7】我が国のLNG輸入価格(CIF価格)の推移
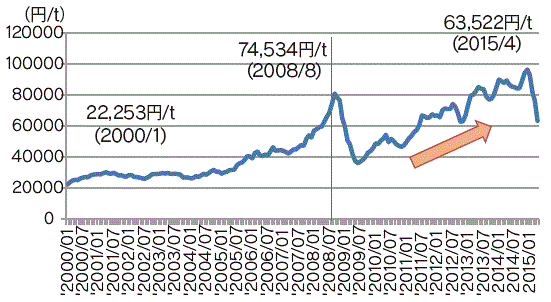
- (出典)
- 財務省「貿易統計」を基に作成
2014年の我が国のLNG調達価格は、他国と比較すると依然として高い価格水準であり、LNG調達が貿易収支に与える影響は、引き続き大きなものとなっています。この背景には、米国価格との比較で言えば、我が国のLNG輸入価格には、米国内の天然ガス価格には含まれていない、液化コストや輸送コスト(注)が含まれていること等が挙げられるほか、円建てで見れば、2010年平均で1ドル88.09円だった円相場が、2014年平均では106.79円と約19円円安方向へ推移したことも影響しています。
- (注)
- 2014年平均の米国の天然ガス価格を前提に、液化コストを3ドルから4ドル、輸送コストを3ドルと仮定し、北米の天然ガスを液化して日本に輸送した場合の日本着価格を試算すると、約11ドル/百万BTU。
(3)石炭
①国際石炭価格の状況
主にボイラー用燃料として発電所やセメント産業などでも多く使用される一般炭の国際価格について見ると、2009年には世界同時不況の影響を受けて下落したものの、その後、中国やインドの輸入増などの影響を受け上昇傾向となり、2008年には豪州のスポット価格で過去最高の194.8ドル(1トン当たり)を記録しました。その後は、欧州経済の不安などから下落基調となっています。主に鉄鋼原料用としてコークスを製造するために利用されている原料炭の国際価格の推移についても、一般炭と同様の傾向が見られます。
石炭の価格は、石油や天然ガスに比べて、カロリーベースの単価では相当程度安価です。2015年3月のCIF価格(1,000kcal当たり)を見ると、原油が4.51円、LNGが5.81円であるのに対して、一般炭は1.65円と低廉であるとともに、価格の推移が原油やLNGよりも安定的です。
②我が国の石炭輸入の状況
我が国の輸入石炭価格(CIF価格)は、2000年以降は原油価格の上昇を受けて、石炭の採炭コスト、輸送コストも上昇し、世界的な石炭需要の増大とも相まって上昇しました。2011年度以降はシェール革命及び世界的な景気停滞による供給過多により、石炭価格は横ばいの状況にあります。2015年初頭では、一般炭は、1トン当たり10,000円前後で推移しています。
我が国の石炭輸入量は、近年は1億9,000万トン前後で小幅な増減となっています。
(4)マクロ経済への影響
東日本大震災以降、火力発電が原子力発電分を穴埋めする形で電力が供給されました。化石燃料の輸入量の増加、原油・LNGの市場価格の上昇、為替の円安方向への推移などにより、化石燃料の輸入額は2010年度の約18兆円から2014年度には25兆円と約7兆円増加しました。2014年度の貿易収支は、昨年度から改善しましたが、9.1兆円と大幅な赤字を記録しました。
【第131-1-8】鉱物性燃料の熱量当たりの輸入価格の推移
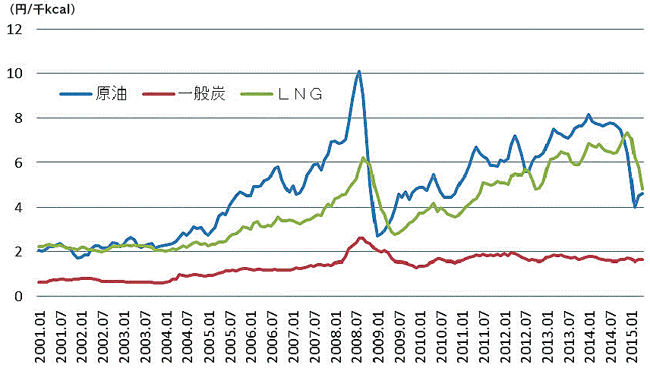
- (出典)
- 財務省「貿易統計」を基に作成
【第131-1-9】我が国の石炭輸入価格の推移
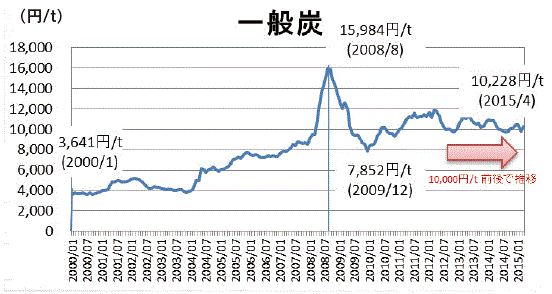
- (出典)
- 財務省「貿易統計」、エネルギー経済研究所資料を基に作成
【第131-1-10】我が国の石炭輸入量の推移
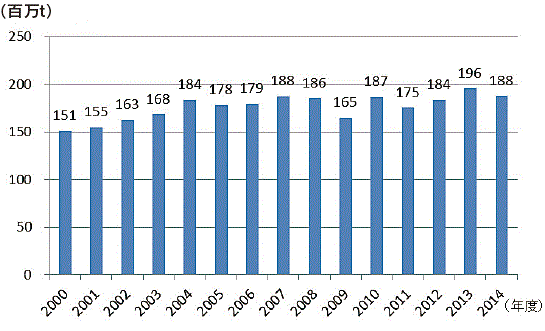
- (出典)
- 財務省「貿易統計」を基に作成
【第131-1-11】貿易収支及び経常収支の推移(年度ベース)
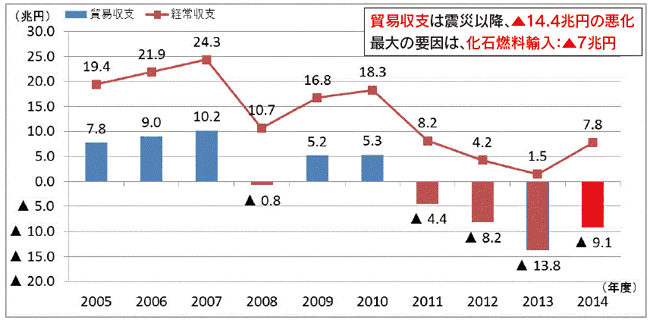
- (出典)
- 財務省「貿易統計」、日本銀行「国際収支統計」等を基に作成
2.電気料金の状況
(1)電気料金上昇の背景事情
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故以降、2013年9月、日本国内の全ての原子力発電所が稼働を停止しました。その結果、我が国の電源構成に占める化石燃料依存度は、東日本大震災前の約62%(2010年度)から約88%(2013年度)へ上昇しました。この水準は、第一次石油ショック時の約76%よりも高いものです。
エネルギー源ごとの発電電力量について2010年度から2014年度の推移を見ると、原子力発電所の停止に伴い、天然ガス、石油など、火力発電の比率が高くなっています。
原子力発電所の停止分の発電電力量を火力発電の焚き増しにより代替していると仮定した場合の燃料費の増加分は、年間約3.4兆円(2014年度)と試算されます。この金額は、2011年度2.3兆円、2012年度3.1兆円、2013年度3.6兆円と、高位で推移しています。2014年度推計の3.4兆円の燃料費増加分は、すなわち、国民一人当たり年間約3万円程度の負担増ということになります。
(2)電気料金の推移
火力発電所の稼働率上昇に伴う火力燃料費の増大などにより、電気料金の平均単価(全国)は、震災前の2010年度と直近値の2014年度を比較すると、家庭用で約25%、産業用で約40%、金額にして家庭用・産業用いずれも約5円/kWh上昇しました。
また、電気料金の上昇は、国民負担の増加に繋がり、電気料金にかかる国民の負担額は、年々増加しています。
例えば、東京電力における標準世帯(従量電灯B、契約電流30A、月間使用電力量290kWh)の電気料金は、東日本大震災前の2010年度は月額6,309円(平均)でしたが、2014年度は月額8,452円(平均)と、約34%上昇しました。
【第131-2-1】電源構成に占める化石燃料依存度
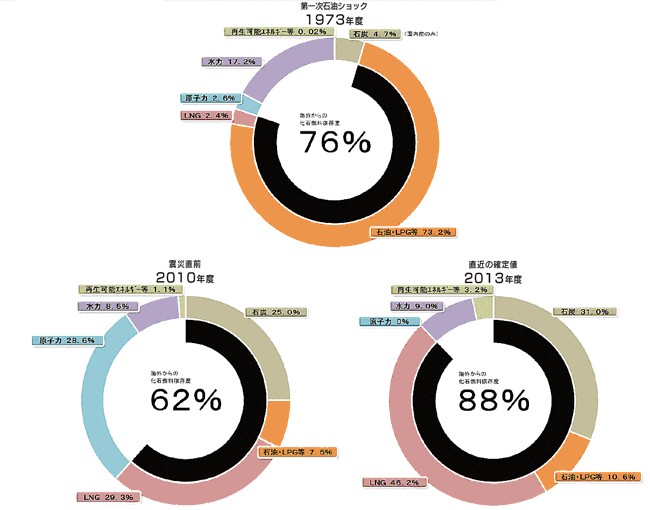
- (出典)
- 経済産業省資源エネルギー庁「電源開発の概要」を基に作成
【第131-2-2】日本の発電電力量の推移と構成割合
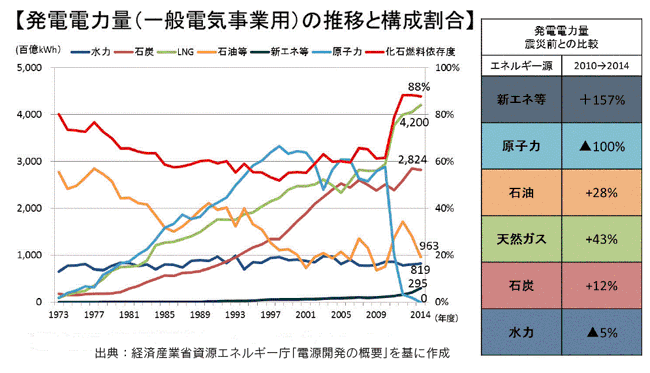
- (出典)
- 経済産業省資源エネルギー庁「電源開発の概要」を基に作成
【第131-2-3】原子力発電停止分を火力発電で代替した場合の燃料費増加の試算
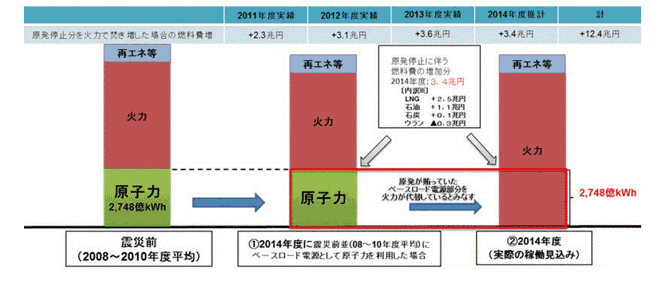
- (出典)
- 資源エネルギー庁電力需給検証小委員会資料を基に作成
- ※
- 各社の直近12ヶ月の焚き増し実績を基に、燃料種別に合算したもの。
- (注)
- この「3.4兆円」の燃料費増は、東日本大震災前の原子力発電の発電量実績(2008~2010年度平均:2,748億kWh)が、火力発電で代替されていると仮定して、これに伴う燃料費の増分を試算したものです。なお、2014年度の「3.4兆円」の発電用燃料費増の試算について、2010年度を基準に要因分析を行うと、原子力発電の発電電力量を火力発電で代替することについて、
(a) 化石燃料消費量の増加による要因が約7割(2.4兆円)
(b) 為替の影響を除いた燃料価格の上昇による要因が約2割(0.8兆円)
(c) 為替が円安方向に推移したことによる要因が約2割(0.6兆円)
このほか、ウラン燃料費の削減による減少要因が約1割弱(0.3兆円)と試算され、化石燃料消費量の増加(a)が最も大きな要因となっています。
(なお、各要因の試算額は四捨五入のため合計が3.5兆円となり、0.1兆円の誤差が生じています)
原子力停止に伴う燃料コスト増
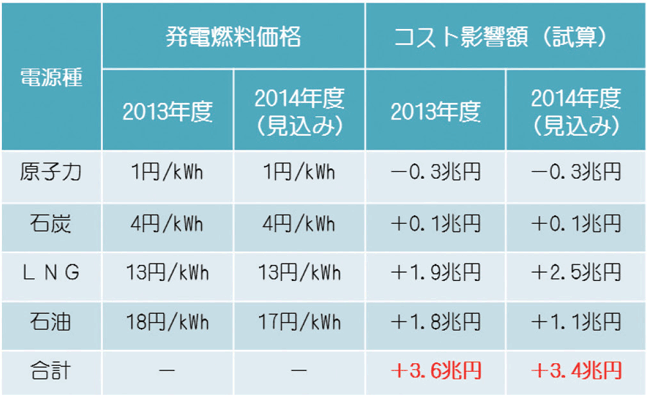
- (出典)
- 資源エネルギー庁電力需給検証小委員会資料を基に作成
【第131-2-4】電気料金の平均単価の推移
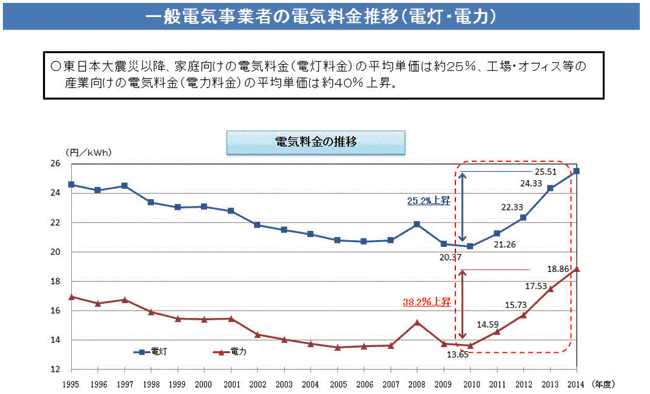
- (出典)
- 電力需要実績確報(電気事業連合会)、各電力会社決算資料等を基に作成
- (注)
- 電灯料金は、主に一般家庭部門における電気料金の平均単価で、電力料金は、自由化対象需要家分を含み、主に工場、オフィス等に対する電気料金の平均単価。平均単価は、電灯料収入、電力料収入をそれぞれ電灯、電力の販売電力量(kWh)で除したもの。
【第131-2-5】電力料金に係る国民負担の増加
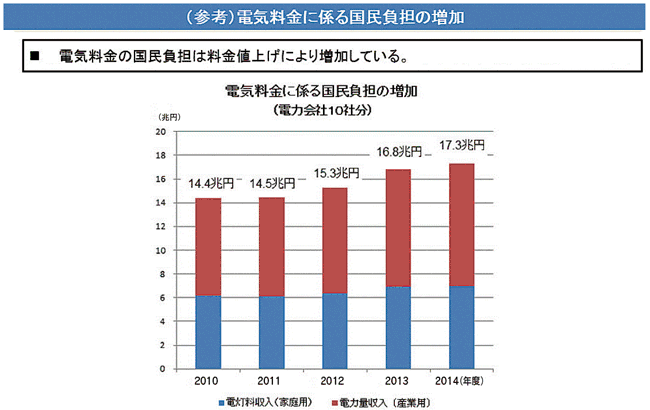
- (出典)
- 電力各社の有価証券報告書を基に作成
【第131-2-6】東京電力における平均モデルの電気料金の推移
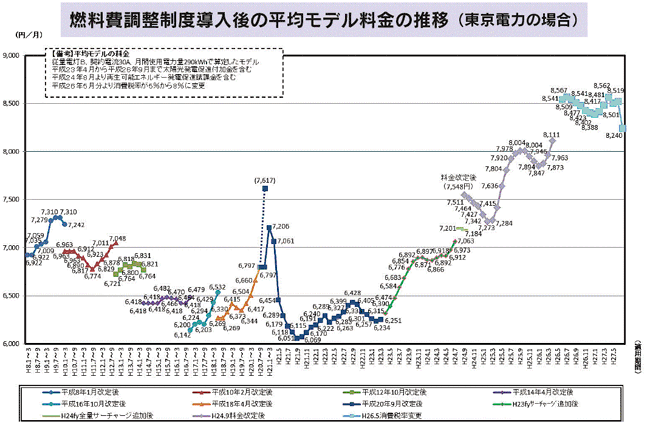
- (出典)
- 東京電力公表資料を基に作成
【第131-2-7】電気料金の構成(一般家庭のモデル・ケース(東京電力)
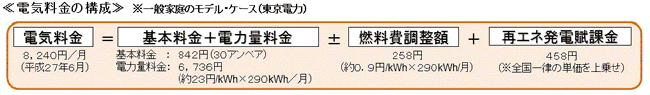
- ※
- 口座振替割引料(54円)を勘案しているため、上記の式の数値は一致しない。
- (出典)
- 東京電力公表資料を基に作成
電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額(注)、再生可能エネルギー発電促進賦課金から構成されます。
- (注)
- 燃料費調整制度は、事業者が直接コントロールできない為替レートや国際的な燃料市況の変動による影響を、毎月の電気料金に自動的に反映する制度です。為替変動による差益を消費者に還元することを目的に、1996年1月に導入されました。
- 海外における原油価格の変動が、原油輸入価格の変動やそれに連動するLNG輸入価格の変動を通じて、電気料金に反映されるまでには、4か月から9か月程度のタイムラグが生じることとなります。
【第131-2-8】原油価格の変動の電気料金への反映までのタイムラグ
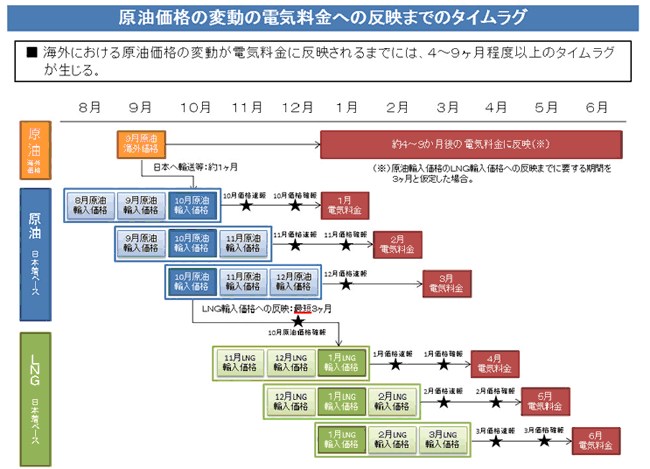
- (出典)
- 資源エネルギー庁作成
(3)電気料金の値上げ認可申請
家庭など規制部門に適用される電気料金については、電力会社から電気料金の値上げ認可申請がなされた場合は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第19条に基づいて、申請が最大限の経営効率化を踏まえたものであるか厳正に審査した上で、経済産業大臣が認可を行うこととなります。
値上げの認可に当たっては、経済産業省総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小委員会(以下「電気料金審査専門小委員会」という。)(委員長:安念潤司 中央大学法科大学院教授)により中立的・客観的かつ専門的な観点から検討するとともに、広く国民の皆様から意見を聴取する公聴会やパブリックコメントも実施することで、透明性の高い審査プロセスを経ることとしています。
【第131-2-9】電気料金改定認可のプロセス
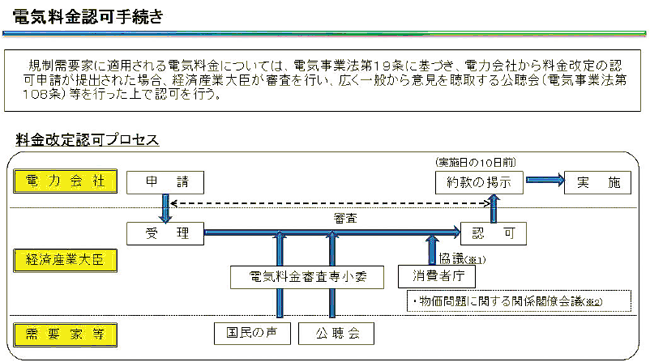
- (※1)
- 物価担当官会議申し合わせ(平成23年3月14日)に基づく。
- (※2)
- 物価問題に関する関係閣僚会議(平成5年8月24日閣議口頭了解)について
○構成員:総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣官房長官。
○会議は、長期及び短期にわたる物価安定対策に関する重要問題について協議することを目的とし、内閣官房長官が主宰。会議の庶務は、消費者庁において処理。
- (出典)
- 「 第19回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小委員会配布資料より抜粋」
【第131-2-10】電力各社の電気料金値上げ改定の動向
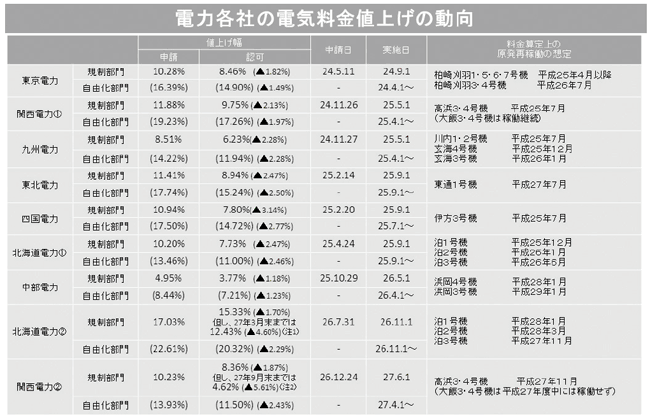
- (※1)
- 平成27年3月31日までは、激変緩和措置として、さらに2.90%圧縮し、12.43%とすることとした。
- (※2)
- 平成27年9月30日までは、激変緩和措置として、さらに3.74%圧縮し、4.62%とすることとした。
- ※
- 自由化部門の値上げ率は、規制部門の値上げ率に対応する原価計算上の数値であり、実際の料金は当事者の交渉によって定められることが原則。
【第131-2-11】電力会社における燃料費の推移
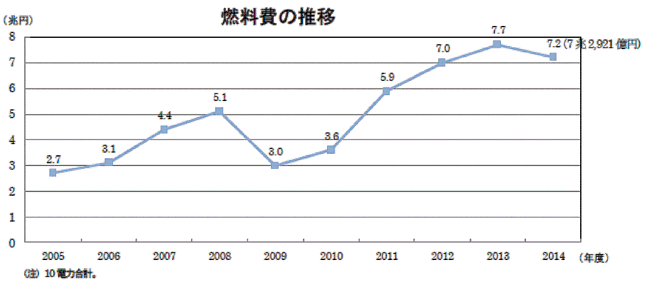
- (注)
- 電気料金の総原価のうち、燃料費(原油、LNG、石炭)の占める割合は大きく、例えば、東京電力の2012年料金改定ベースでは、電気料金の総原価5兆6,783億円のうち、燃料費は2兆4,585億円で約42%を占めています。
- (出典)
- 電気事業連合会資料
東日本大震災以降、原子力発電所の稼働率低下に伴い火力燃料費等が増加し、電力各社の収支を圧迫することとなりました。そのため、2012年以降、東京電力、関西電力、九州電力、東北電力、四国電力、北海道電力及び中部電力が、電気料金の値上げを実施しました。
しかし、原子力発電所の再稼働時期が値上げ実施時に想定していた時期よりも遅延していることにより、火力燃料費が増大し、電力各社の収支を引き続き圧迫したため、2014年11月に北海道電力が、2015年6月に関西電力が、震災後2度目となる電気料金の値上げを実施しました。
右のグラフにあるように、震災以降、電力会社10社の燃料費は上昇しており、2014年度も7.2兆円と、依然として、震災前の2倍相当となっています。こうした燃料費の上昇は、震災以降の電力会社の収支を圧迫しており、電力会社10社合計の経常損益は震災以降、赤字で推移してきました。
【第131-2-12】電力会社10社合計の経常損益
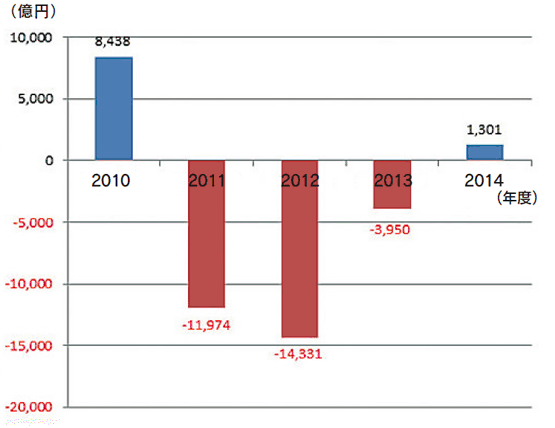
- (出典)
- 電力各社の有価証券報告書を基に作成
①北海道電力の再値上げ
北海道電力は、泊発電所が長期間停止したことによる火力燃料費の増加などを受けて財務状況が大幅に悪化したことから、2013年9月に規制部門の電気料金を7.73%値上げしました。
しかし、同発電所の再稼働が2013年値上げ時の想定(泊1号機:2013年12月稼働、泊2号機:2014年1月稼働、泊3号機:2014年6月稼働)よりも大幅に遅延していることにより、火力発電所における燃料消費量が増加し火力燃料費が更に増大したことから、2014年7月31日、北海道電力は電気料金を規制部門で17.03%引き上げること等を内容とした、電源構成変分認可制度(注)に基づく初めての電気料金値上げ認可申請を行いました。
同年8月から9月にかけて計5回、専門家から構成される電気料金審査専門小委員会において、客観的・専門的な見地から厳正な審査を行うとともに、同年9月11日には値上げに係る公聴会が札幌市にて開催されました。
【第131-2-13】北海道電力の料金改定の概要
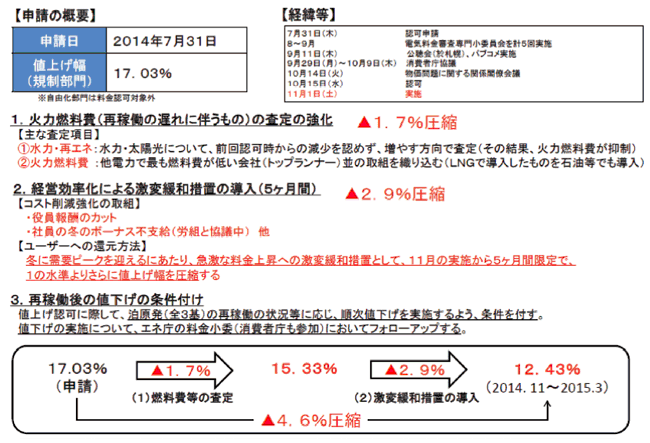
- (出典)
- 資源エネルギー庁作成
その後、委員会で取りまとめられた査定方針案について、同年10月9日まで経済産業省と消費者庁が協議を行い、同月14日の物価問題に関する関係閣僚会議の了承を経て、同月15日に認可されました。
査定のポイントは以下のとおりです。
- (ⅰ) 火力燃料費の単価につき、LNG以外で初となるトップランナー査定を行うなど厳格な査定を行った。この結果、規制部門の値上げ幅は、申請時の17.03%から15.33%となる。実施時期は2014年11月1日とする。
- (ⅱ) 前回の値上げから1年弱での値上げ申請となることを踏まえ、ユーザーのご負担を抑えるべく、更なる効率化の徹底により、激変緩和措置を講ずることとした。具体的には、冬場に需要のピークを迎えることから、2015年3月末までは、更に約3%値上げ幅を圧縮することにより、この間の値上げ幅は12.43%となる。
- (ⅲ) 今回の値上げ申請が泊発電所の再稼働の遅れに起因するものであることから、値上げの認可に際して、泊発電所の再稼働の状況に応じ、順次値下げを実施するよう、条件を付けることとした。
- (注)
- 電源構成変分認可制度について一般電気事業者の電気料金について、料金値上げの認可を経ていることを条件に、当該原価算定期間内において、社会的経済的事情の変動による電源構成の変動があった場合に、総原価を洗い替えることなく、当該部分の将来の原価の変動(燃料費等)を料金に反映させる料金改定を認める制度です。
【第131-2-14】電源構成変分認可制度における電気料金の算定の概要
「前提計画」(需給や効率化計画等)をチェックした上で、社会的経済事情の変動による電源構成の変化があった場合、一般電気事業供給約款料金算定規則に基づき、燃料費、バックエンド関係費用、購入・販売電力料、事業税の変動額から算定される特別変動額を、低圧需要と特別高圧・高圧需要の費用に配分し、原価算定期間の残存期間における低圧需要の変動原価(当初認可時の3年平均原価を上回る部分)と変動収入が一致するように小売規制料金を設定(レートメーク)する。
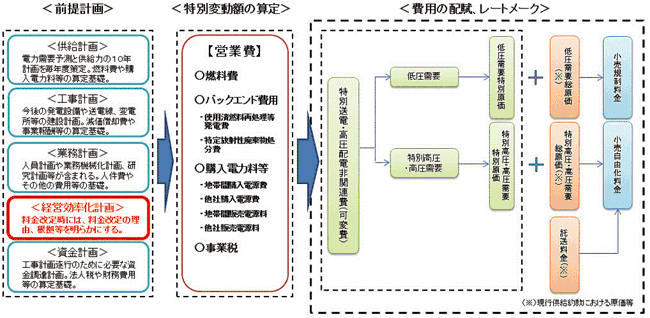
- (出典)
- 「第19回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小委員会配布資料より抜粋」
②関西電力の再値上げ申請
関西電力は、高浜発電所・大飯発電所が長期間停止したことによる火力燃料費の増加などを受けて、財務状況が大幅に悪化したことから、2013年5月に規制部門の電気料金を9.75%値上げしました。
【第131-2-15】関西電力の料金改定の概要
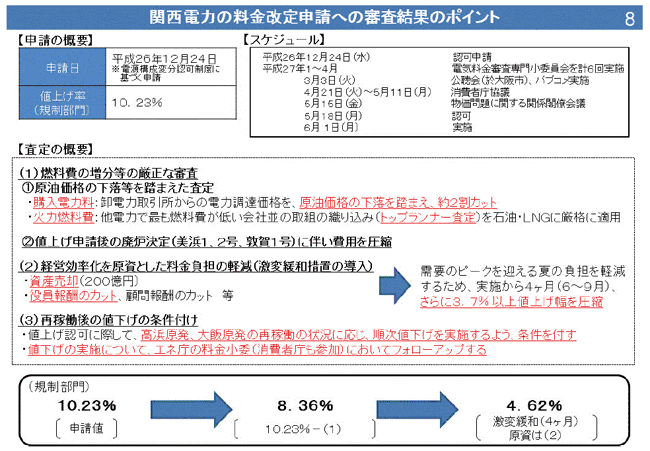
- (出典)
- 資源エネルギー庁作成
しかし、両発電所の再稼働が2013年値上げ時の想定(高浜発電所3・4号機:2013年7月稼働、大飯発電所3・4号機:継続稼働)よりも大幅に遅延していることにより、火力発電所における燃料消費量が増加し火力燃料費が更に増大したことから、2014年12月24日、関西電力は電気料金を規制部門で10.23%引き上げること等を内容とした、電源構成変分認可制度に基づく電気料金値上げ認可申請を行いました。
2015年1月から4月にかけて計6回、電気料金審査専門小委員会において、客観的・専門的な見地から審査を行うとともに、同年3月3日には値上げに係る公聴会が大阪市にて開催されました。
その後、委員会で取りまとめられた査定方針案について、同年5月11日まで経済産業省と消費者庁が協議を行い、同月15日の物価問題に関する関係閣僚会議の了承を経て、同月18日に認可されました。査定のポイントは下記のとおりです。
- (ⅰ) 原油価格の下落を踏まえた卸電力取引所からの調達価格の査定の導入など、増分費用等の厳正な審査を行った。この結果、規制部門の値上げ幅は、申請時の10.23%から8.36%となる。実施時期は6月1日とする。
- (ⅱ) 効率化の徹底を求め、その成果を料金負担の軽減に充てる。具体的には、需要のピークを迎える夏の負担を軽減するため、激変緩和措置として、実施から4 ヶ月間はさらに3.7%以上値上げ幅を圧縮し、その間の値上げ幅は4.62%となる。
- (ⅲ) 今回の値上げ申請が高浜発電所・大飯発電所の再稼働の遅れに起因するものであることから、値上げの認可に際しては、高浜発電所・大飯発電所の再稼働の状況に応じて、順次値下げを実施するよう、条件を付けることとした。
C O L U M N
電力需給対策
(1)2014年度夏季の電力需給対策
①電力需給見通し
2014年度夏季の電力需給見通しについては、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に設置された電力需給検証小委員会において、2014年3月末から4月下旬にわたり、検証を行いました。
検証の結果、「東西間の周波数変換装置(FC)を通じた電力融通をしなければ、中部及び西日本全体の予備率は2.7%(関西では1.8%、九州では1.3%)となり、電力の安定供給に最低限必要となる予備率3%を下回る見込み」、「東日本から中部及び西日本へFCを通じて電力融通を行うことにより、予備率3%以上は各電力管内で確保できるものの、FCによる電力融通を予め織り込むことは、リスクへの対応力がその分喪失するものであり、FCを通じた電力融通を予め頼らずとも電力の安定供給を確保できることを目指した取組を講じるべきであること」が明らかになりました。
これを受けて2014年5月16日に開催された電力需給に関する検討会合において、「2014年度夏季の電力需給対策」を取りまとめました。
【第131-2-16】2014年度夏季の需給見通し(2014年8月)
○FCを通じた電力融通を行わない場合
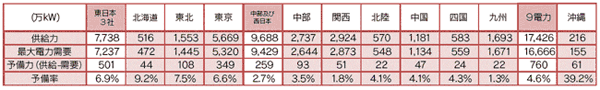
○FCを通じた電力融通を行う場合
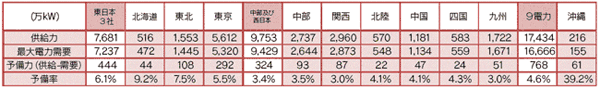
- (出典)
- 電力需給検証小委員会報告書を基本に作成
②電力需給対策
(ア)節電要請
沖縄電力を除く9電力管内について、数値目標を伴わない一般的な節電要請を行いました。節電要請期間は2014年7月1日から9月30日までの平日(同年8月13日から15日を除く)9時から20時としました。なお、節電要請に当たっては、被災地、高齢者や乳幼児等の弱者、熱中症等の健康被害に対して、配慮を行うこととしました。
(イ)その他の電力需給対策
中部及び西日本では、FCを通じた電力融通を行わなければ、電力供給に最低限必要となる予備率3%を下回る厳しい状況であることを踏まえ、(ⅰ)中部及び西日本の電力各社に対し、需給調整契約などで予備力を積み増すことを要請する。特に電力需給が厳しい関西電力及び九州電力に対しては、FCを通じた電力融通に頼らずとも予備率3%以上を確保できるよう、合計で24万kW以上の予備力を6月末までに積み増すこと、(ⅱ)火力発電所の計画外停止を最大限回避するため、電力会社に対して、6月末までに全国で「火力発電所の総点検」を行い、その結果を政府に報告すること、(ⅲ)自家発電設備の活用を図るため、中部及び西日本において設備の増強等を行う事業者に対して補助による支援を行うこと、(ⅳ)中部及び西日本を中心として、大規模な「節電・省エネキャンペーン」を行い、具体的で分かりやすい節電メニューの周知、ディマンドリスポンスなどの取組促進、節電・省エネ診断事業の集中実施等を行うこととしました。
(2)2014年度夏季の結果
2014年度夏季は、需給が厳しい見込みであった西日本において、例年最大需要が発生することが多い8月において2009年以来5年ぶりに低温となる等、西日本を中心に気温が低く、冷房需要が伸びなかったこと等から、結果的に各電力管内において電力の安定供給に必要な予備力は確保されました。
しかし、火力発電所の稼働率が増加する中、老朽火力の計画外停止件数は増加傾向にあり、特に、緊急停止による供給力への影響を未然に防ぐための予防停止や、火力発電所の高稼働に伴う機器や部品の劣化が要因とみられる緊急停止が増加しており、電力の安定供給に対する潜在的なリスクは拡大している可能性があるため、2014年度冬季に向けて、電力需給は引き続き予断を許さない状況であることを再認識せざるを得ない状況でした。
【第131-2-17】2014年度夏季の需給実績
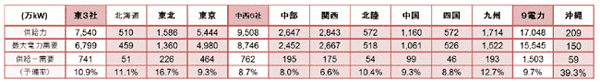
- (出典)
- 電力需給検証小委員会報告書を基本に作成
(3)2014年度冬季の電力需給対策
①電力需給見通し
2014年度冬季の電力需給見通しについては、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に設置された電力需給検証小委員会(以下「本小委員会」という。)において、2014年10月に検証を行いました。
検証の結果、「いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3%以上を確保できる見通しであること」、「北海道電力管内については、他電力からの電力融通に制約があること、発電所一機のトラブル停止が予備率に与える影響が大きいこと、厳寒であるため、万一の電力需給のひっ迫が、国民の生命、安全を脅かす可能性があること等の特殊性があることを踏まえ、電力需給に万全を期す必要があること」が明らかになりました。
これを受けて2014年10月31日に開催された電力需給に関する検討会合において2014年度冬季の電力需給対策を取りまとめました。
【第131-2-18】2014年度冬季の需給見通し(2015年2月)

②電力需給対策
(ア)節電要請
沖縄電力を除く9電力管内について、数値目標を伴わない一般的な節電要請を行いました。節電要請期間は、2014年12月1日から2015年3月31日までの平日(12月29日から31日及び1月2日を除く)9時から21時(北海道電力及び九州電力管内については8時から21時)としました。
(イ)その他の電力需給対策
火力発電所の計画外停止等、大規模な電源脱落により、万が一、電力需給がひっ迫する場合への備えとして、(ⅰ)発電所等の計画外停止のリスクを最小化するため、発電設備等の保守・保全を強化すること、(ⅱ)電力需給のひっ迫が予想される場合に、広域的な電力融通、自家発事業者からの追加的な電力購入等を行えるよう準備すること、及び(ⅲ)随時調整契約等の積み増し、ディマンドリスポンス等、需要面での取組の促進を図ること、(ⅳ)需要家の節電を促進するため、事業者及び家庭向けに具体的でわかりやすい節電メニューの周知や需要家と連動した「節電・省エネキャンペーン」を行うことにより、需給両面での対策を講じることとしました。
また、冬季の北海道の特殊性を踏まえ、計画停電を含む停電を回避するため、北海道電力に対して「計画停電回避緊急調整プログラム」を準備することを要請しました。計画停電回避緊急調整プログラムは、2014年12月15日から2015年2月27日の期間で、過去最大級の電源脱落(137万kW)が発生する場合でも予備率3%以上を確保できるよう、18万kW以上の需要削減量を確保することとしました。
(4)2014年度冬季の結果
2014年度冬季は、12月に強い寒気が日本付近に流れ込んだ結果、北陸電力、中国電力及び四国電力管内の最大需要は、2014年10月に本小委員会が示した想定を上回ったものの、いずれの電力管内においても、電力の安定供給に必要な予備力は確保され、需給ひっ迫に至ることはありませんでした。
しかし、火力発電所の稼働率が増加する中、火力発電所の計画外停電の件数は依然増加傾向にあり、2015年度夏季に向けて、電力需給は引き続き予断を許さない状況にあります。