第4節 今後のエネルギー事情の変化
各国は、その置かれたエネルギー需給や地理的、地政学的な状況等に応じて独自のエネルギー安全保障のかたちを目指し、そのための施策を講じています。
本節では、まず、前節の結果を国別でまとめ、「シェール革命」が世界に広がりつつある時期の、各国のエネルギー安全保障の変化とその背景について改めて確認します。その上で、各国が今後のエネルギー安全保障の強化のため、どのような施策を進めていこうとしているか、そこにはどのような課題があるかについて、シェール関連の施策とそれ以外に分けてみていきます。
1.フランス
【第114-1-1】各項目の点数・評価数値の変化(フランス)
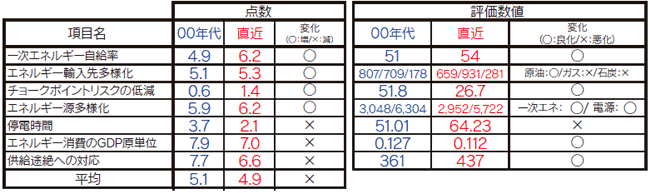
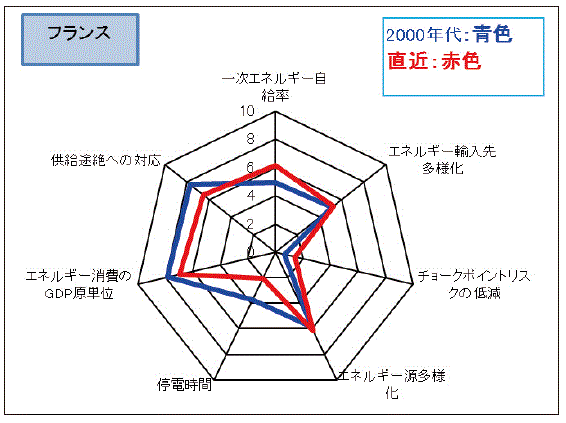
直近の全項目平均点は、2000年代に比べて下がっていますが、各項目の評価数値は概ね良化しています。2012年に決定されたイラン原油禁輸は、エネルギー輸入先の多様化やチョークポイントリスクの低減につながり、エネルギー安全保障の面で良い影響が出ています。
(1)シェール関連
北部に大量のシェールガスの存在が期待されており、その開発が進めば、一次エネルギー自給率の上昇、ロシアからのガス輸入依存の軽減による輸入先多様化、中東からの原油輸入減によるチョークポイントリスクのさらなる低減につながります。
しかし、現在のところ水圧破砕が禁止されており、まずはその変更が必要となります。そのため、早期にシェールガスの生産を開始することは難しい状況です。
(2)その他
2030年までに、再生可能エネルギー(水力含む)の割合を一次エネルギー供給量の2%、発電電力量の40%に引き上げることを目標とした「エネルギー移行法案」を、今夏にも制定する見込みです。これにより、現在、一次エネルギー供給量の約半分、発電電力量の7割以上を占めている原子力の寡占度が下がり、エネルギー源の多様化が進むことになります。
しかし、再生可能エネルギーの導入がどこまで進むかは、巨額の投資を必要とするものもあることから未知数です。場合によっては他のエネルギーへの転換を余儀なくされる可能性があり、前述した国内でのシェール開発の動向にも影響が出てくるものと考えられます。
2.ドイツ
【第114-2-1】各項目の点数・評価数値の変化(ドイツ)
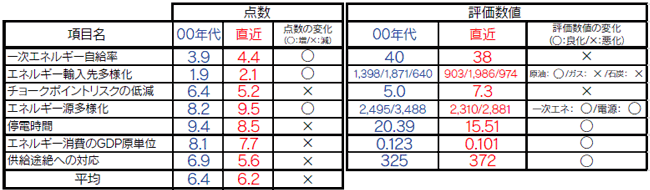
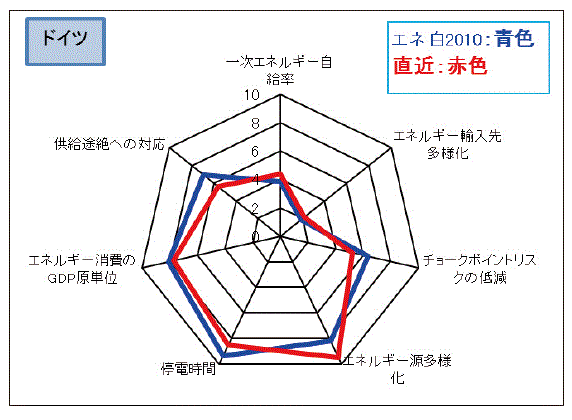
直近の全項目平均点は、2000年代に比べて下がっていますが、6点台の高い水準を維持しています。再生可能エネルギーのシェア拡大により、直近のエネルギー源多様化の項目では対象国中第1位となりました。
再生可能エネルギーのシェア拡大により、一次エネルギーにおける石油のシェアは縮小しており、輸入原油量は減少傾向にあります。このことは、供給途絶への対応に関する評価数値の良化につながりました。
一方、一次エネルギー自給率の点数は上がっているものの、2011年に一部の原子力発電所を停止したこともあり、評価数値である自給率自体は2000年代に比べ直近の方が悪化しています。
(1)シェール関連
化石エネルギーに関しては、ロシアからの輸入依存度の高さが問題となっており、今後、「シェール革命」による増産が進む北米からの原油・天然ガスの輸入が可能になれば、最も点数の低い項目であるエネルギー輸入先多様化について改善が図られることになります。
そのために必要となるLNGターミナルについては、2005年に建設計画が発表されましたが、隣国のオランダに大規模なターミナルが存在することなどから、輸出入業者の関心が低かったため、2011年に計画は無期限延期とされました。2014年のロシアによるクリミア侵攻を受け、政府は同計画の再考を行う旨を明らかにしましたが、その後の具体的な動きは現在までのところありません。
この背景には、米国による原油輸出解禁に関する議論や、従来パイプラインでの米国への天然ガス輸出が中心であったカナダによる輸出用LNGターミナルの建設(東海岸側のターミナル着工予定は最速で2019年)等、輸出国側が直ちに輸出を開始できない事情が存在しています。
(2)その他
2014年現在でも、一次エネルギーにおける石炭と天然ガスのシェアを合わせると約49%、発電電力量における石炭と天然ガスのシェアを合わせると約54%に達しており、政府は、再生可能エネルギーのシェアをさらに拡大しようとしています。
2014年に改正された「再生可能エネルギー法」では、電力総消費量に占める再生可能エネルギー(水力含む)の割合を2025年までに40 ~ 45%、2035年までに55 ~ 60%、2050年までに80%以上とすることが目標として定められました。一方で、電気料金の引き上げにつながるとして問題視されていた再生可能エネルギーの賦課金の一部が削減されるなど、制度の見直しが行われました。
当面は、再生可能エネルギーのシェア拡大により、エネルギー源の多様化がさらに進んでいくことになるでしょう。
エネルギー消費効率の改善については、2010年に設定された「エネルギーコンセプト」において、2020年に20%減、2050年に50%減(いずれも2008年対比)の目標が定められています。
3.英国
【第114-3-1】各項目の点数・評価数値の変化(英国)
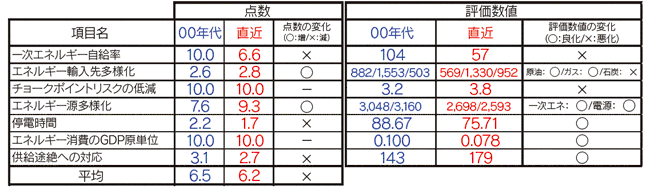
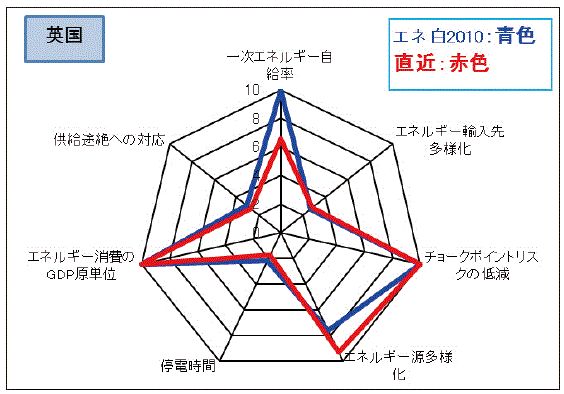
2000年代に比べ、直近の点数と評価数値の双方が悪化したのは、一次エネルギー自給率の項目のみでした。
チョークポイントリスクの低減、エネルギー消費のGDP原単位、全項目平均点については、2000年代に続き、直近でも対象国中第1位となりました。
「シェール革命」の間接的な影響である、アフリカ原油の輸入量拡大は、原油輸入先多様化、供給途絶への対応に関する評価数値の良化につながりました。
(1)シェール関連
2005年に一次エネルギー自給率が100%を割り込み、その後も減少を続ける中、政府は2008年に陸上のシェールオイル・シェールガス開発ライセンスを民間企業に付与しました。しかし、2011年に水圧破砕による地震が発生したことが問題となり、開発は一時中断されました。
その後、2014年には、新たな開発ライセンス付与鉱区が公開されましたが、開発地域付近の住民などから強い抵抗が示されています。また、これまでは海上油田の開発が中心であったため、陸上の原油・ガスを運ぶためのインフラが不足し、コストが高くなることなど、大量の生産を行うために解決すべき課題が多くみられます。
天然ガスの輸入については、直近ではノルウェーからのパイプラインでの輸入(57.1% )に次いで、カタールからのLNG輸入のシェアが多くなっています(17.6%)が、2013年に国内最大のガス供給会社が米国からのLNG輸入に関する20年契約を結ぶ(2015年より輸入開始予定)など、「シェール革命」に関連した輸入先多様化につながる動きが出てきています。
(2)その他
直近の一次エネルギー自給率向上策として政府が進めているのは、北海油田の再開発(非在来型原油・ガスは対象外)であり、本年中に開発促進のための関連機関(Oil and Gas Authority)を正式に立ち上げる予定です。
エネルギー源多様化につながる再生可能エネルギーの推進については、2020年までに最終エネルギー消費の15%に到達することを目標としており、達成のためのロードマップに沿って順調に取組が進められています。
4.米国
【第114-4-1】各項目の点数・評価数値の変化(米国)
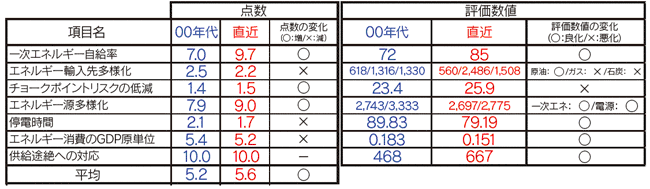
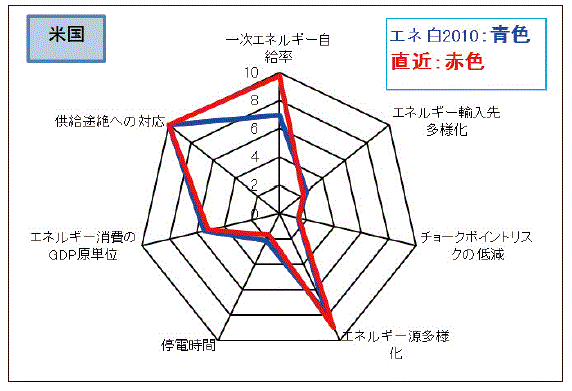
直近の全項目平均の2000年代比での上昇幅は対象国中第1位であり、「シェール革命」は、あらゆる面でエネルギー安全保障を強化させたと考えることができます。
なお、エネルギー輸入先多様化の項目の悪化については、「シェール革命」の影響で、天然ガスの輸入量が減少し、相手国がほぼカナダに限られるようになったことで寡占度が大幅に上昇したことが要因となっています。
(1)シェール関連
シェールオイル・シェールガスの開発に関しては、第1節で述べたとおりです。開発が順調に進めば、一次エネルギー自給率はさらに上昇し、石炭の発電比率が下落することでエネルギー源の多様化が進むことになります。
国内需要の大きさから、一次エネルギーの完全自給は難しいと考えられていますが、原油輸入量は今後も減少する見通しです。仮に中東からの原油輸入量が減少すれば、チョークポイントリスクの低減につながります。しかし、こうした動きが中東の安定についての政治的な関心を低下させることにもつながるのではないか、と危惧する声が出てきています。
また、原油輸入量の減少は、供給途絶対応日数の増加にもつながります。これと関連の深い戦略石油備蓄(SPR)については、2005年に増量計画(100百万バレル)が発表されましたが、「シェール革命」によって国内での原油増産が進んだことから、2011年に撤回されました。これを機に、SPRの目的の転換(同盟国に有事の際に輸出するなど)や削減を求める動きも出ており、こうした議論の結果、供給途絶対応日数が減少する可能性もあります。
最大の論点は、原油価格が急落する中でのOPECの減産見送りや、開発による環境破壊といった問題が指摘される中、このままシェールオイル・シェールガスの開発が進むかどうかです。米国のシェールガス・シェールオイルの動向は、世界のエネルギー情勢を左右していく要因ともなるでしょう。
(2)その他
エネルギー源多様化に関しては、石炭から天然ガスだけでなく、石炭から再生可能エネルギーへのシフトを促す政策が推進されています。
2013年にオバマ大統領が発表した「気候行動計画」では、火力発電所からの排出量規制を促すとともに、2020年までに発電に占める再生可能エネルギー(太陽光・風力・地熱)の比率を倍増させるとしています(対象年度が不明ですが、仮に2012年比で倍増させるのであれば、目標の発電比率は約12%となります)。
5.中国
【第114-5-1】各項目の点数・評価数値の変化(中国)
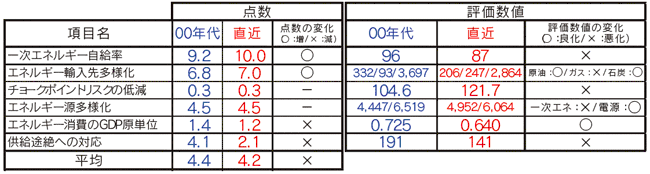
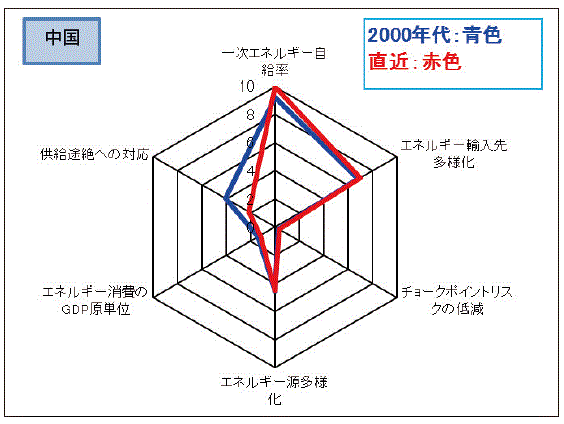
直近では、一次エネルギー自給率の項目で対象国中第1位となりましたが、評価数値である自給率自体は悪化しています。1999年に一次エネルギー自給率が100%を下回って以降、国内のエネルギー消費量の拡大が国内生産量の増加を上回る傾向が続き、エネルギーの輸入量が増加しています。
原油輸入の増加に対応できる供給先は主に中東産油国であることから、2000年代に比べ、直近の中東依存度は上昇し、チョークポイントリスクが増すことになりました。また、直近の中東原油の輸入量が2000年代の3倍近くとなったことが、供給途絶への対応についての評価数値と点数を大幅に悪化させ、全項目平均点を押し下げる要因になりました。
一方、パイプラインによるロシアからの原油輸入も拡大しています。これにより、中国は原油輸入先の多様化を進めることができ、一方のロシア側も、欧州以外の輸出先を確保できるという利点があります。
(1)シェール関連
中国のシェールオイルは、地理的・地質的条件から開発が容易ではなく、短中期的に国内原油生産量の拡大に寄与することは難しいと考えられています。
一方、シェールガスの生産は既に開始されており、政府は補助金制度などを通じて開発を促進しています。国土資源部によると、2014年の生産量は13億立方メートルで前年の6.5倍となりました。これは、国内の天然ガス生産量全体の約1%にあたります。
しかしながら、技術不足や水圧破砕のための水不足などから、当初の見通しほど生産量は増えていません。2012年の段階で、政府はシェールガス生産量の目標を2015年に65億立方メートル、2020年に600 ~ 1,000億立方メートルとしていましたが、2014年に後者の目標を300億立方メートルに下方修正しました。シェールガスの生産が一次エネルギー自給率の上昇につながるかは未知数であり、まずは2015年の生産量が目標に到達するかどうかが注目されます。
直近の天然ガス輸入量の半分はLNG(その約4割はカタールからの輸入)ですが、これまで北米からのLNG輸入は行われておらず、今後の輸入のための長期契約も結ばれていません。輸入先多様化との関連で、これからどのような動きがあるかに関心が集まっています。
(2)その他
国務院が2014年11月に公表した「エネルギー発展戦略構造計画(2014-2020年)」では、エネルギー源多様化と大気汚染問題の解決を目指し、一次エネルギー供給量に占める石炭の割合を2020年までに62%以下、天然ガスを10%以上、非化石エネルギーの比率を15%以上にするという目標が掲げられています。また、2020年の一次エネルギー消費量を2013年比で28%増までに抑えるとしています(2013年は2005年対比で約82%増)。
同計画では、一次エネルギー自給率について、直近の水準である85%前後の維持を目標に定めており、前述したシェールガスの開発に加え、外資系石油企業とのJVによる深海における原油・ガス開発が始まっています。また、非在来型ガスである炭層メタンガス(CBM)の生産も進められています。
天然ガスについては、既に輸入が行われている中央アジアからのパイプラインについて、新ルートを建設する予定があります。また、ロシアとの間でもパイプライン建設の計画が進められています。
「シェール革命」の間接的な影響として、中東の天然ガスが欧州に流れて競争が増す中、ロシアは新たな天然ガスの販路を東アジアに求めています。
こうした計画と、上述の米国からのLNG輸入の動きにより、天然ガスの輸入先多様化が大きく進む可能性もあります。
また、2015年より、ミャンマーからパイプライン経由での原油輸入が開始されました。この原油は中東産ですが、マラッカ海峡を経由せずに中東原油を輸入できるという点で、チョークポイントリスクの低減につながります。
その他、原油の国家備蓄基地については、既に第3期計画(合計備蓄能力141百万バレル、2020年着工開始予定)が発表されています。これに国営石油企業による備蓄等を含めると、将来的には、直近の石油備蓄量の2倍近くとなる約800百万バレルの備蓄能力を保有する見通しであり、供給途絶対応可能日数が伸びることが期待されます。
6.日本
【第114-6-1】各項目の点数・評価数値の変化(日本)
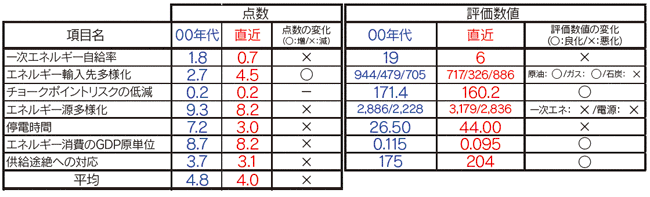
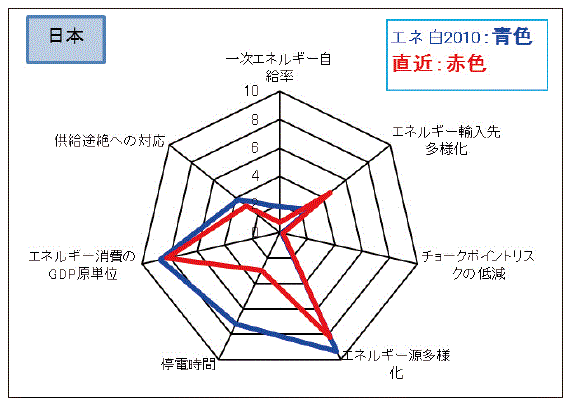
東日本大震災とその後の東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、直近の一次エネルギー自給率、エネルギー源多様化の点数及び評価指数が2000年代に比べ悪化しました。
エネルギー輸入先多様化を除く項目で点数を下げたため、全項目平均点も大きく下がり、直近の点数は対象国中最も低くなりました。
全般的に、エネルギー安全保障の弱体化が見て取れますが、ロシア産原油の輸入増による原油の輸入先多様化、チョークポイントリスクの低減といった改善点も表れています。
(1)シェール関連
原油輸入の中東依存度が依然高く、天然ガスの中東依存度は上昇していますが、今後、北米からの原油・天然ガスの輸入が増えれば、輸入先多様化、チョークポイントリスクの低減、供給途絶対応日数の増加が進むこととなり、エネルギー安全保障が強化されることになります。
特に、シェールガス革命により国内の天然ガスの生産が拡大している米国からのシェールガス・LNGの供給の実現は重要であり、日本企業は、日本のLNG輸入量の約2割に相当するLNGについて引取の契約を締結済みです。これらは、石油価格に連動した契約ではなく、天然ガス価格指標に連動した価格であり、2016年以降、順次、日本への供給が開始される予定です。
(2)その他
2014年4月、第4次となる「エネルギー基本計画」が閣議決定されました。従来の「3E(Energy Security:安定供給、Economic Efficiency:経済性、Environment:環境)+S(Safety:安全性)」という基本的視点に、国際的な視点の重要性、経済成長の視点の重要性を加味した内容となっており、この方向性に沿って、エネルギー安全保障の強化のための改善策も進められていくことになります。
7.韓国
【第114-7-1】各項目の点数・評価数値の変化(韓国)
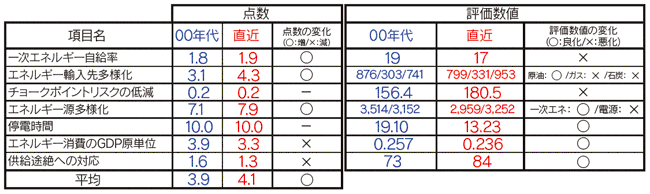
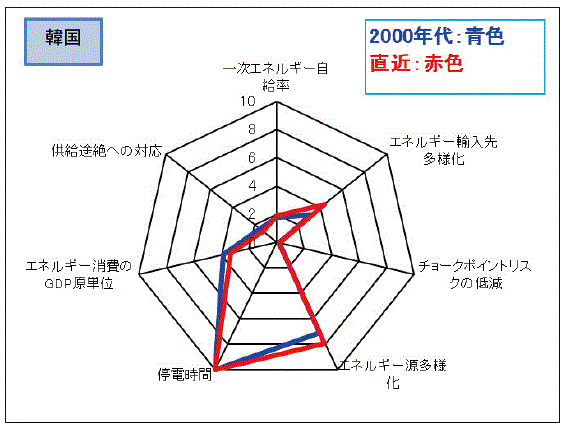
2000年代には一次エネルギー源の半分以上を石油が占めていましたが、これを天然ガスに転換する政策を進めてきたことが、エネルギー源多様化の点数の上昇につながりました。また、天然ガスの輸入先として、インドネシアのシェアが減少する一方、カタール、ナイジェリア、ロシアのシェアが増加することにより、寡占度が低くなり、エネルギー輸入先多様化の点数が上昇しました(ただし、評価指数は供給比率が上昇したことから、やや悪化しています。【第113-3-8】参照。)。
この2項目の点数の上昇により、直近の全項目平均点は2000年代に比べ上昇しましたが、点数自体は対象国で日本に次いで低いものとなっています。
(1)シェール関連
原油・天然ガスの輸入に関して、直近では日本よりも中東依存度が高くなっており、「シェール革命」による北米からの輸入が実施されれば、輸入先多様化やチョークポイントリスクの低減といった恩恵を大きく受けることになります。
(2)その他
2011年から進められていたロシアとの間での天然ガスパイプライン建設計画は、経由地となる北朝鮮の核問題で頓挫しましたが、ロシアとはサハリンからのLNG輸入で合意しており、輸入先多様化が進む見通しです。
エネルギー源多様化については、2013年に産業通商資源部が発表した「第2次国家エネルギー基本計画(2014 ~ 2035)」で、原子力の発電比率の目標を29%と定めました。これは、日本の原子力発電所事故後であり、第1次計画(41%)よりは引き下げられましたが、直近の実績(26%)よりは高いものになっています。
C O L U M N
セキュリティインデックスの策定
【セキュリティインデックス策定の目的】
3Eにおけるエネルギーの経済性(Economy)や環境性(Environment)については、エネルギーコストや温室効果ガス排出と言った数値によって定量的な評価が可能です。
一方で、エネルギー安全保障(Energy Security)については、複数の観点から定性的な情報等を数値化し、ランク付けするといった取組はなされてきましたが、これまで自給率以外に定量的な評価が試みられることはなされていませんでした。このため今回セキュリティインデックスを計算するフォーミュラを策定し、その評価を試みました。
【エネルギーセキュリティインデックスの評価手法】
エネルギーセキュリティインデックスの計算は以下のようなプロセスで行います。
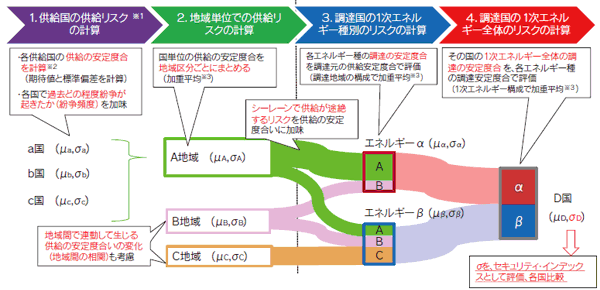
1.資源供給国の供給リスクの計算
資源供給国の月別石油生産量が、その前後6 ヶ月の最大生産量に対してどれだけの割合を占めるかの比率を取り、その時系列データの標準偏差で供給安定性を評価します。これに加え、各供給国で過去どの程度紛争が起きたか(紛争リスク)を加味します。
2.地域単位での供給リスクの計算
1.で求めた供給国単位の供給リスクを、地域単位のリスクにまとめるため、その地域における供給構成比で国単位の供給リスクを加重平均します。
3.調達国のエネルギー種別の調達リスクの計算
石油、天然ガス、石炭等、燃料種毎に地域単位の調達構成比で供給リスクを加重平均します。この際、調達地域から消費国に至る経路の中で何回チョークポイントを通過するか(シーレーンリスク)を加味します。
4.調達国の1次エネルギー全体の調達リスクの計算
エネルギー調達国におけるエネルギー種別の調達リスクを、1次エネルギー構成比で加重平均し、その国の1次エネルギー全体の調達リスクを評価します。
- ※
- 自国で生産されるエネルギーについてはリスクフリーの資源として評価した(再生可能エネルギーはすべてリスクフリー)ほか、ウランについては、複数年での消費が前提とされる準国産燃料としてリスクフリーとしました。
(参考) A国における資源xのセキュリティインデックス:
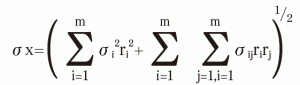
(σiは地域iの調達リスク、riは資源xの調達全体に占めるi国の割合、σijは地域iとjの相関リスク)
【2010年、2012年におけるエネルギーセキュリティインデックスの評価結果】
以下のとおり各国における1次エネルギー供給ベースでのセキュリティインデックスを比較しました。数値が大きい方が高リスク、小さい方が低リスクと評価されます。評価から得られる傾向としては以下のとおりです。
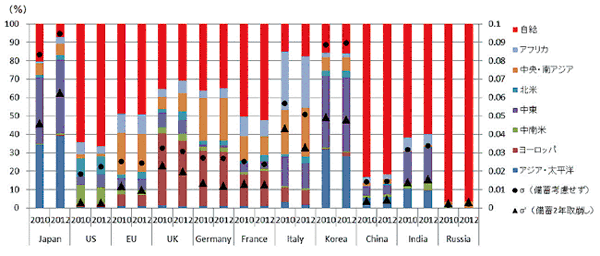
<考察>
- 米国、中国、ロシアといったエネルギー自給率が高い国は、セキュリティインデックスでは低リスクになっています。
- 日本や韓国は、自給率の低さ、調達先のカントリーリスクの高さ、主要な化石燃料産出国から距離のある極東の国であることによるシーレーンリスクの高さから、世界の主要国と比較しても高い水準にあります。
- 2010年と2012年を比較した場合、日本は震災後の原子力発電の稼動停止により、化石燃料の利用割合が増加し、エネルギーセキュリティのレベルはさらに悪化しています。
- また、石油備蓄を自給燃料として評価し、リスクフリーだと想定すれば、備蓄量に応じてセキュリティが改善することが観察できます。特に日本、韓国は備蓄の効果が大きいことが分かります。
( 備蓄を考慮しない場合と2年で取り崩す場合についてセキュリティインデックスをグラフに表示。)
【我が国の電源構成・最終エネルギー消費におけるセキュリティインデックスの評価】
セキュリティインデックスは電源構成や最終エネルギー消費を評価する際にも利用が可能です。
2010年、2012年のIEAの我が国に関するデータを利用してこれを評価しました。
<考察>
- 2010年と2012年の電源構成を比較すると、東日本大震災以降、火力発電の割合が増加したことからインデックスの値は悪化しています。
- また、最終エネルギー消費において各部門を比較すると、石油消費の割合が高い運輸部門については他の部門に比較してリスクが高いことがわかります。
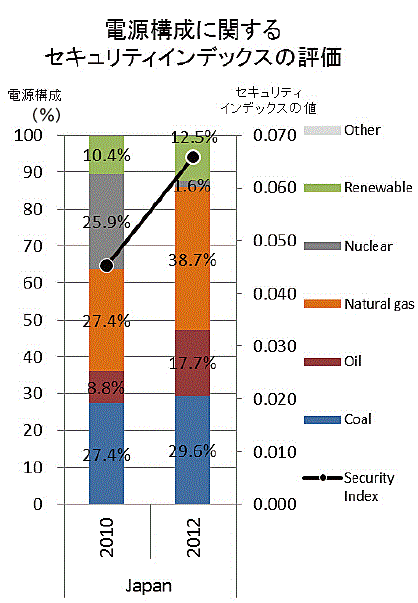
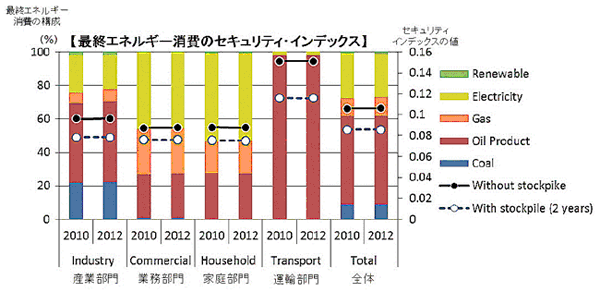
【過去の推移と長期エネルギー需給見通しにおける我が国の1次エネルギー構成、電源構成のセキュリティインデックスの比較】
これまでの1次エネルギー構成や、電源構成のセキュリティインデックスを時系列で示すとともに、今般発表された長期エネルギー需給見通しと比較してそこから得られる示唆を以下に整理しました。
<考察>
- 過去のセキュリティインデックスの推移を見ると2010年度まではセキュリティが改善してきたものの、2012年度、2013年度は東日本大震災による化石燃料の利用増加により、これまでの推移と比較してインデックスは悪化しています。
- 一方、2015年に発表された長期エネルギー需給見通しにおける2030年度のセキュリティインデックスは、再生可能エネルギーの利用増や原子力発電の再稼働等によりインデックスが震災前の水準より改善することが分かります。
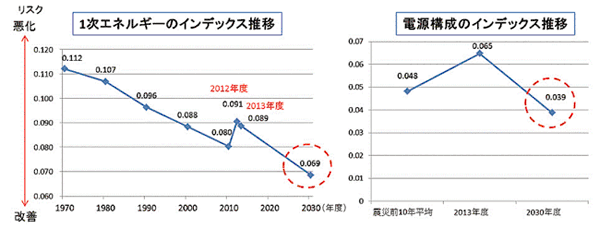
【1次エネルギー構成、調達国構成を変更した場合の効果に関する感度分析】
セキュリティインデックスの計算の際に1次エネルギー構成や調達国構成を変更すれば、これをもたらすような政策を取った場合にエネルギーセキュリティにどのような効果をもたらすか予測できます。
<考察>
- 2012年の1次エネルギー構成において石油から天然ガスに5%振替えた場合インデックスは改善しますが、石炭を天然ガスに5%振り替えた場合にはインデックスが悪化します。
- 原油の調達先を中東から北米に5%振替えた場合には1次エネルギー供給のセキュリティインデックス、原油のみのセキュリティインデックス共に改善します。
- また、長期エネルギー需給見通しにおける2030年の電源構成において、各電源を1%振替えた場合の効果は以下のとおりとなりました。
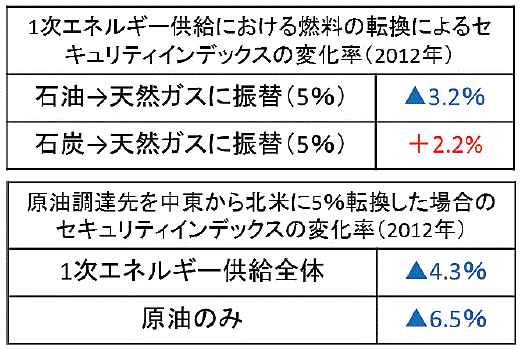
- ※
- 原子力について準国産エネルギーであるが、ウラン調達リスクを考慮している
- ※
- 2030年での電源構成に基づくセキュリティインデックスの変化割合を記載(減少する方がセキュリティが向上)
- ※
- 数値は1%変化した場合の数値であり、振替える割合により変化率は異なる。
- ※
- 燃料調達先等は2012年の割合に変化が無いと仮定
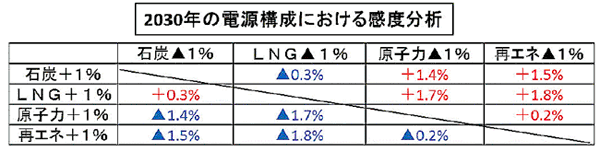
ここまでの考察からも分かるように、ある政策がエネルギーセキュリティにどのような影響を与えるのかを評価する指標として、セキュリティインデックスを利用することは有用であると考えられます。
C O L U M N
メタンハイドレート
メタンハイドレートはメタンと水が低温・高圧の状態で結合した氷状の物質で、「燃える氷」とも呼ばれ、次世代のエネルギー資源として注目されています。石油や石炭に比べ燃焼時の二酸化炭素排出量が少なく、将来のクリーンエネルギーとしても期待されています。しかし、固体で存在するため、高い圧力がかかる状況に閉じ込められた在来型の石油や天然ガスとは異なり井戸を掘っても自噴せず、新たな生産技術を開発することが必要です。
メタンハイドレートは、その特徴によって主に太平洋側の海底面下数百メートルの地層中に存在している「砂層型メタンハイドレート」と、主に日本海側の海底の表面やその近傍に存在している「表層型メタンハイドレート」に分けられます。
砂層型メタンハイドレートについては、2013年3月に海域では世界初となるガス生産試験を実施しました。現在、より長期的に安定した生産が可能となるよう技術開発を行っています。
また、表層型メタンハイドレートについては、資源量の把握のため、2013年度から調査を開始しており、昨年度は世界に先駆けて本格的なサンプル取得に成功しました。十分な資源量が確認されれば、資源量回収技術の本格的な調査・研究開発に取り組んでいきます。

ガス生産試験の様子
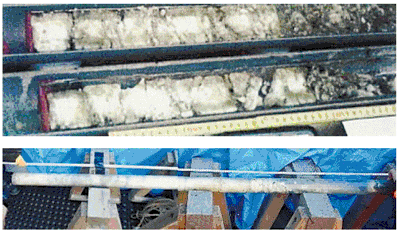
表層型メタンハイドレートを含む地質サンプル
アブダビ陸上油田の権益獲得
2015年4月27日、国際石油開発帝石が、アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ首長国政府及びアブダビ国営石油会社(ADNOC)との間で、アブダビ陸上油田の40年間の権益(5%)の獲得に関する契約文書に署名しました。
同油田は、現在の生産量が日量160万バレル、2017年には同180万バレルの生産量を見込む世界屈指の巨大油田であり、これまで、外国資本では、いわゆる欧米のオイルメジャーのみが権益を保有してきましたが、今般、アジア企業として初めて権益獲得に成功しました。
今般の権益獲得は、我が国の自主開発原油量を約15%引き上げるとともに、同油田からの原油はホルムズ海峡を回避した輸出が可能であることから、我が国の石油の安定供給確保に大きく貢献するものです。
アブダビ首長国との関係では、2013年5月の安倍総理大臣、2015年1月の宮沢経済産業大臣の同国訪問など、陸上油田の権益獲得に向けた働きかけを行ってきたほか、教育・医療等、広範な分野での協力を実施してきました。今般の権益獲得は、国際石油開発帝石のこれまでの実績とともに、日アブダビ間の緊密な関係が高く評価されたものであり、資源外交の大きな成果と言えます。
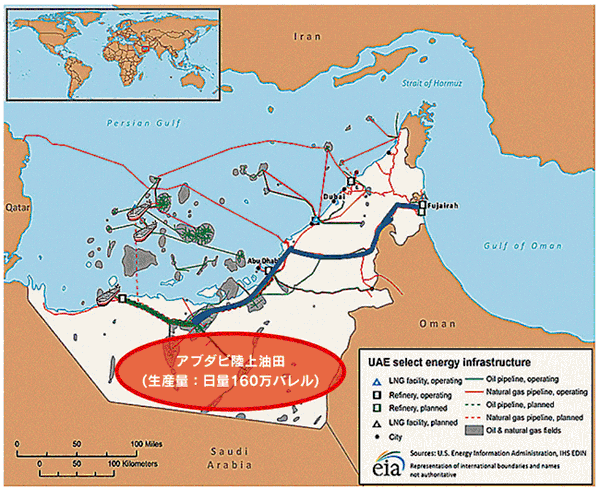
アブダビ陸上油田地図
- (出典)
- EIAホームページを基に作成