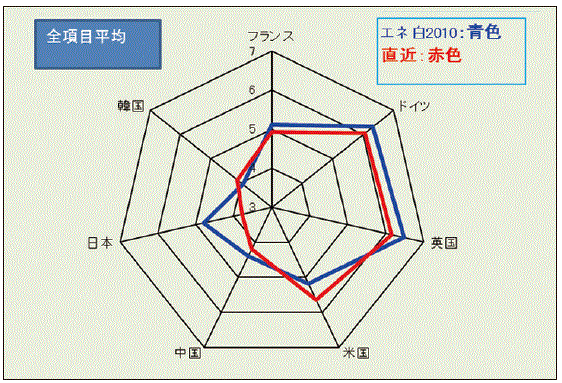第3節 主要国の「エネルギー安全保障」の変化
ここまでみてきたとおり、「シェール革命」は米国だけでなく、世界のエネルギー事情に影響を与えています。米国を含めた主要国のエネルギー事情がどのように変化したかを確認するために、「エネルギー白書2010(以下「エネ白2010」という。)」で使用した「エネルギー安全保障の定量評価指標」を用いて、当時と現在のエネルギー事情の比較を行います。
2010(平成22)年に公表した「エネ白2010」では、主要7か国(フランス、ドイツ、英国、米国、中国、日本、韓国)のエネルギー安全保障が70年代以降の各年代でどのように強化されてきたかを概観するために、7項目の指標(詳細は後述)を用いました。当時の最新情報であった2000年代(データの関係上、最長で2000 ~ 2008年の平均)の数値は、「シェール革命」が本格化する直前の各国の様子を示すものとなっています。
本章では7項目の指標について、直近の数値を算出し、2000年代(「エネ白2010」における)の数値との比較を行うことで、「シェール革命」の時代を経て、各国のエネルギー安全保障がどのように変化したかを見ていきます。また、その「変化」の背景として、「シェール革命」がどのように関わっているのか、あるいは他の要因によるものかについて分析を行います。
- (注)
- 「変化」を確認することが最大の目的のため、本節では「エネ白2010」で用いた評価指標自体の検証は行わず、後述する「要素の選定」「評価手法」については「エネ白2010」の内容を踏襲しました。また、「変化」を把握することを最優先と考え、項目によっては、直近のデータを使用して「エネ白2010」における2000年代の数値を修正したものもあります。
1.エネルギー安全保障を構成する要素の選定
「エネ白2010」では、現代における「エネルギー安全保障」を、「国民生活、経済・社会活動、国防等に必要な量のエネルギーを、受容可能な価格で確保できること」と定義しています。
そして、エネルギー安全保障を構成する要素を「資源調達」、「国内供給」、「国内消費」という一連のサプライチェーンに基づいて選定し、各国が講じてきたエネルギー安全保障政策の定量評価を試みています。
「資源調達」は、国内外で資源を発見・確保し、消費地まで安定的に輸送することを指しますが、その段階でエネルギー安全保障を強化する要素として「国産・準国産エネルギー資源の開発利用」、「海外エネルギー資源の確保」、「資源の輸送リスク管理」が挙げられます。
次に「国内供給」の段階で、安定的な供給を持続してエネルギー安全保障を確保するために「国内リスク管理」が必要となります。
また、「国内消費」の面から、エネルギー安全保障を強化するには「需要抑制」が有効と考えられます。さらに、サプライチェーン全体を支えるものとして「供給途絶への対策」が備わっているかもエネルギー安全保障の重要な要素となります。
【第113-1-1】エネルギーサプライチェーンにおけるエネルギー安全保障を構成する要素
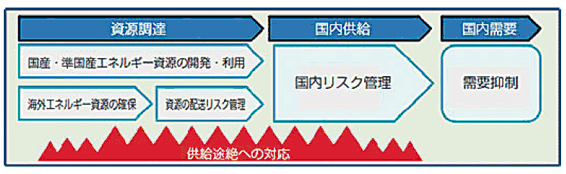
こうした観点から、「エネ白2010」では、エネルギー安全保障を定量評価するための指標として【第113-1-2】の7項目を選定し、下線部分につき評価比較を行いました。
2.エネルギー安全保障の評価手法
「エネ白2010」では、前述の7項目について、フランス、ドイツ、英国、米国、中国、日本、韓国の7か国(最初に欧米諸国をアルファベット順、次にアジア諸国をアルファベット順に並べています)を調査対象国として定量評価比較を行いました。なお、項目によってはデータの入手できない国を除外したものがあります。
評価は10点満点で行い、項目毎に評価の対象となる数値(評価数値)を算出した上で、最も評価数値の良い調査対象国を10点とします。項目によって評価数値が最も大きい国が10点になる場合と、最も小さい国が10点になる場合があります。
【第113-1-2】「エネルギー白書2010」におけるエネルギー安全保障の定量評価指標
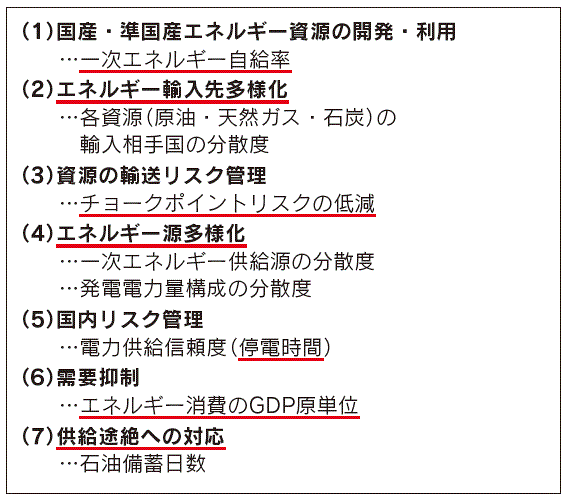
他の国の点数は、その国の評価数値を、最も評価数値の良い国と比較して算出します。評価数値が大きい方が良い評価となる場合と、小さい方が良い評価となる場合とで算出の仕方が異なりますので、例を挙げながら説明します。
【第113-2-1】点数化の方法(評価数値が大きいほど良い評価となる項目)
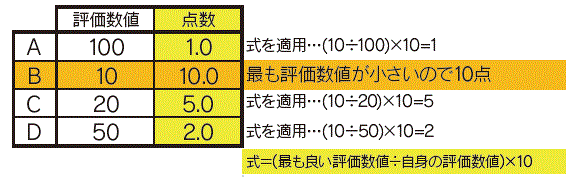
評価数値が大きい方が良い評価となる場合、上の表の中で評価数値が最も大きいAが10点となります。Bの評価数値は10で、最も大きいAの評価数値100と比べると、10分の1となります。これにより、Bの評価はAの10分の1となります。Aの点数は10点なので、Bの点数はその10分の1の1点となります。
これを数式にすると、「(自身の評価数値÷最も良い評価数値)×10」となります。C、Dについても、この式を用いると、それぞれ2点、5点が点数となります。
【第113-2-2】点数化の方法(評価数値が小さいほど良い評価となる項目)
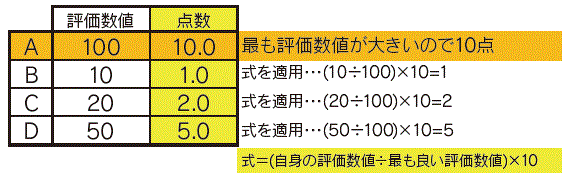
上の表のA ~ Dの評価数値は【第113-2-1】と全く同じですが、評価数値が小さい方が良い評価となる場合には、Bが10点となります。Aの評価数値は100で、最も小さいBの評価数値10と比べると、10倍となります。これはAがBの10倍評価が低いということになるので、Aの評価はBの10分の1と考えます。Bの点数は10点なので、Aの点数はその10分の1の1点となります。
これを数式にすると、「(最も良い評価数値÷自身の評価数値)×10」となります。C、Dについても、この式を用いると、それぞれ5点、2点が点数となります。
この手法に基づき、各項目につき調査対象国の直近での定量評価・点数化を行い、2000年代(「エネ白2010」における)の点数との比較により、その変化の要因を分析します。
3.各要素における評価と分析
(1)一次エネルギー自給率
本項では、国際エネルギー機関(IEA)が公表する各国の一次エネルギー自給率を評価数値として点数化しています。自給率が高いほどエネルギーを安全に確保しやすいことから、自給率が高いほど良い評価となります(なお、IEAは原子力を「準国産エネルギー」と位置付け、一次エネルギー自給率に含めています)。
調査対象国の2000年代(「エネ白2010」公表時)と直近の一次エネルギー自給率及び点数は以下のとおりです。
【第113-3-1】各国の一次エネルギー自給率と点数
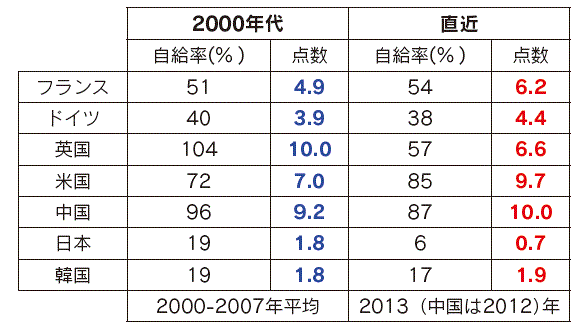
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECDCountries 2009、2014」を基に作成
直近では、中国が調査対象国の中では最も一次エネルギー自給率の高い国となりましたが、国内のエネルギー需要の急増により、自給率自体は2000年代に比べて低下しています。
2000年代と直近の点数を以下のグラフで比較すると、米国の大幅な上昇、英国の大幅な低下といった変化が見て取れます。
【第113-3-2】一次エネルギー自給率(点数)の変化
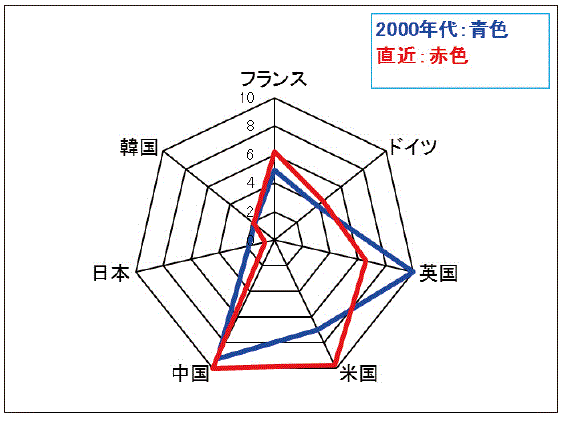
第1節で述べたとおり、米国では、天然ガスは2006年以降、原油は2009年以降増産を続けており、「シェール革命」が一次エネルギー自給率の上昇に大きく寄与したことがわかります。
英国では、2000年代初頭から北海油田に生産量の減衰傾向がみられ、2005年には一次エネルギー自給率が100%を割り込み、その後も下落傾向にあります。
2000年代には韓国とほぼ同じ点数だった日本は、2011年以降の原子力発電所の停止により一次エネルギー自給率が大幅に低下したため、直近では韓国と比べて1点以上低い評価となり、最下位になりました。
(2)エネルギー輸入先多様化
特定の国・地域へのエネルギー依存を低減させることは、エネルギー安全保障の強化に資すると考えられます。ただし、カントリーリスクの高い国・地域へ輸入先を分散していくことは、かえってリスクを高める可能性があります。
本項では、原油・天然ガス・石炭の3種のエネルギー源それぞれにつき、評価対象国における輸入先の寡占度を、経済協力開発機構(OECD)の輸出与信データによるカントリーリスクを加味した上で算出しています(通常の寡占度は各国の輸入シェア(%)の2乗を合計しますが、本項の寡占度はカントリーリスクの高い国の輸入シェアが実際より高くなるように調整しています)。
なお、2000年代と直近ではカントリーリスクが異なるので、その変化も反映されることになります。
【第113-3-3】主要産資源国のカントリーリスクとその変化
直近のカントリーリスク(7=リスク高、0=リスク低)
- ※
- 「エネ白2010」の寡占度算出時のカントリーリスクから変化のあった国は<>内に当時のカントリーリスクを記載
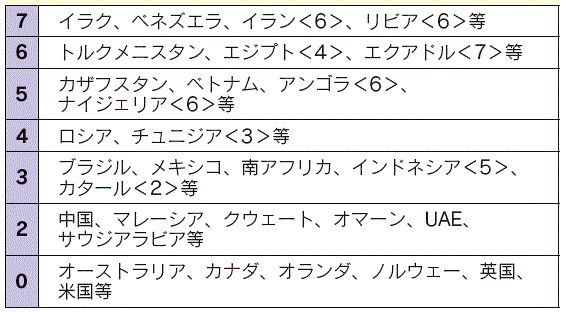
- (出典)
- OECD 「Country Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits(2009年9月23日現在、2015年1月30日現在)」を基に作成
ただし、寡占度が高いとしても、そのエネルギー源の消費量自体が少なければ、エネルギー安全保障への影響は少ないと考えられます。そこで、各エネルギー源の寡占度に、各国におけるそのエネルギー源の供給比率を乗じたものを評価数値としており、評価数値が低いほど良い評価となります。
なお、本項での「供給比率」とは、原油・天然ガス・石炭を合計した一次エネルギー供給量に占めるそれぞれのエネルギー源の供給量の割合のことであり、2000年代と直近では以下のように変化しています。
【第113-3-4】各国の供給比率の変化
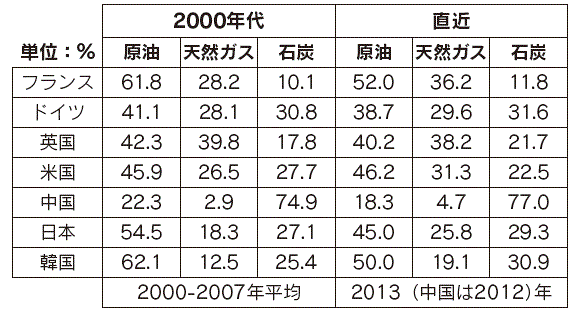
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」を基に作成
本項では、原油・天然ガス・石炭のそれぞれの輸入先多様化に関して、評価数値を10点満点で点数化し、その3つの点数を単純平均したものを最終的な点数としています。
2000年代(「エネ白2010」公表時)と直近のエネルギー輸入先多様化に関する点数の表・グラフは以下のとおりです。
【第113-3-5】各国のエネルギー輸入先多様化の点数
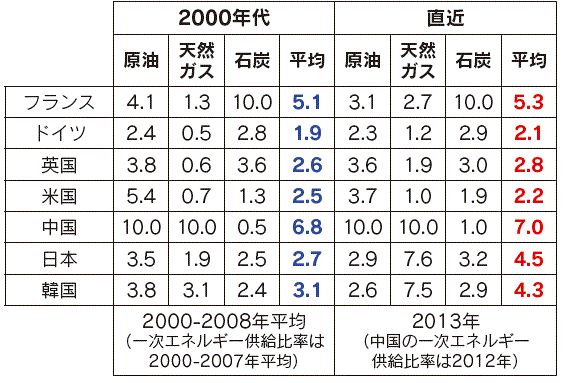
- (出典)
- IEA 「Oil Information 2009、2014」「Natural Gas Information 2009、2014」「Coal Information2009、 2014」、中国輸入統計等を基に作成
【第113-3-6】エネルギー輸入先多様化(点数)の変化
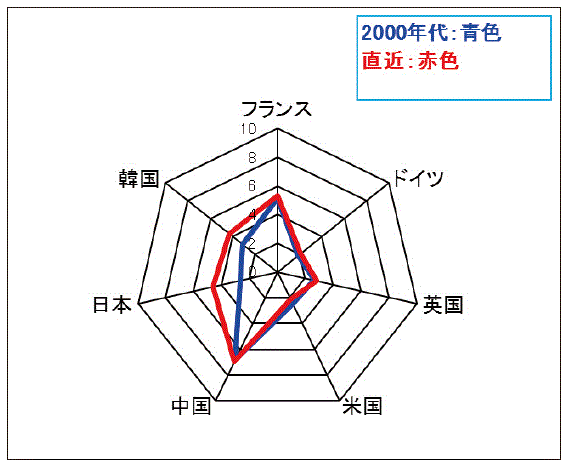
2000年代も直近も、最も点数が高いのは中国で、日本と韓国の点数が大きく上がっています。詳細については、エネルギー源ごとに分析していきます。
①原油
【第113-3-7】エネルギー輸入先多様化(原油評価詳細)
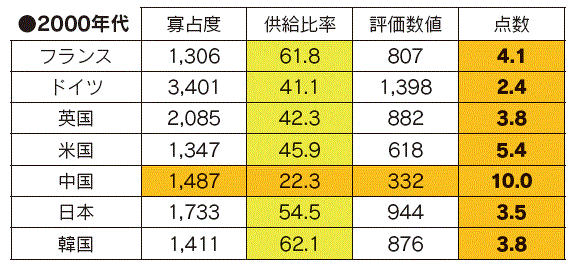
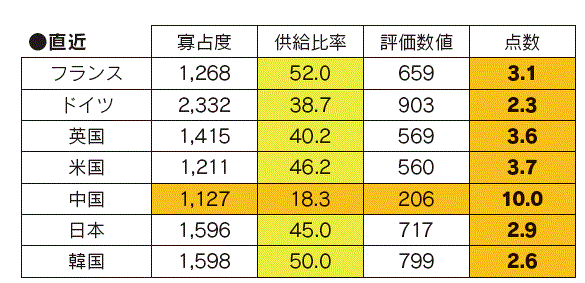
- (出典)
- IEA 「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」「Oil Information 2009、2014」、中国輸入統計等を基に作成
原油輸入に関する寡占度が、2000年代よりも直近の方が高くなったのは韓国だけでした。これは、カントリーリスクが最大レベルの「7」であるイラクからの輸入シェアの増加(2.0%→9.9%:「2000年代→直近」のカントリーリスクを加味しない実際のシェア。以下同様)が主な要因です。しかし、原油の供給比率の減少により、評価数値は減少しています。
2000年代も直近も、中国の評価数値が最良(最小値)となりました。直近では、カントリーリスクが最大レベルの「7」となったイランからの輸入シェアの減少(12.4%→7.6%)により、中東域内における輸入相手国の分散化が図られて寡占度が低下したことに加え、供給比率の減少により評価数値が大幅に減少しています。そのため、他国の直近の点数が総じて2000年代に比べて悪化するという結果になりました。
②天然ガス
【第113-3-8】エネルギー輸入先多様化(天然ガス評価詳細)
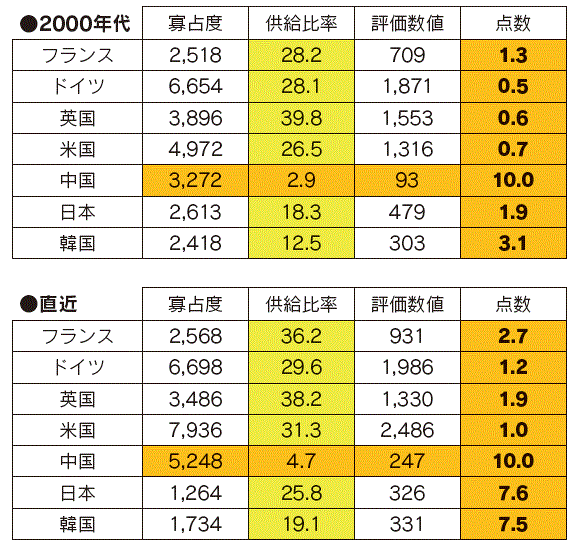
- (出典)
- IEA 「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」「Natural Gas Information 2009、2014」を基に作成
米国の寡占度、評価数値が大幅に増加していますが、これは「シェール革命」の影響で、天然ガスの輸入相手がほぼカナダに限られるようになった(88.3%→96.6%)ためです。したがって、形式的な評価と実質的な影響は、必ずしも一致するものとは言い難いと考えられます。
日本及び韓国は、インドネシアからの輸入減(日本:25.8%→7.5%、韓国:22.6%→14.2%)により分散化が進んだことなどから、寡占度が大きく低下しました。
原油同様、2000年代も直近も中国の評価数値が最良(最小値)となりましたが、カントリーリスクの高めなトルクメニスタンからの輸入開始(0%→52.5%)や、供給比率の増加により、直近の評価数値は大幅に増加しました。そのため、原油の場合とは逆に、米国も含めた他の全ての国の点数が相対的に良化し、評価数値を大きく減少させた日本と韓国の点数は7点台に達しました。
③石炭
【第113-3-9】エネルギー輸入先多様化(石炭評価詳細)
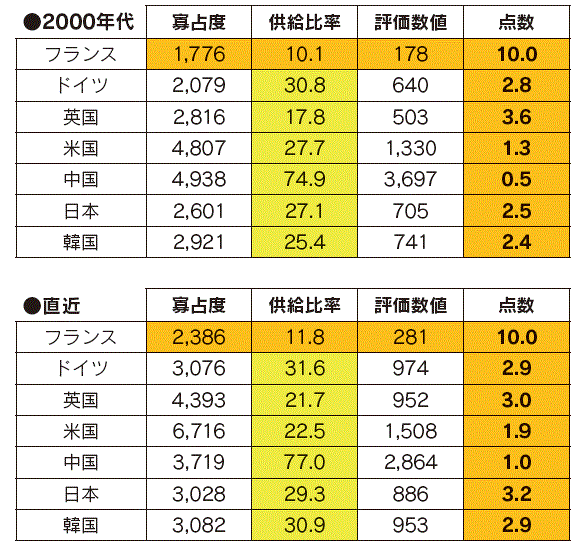
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」「 Coal Information 2009、2014」を基に作成
中国を除く全ての国で、2000年代に比べ直近の寡占度が上昇しています。欧州はロシアからの輸入シェアが増加したこと(フランス:4.1%→17.9%、ドイツ:13.9 % →23.5 %、英国:14.4 % →41.0 %)、米国は「シェール革命」の影響による石炭輸入の減少でコロンビアからの輸入シェアが増加したこと(66.4%→74.9%)、日本は石炭火力の需要増に伴いオーストラリアからの輸入シェアが増加したこと(59.1%→66.5%)、韓国は中国からの輸入減に伴いカントリーリスクのより高いインドネシアからの輸入シェアが増加(18.2%→47.4%)したことが主な要因です。
いずれの国でも寡占度だけでなく評価数値も上昇(悪化)する結果となりました。
中国はベトナムからの輸入減に伴い、カントリーリスクがより低いインドネシアからの輸入シェアが増加したことなどにより、2000年代は対象国中で最も高かった寡占度が直近では低下し、英国・米国よりも低くなりました。ただし、供給比率が依然として非常に高いため、評価数値は対象国の中で最悪(最大値)となっています。
2000年代も直近も評価数値が最良なのはフランスでしたが、直近の評価数値が悪化(上昇)しているため、評価数値が倍近くになった英国を除く他の5か国の点数は良化しています。
(3)チョークポイントリスクの低減
チョークポイントとは、物資輸送ルートとして広く使われている狭い海峡を指しますが、原油やLNGなど大量のエネルギー輸送に際しても利用されることから、その安全確保、あるいはそこに依存しない輸送ルートの確保はエネルギー安全保障にとって非常に重要な要素となります。
本項では、各国が輸入する原油が、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、バル・エル・マンデブ海峡(イエメンとアフリカ大陸の間にあり、紅海とアデン湾を隔てる海峡)及びスエズ運河の4つのチョークポイントを通過することをリスクととらえ、評価を試みます。
チョークポイントを通過する各国の輸入原油の数量を合計し、その総輸入量に対する割合をチョークポイント比率と定め、これを評価数値として点数化します。チョークポイントを複数回通過する場合は数量を都度計上するため、チョークポイント比率は100%を超えることもあります。
チョークポイント比率が低いほど、チョークポイントを通過せずに輸入できる原油が多いということになるため、良い評価となります。
2000年代(「エネ白2010」公表時)と直近の、各国のチョークポイント比率と点数に関する表・グラフはそれぞれ【第113-3-10】・【第113-3-12】のとおりです。
【第113-3-10】各国のチョークポイント比率と点数
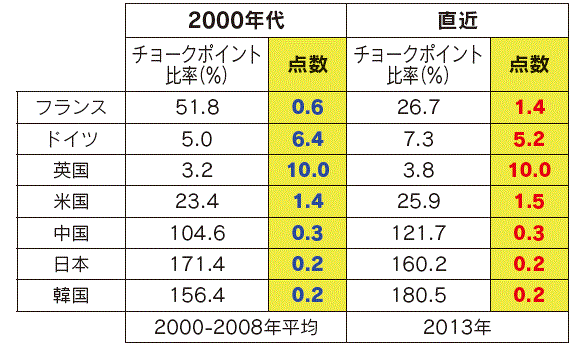
- (出典)
- IEA 「Oil Information 2009、2014」、中国輸入統計を基に作成
欧米の場合、チョークポイントを通過するのは、中東から輸入する原油にほぼ限られます。また、東アジア諸国の場合、輸入原油の大半はマラッカ海峡を通過しますが、中東から輸入する原油の大半はそれに加えホルムズ海峡を通過することになるため、リスクが増加します。
ここで、各国のチョークポイントリスクに大きな影響を与える、原油輸入における中東依存度の変化をみてみます。下の【第113-3-11】の太字は、直近の依存度が2000年代より高くなっていることを示しています。
【第113-3-11】各国の原油輸入における中東依存度とその変化
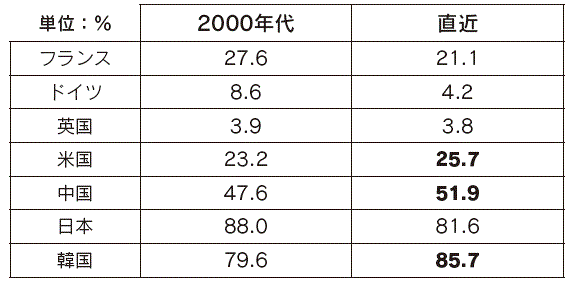
- (出典)
- IEA 「Oil Information 2009、2014」、中国輸入統計を基に作成
フランスの中東依存度の大幅な低下は、2012年に決定された、EUによるイラン原油禁輸が最大の要因です。2000年代には6.6%を記録していたイランからの原油輸入シェアが直近ではゼロになり、アフリカ原油への依存度が高まった(21.6%→34.4%)ことなどから、チョークポイント比率も大きく低下しています(イラン原油がホルムズ海峡、バル・エル・マンデブ海峡、スエズ運河の3つのチョークポイントを通過するものとして計算される一方、アフリカ原油はチョークポイントを通過しないため)。
米国の中東依存度がわずかに上昇している理由は、「シェール革命」と深い関連があります。第1節でも触れたとおり、米国内で増産されているシェールオイルは軽・中質油であり、従来ナイジェリアなどの西アフリカから輸入されていた原油に近い性状です。そのため、アフリカ原油への依存度は急落(18.7%→8.2%)しましたが、重質油が中心の中東原油はその影響を受けず、相対的に依存度が上昇する結果となったのです。
日本は依然として中東依存度が高いままですが、2009年にESPO(東シベリア・太平洋パイプライン)を経由した太平洋側からの原油出荷が可能になったことから、直近ではロシア産原油への依存度が高まり(1.3%→7.6%)、中東依存度及びチョークポイント比率は減少しています。この結果、調査対象国で最もチョークポイントリスクの高い国は、2000年代の日本に代わり、直近では韓国になりました。
しかしこうした変化は、評価数値が最良(最小値)となる英国のチョークポイント比率との差が大きいため、点数上に現れるには至っていません。
【第113-3-12】チョークポイントリスク低減(点数)の変化
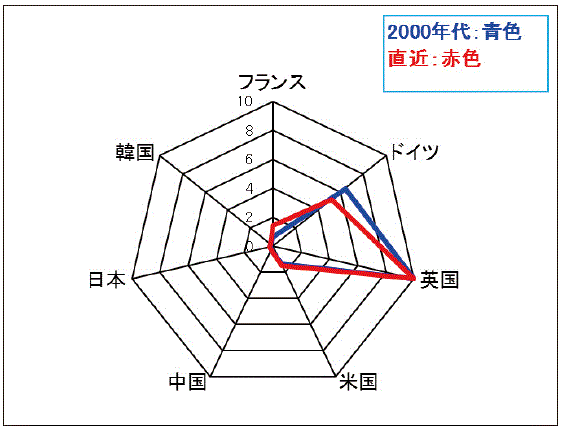
(4)エネルギー源多様化
特定のエネルギーへの依存を減らしてエネルギーのベストミックスを追求することは、エネルギー供給途絶リスクを低減し、エネルギー安全保障の強化に寄与することになります。各国は電源構成の多様化を推進することを中心に、エネルギー源多様化を図ってきました。
本項では、各国の「一次エネルギー供給量」及び「発電電力量」の2つのデータについて、エネルギー源を7種類(石炭、石油、天然ガス、原子力、水力、地熱・太陽光等新エネルギー、可燃性再生可能エネルギー)に区分し、データごとに各エネルギー源のシェア(% )の2乗を合計した値を寡占度として算出し、それを評価数値として点数化しています。寡占度が低いほど良い評価となります。
①一次エネルギー供給量
各国の2000年代(「エネ白2010」公表時)と直近の寡占度及び点数は以下のとおりです。
【第113-3-13】エネルギー源多様化(一次エネルギー供給量評価詳細)
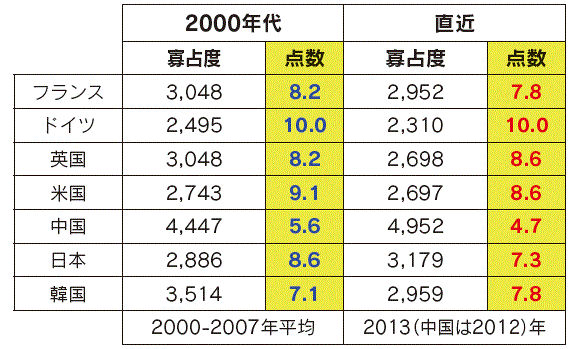
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」を基に作成
寡占度は、上位のシェアが高いほど、数値が大きくなる傾向にあります。各国の一次エネルギー供給量に占める割合が1 ~ 3位のエネルギー源とそのシェアの変化は以下のようになっています。
【第113-3-14】各国の一次エネルギー供給量の上位3エネルギー源とシェアの変化
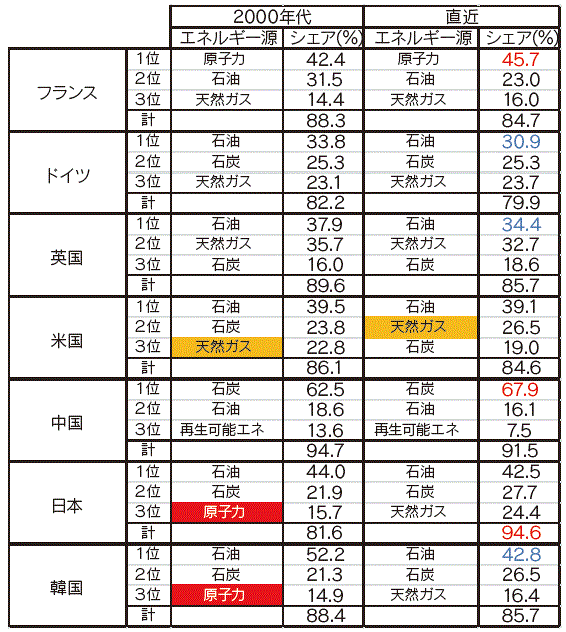
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」 を基に作成直近において、上位3エネルギー源のシェアの合計値が2000年代を上回ったのは日本だけでした。
これは、2000年代に第3位であった原子力のシェアが、2011年以降の原子力発電所の停止により直近では0.6%まで低下したことで寡占化が進んだものです。韓国の原子力も、直近では上位3エネルギー源からは姿を消していますが、第4位で12.4%のシェアを維持しており、分散化傾向は維持されています。
中国の上位3エネルギー源のシェアの合計値は、2000年代に比べ直近の方が低下していますが、第1位の石炭のシェアが5%以上増加しているため、寡占度は高まりました。
「シェール革命」が進む米国では、天然ガスが石炭に代わり第2位のシェアとなる一方、第1位である石油のシェアに大きな変動はありませんでした。
2000年代と直近のいずれでも、ドイツの評価数値が最良(最小値)となりました。直近では上位3エネルギー源のシェアの合計値も、第1位である石油のシェアも、2000年代に比べて低下しており、再生可能エネルギーのシェア拡大(3.8%→8.9%)によって、2000年代に比べさらに分散化が進んでいることがわかります。
そのためフランスや米国は、2000年代に比べ直近の寡占度を低下させたものの、点数は悪化することになりました。
②電源構成
各国の2000年代(「エネ白2010」公表時)と直近の寡占度及び点数は以下のとおりです。
【第113-3-15】エネルギー源多様化(電源構成評価詳細)
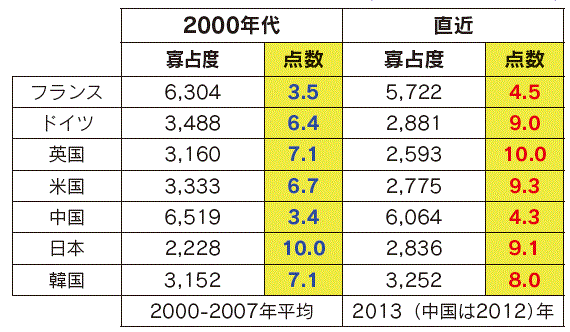
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」 を基に作成
こちらも、各国の電源構成に占める割合が1 ~ 3位のエネルギー源とそのシェアの変化をみることにします。
【第113-3-16】各国の電源構成の上位3エネルギー源とシェアの変化
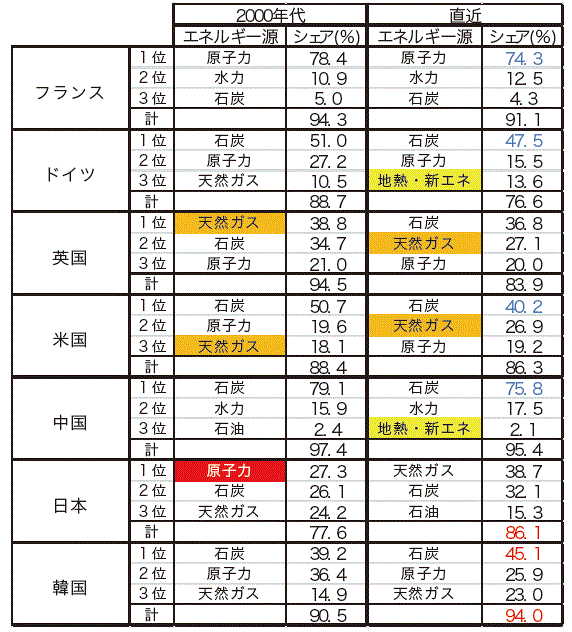
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」 を基に作成
直近において、上位3エネルギー源のシェアの合計値が2000年代を上回ったのは日本と韓国だけでした。その結果、両国のみが寡占度を高め、2000年代には最良だった日本の評価数値は、直近では英国・米国に次ぐ第3位となりました。
米国では、第1節で述べたとおり火力発電用の燃料が石炭から「シェール革命」によって増産されたシェールガスに置き換わっていることが、数字からも見て取れます。第1位である石炭のシェアを10.5%も低下させたことが、寡占度の大幅な低下と点数の大幅な上昇をもたらしました。
英国は国内の天然ガス生産量が減少し、2004年には輸入超過に転じたことから、直近の天然ガスのシェアが2000年代に比べて10.7%も低下しています。それに伴い、地熱・新エネルギーのシェアが上昇(0.6%→8.3%)するなど電源の分散化が進んだことから、直近の評価数値が最良(最小値)となりました。
ドイツは第1位である石炭のシェアが依然高いものの、直近で地熱・新エネルギーのシェアが第3位に上昇し、電源の分散化が進んだことが点数の上昇につながっています。
【第113-3-17】各国のエネルギー源多様化の点数
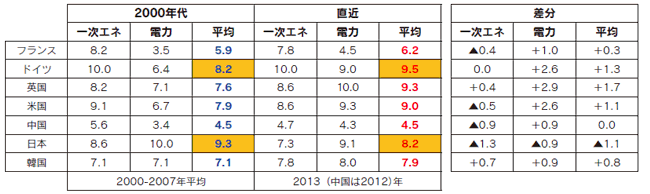
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」を基に作成
③平均(全体評価)
本項では、上記2つの点数を単純平均したものを最終的な点数としています。エネルギー源多様化に関する、各国の2000年代(「エネ白2010」公表時)と直近の最終的な点数の表・グラフはそれぞれ【第113-3-17】・【第113-3-18】のとおりとなりました。
2000年代には、「一次エネルギー供給量」及び「発電電力量」の多様化の点数を平均すると日本が第1位となっていましたが、原子力発電所の停止により一次エネルギー供給量も発電電力量も寡占化が進んだことから、直近の最終的な点数は第4位にまで後退することになりました。
【第113-3-18】エネルギー源多様化(点数)の変化
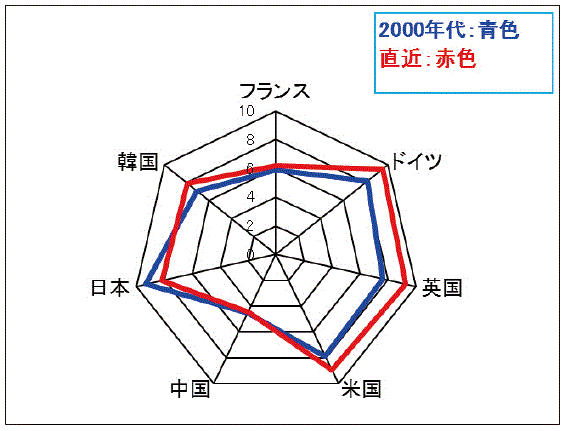
日本と中国を除く他の5か国は全て点数を上げており、様々な取組によってエネルギー源多様化を推進していることがわかります。
(5)停電時間
国内のエネルギー供給の安定度を測るには、電力、ガス、石油、石炭、再生可能エネルギー等の各エネルギーについて、国内における供給ネットワークが安定的に構築されているかを検証する必要がありますが、本項では、そのうちの電力を取り上げ、その供給信頼度を測る指標の一つとして、1世帯あたりの年間停電時間(停電が発生してから復旧するまでの時間)を評価数値として点数化します。評価数値が低いほど良い評価となります。
データの存在しない中国を除く評価対象6か国の、2000年代(「エネ白2010」公表時。ただし数値は一部修正あり)と直近の停電時間と点数の表・グラフは以下のとおりです。
「エネ白2010」でも言及しているとおり、停電は落雷や風雪害といった気象条件等を原因として発生することも多く、停電時間はそれらの自然条件に大きく左右されることになります。そのため、本項目に限り、直近のデータを1年間ではなく3年間の平均としています。
【第113-3-19】各国の停電時間と点数
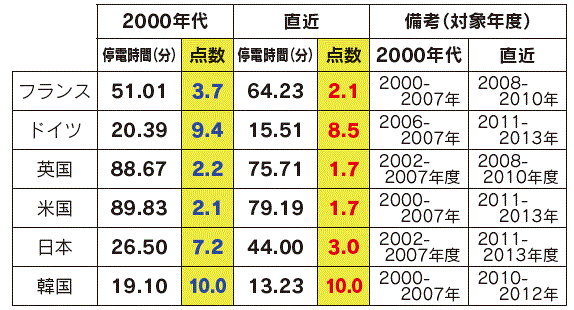
- (注)
- 「エネ白2010」では「海外電気事業統計2009」を出典として使用していたが、フランス・ドイツ・米国の統計については「海外電気事業統計2014」と原典資料が異なっている。2000年代と直近を同じデータを用いて比較することを最優先として、これら3か国の2000年代の値は「海外電気事業統計2014」をベースとしたものに修正している。
- (出典)
- 海外電力調査会「海外電気事業統計2009、2014」、電気事業連合会統計を基に作成
【第113-3-20】停電時間(点数)の変化
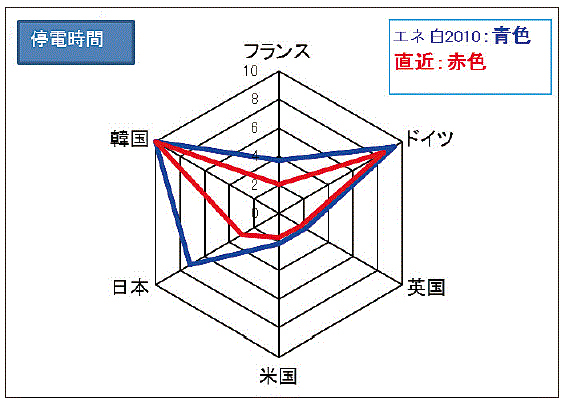
データの関係上、対象年度が国によって異なるため、各国の数値を単純に比較することはできません。また、気象条件等に大きく左右されるため、変化について分析するのは難しい項目です。
日本に関しては、東日本大震災直後の計画停電は上記のデータの対象外ですが(実際されたのが2011年3月であり、2010年度に含まれるため)、2000年代に比べ直近の停電時間が7割近く増加しており、点数を大きく下げることとなりました。
(6)エネルギー消費のGDP原単位
エネルギーの消費を抑制することも、確保する必要のあるエネルギー供給量を削減することにつながるため、エネルギー安全保障を強化するために必要な施策ということができます。しかし、現在の経済水準や生活水準を維持・向上させることとの両立を図ることが不可欠であり、単純にエネルギー消費量を減らすことを目指すのではなく、エネルギー消費器の効率改善、あるいは経済活動や生活におけるエネルギーの使い方の改善を図ることが重要です。
産業構造や気候等が異なる各国とのエネルギー効率の単純な比較は難しいですが、相対的な比較を示す1つの指標として、本項では、各国のGDPあたりの一次エネルギー消費量を評価数値として点数化します。GDPあたりの一次エネルギー消費量が低いほど良い評価となります。
出典となるIEAの統計では2012年より、実質GDPの基準が「2000年の米ドル」から「2005年の米ドル」に変更されています。同一条件のデータにより「変化」を確認することを最優先するため2000年代の数値については、「2000年の米ドル」をベースにした「エネ白2010」のものから、「2005年の米ドル」を基準にしたものに変更しています。この結果、為替影響から2000年代の数値は日本のみ低下し、評価数値が最小値の国が日本に代わり英国となりました。
【第113-3-21】2000年代のエネルギー消費のGDP原単位と点数(変更前後の比較)
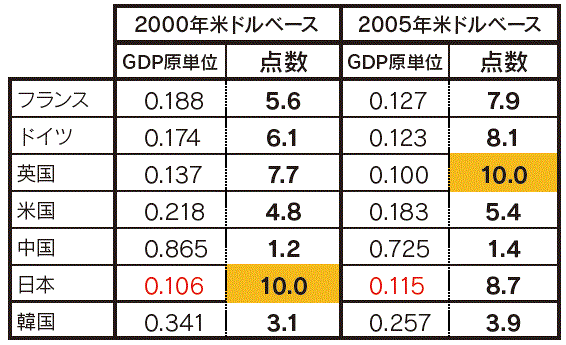
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2009、2014」を基に作成
2000年代(変更後)と直近のエネルギー消費のGDP原単位と点数の表・グラフは以下のとおりです。
【第113-3-22】各国のエネルギー消費のGDP原単位と点数
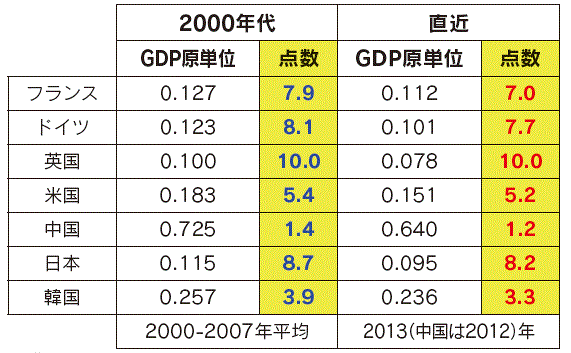
- (出典)
- IEA「Energy Balance of OECD Countries, Non-OECD Countries 2014」を基に作成
【第113-3-23】エネルギー消費のGDP原単位(点数)の変化
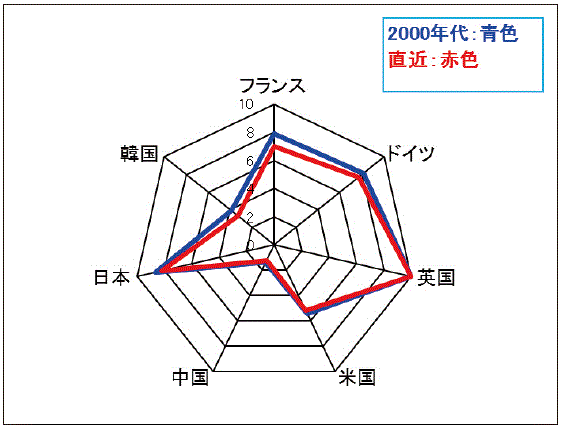
全ての国で2000年代より直近の評価数値が小さくなっておりますが、評価数値が最小値の英国が最も数値の低下が進んだため、相対的に他国の点数が低くなる結果となりました。
ここでは、評価数値の順位よりも低下率の大きな2か国の、2000年代と直近の間に開始された取組について紹介します
【第113-3-24】各国の直近のエネルギー消費と低下率の順位(GDP原単位あたり:2000年代比)
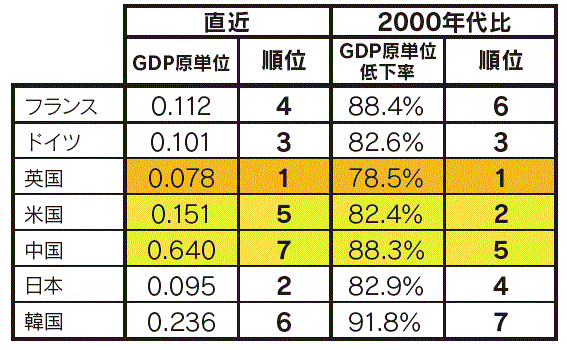
米国では2009年に、エネルギー・気候変動法案(「2009年米国クリーンエネルギー・安全保障法案」)が成立し、新築ビルのエネルギー消費を既存ビルの30%減とするといったビルに関する省エネ化をはじめ、照明・電化製品・運輸・産業部門での様々なエネルギー効率化プログラムが定められました。また、電力小売供給業者に対し義務づけた再生可能エネルギーの利用率の一部を、省エネルギーで補うことができるとしています。
近年の経済発展によりGDPが急拡大している中国は、2011年に策定した「第12次5か年計画」の中で、2015年度までにGDPあたりのエネルギー消費量を2010年対比で16%減少させるという目標を定め、「省エネルギー改造」「省エネルギー製品」「省エネルギー技術産業化モデル」「契約エネルギー管理普及」の4つの重点分野を掲げて、プロジェクトを推進することを定めています。
日本は従来から世界最高水準のエネルギー消費効率を維持し、さらなる改善を進めており、今後も各国とともにエネルギーの効率改善を継続していくことが期待されます。
(7)供給途絶への対応
エネルギー資源の供給が一時的に途絶した場合を想定した備蓄の存在は、エネルギー安全保障の強化において大きな対応力となります。
本項では、国際比較が可能な石油の陸上備蓄量をベースとして、仮に各国の最多輸入先(地域)からの原油供給が途絶した場合、その備蓄によって対応可能な日数を評価数値として点数化します。対応可能日数が多いほど良い評価となります。
2000年代と直近の供給途絶対応可能日数と点数の表・グラフは以下のとおりです。なお、「エネ白2010」では2000年代の備蓄量(中国を除く)について2000 ~ 2008年の各年末在庫の平均値を用いていますが、本白書では2000年代と直近の間の「変化」を最重要視していること、中国は2008年末の備蓄量の推定となっていることを踏まえ、各国とも2008年末の備蓄量を用いることとし、その他の数値についても適宜修正をしています。
【第113-3-25】各国の供給途絶対応可能日数と点数
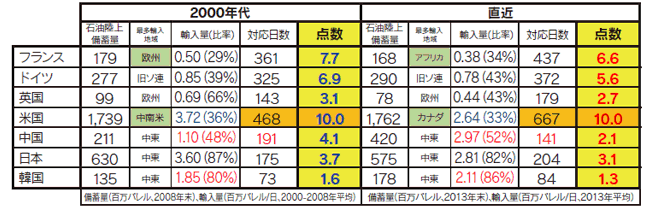
- (注)
- 中国の備蓄日数は業界誌等の情報に基づき推定、原油輸入地域については中国輸入統計を使用。
- (出典)
- IEA「Oil Market Report」「Oil Information 2014」
【第113-3-26】供給途絶対応可能日数(点数)の変化
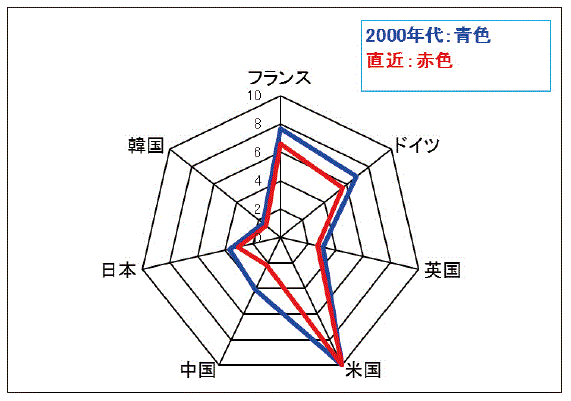
中国はOECD加盟国ではないためIEAの備蓄統計には記載がありませんが、2000年代に入り国家備蓄の整備を進めています。2008年に完成した第1期の国家備蓄基地(合計備蓄能力103百万バレル)について、同国の国家統計局は2014年11月、91百万バレルの原油が備蓄されていることを発表しました。また、第2期(合計備蓄能力191百万バレル)についても、2013年までに約38百万バレル分について完成済であり、他に国営石油会社(PetroChina、Sinopec)等の商業在庫約291百万バレルと合わせて、2013年末の段階で約420百万バレルの備蓄を確保しているとみられます。
「エネ白2010」時点での2008年末の推定備蓄量から倍増していますが、その間に最大の原油輸入先である中東からの輸入量が3倍近くに上昇しているため、供給途絶対応可能日数は、対象国で唯一減少する結果となりました。
2000年代に続き、直近でも米国の評価が最良(供給途絶対応日数が最多)となりました。直近では、2000年代に比べ199日も対応日数を増加させました。これは対象国中最多の増加日数であり、日数を増加させた他の5か国も、米国に対して相対的に評価されることになる点数については悪化するという結果を招いています。
米国の備蓄量自体はほぼ横ばいであり、「シェール革命」による原油輸入量の減少が結果に大きく貢献したことがわかります。なお、2000年代と比較して直近の原油輸入先にも大きな変化が起き、アフリカからの輸入が大幅に減少する一方、カナダからの輸入が倍増し、中南米を上回りました。
最多輸入地域が同一域内にあり、かつ陸上から原油が輸入されているという点は、他の対象国にはみられない特徴です。米国とカナダの長期にわたる友好関係も考慮すれば、供給途絶の可能性は極めて低く、数字以上の安定性を確保していると言えます。
【第113-3-27】米国の原油輸入地域の変化
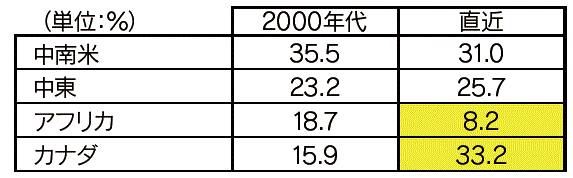
- (出典)
- IEA「Oil Information 2009、2014」を基に作成
英国は直近の備蓄量が2000年代より減少したものの、「シェール革命」の間接的な影響であるアフリカ原油の輸入量拡大が、欧州からの原油輸入量の低下をもたらし、供給途絶対応可能日数は増加する結果となりました。
フランスは、本節の「(3)チョークポイントリスクの低減」で述べたとおり、イラン原油禁輸による直近の中東依存度低下に伴い、直近ではアフリカからの原油輸入比率が34%に達し、2000年代の欧州に代わり最多輸入地域となりましたが、原油需要の減少に伴い輸入量自体が減少していることから、供給途絶対応可能日数は増加しました。ドイツも、最多輸入地域である旧ソ連からの直近の原油輸入比率は上昇していますが、輸入量は減少しており、直近の供給途絶対応可能日数は2000年代に比べ増加しています。
日本の備蓄量は、対象国の中では米国に次いで高い水準にありますが、中東依存度が直近でも8割を超えているため、供給途絶対応日数では低位に留まるのが現状です。
韓国は備蓄量を増加させていますが、日本以上に中東依存度が高く、輸入量自体も増加しているため、直近の供給途絶対応日数は対象国中最小の84日しかありませんでした。
(8)全項目平均(参考)
「エネ白2010」には存在しない切り口ですが、参考として、2000年代と直近の本節(1) ~ (7)の全項目の点数を国別に単純平均して比較した表・グラフを以下に示します。
【第113-3-28】各国の全項目平均点数
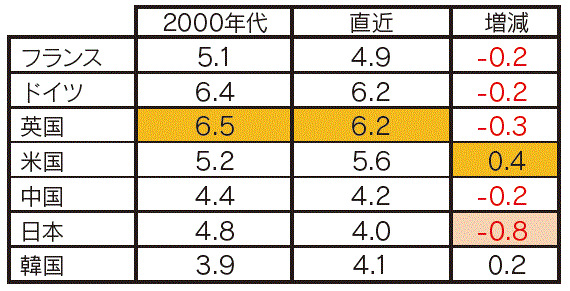
最高点は共に英国ですが、2000年代と直近を比較すると、「シェール革命」による一次エネルギー自給率の増加等により、米国が最も点数を上昇させました。一方、原子力発電所の停止などにより、日本の点数が最も減少し、対象国の中で最も低くなりました。
各国による、エネルギー安全保障の強化に向けた取組については、次節で国別に概観していきます。
【第113-3-29】全項目平均点数の変化