第1節 東京電力福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた取組等
1.東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策の体制強化について
地下貯水槽からの漏えい(2013年4月)、ボルト締め型タンクからの高濃度汚染水の漏えい(同年8月)など、急速に深刻化した汚染水問題について、根本的な解決が急務となり、同年9月、原子力災害対策本部において「東京電力㈱福島第一原子力発電所における汚染水問題に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を決定しました。
この基本方針では、汚染水問題の原因を根本的に断つ対策として、内外の技術や知見を結集し、政府が総力を挙げて対策を実施するための体制を整備しました。具体的には、①原子力災害対策本部の下に、内閣官房長官を議長、経済産業大臣を副議長とした「廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議」(以下「関係閣僚等会議」という。)を設置するとともに、現地における政府、東京電力等の連携と調整を強化するため、②現地に政府職員を常駐させることとし、「廃炉・汚染水対策現地事務所」を設置したほか、③現地における関係者の情報共有体制の強化と関係者間の調整を図る「汚染水対策現地調整会議」を設置しました。
また、2013年9月10日には、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策が喫緊の課題であることに鑑み、「2011年福島第一原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」の下に、「廃炉・汚染水対策チーム」を設置しました。
さらに、2013年12月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を踏まえ、「東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議」を、関係閣僚等会議に統合するとともに、関連する組織の整理を行うことで、廃炉・汚染水対策にかかる司令塔機能を一本化し、体制の強化が図られています。
30年から40年程度かかると見込まれる東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策については、国が前面に立って、より着実に廃炉を進められるよう、技術的観点から支援体制を強化する必要があります。このため、「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改組し、その業務に「事故炉の廃炉支援業務」を追加すること等を定めた「原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案」を2014年2月に通常国会に提出し、5月に成立しました。その後、同年8月の新機構発足以降、廃炉等に関し、研究開発の推進、専門技術的な助言・指導、情報提供等を通じ、福島第一原子力発電所の円滑な廃炉の実施に寄与しています。
2.中長期ロードマップ
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策については、関係省庁等において定めた「東京電力㈱福島第一原子力発電所1 ~ 4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(以下「中長期ロードマップ」という。)に基づき、取組が進められています。
この中長期ロードマップでは、廃止措置終了までの30年から40年の期間を3つに区分し、各期間の目標工程を設定しています。また、東京電力福島第一原子力発電所の状況や、廃炉に関する研究開発成果等を踏まえ、継続的に見直していくことを原則としており、2011年12月21日の初版の策定から随時改訂してきています。具体的には、2012年7月、2013年6月、2015年6月に改訂しています。
2015年6月の改訂のポイントは以下のとおりです。
- (1)リスク低減の重視:長期的にリスクが確実に下がるよう、優先順位をつけて対応
- (2)目標工程(マイルストーン)の明確化:地元の声に応え、今後数年間の目標を具体化
- (3)徹底した情報公開を通じた地元との信頼関係の強化等
- (4)作業員の被ばく線量の更なる低減・労働安全衛生管理体制の強化
- (5)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(廃炉技術戦略の司令塔)の強化
【第121-2-1】 中長期ロードマップ改訂のポイント
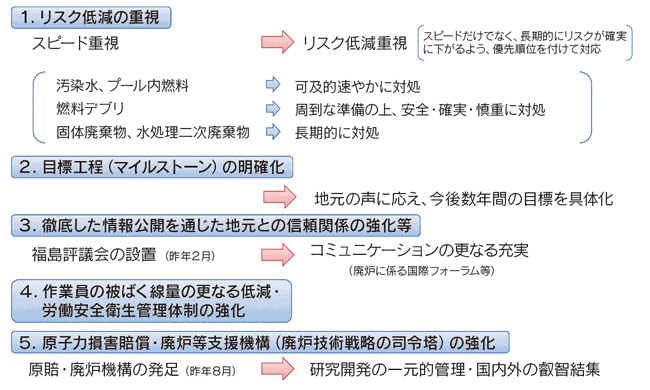
【第121-2-2】 目標工程(マイルストーン)の明確化
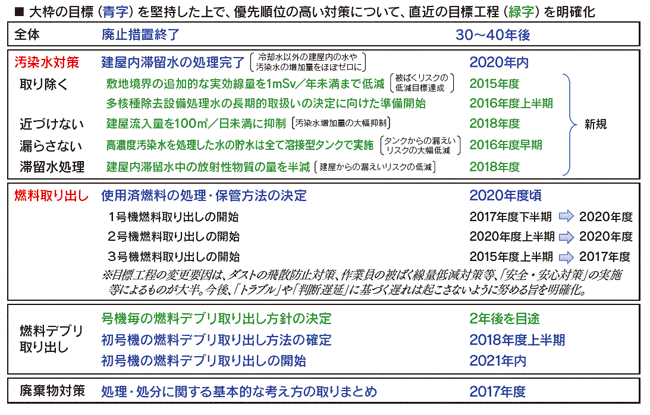
【第121-2-3】 東京電力福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ
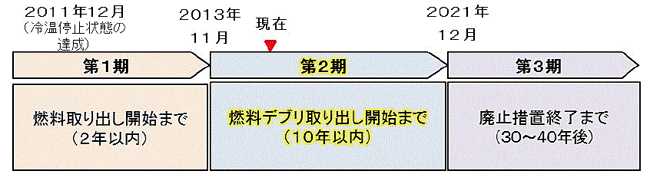
【第121-2-4】 使用済燃料プールからの燃料取り出しにおける工程見直し
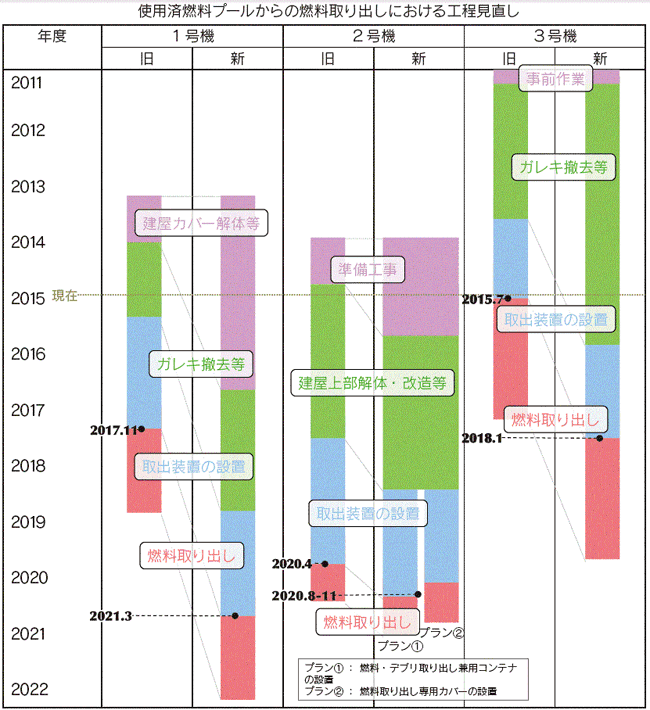
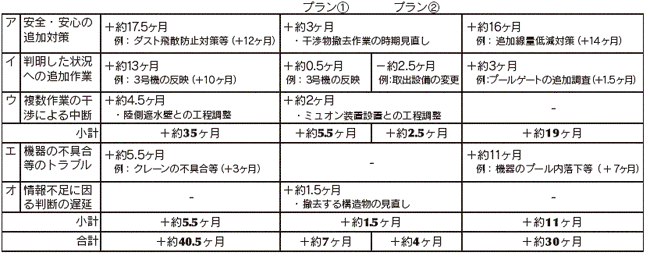
3.冷却・冷温停止状態の維持
1 ~ 3号機の原子炉には、注水冷却を継続しており、低温での安定状態を維持しています。原子炉の状態は、温度や放射性物質等の計測により監視を継続しています。
4.汚染水対策等
基本方針では、汚染水問題に関する3つの対策として、①汚染源を「取り除く」、②汚染源に水を「近づけない」、③汚染水を「漏らさない」という方針を定め、対策を講じていくこととしました。
具体的には、①汚染源を「取り除く」対策として、例えば、多核種除去設備(ALPS)による高濃度汚染水の浄化の加速化、国費を活用した、より高性能な多核種除去設備の開発などを進め、2014年10月より高濃度汚染水の浄化を開始しました。また、②汚染源に水を「近づけない」対策としては、例えば、汚染前の地下水を海に放出する地下水バイパスの稼働や、建屋周辺の井戸(サブドレン)からの地下水のくみ上げ、国費による凍土方式の陸側遮水壁の構築などの対策を進めることとしています。さらに、③汚染水を「漏らさない」対策としては、例えば、タービン建屋東側の海側における水ガラスによる地盤改良や、海側遮水壁の設置、タンクからの漏えいリスクを減らすため、ボルト締め型タンクのリプレースや、溶接型タンクの設置などを進めています。
また、基本方針で定められた内容を実現していくため、2013年9月に、技術的難易度が高く、国が前面に立って取り組む必要がある凍土方式の陸側遮水壁とより高性能な多核種除去設備の実現に対する2013年度予備費が閣議決定されました。
この他、具体的なアクションプランとして、国内外の叡智の活用の実施、予防的・重層的な取組の取りまとめ、現場目線での取組、国際的な情報発信の強化を実施することが、2013年9月に開催された関係閣僚等会議で取りまとめられました。これを踏まえ、国際廃炉研究開発組合(IRID)による汚染水対策に関する技術情報の公募が実施され(2013年9月から10月)、計780件の応募が寄せられました。うち約3割が海外からの応募でした。これらの応募内容を踏まえ、有識者から成る「汚染水処理対策委員会」において、地下水や雨水の挙動に関する技術的な検討結果や、汚染水が漏えいするリスクに関する分析・評価結果を盛り込んだ報告書が、同年12月に取りまとめられました。
この報告書を踏まえ、2013年12月に「東京電力㈱福島第一原子力発電所における廃炉・汚染水問題に対する追加対策」が原子力災害対策本部で決定されています。汚染水問題に対する予防的・重層的な追加対策として、溶接型タンク設置の加速化や2013年度補正予算を活用した技術的難易度が高いもの(港湾内の海水の浄化技術、土壌中の放射性物質の除去技術など)の技術検証などの取組を進めることを決めました。
また、大量貯蔵に伴うリスクが残存するトリチウム水の取扱いについても、同時期に、汚染水処理対策委員会の下に「トリチウム水タスクフォース」を設置し、あらゆる選択肢の総合的な評価を実施するとともに、トリチウムの分離技術についての検証試験事業の公募を実施し、技術検証を進めています。
2015年2月には、K排水路から比較的低濃度の放射性物質を含む水が外洋に流出していたことを受けて、同月末より、流出を抑制するための追加対策(浄化材の設置など)を実施しました。また、国も主体的に関与しながら、東京電力福島第一原子力発電所の敷地境界外に影響を与えるリスクの総点検を実施し、2015年4月28日に点検結果が公表されました。この結果、追加対策が必要なものについては、順次着手しており、適切にフォローアップを図っていきます。また、リスクは、廃炉作業の進捗に応じた環境の変化により、変化していくものであり、抽出されたリスクについては、この変化を適宜反映しながら継続的に管理するとともに、定期的に見直しを行います。
これらの取組を着実に進め、引き続き、予防的・重層的な汚染水問題への対応を進めていきます。
5.使用済燃料プールからの燃料取出し
当面の最優先課題とされていた4号機使用済燃料プールからの燃料取出しについては、2013年11月より取り出しを開始し、2014年12月に作業が完了しました(2014年12月22日に燃料1,533体全てを共用プールへ移送完了)。
また、3号機については、燃料取り出しに向けて2013年12月より、使用済燃料プール内のガレキ撤去作業が開始されています。1号機については、2014年10月から12月にかけて建屋カバーの屋根パネルを一時取り外し、内部調査を実施しました。2号機については、燃料取り出し工法について検討が進められています。
6.燃料デブリ取出し
燃料デブリのある1 ~ 3号機の原子炉建屋内は線量も高く、容易に人が近づける環境ではないため、遠隔操作機器・装置等による除染や調査を進めています。
その結果、例えば1号機では、2015年2月から5月にかけて、宇宙線ミュオンを利用して燃料デブリの所在を透視する装置が設置され、原子炉内部の状況が測定されました。この調査では、元々燃料が配置されていた炉心位置に、1mを超えるような大きい燃料の塊が確認できなかったことが報告されています。
また、2015年4月、格納容器内1階部分に初めて遠隔調査ロボットが投入され、内部の状況が計測・撮影されました。この調査では、次回調査で投入が計画されている、格納容器底部にある燃料デブリを直接見るための遠隔調査ロボットが1階部分から地下階に進入するための入口部分周辺に干渉物がないことを確認しております。
2号機では、2014年1月、遠隔調査ロボットによってサプレッションチェンバー内部の水位が測定されました。この測定により判明した、サプレッションチェンバー内外の水位差から、2号機のサプレッションチェンバーの漏えい開口面積は約10㎠と見積もられています。
3号機では、2014年1月、がれき撤去作業中の遠隔ロボットにより、1階の床面に流水が観測されました。分析の結果、流水は格納容器内部から出ているものと認められたため、3号機格納容器内の水位は、1階床面付近まであるものと推測されています。
また、2014年1月から4月にかけて、低所用除染装置の実証試験を、1号機及び2号機の原子炉建屋1階で実施し、遠隔操作による除染装置の有効性を確認しました。この他にも、原子炉格納容器の止水など、除染・調査以外の研究開発も進められています。
廃炉に関する技術基盤を確立するための拠点整備も進めており、遠隔操作機器・装置の開発・実証施設(モックアップ施設)については、2013年5月に楢葉南工業団地への立地が決定し、「楢葉遠隔技術開発センター」として2014年9月から建設工事に着工しました。
さらに、国内外の叡智を結集するため、2014年6月には、燃料デブリの取り出し工法や燃料デブリの切削技術等の検討について国際公募を実施し、同年10月には計11事業を採択し、検討が進められています。
7.作業要員確保
東京電力福島第一原子力発電所では、今後も引き続き、線量の高い環境下での作業が想定されています。このため、作業員の安全を確保しながら、長期にわたって要員を確保していくための取組が進められています。
具体的には、東京電力は、作業環境の改善に向けた線量低減対策として、除染の加速化による全面マスク省略エリアの拡大やガレキ撤去による作業性の向上が行われています。また、厚生施設等の改善として、事務所棟の拡充や大型休憩所、給食センターも設置しました。このほか、作業員の労務費割増分についての増額措置などが行われています。
こうした取組を通じて、作業の安全性の向上等、実施体制の強化に取り組んでいます。
8.コミュニケーションの充実
東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた取組は、周辺地域の住民の安心・安全に深く関わるものです。また、風評被害を払拭するという観点からも、国内外の叡智を結集して活用するという観点からも、国内外に対して正確な情報を発信し、また、国内外からのご意見を伺い、コミュニケーションを充実させることが重要です。
国際社会とのコミュニケーションとしては、例えば、2013年4月、11月及び2015年2月には、IAEAの専門家からなるレビューミッションを受け入れており、我が国の取組に対しての助言と評価を受けています。2015年2月には、IAEAレビューミッションからは、保管されている汚染水について、より持続可能な解決策が必要であり、トリチウムを含む水について、ステークホルダーとよく協議すべきとの助言を受けるとともに、東京電力福島第一原子力発電所の状況は、4号機からの燃料取り出しが完了するなど、多くの重要なタスクが完了しており、大きく改善しているとの評価を受けています。
また、周辺地域とのコミュニケーションの一環として、2014年2月に、廃炉・汚染水対策チーム事務局長をはじめ、関係省庁、周辺地域の首長や関係団体等を構成員とする廃炉・汚染水対策福島評議会を設置しました。これまで計7回(2015年4月9日時点)開催してきており、周辺地域の方々のご意見を踏まえつつ、廃炉・汚染水対策に係るコミュニケーションの強化等について取り組んでいます。