第2節 「シェール革命」時代の国際的なエネルギー動向の変化
本節では、「シェール革命」が米国以外のエネルギー動向にどのような変化をもたらしているか、また米国の「シェール革命」と同時期に他国のエネルギー動向には、どのような変化があったかについて概観していきます。
1.開発と生産
(1)シェール関連
①シェールガス
現時点では、米国エネルギー省情報局(EIA)によれば、世界のシェールガスの技術的に回収可能な資源量は約35,782兆立方フィートであり、国別でみると、中国が米国をわずかに上回り第1位となっています。
【第112-1-1】シェールガスの技術的に回収可能な資源量
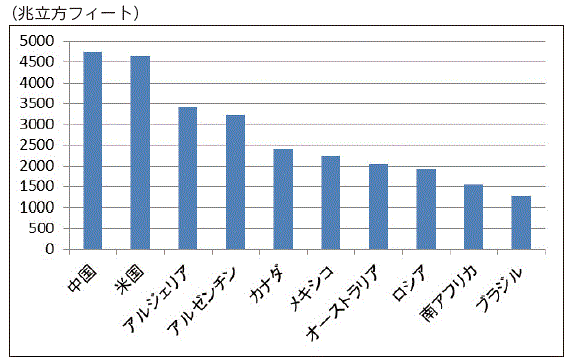
- (注)
- EIA資料では中東については調査されていない。
- (出典)
- EIA資料を基に作成
既に中国やカナダでは少量のシェールガス生産が行われており、アルジェリアなどでもシェールガス開発に向けた探査が実施されていますが、現在のところ米国以外で商業規模の生産は行われていない状況です。
②シェールオイル
米国エネルギー省情報局(EIA)によれば、世界のシェールオイルの技術的に回収可能な資源量は約6.8兆バレルであり、国別でみると、ロシアが米国を上回り第1位となっています。
【第112-1-2】シェールオイルの技術的に回収可能な資源量
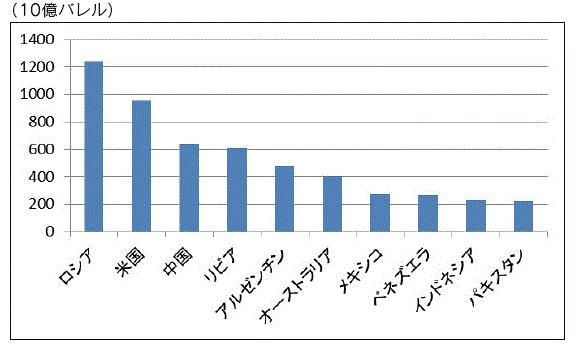
- (注)
- EIA資料では中東については調査されていない。
- (出典)
- EIA資料を基に作成
ロシアとアルゼンチンでは少量ながら、シェールオイルの生産が開始されていますが、商業規模での生産が現在行われているのは米国以外ではカナダだけです。
カナダでは、2005年から少量のシェールオイルの生産が開始され、2010年以降飛躍的に生産量を拡大しています。中心となるシェールオイル層は、米国とカナダの国境を挟んでノースダコタ州からサスカチェワン州に広がるバッケンと、アルバータ州に位置するカーディアムの2か所です。
しかし、米国側においてシェールオイルの大規模な生産量で知られる(100万バレル/日以上で現在も増加中)バッケンも、カナダ側では生産量の拡大は期待できないと見られており、既に2014年初めの生産量(約7.5万バレル/日)でピークを迎えたと考えられています。また、カーディアムも、2014年の初めの生産量(約10万バレル/日)がピークとされています。
そのためカナダにおいては、石油開発会社は、シェールオイルに対する多額の資本投資をやめ、後述するオイルサンドの開発に力を入れるという動きが出ています。
(2)その他化石燃料
米国の「シェール革命」と時期を同じくして、技術の発達や原油価格高騰により採算に見合うようになったことによる、シェール以外の非在来型の原油・ガスの開発・生産が各国で進められています。
カナダの2013年の原油生産量は約400万バレル/日であり、そのうち約半分がオイルサンドからの生産となっています。オイルサンドは、開発に大型の初期資本投資を必要とするものの、数十年間にわたり安定的に一定の生産量が見込めることから、国内外から資本が集まっています。
一方、オイルサンドの生産は、原油の抽出及びその後の精製段階で排出される汚染物質が原因で、米国とカナダ両国の環境保護団体からの強い反対にあっています。
ベネズエラの超重質油は、2010年頃から各種の石油関連統計で確認埋蔵量に加算されることとなり、これにより、同国はサウジアラビアに代わって世界最大の原油埋蔵国となりました。
ベネズエラ政府は2014年3月に、超重質油の生産量を6年間で200万バレル/日増加させる計画を発表しましたが、その後の国際的な原油価格下落等により、プロジェクトは難航しています。
このように、各国で開発が進められるようになった原油・ガスは、環境問題や原油価格下落の影響を受ける恐れがあるという点について、米国のシェールガス・シェールオイルと同様であるといえるでしょう。
【第112-1-3】各国で開発されている主な非在来型原油・ガス
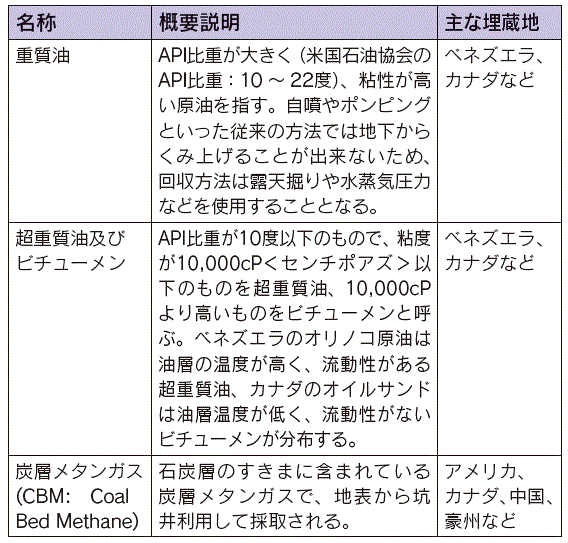
- (注)
- API:米国石油協会(American Petroleum Institute)が定めた原油および石油製品の比重を示す単位。「API比重」、「ボーメ度」とも云う。水と同じ比重を10度とし、数値が高いほうを軽質と定めている。通常の比重とは以下の式で換算できる。
API比重=(141.5/華氏60度の比重)-131.5
2.輸出入
(1)天然ガス輸出入動向の変化
「シェール革命」が現実のものとなる以前は、国際市場では米国のLNG輸入量は増加していくと考えられていました。ロシアに次ぐ天然ガスの輸出国であるカタールは、こうした見方を背景に、米国への輸出拡大を見込んで天然ガス開発を進めていましたが、「シェール革命」によって米国へのLNGの輸出機会を失うこととなり、欧州やアジア市場の開拓に動きました。
日本は、東日本大震災後に火力発電需要が大幅に増加したことに対し、カタールからのLNG輸入を迅速に拡大して対応することができました。また、欧州は、従来ガス市場に強い影響力を有していたロシアへの依存からの脱却を目指すようになっています。一方、ロシアは、こうした構造変化に対応すべく、アジア市場の開拓に乗り出しています。
このように、米国で始まった「シェール革命」は、国際的な資源の需給構造に大きな影響を与えていくことになります。
【第112-1-4】主な非在来型原油・ガスのイメージ図
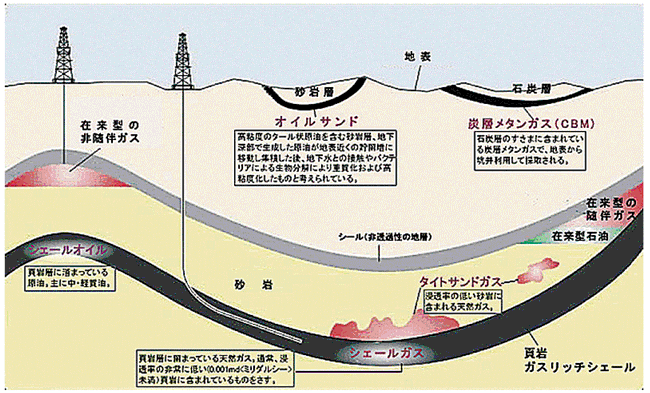
- (出典)
- EIA資料等を基に作成
【第112-2-1】カタールの天然ガス輸出先の変化(単位:百万立方メートル)
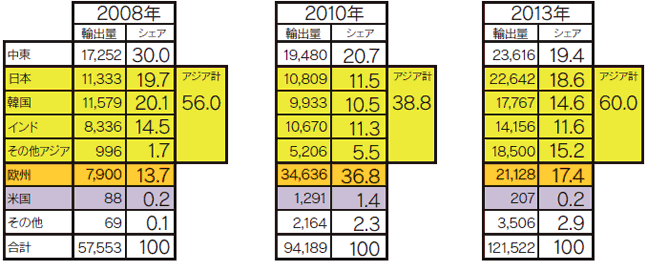
- (出典)
- IEA「Natural Gas Information」を基に作成
【第112-2-2】ロシアの天然ガス輸出先の変化(単位:百万立方メートル)
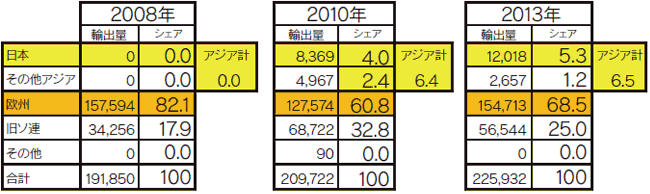
- (出典)
- IEA「Natural Gas Information」を基に作成
(2)カナダのLNG輸出計画
カナダのシェールガス開発は、まだ商業規模には至っていませんが、従来からの米国向けのパイプラインによる天然ガス輸出が、米国のシェールガス増産によって先細りしていく可能性が高いことを睨み、LNG輸出のためのターミナル建設計画に着手しています。今後、供給が開始されることが期待されます。
【第112-2-3】カナダの主なLNGプロジェクト

- (出典)
- NEB資料
3.需要
LNGの輸出拡大の動きを受けて、既に世界的に新たな展開が見えてきているのが、船舶に対する需要の拡大です。
(1)LNG運搬船の需要拡大
全世界で運行されるLNG運搬船の数は、現状では約400隻ですが、今後、新たに年約50隻の需要が生じると見込まれています。16万立方メートルクラスのLNG運搬船の価格は、現在1隻約240億円であり、相当数のLNG運搬船の新設は、非常に大きな規模のビジネスをもたらすことになります。
この結果、競争力のある日本の造船業に大きなチャンスが到来することが期待されます。LNGを液化した状態で貯蔵するためにマイナス約160℃の状態を維持する超低温技術など、LNG運搬船に関する日本の技術は世界トップレベルにあります。また、貯槽タンクや液化装置などの設備についても、日本メーカーのレベルは高く、多くの仕事を受注することが期待されます。
(2)LNG燃料船の需要拡大
重油を主燃料とする海上輸送は、温室効果ガス(GHG)排出の主要な原因の一つであり、世界のCO2排出量の約3%を占めています。この問題を解決するために、国際海事機関(IMO)は海洋汚染防止条約(マルポール条約)において、船舶からのCO2排出に関する規制を定めています。また、現在、バルト海や北海、北米周辺などでは、「大気汚染物質放出規制海域(ECA)」として、船舶用燃料油中の硫黄分濃度を規制しており、2015年からはその規制が強化されることになっています。
こうした排出ガス対策の一つとして、クリーンな燃料であるLNGが注目されています。すでにLNG運搬船等では、LNGは船舶用燃料として約40年の歴史を持っていますが、それ以外の船舶でも、現在約60隻のLNG燃料船が就航しています。特にノルウェーでは、政府による予算措置、補助金制度による経済的なインセンティブの付与により、急速にLNG燃料船の導入が進められています。
「シェール革命」による安価なLNGの出現により、重油より燃料費が3割近く抑えられることから、自動車運搬船などへのLNG燃料の適用も検討されています。
港湾におけるLNG供給のためのインフラ整備や船舶の建造コストの増加といった課題はありますが、ECA規制のさらなる強化などに伴い、LNG燃料船の需要は今後も増加していくと予測されています。
船舶用燃料としてのLNGの需要について、ノルウェー船舶協会は2020年に全世界で400 ~ 700万トン/年に達すると予測しています。一方、ケンブリッジ・エネルギー研究所(CERA)は、船舶用燃料としてのLNG需要は、2030年には全世界で6,500万トン/年まで拡大すると予測しています。