地産地消の先に描く「スマート半島」
鹿児島県肝属郡 | おおすみ半島スマートエネルギー株式会社
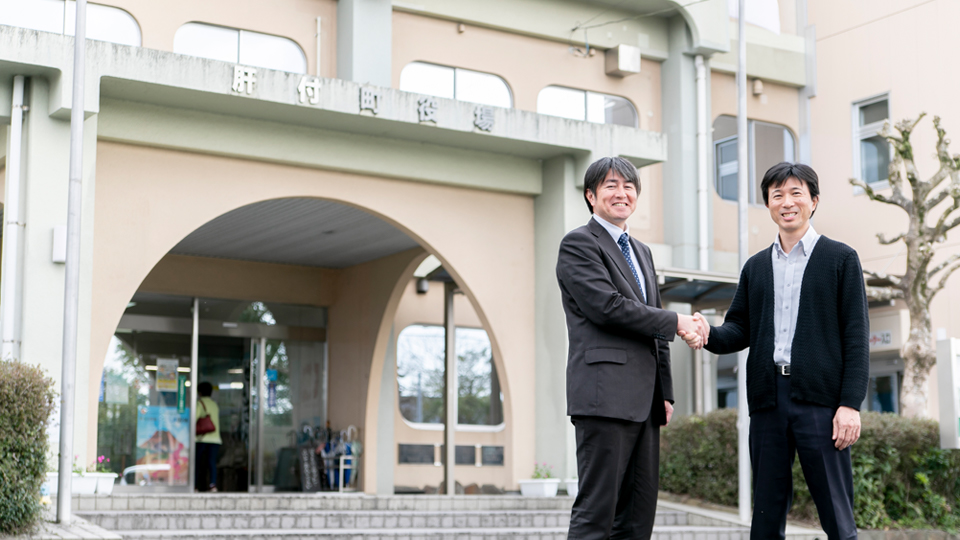
鹿児島県において南東に位置する大隅半島で、4市5町を巻き込んだ「広域圏での電力の地産地消」が動き始めている。先導するのは鹿児島県肝付町と同町の出資により新たに設立された電力事業、おおすみ半島スマートエネルギー株式会社である。目指すは、自ら電力をつくり、自ら稼ぎ、自ら問題を解決していく地域づくり。そして、その先にある「スマート半島構想」だ。
目指すはドイツの「シュタットベルケ」
鹿児島県肝付町の人口は約1万5000人、12世紀から続く伝統の流鏑馬(やぶさめ)と、国内に2カ所あるロケット発射場の一つ、内之浦宇宙空間観測所で知られるのどかな町だ。面積の8割を山林が占め、太平洋に面しているため通年で強い風が吹く。水力発電や風力発電に向いている土地柄を活かし、町内には多くの再生可能エネルギーの発電所が立地している。水力、風力、太陽光を合わせて50MWを超える発電規模 は、町で使用する電力を自給自足するのに十分だ。ただ、発電に適した自然環境という「資源」があるにも関わらず、現存の発電施設は県外の企業による運用であるため、町が得られる収益は固定資産税のみだった。


2017年1月、肝付町は再エネを活用した電力の地産地消で注目されている福岡県のみやまスマートエネルギー株式会社と共同で電力会社を設立。それがおおすみ半島スマートエネルギー株式会社だ。なぜパートナーに福岡の自治体新電力を選んだのか。みやま市は、エネルギー事業を地域の活性化に生かしているドイツの「シュタットベルケ」を標榜していた。肝付町が目指す姿も、まさに同じだったのである。
「シュタットベルケ」とは、エネルギー事業をメインに、地域交通の経営や、プール・図書館といった公共の施設の運営、福祉施設の運営といったさまざまな公共サービスや公益事業を提供している自治体出資の公営企業のことで、ドイツ国内に1000社以上が存在している。肝付町企画調整課課長補佐の西迫雄太氏は「官の手が回らない部分を民の力で補う。肝付町としてはそれを国内において先駆けて実践しているみやま市とみやまスマートエネルギーに強く共感しました」と話す。
ただ、肝付町だけでできることには限りがある。それは周辺の市町も同じで、過疎化、少子高齢化が進むなか、単体で対策を打っても効果は限定的だ。そこで、近隣の4市5町(鹿屋市、垂水市、志布志市、曽於市、肝付町、錦江町、南大隅町、東串良町、大崎町)で連携を取りながら課題解決に挑もうと考えた。4市5町の電力料金は年間約500億円になるが、これを地域内にとどめることができれば、経済が活性化するのではないか。発電量に余剰が出れば、都市部への売電も可能になる。社名に肝付ではなく「おおすみ半島」と入れたのは、電力会社の立ち上げをきっかけとして、大隅半島全域で地方創生を推進したいという強い意志の証だ。
発電所の開発で「マイクログリッド」を

数ある課題の中で、おおすみ半島スマートエネルギーが解決に向けて取り組んでいるのが防災だ。とくに肝付町は台風被害で毎年必ず一度は停電する地域である。「災害に強い町をエリア単位でつくるためのソリューションを発電で実現したい」と同社の代表取締役・村上博紀氏は語る。現在、太陽光発電を自社で建設し、蓄電池(EV)と組み合わせるプロジェクトを構想している。小規模・分散型の発電所で、発電量が地域の電力需要を上回れば蓄電池に充電し、電力需要が発電量を上回る時間帯に放電することで、電力需給バランスをコントロールする計画だ。
まさに小規模な発電施設を設置し、分散型電源を利用することで安定的に電力を供給する「マイクログリッド」を目指すものである。実現すれば、災害により広範囲に停電となった状況においても、導入しているエリアだけは停電を免れることが可能だ。「地元に電力会社があるメリットが一目瞭然です。そうした未来が自らの手で創り出せるということを住民の方々に伝える意味でも、発電所の開設は大切な意味を持つのです」(村上氏)。

役場では庁舎に導入した発電設備の「電気の見える化」がなされている
そう村上氏が言う背景には、これまで「地元の電力事業者が存在することの意義」について住民に理解してもらうことが、簡単なことではなかったからだ。「地域新電力、自治体新電力って何?」「電力を地産地消して、何が変わるの?」「大手企業じゃないと災害時に停電するのでは?」と、地域住民からはこうした声が寄せられる中、西迫氏は「様々な方法でPRを図ってきた」と語る。地域の会合や役員会に出向いて説明したほか、住民向けのセミナーの開催、パンフレットの作成などをすることで周知・理解促進に努めてきた。また、「現在はご近所の方々に再エネの普及、エネルギーの地産地消について説明してもらう推進員を募集しているところです。口コミの力に期待しています」(西迫氏)。

そうした地道な活動と並行して、「地域がどう変わるのか、未来の町の姿を、みんなで共有することが大切」と村上氏は考える。発電所を所有することで、「地域が良くなっていく」ということを、実感を持って理解してもらえることで期待が膨らむ。もちろん、経営面でもメリッットは大きい。発電所の開発は、自ら電力をつくり、自ら稼ぎ、自ら問題を解決していく町への大きな一歩なのだ。
大隅半島のスマート化へ
おおすみ半島スマートエネルギーは以前にも増して、どのように地域に利益を還元するのがベストなのか模索している。2020年度は事業から生まれた収益を使って学校に小規模な発電設備を導入し、ピークカット(電力消費を制御)に活用することを計画している。今後は、サイクルツーリズムが盛んな大隅半島で、観光地をめぐる電気自転車を利用者に貸し出し、サイクリングコースの途中に充電ポイントを設置する、という観光資源の活性化に向けた構想も始めている。電気自動車を使った集落への移動販売も実現可能なアイデアだ。
また、2019年10月から肝付町で運用が開始されたAIタクシーは、今はまだ自治体の予算により運用しているが、将来的にはおおすみ半島スマートエネルギーが運営主体となる展望もある。「『シュタットベルケ』のように交通や福祉、教育など、さまざまな分野におおすみ半島スマートエネルギーが関わり、地域においてリーダーシップを発揮できる企業へと成長していくのが理想です」と西迫氏は期待する。

この電力事業が軌道に乗った先に見据えるのは、「大隅半島のスマート化」だ。2020年1月に肝付町が発案した、4市5町が一丸となって取り組む「おおすみスマート半島構想」では、おおすみ半島スマートエネルギーを半島におけるエネルギー事業の中核を担う会社として位置づけ、豊富な再生可能エネルギーを活用した経済の活性化や地域課題の解決を明言している。低炭素地域の実現、産業育成、雇用創出、人口増、社会サービスの充実などさまざまな面での取り組みが挙げられるが、西迫氏は「最終的に各地域の特色にAIやIoT、ICTを組み合わせた町づくりを進め、半島全体をスマート化したい」と考えている。
たとえば高齢化率が40%に達した肝付町では、農業従事者の割合が多い。支えているのは、ほとんどが70~80代の高齢者だ。後継者は少なく、農業を縮小させないためには大規模化や承継が不可欠である。その農業において再エネやIoTを活用するのだ。バイオマス発電で出た液肥で作物をつくり 、発電の過程で発生する熱も作物の育成に利用。農場はIoTで管理する。今はまだ構想段階だが、実際に取り入れられれば、エネルギーを循環させる最先端の農業に若者が興味を持ち、後継として名乗りをあげてくれる可能性もある。
また、建設を計画しているバイオガス発電所 の電力を農業だけでなく、住居や公共の施設などに供給する。廃校をスモールオフィスにリノベーションした町は、リモートワークの拠点へと成長させる。そしてそれらの市町をAIタクシーやAIバスがつなぐのだ。蓄電池としても利用できる電気自動車を普及させ、買い物弱者が自動運転で自由に町を回遊できる――そんな地域ごとの良さを生かし、各地がネットワークでつながる未来。村上氏は「それらの施設や交通手段、住居に、おおすみ半島スマートエネルギーから生まれる再生可能エネルギーを活用したい」と力強く語る。半島全域が地域の電力会社を中心として一体となる社会。それが、おおすみ半島スマートエネルギーの思い描く世界だ。

肝付町企画調整課
西迫 雄太 (にしさこ ゆうた)

おおすみ半島スマートエネルギー株式会社
村上 博紀 (むらかみ ひろき)