- ホーム>
- 政策について>
- 省エネルギー・新エネルギー>
- 新エネルギー>
- なっとく!再生可能エネルギー>
- 取材レポート>
- 20230201 令和4年度「新エネ大賞」表彰式
再生可能エネルギー
再生可能エネルギー取材レポート 2022年度
令和4年度「新エネ大賞」表彰式
日時:令和5年2月1日(水)
会場:東京ビッグサイト
令和4年度「新エネ大賞」の受賞者の発表と表彰式が行われました。
「新エネ大賞」は平成8年に創設以来、新エネルギー等に係る機器の開発、設備等の導入、分散型エネルギーの活用および地域に根ざした導入の取り組みを広く公募。厳正、公正な審査の上、表彰を通じて新エネルギー等の普及促進に大きな役割を果たしてきました。
令和4年度「新エネ大賞」では11件の受賞者が表彰されました。
全ての受賞事例は、こちらで見ることができます。

一般財団法人新エネルギー財団 市川祐三会長
「事業者の皆さんの創意工夫の中から優秀な事例を発掘表彰し、社会に広く浸透させることが新エネ大賞の社会的役割と考えています」

経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長 井上博雄氏
「2050年のカーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギーの主力電力化を徹底、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促してまいります」

新エネ大賞審査委員会委員長 筑波大学 名誉教授 内山洋司氏
「今年度は商品・サービス部門は14件、導入活動部門は3件、分散型エネルギー先進モデル部門は12件、地域共生部門は7件、合計36件の応募がありました。審査委員会では、先進性、実績、将来性及び地域との共生など、総合的に評価しまして、ヒアリングや現地調査などを踏まえて最終審査を行いました。結果は、資源エネルギー庁長官賞が2件、新エネルギー財団会長賞が9件の合計11件となりました。残念ですが、経済産業大臣賞は該当なしでした。
応募は太陽光分野が全体の約五割以上をしめました。最近申請が増えているのはエネルギーマネージメントに関わる分野で約二割を示しています。全体としては幅広い分野からの応募が見られました。応募内容を見ますと、1社での優れた案件もありましたが、ほとんどが、導入される地域や地方自治体や関連機関等との共同で新たな事業を展開しての応募でした。受賞案件を見ると、いよいよ日本でも新エネルギーがビジネスとして成り立ってきたと感じます。最近の世論調査で主力電源の選択肢として新エネルギーが高く位置づけられました。追い風が吹くことで新エネルギーの技術開発は今後活発になると予想されます。
5月以降には新型コロナが2類から5類になり、国内の経済活動も活発になるでしょう。日本の優れた技術が海外に広く事業を展開して、日本の産業育成に役立っていくことが求められています。今年度、そういった案件がいろいろな形で出てきたということは、非常に期待できることだと思います」
資源エネルギー庁長官賞受賞(商品・サービス部門)
株式会社タクマ「階段炉下水汚泥焼却発電システム」

資源エネルギー庁長官賞受賞(商品・サービス部門)を受賞した、「株式会社タクマ」常務執行役員・前田さんと、水処理技術部長・芹澤さんにお話をうかがいました。
「製品開発を始めたのは10年ほど前です。私どもは色々なものを燃やして、そこからボイラーで蒸気を作って発電をするという製品を作っています。それを、燃えにくくて発電するのが難しかった汚泥でも実現したい、うまくシステムを改良することで発電ができるのではないかと、国交省の実証事業に応募して採択されました。実証事業では従来よりも水分を下げることのできる特別な脱水機を使って、乾燥せず補助燃料もなしで汚泥を燃やして発電できるシステムを開発しました。でも特別な脱水機はお客様が必ずしも持っているとは限らないので、従来の脱水機であっても補助燃料を使わずに発電をやろうと。汚泥というのは下水処理をした結果出てくるものなので、私どもで性状はコントロールできないものです。水分やいろいろな成分が入っている汚泥を、いかに確実に乾燥させて発電できるシステムにするかが大変でした」(芹澤さん)
「私たちはボイラーメーカーなので、この燃料に適したボイラーの材質は何かなど1から開発しました。もともと発電のついてない汚泥焼却システムは納入していましたので、そこでいろいろな試験をしました。その準備期間にすごく時間がかかりましたね。エネルギーコストゼロまで実現できたので、もう少し消費電力を抑えたり、発電効率を上げていくことで、今度はエネルギーを供給する施設にも変わっていけます。今後も製品の価値を高めていきたいです」(前田さん)
「この賞をいただけたことでたくさんの皆さんに知っていただける、そのことが背中を押してもらえると思います」(芹澤さん)
資源エネルギー庁長官賞受賞(分散型新エネルギー先進モデル部門)
株式会社大林組「地熱を活用したグリーン水素サプライチェーン構築の取り組み」

資源エネルギー庁長官賞受賞(分散型エネルギー先進モデル部門)を受賞した、「株式会社大林組」常務執行役員・安藤さんにお話をうかがいました。
「このプロジェクトは2015年からスタートしました。もともと九州の離島で地熱発電の開発をしていたのですが、島民は100人ほどですから電気を多くは必要とはしていませんでした。資源はあるけれども電気にしても運べない。ならば、その電気で水素をつくる事業ができれば島は潤うのではないか、という発想がきっかけです。実はそこ、私のおばあちゃんの島で(笑)。その島で地熱発電を開発して、水素にして運ぼうと。ちょうど種子島の宇宙開発で水素燃料を使っているので、種子島に持っていくのも一つのアイデアだよね、とスタートしました。
地熱は山の中や離島にあるので、系統に繋ぎにくい場所も多いです。でも電気が繋げないところにこそ水素は向いてるんですよ。電気の場合、使う分と作る分をイコールにする必要があるので、多めに作っても無駄になってしまう。でも水素の場合、貯めて、運んで、燃やすこともできるし、燃料電池にも使える。エネルギーを無駄にしなくて済むんです。
ただ、水素を作るために再エネを使うというのにはジレンマもあります。我が社は、現在、事業として270メガほど再エネを持っていますが、では、それを使ってわざわざ水素にするか?ということです。再エネが十分にあれば良いのですが、現在の日本では足りていない。少ない再エネを、水素をつくるために使うのは現実的ではないです。
日本の地熱の資源量は世界3位なのですが、まだまだ活用度は低いです。国立公園内に多いことや、温泉の関係ですね。温泉地の方々はやはり不安に思われることがあると思うので、1箇所に10年ぐらいかけてご説明し、ご納得いただく。何かあれば停めます、補償もしますとお約束をして地域のご理解とご協力を得ながら共生できるように開発を進めているところもあります。
今回の受賞を機に、より一層、水素事業を前進させるとともにカーボンニュートラルの実現に貢献していきたいと思います」(安藤さん)
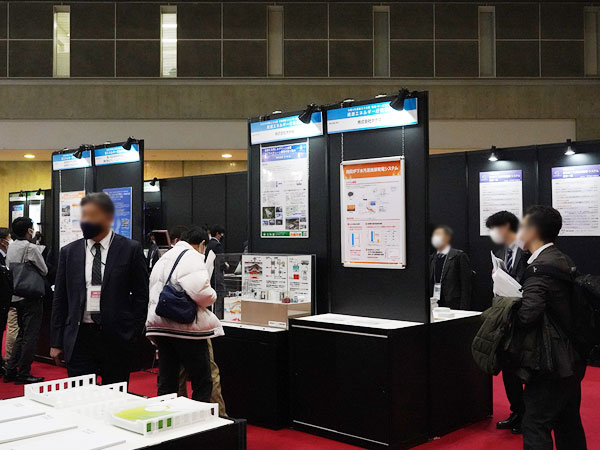
各受賞事例を熱心に見る来場者の方々が多くいました。
ビッグサイト東4ホールで開催された『ENEX2023 第47回地球環境とエネルギーの調和展』のアワードコーナーでは、各受賞者による製品、ビジネスモデル、サービス、事例が展示されました。
コロナ禍の昨年、一昨年も「新エネ大賞」自体は実施されましたが、表彰式は3年ぶりの開催となりました。
また、今回はプレスを集めての記者会見も初開催。資源エネルギー庁長官賞受賞の2組による概要説明も行われ、あらためて広く社会へ発信する好機となりました。
