- ホーム>
- 政策について>
- 省エネルギー・新エネルギー>
- 新エネルギー>
- なっとく!再生可能エネルギー>
- 取材レポート>
- 20200129 令和元年度「新エネ大賞」
再生可能エネルギー
再生可能エネルギー取材レポート 2019年度
令和元年度「新エネ大賞」が決まりました
日時:令和2年1月29日
東京ビッグサイト会議棟703会議室にて表彰式が行われました。
本年度は、経済産業大臣賞1件、資源ネルギー長長官賞1件、新エネルギー財団会長賞10件、審査委員長特別賞1件が選出されました。
地球環境とエネルギーの調和の展示会「ENEX2020」の会場内、アワードコーナーで、新エネ大賞の受賞内容をパネル展示しました。

東京ビッグサイト会場内の様子
「新エネ大賞」は、新エネルギーに関係する商品やサービス、導入促進、普及啓発活動など、新エネルギーに関連する案件を広く募り、優れた商品や活動を表彰するものです。これまで「商品・サービス部門」「導入活動部門」「普及啓発部門」の3部門を設けていましたが、本年度から「先進的ビジネスモデル部門」を新設。FIT制度によらない自立型の発電ビジネスも対象となりました。この中から、経済産業大臣賞、資源エネルギー長長官賞を受賞したプロジェクトの方にお話をうかがいました。
※各受賞事例一覧はこちら[外部サイト]
経済産業大臣賞
経済産業大臣賞を受賞したのは、『宮古島における「再エネサービスプロバイダ事業」の推進』。本年度から新設された「先進的ビジネス部門」から選ばれました。 株式会社ネクステムズ 比嘉直人さんにお話を伺いました。

株式会社ネクステムズ 比嘉直人さん
宮古島の発電設備は年間平均50%以下の稼働率
「宮古島は観光客がここ5年間で3倍増のため、新しい発電も取り入れようとしているのですが、実は発電設備は年間平均で50%以下ぐらいの利用率なのですよ。電気の需要のピークは夏場に観光客がホテルにチェックインしてからの夜7時から8時ぐらい。このピークに合わせて発電設備を入れていくと、稼働率50%以下の発電設備がどんどん増えていく。5年前に、これからIOTの時代がくると着想して、無線通信で家電をうまくコントロールして、ピークをうまく分散できないだろうかと考えました」
需要側がコントロールする電力供給の理想形を探して
「最初に、その制御の対照にしたのがエコキュート。電気で沸かす温水器です。これで制御コントロールして、しかも安く供給できるようにとプロジェクトを立ち上げました。最初の着想から今回の受賞まで3年ぐらいかかりました。電気の需要はこれまで勝手に動くものでしたが、直接的にコントロールできる家電が増えてそこに発電が合わされば、需要をコントロールできるのではないか。そのためにはどんな理想形があるのかを各所相談しながらの3年でした」
エネルギーという側面から宮古島を支えたい
「今回は市営住宅40棟ですが、今後はこれを契機に戸建て住宅に太陽光と蓄電池を広めていきたいと考えています。これまでも、サビの問題、台風強度の問題、生活スタイルなど、宮古島に合う設計で、性能を落とさずにコストはミニマムになるように工夫してきました。いま宮古島はバブルと言われていますが、バブルと表現されている時点で一過性のものですが、これが継続的なものになるように、我々もエネルギー面から下支えしていきます」
資源エネルギー庁長官賞
資源エネルギー庁長官賞を受賞したのは『「隠岐ハイブリッドプロジェクト」日本初の最新技術を活用した、地域一体での再エネ導入拡大』。導入活動部門での受賞です。中国電力株式会社森能隆さんにお話を伺いました。
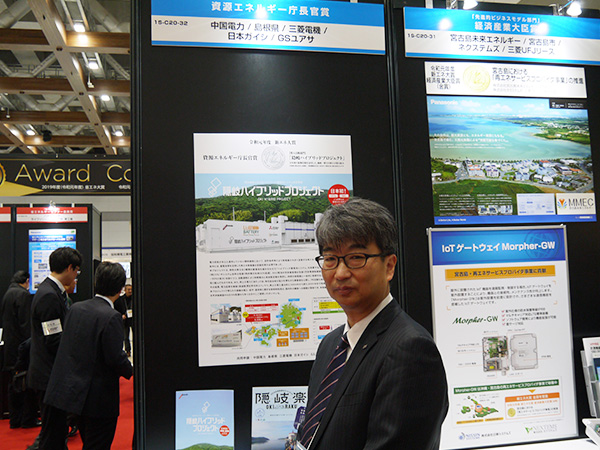
中国電力株式会社 森能隆さん
蓄電池の導入で離島の再エネ拡大を
「隠岐諸島は島根県から50~60kmも離れています。これまでも再エネ(風力・太陽光)を入れていましたが、これ以上増やすとなると電気の安定供給上で無理が出てしまいます。そこで、蓄電池を入れて再エネを拡大しよう、というのがそもそもの発想でした」
リチウム電池とNAS電池のハイブリッド蓄電池
「その中で、コストを安くして、安定供給できる蓄電池にするにはどうしたらいいかと、いろいろな組み合わせを考えました。結果的にリチウム電池とNAS電池の組み合わせたものが一番良いのではないかということで、今回のプロジェクトを立ち上げました。プロジェクトを立ち上げにあたって、再エネを募集するのに島根県さんのご協力によってスムーズに入ってもらえましたし、離島という供給力のない場所でこれだけの再エネを入れても制御できるか、蓄電池はどういう組み合わせがいいか、いかに安くできるかなど、メーカーさんにご協力いただきました」
蓄電池の広がりで自然由来の電気が増えていくように
「最初の発想から今回の受賞まで6年以上かかっているでしょうか。補助金事業に申請して通るまでに一山があり、工事に1年、実証期間が3年半、そのあと実際に制御できて安定供給ができるかと、いくつもの山をみんなで成果を出していこうとタッグを組んで乗り越えてきましたので、今回の受賞を聞いた時は感無量でした。成果が公に認められ、こういう賞があるというのは励みになります。今回の受賞を機に、自然と歴史の宝庫である隠岐諸島の良さを発信できるといいなと思います。それとともに、蓄電池が広がって自然由来の優しい電気が増えていくといいなと思っています」
経済産業大臣賞、資源エネルギー庁長官賞、ともに離島における発電・蓄電のプロジェクトでした。6千以上もの島が存在す日本はもとより、海外の小さな離島でも広く活用されうる取り組みです。
今回の受賞を機にプロジェクトの意義がより広く認識され、新エネルギーのあらたなビジネスモデルとして進化することに期待します。



