第2節 燃料アンモニアの導入拡大に向けた取組
アンモニアは天然ガスや再生可能エネルギー等から製造することが可能であり、燃焼してもCO2を排出しないため、温暖化対策の有効な燃料の一つとされています。さらに、アンモニアは、水素キャリアとしても活用でき、水素と比べ、既存インフラを活用することで、安価に製造・利用できることが特徴となっています(第382-1-1)。
【第382-1-1】燃料アンモニアの製造、輸送から利用
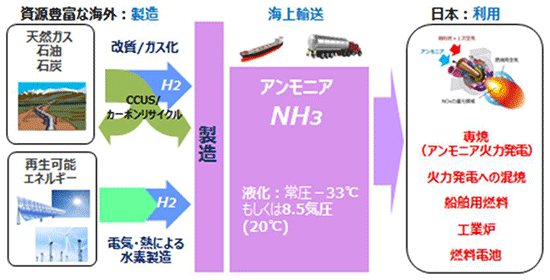
1.燃料アンモニアの発電分野での利用について
アンモニアは肥料等の用途で既に世界中で広く使われていることから、既存の製造・輸送・貯蔵技術を活用したインフラ整備が可能で、安全対策も確立されています。火力発電のボイラにアンモニアを混焼する場合にも、バーナー等を変えるだけで対応できるため、既存の設備を利用することができ、新たな整備や初期投資を最小限に抑えながらCO2排出を削減することができます。特に、アンモニアと石炭は混焼が容易であることから、まずは石炭火力発電への利用が見込まれています。
アンモニアの混焼技術については、2014〜2018年における内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)での研究開発において、燃料時における窒素酸化物(NOx)の排出抑制が可能となり、それを受けて経済産業省(新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))の支援の下、2021年度から、国内最大の火力発電会社である株式会社JERAが愛知県に保有する碧南火力発電所(100万kW)で20%アンモニア混焼の実証事業を実施しているところです(第382-1-2)。
【第382-1-2】石炭火力実機における20%アンモニア混焼の実証事業
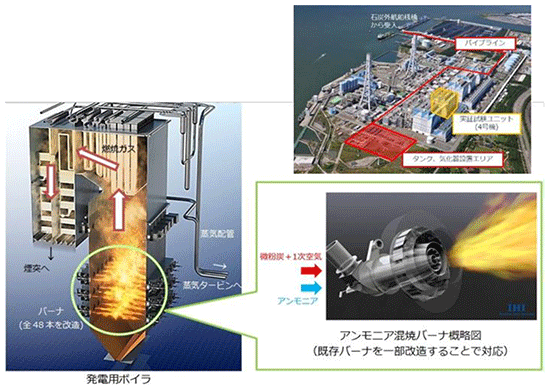
- (出典)
- JERAプレスリリース
他方で、アンモニアが燃料として使われるようになると、石炭火力1基(100万kW)の20%混焼で年間50万トンが必要となるために供給不足につながり、ひいては価格の高騰を招く恐れがあります。そのため、低廉かつ安定的な燃料アンモニアのサプライチェーンを構築する必要があります。
2.燃料アンモニアの利用促進に向けた政策的な取組
(1)2050年カーボンニュートラルを目指した燃料アンモニア政策の全体像
燃料アンモニア政策については、2020年10月の2050年カーボンニュートラル宣言を受けて、同月に燃料アンモニア導入官民協議会を設立し、官民が連携して燃料アンモニアのサプライチェーン構築に向けた課題の共有や導入に向けた道筋について議論を開始しました。こうした動きを踏まえて、2020年12月に公表され、2021年6月に更なる具体化がされた「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、燃料アンモニアは、水素とともに、同戦略の14の重要分野の一つに位置づけられました。
また、2022年3月に総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会の下にアンモニア等脱炭素燃料小委員会を開催し、アンモニアを既存燃料との値差や、燃料供給拠点の整備等の課題について議論しました。
ここで、燃料アンモニアの火力発電への活用については、2030年までに石炭火力への20%アンモニア混焼の導入・普及を目標に、実機を活用した混焼・専焼の実証を推進することで、2030年には国内需要として年間300万トン(水素換算で約50万トン)を想定し、そのために現在の天然ガス価格を下回る、N㎥-H2あたり10円台後半での供給を目指すこととしています。また、2050年には国内需要として年間3,000万トン(水素換算で約500万トン)を想定し、アンモニアの利用拡大に対応した更なる製造の大規模化、高効率化を追求した日本企業主導のサプライチェーンを構築することを目指しています(第382-2-1)。
【第382-2-1】水素・燃料アンモニア産業(燃料アンモニア)
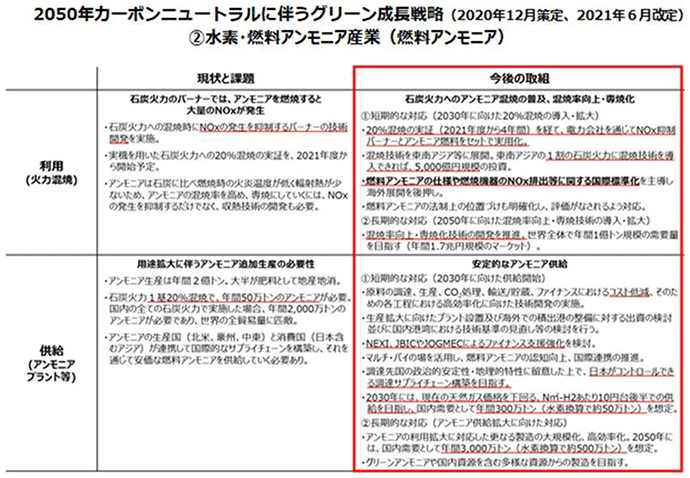
また、こうした動きを踏まえ、2021年10月に閣議決定された第六次「エネルギー基本計画」においては、2030年度の電源構成においてアンモニアが水素とともに明記され、水素・アンモニアで1%程度を賄うこととされました。
さらに、クリーンエネルギー戦略の検討においても、燃料アンモニアの導入・拡大に向けた具体策について議論されているところです。
(2)燃料アンモニアに係る技術開発
燃料アンモニアの大規模な需要の創出と安定的で安価な供給の実現に向けては、長期にわたる技術開発が不可欠です。そこで、2021年9月に、グリーンイノベーション基金事業の一つとして実施する、「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクトの研究開発・社会実装計画を策定しました。
本計画では、①低温・低圧でより高効率にブルーアンモニアを製造する技術や、再生可能エネルギーから水素を経由することなくグリーンアンモニアを製造する技術といった、アンモニアの供給コスト低減に必要な技術の開発、②石炭ボイラやガスタービンでのアンモニア高混焼・専焼技術の開発、を主な内容としています(第382-2-2)。
【第382-2-2】燃料アンモニアサプライチェーンの構築事業(概要)
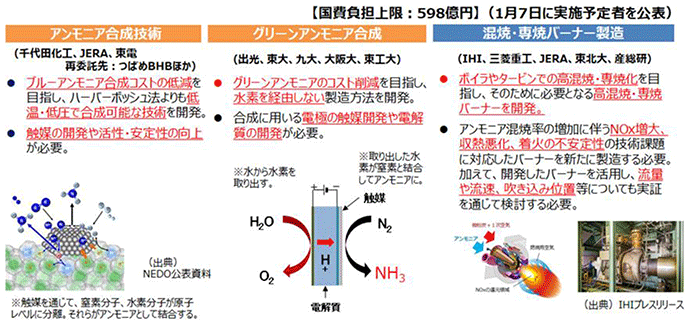
本計画を基に、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクトの公募を行い、本年1月に実施予定者を公表しました。本プロジェクトを通じてアンモニア製造の高効率化・低コスト化から利用拡大までの技術的な課題を解決し、需要と供給が一体となった燃料アンモニアサプライチェーンの構築を目指します。
グリーンイノベーション基金事業「燃料アンモニアのサプライチェーン構築」の事業内容
実施期間:2021年度〜2030年度(予定)
国費負担上限:598億円
【研究開発項目1】アンモニア供給コストの低減
研究開発内容(1)アンモニア製造新触媒の開発・実証
●燃料アンモニアサプライチェーン構築に係るアンモニア製造新触媒の開発・技術実証
燃料アンモニアの利用拡大に向けて、製造コストの低減を実現できるアンモニア製造新触媒をコアとする国産技術を開発します。
研究開発内容(2)グリーンアンモニア電解合成
●常温、常圧下グリーンアンモニア製造技術の開発
水と窒素を原料とした電解反応を活用し、常温常圧でアンモニアを製造する方法を開発します。
【研究開発項目2】アンモニアの発電利用における高混焼化・専焼化
研究開発内容(1)石炭ボイラにおけるアンモニア高混焼技術(専焼技術含む)の開発・実証
●事業用火力発電所におけるアンモニア高混焼化技術確立のための実機実証研究
アンモニアと微粉炭を同時に燃焼するアンモニア高混焼微粉炭バーナを新規開発し、事業用火力発電所においてアンモニア利用の社会実装に向けた技術実証を行います。
●アンモニア専焼バーナを活用した火力発電所における高混焼実機実証
アンモニア専焼バーナを開発し、事業用火力発電所において従来の微粉炭バーナと組み合わせ、アンモニア混焼率50%以上での実証運転を行います。
研究開発内容(2)ガスタービンにおけるアンモニア専焼技術の開発・実証
●アンモニア専焼ガスタービンの研究開発
ガスタービンコジェネレーションシステムからの温室効果ガスを削減するため、2メガワット級ガスタービンに向けた液体アンモニア専焼(100%)技術を開発します。
(3)新たなサプライチェーン構築に向けた取組
前述のとおり、燃料アンモニア導入拡大に向けては、その新たなサプライチェーン構築が不可欠です。そこで、燃料アンモニアの需要・供給両面での国際連携を進めるために、①燃料アンモニアの国際的認知向上のため、国際エネルギー機関(IEA)から分析レポート発行で連携、②燃料アンモニアの新たな供給確保のために、産ガス国や再生エネルギー適地国(北米・中東・豪州等)とサプライチェーン構築に向けた連携、③燃料アンモニアの海外での需要拡大のために、石炭火力利用国(マレーシアやモロッコ)とアンモニア発電可能性調査で連携、④燃料アンモニア国際会議を主催することで、日本主導で国際連携のプラットフォームを設立し、燃料アンモニアサプライチェーンの構築を主導する、という具体的な取組を進めています。
例えば、2021年1月に経済産業省とUAE・ADNOC(アブダビ国営石油会社)との間で、燃料アンモニア及びカーボンリサイクル分野における協力覚書を締結し、同年7月には同覚書に基づき、経産大臣立ち会いの下、INPEX、JERA、JOGMEC、ADNOCの4者が、アブダビにおけるブルーアンモニア生産事業の事業可能性調査(FS)開始に向け、JSA(共同調査契約)を締結しました。また、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)を通じて、複数の国との燃料アンモニアサプライチェーン構築に向けたFSを支援しています。
〈具体的な主要施策〉
1.カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発
(再掲 第5章第1節 参照)