第2節 ガスシステム改革及び熱供給システム改革の促進
1. ガスシステム改革の概要
2015年6月に成立した電気事業法等の一部を改正する等の法律に基づき、2017年4月1日にガス小売全面自由化等のガスシステム改革が実施されました。ガスシステム改革の実施に当たっては、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会(2013年11月から2016年6月にかけて33回開催)、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2016年10月から2017年2月にかけて2回開催)、産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会(2014年6月から2017年3月にかけて16回開催)、同小委員会ガスシステム改革保安対策ワーキンググループ(2015年7月から2016年5月にかけて6回開催)及び電力・ガス取引監視等委員会等において、随時議論がなされてきました。
ガスシステム改革は、1.天然ガスの安定供給の確保、2.ガス料金の最大限の抑制、3.利用メニューの多様化と事業機会の拡大、4.天然ガスの利用方法の拡大の主に4つを目的としており、2017年4月以降も、資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視等委員会のそれぞれにおいてさらなる市場活性化のための検討を進めています。
なお、2022年4月1日には大手ガス事業者の導管部門の法的分離等が予定されています。
2. ガスの小売全面自由化の進捗状況
(1)ガス小売事業者の登録
新規ガス小売事業者については、2016年8月の事前登録申請の受付開始から2021年3月末時点までに、88者が登録されました。ガス小売事業者の登録に当たっては、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会が、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当しないか等、法令に則りそれぞれ審査を行っています。なお、電気事業法等の一部を改正する等の法律の経過措置により、旧一般ガス事業者から203者、旧簡易ガス事業者から1174者が、ガス小売事業者となりました。
【第362-2-1】新規ガス小売事業者の登録状況
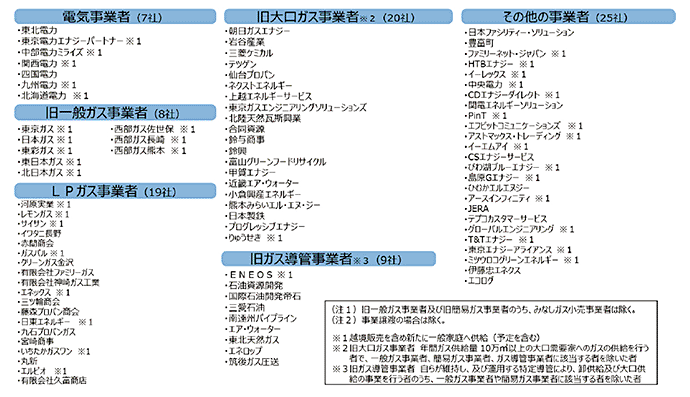
- 出典:
- 経済産業省作成
(2) スイッチング(契約先の切替え)件数及び新規参入者の販売シェア
ガスの小売全面自由化後から、一般家庭等での累計スイッチング申込件数は堅調に増加しており、2020年12月末時点で、全国で約366万件となっています。地域別でみると、近畿が最多となっています。スイッチング率は全国で14.3%です。なお、東北、中国・四国では2020年12月末時点でスイッチングの動きは見られていません(第362-2-2)。
また、家庭用の自社内スイッチング件数(累計)は、2020年12月末時点で、約148万件(全国)、スイッチング率は10.7%(全国)となっており(第362-2-3)、他社へのスイッチングと同様に増加しています。
新規参入者の全需要種に占めるガス販売量については、2020年12月末時点で全体の17.7%となっています。家庭用のガス販売量に占める新規参入者のシェアは全国で12.2%、最もスイッチングが進んでいる近畿地方では、17.4%となっています(第362-2-4)。
【第362-2-2】全国のスイッチング率の推移・申込件数
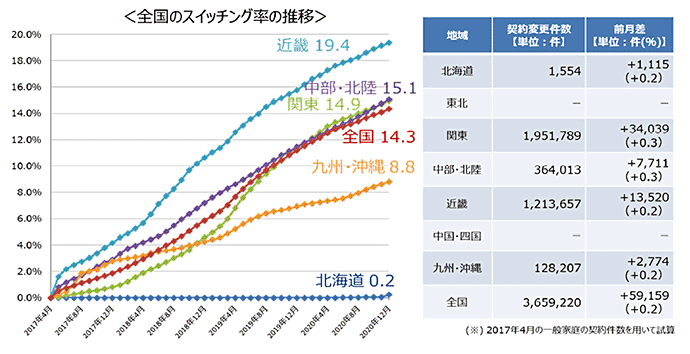
- 出典:
- 経済産業省作成
【第362-2-3】指定旧供給区域内における累計契約変更件数
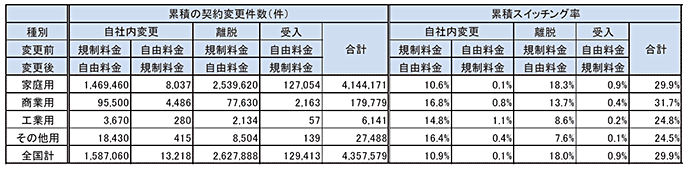
- 出典:
- ガス取引報(令和2年12月分)表14
【第362-2-4】新規小売のガス販売量(需要種・エリア別)
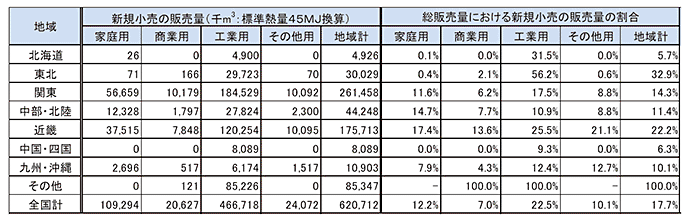
- 出典:
- ガス取引報(令和2年12月分)表3
(3)メニューの多様化
ガス小売全面自由化を契機に、全国各地のガス小売事業者が新たな料金・サービスメニューの提供に取り組んでおり、料金・サービスの多様化が進んでいます。各事業者が提案する新メニューでは、ガス料金の割引を行うもの、電力や通信といった他のサービスとのセット割引を行うもの、料金支払等に対しポイントを付与するもの、顧客の見守りサービスや、トラブル時の駆けつけなどの暮らしサービスを提供するもの、ガスの使用量や料金の見える化サービスを提供するもの、電力の買取サービスを提供するものといった類型が見られます。
【第362-2-5】ガス事業者のサービス向上に向けた新たな取組の類型表
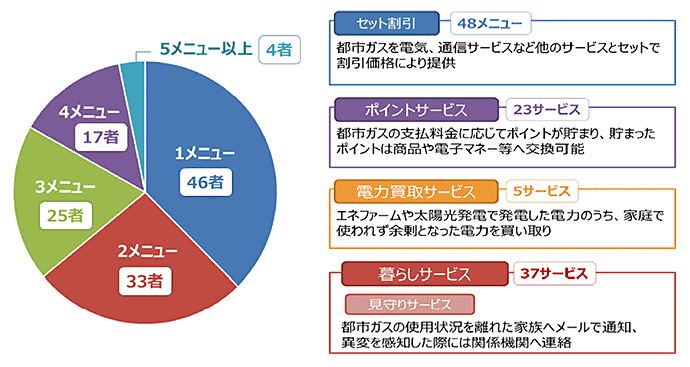
- 出典:
- 各社プレスリリース・HP等より経済産業省作成
(4)経過措置料金規制の対象地域の指定解除
ガス小売全面自由化に伴い、ガスの小売供給に関する料金規制は原則撤廃されましたが、LPガス、オール電化等を含め競争が不十分であると認められた供給区域及び供給地点については、需要家利益の保護の観点から経済産業大臣が指定を行い、経過措置として料金規制を継続しています。ただし、指定を受けた供給区域及び供給地点(以下、「指定旧供給区域等」という。)の競争状況は、経済産業大臣が3か月に一度の事業者報告により継続して把握し、競争が十分であると認められた供給区域については指定を解除することとしています。
ガス小売全面自由化に先駆けて、2016年11月には、ガスシステム改革小委員会等の議論を受けて策定された指定基準に基づき、旧一般ガス事業者の供給区域等のうち12区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点のうち1,730供給地点を「指定旧供給区域等」として指定しました。
その後、解除基準を満たした場合には解除を行い、2021年3月末現在において、旧一般ガス事業者の供給区域等のうち9区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点のうち1,020供給地点が指定されています。
また、料金規制を継続している供給区域の中でも、特に需要家数の大きい東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの供給区域について、2020年8月を期日として事業者から報告された内容を審査したところ、解除基準を数字上は充足する状況が確認されました。
料金規制解除するに当たっては、解除基準を満たしているかどうかに加え、適正な競争関係が確保されていると認められない事由がないかどうかもしっかりと確認しながら総合的に判断することとしており、上記3者の解除基準充足状況等について、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会で検討を開始し、規制を解除して差し支えないかどうか、電力・ガス取引監視等委員会に意見を聴取し、また、パブリックコメントも実施しながら議論を継続しています。
【第362-2-7】指定旧供給区域等一覧(旧一般ガス事業者の供給区域等)
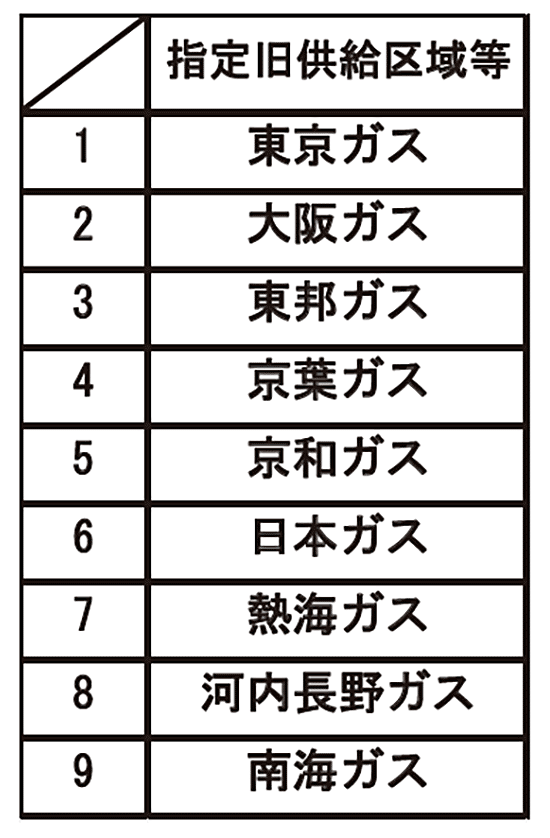
- 出典:
- 経済産業省作成
3. ガス事業制度検討ワーキンググループにおける議論
資源エネルギー庁は2018年9月に、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会の下に「ガス事業制度検討ワーキンググループ(以下、「ガスWG」という。)」を設置しました。ガスWGは、2017年4月のガス小売全面自由化の成果が一定程度見られる中、エネルギー基本計画や規制改革実施計画、一部継続検討課題とされていたテーマを踏まえつつ、ガスシステム改革のさらなる推進に向けてガス事業制度の在り方について専門的な見地から詳細な検討を進めることを目的としています。2020年度中にはガスWGを5回開催し、熱量バンド制、改正ガス事業法等の施行状況の検証、ガス卸供給(スタートアップ卸)の取組状況のフォローアップ、一括受ガスの是正方針等について議論が交わされました。
(1)熱量バンド制
一定の熱量範囲(バンド)に収まれば、熱量が多少変動しても導管への注入を認める仕組みである「熱量バンド制」の導入の適否について、現行の標準熱量制と比較しつつ標準熱量の引下げや小さいバンド幅の選択肢から優先的に取り上げ、検討を継続しました。
対策コスト・移行期間、都市ガスの2050年カーボンニュートラルを見据えた低炭素化効果、脱炭素化技術の進展状況・価格といった観点から、熱量バンド制及び標準熱量制のうちいずれの選択肢が最適か検討を行いました。
対策コストの試算結果によれば、熱量バンド制は標準熱量制に比べて対策コストが膨大となるため、現時点では熱量バンド制に比べて標準熱量の引下げがより適切な熱量制度とされました。
また、対策コストを抑制しつつ2050年カーボンニュートラルを確実に達成する観点から、移行期間は15 ~ 20年とすることとされました。
標準熱量制を採用する場合、引下げ後の標準熱量ごとに低炭素化効果を比較検討する必要があり、メタネーション(水素と二酸化炭素からメタンを合成する技術)による合成メタン等のカーボンニュートラルガスを増熱せずにガス導管に注入する場合、引下げる熱量幅が大きいほどカーボンニュートラルガスの注入量の増加により低炭素化効果を大きくすることが可能となり、小さい熱量の引下げ幅でカーボンニュートラルを達成するためには、合成メタンの技術開発に加え、LNG由来の都市ガスを燃焼させた際に生じる炭素の除去技術(ネガティブエミッション)の進展も前提とすることが必要となります。
標準熱量を40MJ/㎥とすれば、合成メタンを増熱せずに都市ガス導管に注入することでカーボンニュートラルガスを活用した2050年カーボンニュートラルを実現できる蓋然性を高めることができ、42MJ/㎥または43MJ/㎥に引き下げる場合と比べてコストが著しく大きくなることもないことから、現時点では40MJ/㎥へ標準熱量を引き下げることが合理的とされました。
ただし、標準熱量を40MJ/㎥とする場合、家庭用燃焼機器について安全上は問題なく使用することができるものの、製品品質(需要家の使用感)が変化しうると想定されることから、可能な限りコストを抑えつつ、製品品質を良好に維持するための対応を検討することが必要であるとされました。
標準熱量制(40MJ/㎥)へ移行することとしつつ、同時に、将来的に安定的かつ安価にカーボンニュートラルなガスの供給を可能とする技術の導入・拡大を可能とすべく、2050年カーボンニュートラルを実現するためのガス体エネルギーのポートフォリオの検討は継続的に行っていく必要がありますが、移行期間を15 ~ 20年とすることを踏まえ、現時点では2045 ~ 2050年に標準熱量の引下げを実施することとし、事前の検証を行った上で2030年に移行する最適な熱量制度を確定させることとし、カーボンニュートラルを実現する最適な熱量制度への移行を着実に進める観点から、ガスの低炭素化効果カーボンニュートラル化率)等の指標をもとにガスのカーボンニュートラルの達成状況を定期的に把握・検証するなどして、移行までの進捗状況を確認していくこととしました。
なお、合成メタンの供給可能量は水素、合成メタンといった脱炭素燃料の利用状況、CCUS等といった脱炭素化技術の進展状況に大きく左右されることから、移行する最適な熱量制度についてはエネルギー政策全体における都市ガス事業の位置づけや今後の技術開発動向、家庭用燃焼機器の対応状況等を踏まえ、必要に応じて2025年頃に検証を行うこととしました。
(2)改正ガス事業法等の施行状況の検証
2015年に成立した電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下、「改正法」という。)において、改正法第五条(小売市場の全面自由化)及び第六条(導管部門の法的分離)の規定による改正後のガス事業法の施行状況並びにエネルギー基本計画に基づく施策の実施状況及びガスの需給の状況、小売料金の水準等のガス事業を取り巻く状況に関する検証規定が設けられているため、それぞれの項目について検証を行いました。
改正後のガス事業法の施行状況については、自由化後の競争の進展状況や、利用メニューの多様化に向けた事業者の取組状況を確認しました。
エネルギー基本計画に基づく施策の実施状況については、大手ガス事業者の導管部門の法的分離に向けた準備状況の確認、天然ガスの利用形態の多角化の状況、船舶分野におけるLNGの主燃料化、天然ガスパイプラインの整備等、ガス取引の活性化に向けた施策、需要側の強靱化に資する分散型エネルギーシステムの構築、既存インフラを有効利用した脱炭素化のための技術開発、将来的なガスの脱炭素化に向けた水素関連等の技術開発について検証を行いました。
ガスの需給の状況については、国内都市ガス市場全体の需給状況について、自然災害の頻発・激甚化する昨今においても、大規模な供給支障や、需要に比して供給が極端にひっ迫する事態は特段生じていないことを確認しました。
具体的には、LNGの調達先は多角化されており、加えてLNGネットワークの多様化、トレーディングビジネスへの参画等により、調達安定性向上に取り組む事業者も存在します。
また、供給を担う導管ネットワークの強靱化に加え、需要先では分散型エネルギーシステムを導入するなど、都市ガス供給のサプライチェーンの各段階でレジリエンス強化に資する対策が行われていることを確認しました。
引き続き、ガスの安定供給・我が国のレジリエンスを確保する観点から、フォローアップを継続していきます。
小売料金の水準については、LNG輸入価格は2016年度以降上昇傾向にあるものの、ガス小売料金の水準は概ね横ばいであることを確認しました。
ガス小売全面自由化後、新規参入者の市場参入は着実に進んでおり、経過措置料金単価と新規参入者の小売料金単価を比較すると、総じて新規参入者の小売料金単価が安くなっています。
さらに、事業者の創意工夫により料金・サービスの多様化も進んでおり、例えば電気や通信サービスとのセット販売が行われるなど、需要家の選択肢が増えていることが伺えます。
引き続き、天然ガスの安定供給の確保、ガス料金の最大限の抑制、利用メニューの多様化や事業機会の拡大といったガスシステム改革の目的の実現に向けて、適正な競争環境の確保に留意しつつ、フォローアップを継続していきます。その他ガス事業を取り巻く状況の検証として、法的分離に向けた各種ルール(法的分離基準を定める政令、行為規制省令及び適正なガス取引についての指針)の整備状況及び法的分離に向けた一般ガス導管事業者各社における対応状況(システム対応等)について確認を行い、2022年4月の法的分離を円滑に実施するため、特にシステム構築(論理分割等)が予定通り進んでいるか、法的分離後もグループ一体でガスの安定供給を確保できる体制を確実に構築できているか、注視していくこととしました。
また、改正法において、導管部門の法的分離に当たってはLNGの調達並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとされているところ、法的分離に際してこれらの点にかかる支障が生じないか、あわせて検証しました。LNGの調達に関しては、電力会社において送配電分離に伴う格付への影響がなかったことを踏まえて、分社化に起因する各社の格付への影響やそれに伴う新規の調達金利上昇、国際的な市場でのLNG調達競争力の低下等について、現時点で具体的な懸念は示されなかった一方、保安の確保については法的分離に際して課される行為規制により的確な災害対応がとれなくなる懸念が表明されたため、各社が躊躇なく、迅速かつ的確に復旧活動に対応できるよう、必要な事項を「適正なガス取引に関する指針」上で明確化することとしました。
(3)ガス卸供給(スタートアップ卸)の追加的な促進策
2020年度からスタートアップ卸の取組対象事業者である東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、北海道ガス、仙台市ガス局、静岡ガス、広島ガス、西部ガス、日本ガスの9社において取組の運用を開始し、2021年1月31日時点で、全国で7件の活用事例が見られました。
引き続き、本取組の利用状況、対象区域の競争状況、市場規模等のフォローアップを継続していきます。
(4)一括受ガスの是正方針
一括受ガス状態にある案件の是正を2019年度中に完了するようガス事業者に要請を行っていたところですが、2020年3月末時点でも是正未了の案件が存したため、未了となっている案件の分析・検討を行いました。
一括受ガス状態は、一般ガス導管事業者の託送供給約款に規定される一需要場所・一契約の規定が遵守されていない状態のことを指しますが、1988年頃に多くのガス事業者が供給規程の改正(改正後の供給規定の内容は現在の託送供給約款に引き継がれています。)を行っており、改正前の供給規程上では、集合住宅等において必ずしも現行の一需要場所・一契約の規定を遵守することは求められておりませんでした。
そこで、旧供給規程下で合法的に一括受ガス状態として既に存在したあるいは工事中であった案件については、建築基準法における既存不適格建築物の考え方も参考に、原則として、増改築等を実施する機会に一括受ガス状態を是正させることとされました。
この考え方の下で2019年度中に一括受ガスの是正又は是正見込みの確保が完了していない案件は43件ですが、引き続き、ガス小売事業者及び一般ガス導管事業者に対して一括受ガス状態の早急な是正又は是正見込みの確保を求めるとともに、是正状況の進捗確認を継続していきます。
4.ガス小売市場・卸売市場に関する取組
(1)小売取引の監視等
① 経過措置料金規制が存置されているガスの小売料金の事後評価及び特別な事後監視
ガスの小売料金については平成29年4月に自由化されたものの、競争が不十分であると認められた供給区域等については、需要家利益の保護の観点から経済産業大臣が指定を行い、ガスの小売規制料金の経過措置を存続しています。これらの経過措置が講じられているガスの小売規制料金については、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないかなどを経済産業省において確認し、その結果を公表することとなっています。また、ガスの小売規制料金の経過措置が課されない、又はガスの小売規制料金の経過措置が解除されたみなしガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス又は簡易ガスの利用率が50%を超える事業者を対象として、当該旧供給区域等の料金水準について報告徴収を行い、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないか確認をする特別な事後監視を行っています。
(ア) 経過措置料金規制が存置されているガスの小売料金の原価算定期間終了後の事後評価
「電気事業法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第42号)」附則に基づく経過措置が講じられているガスの小売規制料金については、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないかなどを経済産業省において確認し、その結果を公表することとなっています。
2020年11月、料金制度専門会合において、原価算定期間が終了している旧一般ガスみなしガス小売事業者8社(東京ガス、東邦ガス、京葉ガス、京和ガス、日本ガス、熱海ガス、河内長野ガス及び南海ガス)について電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(20170329資第5号。以下、「審査基準」という。)第2(8)④に基づく評価及び確認を行い、以下のとおり取りまとめました。
これを踏まえ、審査基準第2(8)④に照らし、経過措置が講じられているガスの小売規制料金の値下げ認可申請の必要があると認められる事業者はいませんでした。
【第362-4-1】料金制度専門会合の取りまとめ(審査基準の適用結果)
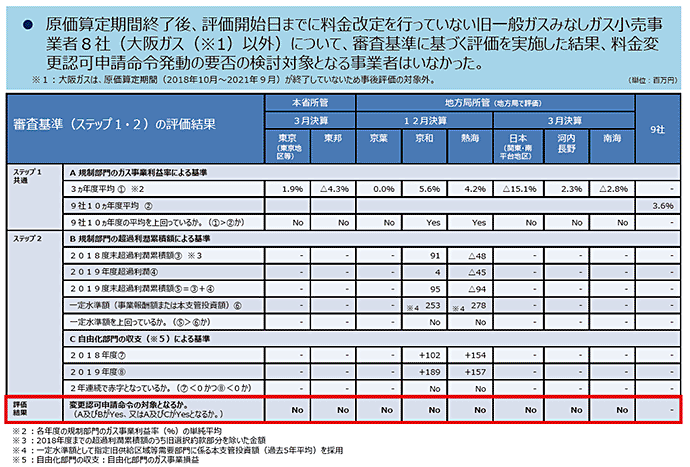
- 出典:
- 各事業者の部門別収支計算書、各事業者へのヒアリングにより当委員会事務局作成
(評価の結果)
- 審査基準のステップ1[ガス事業利益率による基準]では、個社の直近3カ年度平均の利益率が9社10カ年度平均の利益率を上回る会社は、京和ガス及び熱海ガスの2社であった。
- ステップ1に該当した2社について、審査基準のステップ2[超過利潤累積額による基準]⼜は[⾃由化部⾨の収⽀による基準]では、2019年度末超過利潤累積額は⼀定⽔準額を下回っており、直近2年連続で⾃由化部⾨の収⽀が⾚字となっていなかった。
- 上記より、原価算定期間を終了している旧⼀般ガスみなしガス⼩売事業者8社(⼤阪ガス以外)について、審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の要否の検討対象となる事業者はいなかった。
(結論)
- 以上を踏まえ、今回事後評価の対象となった事業者について、現⾏の料⾦に関する値下げ認可申請の必要があるとは認められなかった。
(イ)ガス小売料金の特別な事後監視
第29回総合エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会(平成28年2月)において、ガスの小売規制料金の経過措置が課されない、又はガスの小売規制料金の経過措置が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス及び簡易ガス利用率が50%を超える事業者については、特別な事後監視として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該供給区域等の料金水準(標準家庭における1か月のガス使用料を前提としたガス料金)を、3年間監視することとされました。これを受け、委員会においてはこれらの事業者の家庭向けの標準的な小売料金について、定期的に報告を受け、料金改定の状況等を確認しています。
この結果、2020年4月~ 2021年3月においては、2者に対し、次の内容の文書指導を行いました。
○文書指導の概要
(i)ガス小売事業者A社へ行った指導(2020年6月)
A社の料金改定は、原料費調整制度を導入して以降の原料価格の高騰分を経営合理化により吸収してきたものの、当該供給地点群の収支が近年赤字となっていたことに伴い料金改定を行ったものでした。しかし、赤字の解消額を大幅に超えて相当の利益が発生する改定となっていたことが確認されたため、単年度収支で赤字が発生しない程度に収支が改善する水準とした料金とするように、指導しました。
(ii)ガス小売事業者B社へ行った指導(2021年2月)
B社の料金改定は、値上げの理由に合理性が認められず「合理的でない値上げ」に該当すると判断しましたが、同社が料金を値上げ前の水準に戻したこと等を踏まえ、今後、同様の値上げを行わないように、指導しました。また、当該値上げに係る需要家への説明内容に明確でない点があったため、適切に説明を行うように、併せて指導しました。
(ウ) ガス小売経過措置料金規制に係る指定旧供給区域等の指定の解除について
2020年12月21日、電力・ガス取引監視等委員会において、旧一般ガスみなしガス小売事業者である東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社に係る指定旧供給区域等の指定の解除に関し、必要と考えられる事項として、以下の2点について、審議しました。
- ① 卸取引所が開設されていないといったガスの卸取引市場の現状や、東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社の指定旧供給区域における他のガス小売事業者の実情を踏まえると、これらの区域における他のガス小売事業者に十分な供給余力が確保されていると判断するためには、将来にわたり、他のガス小売事業者が外部から調達する供給力を含めて十分な供給力を確保できる環境が整備されていること
- ② 東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社の指定旧供給区域については、他燃料との競合のみでは指定解除要件を満たしておらず、当該区域の都市ガス利用率が50%を超えている状況を踏まえると、将来にわたって適正な競争関係が確保されるためには、ガス小売事業への新規参入が円滑化される環境が整備されていること
こうした審議の結果を踏まえ、上記指定の解除を行うためには、解除対象の上記3社より次の意思表明がなされている必要があると決定しました。
- ① 他の事業者から、ガス製造に係る業務(熱量調整や付臭など一部工程に係る業務を含む。以下同じ。)の委託の依頼があった場合には、設備余力がないなどの理由がない限りは、それを受託する。特に、既にガス製造に係る業務の委託契約を締結している事業者がその業務の継続を希望する場合には、止むを得ない理由がない限りは、それを継続する。
- ② 他の事業者から、ガスの卸供給の依頼があった場合には、供給余力がないなどの理由がない限りはこれを行う。
- ③「 スタートアップ卸」について、旧一般ガスみなしガス小売事業者の小売事業との競争性を確保できる価格水準で都市ガスを調達できる環境を整備し、新規参入を支援するために開始された趣旨を踏まえ、利用実績が上がるよう、積極的に取り組む。この際、卸価格の設定に当たっては、「旧一般ガスみなしガス小売事業者の標準メニューの最も低廉な小売料金から一定の経費を控除し算定した上限卸価格の下で、卸元事業者と利用事業者が個別に卸価格を交渉する」ものとされていることを踏まえ、他の事業者からの求めに応じて誠実に交渉を行い、対応する。
なお、この記載にある「設備余力がないなどの理由」「供給余力がないなどの理由」とは、それぞれ、「設備余力がない」「供給余力がない」に準ずる客観的かつ合理的な事由を指しています。なおコストを下回るなど経済合理的でない価格水準での他の事業者の依頼に応じることまでを求めるものではありません。
5.ガス導管分野に関する取組
(1) 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者の業務及び経理の監査
電力・ガス取引監視等委員会は、ガス事業法第170条の規定に基づき、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下、本項目において「一般ガス導管事業者等」という。)218者の2019事業年度の業務及び経理について監査を行いました。
2020年度監査においては、主な重点監査項目として、昨年度に引き続き、託送収支が適正に計算されているかを重点的に確認した(託送供給収支に関する監査)。また、2018年度のガス導管事業者の収支状況等の事後評価において、内管工事が適正に管理されていないケースがあることが明らかになったことを踏まえ、一般ガス導管事業者の内管工事に要した収益・費用が受注工事勘定をもって適切に整理しているかを重点的に確認しました(財務諸表に関する監査)。
2020年度において実施した監査の結果、119事業者において211件の指摘事項がありました。これについては、ガス事業法第178条第1項及び同法第179条第1の規定に基づく勧告を行うべき事項は認められませんでしたが、所要の指導を行いました。
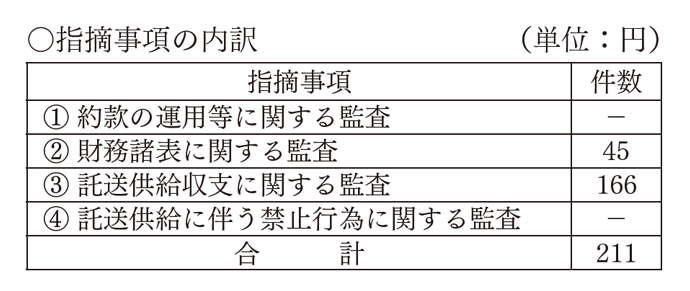
(2)ガス導管事業者の収支状況等の事後評価
一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた者を除く。以下、本項目において「ガス導管事業者」という。)は、事業年度毎に託送収支計算書を作成・公表することとされており、その超過利潤累積額が一定額を超過した場合又は乖離率がマイナス5%を超過した場合には、経済産業大臣が託送料金の値下げ申請を命令できることとされています。このため、2020年11月11日付にて、経済産業大臣及び各経済産業局長等から、ガス導管事業者の2019年度収支状況の確認について、電力・ガス取引監視等委員会宛てに意見の求めがありました。
これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、料金制度専門会合において、法令に基づく事後評価(ストック管理・フロー管理)を実施するとともに、追加的な分析・評価を行い、2020年2月、その結果を取りまとめました。
この結果を踏まえ、事後評価の対象事業者147者のうち5者(うち1事業者においては、2地区)(JERA(四日市コンビナート地区)、秋田県天然瓦斯輸送、小千谷市、中部電力ミライズ、関西電力(堺地区)及び関西電力(姫路地区))については、2019年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準額を超過していました。また、26者(東部ガス(秋田地区)、由利本荘市、熱海ガス、入間ガス、佐野ガス、静岡ガス、諏訪ガス、中遠ガス、野田ガス、袋井ガス、湯河原ガス、吉田ガス、ガスネットワーク吉田、犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、JERA(四日市コンビナート地区)、小千谷市、小田原ガス、北日本ガス、東日本ガス、広島ガス、水島ガス、筑紫ガス、鳥栖ガス及び九州ガス圧送)については、2019年度終了時点での想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となるマイナス5%を超過していました。これらの事業者のうち、2020年12月末日又は2021年3月末日が料金改定の期日とされていた事業者については、現行の託送供給約款料金の水準維持の妥当性について合理的な説明がなされたため変更命令の対象外とした4者(想定単価と実績単価の乖離率が変更命令の発動基準となるマイナス5%を超過した事業者(犬山ガス、大垣ガス、福山ガス及び広島ガス))を除き、期日までに託送供給約款の料金改定の届出が行われない場合、経済産業大臣及び所管の経済産業局長から変更命令を行うことが適当である旨、委員会は経済産業大臣及び経済産業局長等へ意見を回答しました。
なお、2020年12月末日又は2021年3月末日が料金改定の期日とされていた事業者については、託送料金の改定の届出が行われたことを確認し、2022年3月末日が期日とされている事業者からは、期日までに託送料金の改定を行う予定であることを確認しました。
(3) 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細検討
「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」において、令和4年度から、導管規模等が政令で定める要件に該当する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者の法的分離を実施し、あわせて、法的分離された一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者とその特定関係事業者(以下、本項目において「ガス導管事業者等」という。)に行為規制を導入することが規定されました。その詳細は経済産業省令で定める必要があるところ、2019年9月27日に経済産業大臣より電力・ガス取引監視等委員会に対し、行為規制の詳細についての意見の求めがありました。
そこで、電力・ガス取引監視等委員会は、2019年9月より、制度設計専門会合において、ガス導管事業者等にかかる行為規制の詳細について検討を行い、第46回制度設計専門会合(2020年3月)において「2022年度から導入する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について」を取りまとめました。その後、電力・ガス取引監視等委員会は、2020年4月14日に、それらの内容を踏まえ経済産業省令等を改正することに関して経済産業大臣に意見を回答しました。
その後、2021年2月1日から3月2日にかけて、当該取りまとめの内容を踏まえたガス事業法施行規則及び適正なガス取引についての指針の改正案についてパブリックコメントを実施しました。
その後、パブリックコメントでいただいた御意見も踏まえ、2021年4月1日に案のとおり改正されました。
取りまとめの内容(抜粋)
①社名、商標、広告・宣伝等に関する規律
(ア) 法的分離の対象となる一般ガス導管事業者(以下、「特別一般ガス導管事業者」という。)がその特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号、商標を用いることを原則禁止とする
(イ) 一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門が、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門の営業活動を有利にする広告、宣伝その他の営業行為を行うことを禁止とする(特定ガス導管事業者も同様に規定)
②取締役等及び従業者の兼職に関する規律の詳細
(ア) 取締役等の兼職禁止の例外について具体的に規定
(イ) 兼職禁止の対象となる従業者の範囲を具体的に規定
③グループ内での取引に関する規律の詳細
取引規制の対象となる特別一般ガス導管事業者と「特殊の関係のある者」を具体的に規定
④業務の受委託の禁止の例外
(ア) 特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者及びその子会社等に例外的に託送業務等を委託することができる要件
(イ) 特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者から小売・製造業務を例外的に受託することができる要件
⑤ 情報の適正な管理のための体制整備等(特定ガス導管事業者も同様に規定)
(ア) 一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門と当該一般ガス導管者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門とが建物を共用する場合には、別フロアにするなど、物理的隔絶を担保し、入室制限等を行うこと
(イ) 一般ガス導管事業者は、自らの託送供給等業務の実施状況を適切に監視するための体制整備を行うこと
(ウ) 内部規程の整備、従業者等の研修・管理などの法令遵守計画を策定し、その計画を実施すること 等
※ 一部の項目においては、一定の条件に該当する一般ガス導管事業者に限る
6. ガス安全小委員会における議論
ガスの小売全面自由化が行われ、新たなガス小売事業者の参入が開始されたことから、ガス小売事業者の保安水準の維持、向上を図る施策の検討をガス安全小委員会において実施しました。需要家にガス小売事業者の自主保安活動の特徴的な取組状況をホームページで分かりやすく紹介し、消費者が保安面で優れているガス小売事業者を選択することを支援する「見える化」制度を2017年度に構築しました。2020年度においては、経済産業省のホームページにおいて、各ガス小売事業者の自主保安活動を公表できるようにし、ガス小売事業者の保安水準向上を後押ししています。
また、規制改革推進会議において、内管の保安と工事について競争メカニズムが働いていないとの指摘を受け、各一般ガス導管事業者における適切な委託先選定が行われる仕組み作りについて対応方針を示したところ、各一般ガス導管事業者の取組状況についてフォローアップを実施しました
7. 熱供給システム改革の概要
熱供給システム改革は、電力・ガスシステム改革とあいまって、熱電一体供給も含めたエネルギー供給を効率的に実施できるようにするため、2013年11月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に開催された「ガスシステム小委員会」において熱供給事業の在り方などを検討・審議し、2015年6月の「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第74号)」の成立を受けた後は、熱供給システム改革を着実に進めていく上で必要な実務的な課題を含めた具体的な制度設計について議論を行いました。2016年4月に実施された熱供給システム改革では、許可制としていた熱供給事業への参入規制を登録制とし、料金規制や供給義務などを撤廃し(ただし、他の熱源の選択が困難な地域では、経過措置として料金規制を継続)、熱供給事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課しました。
熱供給システム改革の実行により、事業環境の整備が行われ、エネルギー市場の垣根の撤廃や異業種からの参入が促進され、電力・ガスシステム改革が一体的に推進していくことが期待されています。