第2節 ガスシステム改革及び熱供給システム改革の促進
1. ガスシステム改革の概要
2015年6月に成立した電気事業法等の一部を改正する等の法律に基づき、2017年4月1日にガス小売全面自由化等のガスシステム改革が実施されました。ガスシステム改革の実施に当たっては、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会(2013年11月から2016年6月にかけて33回開催)、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2016年10月から2017年2月にかけて2回開催)、産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会(2014年6月から2017年3月にかけて16回開催)、同小委員会ガスシステム改革保安対策ワーキンググループ(2015年7月から2016年5月にかけて6回開催)及び電力・ガス取引監視等委員会等において、随時議論がなされてきました。
ガスシステム改革は、1.天然ガスの安定供給の確保、2.ガス料金の最大限の抑制、3.利用メニューの多様化と事業機会の拡大、4.天然ガスの利用方法の拡大の主に4つを目的としており、2017年4月以降も、資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視等委員会のそれぞれにおいてさらなる市場活性化のための検討を進めています。
なお、2022年4月1日に予定されている大手ガス事業者の導管部門の法的分離等に関する制度設計については、市場の状況も考慮し、引き続き、総合資源エネルギー調査会等での議論を踏まえ、政府として検討を進めることとしています。
2. ガスの小売全面自由化の進捗状況
(1)ガス小売事業者の登録
新規のガス小売事業者については、2016年8月の事前登録申請の受付開始から2020年3月末時点までに、79者が登録されました。ガス小売事業者の登録に当たっては、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会が、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当しないか等、法令に則りそれぞれ審査を行っています。なお、電気事業法等の一部を改正する等の法律の経過措置により、旧一般ガス事業者から203者、旧簡易ガス事業者から1,174者が、ガス小売事業者となりました。
【第362-2-1】新規ガス小売事業者の登録状況
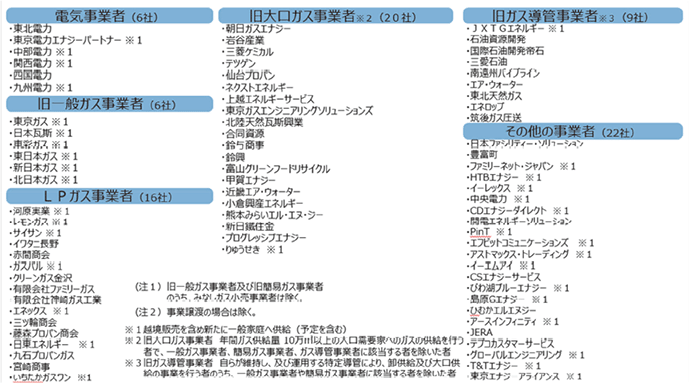
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(2) スイッチング(契約先の切り替え)件数及び新規参入者の販売シェア
ガスの小売全面自由化から、一般家庭等での累計ガスの小売全面自由化から、一般家庭等での累計スイッチング申込件数は堅調に増加しており、2020年3月末時点で、全国で約343万件となっています。地域別でみると、近畿が最多となっています。スイッチング率は全国で13.5%です。なお、北海道、東北、中国・四国では2020年3月末時点でスイッチングの動きは見られていません(第362-2-2)。
]また、自社内スイッチング件数(累計)は、2019年12月末時点で、約134万件(全国)、スイッチング率は9.6%(全国)となっており(第362-2-3)、他社へのスイッチングと同様に増加しています。
新規参入者の全需要種に占めるガス販売量については、2019年12月末時点で全体の14.6%となっています。家庭用のガス販売量に占める新規参入者のシェアは全国で9.8%、最もスイッチングが進んでいる近畿地方では、14.6%となっています(第362-2-4)。
【第362-2-2】全国のスイッチング率の推移・申込件数
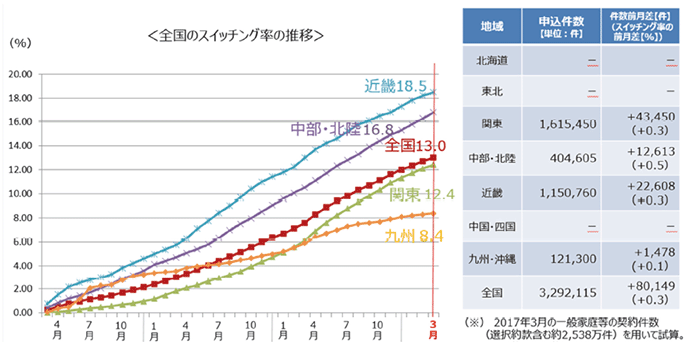
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
【第362-2-3】指定旧供給区域内における累計契約変更件数
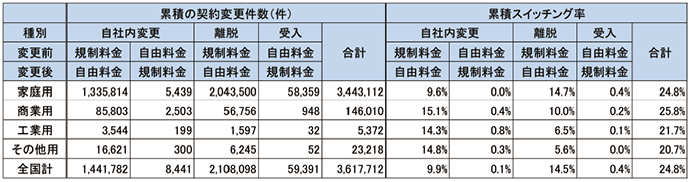
- 出典:
- ガス取引報(2019年12月分)表14
【第362-2-4】新規小売のガス販売量(需要種・エリア別)
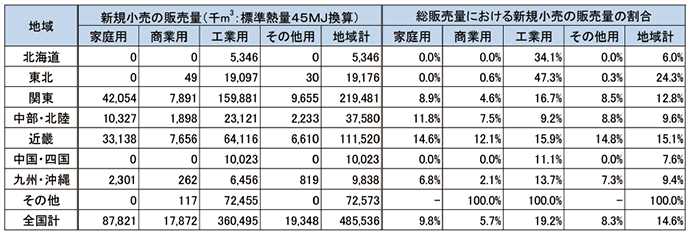
- 出典:
- ガス取引報(2019年12月分)表3
(3)メニューの多様化
ガス小売全面自由化を契機に、全国各地のガス小売事業者が新たな料金・サービスメニューの提供に取り組んでおり、料金・サービスの多様化が進んでいます。各事業者が提案する新メニューでは、ガス料金の割引を行うもの、電力や通信といった他のサービスとのセット割引を行うもの、料金支払いに対しポイントを付与するもの、顧客の見守りサービスを提供するもの、トラブル時の駆けつけサービスを提供するもの、ガスの使用量や料金の見える化サービスを提供するもの、といった類型が見られます。
【第362-2-5】ガス事業者のサービス向上に向けた新たな取組の類型表
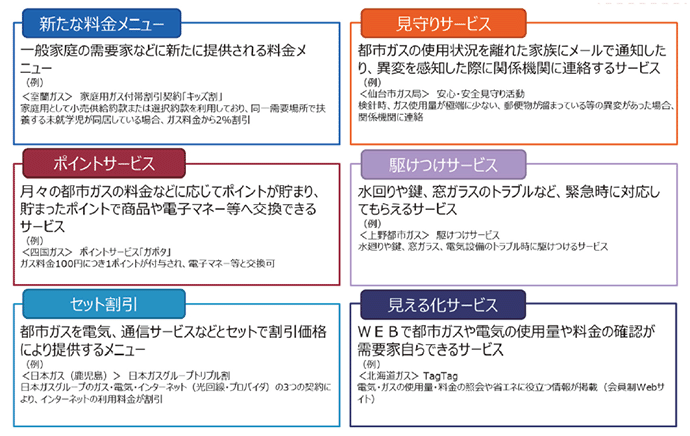
- 出典:
- 各社プレスリリース・HP等より資源エネルギー庁が作成
【第362-2-6】ガス事業者のサービス向上に向けた新たな取組
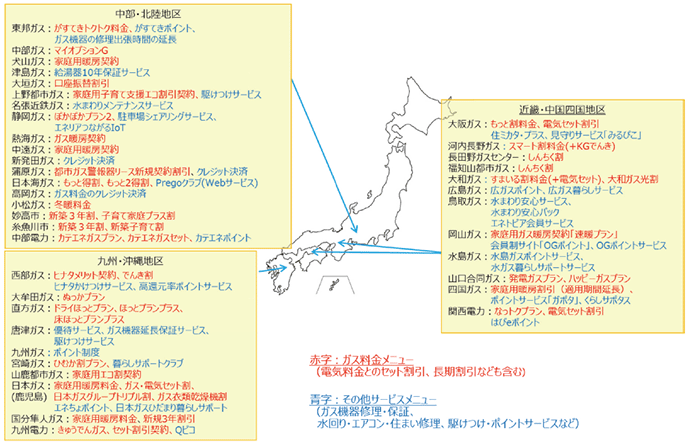
- 出典:
- 日本ガス協会作成(2019年1月末時点)
(4)経過措置料金規制の対象地域の指定解除
ガス小売全面自由化に伴い、ガスの小売供給に関する料金規制は原則撤廃されましたが、LPガス、オール電化等を含め競争が不十分であると認められた地域については、需要家利益の保護の観点から経済産業大臣が指定を行い、経過措置として料金規制を継続しています。ただし、指定を受けた地域の競争状況は、経済産業大臣が3か月に一度の事業者報告により継続して把握し、競争が十分であると認められた地域については指定を解除することとしています。
ガス小売全面自由化に先駆けて、2016年11月には、ガスシステム改革小委員会等の議論を受けて策定された指定基準に基づき、旧一般ガス事業者の供給区域等では12区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点では1,730供給地点群を指定しましたが、2020年3月末現在において、旧一般ガス事業者の供給区域等では9区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点では1,135供給地点群が指定されています。
【第362-2-7】指定旧供給区域等一覧(旧一般ガス
事業者の供給区域等)

- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
3. ガス事業制度検討ワーキンググループにおける議論
資源エネルギー庁は2018年9月に、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会の下に「ガス事業制度検討ワーキンググループ(以下、「ガスWG」という。)」を開催しました。ガスWGは、2017年4月のガス小売全面自由化の成果が一定程度見られる中、エネルギー基本計画や規制改革実施計画、一部継続検討課題とされていたテーマを踏まえつつ、ガスシステム改革のさらなる推進に向けてガス事業制度の在り方について専門的な見地から詳細な検討を進めることを目的としています。
2019年度中にはガスWGを6回開催し、ガス卸供給の追加的な促進策、一括受ガスその他消費者の利益を最大限実現するための措置、熱量バンド制、二重導管規制に係る変更・中止命令の判断基準、LNG基地の第三者利用の追加的な促進策の要否について議論が交わされました。
(1)ガス卸供給の追加的な促進策
「適正なガス取引についての指針」における積極的なガスの卸供給に関する記載を踏まえた旧一般ガス事業者の自主的取組と位置づけられたスタートアップ卸に関し、2019年7月末までに旧一般ガス事業者による利用受付が開始されました。2020年3月末を旧一般ガス事業者による卸供給を開始いたしました。
(2) 一括受ガスその他消費者の利益を最大限実現するための措置
ガスWGでの議論を踏まえ、2019年9月28日に「ガスの小売営業に関する指針」を改定し、一括受ガスが許容されない補足理由、需要家代理モデル活用により期待されるメリット、需要家代理モデルへの消費者契約法等の適用可能性、等について新たに規定しました。
(3)熱量バンド制
一定の熱量範囲(バンド)に収まれば、熱量が多少変動しても導管への注入を認める仕組みである「熱量バンド制」の導入の適否について追加調査を実施し、調査内容をガスWGに報告しました。追加調査の具体的内容として、まず欧州(英独)における熱量バンド制の調査を行い欧州と日本のガス供給の差異について報告を行いました。続いて、熱量バンドに移行する際の費用と便益の調査を行いました。引き続き、具体的な制度設計の検討を進めながら、現行の標準熱量制と比較しつつ標準熱量の引き下げや小さいバンド幅の選択肢から優先的に取り上げ、引き続き検討を継続することといたしました。)
(4)二重導管規制に係る変更・中止命令の判断基準
二重導管規制とは、特定ガス導管事業者の供給地点が一般ガス導管事業者の供給区域に含まれる場合に、当該特定ガス導管事業によりガスの使用者の利益が阻害される(託送料金の値上げが実際に行われる)おそれの有無を国が審査し、おそれがあると認められる場合には、特定ガス導管事業の届出内容に係る変更または中止の命令を可能とする制度であり、その趣旨は既存導管網の効率的利用を図り、一般ガス導管事業者の供給区域内の導管利用コストの上昇を抑制するとともに、効率的な導管網形成を促すことにあります。
ガスシステム改革小委員会での議論を踏まえ、小売全前面自由化(2017年4月1日)後3年度間では、原則としてネットワーク需要の4.5%に相当する既存需要の獲得が可能とされていましたが、2019年度のガスWGでは、2020年度以降の二重導管規制の在り方について議論し、特定ガス導管事業の届出による需要獲得時点を「届出時点」とすること、一般ガス導管事業者の供給区域毎にネットワーク需要の伸び率を基礎として2020年度から2022年度の3年間の利益阻害性の判断基準とすること、2020年度4月からの獲得可能量が2017 ~ 2019年度の獲得可能量(ネットワーク需要の4.5%)の残余分未満となる供給区域においては、新規参入者の予見可能性確保の観点から、激変緩和措置として、2020年度~ 2022年度に限り当該残余分を獲得可能量とすること、新制度開始後3年を目途に本制度の運用状況を確認し、必要な対応を検討すること、等が整理されました。
(5)LNG基地の第三者利用の追加的な促進策の要否
2018年6月15日閣議決定の規制改革実施計画において、ガス受託製造約款の策定が義務づけられるLNG基地の対象拡大について利用事業者の意見も広く取り入れて検討することとされたことを受けて、「ガス導管に接続している貯蔵容量が20万kl未満のLNG基地」の利用ニーズを資源エネルギー庁において調査しました。
調査により、ガス製造事業に該当しないLNG基地について具体的な利用の申出や利用の問い合わせが行われた事例がなかったことがわかりましたが、他方で一部事業者は利用に興味を有していることがわかりました。
「適正なガス取引についての指針」では、法定LNG基地に該当しないLNG基地について、第三者から利用の申出を受けた場合には、当事者間の相対交渉を通じて適切な条件で応じることが望ましいとされていることから、まずは指針に基づき相対交渉の事例を積み重ねることが必要、と整理されました。
4. ガス市場における適正な取引確保のための厳正な監視など
(1)ガス市場の監視
2017年4月にはガスの小売事業への参入が全面自由化され、家庭を含む全ての需要家がガス会社や料金メニューを自由に選択できることとなりました。こうした中、ガスの小売供給に関する取引の適正化を図るため、「ガスの小売営業に関する指針」を踏まえ、需要家への情報提供や契約の形態・事業者の営業活動の監視などを行い、必要に応じて、ガス事業法上問題となる事業者に対して指導等を行っています。また、相談窓口などに寄せられた不適切な営業活動などについて、事実関係の確認や指導を行っています。
【第362-4-1】特別な事後監視の概要
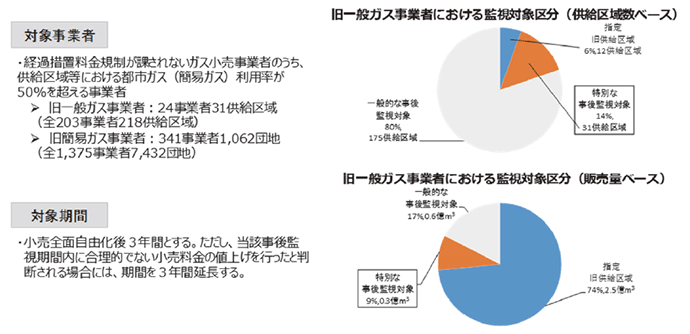
- 出典:
- 2017年8月ガス取引報に基づき電力・ガス取引監視等委員会作成
(2)小売料金に係る事後監視
2017年4月以降、一般的な監視に加え、経過措置料金規制が課されない、または経過措置料金規制が解除されたみなしガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス(または簡易ガス)の利用率が50%を超える事業者を対象として、当該旧供給区域等の料金水準について報告徴収を行い、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、3年間監視(以下、「特別な事後監視」という。)を行っています。
四半期ごとに実施される特別な事後監視の結果については、電力・ガス取引監視等委員会のホームページにて公表することになっています。これまでに、「合理的でない値上げ」に該当すると判断し、また料金改定の際に需要家に対する説明が不十分であることが確認された事業者1社及び料金改定の際に需要家に対する説明が不十分であることが確認された事業者1社に対して指導を行いました。
(3)原価算定期間終了後の経過措置料金の事後評価
「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」(以下、「第3弾改正法」という。)附則の経過措置に基づくガス小売料金については、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないかなどを経済産業省において確認し、その結果を公表することとなっています。
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣等からの意見聴取を受けて、料金審査専門会合において2018年度の状況について評価及び確認を行い、2019年11月、以下のとおりとりまとめました。
これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣等に対し、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20170329資第5号)第2(8)④に照らし、経過措置料金の変更申請を命じることが必要となる事業者はいなかった旨回答しました。
①料金審査専門会合のとりまとめ(2019年11月)
(ア)事後評価のポイント
旧一般ガスみなしガス小売事業者全9社のうち、本省所管の対象事業者2社(東京ガス及び東邦ガス)※及び、地方局所管の対象事業者6社(京葉ガス、京和ガス、日本ガス、熱海ガス、河内長野ガス及び南海ガス)の計8社について、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20170329資第5号)第2(8)④に基づく値下げ認可申請の必要がないか確認を行いました。
※ 原価算定期間終了前の大阪ガスは、事後評価の対象外。
(イ)料金審査専門会合の開催実績
2019年11月20日 第38回料金審査専門会合
【第362-4-2】料金変更認可申請命令に係る審査基準
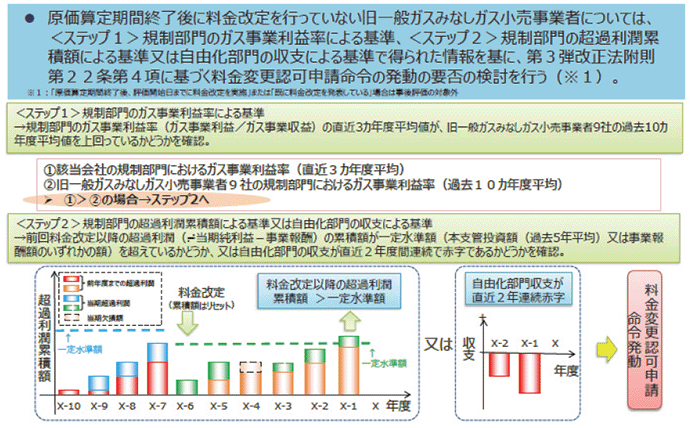
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(ウ)事後評価の結果
第3弾改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前の「ガス事業法(昭和29年法律第51号)」第18条第1項の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令に係る「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20170329資第5号)第2(8)④に照らし、値下げ認可申請の必要は認められませんでした。評価の詳細は以下のとおりです。
審査基準のステップ1「ガス事業利益率による基準」では、個社の直近3か年度平均の利益率が9社10か年度平均の利益率を上回る会社は、京和ガス及び熱海ガスの2社でした。ステップ1に該当した2社について、審査基準のステップ2「超過利潤累積額による基準」では、2018年度末超過利潤累積額は一定水準額である指定旧供給区域等需要部門に係る本支管投資額(過去5年平均)を下回っており、ステップ2「自由化部門の収支による基準」では、直近2年連続で自由化部門の収支が赤字となっていませんでした。以上より、原価算定期間を終了している旧一般ガスみなしガス小売事業者8社(大阪ガス以外)について、審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の検討対象となる事業者はいませんでした。
以上を踏まえ、2019年度の事後評価の対象となった事業者について、現行の認可料金に関する値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでした。
【第362-4-3】審査基準の適用結果
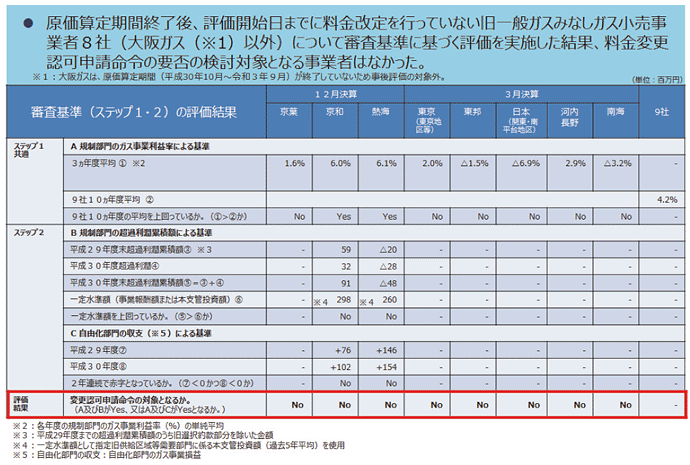
- 出典:
- 各事業者の部門別収支計算書、各事業者へのヒアリングにより資源エネルギー庁作成
(4)ガス導管事業者の収支状況等の事後評価
2017年度から施行されたガスシステム改革関連の制度改正により、ガス事業にライセンス制が導入され、ガス導管事業は中立的なネットワーク部門として引き続き地域独占とすることとされました。これを踏まえ、各一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下、「ガス導管事業者」という。)は新たな託送供給約款を策定して2017年4月から実施、その後、事業年度毎に託送収支計算書が公表されています。これを踏まえ、2019年11月1日付にて、経済産業大臣及び各経済産業局長等から、ガス導管事業者の2018年度収支状況の確認について電力・ガス取引監視等委員会宛てに意見の求めがありました。
これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会 料金審査専門会合において、法令に基づく事後評価(ストック管理・フロー管理)を実施するとともに、託送料金の低廉化を促進するために、追加的な分析・評価を行いました。
①法令に基づく事後評価
2018年度に事業を実施した全国のガス導管事業者(222社)のうち、託送供給約款を策定している等の事業者(143社)について、2018年度の収支状況を評価しました。
これら143社のうち、8社(苫小牧ガス、仙南ガス、東部液化石油、新発田ガス、松本ガス、長南町、妙高市(妙高高原区域)及び魚沼市)については、2018年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準額を超過しました。
このうち、1月~ 12月の会計年度を採用している3社(東部液化石油、新発田ガス及び松本ガス)については、2019年12月中に託送供給約款料金の改定の届出が行われ、ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に従って、託送供給約款届出料金が適切に算定されていることを確認しました。
また、4月~ 3月の会計年度を採用している5社(苫小牧ガス、仙南ガス、長南町、妙高市(妙高高原区域)及び魚沼市)に対応方針を聴取したところ、5社とも期日までに料金改定を実施予定であるとの回答でした。
②追加的な分析・評価
(ア) 超過利潤累積額が一定水準額を超えた事業者の料金値下げ届出について
東部液化石油、新発田ガス及び松本ガスの3社については、所管の経済産業局長に対して、2020年1月1日を実施日とする託送供給約款の変更(料金値下げ)の届出が行われたため、その内容を確認しました。届出のあった3社はいずれも、ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に従って、届出上限値方式により変更後の料金が算定されました。このため、基本的には、(A)超過利潤が一定水準を超過したことによる、省令の算定式により算出される超過利潤等の管理に基づく料金引下げ原資及び(B)届出上限値方式を採用したことによる、同方式に基づく料金引下げ原資の合計が還元されることとなりますが、このうち(A)については、新発田ガス及び松本ガスは、省令上算定が免除される要件を満たしているため、還元が行われませんでした(次回料金改定には反映)。
前述の(B)については、ガス託送料金の値下げ届出は、総括原価方式と届出上限値方式の選択制であり、届出上限値方式が選択された場合、料金引下げ原資は、経営効率化等によって生じた費用減の一部を事業者が自らの経営判断で設定することとなります。本制度の趣旨は、託送料金原価の適正性が十分に担保されている状況であれば、総括原価方式に比べ簡易である同方式を通じ、料金値下げの機動性向上が図られることにあります。
しかしながら、これまで料金審査専門会合で事後評価を行ってきたとおり、新制度に基づく各社の託送料金(2017年4月実施)については、一部の事業者で、当時の査定に限り認められた原価算定方式が適用された費用項目において、「実績費用と想定原価との大きなずれ」が確認されており、本来制度が前提としていた状況に必ずしも当てはまらない可能性があります。
会合では、こうした事業者の超過利潤が一定水準を超過した場合、原価を速やかに実態に合わせる観点から、まずは、「総括原価方式での値下げ」を行う必要性が高いと考えられるため、新制度に基づく託送料金(2017年4月実施)の認可を受けた事業者で、超過利潤が一定水準を超過した者については、次に料金値下げ届出を行おうとする場合、選択制ではなく、総括原価方式で行わなければならない旨の制度的措置を速やかに講じるべきとされました。_
(イ)大きな超過利潤が発生した事業者の分析・評価
一定水準を超過した事業者以外にも、2018年度の収支において比較的大きな超過利潤が発生した事業者があったことを踏まえ、当期超過利潤額が営業収益の5%以上であった7社(昨年度の追加的な分析・評価で対象外とした4月~ 3月以外の会計年度を採用している事業者が対象。ただし、超過利潤累積額が一定水準を超過した事業者を除く)について、その超過利潤の要因と今後の見通しを分析・評価するとともに、各事業者から今後の対応方針を聴取しました。
これらの事業者の超過利潤の要因については、想定より収益が増加したことが要因であるもの、想定より費用が減少したことが要因であるもの、そしてその両者が要因となっているもののそれぞれが存在しました。
収益増の要因については、大口需要家への供給量の増加、新規の需要獲得などがあげられました。費用減の要因については、設備投資が減少した・実施されなかった、簡易な原価算定方式(簡素合理化方式)によって想定原価が大きく見積もられていた、などがあげられました。
こうした要因分析を踏まえ、各事業者の超過利潤が一過性のものか継続する可能性が高いものかについて分析・評価を行いました。その結果、4社については、来年度以降も2018年度と同じ要因での超過利潤が継続する可能性が高いと評価され、来年度の事後評価において重点的にフォローアップを行うことが適当とされました。また、それ以外の3社については、2018年度の超過利潤の発生は一過性である可能性があると評価されました。
この結果を踏まえ、各事業者に対し、料金改定を含めた今後の方針について聴取したところ、超過利潤の継続性が高い4社のうち2社から、2021年1月に自主的に料金改定を実施する予定であるとの回答がありました。
また、昨年度の事後評価において大きな超過利潤が発生した事業者について、フォローアップを実施したところ、超過利潤の発生状況が変化し、方針が変更された事業者が一部あったものの、2018年度収支でも大きな超過利潤が継続した事業者については、基本的には2020年4月からの料金改定を自主的に実施する予定であるとの回答がありました。
③需要開拓費、二重導管離脱需要の分析
(ア)需要開拓費の分析
需要開拓費を原価に計上した事業者について、2017年度~ 2019年度需要開拓費の想定原価と実績費用(実績見込みを含む)を聴取しました。全体としては、想定を上回る実績、概ね想定通りの執行となる事業者が多かったですが、一部の事業者では想定外の案件数の減少などの理由により、実績が想定を下回りました。
また、需要開拓費は、第26回ガスシステム改革小委員会において、「ガス導管事業者が得る託送料金収入は増加することとなるため、その一部を需要開拓を行ったガス小売事業者に対して還元する(実質的な託送料金の割引)」及び「需要開拓により見込まれる5年間の託送料金収入増加額の2分の1に相当する額を託送料金原価に織り込むことを認める」と整理されました。これらの整理を踏まえ、5年間の託送料金収入増加見込額が、需要開拓費執行額の2倍以上であれば当初期待された費用対効果が達成されていると評価できるとし、需要開拓費を執行した7社の状況を分析したところ、各社とも、5年間の託送料金収入増加見込額は、需要開拓費執行額の2倍以上となっていました。
これらの託送料金収入の増加は、超過利潤、ひいては将来の託送料金値下げの原資となり得るため、引き続き、制度に基づき、超過利潤の発生状況について事後評価を行っていくこととされました。
(イ)二重導管離脱需要の分析
2016年に二重導管規制が見直され、ガス導管事業者は、原則として、小売り全面自由化後3年間において、各一般ガス導管事業者のネットワーク需要の4.5%に相当する既存需要を獲得することが可能となりました。一般ガス導管事業者の中には、需要想定を行うにあたり、自社の状況に応じて、一定程度の需要減少量を織り込んだ事業者もいることから、申請時想定と実績を比較し、その乖離理由を各事業者から聴取しました。
二重導管離脱需要の実績が申請時の想定を下回った事業者(東京ガス及び東邦ガス)からは、乖離理由について報告があったとともに、今後の申請時の想定については、適切な想定に努める旨が表明されました。
④効率化に向けた取組状況
昨年度の事後評価においては、先進的な取組を行っていると期待される大手3社(東京ガス、大阪ガス、東邦ガス)の取組を確認し、特に先進的で効果の高い取組について取りまとめ、中小事業者等への横展開の技術的サポート等を日本ガス協会に依頼したため、今年度は、日本ガス協会の取組状況のフォローアップを行いました。
日本ガス協会からは、昨年度の要請を受けた新たな取組として、一般ガス導管事業者の経営者や実務の責任者等に対し、直接、昨年度の事後評価のとりまとめ内容を情報発信したこと等が報告されました。引き続き、こうした取組を通じ、ガス業界全体の効率化意識のさらなる醸成と、より一層の取組促進に繋がることが期待されます。
また、昨年度の事後評価で取り上げられた先進的な効率化取組を経済産業省がとりまとめ、発出した効率化事例集について、一般ガス導管事業者各社が当該事例集の内容に関する疑問点を解決し、スムーズに導入検討を進められるよう、「効率化事例集に関連する問合せ窓口」を設置し、導入済みの事業者(大手3社)とのマッチングを迅速かつ確実に行う仕組みが設けられました。
今後、日本ガス協会を中核とした一般ガス導管事業者への情報発信や課題解決のためのサポートが、より一層深化していくことにより、一般ガス導管事業者全体の自主的な業務効率化が加速化していくことが期待されます。
⑤内管工事の取組状況
(ア) 内管工事の利益率が大きく、かつ直近で見積単価表の改定が行われていない事業者の分析
昨年度実施した事後評価を踏まえ、内管工事の利益率が大きく、かつ直近で見積単価表の改定が行われていない事業者16社に対して、その利益率の妥当性または利益率を踏まえた見積単価表の改定の見通しを聴取したところ、8社からは見積単価表の見直しをする、または見直しを検討するとの回答がありました。
内管工事の利益率が大きくなる主な原因については、複数の事業者から、見積単価表に基づかない特殊な工事が発生したためとの回答がありました。他方、各一般ガス導管事業者の託送供給約款等には見積単価表に基づかない特殊な工事であっても、その工事金額は、その工事に要する材料費、労務費等の費用に基づき算出した個別の設計見積金額にするものと記載されています。これを踏まえ、当該特殊な工事であっても、その工事金額は、その工事に要する費用に基づき算出した個別の設計見積金額となるよう、各一般ガス導管事業者に対し、2019年10月に当委員会事務局から日本ガス協会を経由して周知徹底を行いました。
(5)法的分離に伴う行為規制
「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」において2022年度から、導管規模等政令で定める要件に該当する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者の法的分離を実施し、併せて、法的分離された一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者とその特定関係事業者(以下、「ガス導管事業者等」という。)に行為規制を導入することが規定されたところ、その詳細は経済産業省令に定めることとされています。
そこで、2019年9月より、電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合において、ガス導管事業者等にかかる行為規制の詳細について検討を行い、2020年3月31日の制度設計専門会合において「2022年度から導入する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について」をとりまとめました。
○とりまとめの内容(例)
①社名、商標、広告・宣伝等に関する規律
(ア)法的分離の対象となる一般ガス導管事業者(以下、「特別一般ガス導管事業者」という。)がその特定関係事業者たるガス小売事業者またはガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号、商標を用いることを原則禁止とする
(イ)一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門が、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業またはガス製造事業に係る業務を営む部門の営業活動を有利にする広告、宣伝その他の営業行為を行うことを禁止とする(特定ガス導管事業者も同様に規定)
②取締役等及び従業者の兼職に関する規律の詳細
(ア)取締役等の兼職禁止の例外について具体的に規定
(イ)兼職禁止の対象となる従業者の範囲を具体的に規定
③グループ内での取引に関する規律の詳細
取引規制の対象となる特別一般ガス導管事業者と「特殊の関係のある者」を具体的に規定
④業務の受委託の禁止の例外
(ア)特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者及びその子会社等に例外的に託送業務等を委託することができる要件
(イ)特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者から小売・製造業務を例外的に受託するができる要件
⑤情報の適正な管理のための体制整備等 (特定ガス導管事業者も同様に規定)
(ア)一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門と当該一般ガス導管者のガス小売事業またはガス製造事業に係る業務を営む部門とが建物を共用する場合には、別フロアにするなど、物理的隔絶を担保し、入室制限等を行うこと
(イ)一般ガス導管事業者は、自らの託送供給等業務の実施状況を適切に監視するための体制整備を行うこと
(ウ)内部規程の整備、従業者等の研修・管理などの法令遵守計画を策定し、その計画を実施すること 等
※一部の項目においては、条件に該当する一般ガス導管事業者に限る_
5. ガス市場のさらなる効率化、競争促進のための取組
(1)ガス市場での競争促進策の検討
電力市場及びガス市場における競争を促進することによって、需要家の利益を最大化し、電気事業及びガス事業の健全な発達を図る観点から、これらの市場の競争促進策(競争評価、卸取引、小売取引の在り方等)を検討する必要があります。このため、電力・ガス監視等委員会事務局長の私的懇談会として、2017年10月より競争的な電力・ガス市場研究会(以下、「競争研」という。)を開催し、ガスシステム改革の趣旨を踏まえて、より一層競争を促進していくため、ガス市場における競争促進策の検討を行いました。
具体的には、①ガス事業における市場の画定の理論的整理を行ったうえで、②ガス小売市場と③ガス卸市場について、それぞれの競争政策上の課題の検討を行い、中間論点整理を取りまとめました。以下がその概要です。
①ガス事業における市場の画定
市場画定の理論的、実務的な目的・位置づけ等については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」(以下、「独禁法」という。)においても多くの議論がありますが、客観的、論理的な議論を進める上で有用です。ガス事業法の観点からも、独禁法における市場画定の考え方を踏まえて、市場支配的事業者の行為等によってどのような市場で競争に歪みが生じる可能性があるかを検討し、必要な措置を検討することが有益です。
競争研における議論では、ガス事業における市場画定として、電力市場と比較すると卸取引は限定的ですが、導管でつながっているエリア内では、理論的には、競争は可能であると考えられ、地理的にはそのような市場画定が将来的にありうるとの整理を行いました。
ただし、現状としては、導管が物理的につながっているエリアであっても、各社の間での供給区域を越える競争は相当に限定的であるといった実態を踏まえれば、事実上は市場が分割されることになっている可能性があることから、越境取引の実態、越境託送の状況等を十分に踏まえて、実証的に検討する必要があります。また、熱量、圧力、成分等の違い等によりエリア間またはエリア内の競争に制約がある場合には、個別の判断が必要となる可能性もあると考えられます。
②ガス小売市場における競争政策上の課題
一般論として、契約期間は、当事者の合意によることが原則であるが、ガス市場において存在するとの指摘がある長期契約を高額の違約金によって担保するような取引慣行(電力市場においても一部存在するとの指摘がある)は、ガス事業法上は、サンクコストになるような投資が必要といった事情により正当化しうる場合を除いては、経済合理性が乏しいものであり、競争研における議論においても、そもそも、ガス事業において、不当に高額な違約金を伴う長期契約を締結する合理性について大いに疑問があり、そのような取引慣行の合理性は検証される必要があると整理されました。
特に、ガスについては、長期契約とその解除に伴う高額の違約金を課す取引慣行について、LNGの引き取り量の削減に限界がある等の経緯を主張する指摘があるが、本来的には、企業自身が調達から販売までリスク管理を行う余地があり、また、需要離脱が生じた場合にも同量を競争者等に卸供給を行うことによって解決可能であるため、ガス事業法上の考え方としては、需要家のためにサンクコストとなる特別の投資を行った場合などの例外的な場合を除けば、基本的には、正当化は困難です。このため、市場支配的事業者や市場における有力な地位にある事業者による長期契約に関する規制の在り方について、さらに検討される必要があります。
③ガス卸市場における競争政策上の課題
ガス小売市場の競争促進に向けて、現在及び将来の需要者に資するために、取引所創設等の取引量の増大に向けた措置、ガス卸市場の支配的事業者等による自社の小売部門と同水準での卸供給に向けた措置などについて、ガス事業法の枠組みの中で検討を行い、必要な措置を講ずることが必要であるとの整理を行いました。
関連して、現行の実務において、一部の地域で旧一般ガス事業者等によって行われているワンタッチ卸(小売事業者は卸事業者から需要場所でガスの卸供給を受ける仕組み)は、ガスの調達、託送契約及び同時同量オペレーションを卸事業者に委ねることができるという点で、新規参入の促進に寄与するものであり、保安業務の委託の円滑化とともに実施することで、有益であるとの指摘がありました。
(2)ガスにおけるスイッチング業務等の標準化
小売全面自由化前、ガスシステム改革小委員会においてスイッチング業務フロー等を標準化することと整理されたことを受けて、日本ガス協会が主体となって標準化を進めてきました。他方、実際にはスイッチング業務フロー等の標準化は不十分であり、ガス導管事業者毎に業務フローやフォーマットが異なることによって、複数のエリアに参入する事業者の業務コストの増加を招き、新規参入者の負担となっていることが、2017年11月の第24回制度設計専門会合で新規参入者より指摘されました。
これを受けて、委員会は、日本ガス協会が行ってきたスイッチング業務等の標準化状況と今後の対応方針を確認・整理するとともに、スイッチング環境等のさらなる整備に向けて検討することとしました。
円滑なスイッチングの実現に向けて、スイッチング業務をはじめとする小売事業者と導管事業者との間で発生する業務の標準化を検討しました。具体的には、(ア)業務フロー(各業務に必要な申込・報告等の手順、必要な様式を作業プロセスとともに明らかにしたフロー)、(イ)要求項目(各様式でやりとりする情報項目)、(ウ)情報共有手段(各様式をやりとりするための手段)、(エ)レイアウト(各様式のレイアウト)の標準化を図りました。
2018年2月から電気・石油を含む新小売事業者、一般ガス導管事業者として日本ガス協会、委員会事務局との間で検討会議を定期的に開催、スイッチング業務等の標準化に向けた協議を実施し、今般、2019年2月に開催された制度設計専門会合にてとりまとめの報告を行いました。
その後、業務マニュアルの作成、事業者への周知を業界団体とも連携して行い、ガススイッチング業務等に関する標準的な手続マニュアルをとりまとめ、公表すると共に、標準化された業務の運用について導管事業者に求めました。
【第362-5-1】ガスのスイッチング業務等の標準化の考え方
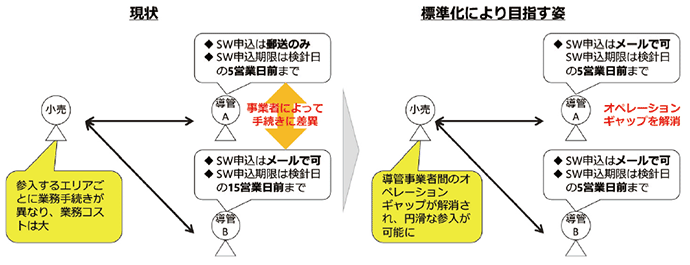
- 出典:
- 第36回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019年2月15日)より抜粋
【第362-5-2】ガスのスイッチング業務等の標準化内容
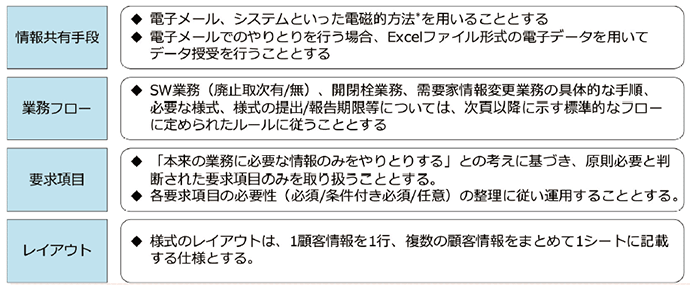
- 出典:
- 第36回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019年2月15日)を基に電力・ガス監視等委員会作成
(3)ガス卸市場における競争政策上の課題
制度設計専門会合において、都市ガスの卸取引に関する競争の促進について、卸受事業者に対する実態調査や都市ガスの卸元事業者へのヒアリング等を踏まえた検討を行い、中途解約補償料を伴う長期契約及び需要家情報の取り扱いについて、以下の問題に対する考え方の整理を行いました。
都市ガスの卸供給に伴い、卸元事業者が基地建設、導管敷設等の設備投資を行うことによって、卸受事業者に対して卸供給することが主流であった時期においては、中途解約補償料が盛り込まれた10年を超える長期契約を当事者間で締結することは、一般的です。
現在は一定程度インフラの整備が進み、かつ、卸市場及び小売市場の参入が自由化されており、競争の促進が重要な課題となっています。そのような中で、都市ガスの卸契約について、事務局による実態調査を踏まえ、その契約期間や、中途解約補償料の設定方法・水準の考え方を検討されていくことの必要性について指摘がありました。
また、ガス卸市場で卸元事業者と卸受事業者が小売事業において競争関係にあり、または、その可能性がある場合において、具体的な需要家の情報の提供を卸元事業者が卸受事業者に求め、当該情報を卸元事業者が卸受事業者と共有するような場合は、ガス卸市場及び小売市場の競争を阻害することにつながるおそれもある、との指摘もありました。
上記の問題の整理を踏まえ、都市ガスの卸元事業者(旧一般ガス事業者、国内天然ガス事業者、旧一電等)に対して、以下内容を要旨とする自主的な取組を2019年9月に要請を行いました。
①中途解約補償料を伴う長期契約について
- 有力な地位にある(または見込まれる)都市ガスの卸元事業者が、ガスの卸売において高額な中途解約補償料を伴う長期契約を締結することは、長期の契約及び違約金の水準という2要素があいまって、競争者(卸元事業者)の取引機会を過小にする可能性があります。
- このため、資料内で示した考え方を踏まえ、都市ガスの卸元事業者に対し、今後更新する中途解約補償料を伴う長期契約については、合理的な根拠に基づく中途解約補償料と契約期間の設定とするよう求めることとします。
②需要家情報の取り扱いについて)
- ガス卸市場で卸元事業者と卸受事業者が小売事業において競争関係にある(またはその可能性がある)場合において、具体的な需要家の情報の提供を卸元事業者が卸受事業者に求め、当該情報を卸元事業者が卸受事業者と共有することは、卸取引の円滑な実施のために必要不可欠な場合など合理的な理由がある場合を除いて、ガス卸市場及び小売市場の競争を阻害することにつながるおそれもあると考えられます。
- このため、資料内で示した考え方を踏まえ、都市ガスの卸元事業者に対し、合理的な理由がない場合は需要家情報の提供を求めないこと、合理的な理由があって需要家情報を入手する場合には、その情報の管理体制の構築等について適切に対応すること、を求めることとします。
今後の対応としては、上記までに示した考え方を踏まえ、適切な時期において、フォローアップ調査を行うこととしております。
6. ガス安全小委員会における議論
ガスの小売全面自由化が行われ、新たなガス小売事業者の参入が開始されたことから、ガス小売事業者の保安水準の維持、向上を図る施策の検討をガス安全小委員会において実施しました。需要家にガス小売事業者の自主保安活動の特徴的な取組状況をホームページで分かりやすく紹介し、消費者が保安面で優れているガス小売事業者を選択することを支援する「見える化」制度を2017年度に構築しました。2019年度においても引き続き、「見える化」制度を実施し、自主保安活動の推進を後押ししています。
また、規制改革推進会議において、内管の保安と工事について競争メカニズムが働いていないとの指摘がありました。これを受け、保安水準の確保及び一般ガス導管事業者の自主的な保安の取組を前提に、内管保安業務を委託する際の委託要件とすべき項目を精査・抽出し、各一般ガス導管事業者における適切な委託先選定が行われる仕組み作りについて対応方針を示しました。
7. 熱供給システム改革の概要
熱供給システム改革は、電力・ガスシステム改革とあいまって、熱電一体供給も含めたエネルギー供給を効率的に実施できるようにするため、2013年11月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に開催された「ガスシステム小委員会」において熱供給事業の在り方などを検討・審議し、2015年6月の「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第74号)」の成立を受けた後は、熱供給システム改革を着実に進めていく上で必要な実務的な課題を含めた具体的な制度設計について議論を行いました。2016年4月に実施された熱供給システム改革では、許可制としていた熱供給事業への参入規制を登録制とし、料金規制や供給義務などを撤廃し(ただし、他の熱源の選択が困難な地域では、経過措置として料金規制を継続)、熱供給事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課しました。
熱供給システム改革の実行により、事業環境の整備が行われ、エネルギー市場の垣根の撤廃や異業種からの参入が促進され、電力・ガスシステム改革が一体的に推進していくことが期待されています。