第1節 電力システム改革の推進
1. 電力広域的運営推進機関の取組
東日本大震災により、大規模電源が被災する中、東西の周波数変換設備や地域間連系線の容量に制約があり、また、広域的な系統運用が十分にできませんでした。このため、不足する電力供給を十分に手当てすることができず、国民生活に大きな影響を与えたことから、2013年11月に成立した「電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)」に基づき、強い情報収集権限と調整権限の下で広域的な系統計画の策定や需給調整等を行う「電力広域的運営推進機関(以下、「広域機関」という。)」が2015年4月に発足しました。
広域機関では、地域間連系線等の整備等に関する方向性を整理した「広域系統長期方針」を取りまとめるとともに、東西の周波数変換設備及び東北東京間連系線の増強に関する「広域系統整備計画」を策定し、増強に向けた工事の準備が行われています。また、電力系統の増強に当たっての発電設備設置者と一般送配電事業者の費用負担のルール(発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担の在り方に関する指針)に基づく一般負担の上限額の見直しや既存系統の最大限の活用に向け、「日本版コネクト&マネージ」の検討・実現など、系統運用ルールの整備にも取り組んでいます。また、電気事業法第28条の44第1項に基づく電力融通の指示も行っています。2019年度は例えば、9月に台風等の影響によって全国的に高気温となり、想定以上に需要が増加し、東京・中部・中国・九州エリアにおいて需給状況が悪化するおそれがあったため、関係する一般送配電事業者に電力融通の指示を行いました。
2. 電力の小売全面自由化への対応
家庭を含めた全ての電気の利用者が電力供給者を選択できるようにするため、2016年4月に電力の小売全面自由化を実施しました。全面自由化に際しては、まず旧一般電気事業や旧特定規模電気事業といった類型に代わる区分として、小売電気事業(登録制)、送配電事業(許可制)、発電事業(届出制)という事業ごとの類型を設け、それぞれ必要な規制を課すこととしました。具体的には、自由化後も電力の安定供給を確保し、需要家保護を図るため、以下のような様々な措置を講じています。
まず、電気の安定供給を確保するための措置として、適切な投資や人材の確保の必要性に鑑み、一般送配電事業者に対して、需給バランス維持、送配電網の建設・保守、最終保障サービスの提供、離島のユニバーサルサービスの提供を義務付けるとともに、これらを着実に実施できるよう、地域独占と総括原価方式の託送料金規制(認可制)を措置しました。また、小売電気事業者に対して、需要を賄うために必要な供給力を確保することを義務付けることとし、将来的な供給力不足が見込まれる場合に備えたセーフティネットとして、広域機関が発電所の建設者を公募する仕組みを創設しました。さらに、需要家保護を図るための措置として、小売電気事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課すとともに、旧一般電気事業者(以下、「旧一電」という。)に対し、2020年3月末まで経過措置として料金規制を継続することとしていたところです。ただし、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして、経済産業大臣が指定する指定旧供給区域のみ経過措置料金が存続することとされています。2019年4月、電力・ガス取引監視等委員会から、消費者等の状況、競争者による競争圧力及び競争環境の持続性の状況を総合的に考慮したうえで、すべての供給区域において、2020年4月の時点においては、経過措置料金を存続させることが適当と考えられる旨、経済産業大臣に対する意見が示されました。本意見を踏まえ、2019年7月、すべての旧一電に係る供給区域について、小売規制料金に係る経過措置の存続のための指定が行われました。以降、概ね年に1回程度、審査対象区域の検討を行うこととしております。
加えて、小売全面自由化に伴い、多種多様な事業者が卸電力取引所で取引を行う機会が増加することや、一時間前市場の創設等、制度変更により卸電力市場を利用して不当に利益を得るケースが想定されることから、不正取引(相場操縦等)の防止、国による市場監視、取引所の運営の適切性確保を可能とする規制措置を講じています。こうした措置を通じて、市場の透明性と廉潔性を維持することが、卸電力市場の活性化に資すること、ひいては小売電力市場の活性化につながることと考えています。
3.電力の小売全面自由化の進捗状況
(1)電気事業に係る制度設計について
2015年9月に開催された電力取引監視等委員会(2016年4月に電力・ガス取引監視等委員会に改組。)において、①小売営業に関するルール、②卸電力市場における不公正取引の取締手法、③今後の託送料金制度の在り方など、電力取引の監視に必要な詳細な制度設計の議論が進められてきました。
また、電力システム改革が進展する中で、電力分野において、エネルギー政策の基本的視点である、安全性、安定供給、経済効率性、及び環境適合を同時に達成していくことが求められます。効率的かつ競争的な電力市場の整備等の環境整備を進めると同時に、電力システム改革が我が国経済における成長戦略としての効果を最大限に発揮するためにも、市場における担い手としてのエネルギー産業を国際的にも競争力のあるものとしていくことが必要不可欠です。このため、電気事業制度に係る制度設計をはじめとして、電力分野の産業競争力強化に向けた幅広い政策課題を検討する場として、2015年10月、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の下に電力基本政策小委員会を開催し、2016年10月より、電力・ガス基本政策小委員会に検討の場を移しています。ここでは例えば、先述の料金規制の経過措置について2017年10月から議論が開始され、2018年度中には、規制下にある料金メニューぞれぞれの用途や契約状況が確認され、また、それらに関する新電力や需要家へのヒアリング・アンケート結果等を踏まえた議論が行われたほか、燃料費調整度や最終保障供給制度の在り方など、多岐に渡る議論が行われました。ほかにも、「電気事業法(昭和39年法律第170号)」に基づき、2020年度の発送電分離を前にした検証が開始され、2018年9月から合計7回にわたり、小売全面自由化後の競争の状況や広域機関の活動状況のほか、電力各社のシステム対応状況などについて議論を実施の上、2019年6月に送配電部門の法的分離に向けた電気事業を取り巻く状況についての検証結果を取りまとめました。
このように、電力システム改革の制度設計については、総合資源エネルギー調査会や電力・ガス取引監視等委員会において検討してきたところであり、引き続き適切な場において検討を進めます。
(2)登録小売電気事業者数について
2020年3月31日時点で646者を登録しています。
この小売電気事業登録は、法令に則り、資源エネルギー庁が、最大需要電力に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがあるか、電力・ガス取引監視等委員会が、電気の使用者の利益の保護のための措置が講じられているかといった観点から、それぞれ審査を行っています。
登録された事業者の内訳は、もともと高圧の小売電気事業を行っていた新電力事業者(PPS)に加え、LPガス及び都市ガス関係、石油関係、通信・放送・鉄道関係等の事業者など、非常に多岐にわたります。従来の料金体系とは異なる段階別料金や既存事業とのセット割、時間帯に応じて料金差を付ける時間帯別料金等の新たなメニューの提供が見られます。
また、異業種の事業者間の連携や、地域の枠を超えた事業統合なども始まっており、事業者の事業機会の拡大も進んでいます。
(3) 新電力へのスイッチング(契約先の切替え)実績
2019年12月までの電力取引報によると、電力の小売全面自由化で新たに自由化された低圧部門において、新電力への契約の切替えを選択した需要家が全国で約1,226万件となっています。また、地域の既存電力会社が設定した自由料金メニューへの切替えを選択した需要家も約706万件となっており、両者を合わせると、約1,932万件の消費者が自由料金メニューへの切替えを行っています。また、2019年12月時点で電力市場全体としては、販売電力量ベースの新電力のシェアで約16.2%となっています。
地域別には、低圧分野では、東京・関西地域において新電力への切替えが進展しています。
(4)料金メニューの多様化
新電力の提供する料金メニューを見ると、全体的な傾向としては、基本料金と従量料金の二部料金制からなる既存の料金メニューに準じた料金設定が多く見られます。他方、一部では、完全従量料金メニュー、定額料金メニュー、指定された時間帯における節電状況に応じた割引メニューやセットプランなど、新しい料金メニューも提供されるようになっています。
なお、多くの新電力は、料金規制の残る大手電力会社が毎月公表する燃料費調整額を引用した料金メニューを採用しておりますが、経済産業省では需要家の選択肢を拡大するとともに、予算執行の予見性を高めるなどの総合的な観点から、2019年度中に経済産業省庁舎で使用する電気の調達に際して、燃料費調整を行わないことを条件とする公募を行い、複数の事業者からの応札の結果、株式会社V-Powerと契約を締結しました。
また、再生可能エネルギー等の電源構成や、地産地消型の電気であることを訴求ポイントとして顧客の獲得を試みる小売電気事業者の参入も見られ、中には需要家が発電所を選んで得票数の多かった発電所に報奨金を与えることができるなど、特色のある小売電気事業者も存在しています。
さらに、電力消費の見える化(電気の使用状況の可視化)や、電気の使用状況等の情報を利用した家庭の見守りサービスなども提供され始めています。応援するスポーツチームとの繋がりや里山の景観保存など、需要家の好みや価値観に訴求するサービスも始まっています。
加えて、需要家側の取組として、電力コスト削減の観点から、同種の事業者間における電気の共同調達や、地域を問わない事業グループ全体としての一括調達の動きも出始めています。
4. 電力市場における適正な取引確保のための厳正な監視など
(1)小売部門の監視
2016年4月には電気の小売事業への参入が全面自由化され、家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択できることとなりました。こうした中、電気の小売供給に関する取引の適正化を図るため、「電力の小売営業に関する指針」を踏まえ、需要家への情報提供や契約の形態・内容などについて、電気事業法上問題となる行為を行っている事業者に対して指導を行うなど、事業者の営業活動の監視などを行っています。
具体的には、2019年度には以下のような事案について指導、勧告などを実施しました。
①勧告
(ア)関西電力株式会社へ行った勧告(2019年8月)
関西電力株式会社は、電力及びガス供給契約の締結をした際、20,297件の電力供給契約について契約締結後交付書面を交付せず、うち17,016件は契約締結前交付書面を交付しませんでした。
このため、電気事業法及び「ガス事業法(昭和29年法律第51号)」に基づき、(ⅰ)今後同様行為を行わないよう、必要な措置を講ずること、(ⅱ)上記(ⅰ)に基づいて講じた措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること、(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)に基づいて講じた措置について、文書で報告することを求める業務改善勧告を行いました。
(イ) あくびコミュニケーションズ株式会社へ行った勧告(2019年12月)
あくびコミュニケーションズ株式会社は、少なくとも9,159件の需要家を対象とする小売供給契約の変更(電気料金の支払期日の変更を内容とするもの)について、電気事業法の規定による説明及び書面交付をしませんでした。また、同社は、2019年10月下旬、同月までの電気料金が請求済みであったにもかかわらず、一部の需要家について口座引落しのための決済処理を行い、7,862件の需要家から合計6,598万2,225円を過大に徴収しました。
このため、2019年12月、電気事業法に基づき、(ⅰ)電気料金の支払方法の変更について、電気事業法の規定による説明及び書面交付をしなかった需要家に対し、適切な措置を講ずること、(ⅱ)電気料金を過大に徴収した需要家に対し、適切な措置を講ずること。また、同様の事案の有無を調査し、調査結果を踏まえ需要家保護の観点から適切な措置を講ずること、(ⅲ)電気事業法の説明義務及び書面交付義務に違反する事案並びに電気料金を過大に徴収する事案が今後発生しないよう必要な措置を講ずること、(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までに基づいて講じた措置について、文書で報告することを求める業務改善勧告を行いました。
②指導
(ア)小売電気事業者A社へ行った指導(2019年4月)
A社は、2018年10月から2019年2月までの間に、特定の者から、その者が指定する多数の需要家について合計723件の電気の小売供給契約の申込みを受け、うち426件について小売供給契約を締結したが、そのうち少なくとも5件の小売供給契約について、需要家の意思を確認しないまま契約締結手続を行い、電気事業法に規定する供給条件の説明及び書面の交付を行いませんでした。当該行為は、需要家の意思に反し、小売供給契約を行うものであって、需要家の利益を著しく害する行為であることから、A社に対し、電力の適正な取引の確保を図るため、所要の改善措置を講じるように指導を行いました。
(イ)小売電気事業者B社へ行った指導(2019年8月)
B社は、2019年5月28日から同年6月5日までの間に、同社の電力申込みウェブサイトにおいて、重要事項説明ページのリンクが切れていたことにより、重要事項説明を表示しませんでした。これにより、申し込みをした需要家に対し、供給条件の説明義務違反及び契約締結前交付書面の交付義務違反が生じたため、B社に対し、電力の適正な取引の確保を図るため、所要の改善措置を講じるように指導を行いました。
(2)卸部門の監視
電気の適正な取引を確保するため、卸電力市場における取引の状況を把握・分析するとともに、問題となる行為等が見られた場合には指導等を行っています。
また、四半期毎に、旧一電の自主的取組や電力市場における競争状況を定点的に分析・検証した電力市場のモニタリングレポートを作成・公表しています。第44回制度設計専門会合までに、制度設計ワーキング・グループでの報告も含め、累計で21回にわたりモニタリングレポートを作成・公表しました。
【第361-4-1】2019年7月~ 9月の報告における主要指標
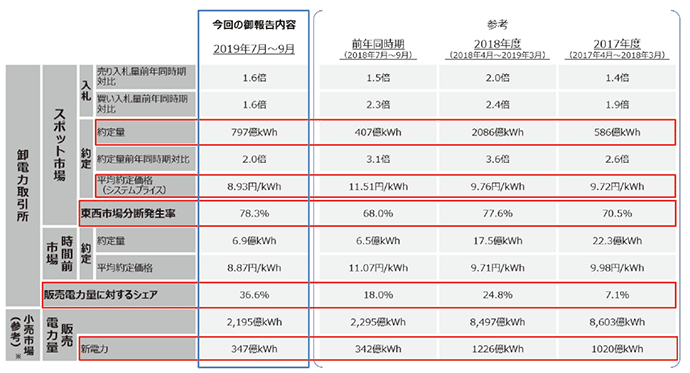
- 出典:
- 第44回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019年12月17日)を基に電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
(3)原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価
「電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)」(以下、「第2弾改正法」という。)附則の経過措置に基づく小売電気料金については、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないかなどを経済産業省において確認し、その結果を公表することとなっています。
電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣からの意見聴取を受けて、料金審査専門会合において2018年度の状況について評価及び確認を行い、2020年1月、以下のとおりとりまとめました。
これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣に対し、「電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20160325資第12号)第2(7)④に照らし、経過措置料金の変更申請を命じることが必要となる事業者はいなかった旨回答しました。
料金審査専門会合のとりまとめ(2020年1月)
①事後評価のポイント
原価算定期間を終了しているみなし小売電気事業者8社(北海道電力、東北電力、東京電力EP、中部電力、北陸電力、中国電力、四国電力及び沖縄電力)※について、「電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20160325資第12号)第2(7)④に基づく値下げ認可申請の必要がないか確認を行いました。
※ 原価算定期間終了前の関西電力及び九州電力は、事後評価の対象外。
②料金審査専門会合の開催実績
2020年1月21日 第39回料金審査専門会合
③事後評価の結果
第2弾改正法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の「電気事業法(昭和39年法律第170号)」第23条第1項の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令に係る「電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20160325資第12号)第2(7)④に照らし、値下げ認可申請の必要は認められませんでした。評価の詳細は以下のとおりです。
【第361-4-2】料金変更認可申請命令に係る審査基準
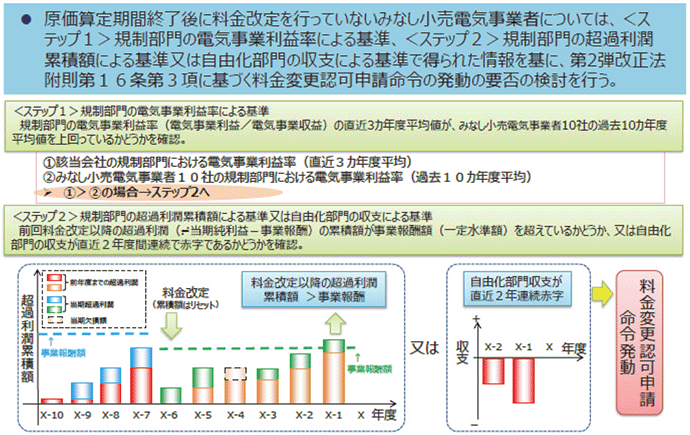
- 出典:
- 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
【第361-4-3】審査基準の適用結果
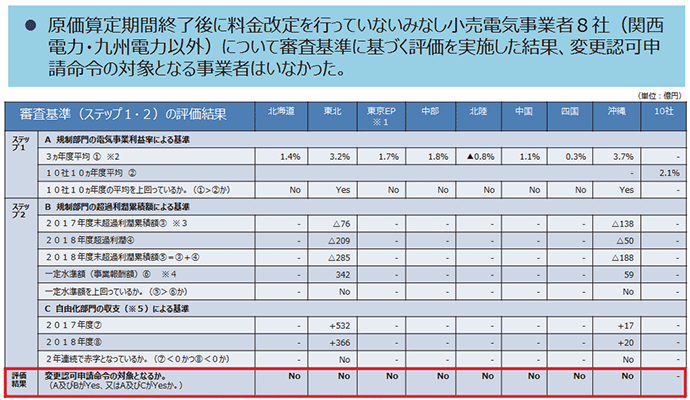
※1:2015年度以前は旧東京電力の数値、2016年度以降は東京電力エナジーパートナーの数値を基に算出。
※2:各年度の規制部門の電気事業利益率(%)の単純平均
※3:2015年度までの超過利潤累積額のうち旧選択約款部分を除いた金額
※4:一定水準額:規制部門(特定小売供給約款に係る分に限る)に相当する事業報酬額
- 出典:
- 各事業者の部門別収支計算書、各事業者へのヒアリングにより電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
審査基準のステップ1「電気事業利益率による基準」では、個社の直近3か年度平均の利益率が10社10か年度平均の利益率を上回る会社は、東北電力及び沖縄電力の2社でした。ステップ1に該当した2社について、審査基準のステップ2「超過利潤累積額による基準」では、2018年度末超過利潤累積額は一定水準額である事業報酬額を下回っており、ステップ2「自由化部門の収支による基準」では、直近2年連続で自由化部門の収支が赤字となっていませんでした。以上より、原価算定期間を終了しているみなし小売電気事業者8社(関西電力・九州電力以外)について、審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の検討対象となる事業者はいませんでした。
以上を踏まえ、2019年度の事後評価の対象となった事業者について、現行の認可料金に関する値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでした。
(4)一般送配電事業者の収支状況(託送収支)の事後評価
我が国の電力系統を取り巻く事業環境は、人口減少や省エネルギーの進展等により電力需要が伸び悩む傾向にある一方で、再生可能エネルギーの導入拡大による系統連系ニーズや経済成長に応じて整備されてきた送配電設備の高経年化への対応が増大するなど、大きく変化しつつあります。
こうした事業環境の変化に対応しつつ、将来の託送料金を最大限抑制するため、一般送配電事業者においては、経営効率化等の取組によりできるだけ費用を抑制していくとともに、再生可能エネルギーの導入拡大や将来の安定供給等に備えるべく、計画的かつ効率的に設備投資を行っていくことが求められます。
以上のような問題意識の下、電力・ガス取引監視等委員会は、料金審査専門会合において、一般送配電事業者の2018年度託送収支の事後評価を行い、2020年2月、以下のとおり取りまとめました。
<料金審査専門会合のとりまとめ内容(抜粋)>
①託送収支の状況
2018年度の当期超過利潤累積額について、託送供給等約款の変更認可申請命令(値下げ命令)の発動基準となる一定の水準を超過した事業者はいませんでした(ストック管理)。また、想定単価と実績単価の乖離率について、変更認可申請命令の発動基準を超過した事業者はいませんでした(フロー管理)。東京電力PGについては2017年度収支から廃炉等負担金を踏まえて厳格な値下げ基準が適用されることとなりましたが、当該基準に達していませんでした。
収入面においては、節電・省エネ等により電力需要が減少したため、北陸電力を除く9社で実績収入が想定原価を下回りました。特に、北海道電力、関西電力は5%以上減少となりました。
費用面においては、北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、沖縄電力の5社において、主に人件費・委託費等の増加により、実績費用が想定原価を上回った一方で、東京電力PG、中部電力、関西電力、四国電力、九州電力の5社においては、主に設備関連費の減少により実績費用が想定原価を下回りました。この結果、2018年度の託送収支においては、東京電力PG、中部電力を除く8社で当期超過利潤がマイナス(当期欠損)となりました。
なお、実績費用が増加した5社中3社(北海道電力、北陸電力、中国電力)においても、設備関連費は想定原価を下回っていました。一般送配電事業者の収支全体としては、収入が減少または横ばいとなる中で、総じて人件費・委託費が維持・増加し、設備関連費が減少しているといえます。
②効率化に向けた取組状況
(ア)経営効率化の実施状況
ヒアリング対象事業者3社(北海道電力、東京電力PG及び中部電力)における経営効率化の取組状況を確認したところ、例えば北海道電力では、抜本的な効率化に向けた意識改革を全社的に進めるべく、2018年12月から東京電力PGや中部電力でも取り入れている「カイゼン」に取り組んでいました。また、需要家からの設備障害に関する通報の際、インターネット経由で当該設備写真を送付してもらうことにより設備障害の緊急性、現地出向の必要性等を迅速に判断できるWebツールを開発するといった東京電力PGの取組など、IoTを活用しながら効率化を進めていることを確認しました。こうした各社の費用削減に向けた取組は一定の評価ができます。各社においては、今回紹介された新たな取組事例も参考に、引き続き、更なる効率化やコスト削減に向けて様々な取組を進めていくべきです。また、各社間で協力しながら、各社による効率化事例を全社共通の取組へと広げていくことを期待します。
なお、前回の事後評価では、送配電部門全体としての効率化の実績・見通し・目標や個別取組に関する各社の説明が必ずしも具体的・定量的ではないこと等を課題として指摘しましたが、昨年3月に各社が自主的に策定・公表した調達改革ロードマップにおいて、全10社で統一した仕様に基づく調達についてKPIを設定するなど、一定の進展も見られました。ただし、その取組も限られた範囲のものとなっています。
今後、再生可能エネルギー電源等の系統連系ニーズの増加や高経年化への対応など、送配電設備に関する費用上昇が見込まれます。公共性のある財・サービスの提供を独占的に担う各社においては、東京電力PGが2025年度までに「託送料金原価2016年度比▲1,500億円」と掲げているように、中長期的なコスト削減目標を掲げて、効率化に向けた自社の対応や取組の全体像を具体的かつ定量的に説明していくことが求められます。
(イ)調達合理化に向けた取組状況
(i)仕様の統一化
仕様の統一化について、前回の事後評価で各社が掲げた今後の取組の進捗状況を確認したところ、超高圧送電線の付属品や154kVCVケーブル、66・77kV変圧器の付帯品の仕様統一化に向けた検討が継続されていること等が報告されました。また、架空送電線(ASCR/AC)、66・77kVガス遮断器、6.6kV地中ケーブルについて、仕様統一化や調達改革に向けた自主的ロードマップを各社が策定し、全10社による仕様統一化に向けた調整が完了したこと等も報告されました。
付属品や個別の要求仕様(オプション)など、基本仕様に上乗せした各社独自の仕様の存在が調達市場の規模を小さくし、調達コストの上昇につながっている可能性もあります。また、設備仕様の共通化は災害時等の復旧作業の円滑化等に資するとも指摘されています。各社においては、調達改革ロードマップの品目拡大や国際調達を可能にすることも含め、調達コストの削減に向けて、さらなる仕様の標準化・共通化に取り組むべきです。将来的には、原則各社共通仕様とし、自社仕様を用いる場合はその合理性について説明が求められるといった方向に考え方を転換していくことが期待されます。
(ii)競争発注比率/発注方法の工夫・改善
東京電力PGは競争発注比率が70%を超える一方、北海道電力及び中部電力は競争発注比率が40%台となっていました。北海道電力、中部電力においては、特に配電工事にかかる比率が7%程度と低くなっていましたが、両社ともに、発注の競争化に向けて取り組んでいることを確認しました。
また、今回の事後評価では、競争発注比率の向上は透明性を高めていく観点から進めていくべきであるものの、新規取引先の拡大など、実質的な競争を働かせる取組を推進していくことが非常に重要との認識が改めて共有されました。地元の中小・中堅企業などに取引先を拡大していくことは、競争を通じた調達コストの低減のみならず、災害時等に備えた体制整備などレジリエンス強化の観点からも重要です。その観点から、配電工事に係る机上管理業務と施工を分離発注することで、申請書作成等の事務負担が原因で入札できないという制約を取り除き、地元工事会社などの参入促進を図っているという中部電力の取組は評価に値します。
各社においては、競争発注比率を可能な限り高めていくとともに、今回紹介された中部電力の取組事例や、前回の事後評価で東京電力PGから紹介された取引先との協働(コスト削減及びそれにより生まれた利益の共有)によるWin-Winの関係構築といった取組なども参考に、発注方法のさらなる工夫・改善に向けて継続的に取り組んでいくべきです。
(ウ)計画的かつ効率的な高経年化対策の推進
高経年化対策の状況を確認したところ、北海道電力及び東京電力PGからは中長期的にみた更新工事量の見通しが提示されるとともに、東京電力PGや中部電力からは10年程度、北海道電力からは5年程度の工事量ベースでの更新計画が提示されました。一方で、中部電力が1年あたりの更新投資想定額を提示した以外は、中長期的にみた更新投資額の見通しや計画は提示されませんでした。このため、安定供給のために必要となる投資金額が十分確保できているか定量的に確認できるよう、投資額に関する計画についても提示してほしいとの意見が多く見られました。
高度成長期に整備された設備が今後更新の時期を迎えます。こうした中で、安定供給を確保しつつ、託送料金を抑制するには、設備ごとに、劣化状況等を踏まえて故障確率及び故障した場合の影響の大きさを評価し、修繕・更新等の対策に要する費用を見積もり、これらを踏まえて最適なタイミング・方法で対策を講じるなど、できるだけ効率的に高経年化対策を進めていくことが重要です。またその際、施工力の観点から、工事量をできるだけ平準化して対策を進めることが望ましく、中長期的に計画的に進めることが有効であると考えられます。
東京電力PG及び中部電力からは、IoTやAI等を活用したアセットマネジメントシステムの導入により、点検・故障等のデータをデータベース化して分析・活用し、設備投資・更新の最適化や平準化を進めていく方向で取り組んでいるとの表明がありましたが、これを各社共通の取組として進めていくことが求められます。このシステムが適切に機能すれば、設備投資や高経年化対策の計画を効率的なものへと深化させていくことが可能になるとともに、系統利用者や最終的な費用負担者である需要家が高経年化に係る工事量や投資額が適切であると判断しやすくなると考えられます。
各社においては、再生可能エネルギーの導入拡大や人口減少といった事業環境の変化も踏まえ、将来の系統がどうあるべきか検討しつつ、アセットマネジメントシステムの導入を通じて、中長期的視点で計画的かつ効率的に設備投資や高経年化対策を進めるべきです。また、設備投資や高経年化対策に係る中長期計画や進捗について、工事量のみならず投資金額も提示するなど、その取組状況を適切に説明していくことが求められます。
(エ)安定供給に向けた取組
一需要家当たりの停電回数、停電時間を確認したところ、2018年度は、地震や台風といった大規模災害の影響によって、北海道電力及び中部電力の一需要家当たりの停電回数・停電時間が大きく増加しました。東京電力PGにおいても先般の台風の影響による停電等がありましたが、各社はそれらの経験を踏まえ、アクションプランをとりまとめ、自治体を含む関係者による訓練に加え、関係機関等との連携強化、災害復旧対応に資するシステム整備(ドローン活用、活動状況のリアルタイム共有等)、需要家への情報発信の強化(他電力とのコンタクトセンターの共同運営、スマホアプリの機能拡充等)など、災害時等に備えた様々な取組を進めていました。
大規模災害時を含め、一般送配電事業者が安定供給面で果たす役割は大きいです。効率化等によるコスト削減に取り組みつつも、安定供給に必要となる投資等についてはしっかり確保していくことが重要です。
③さらなるコスト削減と質の高い電力供給の両立に向けて
再生可能エネルギーの導入拡大や送配電設備の高経年化への対応が増大する一方で、人口減少や省エネ等により電力需要が伸び悩むなど、我が国の電力系統を取り巻く事業環境が大きく変化していく中においては、再生可能エネルギーの拡大や安定供給の確保など、将来に向けた投資をしっかり確保すると同時に、さらなるコスト削減を促していくことが重要となります。一般送配電事業者の収支状況をみると、収入が減少または横ばいとなる中で、総じて設備関連費が減少していますが、この費用削減が効率化によるものであれば良いものの、本来であれば再生可能エネルギーの拡大や安定供給のために必要であった投資が先送りされたり、実施されなかったりといった結果によるものであってはなりません。
現在、資源エネルギー庁において、必要な投資促進と効率化の徹底を両立させる託送料金制度の在り方について検討が進められていますが、料金審査専門会合における事後評価で得られた経営効率化や高経年化対策等に関する知見・情報・分析結果等を活かしつつ、電力・ガス取引監視等委員会においても、収支を中心として一般送配電事業者の実態の把握・分析をさらに進め、今後の料金審査や事後評価の在り方など、託送料金制度の詳細検討を進めていくべきです。
(5)法的分離に伴う行為規制
「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」において、送配電部門の中立性を一層確保するため、2020年度から一般送配電事業者と送電事業者の法的分離を実施し、併せて、一般送配電事業者とその特定関係事業者(以下、「一般送配電事業者等」という。)及び送電事業者とその特定関係事業者(以下、「送電事業者等」という。)に行為規制を導入することが規定されたところ、その詳細は経済産業省令に定めることとされています。
そこで、電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合において一般送配電事業者等及び送電事業者等にかかる行為規制の詳細や監視の在り方等について議論を行い、「一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離に併せて導入する行為規制の詳細について」を取りまとめました。さらに、「一般送配電事業者及び送電事業者の法的分離に併せて導入する行為規制の詳細について」を踏まえ、電力の適正な取引の確保を図るために必要な行為規制を内容とする「電気事業法施行規則等」の改正を、2018年6月に電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に建議しました。建議を踏まえ、行為規制の具体的な内容等を定めるため、2018年12月に「電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)」の改正を行いました。また、とりまとめの内容については省令に反映するものに加えて、「適正な電力取引についての指針」(以下、「適取GL」という。)に反映すべきと考えられるものがあることから、そのとりまとめの内容や制度設計専門会合における議論を踏まえた適取GLの改定を2019年9月に行いました。
「適取GL」に追記される項目(例)
- 一般送配電事業者は、その特定関係事業者との間で兼職を行う者がいる場合、あらかじめ、電力
- ガス取引監視等委員会へ説明するとともに、年1回程度、その業務内容等を一般に公表することが望ましい旨
- 取締役等の兼職禁止の例外となるかどうかを判断する視点の詳細
- 一般送配電事業者は、その特定関係事業者との間で人事交流を行う場合には、社内規程等により行動規範を作成することが望ましい旨
- 一般送配電事業者は、電柱に埋め込まれたサイズの小さい表示板等に刻印された商号等(法的分離前に設置されたもの)については、「容易に視認できない場所に刻印または表示する場合」として、引き続き用いることができる旨
- 一般送配電事業者からその特定関係事業者への送配電等業務の委託禁止の例外にあたるかどうかの判断基準の詳細
5. 電力市場のさらなる効率化、競争促進のための取組
(1)卸電力取引の活性化
電力システム改革の目的である小売電気事業者間の競争を通じた安定的かつ安価な電力供給を実現するためには、小売電気事業者が小売供給に必要な電源を市場から調達できるだけの卸電力市場の活性化が不可欠となっています。このため、制度設計専門会合では、卸電力市場の活性化に向けた取組などについての議論を行っています。
具体的には、制度設計専門会合において、入札制約の整理、卸供給の在り方について検討などを実施しました。
入札制約の整理については、段差制約及び入札制約について考え方や定義の取り纏めを行い制約に対する望ましい運用方法の明確化を行いました。また、卸供給の在り方については、公正な競争を促進する等の観点から、卸供給の諾否に関する判断や交渉体制について考え方の整理を行い、旧一電に対して自主的な取り組みとして適切に対応するよう要請を行いました。
① 旧一電における、新規参入者との卸供給に関する交渉について
「競争的な電力・ガス市場研究会中間論点整理」(2018年8月)において、旧一電における、新規参入者との卸供給に関する交渉は、発電部門など新規参入者等との競争を排除する誘因を持たない部門が行うことが望ましいとして、その在り方について検討を進めていくこととした。
これを踏まえ、事務局による交渉実態等のヒアリング等を踏まえて、公正な競争を促進する等の観点から、旧一電における卸供給の諾否に関する判断の在り方や卸供給の交渉体制に関する考え方を整理し、旧一電に対して自主的な取り組みとして適切に対応するよう要請を行いました。
②JEPXにおける市場監視業務等の体制について
JEPX(日本卸電力取引所)における取引規模の著しい拡大やベースロード市場の開設をはじめとする新たな市場開設などの取組みによって、JEPXにおける各種市場の公正な取引を確保する必要性が従前にもまして増大しています。一方で、諸外国や類似の取引所においては、市場監視業務等の実施体制について、様々な取組が見られるところです。
このため、今後のJEPXにおける市場監視業務及び取引参加者の資格審査、制裁その他個別事業者の監督に類する業務を行う体制について、現時点では何らかの具体的な問題行為が生じている訳ではないものの、今後より一層、中立性、独立性を向上させていくために、既存体制の点検や所要の体制整備を行っていくことが望ましい。以上を踏まえ、2019年6月JEPXに対し、今年度中を目処に、中立性・独立性を確保しつつ、その機能を向上させるための体制について検討するよう要請を行いました。
【第361-5-1】JEPX取引量(約定量)のシェアの推移(2012年4月~ 2019年9月)
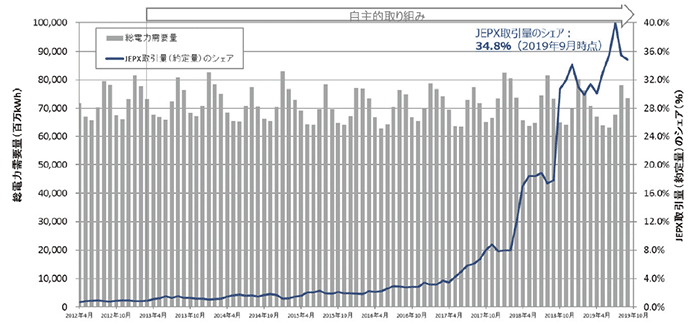
- 出典:
- 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
(2)間接オークション・間接送電権の導入
地域間(エリア間)連系線の利用については、従来、「先着優先」と「空おさえの禁止」を原則として、広域機関によって利用計画が管理されていました。電力システム改革貫徹のための政策小委員会(以下、「貫徹小委」という。)の中間とりまとめにおいては、連系線利用ルールを見直すことで、公正な競争環境の下、送電線の利用と広域メリットオーダーの達成を促し、さらなる競争活性化を通じて電気料金を最大限抑制し、事業者の事業機会の拡大を実現していくことが適当とされました。また、公平性・公正性を確保するとともに、卸電力市場の取引量増加を図るため、現行連系線利用ルールを「先着優先」から、市場原理に基づきスポット市場を介して行う「間接オークション」へと変更することを軸にルールの見直しを行うこととされました。その後、2017年7月の制度検討作業部会の第一次中間論点整理において、「先着優先」に基づく連系線の利用登録の受付を停止する形で間接オークションが導入されることとされ、2018年10月から間接オークションが導入されました。間接オークションの開始後、前日スポット市場の約定量は、間接オークションの開始前後で、約1.5倍に増加しました。スポット市場の約定量は引き続き増加しております。
JEPXの前日スポット市場においては、全国の参加者が売り買いの入札を行い、売り札についている最も価格の安いものから、買い札については最も価格が高いものから約定するよう約定計算が行われます。こうした約定計算を行う際、連系線をまたぐ取引の量が計算され、全ての取引が連系線の空容量の範囲内で取引を行うことができれば、全国一律の価格(システムプライス)に決定されます。他方で、連系線の空容量の範囲内では取引できない場合、連系線の空容量を勘案し、各々の連系線を最大限活用するよう、改めて約定計算が行われます。こうして連系線混雑を考慮し約定計算をした結果、エリアごとに計算されるスポット価格(エリア価格)が異なる場合があり(市場分断)、このエリア間の価格の差異を「エリア間値差」と称します。
貫徹小委や制度検討作業部会においては、先着優先から間接オークションへの移行やBL市場等の卸電力市場活性化策の実施に伴い、エリア間値差がより多くの事業者に影響を及ぼしうることを踏まえ、こうしたリスクを軽減する仕組みが必要との議論が行われてきました。
諸外国においても、例えば、米国のPJMエリア(ペンシルバニア州、ニュージャージー州、メリーランド州、バージニア州及びデラウェア州)においては、地点別の限界価格(LMP)に頻繁に値差が発生することによる事業者のエリア間値差の負担リスクを減少させられるよう、エリア間の値差発生リスクを軽減する間接送電権の仕組みが整備されています。
上記を踏まえ、我が国においても、①ベースロード市場を含む先渡市場や、前日スポット市場、相対取引等における、エリアをまたぐ広域的取引の環境の整備、②連系線の効率的な利用、③間接送電権の取引の透明性の確保という視点を踏まえながら、取引参加者にとっての利便性や、ベースロード市場を含む先渡市場の活性化にも留意しつつ間接送電権の仕組みを整備することとなり、2019年4月から間接送電権市場の取引を開始しました。
【第361-5-2】新電力の電力調達の状況(2012年9月~ 2019年9月)
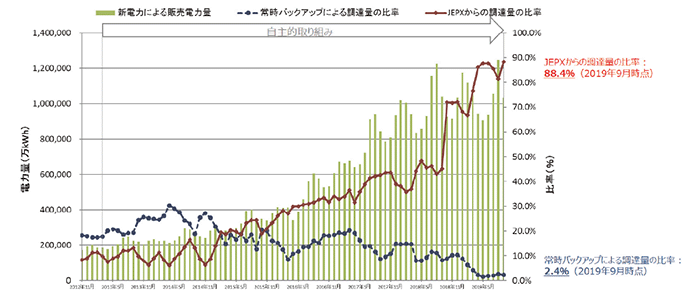
- 出典:
- 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
【第361-5-3】連系線利用状況イメージ
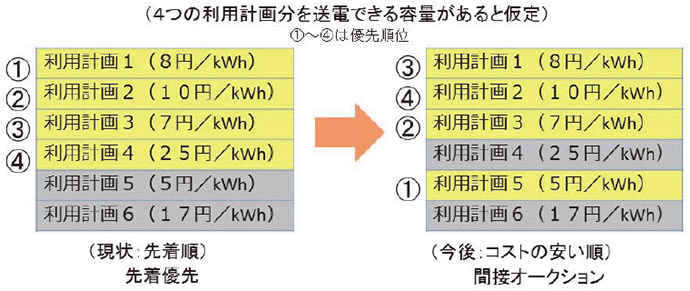
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(3) 効率性向上のための送配電網の維持・運用費用の負担の在り方
制度設計専門会合では、2015年秋以降、効率性向上のための送配電網の維持・運用費用の負担の在り方について、電力システム改革の進展など電力市場を取り巻く環境変化を踏まえ、検討を進めてきました。2016年7月の第9回制度設計専門会合において、それまでの検討内容を踏まえ、論点整理を行いました。具体的には、①発電事業者の負担の在り方、②小売事業者の負担の在り方、③ネットワーク利用の効率化の推進、と論点を大きく3つに分け、また、それらは相互に深く関連することから、今後、一体として、引き続き関係者の意見も聴きながら検討を深めていくこととしました。
2016年9月、上記の各論点について検討を深めるため、制度設計専門会合の下に送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループ(座長:横山明彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授)が開催され、2017年6月、第6回会合において、今後の検討課題について示した「検討すべき論点」を公表しました。その後、2018年6月、全13回にわたる議論の結果を中間とりまとめとして公表するとともに、その内容を踏まえた今後の託送料金制度の見直しについて、経済産業大臣に対して建議を行いました。
中間とりまとめにおいては、人口減少や省エネルギーの進展等による電力需要の伸び悩み、再生可能エネルギーの導入拡大等による系統連系ニーズの拡大、送配電設備の高経年化に伴う修繕・取替等の増大など、電力系統を取り巻く環境変化に対応しつつ、託送料金を最大限抑制しつつ必要な投資を確保すべく、①送配電設備を利用する者の受益や送配電関連費用に与える影響に応じた公平、適切な費用負担の実現、②一般送配電事業者だけでなく、送配電設備の利用者である発電側・需要側両方に対して合理的なインセンティブが働く制度設計、といった2点を基本的な視座として、以下の4点を柱とする制度見直しの方向性を示しています。
(i)発電側基本料金の導入
- 現行の託送料金原価の範囲を変えないことを前提に、従来、小売電気事業者側(需要側)にのみ負担を求めていた託送料金の一部について、その受益に応じて発電側にも負担を求めること
(ii) 送配電関連設備への投資効率化や送電ロス削減に向けたインセンティブ設計
- 需要地近郊や既に送配電網が手厚く整備されている地域など、送配電網の追加増強コストが小さい地域の電源について発電側基本料金の負担額を軽減すること
(iii)電力需要の動向に応じた適切な固定費の回収方法
- 送配電関連費用のうち固定費に関する部分については、原則として基本料金で回収する方向で託送料金を見直すこと
(ⅳ)送電ロスの補填に係る効率性と透明性の向上
- 一般送配電事業者に送電ロスに係る情報の公表、送電ロスの削減に向けた取組を促すとともに、送電ロスの調達・補填主体を小売電気事業者から一般送配電事業者へ移行することを基本として検討を深めること
発電側基本料金については、一般送配電事業者におけるシステム開発や発電・小売間の既存相対契約の見直し等に要する期間等を踏まえて、2023年度の導入を目指すこととしており、現在、制度設計専門会合において、システム開発に必要となる制度設計や他の制度改革との関係で整理が求められる事項を優先しつつ、課金方法や割引制度、転嫁の円滑化といった制度の詳細設計に向けた議論を進めています。
(4)託送供給等約款における送電ロスの取り扱いの見直し
送電ロスの削減は、電力に係る全体コストの抑制につながる重要な取組であるところ、制度設計専門会合の下に開催された送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループの中間とりまとめ(2018年6月)においては、「送電ロスの削減に向け、電圧別等の送電ロスの発生状況等を詳細に把握・公表し、透明性の向上を図る」とした上で、その具体策として、一般送配電事業者に情報の公表を求め、送電ロスの削減に向けた取り組みを促すとともに、「託送供給等約款上のロス率との乖離が大きい場合等にロス率の見直しを求める」とされました。
これを受け、2019年2月の第36回料金審査専門会合において、電圧別にみた送電ロスの発生状況(実績値)を確認したところ、大部分のエリア・電圧において、約款上のロス率が、実績値よりも上回っていることが確認されました。
これを踏まえ、事務局においてさらに分析を深め、2019年7月の第40回制度設計専門会合において、対応の方向性について議論しました。具体的には、スマートメーターの設置が完了するまでの間は新電力と旧一電小売との間で需要インバランスの計算方法が異なるとされているところ、約款ロス率と実績ロス率とが乖離していると、新電力と旧一電小売との公平性が阻害されていることが確認されたため、できるだけ速やかにそうした状況を改善すべく、スマートメーターの設置が完了するまでの間は、過去3年分の実績値の平均値を用いて、約款上の送電ロス率を毎年改定(一般送配電事業者が毎年約款改定を申請)することが適切との結論を得ました。それを踏まえ、2020年2月、各一般送配電事業者の託送供給等約款上の送電ロス率が改定されました。
なお、スマートメーターの設置が完了した後の対応については、別途検討していくこととしています。
【第361-5-4】一般送配電事業者の約款上の送電ロス率
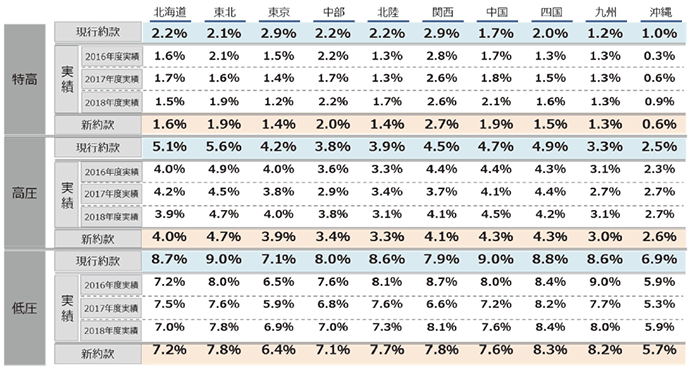
- 出典:
- 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
(5)容量市場の創設に向けた検討
かつての総括原価方式の枠組みの下では、発電投資は規制料金を通じて安定的に回収されてきました。総括原価方式と規制料金の枠組みによる投資回収の枠組みがない中では、原則として、発電投資は市場取引を通じて、または市場価格を指標とした相対取引の中で投資回収されていく仕組みに移行していくと考えられます。このため、固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー電源を除けば、大部分の電源に係る投資回収の予見性は、従来の総括原価方式下の状況と比較して、低下すると考えられます。
また、固定価格買取制度等を通じて、再エネが拡大することになれば、従来型電源の稼働率が低下するとともに、再エネ電源が市場に投入される時間帯においては市場価格が低下し、全電源にとって売電収入が低下すると考えられます。その結果、電源の将来収入見通しの不確実性が高まり、事業者の適切なタイミングにおける発電投資意欲をさらに減退させる可能性があります。
今後、仮に電源投資が適切なタイミングで行われなかった場合、電源の新設やリプレース等が十分になされない状態で、既存発電所が閉鎖されていくこととなります。そのような場合には、中長期的に供給力不足の問題が顕在化し、さらに電源開発に一定のリードタイムを要することから、①需給が逼迫する期間にわたり、電気料金が高止まりする問題や、②再エネをさらに導入した際の需給調整手段として、必要な調整電源を確保できない問題等が生じると考えられます。
こうした状況を踏まえると、単に卸電力市場(kWh価値の取引)等に供給力の確保・調整機能を委ねるのではなく、一定の投資回収の予見性を確保する施策である容量メカニズムを追加で講じ、電源の新陳代謝が市場原理を通じて適切に行われることを通じて、より効率的に中長期的に必要な供給力・調整力が確保できるようにすることが求められます。
貫徹小委中間とりまとめにおいては、こうした観点から検討を進めた結果、一定量の供給力を確保することができる「容量市場」は、①予め必要な供給力を確実に確保することができること、②卸電力市場価格の安定化を実現することで、電気事業者の安定した事業運営を可能とするとともに、電気料金の安定化により需要家にもメリットがもたらされること、③再エネ拡大等に伴う売電収入の低下は全電源に影響していること等を踏まえると、最も効率的に中長期的に必要な供給力等を確保するための手段であるとされました。
また、こうした措置は、投資回収の予見性を高めるための措置であり、必要な電源投資等のための総コストは変わらない、もしくはリスクプレミアム等の金利分が減少することから、中長期的に見た小売事業者の負担はむしろ抑えられると評価されています。
ほとんどの自由化先進国において、前述した意義に基づき、容量メカニズム等の投資回収の予見性を高める施策が措置されています。一般に、容量メカニズムは供給信頼度確保を目的として導入され、容量市場は、長期的に必要な供給力を確保する観点からは、他の同種の制度よりも、より良いと考えられています。
制度検討作業部会においては、貫徹小委中間とりまとめを受け、容量市場の詳細制度設計について、本作業部会におけるヒアリングや、広域機関における検討も踏まえつつ、検討を行っており、2024年度における必要供給力を確保するため2020年7月に予定している初回メインオークションに向けた準備を進めています。
【第361-5-5】容量市場創設後の収入
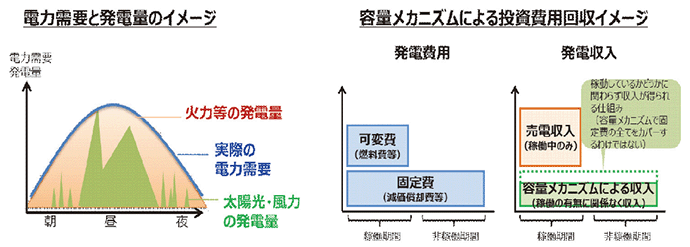
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(6)需給バランス調整のための調整力確保
①調整力の調達・運用の改善
2016年4月1日に、電力小売全面自由化や新たなライセンス制の導入を定めた第2弾改正法が施行され、これまで旧一電が自社の発電設備を用いて行ってきた、系統全体の周波数維持などの高品質な電力供給を確保する業務であるアンシラリーサービスは、一般送配電事業者が担うこととなりました。また、一般送配電事業者は、アンシラリーサービスの実施に必要な電源などを調整力として発電事業者などから調達するとともに、その調整力の確保に必要なコストは託送料金で回収される仕組みとなりました。この仕組みにより、発電事業者などによる競争が進み、多様な発電事業者などの参画による調達が可能な調整力の量の増大や、質の向上、一般送配電事業者によるさらなる効率的な調整力の活用が期待されています。
この仕組みは、一般送配電事業者による調整力の調達が公平性・透明性を確保した上で行われることを前提として機能するものであることから、2016年度から行われている一般送配電事業者による調整力の調達は、原則として、公募などの公平性かつ透明性が確保された手続により実施する必要がありますが、その手続の具体的な内容は各一般送配電事業者に委ねられていました。
このため、事前に一般送配電事業者による適切な調整力の調達の在り方について基本的な考え方を示し、調整力の公募調達が公平性・透明性を確保した形で円滑に開始できるよう、電力・ガス取引監視等委員会の下に開催した制度設計専門会合において、公募調達の公平性・透明性を担保するための考え方、望ましいと考える公募調達の実施方法などをその内容とする「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」を取りまとめ、2016年9月26日に電力・ガス取引監視等委員会として経済産業大臣に対して建議を行いました。
その後、本建議を踏まえ、経済産業大臣により、「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」(以下、「公募ガイドライン」という。)が制定され、一般送配電事業者は当該考え方に基づき、調整力の公募調達を実施しています。
(i)2019年度向けの公募調達に係る評価
電力・ガス取引監視等委員会では、2019年4月の制度設計専門会合において、2019年度向けの調整力公募結果を取りまとめ、前年度との変動要因を分析しました。また、旧一電(発電・小売部門)がどのような考え方で電源Ⅰに応札したか等を把握するため、各社に対し応札する電源の選定の考え方、及び応札価格設定の考え方を聴取し、妥当性を評価しました。
(ii)2020年度向けの公募調達の実施に向けた改善
2019年5月の制度設計専門会合において、2020年度の公募に向け、さらなる改善の必要性などについて、発電、小売事業者やディマンドリスポンス事業者などに対してアンケート等を実施し、その結果を踏まえた公募の改善要請を一般送配電事業者に対して実施しました。
その結果、2019年6月の制度設計専門会合において、電源Ⅰ’の広域調達の実施等の改善策が了承され、2019年秋に実施される公募から当該改善策が実施されることとなりました。
(iii) 2024年度向けのブラックスタート機能公募の検討
ブラックスタートとは、ブラックアウト(全域停電)の状態から、外部電源より発電された電気を受電することなく、停電解消のための発電を行うことを言います。万が一のブラックアウトに備え、各エリアではブラックスタート機能を有する電源を調達する必要があり、広域機関における検討の結果、容量市場創設後(2024年度以降)に必要なブラックスタート機能は、容量市場におけるkW価値の調達時期(kW価値を受け渡す4年前)と同時期に年間公募で調達することと整理されました。
これを受けて、電力・ガス取引監視等委員会では、2019年10月の制度設計専門会合において、2020年度に実施する2024年度向けのブラックスタート機能公募の実施方法等について議論を行い、ブラックスタート機能に必要な調達対象の範囲、落札電源への支払額の考え方、入札価格に規律を設けることが決定されました。
(ⅳ) 調整力公募における逆潮流アグリゲーションの取り扱いの検討
現在の公募ガイドラインでは、電源は原則としてユニット単位で応札することとしており、複数の電源等を組み合わせる逆潮流アグリゲーションは公募対象として認められていません。
他方、分散型リソース(蓄電池、コージェネレーション等)の普及や技術進歩を背景に、逆潮流アグリゲーションを調整力として活用するニーズが拡大していることや、新たなリソースの参入が調整力公募における競争促進の観点から重要であることに鑑み、電力・ガス取引監視等委員会では、2019年11月の制度設計専門会合において、調整力公募における逆潮流アグリゲーションの取り扱いを検討しました。
その結果、調整力に求められる確実性や透明性及び発電事業者の規模による公平性を確保しつつ、一定の要件を設けた上で、調整力公募への入札を認めるよう、公募ガイドラインの見直しを含めた検討を開始しました。
②需給調整市場の創設
一般送配電事業者が電力供給区域の周波数制御、需給バランス調整を行うために必要な調整力を調達するにあたっては、特定電源への優遇や過大なコスト負担を回避しつつ、実運用に必要な量の調整力を確保することが重要となります。
このような観点から、一般送配電事業者による調整力の公募が2016年から実施されることとなり、ディマンドリスポンス(DR)等の調整力も調達されるようになっています。
貫徹小委中間とりまとめにおいては、今後、公募結果を踏まえつつ、需給調整市場の詳細設計を行い、一般送配電事業者が調整力を市場で調達・取引できる環境を整備することが適当であるとされました。また、電力システム改革専門委員会報告書においても、系統運用者が供給力を市場からの調達や入札等で確保した上で、その価格に基づきリアルタイムでの需給調整・周波数調整に利用するメカニズムを送配電部門の一層の中立化に伴い導入することが適当であると記載されています。
諸外国においても、需給調整市場を開設し、調整力を市場の仕組みを活用して前週や直前に調達しています。同時に、欧米においては需給調整の広域化にも取り組んでおり、例えば欧州は卸電力市場の広域統合から、需給調整市場の広域統合へと、ルール・プラットフォームの整備を進めています。
我が国においても、再エネの導入が進む中で、調整力を効率的に確保していくことは重要な課題です。調整力公募は一部の調整力を除き各エリアの一般送配電事業者がエリア内の調整力のみを調達していますが、効率的に調整力を調達するためには、エリアを超えて広域的に調整力を確保することも課題となっています。他方で、各一般送配電事業者のシステムは、現状において、広域的な調整力の市場調達やその運用を前提として構築されておらず、こうしたシステムの改修や、実運用の変更を、日々の需給調整に支障を生じさせない形で行うためには、ルール検討やシステム構築を慎重に行っていく必要があります。
現在、制度検討作業部会や広域機関の委員会において、需給調整市場の詳細設計が進められており、2021年からは再生可能エネルギー予測誤差に対応する調整力が、2024年までにはすべての調整力が需給調整市場を通した調達に切り替わる予定です。また各一般送配電事業者のシステム改修にむけた検討や調整力の広域運用に向けた準備も並行して進められています。
(i)調整力の広域調達に必要な地域間連系線の容量確保の検討
2021年度から需給調整市場を通した調整力の広域調達が開始されると、調達された調整力が確実に活用できるよう事前に地域間連系線の容量を確保する必要があります。
そこで、電力・ガス取引監視等委員会では、2019年9月及び2020年3月の制度設計専門会合において、調整力の広域調達に係る地域間連系線の確保量について議論を行い、連系線の容量確保については卸電力市場への影響も考慮し、一定の上限量を設けることが決定されました。
(ii)需給調整市場の情報公表の検討
発電事業者やDR事業者などによる需給調整市場への参加促進、競争を活性化する観点から、落札結果等の関連情報については、タイムリーに公表することが重要です。
そこで、電力・ガス取引監視等委員会では、2019年9月の制度設計専門会合において、需給調整市場で公表されるべき情報の項目及びタイミングについて議論を行い、情報公表の項目については、現在の調整力公募結果の公表と同じレベルの内容を維持した上で、各エリアの結果が一覧できるものとすること、情報公表のタイミングについては、約定処理を行った当日の17時頃を目途に公開することが決定されました。
(iii)需給調整市場の監視及び価格規律の在り方の検討
需給調整市場における競争が十分でない場合、市場支配力を有する事業者が市場支配力を行使し、不当に高い入札価格等を設定することにより、不当な利益を得るといったことが起こり得ます。こうしたことを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会では、2020年2月の制度設計専門会合において、需給調整市場の監視及び価格規律の在り方について検討を開始しました。
【第361-5-6】需給調整市場の概要
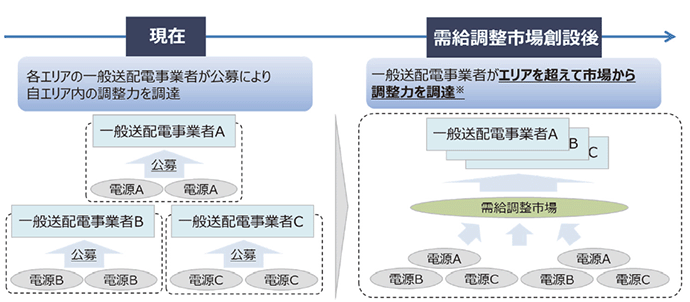
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(7)非化石価値取引市場の創設に向けた検討
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)」(以下、「高度化法」という。)により、小売電気事業者は、自ら調達する電気の非化石電源比率を2030年度に44%以上にすることが求められています。
しかし、卸電力取引所では、非化石電源と化石電源の区別がされないため、非化石電源の持つ価値が埋没し、非化石電源比率を高める手段として活用ができません。結果、取引所取引の割合が比較的高い新規参入者にとっては、非化石電源を調達する手段が限定される状況になっており、高度化法の目標達成が困難な面があります。
このような状況を踏まえ、新たな市場である非化石価値取引市場を創設することによって非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするとともに、需要家にとっての選択肢を拡大することとされました。またFIT非化石証書の売上については、FIT賦課金の低減に充てることとされ、これにより、FIT制度による国民負担の軽減を促すこととされました。
FIT電気に由来する非化石証書(FIT非化石証書)の取引については、2018年5月に初回オークションを開始し、四半期に一度の頻度でオークションを実施しています。
また、FIT電気以外の再生可能エネルギー等の電気については、原則2020年4月発電分以降から非化石証書(非FIT非化石証書)の対象とされることとされています。
なお、本市場の創設に当たっては、上記の制度趣旨を踏まえ、非化石価値を顕在化し、その価値に適切な評価を与えることができるよう、以下のとおり、非化石証書の有する環境価値と、需要家にとっての選択肢拡大という非化石証書の主な役割について基本的な考え方を整理しました。
(i)非化石証書の有する環境価値
電気の持つ環境価値としてはいくつかの概念が考えられますが、①非化石価値(高度化法上の非化石比率算定時に非化石電源として計上できる価値)以外に、②ゼロエミ価値(CO2排出係数が0kg-CO2 /kWhであることの価値)や③環境表示価値(小売電気事業者が需要家に対しその付加価値を表示・主張する権利)が主なものとして挙げられます。
非化石証書の購入者は販売する電気に非化石証書を使用することで、こうした価値を需要家に訴求することができます。電力の小売営業に関する指針において、電源構成表示に関しては、実際に受電した電源の構成を表示するとの整理がなされており、非化石証書を使用しても電源構成は変わらない点に留意が必要ですが、同指針において、再エネ由来の証書に関しては、電源構成外にて「実質再エネ100%」等の表示することは許容することとしています。
(ii)需要家の選択肢の拡大
証書を購入した小売電気事業者は、環境価値を電気とともに需要家に販売することが可能となります。非化石証書には、再生可能エネルギーの電気に由来する再エネ指定の非化石証書と、再生可能エネルギー以外の非化石電源の電気に由来する指定無し証書の2種類が存在します。例えば、再エネの推進に貢献したいと考える需要家は、数ある料金メニューから、こうした小売電気事業者が提供する再エネ指定の非化石証書を活用した環境価値付きのメニューを選択することで、実際に貢献することが可能となります。需要家のニーズが高ければ、非化石価値取引市場が積極的に活用され、小売電気事業者のサービス多様化が図られることが期待されます。
なお、2019年2月のオークションから、非化石証書に発電所情報等を付与した証書を調達できるよう、実証実験を開始しており、2019年度のオークションについても、この実証実験を継続して実施しました。
【第361-5-7】市場創設効果(イメージ)
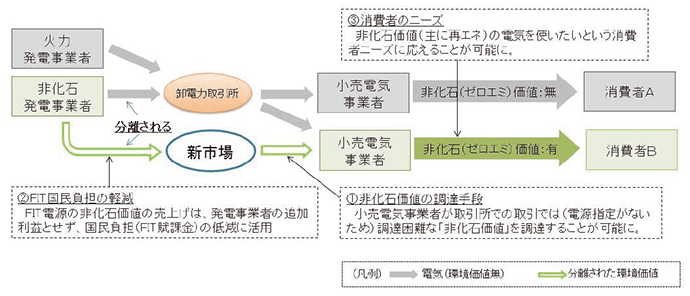
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(8) 自由化の下での財務会計面での課題解決に向けた取組
2016年4月の小売全面自由化以降、総括原価方式による料金規制の撤廃に伴い、電気事業の財務・会計上の特性にも変化が生じました。このため、電力分野の自由化を進めるに当たっては、これら制度変更に伴う課題として、一般の事業においては問題とならないような、例えば、制度変更により事後的に費用が増大する場合の対応費用をどのように回収するかが課題となり得ます。このため、財務・会計制度や負担の在り方について、具体的な措置の検討・審議を行うため、貫徹小委の下に「財務会計ワーキンググループ」を開催し、小売全面自由化の下での原子力事故に係る賠償への備えに関する負担や廃炉に係る会計制度の在り方に関する議論を行い、2017年2月に結果をとりまとめました。
とりまとめで示された方向性を踏まえ、財務会計面での課題解決に向け、2017年10月、2018年4月に制度改正を実施しました。
①原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方
東京電力福島第一原子力発電所の事故後、原子力事故に係る賠償への備えとして、従前から存在していた「原子力損害賠償法(昭和36年法律第147号)」に加えて新たに「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)」が制定され、現在、同法に基づき、原子力事業者が毎年一定額の一般負担金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に納付しています。原子力損害賠償法の趣旨に鑑みれば、本来、こうした万一の際の賠償への備えは、東京電力福島第一原子力発電所事故以前から確保されておくべきでしたが、政府は何ら制度的な措置を講じておらず、事業者がそうした費用を料金原価に算入することもありませんでした。従来、総括原価方式の下で営まれてきた電気事業においては、一般の事業と異なり、将来的な費用増大リスクを見込んだ自由な価格設定を行うことはできず、料金の算定時点で合理的に見積もられた費用以外を料金原価に算入することは認められていませんでした。これは、規制料金の下では、全ての需要家から均等に費用を回収することとなるため、同じ電気を利用した需要家間では不公平は生じないということを前提として、その電気を利用した時点で現に要した費用(合理的に見積もられた費用)のみ料金原価への算入を認めるという考え方に基づいています。しかし、2016年4月に小売が全面自由化され、新電力への契約切替えにより一般負担金を負担しない需要家が増加していることを踏まえ、賠償の備えを小売料金のみで回収するとした場合、過去に安価な電気を等しく利用してきたにもかかわらず、原子力事業者から契約を切り替えた需要家は負担せず、引き続き原子力事業者から電気の供給を受ける需要家のみが全てを負担していくことになります。こうした需要家間の格差を解消し、公平性を確保するためには、全需要家が等しく受益していた賠償の備えについて、全ての需要家が公平に負担することが適当であり、また、そうした措置を講ずることが、福島の復興にも資するものとの考えに立ち、負担の在り方について、貫徹小委で検討を進めました。その結果、回収する金額の規模は、現行の一般負担金の算定方法を前提とすることが適当と考えられ、現在の一般負担金の水準をベースに、1kWあたりの単価を算定した上で、これを前提に、2010年度までの我が国の原子力発電所の毎年度の設備容量等を用いて算出した金額から、回収が始まる前の2019年度末時点までに納付したまたは納付することになると見込まれる一般負担金の合計額を控除した約2.4兆円としました。回収方法については、電源構成に占める原子力の割合は供給区域ごとに異なる一方で、賠償の備えの負担は、過去の原子力の電気の利用に応じて行うべきものであることや、現状、一般負担金は小売規制料金に含まれ、供給区域ごとに異なる水準となっていること等を踏まえると、賠償の備えを国民全体で負担するに当たっては、特定の供給区域内の全ての需要家に一律に負担を求める託送料金の仕組みを利用することが適当と考えられました。こうした検討を踏まえ、東京電力福島第一原子力発電所事故以前から確保されておくべきであった賠償の備えを託送料金で回収する仕組みを可能とする制度改正(電気事業法施行規則の改正)を2017年9月に実施しました(施行は2020年4月1日)。なお、留意点として、本来、発電部門の原価として回収されるべき賠償の備えについて、託送料金の仕組みを通じて広く全需要家に負担を求めるに当たっては、その額の妥当性を担保する措置を講ずるとともに、個々の需要家が自らの負担を明確に認識できるよう、指針等を通じ、小売電気事業者に対し、需要家の負担の内容を料金明細票等に明記する措置を講じることとされました。また、原子力に関する費用について、託送料金の仕組みを通じた回収を認めることは、結果として、原子力事業者に対し、他の事業者に比べて相対的な負担の減少をもたらすものであり、競争上の公平性を確保する観点から、原子力事業者に対しては、例えば、原子力発電から得られる電気の一定量を小売電気事業者が広く調達できるようにするなど、一定の制度的措置を講じることとしています。
【第361-5-8】全ての需要家から公平に回収する賠償の備えのイメージ
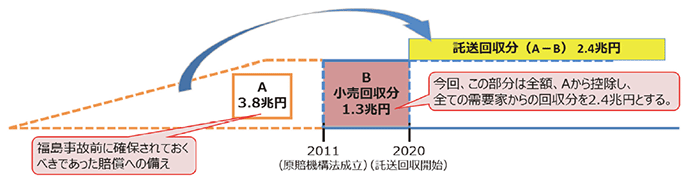
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
②福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・確保の在り方
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に必要な資金については、東京電力が負担することが原則であり、東京電力にグループ全体で総力を挙げて捻出させる必要があるとの考え方の下、「国民負担増とならない形で廃炉に係る資金を東京電力に確保させる制度」について、2016年10月に東電委員会から国に対して検討要請がなされました。この要請を踏まえ、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の円滑かつ着実な実施を担保するため、長期間にわたり必要となる巨額の資金の管理を担保する制度として、事故炉の廃炉を行う原子力事業者(事故事業者)に対し、廃炉に必要な資金を機構に積み立てることを義務付ける等の措置を講じることを内容とする廃炉等積立金制度を2017年10月より開始し、2018年4月及び2019年4月に政府は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構から申請のあった廃炉等積立金を認可しました。
また、発電・送配電・小売に分社化されている東京電力において、グループ全体で総力を挙げて捻出する資金が自由化の下でも確実に廃炉に充てられるための制度として、東京電力パワーグリッド(送配電部門、以下、「東電PG」という。)が親会社(東京電力ホールディングス)に対して支払う東京電力福島第一原子力発電所の廃炉費用相当分について、超過利潤と扱われないように費用側に整理して取り扱われるようにするとともに、乖離率の計算に際して実績単価の費用の内数として扱われるようにする制度的措置を2018年3月に実施しました。なお、この措置を講ずるに当たっては、東電PGの託送料金の値下げ機会が不当に損なわれないよう、東電PG自体の超過利潤・乖離率の代わりに、他の一般送配電事業者の効率化達成状況によって値下げ命令の要否を判断するとともに、東電グループ全体の中で東電PGの負担が過大なものとならないよう、例えば収益性や資産状況を参考に、グループ各社との負担の程度を比較し、著しく不適当な分担となっていないかどうかを確認する措置についても併せて講じています。
③廃炉に関する会計制度の扱い
(ア)廃炉会計制度について
従前の電気事業会計制度の下では、廃炉に伴う資産の残存簿価の減損等により、一時に巨額の費用が生じることで、(i)事業者が合理的な意思決定ができず廃炉判断を躊躇する、(ii)事業者の廃炉の円滑な実施に支障を来す、との懸念がありました。このため、2013年と2015年に、設備の残存簿価等を廃炉後も分割して償却(=負担の総額は変わらないが、負担の水準を平準化)する会計制度が措置されました。こうした制度整備を受けて、2015年に5基、2016年に1基の原子炉について、廃炉決定が行われています。
廃炉会計制度は、計上した資産の償却費が廃炉後も着実に回収される料金上の仕組みが併せて措置されることを前提としており、現在は小売規制料金により費用回収することが認められています。したがって、現在経過的に措置されている小売規制料金が将来的に撤廃されることを見据えた場合、今後も制度を継続するには、着実な費用回収を担保する措置を講ずることが不可欠です。この点、2015年3月の廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ報告書(「原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるための会計関連制度について」)においては、競争が進展した環境下においても制度を継続させるためには、「着実な費用回収を担保する仕組み」として、総括原価方式の料金規制が残る送配電部門の託送料金の仕組みを利用することとされていました。
制度創設の経緯・趣旨を踏まえれば、廃炉会計制度は、原発依存度低減というエネルギー政策の基本方針に沿って措置されたものとして、本制度を継続することが適当であるとされました。本制度を継続するために必要となる着実な費用回収の仕組みについては、小売規制料金が将来的に撤廃されることから、自由化の下でも規制料金として残る託送料金の仕組みを利用することが妥当と考えられます。
こうした検討を踏まえ、廃炉を行う際の設備の残存簿価等について、引き続き小売料金での償却等を認め、2020年4月以降に託送料金での回収を可能とする制度改正(電気事業会計規則等の改正)を2017年10月に実施しました。なお、発電、送配電、小売の各事業が峻別された自由化の環境下で、発電に係る費用の回収に託送料金の仕組みを利用することは、原発依存度低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策の目的を達成するために講ずる例外的な措置と位置付けられるべきと考えられます。
(イ)原子力発電施設解体引当金について
原子炉の運転期間中に廃炉に必要な費用を着実に積み立てるため、原子力事業者は、毎年度、原子力発電所一基ごとの廃止措置に要する総見積額を算定し、経済産業大臣の承認を得た上で、各原子炉の発電実績に応じて原子力発電施設解体引当金として積み立てることが義務付けられています。解体引当金は、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電所の長期にわたる稼働停止が続き、従来の生産高比例法では引当が進まないといった課題が生じたことから、2013年、引当方法を定額法に、引当期間を運転期間40年に廃炉後の安全貯蔵期間10年を加えた原則50年に変更する制度改正が行われ、今後、競争が進展した環境下でも本制度を継続し、廃炉後の安全貯蔵期間中も引当を継続させるためには、廃炉会計制度と同様、費用回収が着実に行われる仕組みが必要となっています。
その引当期間については、事業者が負担するという原則に立てば、着実な費用回収が前提となる安全貯蔵期間に入る前、すなわち、廃炉前に引当を完了していることが廃炉を円滑に実施する観点からより適切な制度の在り方であり、原則50年としている引当期間を原則40年に短縮することとしました。
引当期間の見直しを行った場合、2013年の制度改正以降に廃炉決定し、解体引当金の残額を10年間に分割した引当を現在行っているものや、今後早期廃炉するものについては、解体引当金の未引当分を一括して引き当てる必要が生じます。しかし、制度の事後的な変更によって、事業者の財務に影響を与えることは適当でないことに加え、こうした費用の発生が早期廃炉を志向する事業者の判断を歪めるようなことがあれば、廃炉会計制度の趣旨にも反するので、2013年の制度改正以降に廃炉決定したものや今後早期廃炉するものに限り、廃炉に伴い一括して計上することが必要となる費用を廃炉会計制度の対象とすることで、一括して発生する費用を分割して計上する仕組みとすることとしました。
解体引当金の基礎となる原発の解体に必要な費用は、1985年及び1999年の総合資源エネルギー調査会原子力部会において示された算定式に基づき、毎年度、物価変動や廃棄物量の変動を加味し、炉ごとに総額(:総見積額)を算定しています。この算定式は、原子力部会において技術的な検討を行った結果として導き出されたものであり、その前提に大きな変更はないことから、現時点で合理的に見積もることができる費用が不足なく含まれているものと評価できます。一方で、この算定式は、モデルとなるプラントの廃炉工程を前提としたものであるため、今後、個々のプラントにおいて廃止措置を実施していく過程等で、例えば、多数の炉が設置されている原子力発電所では、設備の共有等による効率化などにより、総見積額の見直しが必要となり得ます。こうしたことを踏まえ、自由化の下でも廃炉に必要な費用があらかじめ確実に確保されるよう、個別の炉・発電所ごとに固有の事情(規制変更などにより算定式の前提を大幅に変更する必要がある場合を除く)が生じた場合に、当該事象を速やかに総見積額に反映させることが可能な仕組みを導入することが必要と考えられます。ただし、総見積額の妥当性を確保するため、これまでと同様に、総見積額を経済産業大臣が承認する仕組みとすることとしました。
これらの検討を踏まえ、引当期間を原則40年することに加えて、2013年の制度改正以降に廃炉決定したものや今後早期廃炉するものに限り、廃炉に伴い一括して計上することが必要となる費用を廃炉会計制度の対象とする等の制度改正(解体引当金省令の改正)を2018年4月に実施しました。