第2節 ガスシステム改革及び熱供給システム改革の促進
1.ガスシステム改革の概要
2015年6月に成立した「電気事業法等の一部を改正する等の法律」に基づき、2017年4月1日にガス小売全面自由化等のガスシステム改革が実施されました。ガスシステム改革の実施に当たっては、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改革小委員会(2013年11月から2016年6月にかけて33回開催)、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2016年10月から2017年2月にかけて2回開催)、産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会(2014年6月から2017年3月にかけて16回開催)、同小委員会ガスシステム改革保安対策ワーキンググループ(2015年7月から2016年5月にかけて6回開催)及び電力・ガス取引監視等委員会等において、随時議論がなされてきました。
ガスシステム改革は、1.天然ガスの安定供給の確保、2.ガス料金の最大限の抑制、3.利用メニューの多様化と事業機会の拡大、4.天然ガスの利用方法の拡大の主に4つを目的としており、2017年4月以降も、資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視等委員会のそれぞれにおいて更なる市場活性化のための検討を進めています。
なお、2022年4月1日に予定されている大手ガス事業者の導管部門の法的分離等に関する制度設計については、市場の状況も考慮し、引き続き、総合資源エネルギー調査会等での議論を踏まえ、政府として検討を進めることとしています。
2.ガスの小売全面自由化の進捗状況
(1)ガス小売事業者の登録
新規のガス小売事業者については、2016年8月の事前登録申請の受付開始から2019年3月末時点までに、67者が登録されました。ガス小売事業者の登録に当たっては、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会が、「ガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者」に該当しないか等、法令に則りそれぞれ審査を行っています。なお、電気事業法等の一部を改正する等の法律の経過措置により、旧一般ガス事業者から203者、旧簡易ガス事業者から1174者が、ガス小売事業者となりました。
【第362-2-1】新規ガス小売事業者の登録状況
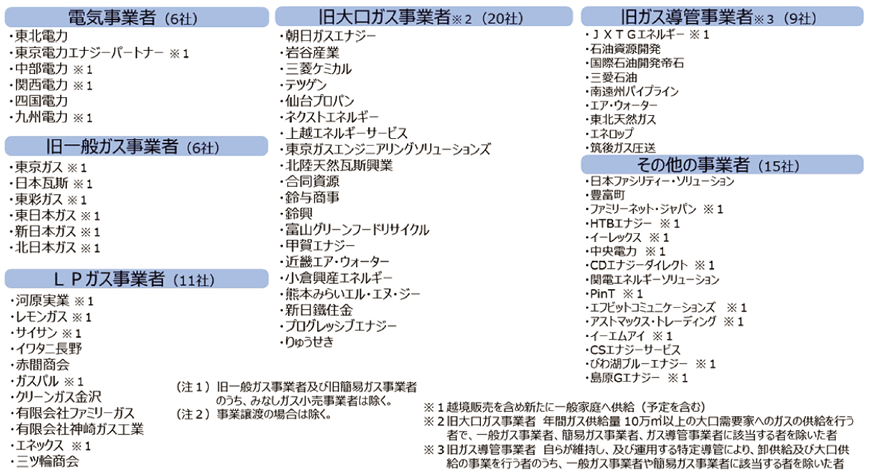
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
(2)スイッチング(契約先の切り替え)件数及び新規参入者の販売シェア
ガスの小売全面自由化から、一般家庭等での累計スイッチング申込件数は堅調に増加しており、2018年12月末時点で、全国で約170万件となっています。地域別でみると、最近は関東が大きく伸びており、最多の近畿に着実に迫ってきています。スイッチング率は全国で6.7%となっており、地域別でみると、母数の影響から、関東は近畿の半分程度となっています。なお、北海道、東北、中国・四国では2018年12月末時点でスイッチングの動きは見られていません(第362-2-2)。
また、自社内スイッチング件数(累計)は、2018年12月末時点で、約124万件(全国)、スイッチング率は8.5%(全国)となっており(第362-2-3)、他社へのスイッチングと同様に増加しています。
新規参入者の全需要種に占めるガス販売量については、2018年12月末時点で全体の12.8%となっています。家庭用のガス販売量に占める新規参入者のシェアは全国で5.2%、最もスイッチングが進んでいる近畿地方では、9.3%となっています(第362-2-4)。
【第362-2-2】全国のスイッチング率の推移・申込件数
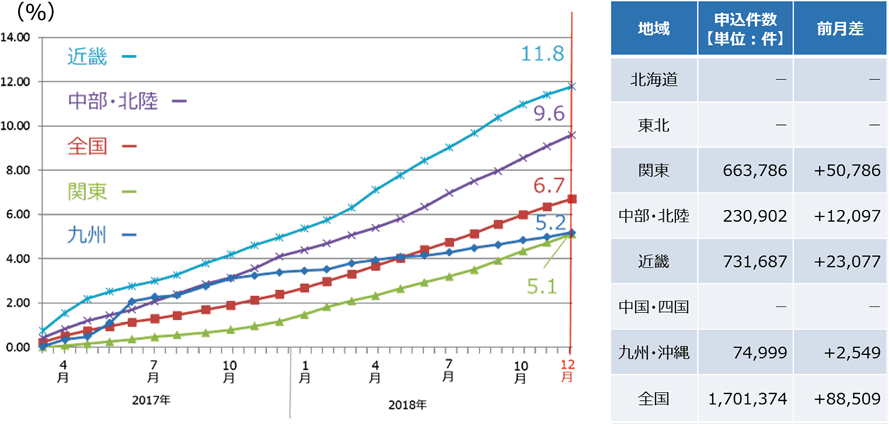
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
【第362-2-3】指定旧供給区域内における累計契約変更件数
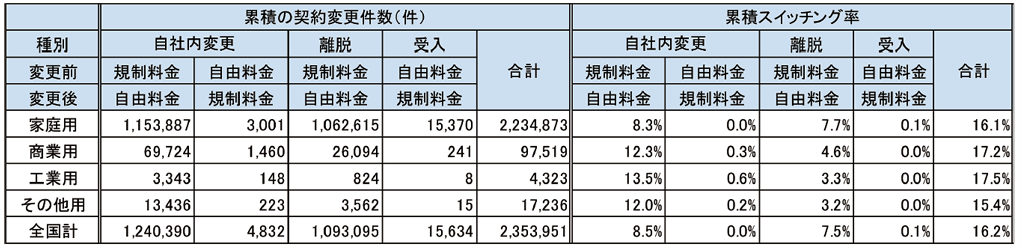
- 出典:
- ガス取引報(平成30年10月分)表3
【第362-2-4】新規小売のガス販売量(需要種・エリア別)
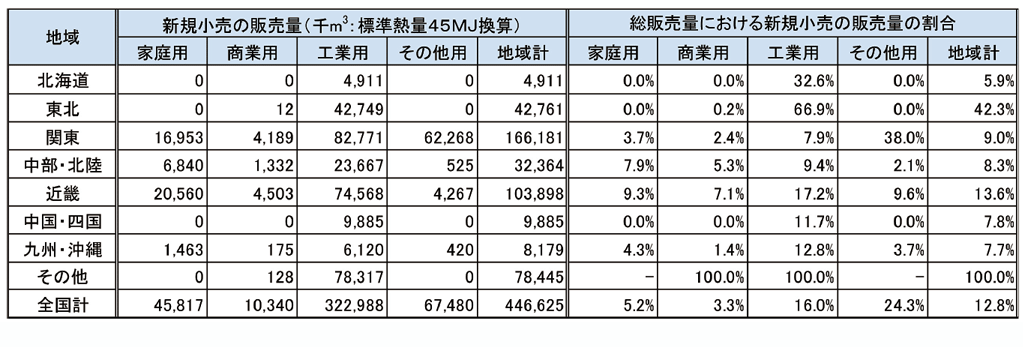
- 出典:
- ガス取引報(平成30年10月分)表3
(3)メニューの多様化
ガス小売全面自由化を契機に、全国各地のガス小売事業者が新たな料金・サービスメニューの提供に取り組んでおり、料金・サービスの多様化が進んでいます。各事業者が提案する新メニューでは、ガス料金の割引を行うもの、電力や通信といった他のサービスとのセット割引を行うもの、料金支払いに対しポイントを付与するもの、顧客の見守りサービスを提供するもの、トラブル時の駆けつけサービスを提供するもの、ガスの使用量や料金の見える化サービスを提供するもの、といった類型が見られます。
【第362-2-5】ガス事業者のサービス向上に向けた新たな取組の類型表
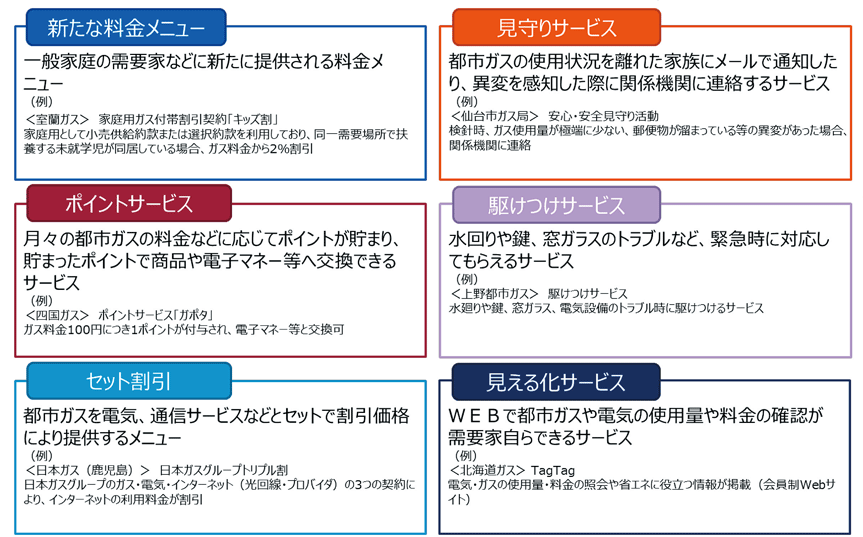
- 出典:
- 各社プレスリリース・HP等より資源エネルギー庁が作成
【第362-2-6】ガス事業者のサービス向上に向けた新たな取組
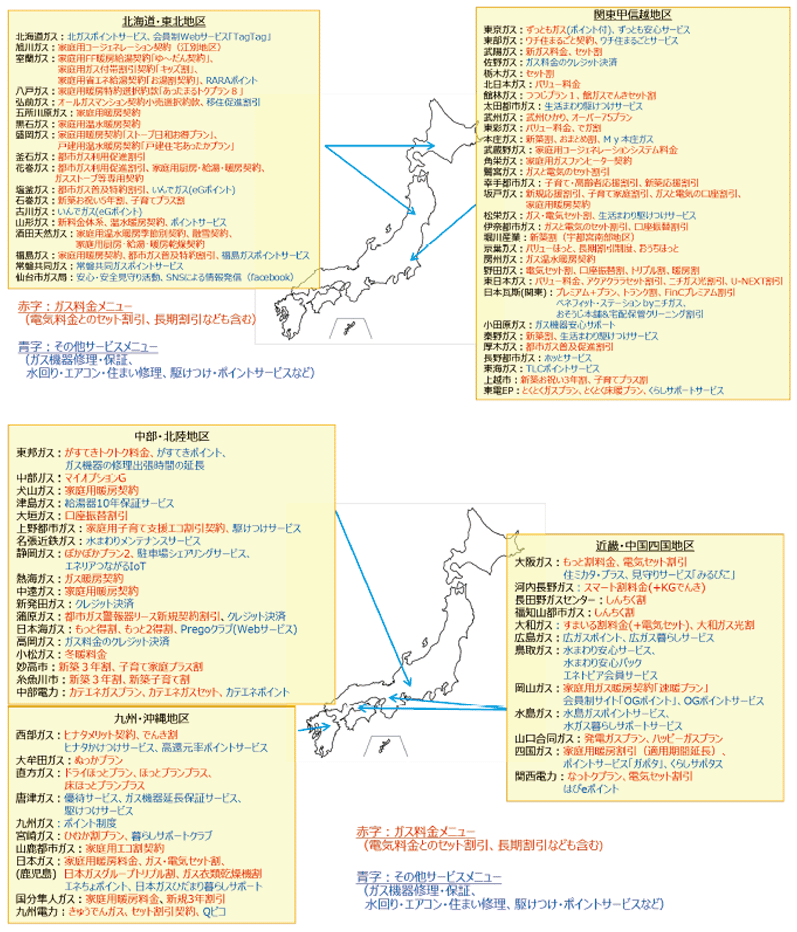
- 出典:
- 日本ガス協会作成(2019年1月末時点)
(4)経過措置料金規制の対象地域の指定解除
ガス小売全面自由化に伴い、ガスの小売供給に関する料金規制は原則撤廃されましたが、LPガス、オール電化等を含め競争が不十分であると認められた地域については、需要家利益の保護の観点から経済産業大臣が指定を行い、経過措置として料金規制を継続しています。ただし、指定を受けた地域の競争状況は、経済産業大臣が3か月に一度の事業者報告により継続して把握し、競争が十分であると認められた地域については指定を解除することとしています。
ガス小売全面自由化に先駆けて、2016年11月には、ガスシステム改革小委員会等の議論を受けて策定された指定基準に基づき、旧一般ガス事業者の供給区域等では12区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点では1,730供給地点群を指定しましたが、2018年12月現在において、旧一般ガス事業者の供給区域等では9区域等、旧簡易ガス事業者の供給地点では1,267供給地点群が指定されています。
【第362-2-7】指定旧供給区域等一覧(旧一般ガス事業者の供給区域等)
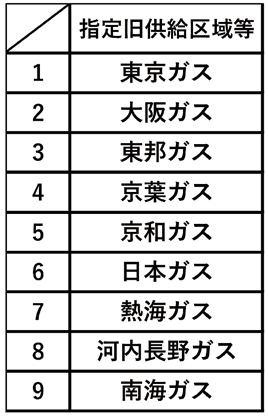
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成(※2018年3月に経過措置対象の指定解除済み)
3.ガス事業制度検討ワーキンググループにおける議論
資源エネルギー庁は2018年9月に、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会の下に「ガス事業制度検討ワーキンググループ(以下「ガスWG」という。)」を設置しました。ガスWGは、2017年4月のガス小売全面自由化の成果が一定程度見られる中、エネルギー基本計画や規制改革実施計画、一部継続検討課題とされていたテーマを踏まえつつ、ガスシステム改革の更なる推進に向けてガス事業制度の在り方について専門的な見地から詳細な検討を進めることを目的としています。
2018年度中にはガスWGを7回開催し、ガス卸供給の追加的な促進策、一括受ガスその他消費者の利益を最大限実現するための措置、熱量バンド制の導入、LNG基地の第三者利用の追加的な促進策について議論が交わされました。
【第362-4-1】消費者からの相談状況
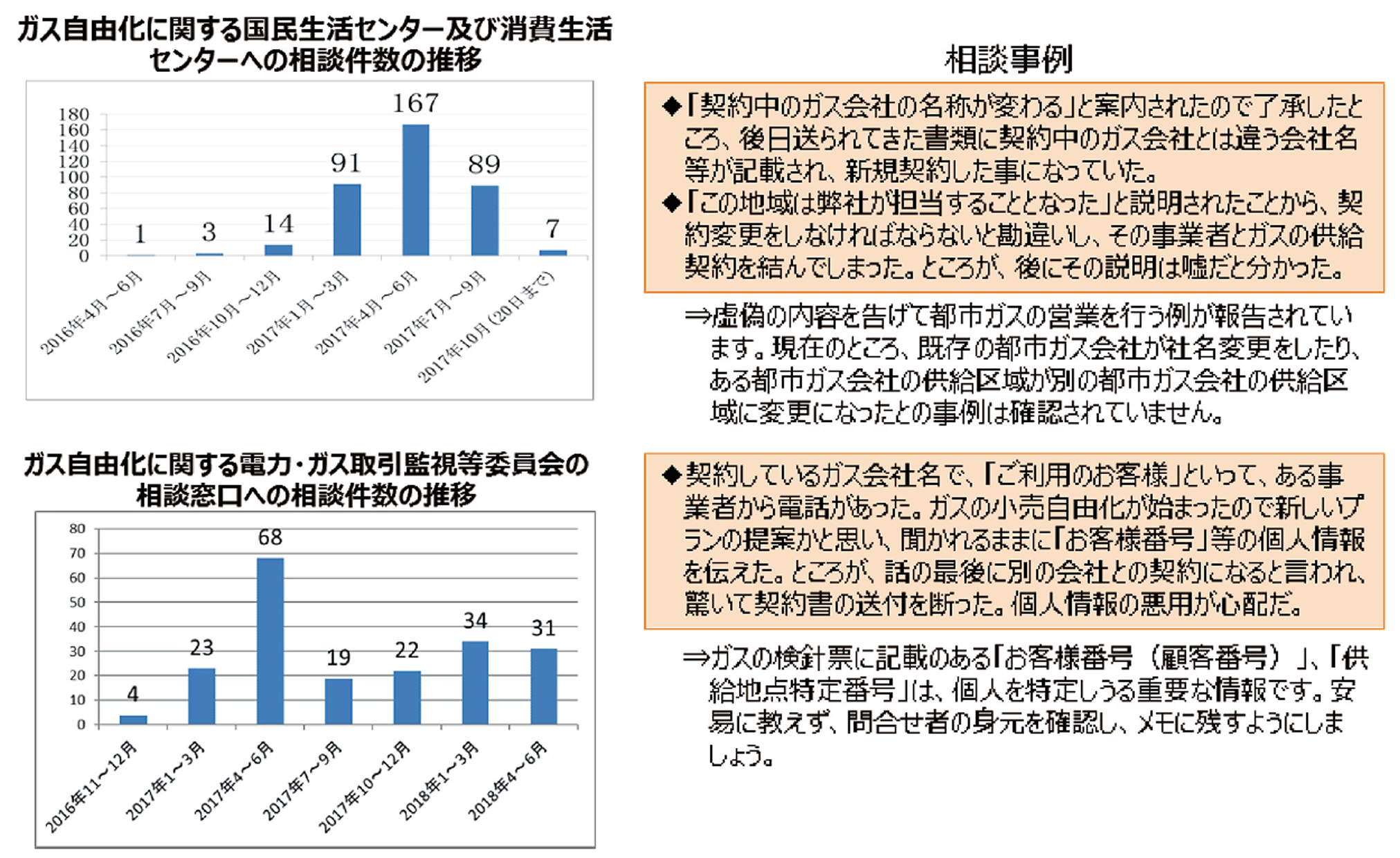
- 出典:
- 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
4.ガス市場における適正な取引確保のための厳正な監視など
(1)ガス市場の監視
2017年4月にはガスの小売事業への参入が全面自由化され、家庭を含む全ての需要家がガス会社や料金メニューを自由に選択できることとなった。こうした中、ガスの小売供給に関する取引の適正化を図るため、「ガスの小売営業に関する指針」を踏まえ、需要家への情報提供や契約の形態・内容などについて、事業者の営業活動の監視などを行い、必要に応じて、ガス事業法上問題となる事業者に対して指導等を行っている。また、委員会の相談窓口などに寄せられた不適切な営業活動などについて、事実関係の確認や指導を行っている。
(2)小売料金に係る事後監視
一般的な監視に加え、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたみなしガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス(又は簡易ガス)の利用率が50%を超える事業者を対象として、当該旧供給区域等の料金水準について報告徴収を行い、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないための事後監視(以下「特別な事後監視」という。)を行っています。
四半期ごとに実施される特別な事後監視の結果については、委員会HPにて公表することになっています。なお、特別な事後監視を開始して以降、これまでに問題となるような事例は認められていません。
【第362-4-2】特別な事後監視の概要
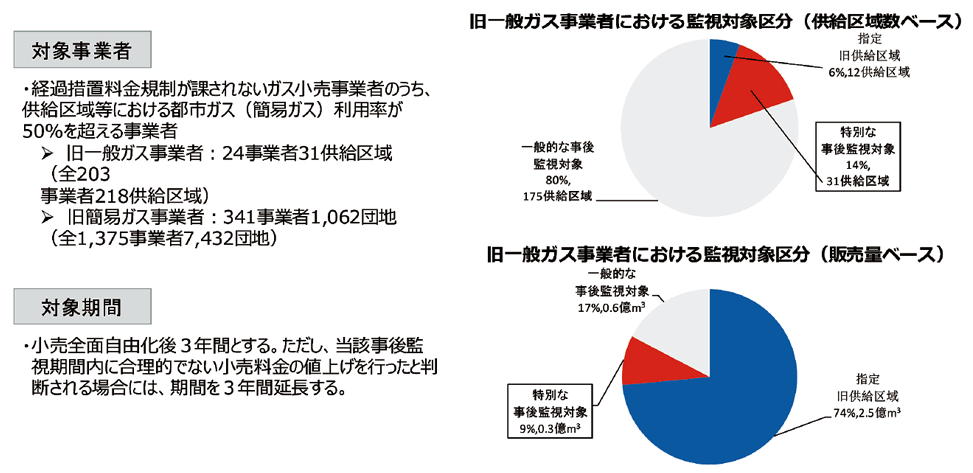
- 出典:
- 2017年8月ガス取引報に基づき電力・ガス取引監視等委員会作成
(3)原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価
電気事業法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下「第3弾改正法」という。)附則の経過措置に基づく小売ガス料金については、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないかなどを経済産業省において確認し、その結果を公表することとなっています。電力・ガス取引監視等委員会では、経済産業大臣等からの意見聴取を受けて、2018年度は以下の旧一般みなしガス小売事業者に対して料金審査専門会合において評価及び確認を行いました。
<事後評価のポイント>
本省所管の1社(東邦ガス)※ に地方局所管の6社(京葉ガス、京和ガス、日本ガス、熱海ガス、河内長野ガス、南海ガス)を加えた計7社について、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20170329資第5号)第2(8)④に基づく値下げ認可申請の必要がないか確認を行いました。
<料金審査専門会合の開催実績>
- 平成30年10月25日 第33回料金審査専門会合
- 平成30年12月12日 第34回料金審査専門会合
<事後評価の結果>
第3弾改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号)第18条第1項の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令に係る「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」(20170329資第5号)第2(8)④に照らし、値下げ認可申請の必要は認められませんでした。評価の詳細は以下のとおりです。
審査基準のステップ1[ガス事業利益率による基準]では、個社の直近3か年度平均の利益率が9社10か年度平均の利益率を上回る会社は、京和ガス及び熱海ガスの2社でした。ステップ1に該当した2社について、審査基準のステップ2[超過利潤累積額による基準]では、2017年度末超過利潤累積額は一定水準額である指定旧供給区域等需要部門に係る本支管投資額(過去5年平均)を下回っており、ステップ2[自由化部門の収支による基準]では、直近2年連続で自由化部門の収支が赤字となっていませんでした。以上より、原価算定期間を終了している旧一般ガスみなしガス小売事業者7社(東京ガス・大阪ガス以外)について、審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の検討対象となる事業者はいませんでした。
以上を踏まえ、2018年度の事後評価の対象となった事業者について、現行の認可料金に関する値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでした。
また、各社においては、今後とも料金原価と直近実績の比較・経営効率化の状況・収支見通し等現行の経過措置料金に関連した分かりやすい情報提供に努めるとともに、安全対策・供給信頼度維持に不可欠な投資は最優先に実施した上で、引き続き経営効率化に真摯に取り組むことにより、コスト低減を進めていくべきであるとの評価を行いました。
【第362-4-3】料金変更認可申請命令に係る審査基準
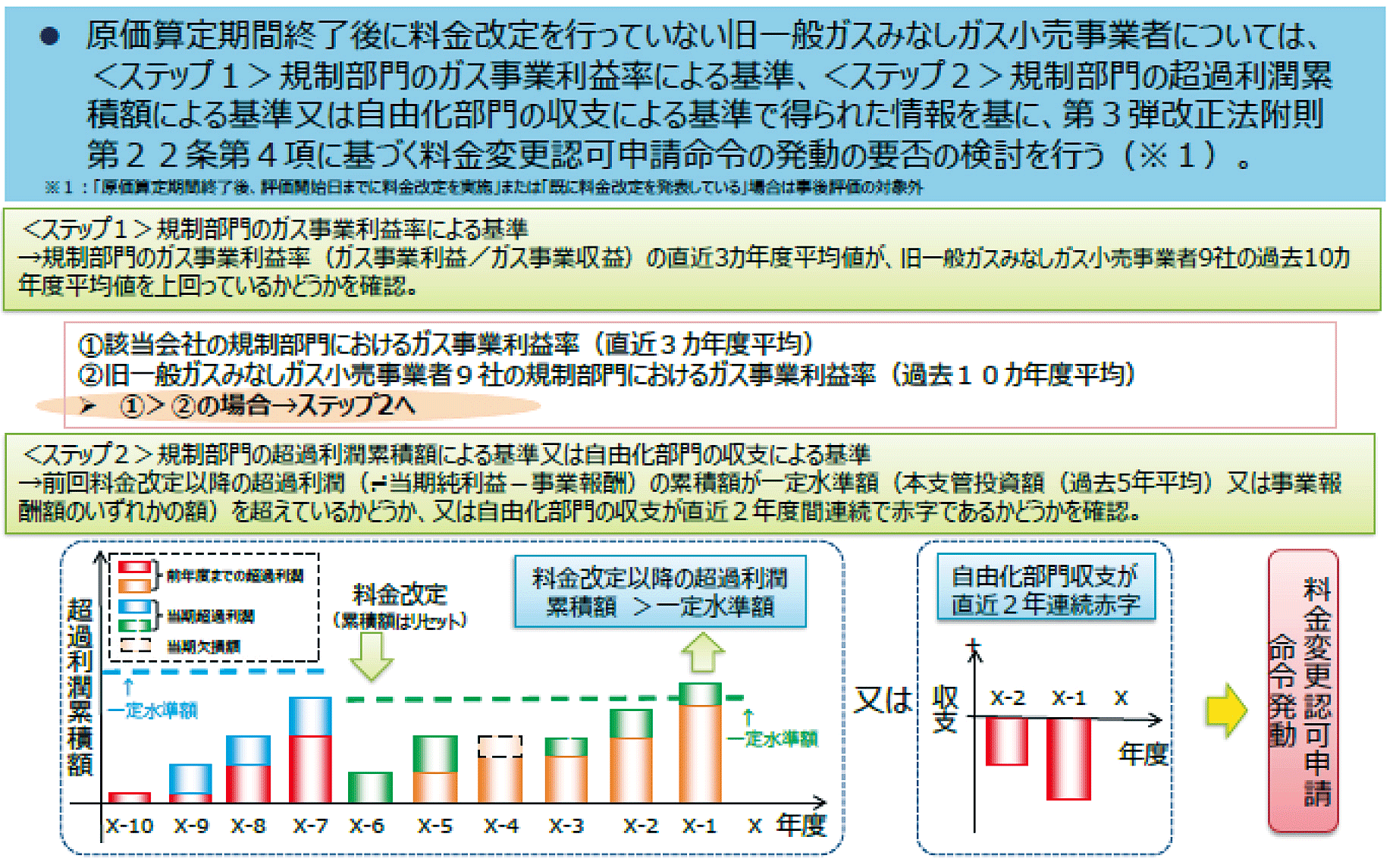
- 出典:
- 資源エネルギー庁作成
【第362-4-4】審査基準の適用結果
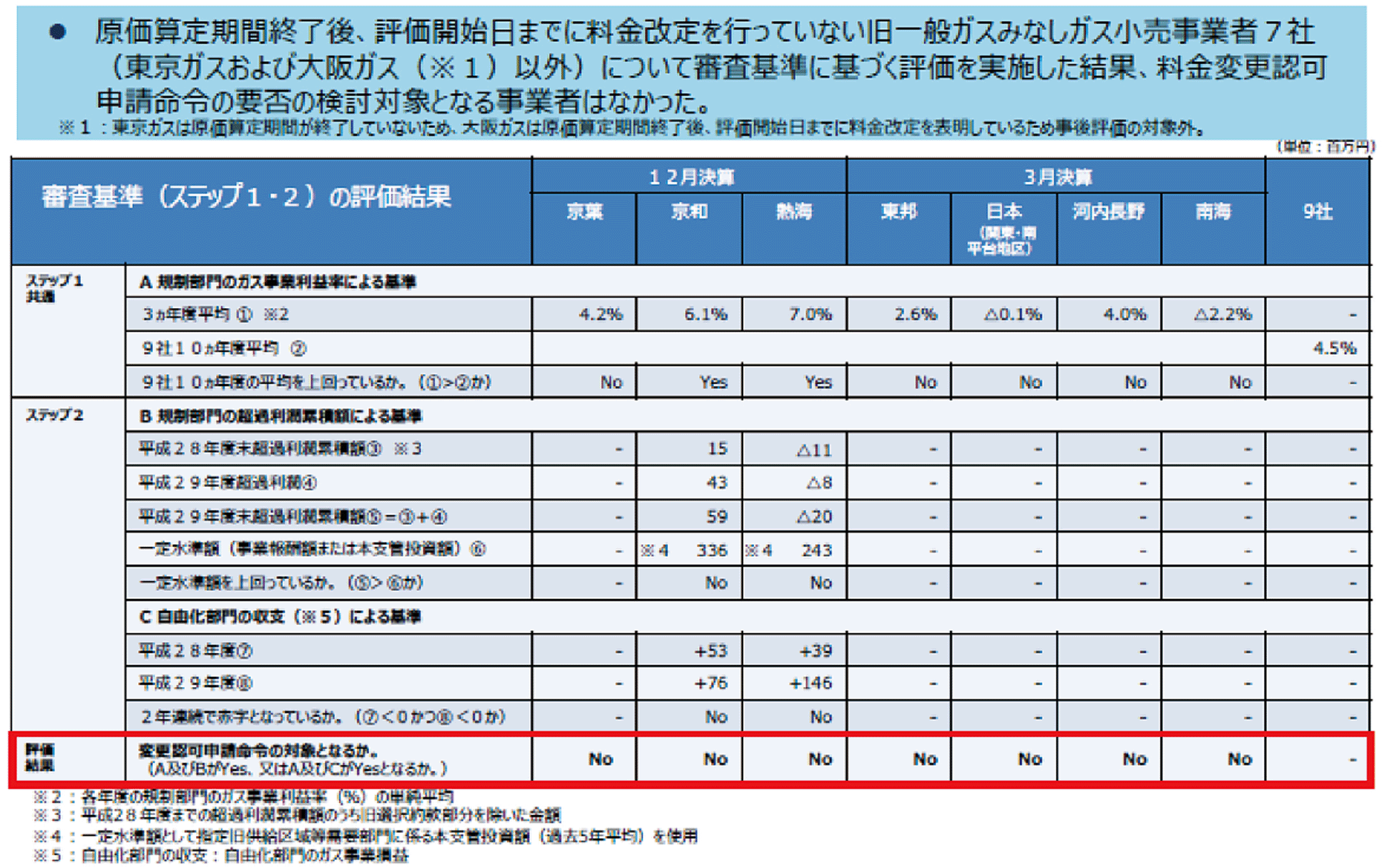
- 出典:
- 各事業者の部門別収支計算書、各事業者へのヒアリングにより資源エネルギー庁作成
(4)ガス導管事業者の収支状況等の事後評価
ガス導管事業の効率化・料金の低廉化と質の高いガス供給サービスの維持・向上を促すことは、ガスの需要家の便益を高めるだけでなく、小売・製造事業者間の競争の活性化にも寄与し、エネルギー供給全体の生産性向上に資するものです。
これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会において、2017年度託送収支等を分析・評価しました。
①託送収支の状況
(ア)超過利潤が一定水準を超過した事業者
2017年度に事業を実施した全国のガス導管事業者(224社)のうち、託送供給約款を策定している等の事業者(143社)について、2017年度の収支状況等を評価しました。
これら143社のうち、6社(仙南ガス、のしろエネルギーサービス、東部液化石油、下仁田町、魚沼市、筑後ガス圧送)については、2017年度終了時点での超過利潤累積額が、変更認可申請命令の発動基準となる一定水準を超過したたため、このまま2020年4月1日までに託送供給約款料金の改定の届出が行われない場合、所管の経済産業局長の変更認可申請命令の対象となる可能性があります。各事業者に対応方針を聴取したところ、6社とも期日までに料金改定を実施予定であるとの回答でした。
(イ)大きな超過利潤が発生した事業者の評価
一定水準を超過した事業者以外にも、2017年度の収支において比較的大きな超過利潤が発生した事業者があったことを踏まえ、4月~3月の会計年度を採用している事業者85社のうち、超過利潤が営業収益の5%以上であった22社(このうち、超過利潤が一定水準を超過したのは4社)について、その超過利潤の要因が一過性のものか継続する可能性が高いものかについて分析・評価を行いました。その結果、19社(超過利潤が一定水準を超過した4社を含む)については、来年度以降も2017年度と同じ要因での超過利潤が継続する可能性が高いと評価されました。また、それ以外の3社については、2017年度の超過利潤の発生は一過性である可能性があると評価されました。
この結果を踏まえ、各事業者に対し、料金改定を含めた今後の方針について聴取したところ、超過利潤の継続性が高い19社のうち15社(超過利潤が一定水準を超過した4社を含む)及びそれ以外の3社のうち1社から、2020年4月までに自主的に料金改定を実施する予定であるとの回答がありました。
(ウ)制度改正後新たに原価算入された費用の状況について
事業者間精算費について、2017年度実績費用と想定原価の比較を行ったところ、実績費用が想定原価から大きくずれた事業者が多くありました(実績費用が20%以上想定原価から下振れした事業者が11社、実績費用が想定原価の2倍以上となった事業者が2社)。
今回の分析を通じ、事業者間精算により収益を得ているガス導管事業者の一部には、小売供給、託送供給及び卸供給の合計が3に満たないことから託送供給約款の制定が免除されている特定ガス導管事業者があり、これらについてはストック管理・フロー管理が行われていない状況が明らかになりました。これを適正化するため、2019年3月27日ガス事業法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(平成12年10月2日平成12・09・28資第8号)についての改正を実施しました。
需要調査・開拓費について、2017年度の実績費用を想定原価と比較したところ、需要調査・開拓費を原価に計上していた全8社のうち、7社について実績費用が想定原価から下振れしていました。
(エ)収支管理の更なる適正化に向けた対応
託送料金の適正性の観点からは、地域別または特定導管ごとのコストが適切に託送料金に反映される必要があります。地域別または特定導管ごとに異なる託送料金を設定しているガス導管事業者について、それぞれの単位で託送収支計算書等を作成するよう、2019年3月29日にガス事業託送供給収支計算規則(平成29年経済産業省令第23号)の改正を実施しました。
②効率化に向けた取組状況
大手3社(東京ガス・大阪ガス・東邦ガス)の取組状況
ガス導管事業の効率化を促進していく観点から、先進的な取組を行っていると期待される大手3社の取組状況を聴取し、特に効果の大きいものや先進的な取組の内容を確認しました。
これらのうち、例えば、以下のような取組は、他のガス導管事業者への横展開が期待されるものであり、今後、これらの取組も参考にしつつ、各事業者において効率化に向けた取組が進められることが期待されます。
- 計測機器等の点検・部品交換頻度の見直し
- 工法の工夫(中圧へのPE管導入、非開削工法の導入等)
- 業務効率化の取組(現地作業でのタブレット導入、通信機能付きマイコンメーターの活用による検査コストの低減等)
- 工事発注・契約手法の工夫(取引先からの費用低減提案の受け入れ、まとめ発注、施工条件変更時の単価事前設定による協議コストの低減等)
- 行政区との交渉(掘削幅の削減、埋設深さの変更等) 等
③中長期的な安定供給の確保に向けた取組状況
(ア)導管延伸の取組状況
今回の事後評価の対象となったガス導管事業者(143社)の、2017年度の導管総延長の伸びは、全社の平均で、高圧導管は平均1.91%、中圧導管は平均0.67%、低圧導管は平均0.72%の伸びでした。
(イ)メーター取付数及び供給区域拡張の状況
今回の事後評価の対象となった一般ガス導管事業者(126社)の2017年度のメーター取付数の伸びについては、85社が増加、3社が横ばい、38社が減少でした。また、各社の2017年度の供給区域の拡張実績を分析したところ、42社が増加、84社が横ばいでした。
④内管工事の取組状況
内管工事見積単価表及び内管工事収支の分析
(ア)標準モデルによる内管工事見積額の横比較
一般ガス導管事業者が実施する需要家の資産である内管の工事について、全社共通の見積条件(内管工事の標準モデル)に基づき、全ての一般ガス導管事業者(196社)に内管工事の参考見積を依頼しました。その結果、各社の参考見積額の平均は13万円でしたが、最低5千円から最高26万円まで、大きな幅があることを分析し、結果を公表しました。
参考見積額が比較的高かった事業者については、他の事業者の参考見積額等を踏まえつつ、資材調達の工夫など、効率化に取り組むことが期待されます。
(イ)内管工事の利益率が高く、かつ直近で見積単価表の改定が行われていない事業者の分析
今回の事後評価の対象となった一般ガス導管事業者(126社)について、内管工事の2015年度から2017年度の収支状況を分析したところ、3年合計で収益が支出を上回った社が95社、下回った社が30社でした(2015年度から2017年度の内管工事の実績のない1社を除く)。また、内管工事の3年間の平均利益率が20%以上の事業者も存在しました。
内管工事の3年平均利益率が10%以上で、かつ直近で見積単価表の値下げが行われていない25社に対し、利益率が高い理由を聴取したところ、「自社の労務費等を内管工事の収支に振り分けていなかったため、実際よりも収支上の利益率が高くなっていた」(13社)、「利益率が高いとは考えていない等」(12社)との回答がありました。
これを踏まえ、自社で内管工事を行った場合の労務費等が適切に振り分けられるようにするなど、内管工事の収支管理の詳細を整理し、事業者に対し、改めて周知徹底を行いました。
5.ガス市場の更なる効率化、競争促進のための取組
(1)ガス市場での競争促進策の検討
電力市場及びガス市場における競争を促進することによって、需要家の利益を最大化し、電気事業及びガス事業の健全な発達を図る観点から、これらの市場の競争促進策(競争評価、卸取引、小売取引のあり方等)を検討する必要があります。
このため、電力・ガス監視等委員会事務局長の私的懇談会として、2017年10月より競争的な電力・ガス市場研究会(以下「競争研」という。)を設置し、ガスシステム改革の趣旨を踏まえて、より一層競争を促進していくため、ガス市場における競争促進策の検討を行いました。
具体的には、(ア)ガス事業における市場の画定の理論的整理を行ったうえで、(イ)ガス小売市場と(ウ)ガス卸市場について、それぞれの競争政策上の課題の検討を行い、中間論点整理を取りまとめました。以下がその概要です。
(ア)ガス事業における市場の画定
市場画定の理論的、実務的な目的・位置づけ等については、独禁法においても多くの議論がありますが、客観的、論理的な議論を進める上で有用です。事業法の観点からも、独禁法における市場画定の考え方を踏まえて、市場支配的事業者の行為等によってどのような市場で競争に歪みが生じる可能性があるかを検討し、必要な措置を検討することが有益です。
競争研における議論では、ガス事業における市場画定として、電力市場と比較すると卸取引は限定的ですが、導管でつながっているエリア内では、理論的には、競争は可能であると考えられ、地理的にはそのような市場画定が将来的にありうるとの整理を行いました。
ただし、現状としては、導管が物理的につながっているエリアであっても、各社の間での供給区域を越える競争は相当に限定的であるといった実態を踏まえれば、事実上は市場が分割されることになっている可能性があることから、越境取引の実態、越境託送の状況等を十分に踏まえて、実証的に検討する必要があります。また、熱量、圧力、成分等の違い等によりエリア間またはエリア内の競争に制約がある場合には、個別の判断が必要となる可能性もあると考えられます。
(イ)ガス小売市場における競争政策上の課題
一般論として、契約期間は、当事者の合意によることが原則であるが、ガス市場において存在するとの指摘がある長期契約を高額の違約金によって担保するような取引慣行(電力市場においても一部存在するとの指摘がある)は、事業法上は、サンクコストになるような投資が必要といった事情により正当化しうる場合を除いては、経済合理性が乏しいものであり、競争研における議論においても、そもそも、ガス事業において、不当に高額な違約金を伴う長期契約を締結する合理性について大いに疑問があり、そのような取引慣行の合理性は検証される必要があると整理されました。
特に、ガスについては、長期契約とその解除に伴う高額の違約金を課す取引慣行について、LNGの引き取り量の削減に限界がある等の経緯を主張する指摘があるが、本来的には、企業自身が調達から販売までリスク管理を行う余地があり、また、需要離脱が生じた場合にも同量を競争者等に卸供給を行うことによって解決可能であるため、事業法上の考え方としては、需要家のためにサンクコストとなる特別の投資を行った場合などの例外的な場合を除けば、基本的には、正当化は困難です。このため、市場支配的事業者や市場における有力な地位にある事業者による長期契約に関する規制の在り方について、さらに検討される必要があります。
(ウ)ガス卸市場における競争政策上の課題
ガス小売市場の競争促進に向けて、現在及び将来の需要者に資するために、取引所創設等の取引量の増大に向けた措置、ガス卸市場の支配的事業者等による自社の小売部門と同水準での卸供給に向けた措置などについて、事業法の枠組みの中で検討を行い、必要な措置を講ずることが必要であるとの整理を行いました。
関連して、現行の実務において、一部の地域で旧一般ガス事業者等によって行われているワンタッチ卸(小売事業者は卸事業者から需要場所でガスの卸供給を受ける仕組み)は、ガスの調達、託送契約及び同時同量オペレーションを卸事業者に委ねることができるという点で、新規参入の促進に寄与するものであり、保安業務の委託の円滑化とともに実施することで、有益であるとの指摘がありました。
(2)ガスにおけるスイッチング業務等の標準化
小売全面自由化前、ガスシステム改革小委員会においてスイッチング業務フロー等を標準化することと整理されたことを受けて、日本ガス協会(以下「JGA」という。)が主体となって標準化を進めてきました。他方、実際にはスイッチング業務フロー等の標準化は不十分であり、ガス導管事業者毎に業務フローやフォーマットが異なることによって、複数のエリアに参入する事業者の業務コストの増加を招き、新規参入者の負担となっていることが、2017年11月の第24回制度設計専門会合で新規参入者より指摘されました。
これを受けて、委員会は、JGAが行ってきたスイッチング業務等の標準化状況と今後の対応方針を確認・整理するとともに、スイッチング環境等の更なる整備に向けて検討することとしました。
円滑なスイッチングの実現に向けて、スイッチング業務をはじめとする小売事業者と導管事業者との間で発生する業務の標準化を検討しました。具体的には、(ア)業務フロー(各業務に必要な申込・報告等の手順、必要な様式を作業プロセスとともに明らかにしたフロー)、(イ)要求項目(各様式でやりとりする情報項目)、(ウ)情報共有手段(各様式をやりとりするための手段)、(エ)レイアウト(各様式のレイアウト)の標準化を図りました。
2018年2月から電気・石油を含む新小売事業者、一般ガス導管事業者としてJGA、委員会事務局とのたため、実際よりも収支上の利益率が高くなっていた」(13社)、「利益率が高いとは考えていない等」(12社)との回答がありました。
間で検討会議を定期的に開催、スイッチング業務等の標準化に向けた協議を実施し、今般、2019年2月に開催された制度設計専門会合にてとりまとめの報告を行いました。
今後は、業務マニュアルの作成、事業者への周知を業界団体とも連携しつつ行い、2019年度以降、標準化された業務の運用を導管事業者に求めていく予定です。
【第362-5-1】ガスのスイッチング業務等の標準化の考え方
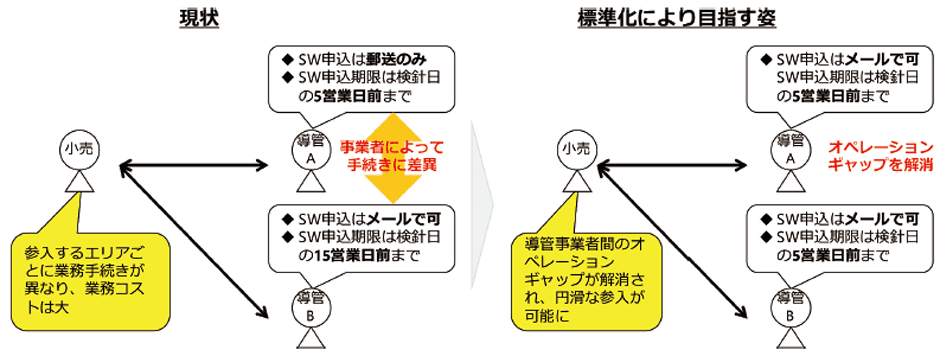
- 出典:
- 第36回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019年2月15日)を基に電力・ガス監視等委員会作成
【第362-5-2】ガスのスイッチング業務等の標準化内容
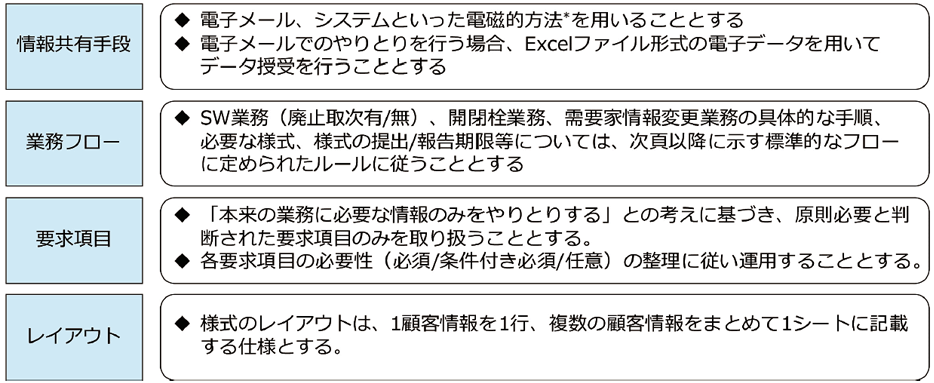
- 出典:
- 第36回制度設計専門会合 事務局提出資料(2019年2月15日)を基に電力・ガス監視等委員会作成
(3)LNG基地第三者利用の促進
ガス卸選択肢の拡大による小売市場の競争促進の観点から、2017年4月に整備されたLNG基地の第三者利用制度でしたが、利用を希望するあるいは利用する可能性のある事業者の一部から下記のような意見が寄せられたことから、制度の利用促進に向けて制度の改善を検討しました。
- (ア)製造設備の余力(情報開示が不十分、余力の判定方法が厳しい)
- (イ)基地利用料金(情報開示が不十分、利用料金が高い)
- (ウ)事前検討申込時に必要な情報(求められる情報が過剰)
上記3つの項目について、各事業者への個別ヒアリング、アンケート調査を重ね実態を把握するとともに、制度設計専門会合(2018年2月23日、4月23日、6月19日、9月20日開催)にて審議を行い、当審議会での議論を踏まえ、(ア)製造設備の余力、(イ)基地利用料金、(ウ)事前検討申込時に必要な情報について「適正なガス取引についての指針」の改定などが必要であると取りまとめました。
「適正なガス取引についての指針」の改定については、2018年10月29日開催された電力・ガス取引監視等委員会の議決、同年10月30日から11月28日の間に実施されたパブリックコメントを経て、同年12月6日に電力・ガス取引監視等委員会が経済産業大臣に建議しました。その後、2019年1月15日付で、「適正なガス取引についての指針」は改定されています。
LNG基地の第三者利用制度の促進に向けた制度改善のポイント
(ア)製造設備の余力
(i)リスク容量の設定方法
- 利用可能容量と在庫量との間に大きな乖離を発生させるなどして、タンク余力を過小に評価している可能性のあった製造事業者に対して、合理的な説明や運用実態に合わせたリスク容量の改善を求めた。
- 該当する事業者は過去の実績に基づきリスク容量の設定を改善。
(ii)自社利用計画の範囲の設定方法
- 毎年度定量的な情報に基づき自社利用計画の範囲を設定していない、あるいは設定していたとしても当該情報を的確に公表情報に反映していない製造事業者に対して是正を求めた。
- 該当する事業者は直近の情報に基づき自社利用計画の範囲を改善。
(iii)余力見通しの開示方法
- 「①ルームレント方式において利用可能となる容量、②ルームシェア方式において利用可能となる量を定量的に示すこと」を望ましい行為としてガイドラインに明記。
(イ)基地利用料金
(i)貯蔵料金の算定に用いる課金標準の在り方
- 「ルームシェア方式においては「平均貯蔵量」のようなタンクの占有状況を適切に反映する課金標準、「払出量」のような競争促進に資する課金標準に基づき料金算定を行うこと」を望ましい行為としてガイドラインに明記。
(ii)配船計画策定時の調整に伴い発生する貯蔵料金の変動の考え方
- 「配船調整又はLNGの貸借によって生じた貯蔵量の増加分を貯蔵料金に反映させること」を問題となる行為としてガイドラインに明記。
- 「配船調整又はLNGの貸借によって生じた貯蔵量の減少分を貯蔵料金に反映させること」を望ましい行為としてガイドラインに明記。
(iii)基地利用料金の情報開示
- 「守秘義務契約締結後速やかに基地利用料金の目安を、検討結果回答時に概算額を基地利用希望者に通知すること」を望ましい行為としてガイドラインに明記。
(ウ)事前検討申込に必要な情報
- (i) LNG船の情報については基地利用希望者の任意、LNG性状の情報については、発熱量のみ必須(申込時点で確定していない場合は想定値でも可)、それ以外の情報は基地利用希望者の任意での提供とすることを製造事業者に対して求めていく。
- (ii)基地受入可否の判断に必要のない情報の提供は要求しないよう製造事業者に是正を求めていく。
【第362-5-3】液化貯蔵設備の余力見通しの改善のポイント
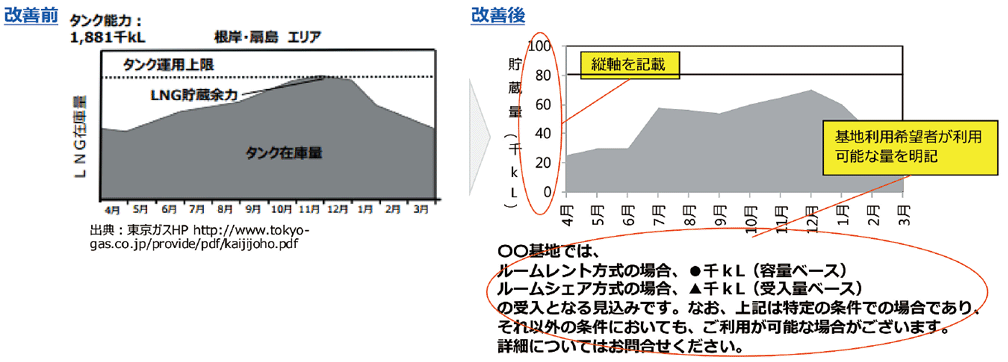
- 出典:
- 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
【第362-5-4】基地利用料金の適切な情報開示の在り方のポイント
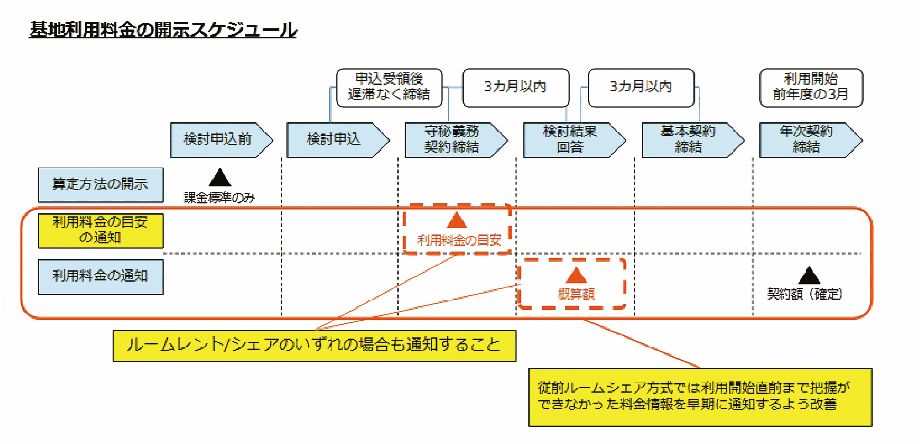
- 出典:
- 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成
6.ガス安全小委員会における議論
ガスの小売全面自由化が行われ、新たなガス小売事業者の参入が開始されたことから、ガス小売事業者の保安水準の維持、向上を図る施策の検討をガス安全小委員会において実施しました。需要家にガス小売事業者の自主保安活動の特徴的な取組状況をホームページで分かりやすく紹介し、消費者が保安面で優れているガス小売事業者を選択することを支援する「見える化」制度を2017年度に構築しました。2018年度においても引き続き、「見える化」制度の拡充を図り、自主保安活動の推進を後押ししています。
また、新規参入に伴い、一般ガス導管事業者は担い手と一体になり、保安水準の維持、継続的な体制の確保を行っていくとともに、内管の保安や工事の委託に関する要件の透明化を図っていくためガス安全小委員会で引き続き議論を行っています。
7.熱供給システム改革の概要
熱供給システム改革は、電力・ガスシステム改革とあいまって、熱電一体供給も含めたエネルギー供給を効率的に実施できるようにするため、2013年11月に総合エネルギー調査会基本政策分科会の下に設置された「ガスシステム小委員会」において熱供給事業の在り方などを検討・審議し、2015年6月の電気事業法等の一部を改正する等の法律の成立を受けた後は、熱供給システム改革を着実に進めていく上で必要な実務的な課題を含めた具体的な制度設計について議論を行いました。2016年4月に実施された熱供給システム改革では、許可制としていた熱供給事業への参入規制を登録制とし、料金規制や供給義務などを撤廃し(ただし、他の熱源の選択が困難な地域では、経過措置として料金規制を継続)、熱供給事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課しました。
熱供給システム改革の実行により、事業環境の整備が行われ、エネルギー市場の垣根の撤廃や異業種からの参入が促進され、電力・ガスシステム改革が一体的に推進していくことが期待されています。
- ※
- 原価算定期間終了前の東京ガス及び料金改定表明済みの大阪ガスは、事後評価の対象外。