第1節 電力システム改革の断行
1.電力広域的運営推進機関の取組
東日本大震災により、大規模電源が被災する中、東西の周波数変換設備や地域間連系線の容量に制約があり、また、広域的な系統運用が十分にできませんでした。このため、不足する電力供給を手当てすることができず、国民生活に大きな影響を与えたことから、2013年11月に成立した電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)に基づき、強い情報収集権限と調整権限の下で広域的な系統計画の策定や需給調整等を行う「電力広域的運営推進機関」が2015年4月に発足しました。
電力広域的運営推進機関では、地域間連系線等の整備等に関する方向性を整理した「広域系統長期方針」を取りまとめるとともに、東西の周波数変換設備及び東北東京間連系線の増強に関する「広域系統整備計画」を策定し、増強に向けた工事の準備が行われています。また、電力系統の増強に当たっての発電設備設置者と一般送配電事業者の費用負担のルール(発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担の在り方に関する指針)に基づく一般負担の上限額の検討や連系線利用ルールの見直しなど、系統運用ルールの整備にも取り組んでいます。また、2018年1、2月には東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域において、強い寒気の影響による需要増加と、揚水発電可能量の減少が見込まれ、需給の状況が悪化するおそれがあったため、電気事業法第28条の44第1項に基づき、関係する電気事業者に対し、電力融通の指示を行いました。
2.電力の小売全面自由化への対応
家庭を含めた全ての電気の利用者が電力供給者を選択できるようにするため、2016年4月に電力の小売全面自由化を実施しました。全面自由化に際しては、まず旧一般電気事業や旧特定規模電気事業といった類型に代わる区分として、小売電気事業(登録制)、送配電事業(許可制)、発電事業(届出制)という事業ごとの類型を設け、それぞれ必要な規制を課すこととしました。具体的には、自由化後も電力の安定供給を確保し、需要家保護を図るため、以下のような様々な措置を講じています。
まず、電気の安定供給を確保するための措置として、適切な投資や人材の確保の必要性に鑑み、一般送配電事業者に対して、需給バランス維持、送配電網の建設・保守、最終保障サービスの提供、離島のユニバーサルサービスの提供を義務付けるとともに、これらを着実に実施できるよう、地域独占と総括原価方式の託送料金規制(認可制)を措置しました。また、小売電気事業者に対して、需要を賄うために必要な供給力を確保することを義務付けることとし、将来的な供給力不足が見込まれる場合に備えたセーフティネットとして、電力広域的運営推進機関が発電所の建設者を公募する仕組みを創設しました。さらに、需要家保護を図るための措置として、小売電気事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課すとともに、旧一般電気事業者に対し、少なくとも2020年3月末まで経過措置として料金規制を継続することとしています。
加えて、小売全面自由化に伴い、多種多様な事業者が卸電力取引所で取引を行う機会が増加することや、一時間前市場の創設等、制度変更により卸電力市場を利用して不当に利益を得るケースが想定されることから、不正取引(相場操縦等)の防止、国による市場監視、取引所の運営の適切性確保を可能とする規制措置を講じています。こうした措置を通じて、市場の透明性と廉潔性を維持することが、卸電力市場の活性化に資すること、ひいては小売電力市場の活性化につながることと考えています。
3.電力の小売全面自由化の進捗状況
(1)電気事業制度に係る制度設計について
2015年9月に設置された電力取引監視等委員会(2016年4月に電力・ガス取引監視等委員会に改組。)において、①小売営業に関するルール、②卸電力市場における不公正取引の取締手法、③今後の託送料金制度のあり方など、電力取引の監視に必要な詳細な制度設計の議論が進められてきました。
また、電力システム改革が進展する中で、電力分野において、エネルギー政策の基本的視点である、安全性、安定供給、経済効率性、及び環境適合を同時に達成していくことが求められます。効率的かつ競争的な電力市場の整備等の環境整備を進めると同時に、電力システム改革が我が国経済における成長戦略としての効果を最大限に発揮するためにも、市場における担い手としてのエネルギー産業を国際的にも競争力のあるものとしていくことが必要不可欠です。このため、電気事業制度に係る制度設計をはじめとして、電力分野の産業競争力強化に向けた幅広い政策課題を検討する場として、2015年10月、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の下に電力基本政策小委員会が設置されています。また、2016年9月には、競争活性化の方策とともに、自由化の下でも公益的課題への対応を促す仕組みの整備のため、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に電力システム改革貫徹のための政策小委員会を設置し、競争活性化の方策と競争の中でも公益的課題への対応を促す仕組みの具体化に向けた検討を開始しました。
このように、電力システム改革の制度設計については、総合資源エネルギー調査会(電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会、基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会)や電力・ガス取引監視等委員会(制度設計専門会合)において、検討してきたところであり、引き続き適切な場において検討を進めます。
(2)小売電気事業者の登録
2018年3月時点で約570件の小売電気事業者登録の申請があり、2018年3月31日時点で467者を登録しています。
この小売電気事業登録は、法令に則り、資源エネルギー庁が、最大需要電力に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがあるか、電力・ガス取引監視等委員会が、電気の使用者の利益の保護のための措置が講じられているかといった観点から、それぞれ審査を行っています。
登録された事業者の内訳は、もともと高圧の小売電気事業を行っていた新電力事業者(PPS)に加え、LPガス及び都市ガス関係、石油関係、通信・放送・鉄道関係等の事業者など、非常に多岐にわたります。従来の料金体系とは異なる段階別料金や既存事業とのセット割、時間帯に応じて料金差を付ける時間帯別料金等の新たなメニューの提供が見られます。
(3)新電力への契約先の切替え(スイッチング)実績
2017年12月の電力取引報によると、電力の小売全面自由化で新たに自由化された低圧部門において、新電力への契約の切替えを選択した需要家が全国で約8.7%となっています。また、地域の既存電力会社が設定した自由料金メニューへの切替えを選択した需要家も約5.5%となっており、両者を合わせると、約14.2%の消費者が自由料金メニューへの切替えを行っています。また、全面自由化後、特高・高圧部門における新電力のシェアも増加しており、結果として、電力市場全体としては、新電力のシェアが約12.7%となっています。
地域別には、低圧分野では、東京・中部・関西地域など、都市圏において自由料金メニューへの切替えを選択した需要家の割合が高くなっており、北陸・四国地域においては、相対的に低い傾向にあります。
(4)料金メニューの多様化
新電力の提供する料金メニューを見ると、全体的な傾向としては、基本料金と従量料金の二部料金制からなる既存の料金メニューに準じた料金設定が多く見られます。他方、一部では、完全従量料金メニュー、定額料金メニュー、指定された時間帯における節電状況に応じた割引メニューなど、新しい料金メニューも提供されるようになっています。
なお、多くの新電力は、料金規制の残る大手電力会社が毎月公表する燃料費調整額を引用した料金メニューを採用しておりますが、経済産業省では需要家の選択肢を拡大する観点から、2018年度に庁舎で使用する電気の調達に際して、燃料費調整を行わないことを条件とする公募を行いました。
また、再生可能エネルギー等の電源構成や、地産地消型の電気であることを訴求ポイントとして顧客の獲得を試みる小売電気事業者の参入も見られ、中には需要家が発電所を選んで得票数の多かった発電所に報奨金を与えることができるなど、特色のある小売電気事業者も存在しています。
さらに、電力消費の見える化(電気の使用状況の可視化)や、電気の使用状況等の情報を利用した家庭の見守りサービスなども提供され始めています。応援するスポーツチームとの繋がりや里山の景観保存など、需要家の好みや価値観に訴求するサービスも始まっています。
(5)卸電力取引の活性化について
電力システム改革の目的である小売電気事業者間の競争を通じた安定的かつ安価な電力供給を実現するためには、小売電気事業者が小売供給に必要な電源を市場から調達できるだけの卸電力市場の活性化が不可欠となっています。このため、電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合では、卸電力市場の活性化に向けた取組などについての議論を行っています。
具体的には、制度設計専門会合において、①旧一般電気事業者による自主的取組の改善、②グロスビディングなどの卸電力市場活性化策の検討、③常時バックアップや相対取引に関する社内外取引価格の検証、④原子力再稼働や太陽光などが卸電力市場へ与える影響の分析などを実施しています。
まず、①旧一般電気事業者による自主的取組の改善については、「電力システム改革専門委員会報告書」(2013年2月)において、旧一般電気事業者は必要な予備力を除く余剰電力を限界費用ベースで全量市場へ供出する旨の整理が行われているところ、旧一般電気事業者へのヒアリングなどを通じ、入札可能量の算定方式や入札価格設定方法の見直しなどの改善を提案することで、自主的取組の更なる改善を推進し、卸電力市場の流動性の向上を実現しました。また、旧一般電気事業者が電源開発株式会社の保有する電源(以下「電発電源」とする。)と長期相対契約を締結している現状を踏まえ、契約内容の分析やヒアリングなどを通じ、電発電源の更なる切出しを実現しました。
次に、②グロスビディングなどの卸電力市場活性化策については、諸外国における卸電力市場の活性化策も踏まえつつ、卸電力市場の流動性向上や価格指標性の向上、社内取引価格の透明性向上などを目的として、旧一般電気事業者の社内取引の一部又は全部について、必要量の買戻しを前提に取引所を介して売買するグロスビディングの導入に向けた取組を実施しました。委員会においては、グロスビディングの自己約定分に対する事業税課税などの課題を克服することで、第13回制度設計専門会合(2016年11月30日)において、旧一般電気事業者9社より、自主的取組としてグロスビディングを実施する旨の表明が行われており、2017年7月末時点において、表明のあった全ての旧一般電気事業者がグロスビディングを実施済みであることを確認しました。今後、グロスビディングの評価方法や同取組が卸電力市場へ与える影響などについては、制度設計専門会合において検討を行うことを予定しています。
また、③常時バックアップや相対取引に関する社内外取引価格の検証については、発電設備の大宗を保有する旧一般電気事業者が新電力へ社内取引と同条件で取引を行っているかをデータに基づいて検証するべく、旧一般電気事業者の社内取引コストと常時バックアップ価格や新電力の電源調達コストなどの検証を実施しています。また、旧一般電気事業者との競争格差などを分析するべく、公共入札に関する旧一般電気事業者と新電力の入札結果分析などを実施するなど、データに基づいた競争環境の分析や検証を進めてきました。
さらに、④原子力再稼働や太陽光などが卸電力市場へ与える影響の分析については、2017年4月より、卸電力取引所へFIT電気が供出されることや原子力発電所の再稼働などの市場環境の変化を受け、これらが卸電力市場の流動性向上や価格にどのような影響を与えるかについて定量的な分析を行いました。
その他、旧一般電気事業者や新電力へのアンケートを通じ、卸電力取引所に設置された発電情報公開システムの改修提案や沖縄地域における卸電力市場の活性化策の検討などを実施しております。
上記の取組等により取引所取引量は大きく増加しました。具体的には2016年度(2016年4月~2017年3月)の取引量は、2005年の市場開設以来、初めて200億kWhを突破し、販売電力量全体に占める2018年3月末時点の割合は、8.2%となっております
【第361-3-1】2017年10月〜12月の報告における主要指標
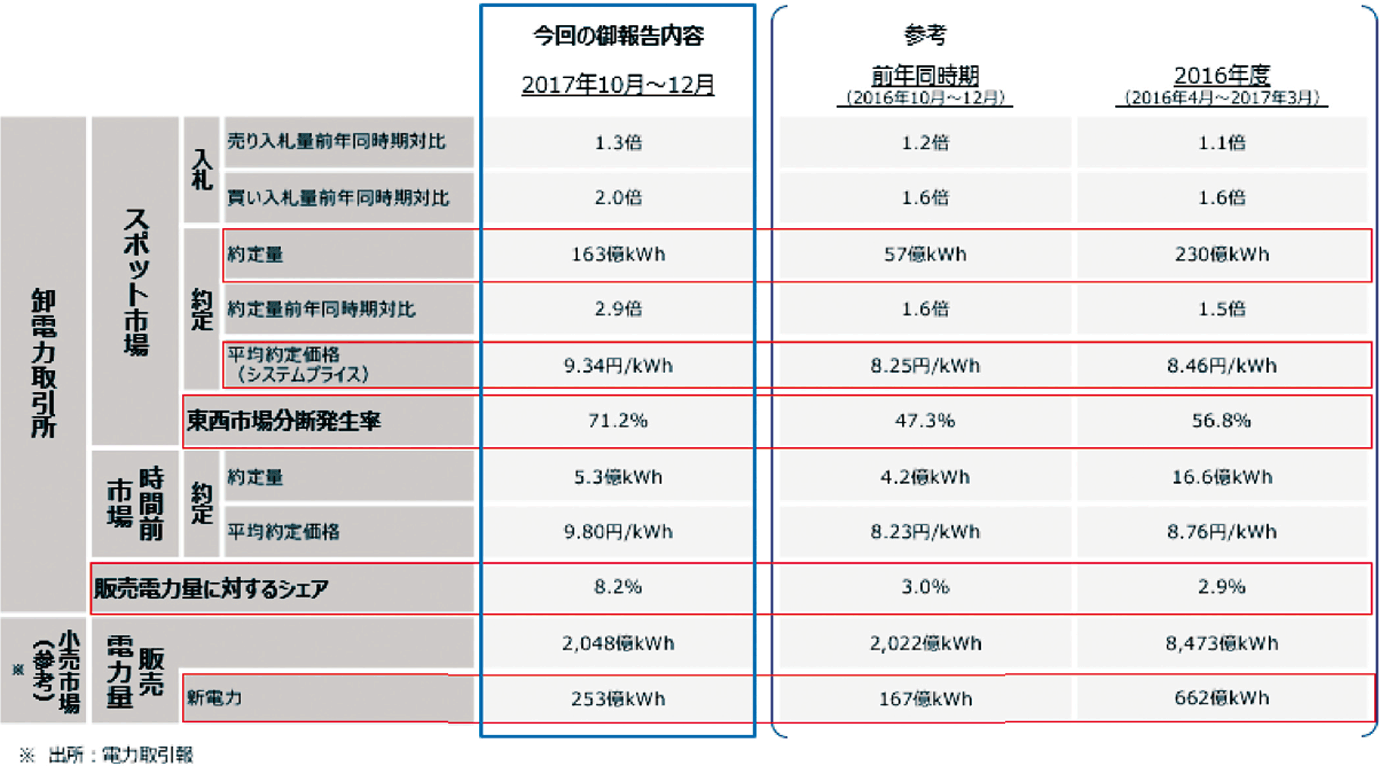
加えて、電力・ガス取引監視等委員会では、旧一般電気事業者の自主的取組や電力市場における競争状況を定点的に分析・検証するため、四半期毎に電力市場のモニタリングを実施しています。第28回制度設計専門会合までに、制度設計ワーキング・グループでの報告も含め、累計で12回にわたりモニタリングレポートを作成・公表しており、今後も継続的に電力市場のモニタリングを行っていきます。
【モニタリングレポートの実施状況】
- 第1回 制度設計ワーキング・グループ(2013年8月2日)
- 第6回 制度設計ワーキング・グループ(2014年6月23日)
- 第13回 制度設計ワーキング・グループ(2015年6月25日)
- 第4回 制度設計専門会合(2016年1月22日)
- 第8回 制度設計専門会合(2016年6月17日)
- 第11回 制度設計専門会合(2016年9月27日)
- 第14回 制度設計専門会合(2016年12月19日)
- 第16回 制度設計専門会合(2017年3月31日)
- 第19回 制度設計専門会合(2017年6月27日)
- 第22回 制度設計専門会合(2017年9月29日)
- 第25回 制度設計専門会合(2017年12月26日)
- 第28回 制度設計専門会合(2018年3月29日)
(6)電力の小売営業に関する指針の改定
2016年4月からの電力小売全面自由化を契機に多様な事業者が参入することを踏まえ、関係事業者が電気事業法などを遵守するための指針を示し、これにより電気の需要家の保護を図るため、2016年1月に新たなガイドライン(「電力の小売営業に関する指針」)を策定しました。同年7月には小売電気事業者が、業務提携先である媒介・代理・取次業者を自社ホームページなどにおいて分かりやすく公表することを「望ましい行為」として追加するなどの改定を行うことについて委員会より建議し、経済産業大臣が改定しました。
2017年6月には電気そのものの価値と環境価値(非化石価値)を分離して、環境価値のみを取引する「非化石価値取引市場」が開設されることに伴い、①再生可能エネルギー指定の非化石証書を購入した小売電気事業者による「再生可能エネルギー指定の非化石証書の購入により、実質的に、再生可能エネルギー電気●●%の調達を実現している」との訴求や、②非化石証書を購入した小売電気事業者による「非化石証書の購入により、実質的に、二酸化炭素排出量がゼロの電源(いわゆる「CO2ゼロエミッション電源」)●●%の調達を実現している」などとの訴求は、実際の電源構成の表示を併せて行うなど、小売供給に係る電源構成と異なることについて誤認を招かない表示である限りにおいては、問題とならない旨明記するなどの改定を行いました。
【第361-3-2】電源構成の開示の方法(表示の例)
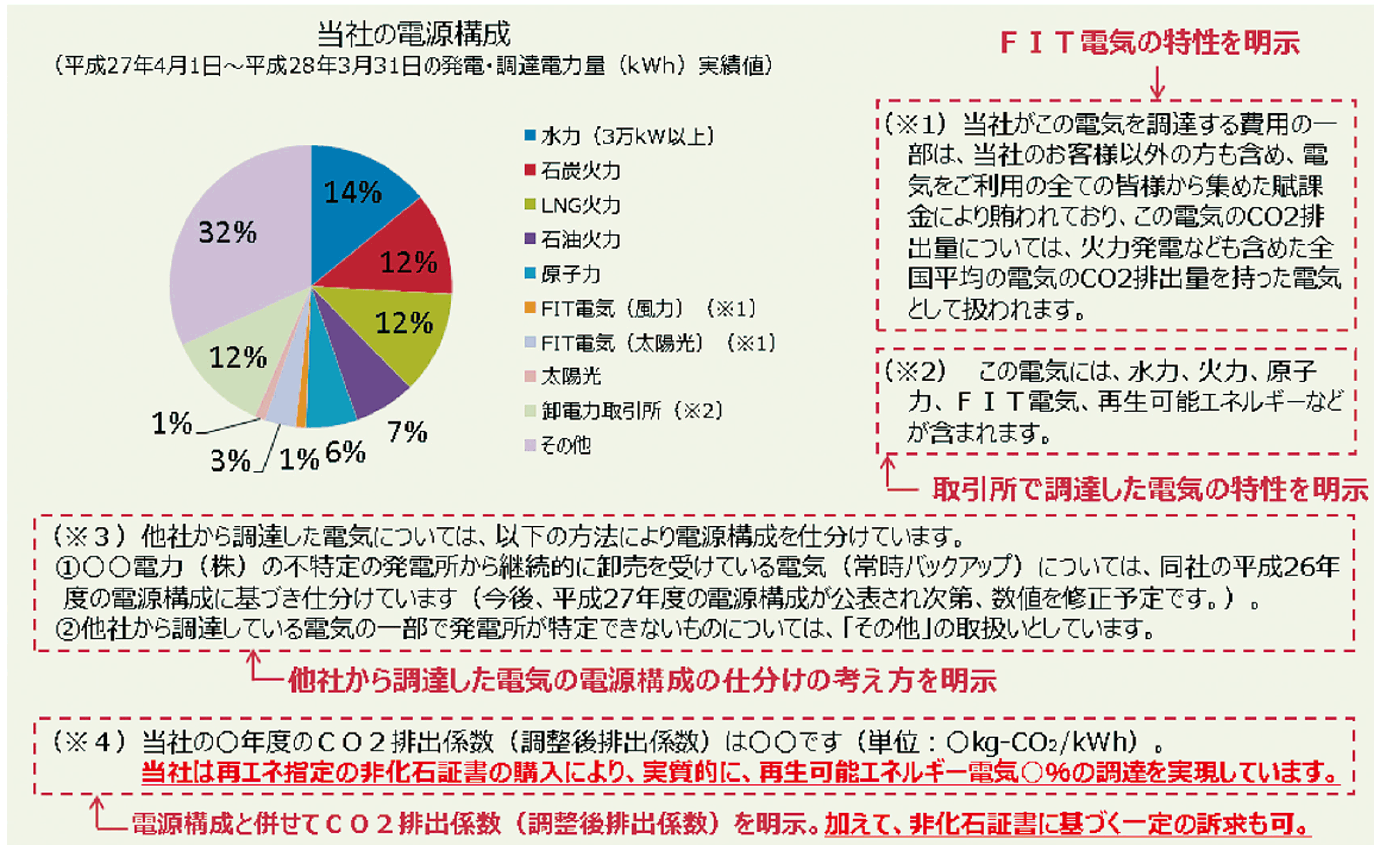
(7)小売電気事業者に対する指導等について
2016年4月には電気の小売事業への参入が全面自由化され、家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択できることとなりました。こうした中、電気の小売供給に関する取引の適正化を図るため、「電力の小売営業に関する指針」を踏まえ、需要家への情報提供や契約の形態・内容などについて、電気事業法上問題となる行為を行っている事業者に対して指導を行うなど、事業者の営業活動の監視などを行いました。また、委員会の相談窓口などに寄せられた不適切な営業活動などについて、事実関係の確認や指導を行うとともに、独立行政法人国民生活センターと共同し、2016年3月~2017年11月の間に相談事例の紹介及びアドバイスについてプレスリリースを8回行い、情報提供しました。
(プレスリリースの実施状況)
- 第3回 2016年3月14日 2016年3月までの相談内容について
- 第4回 2016年4月1日 2016年3月までの相談内容について(自由化開始後)
- 第5回 2016年4月26日 2016年4月までの相談内容について
- 第6回 2016年6月17日 2016年5月までの相談内容について
- 第7回 2016年9月1日 2016年 8月までの相談内容について
- 第8回 2016年11月16日 2016年10月までの相談内容について
- 第9回 2017年3月30日 2017年2月までの相談内容について
- 第10回 2017年11月30日 2017年10月までの相談内容について
【第361-3-3】消費者からの相談状況
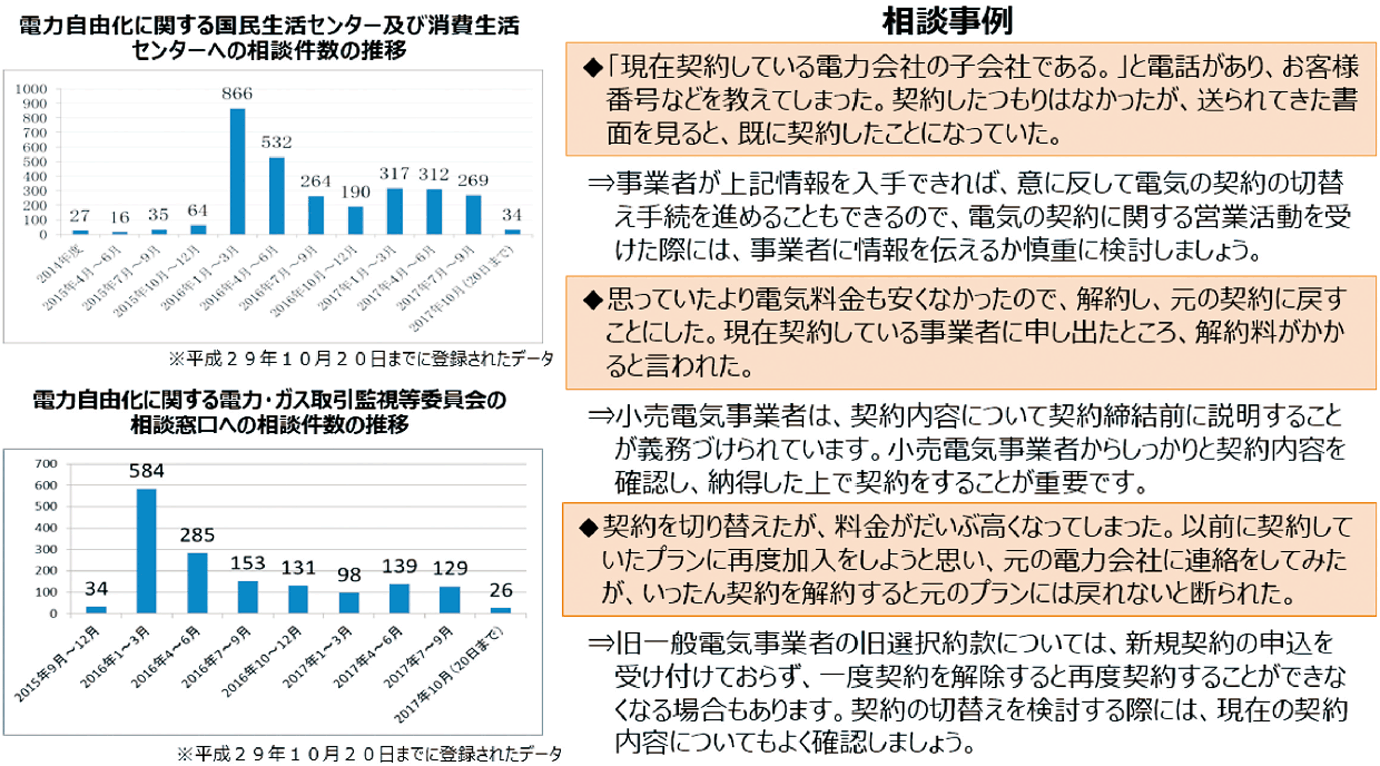
(8)東京電力エナジーパートナーへの業務改善勧告について
東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東京電力EP」)は、2016年10月から2018年2月までの間、需要家に対し訪問営業又は電話営業により電力供給契約に係る供給条件について説明した際(電話営業においては供給条件について説明を行った後)、5,735件の需要家について、契約締結前交付書面を交付していませんでした。
また、同社は、2017年5月から2018年1月までの間、需要家に対し訪問営業によりガス供給契約に係る供給条件について説明した際、6,606件の需要家について、契約締結前交付書面を交付していませんでした。(※電力供給契約及びガス供給契約をセットで契約しようとした際に契約締結前交付書面を交付されなかった需要家が5,282件いたことから、契約締結前交付書面を交付されなかった需要家の実数は、7,059件。)
このため、電力・ガス取引監視等委員会は、本事案について、電力及びガスの適正な取引の確保を図るべく、電気事業法及びガス事業法に基づき、東京電力EPへの業務改善勧告を行いました。同勧告の内容は、以下のとおりです。
(東京電力EPに対する業務改善勧告の概要)
- 契約締結前交付書面を交付しなかった需要家に対し、適切な措置(電力供給契約又はガス供給契約の継続の意思確認を含む。)を講ずること。
- 需要家に対する契約締結前交付書面の不交付事案が今後発生しないよう必要な措置を講ずること。
- 前記1.及び2.に基づいて講じた措置について、2018年4月2日までに、電力・ガス取引監視等委員会に対し、文書で報告すること。
同勧告に基づき、東京電力EPは、2018年4月2日付けで以下のとおり回答しています。
(業務改善勧告に対する東京電力EPの回答の概要)
需要家対応について
- 契約締結前交付書面を交付しなかったとされる7,059件の需要家のうち、再度の確認で適切に当該書面を交付していたことが判明した157件を除く6,902件の需要家に対し、2月7日および8日に「お詫びの文書」を郵送または持参し、その後電話や訪問により契約継続の意思確認を実施。この際、解約の意向のあった需要家にはスイッチングの手続きを説明する等の対応を実施。
- 「申込意思が不明確」を理由に解約した需要家を対象に、営業拠点の管理・監督を行う立場にない部署の職員により、営業当時の経緯の詳細について再ヒアリングを行い「申込意思が不明確」な解約事案を担当した営業職員に対し、営業部門以外の企業倫理担当等がヒアリングを実施した。この結果、需要家に契約の意思がないことを認識しつつ需要家に無断で契約を締結したと認めるに足る事実は確認できなかった。
再発防止策について
- 経営陣のコンプライアンスへのコミットメント
- 規範を容易に遵守できる環境の整備
- 不祥事の芽を早期に摘み取る仕組み作り
また、東京電力EPは、2018年4月2日以降に改めて営業職員に対して研修を実施し、営業職員が新しい内規および法規範と業務の関係について理解していることを確認した上で、営業を再開する予定である旨、電力・ガス取引監視等委員会に対して報告しました。
(9)一般送配電事業者に対する指導など
2016年4月の電力小売全面自由化に伴い、各需要家の電気使用量は、毎月、東京電力パワーグリッド(以下「東京電力PG」という。)などの一般送配電事業者が検針し、小売電気事業者へ通知する仕組みとなった。こうした中、東京電力PGにおいて、情報システムの不具合などにより、同月から電気使用量の小売電気事業者への通知遅延が発生しました。
これにより、小売電気事業者から各需要家に対する電気代の請求が遅れるなどの影響が生じることとなりました(未通知件数は、同年5月から8月までの間、約2万件で推移)。
本件は、同年5月19日に、同社から委員会へ報告があり、これに対して、翌20日付け及び6月3日付けで、システムの不具合の詳細と対策などを求める報告徴収を行いました。これらの報告徴収に対する回答などを受け、委員会において検討を行った結果、①約2万件に及ぶ最終需要家に影響が生じていること、②小売電気事業者の切替えを行った最終需要家にとっては、切替えをした結果、電気料金の請求書送付が遅れた形となり、切替え先の小売電気事業者の信用に影響が生じていることなどが確認され、電気事業法第66条の11第1項に規定された「電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるとき」に該当すると判断したため、同月17日付けで、同社に対し、業務改善勧告を発出しました。具体的な内容は以下のとおりです。
(業務改善勧告の概要)
- 具体的かつ効果的な改善計画の策定(小売電気事業者及び小売電気事業者の需要家への対応を含む。)
- 計画実現のための体制整備
- 改善計画の的確な実施と定期的な検証・報告本勧告に基づき、同社は、同年7月1日付けで改善計画を策定しました。具体的な内容は以下のとおりです。
(改善計画の概要)
- 通知遅延対策
個々のメーターの検針データを再度確認する作業の実施 など - 小売電気事業者及び小売電気事業者の需要家への対応
小売電気事業者の需要家向けの問合せ専用窓口の開設 など - 経営管理体制の強化
遅延解消対策の執行状況を監視するチェック機能の強化 など
その後も、委員会は、同社の改善計画の実施状況について月2回報告を受け、状況をフォローするとともに、委員会事務局の職員が月2回程度同社を訪問し、状況を把握し、追加的な対策を求めるなど、問題の解決に向けた指導を行った。同年8月26日には、同社社長に委員会での説明を求めるなどの対応を行いました。
東京電力PGにおいて、当面の目標としていた7営業日以内の通知は、2016年9月以降ほぼ定常的に達成され、その後、更なる業務・システム両面での取組を進め、2017年2月以降、やむを得ない理由を除き、4営業日以内の通知が概ね実現されました。
引き続き、事態の正常化に向けて、指導を続けた結果、同年6月7日付けの同社からの報告により、同社における電気使用量の通知遅延とそれによる関係事業者及び需要家などへの影響は概ね収束しつつあり、また、今後の再発防止策などの実施について一定の見通しが立ったと考えられることから、これまで月2回の提出を求めてきた同社の改善計画の実施状況の報告を終了することとしました。
(10)一般送配電事業者による調整力の公募調達について
2016年4月1日に、電力小売全面自由化や新たなライセンス制の導入を定めた第2弾改正法が施行され、これまで旧一般電気事業者が自社の発電設備を用いて行ってきた、系統全体の周波数維持などの高品質な電力供給を確保する業務であるアンシラリーサービスは、一般送配電事業者が担うこととなりました。また、一般送配電事業者は、アンシラリーサービスの実施に必要な電源などを調整力として発電事業者などから調達するとともに、その調整力の確保に必要なコストは託送料金で回収される仕組みとなりました。この仕組みにより、発電事業者などによる競争が進み、多様な発電事業者などの参画による調達が可能な調整力の量の増大や、質の向上、一般送配電事業者による更なる効率的な調整力の活用が期待されています。
この仕組みは、一般送配電事業者による調整力の調達が公平性・透明性を確保した上で行われることを前提として機能するものであることから、2016年度から行われる一般送配電事業者による調整力の調達は、原則として、公募などの公平性かつ透明性が確保された手続により実施する必要がありますが、その手続の具体的な内容は各一般送配電事業者に委ねられてきました。
このため、事前に一般送配電事業者による適切な調整力の調達の在り方について基本的な考え方を示し、調整力の公募調達が公平性・透明性を確保した形で円滑に開始できるよう、電力・ガス取引監視等委員会の下に設置した制度設計専門会合において、公募調達の公平性・透明性を担保するための考え方、望ましいと考える公募調達の実施方法などをその内容とする「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」を取りまとめ、2016年9月26日に委員会として経済産業大臣に対して建議を行いました。
その後、本建議を踏まえ、経済産業大臣により、「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」(以下「公募ガイドライン」という。)が制定され、一般送配電事業者は当該考え方に基づき、調整力の公募調達を実施しました。
公募ガイドラインにおいて、「調整力の必要量の適切性」、「電力量(kWh)価格の適正性」、「メリットオーダーの状況」を確認することが明記されていることから、2016年度及び2017年度に実施された公募に対し、入札事業者がどのような考え方に基づき電源を選定して入札したか、また、その際のkW価格をどのように算定したか、実運用段階におけるkWh価格の設定に係る考え方を確認し、公表しました。
公募ガイドラインにおいては、情報の公開についても定められており、委員会では、2017年4月からの調整力の運用に関する情報をホームページで公開しています。
2018年度の公募に向けては、電力・ガス取引監視等委員会において更なる改善の必要性などについて、発電事業者やネガワット事業者などに対してアンケートを実施し、その結果を踏まえ、一般送配電事業者に対して公募の改善を要請したことにより、当該アンケートにおいて寄せられた要望等について、一部改善がなされました。
(11)効率性向上のための送配電網の維持・運用費用の負担の在り方について
制度設計専門会合では、2015年秋以降、効率性向上のための送配電網の維持・運用費用の負担の在り方について、電力システム改革の進展など電力市場を取り巻く環境変化を踏まえ、①送配電網の維持・運用コストの抑制・低減、②公平性の確保、③イノベーションの促進の観点より、関係事業者などからのヒアリングを行いつつ、検討を進めてきました。
2016年7月の第9回制度設計専門会合において、それまでの検討内容を踏まえ、一旦論点整理を行いました。具体的には、①発電事業者の負担の在り方、②小売事業者の負担の在り方、③ネットワーク利用の効率化の推進、と論点を大きく3つに分け、また、それらは相互に深く関連することから、今後、一体として、引き続き関係者の意見も聴きながら検討を深めていくこととなりました。
2016年9月、上記の各論点について検討を深めるため、制度設計専門会合の下に送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループ(座長:横山明彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授)が設置され、事業者へのヒアリングなどを行いつつ検討を深めました。
2017年6月、第6回送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループにて、これまでのワーキング・グループにおける議論の論点を整理し今後の検討課題について示した「検討すべき論点」を公表し、その後、検討すべき論点を深めるための議論を進めています。
4.電気料金及び託送料金の事後評価
(1)原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価
家庭など規制部門に適用される電気料金については、原価算定期間終了後に小売電気料金の原価の洗い替えを行わない場合において、引き続き当該料金原価を採用する妥当性については、従来、経済産業省で評価を実施するとともに、経済産業省及びみなし小売電気事業者各社において、以下のような情報公開の取組を実施しています。
① 経済産業省において、原価算定期間終了後に毎年度事後評価を行い、利益率が必要以上に高いものとなっていないかなどを確認し、その結果を公表する(必要に応じて、料金値下げに係る変更認可申請命令の要否を検討する)。
② みなし小売電気事業者各社において、規制部門と全社計に区分した人件費等の実績値の比較結果をホームページで公表する。
【第361-4-1】料金変更認可申請命令に係る審査基準
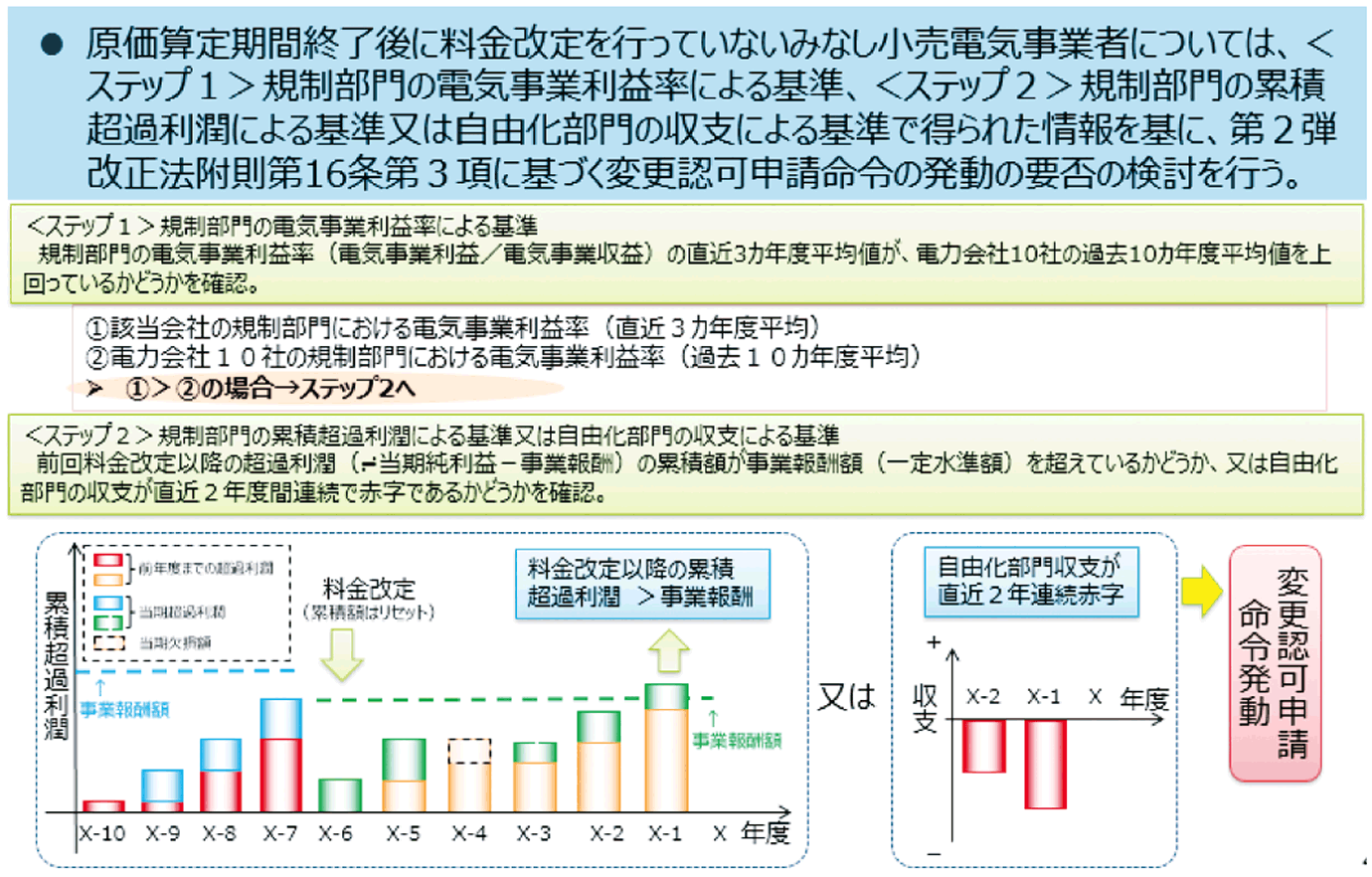
中部電力については、2014年以降の料金値上げ時に経済産業省として継続的に監視していくこととされているとともに、震災後行われた値上げに係る初めての原価算定期間終了後の事後評価であることから、消費者基本計画の工程表において今年度に事後評価を行う旨が記載されています。また、東京電力EPについては、審査基準の<ステップ1>電気事業利益率による基準に抵触し、かつ公的資金の投入がされており、規模が大きく影響が広範と判断しました。加えて、四国電力は現行料金原価において稼働を織り込んでいる原子力発電所(伊方3号機)のすべてが2016年度再稼働しており慎重な確認が必要と判断しました。
これらを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会の下に設置した料金審査専門会合(座長:山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授)において、原価算定期間が終了している他のみなし小売電気事業者(北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、九州電力及び沖縄電力)への事後評価を実施すると共に、上記3社についてはより詳細な、原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価(原価算定期間終了後の追加検証)を実施しました。
(本件に係る料金審査専門会合の開催実績)
- 2017年10月13日 第26回料金審査専門会合
- 2017年11月7日 第27回料金審査専門会合
審査基準のステップ1[電気事業利益率による基準]では、個社の直近3か年度の利益率が10社10か年度平均の利益率を上回る会社は、北海道電力、東北電力、東京電力EP、中部電力、九州電力及び沖縄電力の6社でした。ステップ1に該当した6社について、審査基準のステップ2[累積超過利潤による基準]では、2016年度末累積超過利潤額は一定水準額である事業報酬額を下回っており、ステップ2[自由化部門の収支による基準]では、直近2年連続で自由化部門の収支が赤字となっていませんでした。以上より、原価算定期間を終了しているみなし小売電気事業者9社(2017年8月に値下げを行った関西電力以外)について、審査基準に基づく評価を実施した結果、変更認可申請命令発動の検討対象となる事業者はいませんでした。
【第361-4-2】今年度の審査基準の適用結果
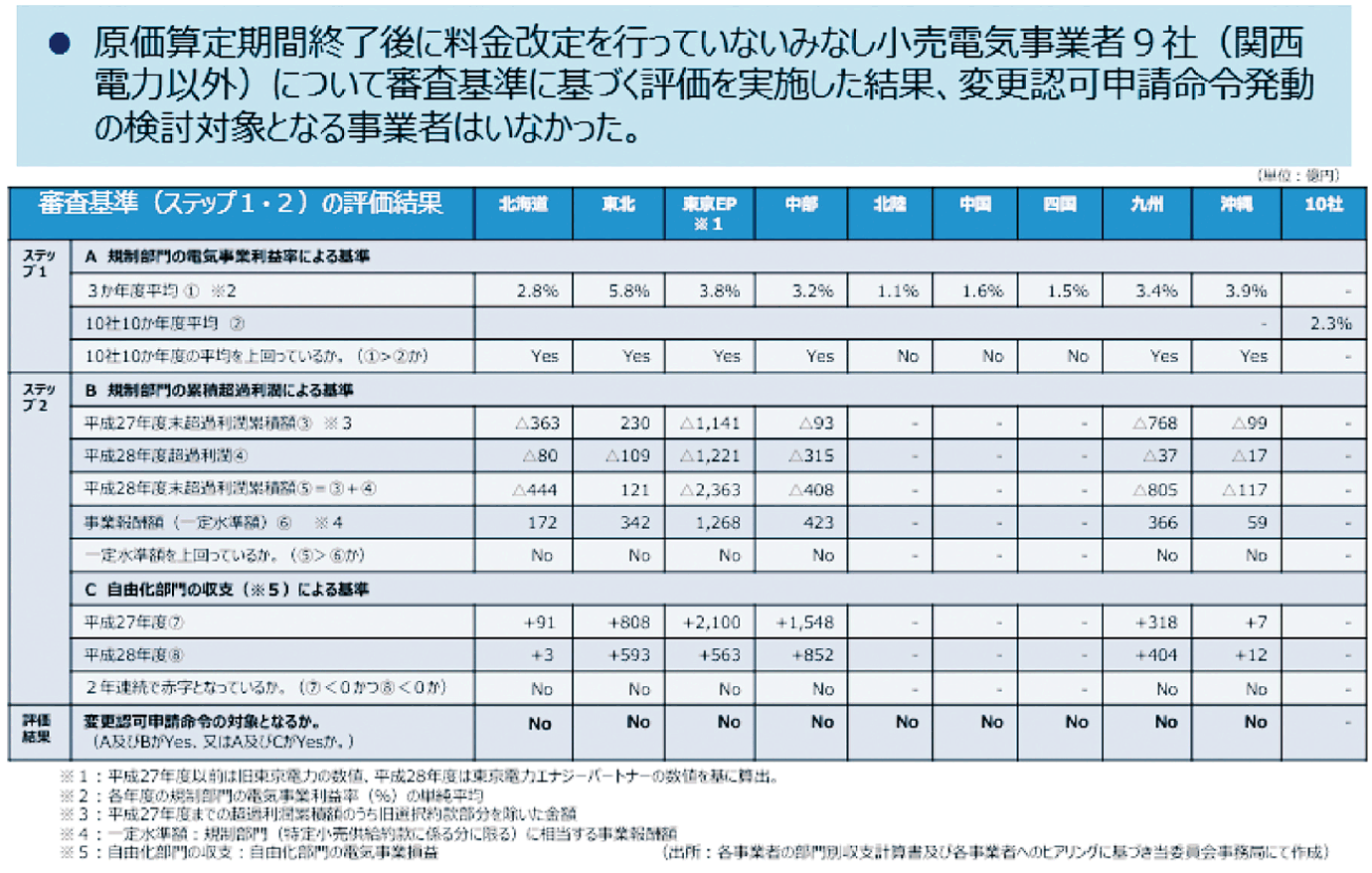
また、原価算定期間終了後の追加検証(中部電力・東京電力EP・四国電力)に関しては、以下の通り、料金適正化の観点から問題となるものは認められませんでした。
(原価算定期間終了後の追加検証(中部電力・東京電力EP・四国電力))
1.原価と実績の比較
燃料価格や為替レートの大幅な変動、原子力発電所の再稼働遅延等の諸事情を踏まえると、個別費目の実績が不合理な理由に基づき料金原価を上回っているものは認められなかった。
2.規制部門と自由化部門の利益率の乖離
各社とも、規制部門と自由化部門の利益率の比較では、規制部門が自由化部門を下回っていたが、この利益率の乖離については、個別の乖離要因の検討の結果、不合理な理由に基づくものではなかった。
3.経営効率化
今回の事後評価では、各社において、緊急避難的な支出抑制・繰延べはなかった。また、恒常的な経営効率化の取組については、各社によって取組の進捗にばらつきがあるものの、各社とも実績が料金原価認可時の計画値を上回っていた。昨年度の事後評価において、緊急避難的な支出抑制・繰延べを恒常的な取組に繋げていく必要があるとの指摘があったが、この点について取組が進んでいる点は評価できる。
以上を踏まえ、今回事後評価の対象となった事業者について、現行の認可料金に関する値下げ認可申請の必要があるとは認められませんでした。
ただし、東日本大震災後の小売規制料金の値上げは、原子力発電所の再稼働遅延を主因とするものであったことに鑑みると、今後原子力発電所が再稼働を果たした場合には火力燃料費等の負担が軽減されていくことから、料金原価への原子力利用率の織り込み状況も踏まえ、そのコスト低減効果を緊急避難的な支出抑制・繰延べの抑止、需要家への還元等に適切に充当するよう検討すべきです。
また、各社においては、今後とも料金原価と直近実績の比較・経営効率化の状況・収支見通し等現行の経過措置料金に関連した分かりやすい情報提供に努めるとともに、安全対策・供給信頼度維持に不可欠な投資は最優先に実施した上で、引き続き経営効率化に真摯に取り組むことにより、コスト低減を進めていくべきです。
なお、送配電非関連固定費の配分の際における部門別収支計算規則に基づく需要補正の実施により、各社で規制部門の利益が減少し自由化部門の利益が増加する結果となっていました。当該規定が、部分自由化当初における導入目的とは異なる形で作用している可能性も踏まえ、制度設計専門会合及び本体委員会である電力・ガス取引監視等委員会において、見直しを含めて議論し、2018年1月24日に経済産業大臣に当該規則の見直しを建議いたしました。2018年3月30日には、需要補正を行わずに実績需要に基づいて配分する規定に改正されております。
(2)一般送配電事業者の収支状況(託送収支)の事後評価
我が国の電力系統を取り巻く事業環境は、中長期的な人口減少や省エネルギーの進展等により電力需要が伸び悩む一方で、再生可能エネルギーの導入拡大による系統連系ニーズの増加、経済成長に応じて整備されてきた送配電設備の高経年化への対応が増大するなど、大きく変化しつつあります。
こうした事業環境の変化に対応し、将来的に託送料金を最大限抑制するため、一般送配電事業者においては、経営効率化等の取組によりできるだけ費用を抑制していくとともに、再生可能エネルギーの導入拡大や将来の安定供給等に備えるべく、計画的かつ効率的に設備投資を行っていくことが求められます。
以上のような問題意識のもと、料金審査専門会合(以下、本項において「専門会合」という)では、託送料金の低廉化と質の高い電力供給の両立の実現を目指して、2016年度託送収支の事後評価を実施し、①効率化に資する他社の取組の導入や、仕様の統一化等を通じた調達合理化を進めることで、更なる費用削減を図ること、②中長期的な観点から、計画的かつ効率的に設備投資や高経年対策を進めること、の2点について重点的に議論しました。
(2016年度託送収支の状況:収支全体について)
2016年度の当期超過利潤累積額について、値下げ命令の発動基準となる一定の水準を超過した事業者はいませんでした(ストック管理)。また、想定単価と実績単価の乖離率について、値下げ命令の発動基準となる▲5%以上の事業者はいませんでした(フロー管理)。
収入面においては、主に電力需要が減少したため、北陸を除く9社で2016年度の実績収入が想定原価を下回りました。一方、費用面においては、北海道電力、東京電力PG、関西電力、九州電力の4社については、主に設備関連費の減少により、2016年度の実績費用が想定原価を下回りました。他の6社については、主に人件費・委託費等の増加により、2016年度の実績費用は想定原価を上回りました。
この結果、2016年度の託送収支においては、東京電力PG、関西電力、九州電力を除く7社で当期欠損となりました。
- ※
- 2018年10月時点で各社が公表していた2017年度託送収支及び料金審査専門会合にて事業者が公表した資料より事務局作成。なお、本託送収支の数値は電気事業監査による指摘等により今後変更の可能性がある。
(コスト削減に向けた取組)
(ア)経営効率化に向けた各社の取組状況について
今回の事後評価で、各社とも様々な経営効率化に資する取組を行い、費用削減に向けて努力していることを確認しました。こうした各社の取組は評価されるべきものです。
各一般送配電事業者には、他社の取組事例も参考に、特に各取組の展開性や削減率の大きさなども考慮しつつ、各社で取り入れられる取組は積極的に取り入れ、更なる効率化やコスト削減に向けて様々な取組を進めることを求めていきます。専門会合としても、引き続き、経営効率化に向けた各社の取組状況を確認していきます。
(イ)送配電設備の仕様の統一化等について
(i)仕様統一化の状況
代表的な設備について各社の仕様を確認したところ、例えば架空送電線といった共通性が高いと考えられる設備であっても、事業者によって仕様が様々でした。気候の違いなどによるものもあると考えられますが、仕様を細分化し他社と異なる仕様となっていることで、それぞれの市場が小さくなり調達コストの上昇につながっている可能性もあります。
このため、今後、各社においては、調達コストの削減に向けてJIS規格の採用といった取組だけではなく、事業者間の仕様の差の実態を把握してその必要性を精査し、国際調達を可能にすることも含め可能な限り仕様の標準化・共通化を進めるよう取り組むべきであり、専門会合としても、引き続き、その実施状況を確認していきます。
(ii)調達の状況
代表的な設備の調達単価について、専門会合の委員及び事務局で具体的な情報を確認し、その経年変化を分析したところ、震災前に比べて調達単価が大きく減少している事業者もいました。このため、当該事業者に調達単価の低減に向けた取組を確認したところ、共同調達、新規取引先の開拓、競争発注の拡大等を含む様々な取組を行っていることが判明しました。
各社においては、他社の取組事例も参考に、取り入れられる取組は積極的に取り入れ、更なる調達コスト削減に向けた取組を進めることを求めていきます。
なお、調達コスト削減に当たっては、調達価格を比較可能な形で公表し、多様な視点から評価されることが有効であると考えられます。このため、専門会合では、引き続き、各社の調達にかかる効率化努力を確認していくこととあわせ、情報公開の在り方について、更に検討を深めていきます。
(iii)競争発注比率
調達コストの低減を図るには、競争発注比率の向上など発注方法の改善に取り組み、受注業者間のエリアを越えた競争を促進することも重要です。
各社の送配電部門の競争発注比率について経年比較を行ったところ、各社の競争発注比率は年々上昇し、2016年度には70%以上となる事業者がいる一方、東北電力、四国電力では30%程度にとどまることを確認しました。
専門会合としては、引き続き、各社の競争発注比率の推移について確認するとともに、次年度以降は、実質的な競争が働いているかどうかを把握することを目的として、競争発注比率の高い事業者に具体的な調達手続き、応札状況、入札結果の開示等についても確認していきます。
(ウ)効率化に向けた取組の公表と着実な実施
上記を踏まえ、各社においては、更なる効率化に向けた今後の取組を具体化するとともに、効率化に向けた様々な努力を需要家である国民も確認することができるよう対外的に公表し、着実なコスト削減に取り組むことを求めていきます。また、その具体化に当たっては、可能な限り定量的に説明を行うことが望ましいです。
専門会合としては、各社の取組の実施状況等について、次年度以降も確認していきます。
(計画的かつ効率的な設備投資や高経年化対策の推進)
(ア)高経年化対策について
経済成長に応じて整備されてきた設備が、今後、高経年化を迎える中、送配電事業者が求められるサービスレベルを将来にわたりできる限り低コストで維持し、将来的に託送料金を最大限抑制するためには、中長期的視点で計画的かつ効率的に高経年化対策を進めることが重要です。
各社の高経年化対策にかかる計画を確認したところ、各社とも3~10年程度の中長期計画を作成し、高経年化対策に取り組んでいました。その際、設備の劣化状況を評価して、延伸化の措置を講じるなどコスト削減にも努めていました。
しかし、各社の設備関連費について見ると、グループ全体の収支・財務状況等を考慮して修繕等を一時的に繰延べたため設備関連費が減少したと見受けられる事業者もいました。
各社においては、中長期的にトータルコストを最小化するよう、IoTやAIの活用など、最新のアセットマネジメントの手法等も取り入れ、更なる費用削減に向けた検討等を継続的に行って計画を随時見直しつつ、その中長期的な計画に基づいて着実に高経年化対策を進めるべきです。
専門会合としても、各社の取組や計画作成状況について、次年度以降も確認していきます。
(イ)設備投資について
各社とも設備投資の考え方に沿った3~10年程度の中長期的な設備投資計画を作成していました。今後、各社には、電力系統の既存設備をそのまま維持するのではなく、再生可能エネルギーの導入拡大や人口減少といった事業環境の変化も踏まえ、将来の系統がどうあるべきか検討し、適宜計画を見直し、効率的に設備投資を実施していくことが求められます。
専門会合としても、各社が将来の事業環境の変化に対応する設備投資を中長期的視点で計画的かつ効率的に行っているか、次年度以降も確認していきます。
今回、託送収支の事後評価を初めて本格的に実施しました。今後も事後評価の中で、各社の取組のフォローアップを強化することが重要であり、特に、各社のコスト削減に向けた取組(更なる効率化に向けた取組の具体化とその実施状況、調達価格削減に向けた取組状況)等について、重点的に確認、評価を行います。加えて、系統連系する際の工事費負担金の評価、効率化を促す新たな仕組みの検討等も行っていきます。