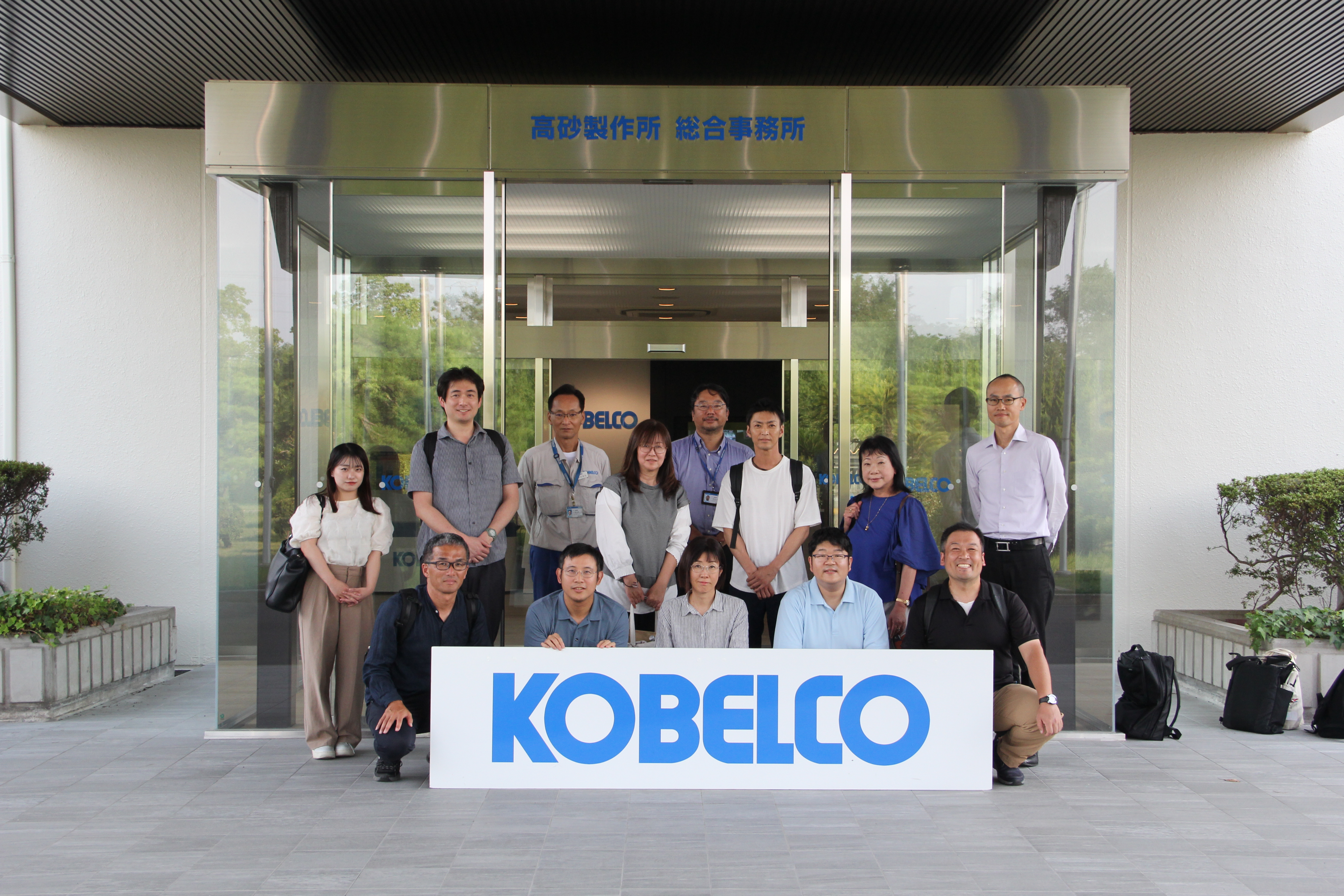講義「エネルギー政策の今後と方向性について」
(資源エネルギー庁 須山照子、
近畿経済産業局資源エネルギー環境課 片瀬眞悟)

参加者に対して、日本が直面するエネルギー情勢や、今後の政策の方向性についての講義を実施。エネルギーの安定供給と脱炭素の重要性について、資源エネルギー庁の須山氏、近畿経済産業局の片瀬氏が最新の動向を語った。
近畿圏内の経済の現状とエネルギー政策
近畿経済産業局が管轄する関西は、かつて「2割経済」と呼ばれ、前回の大阪万博の時期に日本の人口とGDPの約20%を占めていた。しかし、現在ではその割合が16%〜17%に減少しており、日本の全体に占めるプレゼンスはやや低下しているのが現状だ。
一方で、特定の産業に特化せず、多種多様な分野の企業がバランスよく集積しているのが特徴。「関西で作れないものはない」と言われるほど、オールマイティな産業構造こそが関西の強みだと考える。
電力の面では、関西は家庭用(低圧)や工場・ビル用(高圧・特別高圧)の電気料金を加重平均した料金が、日本で最も安価な地域のひとつであり、このことは同地域の産業に寄与する一面がある。九州や四国と並び、これらの地域は原子力発電所を再稼働しており、化石燃料への依存度が低下しているという背景がある。

日本が直面するエネルギー情勢と安定供給の重要性
上記のように地域間での状況の違いはあるが、総じて日本は、石油や天然ガスといった化石燃料のほとんどを自給できない「資源を持たざる国」だ。2023年のエネルギー自給率はわずか15%と低く、その大部分を海外からの輸入に頼っている。このため、原油やLNGの価格変動、そして地政学的なリスクが日本のエネルギー供給に大きな影響を与えている。
特に、2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、世界的なエネルギー安全保障の危機が高まった。これにより、当年のLNGのアジア価格は2019年頃と比較し2022年は平均で約6倍に高騰するなど、日本の家計や企業活動を圧迫する状況が今なお続いている。

このような状況を踏まえ、私たちはエネルギーの安全性(Safety)に加え、安定供給(Energy Security)、経済性(Economic Efficiency)、環境性(Environment)という「S+3E」のエネルギー安全保障の原則に基づいて、これらのバランスの取れたエネルギー政策を進めていく必要がある。海外からの輸入に依存する特定の電源や燃料源に過度に依存しないエネルギーの安定供給に努めている。
世界的な脱炭素社会の実現に向けて
一方で、エネルギーの安定供給を叶えつつも、世界共通の目標であるカーボンニュートラル社会実現への貢献も、今日の日本のエネルギー政策には求められている。日本では2050年までのカーボンニュートラルを目標に掲げており、そのために、第7次エネルギー基本計画の中では、徹底した省エネに加え、脱炭素電源である再生可能エネルギーや原子力を最大限に活用していく方針を示している。
特に、発電時にCO2を出さない再生可能エネルギーの導入においては、世界で第6位の水準であり、太陽光発電の導入量に限れば世界第3位にまで増加した。しかし、国土の約6割以上が山林である日本では、太陽光パネルの設置に適した平地が少なく、ビル壁面などのこれまでは設置が難しかった場所にも組み込める「ペロブスカイト太陽電池」などの新技術の開発が急がれている。
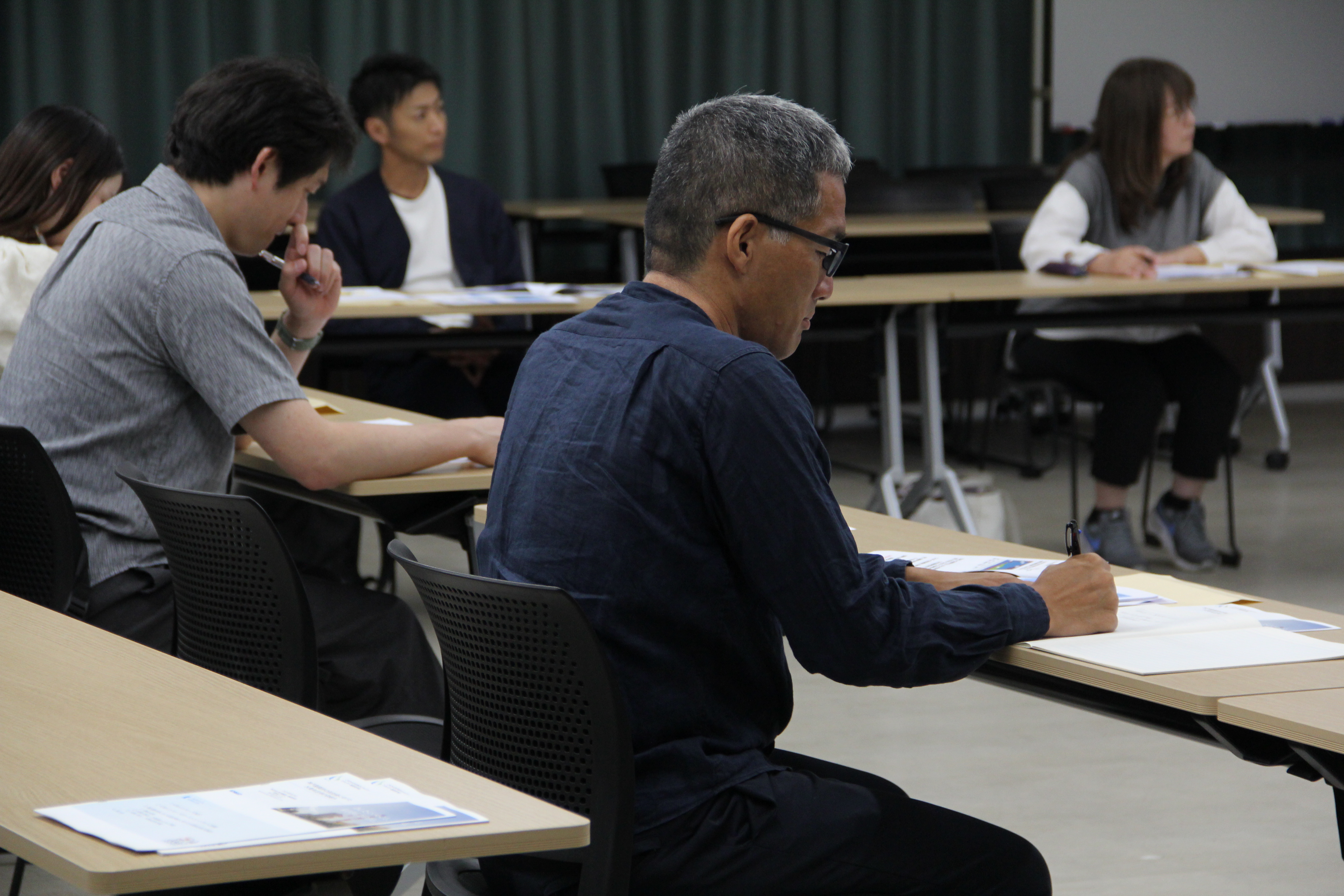
また、国際統計上、準国産エネルギーに分類される原子力発電は、エネルギー自給率の向上には不可欠だ。東日本大震災の事故以降、「新規制基準」が設けられ、世界で最も厳しい基準で再稼働が判断されるようになった。また、原子力は他の電源と比べ実用化までにかかる期間がかなり長い。そのため、次世代を担う革新炉の開発やそれに携わる人材の育成が急務として進められている。
更に今後、世界的なデジタル化の進行やEV(電気自動車)の普及により、電力需要は増加していく見込みだ。これに対応するため、CO2を回収・利用・貯留するCCUSや、CO2と水素から燃料を合成するメタネーションや合成燃料、水素・アンモニアによる既存燃料の代替、などの新たな技術の開発・社会実装も進められている。
我々には、これらの取り組みを通し、脱炭素社会の実現に貢献するだけではなく、日本のエネルギーの安定供給との両立も叶えていくことが求められている。
参加者の声
- 詳細が記載された根拠資料をもとに、要点を平易な言葉でまとめてご説明くださっていた。
- 今までエネルギーに対してここまで考えることがなく、実りある研修だった
- 戦後のエネルギー事情ついての変遷や数値、社会、国際、政治情勢とのからみなどを網羅して説明いただき、概要がよくわかった。
ワークショップ
脱炭素社会の実現に向けて、次世代層へ伝えていくべきこととは
資源エネルギー庁 須山氏の講義を受け、次世代層へ教育を行う立場の参加者同士で、2050年の脱炭素社会の実現に向けての展望を、ワークショップの中で交換した。それぞれの立場から、様々な意見が飛び交った。

参加者A 教職員
学校教育の中でもリサイクルや環境教育を通して、資源の循環について考える機会が与えられている。一方で、今後はエネルギー分野についても同様に重要視されていくべきだと考えた。その中で、国の現状や政策方針などの大局を意識した学習を創り上げていく必要性を感じている。そして、次世代層とは学習を通して「自分たちがどんな社会を作っていきたいか」ということを一緒に考えていきたい。
参加者B 教職員
今後、次世代層への発信・教育を通して、子どもたちには環境課題やエネルギー政策を「自分ごと」として捉えられるようになってほしいと考えている。再生可能エネルギーについても、良い面がある一方で、山を覆いつくす太陽光パネルや、風力発電の騒音問題などの解決すべき面も共存しており、子供たちに正しい知識を伝えることを通して、自分なりの考えをもってエネルギー課題に関われるようになってほしい。
参加者C 教職員
次世代層への発信はもちろん、前提として教育を行う側である我々大人が学ぶ機会をもっと増やすことの重要性を感じた。人権や多様性、SDGsといった内容は現状でも学校で教える時間が設けられている。一方で、エネルギー関連を含めて、カリキュラムに含まれていない内容は、私たち大人も知識をアップデートされにくい現状だ。次世代層への教育を行うためには、まずは教育を行う側が学ぶチャンスが増えることを期待している。
参加者D 科学館職員
科学館では、産業技術の展示に加え、小中学校での出前授業なども行っている。電気の仕組み、水素燃料電池、放射線など学年に合わせた内容を、主に実験を通して知識普及をめざしている。現状の学校教育のカリキュラムでは、エネルギーを扱う時間自体がそもそも少ないという中で、いきなり学習指導要領を改定するということは現実的ではない。だからこそ、単発の出前授業を通してエネルギーに対する興味関心を持ってもらう、ということの意義は大きいと感じている。
参加者E 教職員
日本の食料自給率の低さは多くの人に知られているのではないか。一方で、エネルギーも同様の状況であるということをもっと広く知ってもらい、危機感を持ってもらう必要を感じた。私の経験上、特に小学生にとっては「脱炭素」と言ってもピンとこないと思う。だからこそ、小学生でも理解できるような切り口や伝え方、そして子どもたちが主体的に課題を考え、取り組めるような環境づくりをしていきたい。
参加者F 教職員
これまでエネルギー問題については、子どもたちにはあまり伝えてこられなかった。それは、自分自身がこの課題について向き合って考えたことが無かったからだと思う。今回のような場があると現状や危機感を自分ごととして考えられる。だからこそ、私たち先生が正しい情報について身を持って知れる場の重要性を感じた。
参加者G 科学館職員
子どもたちに対するエネルギー教育において重要だと感じていることは、情報の正確性と公平性だ。例えば、「原子力」についてもその言葉の悪いイメージが先行しているのではないか。印象ではなく、実際に何が起こっているのか、ということを正しく理解させる説得力が必要だと考えている。また、良い面も悪い面も公平に発信することも重要だ。これらの情報が、子どもたちが自発的にエネルギー問題を考えるきっかけとなるのではないだろうか。
参加者H 教職員
エネルギー問題の解消やカーボンニュートラルの実現に対しては、もちろん企業の努力も非常に重要だと思う。一方で、個人一人ひとりの意識改革も重要だと考える。次世代の教育現場においても、子どもたちが幼いうちから日常生活の中でエネルギーや環境について考えられるような教育現場の整備は重要でしょう。また、国としても次世代のエネルギー政策を支える技術者や研究者の育成にも注力してほしいと思っている。
参加者の声
- 現在の日本のエネルギー事情がよく分かった。また、これからのエネルギーについて自分自身の意識と共に、児童達にも知ってもらう必要があるのではないか。
- 私は、小学校の中学年を主に対象とした総合的な学習や環境・福祉の学びを担当しているが、脱炭素GXや、省エネなど行動につなげられているかなど、児童に問うとき、今までよりもより理解した状態で向き合うことができると思う。
- それぞれの視点からのお話を伺うことで新たな視点が得られ、自分の考えを多面的に深めるきっかけを得ることができた。
- 「自分の考えをまとめて発表する」という活動も、ただ聞くだけではなく、伺った内容をもとにテーマに沿って自分なりに咀嚼してまとめてアウトプットすることで、自分の考えを深めたり再構築したりすることにつながったように感じる。
施設見学
株式会社神戸製鋼所 高砂製作所 水素関連施設
株式会社神戸製鋼所の高砂製作所は、同社の鋳鍛鋼部門として操業を開始し、鋳鍛鋼・鉄粉・チタン・機械の開発・製造拠点として世界シェアを誇っている。その製造工程では熱源として大量の化石燃料を消費するため、この置き換えを目的として製作所内で水素エネルギーの実証実験を行い、同社のカーボンニュートラルの推進役を担う。参加者は、水素エネルギーが実際に社会実装されている現場を見学し、未来の水素社会の実現に思いを馳せた。

神戸製鋼所がめざす、水素社会の実現に向けて
神戸製鋼所は、カーボンニュートラルへの挑戦として、私たちの技術・製品・サービスにおいて顧客のCO2削減への貢献と、自社の生産プロセスにおけるCO2削減という、二つの観点から取り組んでいる。
前者については、従来の素材と比べより強度の高い鉄などを使い車両の軽量化に貢献したり、圧縮機などの生産効率を向上させたりすることで、お客様でのCO2排出低減に貢献している。
また後者については、製鉄プロセスの中では、CO2排出源の石炭利用量の低減のためバイオマスの活用や還元鉄などの利用を検討中。2013年度比で2030年には30~40%のCO2削減をめざしており、今年時点で約20%減までたどり着いたという状況だ。

高砂製作所では、水素によるカーボンニュートラルへの貢献を目的として、「ハイブリッド型水素ガス供給システム」を構築し、水素を「作る」側と「使う」側の両方の視点から研究・実装を進めている。太陽光発電で得た電力で水を電気分解して水素を製造。また大量に水素が必要な場合は、液化水素を気化することで安定した水素供給が可能となっている。その水素を、ボイラや加熱炉のエネルギー源として利用する。加えて、液化水素の気化時に生じる冷熱を、空調や機械の冷却に再利用するなど、エネルギーの無駄をなくす工夫も行っている。その他にも、水素燃料電池を用いた建設機械の開発も実施しており、耐久性や性能を検証する実証試験も高砂製作所内で実施中である。
神戸製鋼所では、これらの取り組みを通じて、自社でのカーボンニュートラルを推進するだけでなく、研究・実装を通して得たノウハウを活かし、水素社会の実現とエネルギーの安定供給の両立に貢献していきたい。
参加者の声
- 水素エネルギーについて、具体的に研究を進められている神戸製鋼さんが近くにあることを知れたこと、培われてきたものを実際に見せて頂けて、参考になった。
- 内容の一つ一つについては、小学生に伝えるには難しいところがありますが、最前線で働く方々が、情熱をもって取り組んでおられることや、最先端の技術が身近あることなど、ものづくりや、他国、他社、他者との協力などについても伝えられると思う。
- 現在、水素が実際に使用されていることに驚きました。今後、もっと実用化されると考えると先進的な取り組みだなと感じた。