第3節 原子力被災者支援
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から4年が経過しましたが、福島県内の避難状況については、2015年3月31日時点で、福島県全体の避難者数は約12万人であり、このうち、避難指示区域からの避難者数は約7.9万人、既に指示が解除された区域(旧避難指示区域・旧緊急時避難準備区域)からの避難者数は約2.0万人という状況です。
政府は2013年12月に「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を策定し、早期帰還支援と新生活支援の両面での支援、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策の強化、国と東京電力の役割分担の明確化について、方向性を提示しました。その後、指針に沿って取組を進め、福島の復興・再生は着実な進展を見せています。具体的には、田村市及び川内村について避難指示の解除が実現し、住民の方々の故郷への帰還が可能となりました。また、南相馬市の特定避難勧奨地点全142地点・152世帯が解除されました。
このように具体的な進展が見られるものの、復興の進捗にはばらつきがあり、未だ復興に向けた道筋が見えないとの声が依然として地元に存在していることも現実です。また、事故発生から4年以上の長期にわたり避難状態が継続していることに伴う課題も顕在化してきています。一日も早い住民の方々の生活再建や地域の再生を可能にしていくためには、こうした実態に向き合い、これまで以上に対策を加速・充実し、様々な課題に迅速に対応していく必要があります。このような状況を踏まえ、原子力災害からの福島の復興・再生を一層加速していくため、2015年6月に「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を改訂し、必要な対策の追加・拡充を行うこととしました。具体的には、早期帰還支援と新生活支援の両面の対策を深化させるとともに、事業・生業や生活の再建・自立に向けた取組を拡充することとしています。
1.避難指示区域等
2014年4月1日に田村市で初の避難指示区域の解除を行い、同年10月1日に川内村の一部でも避難指示区域の解除を行いました。また、川内村、伊達市に続いて、同年12月28日に南相馬市において特定避難勧奨地点(避難指示区域の外側に存在するが、スポット的に年間積算線量が20mSvを超えると推定され、指定された地点)の指定解除を行い、特定避難勧奨地点全ての解除を行いました。
故郷への帰還を望む住民の方々の思いに応えるため、引き続き、他の市町村についても避難指示区域の解除に向けた調整を行っていくこととしています。
【第123-1-1】避難指示区域の概念図(2015年3月31日現在)
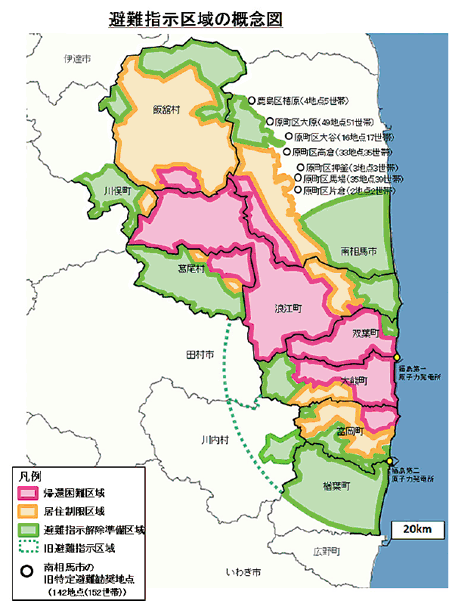
【第123-1-2】市町村の避難指示区域の見直し及び解除について(2015年1月1日現在)
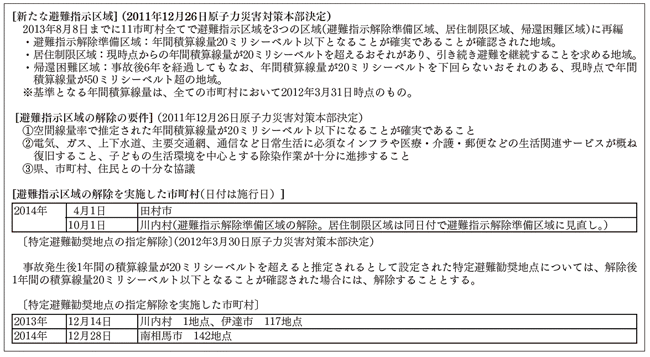
2.帰還に向けた安全・安心対策
国としては、2013年12月に閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」において、住民の方々の自発的な活動を支援する以下を柱とした総合的・重層的な防護措置を講じることとしています。
- 国が率先して行う個人線量水準の情報提供、測定の結果等の丁寧な説明なども含めた個人線量の把握・管理
- 個人の行動による被ばく低減に資する線量マップの策定や復興の動きと連携した除染の推進などの被ばく低減対策の展開
- 保健師等による身近な健康相談等の保健活動の充実や健康診断等の着実な実施などの健康不安対策の推進
- 住民の方々にとって分かりやすく正確なリスクコミュニケーションの実施
- 帰還する住民の方々の被ばく低減に向けた努力等を身近で支える相談員制度の創設、その支援拠点の整備
このような対策を通じ、住民の方々が帰還し、生活する中で、個人が受ける追加被ばく線量を、長期目標として、年間1ミリシーベルト以下になることを引き続き目指していくこととしています。また、線量水準に関する国際的・科学的な考え方を踏まえた我が国の対応について、住民の方々に丁寧に説明を行い、正確な理解の浸透に努めています。2015年6月に閣議決定した「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」の改訂においても、前述の総合的・重層的な防護措置の取組を今後とも国が、将来にわたり責任をもって、きめ細かく着実に講じていくこととしています。
【第123-1-3】「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂のポイント
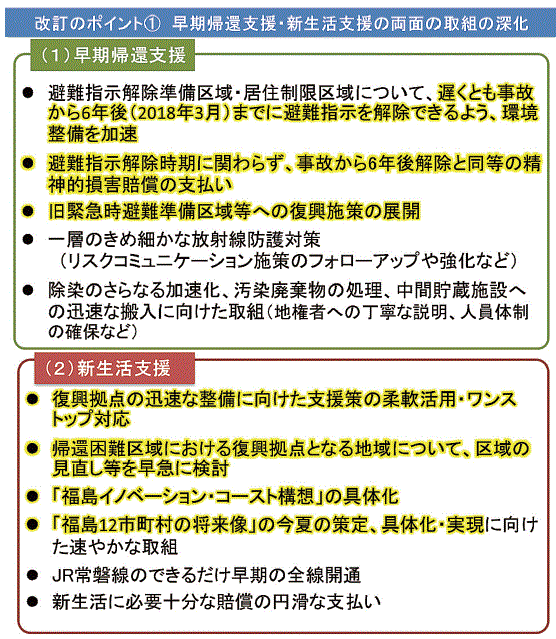
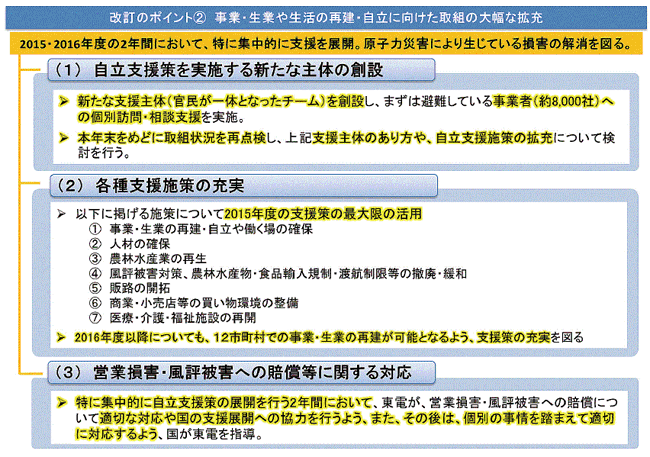
3.福島・国際研究産業都市構想(イノベーション・コースト構想)
福島浜通り地域の多くでは、これまで原子力関連企業の事業活動が地域経済の大きな部分を担ってきましが、震災、原子力災害により産業基盤の多くが失われました。今後、住民の経済的自立と地域経済の復興を実現していくためには、その前提となる東京電力福島第一原子力発電所事故の収束なども進めながら、新技術や新産業を創出していくことが求められています。
そうした中、原子力災害現地対策本部長の私的懇談会として、福島県副知事をはじめ、地元市町村長、有識者、関係府省で構成される「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想研究会」が2014年1月に立ち上げられ、同年6月に報告書がとりまとめられました。本構想は、廃炉の研究開発拠点、ロボットの研究・実証拠点などの整備、これらを支える「まちづくり」を含んだ幅広い構想です。
本構想の具体化に向けて、構想の主要プロジェクトのうち、更に検証・検討が必要な①ロボット研究・実証拠点、②国際産学連携拠点、③スマート・エコパークについて、関係省庁、福島県庁、有識者等を中心に、採算性や事業面での実現可能性など技術的な視点から検討を行う個別検討会がそれぞれ2014年11月に開催されました。また、構想の具体化に当たっては、国、福島県、市町村が単独で成し遂げることは難しく、この3者をはじめ関係者が一体となって取組を進めていく必要があります。このため、個別検討会における検討状況の報告、その他構想具体化に向けた進捗状況を共有しつつ、構想の実現に向けた方策について意見交換等を行うため、原子力災害現地対策本部長を座長として、福島県知事、地元市町村長、有識者、関係省庁で構成される「イノベーション・コースト構想推進会議」が同年12月に開催されました。2015年6月に閣議決定した「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」の改訂においても、本構想についての検討等も踏まえつつ、中長期・広域の視点で、福島12市町村の将来像を2015年夏に策定すること、また、国・県・その他関係する主体でよく連携して将来像の個別具体化・実現に向けて速やかに取り組むこととしています。
4.除染の実施
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっています。こうした状況を踏まえ、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)が可決・成立し、2011年8月30日に公布されました。
2011年11月11日には「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針」が閣議決定され、環境の汚染の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考え方が取りまとめられ、関係者の連携の下、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響が速やかに低減されるよう、また、復興の取組が加速されるよう、同方針に基づき取り組むこととしています。放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が除染を実施する除染特別地域においては、市町村ごとに策定する特別地域内除染実施計画に従って事業を進めることとしており、福島県の11市町村(田村市、楢葉町、川内村、南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町、大熊町、富岡町及び双葉町)について、同計画を策定しました。2014年度までに、田村市、楢葉町、川内村及び大熊町の全体並びに葛尾村及び川俣町の宅地部分並びに常磐自動車道については同計画に基づく除染が終了し、飯舘村の宅地部分でも概ね終了しました。川俣町及び葛尾村の宅地以外並びに南相馬市、飯舘村、浪江町、富岡町及び双葉町については、同計画に基づき除染作業を実施中です。また、市町村が中心となって除染を実施する汚染状況重点調査地域においては、市町村が除染実施計画を策定し、除染事業を進めることとされており、8県94市町村において除染実施計画が策定され(2015年3月末現在)、各地で除染作業が進められています。これらについては、公共施設等の8割以上で除染が実施されるなど着実な進捗が見られており、計画した除染が終了した市町村も見られるところです。
環境省においては、放射性物質汚染対処特措法が2012年1月に全面施行されたことに伴い、福島県等における除染を推進するために、同月、福島環境再生事務所を開所し、体制の整備を行いました。また、除染に関する情報発信の拠点として、福島県と共同で除染情報プラザを設置しました。
また、福島県内では、除染に伴う放射性物質を含む土壌や廃棄物等が大量に発生し、現時点でこれらの最終処分の方法を明らかにすることは困難であることから、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設の整備を進めているところです。
2013年12月には、福島県及び地元町に対して、中間貯蔵施設の設置の案を提示して受入れの要請を行い、その後、地元からの了解を得て、住民説明会を2014年5月から6月にかけて開催し、そこで頂いたご意見を踏まえた政府の取組を、福島県・大熊町・双葉町にお示ししました。その後、同年9月には福島県から、同年12月には大熊町から、2015年1月には双葉町から施設の建設を受入れていただきました。 同年2月に福島県に対し、施設への搬入の開始に当たって確認が必要な5項目に係る取組状況等を説明し、搬入について、速やかな判断をお願いしました。同年2月25日には、福島県並びに大熊町及び双葉町から搬入の受入れについて国に伝達があり、福島県、大熊町及び双葉町並びに環境省の間で安全協定を締結しました。同日に、大熊町及び双葉町から搬入開始を3月12日以降にすること等について申入れがありました。この申入れを重く受け止め、3月13日に大熊町の仮置場から、3月25日に双葉町の仮置場から中間貯蔵施設内の保管場への除去土壌等のパイロット輸送(注)を開始しました。
これらの取組と並行して、環境省として連絡先を把握している全ての地権者に連絡を取り、順次個別訪問や物件調査等を進めるとともに、連絡先が不明の地権者についても戸籍簿等による調査を進めてきました。今後も、地権者を始めとした地元の方々への丁寧な説明を尽くし、その御理解を得ながら、安全に万全を期して中間貯蔵施設の整備や施設への除去土壌等の搬入を進めていきます。
- (注)
- 大量の除染土壌などを輸送する本格的な搬入に向けて、安全かつ確実に実施できることを確認するため、おおむね1年間実施。